1 / 4
第一章:冷たい婚礼
しおりを挟む白いレースのカーテンから差し込む朝の陽光が、部屋の中を淡く照らしていた。周囲を飾る花々や貴石を散りばめた調度品は、まるで豪華な舞台装置のように静まり返っている。その中心に立つのは、一人の少女――アスカ。
彼女は大きな姿見の前でじっと自分を見つめていた。長い黒髪は丁寧に結い上げられ、肌を覆う純白のドレスは抜けるように眩しい。だが、その瞳には不安と諦念が混ざり合った色が宿っている。まるで、これから迎える未来が自分のものではないと悟っているかのように。
ドレスの裾を微かに揺らしながら、アスカはふと、小さく息をついた。豪奢な花嫁衣装を与えられたのは、決して彼女の望みが叶ったからではない。むしろ望みなど、とうの昔に捨て去ってしまった。生まれ落ちた家が貴族である以上、女性が担う役割はほとんど限られている。ましてや彼女の家――リュミエール侯爵家は、その名声と財力を保つためにあらゆる手段を惜しまない家柄として知られていた。
結婚。政略結婚。個人の意志など一顧だにされない取引。
アスカにとっては、ここ数カ月、否、幼少の頃からの教育を含めれば十数年にわたる「花嫁修業」と呼ばれる押し付けが、そのままこの日へと集約されているように感じられた。愛など存在しない。あるのはただ、家同士の打算と駆け引きで結ばれる契約だけだ。
コツン、コツン、と控えめに扉が叩かれる音がして、侍女のリディアが顔を覗かせた。彼女は優しい光を宿した瞳でアスカを見つめ、穏やかな声で話しかける。
「アスカ様、そろそろ支度が整いました。ご両親がお待ちです。」
「……わかったわ。ありがとう、リディア。」
リディアは幼い頃からアスカに仕えてきた侍女であり、唯一といってもいい理解者だった。その温かさと忠誠心に、アスカは何度も救われてきた。しかし今この瞬間は、その心の支えすらも薄れていくような感覚がある。自分がどんなに嫌がっても、結局は婚礼の儀式へと引きずり出されるのだから。
アスカはドレスの裾を軽く整え、部屋を後にした。長く続く廊下を抜けて、広々とした階段を降りると、そこには華やかに着飾った両親の姿があった。父・イザークと母・マリアンヌ。どちらも冷たい雰囲気を漂わせながら、今日という日をただ「成功」として迎えようとしているようだ。
「アスカ、身だしなみはもう十分に整えているだろうな?」
父のイザークは厳格そうに唇を引き結んでいる。その声には決して温かみはなかった。
「はい、父上。問題ございません。」
アスカは静かに答える。それ以外に何が言えるというのだろう。
母のマリアンヌは淡々とアスカの姿を眺め、厳しい目で最後のチェックを行った。ワインレッドのドレスを纏った彼女は、若い頃から社交界の華と称えられてきた女性だ。しかし、その美貌とは裏腹に、娘への愛情はどこか希薄だった。
「やはり美しいわね。これならレイヴン公爵家への示しも完璧。リュミエール家の名を損なうようなことはしないでちょうだい。」
それは祝福でもなければ、労わりの言葉でもない。ただ「失敗するな」という圧力に等しかった。
結婚式場へ向かう馬車の中、アスカは隣に座る両親とほとんど会話らしい会話をしなかった。馬車の揺れとともに、窓の外を流れ去っていく街の景色を眺める。人々が行き交い、賑やかな市場が広がる通り。その活気はまるで、これから行われる華麗な貴族の婚礼と無関係のように映った。
(私はいったい、どこへ行くのだろう――。)
ぼんやりとした疑問が心の中を占める。愛のない結婚生活。その先に何が待っているのか、想像さえできない。
家族の思惑と、アスカの無力
リュミエール侯爵家は、この十数年で急速に財力を落としていた。かつては強大な影響力を持ち、社交界の中心にいたが、戦乱による出費や度重なる不正投資の失敗で、もはや多額の借金を抱えるほどに困窮しているのが実情である。
アスカの婚約者――レイヴン公爵家は、幸運にも近年の政変で大きく勢力を伸ばし、その莫大な富と政治的権力を握った。アスカの父・イザークは、いつかこの状況を打開し、再び家名を高らしめる機会を虎視眈々と狙っていたのだ。
その切り札こそが、この娘・アスカであった。
「この縁談をまとめるまでには多くの苦労があったのだ。」
馬車の中でイザークが唐突に口を開いた。彼の顔には自己陶酔にも似た高揚感が見える。
「レイヴン公爵家に見初められるなど、そう簡単な話ではない。だが、我がリュミエール家の“体裁”を保つためには、どうしてもこの政略結婚が必要だったのだよ。」
アスカは黙って聞いていた。彼女の思いなど、一切考慮に入れてはいないことが、言外に伝わってくる。
母のマリアンヌは苦笑のような表情を浮かべ、窓の外へ視線を移す。
「アスカのことも、多少は気がかりよ。けれど仕方がないわね。貴族の娘というのは、こうして家のために嫁いでいくものなんだから。」
そう呟きはするものの、そこに娘を思う母の情がどれほどあるのかは疑わしい。もはや形だけの“気がかり”でしかないのは明白だった。アスカはその冷ややかな空気を全身で感じ取りながら、ただ唇を噛み締めてうつむく。自分がこの家に生まれ落ちた時点で、もう運命は決まっていたのかもしれない。
娘として、道具として
婚礼会場となる大聖堂は、白く輝く大理石の壁と尖塔が印象的な壮麗な建築だった。王都でも有数の格式を誇り、多くの貴族が結婚式を挙げる憧れの場所である。
しかしながら、アスカの心には一抹の感動も湧かない。長く伸びる石畳の先には、すでに多くの招待客が集まり、彼女を待ちわびていた。家同士の結びつきを確認し合うかのように、誰もが上辺だけの言葉を交わしながら、退屈そうに開式を待っている。
リディアがさりげなくアスカの手を握り、そっと小声で励ます。
「アスカ様、どうかご自身を大切に。どんなときでも、私はあなたの味方ですから。」
「ありがとう、リディア……。」
その言葉に救われる想いだった。誰一人として自分をまともに見ようとしないこの場所で、彼女だけはいつも寄り添ってくれる。だが、リディアの存在がどれほど心強くとも、結局はこの結婚を回避できる力にはならない。
白い花束を手渡されたアスカは、ゆっくりと祭壇へと歩みを進める。聖堂内を埋め尽くした人々の視線が、一斉に彼女へ注がれるのがわかった。視線の奥には、「リュミエール侯爵家の令嬢はどのような女か」という興味が見え隠れする。慈しみや祝福とは程遠い。
深く息をついて、顔を上げると、そこに立っていたのは――レイヴン公爵。黒髪を短く整え、長身の身体には漆黒の礼服が映えていた。誰もが目を奪われるほどの整った容姿を持ちながら、どこか冷徹な空気をまとっている。
「……よろしく、頼む。」
レイヴンは儀礼的に言葉をかけるが、その声には温かさも感動も含まれていなかった。まるで人形を扱うように、形式だけを示している。
アスカもまた、作り物の微笑みを浮かべて応じる。
「こちらこそ、よろしくお願いいたします……。」
指輪の交換も、誓いの言葉も、すべてが流れるように滞りなく進んでいく。まるで手順書でもあるかのように、関係者が淡々と式を進行していくのだ。祭壇の上で神父が神聖な祝福を告げる声が響くが、その厳かな響きとは裏腹に、アスカは自分の心がどんどん遠のいていくような気さえしていた。
(これが私の……結婚?)
冷たく重い現実が、鈍痛となって胸を締めつける。もしこの場で逃げ出したら、どうなるのだろう。家族は激怒し、レイヴン公爵家からは何らかの制裁を受けるかもしれない。そんなことを考えているうちに、神父が最後の宣言を行い、周囲が拍手で満たされる。
こうしてアスカは、“レイヴン公爵夫人”として新たな人生をスタートさせることになったのだ。
仮面の祝福と冷たい宴
婚礼の後、同じ大聖堂に隣接する豪奢なホールで盛大な披露宴が催された。幾重にも並べられたテーブルには、贅の限りを尽くした料理が彩りを添え、その間を行き交う給仕たちが忙しなく動いている。
招待客たちは互いに杯を掲げ、祝福の言葉を投げ合う。だが、その笑顔の多くは仮面の裏にあり、本音など見えていない。特に貴族同士の宴は、誰と誰が繋がっているのか、どの家がどれほどの財力を保持しているのか、といった情報戦の場でもあるからだ。
アスカは披露宴の中心――高座の席に座していた。隣にはレイヴンがいるが、彼は一度たりとも彼女に興味を示そうとはしなかった。祝辞を述べに来る客人にはにこやかに応対するものの、アスカと目を合わせることはほぼない。
その姿を見ているうちに、アスカの中に微かな怒りが芽生え始める。だが、その気持ちを表情に出すわけにはいかない。公爵夫人としての初日から、感情的な振る舞いをすれば、家同士の関係に亀裂を生じさせかねない。
そんな彼女の内心を知ってか知らずか、両親は上機嫌に周囲へ挨拶を続けている。リュミエール家が公爵家と縁を結んだという事実が、彼らにとってどれほど重要かは言うまでもない。アスカは、その光景を遠巻きに眺めながら、まるで他人事のように思えて仕方がなかった。
(私はただの飾り。誰かの幸せを祝う道具でも、誰かに愛される存在でもない。ただ、家のための一コマ……。)
胸の奥底から込み上げてくる虚しさに、彼女はそっと目を伏せた。これまでも何度も味わってきた感情だが、今日ほど痛烈に突き刺さることはなかった。
式の終わり、始まる違和感
長かった披露宴がようやく終わる頃、アスカは疲労のあまり立ち上がることすら億劫になっていた。人々に愛想を振りまき、笑顔を作り続けた代償は大きい。だが、公爵家の新婦として、これ以上醜態を晒すわけにはいかない。
レイヴンが先に席を立ち、関係者と何やら小声で話をしているのを視界の隅に捉える。彼は誰か――金髪の女性――と親しげに言葉を交わしていた。遠目に見ただけでは、相手の素性までははっきりしないが、その距離感からしてかなり近しい仲のように思える。
(あれは……誰?)
アスカは自分でも驚くほど冷静だった。嫉妬というよりは、どこか達観したような感覚だ。結婚して初日から、夫が別の女性と言葉を交わしている。それも親密そうに。それでも胸が痛まないわけではないが、何か“ああ、やっぱり”と納得している自分がいる。
「アスカ様、お身体は大丈夫ですか? 少し休まれたほうがよろしいのでは……」
リディアが心配そうに声をかける。
「ありがとう。でも、まだ大丈夫よ。私にはまだ、“義務”が残っているもの。」
アスカはそっと微笑んだ。真実かどうかはわからないが、リディアの優しいまなざしにだけは感謝したい。そして今は、結婚初日に公爵夫人としての振る舞いをまっとうするしかない。
やがて、客人たちが次々に帰り支度を始める中、両親がにこやかな顔でアスカのもとへとやってきた。
「よくやったな、アスカ。これでリュミエール家も安泰だ。公爵夫人としての役目をしっかり果たすんだぞ。」
まるで娘を誇るようでありながら、その言葉は自分たちの思惑が成功した喜びに満ちている。
「……わかりました、父上。ご心配なく。」
アスカはもう、何も感じなかった。心が白く、空虚になっていくようだ。これから夫婦としての生活が始まるにもかかわらず、希望らしい希望を抱けない。
屋敷へと向かう馬車の中で
披露宴後、アスカとレイヴンは同じ馬車に乗って、公爵家の屋敷へ向かった。屋敷は王都の中心から少し離れた丘の上にあり、広大な敷地に立ち並ぶ建物群は、一見すると城砦のようにも見える。
夜も更けてきたためか、道行く人々もまばらで、暗い街灯が通りを照らしている。馬車の揺れに身を委ねる中、アスカはレイヴンに声をかけるべきか迷った。夫となった彼に、聞きたいことは山ほどある。これからの生活、求められる役割、そして先ほどの金髪の女性について――。
だが、レイヴンは馬車の隅で静かに外を見つめ、一向にこちらを向かない。彼の横顔は鋭利な彫刻のように整っているが、そこに温かみは微塵も感じられない。
「……今日の宴、疲れたでしょう。」
意を決して声をかけてみたが、彼はほんの少し視線を寄越しただけで、すぐにまた窓の外へと目を戻した。
「特に。ああ、アスカ……だったな。俺の家では、余計なことはしなくていい。公爵夫人として最低限の役目を果たしてくれれば、それで構わない。」
淡々とした言い回し。それは、彼女と深く関わる気がないことを明確に示していた。まるで“君に感情なんて抱くつもりはない”とでも言わんばかりに。
「……わかりました。私も、あなたに迷惑をかけるつもりはありません。必要最低限のことだけ、すればよろしいのですね。」
自然と、自分でも驚くほど落ち着いた声が出た。まるで以前から決められていた台本の台詞を読み上げるかのように。
やがて馬車は、公爵家の屋敷へと到着する。高い石壁と重厚な門が出迎えるその様は、確かに“栄華の象徴”に相応しい壮麗さだ。だが、アスカが感じたのは圧迫感だけだった。まるで自分が牢獄へと足を踏み入れたかのように思えてならない。
始まる“白い結婚”
公爵家の使用人たちが、明かりをともしながら二人を迎え入れる。夜気を含んだ冷たい風が、屋敷の外回廊を抜けてかすかにうなり声を上げた。石造りの廊下を歩く足音が、どこまでも響き渡る。
アスカは膨大な書物や調度品が並ぶ広間を抜け、案内されるままに自室へ向かった。
「こちらがお部屋でございます、公爵夫人様。必要なものはすべて揃えております。もし不足がありましたら遠慮なくお申し付けください。」
年配の執事が淡々と告げる。アスカは微笑みを作り、「ありがとう」と応じた。部屋の扉を開けると、そこには豪華な調度品が立ち並び、まるで小さな宮殿のような内装が施されていた。
しかし、その豪奢さを前にしても、アスカの心は少しも浮き立たない。広すぎる部屋、外界を拒むかのように分厚いカーテン――どこか冷たさと孤独を感じさせる要素ばかりが目についてしまう。
しんと静まり返った空間に一人取り残されたような気分。新婚の夜だというのに、夫の姿はなく、ただ彼の領地――屋敷の奥底で眠りにつくだけだ。
(私の望んだ結婚なんかじゃない。それでも、この道を選ばざるを得なかった。)
ベッドの傍らに腰を下ろし、ぼんやりと手元を見る。ドレスの裾にはまだ白い花の装飾が残り、ところどころに小さな汚れがついている。披露宴で人々と挨拶を交わし、歩き回った証だろう。しかし、アスカにはそれすらも他人事のように思えてならない。
このとき、ふと部屋の扉が小さくノックされた。
「アスカ様、失礼いたします。」
声の主はリディアだった。彼女は新婦の世話をするために、しばらくこの公爵家に滞在を許可されている。表向きは「花嫁付きの侍女」という名目だが、その実、アスカが一人きりで心折れてしまわないための配慮なのだろう。父や母が気遣っているわけではなく、あくまで公爵家との関係を円滑にするための一時的な措置である。
「何か問題でもあった?」
アスカが問いかけると、リディアはかぶりを振って静かに微笑んだ。
「いいえ。ただ、アスカ様の様子が気になって……。少しお休みになられたほうがいいかと思いまして。」
「……そう、ね。もう疲れたし、今日は休むことにするわ。」
リディアが隣に座り、そっとアスカの手に触れる。その温かな感触に、アスカはようやく強張っていた肩をゆるめた。ふわりと、優しい香りが鼻をかすめる。
「ご結婚、おめでとうございます。」
リディアが心からそう言ってくれるのが伝わってきた。しかし、アスカは胸が痛むのを感じる。これが本当に“おめでたい”ことなのか、自分でもわからなくなっているのだ。
「ありがとう、リディア。でも、まだ私には実感がわかないの……。それに、ここでの生活がどうなるかもわからない。」
「何があっても、私はアスカ様のお側でお仕えします。どうかご安心ください。」
その言葉は、暗闇の中に一筋射し込む光のようだった。アスカは目を伏せながら微笑む。もしかしたら、今この屋敷で自分にとっての支えはリディアだけかもしれない。
前編の幕引き:冷たい始まり
リディアが退出し、部屋に一人残されたアスカは、重たいドレスから身を解放するようにして夜着へと着替えた。レースやコルセットから逃れてやっと自由になった身体。しかし、その解放感すらも刹那的なものでしかない。
窓を開けてみると、外には暗闇が広がり、遠くに王都の灯りがぼんやりと揺れている。冷たい夜風が頬をかすめ、アスカの長い髪を揺らす。
この夜風は、まるで彼女の新しい人生の幕開けを嘲笑するかのようだ。結婚式という大舞台を終え、歓喜や祝福の嵐の中にあるはずなのに、彼女の心には希望どころか深い淵のような空虚さが渦巻いている。
明日からは、公爵夫人としての日々が始まる。夫は自分に興味を示さず、家族も既に用済みとばかりに手を引くことだろう。愛のない“白い結婚”――華やかな外見とは裏腹に、そこには冷たく閉ざされた関係しか存在しない。
(これから私はどうすればいいの……。)
答えのない問いを夜空に投げかけ、アスカは小さく震える。まだ涙を流すことすらできない。泣けば何かが変わるなら、いくらでも泣いただろう。しかし、そんなことで運命が変わるわけではないと、彼女は幼い頃から教え込まれてきたのだ。
だからこそ、今は耐えるしかない――そう思いながら、アスカはゆっくりと窓を閉じた。そして、灯りを落とした部屋の闇の中で、静かに目を閉じる。いつしか眠りに落ちるまでの間、彼女の脳裏には、白いドレスを身にまとった自分と、遠くに立つレイヴンの冷ややかな瞳ばかりが浮かんで消えていった。
こうして始まる彼女の結婚生活は、いわゆる「幸せな新婚生活」とは程遠い。むしろ“契約”という言葉が相応しいほどに、愛情や温もりが欠落した婚姻関係の第一歩だ。
だが、アスカはまだ知らない。これから訪れる数々の出来事が、彼女自身を大きく変え、やがては“ざまあ”と呼べるような反撃へと繋がっていくことを――。
新婚初夜とは名ばかりの寒々しい夜が明けた頃、アスカはまだ日が昇りきらないうちに目を覚ました。慣れない寝台で熟睡できなかったのもあるが、何より、これから始まる日々への不安が頭をもたげ、彼女の眠りを浅くしていた。
窓の外を覗けば、東の空がかすかに白みを帯びている。公爵家の屋敷は広大で、一際高い位置にあるため、王都の街並みが遠くにうっすらと見渡せた。冷たい風が石造りの壁を揺らす音が、どこか不気味に感じられる。まるで、自分が閉じ込められた檻の外側で、世界が勝手に動き続けているかのようだ。
見えない夫の存在
結婚式翌日にもかかわらず、夫であるレイヴンの姿は見当たらなかった。夜のうちにどこかへ出かけてしまったのか、それとも別室で休んでいるのか。いずれにせよ、新婚生活の“甘い時間”など、影も形もない。アスカはやり場のない気持ちを抱えながら、少しずつ朝の支度を進めた。
鏡台の前で髪を整えていると、侍女のリディアが静かに部屋へ入ってくる。リディアはそっと微笑みを浮かべ、か細い声で話しかける。
「おはようございます、アスカ様。よくお休みになれましたか?」
「……あまり。慣れないベッドで、少し疲れが残っているわ。」
リディアは申し訳なさそうに目を伏せた。彼女はアスカの父母からの指示で一時的に滞在を許されている身であり、この屋敷では完全に部外者である。そのため、あまり自由には動けない立場だ。けれど、アスカの心を唯一気遣ってくれる存在であることに変わりはない。
「よろしければ、朝食の準備を整えます。公爵家の使用人がいくつか指示を仰ぎたいと申しておりますが、アスカ様のご気分が優れないようでしたら、私から伝えておきますが……」
「いいえ。私が直接話すわ。公爵夫人としてやるべきことがあるもの。」
そう答えながら、アスカはわずかな躊躇を感じていた。公爵夫人として、使用人を指揮し、家を取り仕切る――それは表向きの役目であり、本来なら新妻であるアスカが堂々と振る舞うべきところだ。だが、夫がまるで自分に興味を示さず、挨拶すらしない状況で、公爵家全体をどうやって切り盛りすればいいのか。そんな疑問ばかりが募る。
冷え切った屋敷の朝
広い廊下を抜けて向かった先は、一階にある応接室。そこでは数名の使用人が待機しており、アスカの登場と同時に深々と頭を下げる。彼らの表情は一様に固く、どこかぎこちない。
「公爵夫人様、おはようございます。朝食は温かいスープとパン、それに果物をご用意しております。お部屋でお召し上がりになりますか、それとも……」
「応接室でいただくわ。皆さんにも挨拶を兼ねたいから。」
アスカがそう告げると、使用人たちは少し安心したように「承知いたしました」と答えて作業に戻った。リディアが給仕に協力し、手際よく朝食の準備を進める。
やがて整えられたテーブルには、確かに見た目にも美しい食事が並んだ。薄めのミルクスープ、香ばしいパン、彩りを添える果物やハーブ。豪奢というよりは質素に近いが、気遣いが感じられる。公爵家と聞けばもっと豪勢なものを連想しがちだが、意外にも抑制が効いている様子だ。
アスカは一口スープを口に含む。温度もちょうどよく、ほんのりとした甘みが身体に染み渡っていく。だが、味わいとは裏腹に、心の冷えは癒えない。夫の姿がないまま、公爵夫人として過ごす朝――この光景は、彼女にとって想像していたどんな“新婚生活”ともかけ離れたものだった。
隠された緊張感
朝食をとりながら、アスカは使用人たちに軽く挨拶をし、屋敷の中を案内してもらう段取りを確認した。まだ把握しきれていない施設が山ほどあるうえ、どの使用人が何の仕事を担当しているのかも分からない。
だが、使用人たちもどこか落ち着かない様子を見せる。アスカが問いかけると、一瞬視線を彷徨わせ、要領を得ない返事をすることもあった。まるで「新しい公爵夫人がきちんと権限を振るえるのか」と内心疑っているようにも見えた。
(私のことを信頼していないのかしら……。それとも、誰かに報告されるのを恐れているの?)
アスカの胸に、淡い警戒心と不安が湧く。ここは公爵家という大きな組織だ。何十人、何百人という使用人が働いており、皆がそれぞれの役目を持っている。その頂点にいるのはもちろんレイヴンだが、彼が屋敷に滞在することは少ない――そんな噂も耳にした。
そして、新しく迎え入れられた公爵夫人が、その不在をどう補うのかは屋敷中の関心事でもあるだろう。アスカの立ち居振る舞い一つが、今後の待遇を左右するかもしれない。
謎めいた金髪の美女
朝食を終え、アスカはリディアや数人の使用人と共に屋敷の中庭へ足を運んだ。花壇や噴水が整備された優美な庭だが、アスカの目にはどこか人工的すぎる印象が拭えない。華やかではあるが、誰かが心を込めて育てているという温かさを感じられないのだ。
そのとき、視界の端に人影が映った。長い金髪をゆるやかに巻いた女性が、庭の片隅で花を摘むような仕草をしている。黒いドレスを纏っているが、光を受けて際立つ金髪がとても印象的だ。
「あの方は……どなたかしら?」
アスカが問いかけると、案内役の使用人たちは一瞬言葉を濁し、互いに視線を交わす。リディアも怪訝そうに眉をひそめた。
しばしの沈黙の後、一人の使用人が小さな声で答える。
「それは……セシリア様とおっしゃいます。この屋敷に、以前から時々出入りなさっておりまして……今は、客人として滞在されております。」
「客人、ね。」
アスカは胸の奥でチクリと棘が刺さる感覚を覚えた。前日の披露宴の最中、レイヴンが親しげに話していた金髪の女性――まさかこの屋敷に滞在しているとは。
何も知らされていないうちから、夫の“親しい女性”と一つ屋根の下で過ごすという現実。最初からわかっていたはずの“白い結婚”の象徴が、こうして目の前に現れると、動揺を隠せなかった。
公爵夫人としての初仕事
昼下がりになると、屋敷の執事や秘書官がアスカのもとを訪れ、いくつかの書類への確認を求めてきた。公爵家の財務や行事のスケジュール、商人たちとの契約内容など、多岐にわたる。
「公爵様が不在の間、これらの管理を公爵夫人様に仰せつかっております。大枠の決定権は公爵様にありますが、細かな運営や人事面は夫人のご指示で進めるよう、承っております。」
執事の落ち着いた声を聞きながら、アスカは胸中で困惑していた。結婚して一日しか経っていない状態で、こんなにも重要な業務を任されるものなのか。レイヴンがどのような意図でこの決定を下したのか、まるで見当がつかない。
ただ、アスカは幼い頃から貴族としての教養や、領地経営に関する基礎は叩き込まれていた。リュミエール家で長年見聞きしてきた経験もある。表面をさらっと読むだけなら、何とか対処できると判断し、意を決して書類に目を落とした。
数字の羅列や契約文言を集中して追っていると、不思議と心が落ち着く。愛や感情とは無縁の“公的な仕事”は、ある意味でアスカにとって逃げ場になるかもしれない。
しかし、しばらく読み進めるうちに、どうにも釈然としない点が出てきた。契約金額や領地開発の予算が大きく歪んでいるように見えるのだ。特定の商人だけが優遇され、逆に他の業者は冷遇されているような痕跡がある。
「……これは、どういうことかしら?」
アスカが問いかけると、執事も秘書官も苦い表情を浮かべた。
「詳細はわかりかねますが……公爵様ご自身が、親交のある商人を贔屓になさることは、まれにあるようです。ここ最近は特に、財務のバランスが崩れ気味と耳にしておりますが……」
言いにくそうに口をつぐむ様子から、何やら裏があることは明らかだった。しかし、公爵夫人としてはこれを見過ごすわけにはいかない。もしかすると、レイヴンが何かの利権を得るために恣意的な経営をしているのかもしれないし、あるいは“金髪の女性”セシリアと何らかの繋がりがあるのかもしれない。
アスカは一度深呼吸し、落ち着いた声で執事に向き直った。
「わかりました。もう少し精査してから、改めてお話を伺いたいと思います。それまでに、各部署の担当者のリストをまとめていただけますか?」
「承知いたしました、公爵夫人様。」
こうして、彼女の“公爵夫人としての初仕事”は一筋縄ではいかない幕開けとなった。
セシリアとの遭遇
夕方になり、アスカは執事から屋敷内の執務室を紹介された。ここはもともとレイヴンの私室を兼ねているが、公爵が不在のときは公爵夫人が使用して良いとのことだった。重厚な机や、本がぎっしり詰まった書架が並び、窓からは庭が一望できる。
アスカが机の前に腰掛け、先ほどの書類を整理し始めた矢先、扉がノックもなく開け放たれた。驚いて振り返ると、そこに立っていたのは昼に中庭で見かけた金髪の美女――セシリアだった。
「あなたが、新しい公爵夫人……アスカさん、でいいのかしら?」
軽薄とも思えるほど柔らかな声。しかし、その瞳には高慢とも取れる鋭さが宿っている。アスカは一瞬ひるんだが、すぐに背筋を伸ばし、できるだけ冷静に微笑んでみせた。
「ええ、そうですが。あなたはセシリア様……ですよね。」
「そうよ。昨日の披露宴では忙しそうだったから、ご挨拶できなくて残念だったわ。」
セシリアはスカートの裾を軽く揺らしながら、室内をゆっくりと見回す。その様子は、この部屋が自分の領域であるかのような振る舞いだ。まるで、長年公爵家に住んでいるかのような気安さを感じさせる。
「でも、こうしてお顔を拝見する限り、とても綺麗なお方。さすがはリュミエール侯爵家のお嬢様ね。それにしても……」
と、セシリアは口元に手を当てて笑う。
「レイヴン公爵との新婚生活はいかが? もう熱烈に愛を囁いてもらった?」
その問いかけに、アスカの胸は微かに痛む。愛など皆無の結婚であることを、わざわざ問い詰めるように聞いてくる意図は何なのか。嘲笑されているようにも思える。
自分がどう答えるか迷っているうちに、セシリアはあからさまな嘲弄の笑みを浮かべて続けた。
「ま、あの人は気まぐれで冷たい人だから、花嫁を大事にする余裕なんてないのかもしれないわね。特に、最近は仕事が忙しいみたいだし……うふふ。」
アスカは、できる限り表情を変えずに応じる。
「お心遣い痛み入ります。まだ新婚早々で、夫との時間がほとんど取れていないのは事実です。ですが、公爵としての仕事は重要ですから、私もできる範囲でサポートしていく所存です。」
淡々と述べながらも、内心では複雑な感情が渦巻いていた。明らかにセシリアは、レイヴンとの“親密さ”を誇示するかのような態度を取っている。もしかすると、彼女は既に愛人のような立場にあるのかもしれない。それを新妻にわざと見せつける――その傲慢さが不快だったが、ここで感情を爆発させるわけにはいかない。
「ふふ、あなたって案外しっかりしているのね。退屈な『お人形さん』かと思っていたけれど、まぁ少しは楽しませてもらえるかもしれないわ。」
セシリアはつま先で軽く床を鳴らし、くるりと身を翻して部屋を出て行った。その背中から漂う香りと、挑発的な笑みが、アスカの神経を逆なでする。しかし、アスカはただ唇を結び、静かに息を吐くだけだった。
自分にできることを探して
セシリアの出現によって、アスカの不安はさらに増幅した。夫の不在、愛人と思しき女性の居座り、そして歪んだ財務状況。どれもこれも、彼女が想像していた以上に複雑だ。
とはいえ、嘆いてばかりでは何も解決しない。アスカは机に広げた書類を改めて確認し、まずは現状を把握することから始めることにした。自分にとって唯一確かなのは、これまで学んできた知識と、リュミエール家で培った分析力。愛のない結婚であっても、この家の“公爵夫人”という立場を最大限に活かす方法があるかもしれない。
「……やるしかないわよね。」
誰に向けるでもなく小さく呟き、アスカは書類にペンを走らせる。数字の不整合を洗い出し、改善策のメモをまとめ、さらに使用人たちからの報告を精査する。やがて日が暮れ始める頃には、机の上に分厚い資料の山が築かれていた。
顔を上げれば、外はもう夜の帳が降り始めている。部屋のランプに火を灯し、冷めきった夕暮れの空気を感じながら、アスカは自嘲的に笑った。新婚初日と二日目を文字通り事務仕事に費やすなど、誰が想像しただろう。
しかし、不思議と後悔はなかった。むしろ、こうして頭を働かせている間は、レイヴンとの不和やセシリアの存在を忘れられるからだ。何より、今のアスカにとっては「このまま黙って周囲に翻弄されるしかない」という立場は耐え難い。
であれば、自分の手元にある“公爵夫人としての権限”を少しずつでも行使し、徐々に立場を確立していくのが得策だろう――そう直感的に悟っていた。
冷たい再会
夜が更けた頃、アスカは廊下に出てみることにした。書類に埋もれ続けるのも限度があるし、そろそろ身体を動かして血行を良くしたかったのだ。
歩き慣れない長い回廊を抜け、螺旋階段を下りると、正面玄関の扉がゆっくりと開かれる音が聞こえる。アスカが振り返ると、そこにはレイヴンの姿があった。黒いマントをはためかせ、無言で屋敷に戻ってきた公爵の表情は疲労と冷淡さがないまぜになっている。
レイヴンはアスカの存在に気づくと、一瞬だけ目を細めた。だが、すぐに無表情へと戻り、形式ばった会釈をする。
「……外出していた。戻りが遅くなったが、気にするな。」
「おかえりなさいませ。お仕事、お疲れ様でした。」
まるで赤の他人のような会話だった。夫婦としての情も感じられず、必要最低限の言葉だけが交わされる。昨日から続く、この冷たい距離感にアスカはやるせない思いを抱きながらも、微かな期待を捨てきれずに問いかける。
「よろしければ、少しお話をうかがっても……。公爵家の財務管理について、確認したいことがあります。あなたに直接ご相談できればと思っていたのですが……」
しかし、レイヴンはわずかに顔をしかめて、首を横に振った。
「悪いが、今日は疲れている。また今度にしてくれ。」
それだけ言い残し、彼は執事とともに廊下の奥へと消えていった。アスカは足元に広がる影を見つめながら、何をどうすればいいのか、一瞬わからなくなった。
(この人は、本当に私と夫婦でいるつもりなんてあるのだろうか……。)
夜と孤独
結局、レイヴンと話をすることは叶わず、アスカは再び自室に戻ってきた。ベッドの脇にはすでに夜着が用意され、部屋に灯ったランプの柔らかい光が一日の終わりを告げている。
窓の外を見れば、昨夜と同じように闇が広がり、遠くの街灯りがまるで別世界のように揺れていた。ここから見下ろす王都は、相変わらず賑やかに人々の営みを続けているはずなのに、アスカに届く気配はない。
心細さが胸を満たし始めたころ、控えめなノックの音がする。扉を開けると、そこにいるのはリディアだった。彼女は温かいハーブティーを乗せた銀のトレーを手にし、申し訳なさそうに微笑んでいる。
「アスカ様、今夜はずいぶん遅くまでお仕事されていたと聞きました。少しでも心を落ち着けられればと思いまして……。」
「ありがとう、リディア。本当に助かるわ。」
アスカはリディアを部屋に招き入れ、机の端にティーカップを置いた。香り立つハーブの匂いに、ふっと緊張が和らぐ。
しばらく無言のまま、アスカはハーブティーを口に含んだ。ほどよい苦みと爽やかな香りが、乾いた心に染み渡る。
「……ここでの暮らし、どう? まだ勝手がわからなくて混乱してるんじゃない?」
リディアが恐る恐る尋ねる。彼女自身も、公爵家の使用人に混じって働くのは気詰まりなはずだ。
「そうね。わからないことだらけよ。でも、知らないまま放っておいたら、私という存在は誰にも見てもらえないかもしれない。それなら、多少強引でも、自分から動くしかないと思っているの……。」
アスカの言葉に、リディアはしんみりとした表情を浮かべた。
「アスカ様はやはり強いお方ですね。私が見ていても、心が折れてしまいそうな環境なのに……。」
「強いわけじゃないわ。ただ、これ以上、無力だと思い知らされるのは嫌なだけ。」
その言葉には、アスカ自身も驚くほどの決意がこもっていた。愛のない結婚。家の道具としての人生。そんな運命を受け入れるだけでは終わらない――そう自分に言い聞かせるように。
白い結婚の幕は上がったばかり
そして夜が深まるにつれ、アスカは今日一日の出来事を思い返す。レイヴンの冷たい態度、セシリアの挑発、執事や秘書官が抱える謎の財務事情。この“白い結婚”の裏には、思った以上に複雑な事情が渦巻いているのかもしれない。
だが、彼女はかすかな手応えを感じてもいた。政略結婚とはいえ、公爵夫人という立場を得たからには、それ相応の権限と責任がある。それを巧みに使えば、自分がただの人形で終わることなく、やがては家族やレイヴン、そしてセシリアすらも出し抜く可能性があるかもしれない――。
リディアが退出した後、アスカは重厚なカーテンを引き、ベッドに潜り込む。体は疲れ果てているはずなのに、頭は冴えたまま眠気を感じない。
暗い天井を見つめながら、彼女は密かに誓う。
(私は、こんな結婚を望んだわけじゃない。でも、だからと言って無力に甘んじるつもりもない。いつか必ず、この結婚に“ざまあ”と笑える日を迎えてみせる――。)
その誓いは、白く冷たい婚礼が済んだばかりの夜にしては、あまりにも熱を帯びていた。しかし、彼女の中で芽生え始めたこの炎は、まだ誰にも知られてはいない。
外の夜空では雲が重なり合い、月明かりさえも遮られている。だが、厚い雲の向こうに月が輝いているように、アスカの心の奥底にも光が潜んでいると信じたかった。今はまだ微弱な光でも、必ずそこから道が開けると――。
こうして、公爵家での生活が本格的に動き出す。夫との会話もままならず、彼の周囲には謎をはらんだ愛人らしき女性。そして屋敷の使用人たちの不穏な空気。数多の難題を抱えたまま、アスカは公爵夫人としての地位を少しずつ固めようと足掻き始めていた。
2
あなたにおすすめの小説

冷酷侯爵と政略結婚したら、実家がざまぁされました
鍛高譚
恋愛
「この結婚は、家のため。ただの政略結婚よ」
そう言い聞かせ、愛のない結婚を受け入れた公爵令嬢リゼット。
しかし、挙式後すぐに父が「婚約破棄しろ」と命じてきた!?
だが、夫であるアレクシス・フォン・シュヴァルツ侯爵は冷たく言い放つ。
「彼女を渡すつもりはない」
冷酷無慈悲と噂される侯爵が、なぜかリゼットを溺愛し始める!?
毎日甘やかされ、守られ、気づけば逃げ場なし!
さらに、父の不正が明るみに出て、公爵家は失墜――
リゼットを道具として利用しようとした者たちに、ざまぁの鉄槌が下される!
政略結婚から始まる、甘々溺愛ラブストーリー!
「愛なんてないはずなのに……どうしてこんなに大切にされるの?」
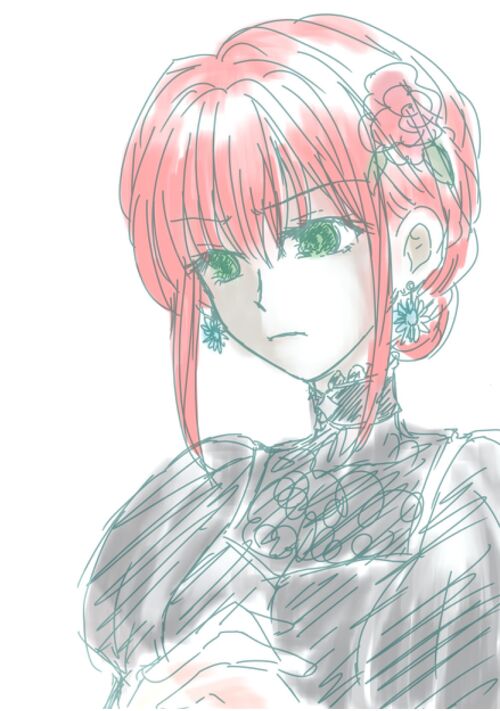
捨てられた悪役はきっと幸せになる
ariya
恋愛
ヴィヴィア・ゴーヴァン公爵夫人は少女小説に登場する悪役だった。
強欲で傲慢で嫌われ者、夫に捨てられて惨めな最期を迎えた悪役。
その悪役に転生していたことに気づいたヴィヴィアは、夫がヒロインと結ばれたら潔く退場することを考えていた。
それまでお世話になった為、貴族夫人としての仕事の一部だけでもがんばろう。
「ヴィヴィア、あなたを愛してます」
ヒロインに惹かれつつあるはずの夫・クリスは愛をヴィヴィアに捧げると言ってきて。
そもそもクリスがヴィヴィアを娶ったのは、王位継承を狙っている疑惑から逃れる為の契約結婚だったはずでは?
愛などなかったと思っていた夫婦生活に変化が訪れる。
※この作品は、人によっては元鞘話にみえて地雷の方がいるかもしれません。また、ヒーローがヤンデレ寄りですので苦手な方はご注意ください。

「君を愛することはない」と言われたので、私も愛しません。次いきます。 〜婚約破棄はご褒美です!
放浪人
恋愛
【「愛さない」と言ったのはあなたです。私はもっとハイスペックな次(夫)と幸せになりますので、どうぞお構いなく!】
侯爵令嬢リディアは、建国記念舞踏会の最中に、婚約者である王太子レオンハルトから婚約破棄を宣言される。 「君を愛することはない!」という王太子の言葉は、国中に響く『公的拒絶誓約』となってしまった。
しかし、リディアは泣かなかった。 「承知しました。私も愛しません。次いきます」 彼女は即座に撤退し、その場で慰謝料請求と名誉回復の手続きを開始する。その潔さと有能さに目をつけたのは、国の行政を牛耳る『氷の宰相』アシュ・ヴァレンシュタインだった。
「私の政治的盾になれ。条件は『恋愛感情の禁止』と『嘘がつけない契約』だ」
利害の一致した二人は、愛のない契約結婚を結ぶ。 はずだったのだが――『嘘がつけない契約』のせいで、冷徹なはずの宰相の本音が暴走! 「君を失うのは非合理だ(=大好きだ)」「君は私の光だ(=愛してる)」 隠せない溺愛と、最強の夫婦による論理的で容赦のない『ざまぁ』。
一方、リディアを捨てた王太子は「愛さない誓約」の呪いに苦しみ、自滅していく。 これは、悪役令嬢と呼ばれた女が、嘘のない真実の愛を手に入れ、国中を巻き込んで幸せになるまでの物語。

婚約破棄?結構ですわ。公爵令嬢は今日も優雅に生きております
鍛高譚
恋愛
婚約破棄された直後、階段から転げ落ちて前世の記憶が蘇った公爵令嬢レイラ・フォン・アーデルハイド。
彼女の前世は、ブラック企業で心身をすり減らして働いていたOLだった。――けれど、今は違う!
「復讐? 見返す? そんな面倒くさいこと、やってられませんわ」
「婚約破棄? そんなの大したことじゃありません。むしろ、自由になって最高ですわ!」
貴族の婚姻は家同士の結びつき――つまりビジネス。恋愛感情など二の次なのだから、破談になったところで何のダメージもなし。
それよりも、レイラにはやりたいことがたくさんある。ぶどう園の品種改良、ワインの販路拡大、新商品の開発、そして優雅なティータイム!
そう、彼女はただ「貴族令嬢としての特権をフル活用して、人生を楽しむ」ことを決めたのだ。
ところが、彼女の自由気ままな行動が、なぜか周囲をざわつかせていく。
婚約破棄した王太子はなぜか複雑な顔をし、貴族たちは彼女の事業に注目し始める。
そして、彼女が手がけた最高級ワインはプレミア化し、ついには王室から直々に取引の申し出が……!?
「はぁ……復讐しないのに、勝手に“ざまぁ”になってしまいましたわ」
復讐も愛憎劇も不要!
ただひたすらに自分の幸せを追求するだけの公爵令嬢が、気づけば最強の貴族になっていた!?
優雅で自由気ままな貴族ライフ、ここに開幕!

ぽっちゃり侯爵と大食い令嬢の甘い婚約生活
piyo
恋愛
女性秘書官として働きながら、“大食い令嬢”の異名を持つダニエラ。そんな彼女に、上司のガリウスがひとつの縁談を持ってくる。
相手は名門オウネル侯爵家の当主、キーレン・オウネル。
大変ふくよかな体形の彼は、自分と同じように食を楽しんでくれる相手を探していた。
一方のダニエラも、自分と同じくらいの食欲のある伴侶を求めていたため、お茶会を通じて二人は晴れて婚約者となる。
ゆっくりと距離を縮め、穏やかに愛を育んでいく二人だが、
結婚式の半年前、キーレンが交易交渉のため国外へ赴くことになり――
※なろうにも掲載しています

天然だと思ったギルド仲間が、実は策士で独占欲強めでした
星乃和花
恋愛
⭐︎完結済ー本編8話+後日談7話⭐︎
ギルドで働くおっとり回復役リィナは、
自分と似た雰囲気の“天然仲間”カイと出会い、ほっとする。
……が、彼は実は 天然を演じる策士だった!?
「転ばないで」
「可愛いって言うのは僕の役目」
「固定回復役だから。僕の」
優しいのに過保護。
仲間のはずなのに距離が近い。
しかも噂はいつの間にか——「軍師(彼)が恋してる説」に。
鈍感で頑張り屋なリィナと、
策を捨てるほど恋に負けていくカイの、
コメディ強めの甘々ギルド恋愛、開幕!
「遅いままでいい――置いていかないから。」

主人公の恋敵として夫に処刑される王妃として転生した私は夫になる男との結婚を阻止します
白雪の雫
ファンタジー
突然ですが質問です。
あなたは【真実の愛】を信じますか?
そう聞かれたら私は『いいえ!』『No!』と答える。
だって・・・そうでしょ?
ジュリアーノ王太子の(名目上の)父親である若かりし頃の陛下曰く「私と彼女は真実の愛で結ばれている」という何が何だか訳の分からない理屈で、婚約者だった大臣の姫ではなく平民の女を妃にしたのよ!?
それだけではない。
何と平民から王妃になった女は庭師と不倫して不義の子を儲け、その不義の子ことジュリアーノは陛下が側室にも成れない身分の低い女が産んだ息子のユーリアを後宮に入れて妃のように扱っているのよーーーっ!!!
私とジュリアーノの結婚は王太子の後見になって欲しいと陛下から土下座をされてまで請われたもの。
それなのに・・・ジュリアーノは私を後宮の片隅に追いやりユーリアと毎晩「アッー!」をしている。
しかも!
ジュリアーノはユーリアと「アッー!」をするにしてもベルフィーネという存在が邪魔という理由だけで、正式な王太子妃である私を車裂きの刑にしやがるのよ!!!
マジかーーーっ!!!
前世は腐女子であるが会社では働く女性向けの商品開発に携わっていた私は【夢色の恋人達】というBLゲームの、悪役と位置づけられている王太子妃のベルフィーネに転生していたのよーーーっ!!!
思い付きで書いたので、ガバガバ設定+矛盾がある+ご都合主義。
世界観、建築物や衣装等は古代ギリシャ・ローマ神話、古代バビロニアをベースにしたファンタジー、ベルフィーネの一人称は『私』と書いて『わたくし』です。

【完結】番としか子供が産まれない世界で
さくらもち
恋愛
番との間にしか子供が産まれない世界に産まれたニーナ。
何故か親から要らない子扱いされる不遇な子供時代に番と言う概念すら知らないまま育った。
そんなニーナが番に出会うまで
4話完結
出会えたところで話は終わってます。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















