4 / 4
第四章:自由への解放
しおりを挟む冷たい朝の光が、公爵家の広大な中庭を照らし出す。その眩しさとは裏腹に、屋敷の内側は重苦しい空気に包まれていた。数日前に起こった地下書庫での“騒ぎ”について、表立った説明はいまだになされていないが、使用人たちはどこか落ち着きを失い、ひそひそと囁き合っている。
その原因は明らかに、セシリアやアーヴィング商会の暗躍、あるいはレイヴン公爵の長期不在だろう。だが、表面上は誰もが「何事もない」ふりを装い、日常業務に追われている。
アスカは執務室で朝食を軽く済ませながら、改めて机上に並べた書類を確認した。いずれも地下書庫から持ち出した古文書や、謎の男から受け取った紙片の“写し”である。原本そのものは危険が大きいため、一部は別の場所に隠しておき、ここではメモ程度のものを精査するにとどめている。
「先代公爵の時代にかわされた闇契約……担保としての領地譲渡……アーヴィング商会からの融資……。どれをとっても、まともな手段じゃ返済できない莫大な額ばかり。もし期限が迫っているなら、公爵家が一気に崩壊してもおかしくないわね。」
思わずつぶやく言葉には、やりきれない怒りと焦燥がにじむ。自分が嫁いでくるより前――もっと言えば先代公爵の生前から仕組まれていた借金地獄。それを若くして公爵を継いだレイヴンが、強引な手段で何とか凌いできた。しかし今、その綻びがついに限界に達しようとしているのだろう。
結果としてアーヴィング商会のような大口の貸主が、実質的に公爵家の支配権を手中に収めつつあり、セシリアはそこに食い込んで“愛人”以上の権力を振るっている。もし本当に返済不能となれば、彼女は公爵家そのものを呑み込み、レイヴンを完全に排除できる立場になるかもしれない。
(セシリアは最初から、レイヴン様を手玉にとって公爵家を乗っ取る気だったの……? それとも、レイヴン様が自主的に彼女を利用している?)
疑念と不安が渦巻く中で、アスカは唇を噛み、書類を一枚ずつ丁寧に重ね直す。
――とはいえ、これだけの情報を手にしても、ただ嘆いているだけでは何も変わらない。むしろ危険を承知で動き出すしかないのだ。アスカは決意を新たにし、椅子から立ち上がった。
---
不安定な朝の屋敷
執務室を出ると、廊下でアスカを見つけた侍女が駆け寄ってくる。顔見知りの若い侍女――ロザリーだ。彼女は何やら落ち着かない様子で、アスカに耳打ちした。
「アスカ様、大変です。玄関ホールにアーヴィング商会の方々が来られています。公爵様がお戻りでないのに、執事や秘書官を問い詰めているようで……どうやら差し押さえがどうとか騒いでいるみたいで……。」
「差し押さえ……? まさか、本当に期限が迫っていて、商会が動き出した……?」
アスカの背筋が冷たくなる。まさに最悪のシナリオが現実になろうとしているのかもしれない。レイヴィンがいない今、商会が公爵家の財産を差し押さえようと進めば、使用人たちはなす術がない。屋敷にある調度品や芸術品だけでなく、領地の管理権まで奪われる可能性もある。
足早に玄関ホールへ向かうと、そこではスーツ姿の男たちが執事のオーランドと激しい口論をしていた。商会の手代とおぼしき男が、大きな帳簿を開きながらまくし立てる。
「確かに期日が迫っているのに、肝心の公爵殿はどこにいるのかね!? このまま不在を貫くつもりか? それならそれで結構。我々は契約に則り、担保物の引き渡しを要求するまでだ!」
「し、しかし……公爵様は近々お戻りになるはずで……もう少しお待ちいただければ……。」
オーランドが必死に取り繕うものの、相手は聞く耳を持たない。周囲の使用人たちは怖気づいて近づけないでいる。そこへアスカが足を踏み出すと、ホールの空気が一変した。
商会の男たちが振り返り、新妻であるアスカの姿を認めるなり、嫌な笑みを浮かべる。
「これはこれは、公爵夫人か。あなたに支払い能力がおありなら、すぐにでも帳尻を合わせていただきたいのですがね。」
「お前たち……言葉を慎みなさい。ここはレイヴン公爵家の邸内よ。私が夫人として対応するわ。」
アスカはわずかに顎を上げ、気丈な態度を示した。胸の奥に湧き上がる動揺を抑え込み、冷静に対話を試みる。ここで取り乱せば、相手の思うツボだ。
だが、男たちは意に介さず、帳簿を突きつけてくる。
「では夫人、申し訳ありませんが、すぐに支払いの段取りを示してください。利子を含めた全額で、少なくとも王都の金貨でこのくらい――」
「……!」
男が見せた金額は想像を絶する大きさだった。アスカが実家のリュミエール家で聞いた財力と比べても、到底まかなえるレベルではない。すぐに現金化など不可能だろう。
使用人たちは青ざめ、オーランドが途方に暮れたように首を振る。アスカは平静を装いながらも、絶望感に近い重みを感じていた。
(この額……本当に返済期限が“今日”なの? レイヴン様は何を考えているの……こんな最悪の事態をどうするつもりだったの?)
困惑を押し殺し、彼女は言葉を選びながら反論する。
「あなたたちが提示する金額が正しいかどうか確認が必要よ。契約書の写しを改めて出していただけない? こちらにも“把握している資料”がありますので、照合しましょう。」
「ふん、公爵夫人が財政を仕切るなどとは聞いていないが……まあいいだろう。もっとも、あれこれ調べて時間稼ぎをしても無駄だぞ。すでに期限を過ぎているんだからな。」
男はあからさまな嘲笑を浮かべ、使用人に目配せする。すると、数人が大荷物を抱えてホール内に入り込み、奥の部屋へと向かおうとする。
それはまるで「差し押さえに必要な物品を運び出す準備」を始めているかのような光景だった。アスカの胸に激しい怒りと焦燥が燃え上がる。
---
必死の対抗策
「待って! あなたたち、許可なく奥へ入ることはできないわ。」
アスカは彼らの進路を塞ぐように立ちはだかる。ここで強引に差し押さえを進められれば、貴重な財宝や公爵家の証として扱われる品々が根こそぎ奪われる可能性がある。
男たちは明らかに苛立ちを見せ、「どけ」と言わんばかりに睨みつけてくる。けれどもアスカは一歩も引かない。使用人たちも困惑気味ではあるが、夫人の決意を感じ取ったのか、密かに彼女の背後へ集まり始めた。
「公爵が不在のうちに、勝手な行動は許しません。あなたたちは債権者であっても、この屋敷を勝手に踏みにじる権利などないはずよ。」
「しかし、公爵家は既に期限を踏み倒している。無断の強制執行をしたくはないが、これ以上の猶予も与えられんぞ。」
男の言葉は強硬だが、法的に見れば強制執行には手続きが必要だ。すぐに押収や差し押さえができるわけではない。アスカはそのわずかな隙を突きたいと考えた。
「まずは契約と書類を照合させて。もしその手続きなく屋敷の奥へ踏み込むのであれば、それこそ違法行為として王宮に訴えるわ。……あなたたちも、無用なトラブルは望んでいないでしょう?」
口にする言葉はあくまでも冷静に、しかし毅然とした調子で。実際、王家や貴族会議の裁定を仰ぐとなれば、手間や時間がかかる。アーヴィング商会もできることなら短期で片づけたいはずだ。
男たちは視線を交わし合い、やがてリーダー格らしき人物が溜め息をつく。
「……わかった。そこまで言うなら、ひとまず書類の照合に応じてやろう。だが、時間は限られているぞ。公爵夫人、今から数時間以内に正当な支払いの見通しが立たないなら、我々は本当に強制執行に踏み切る。それでいいな?」
「承知しました。オーランド、応接室へ案内してちょうだい。すぐに照合を始めます。」
アスカは男たちを応接室へと誘導し、執事や秘書官の協力を仰いで書類を持ち寄るよう指示を出す。わずかではあるが、この場で差し押さえを強行される最悪の事態は回避できた。だが、時間稼ぎにしか過ぎない。
少なくとも数時間、まとまった金額がどこかから用意できない限り、いずれ商会は再び屋敷を蹂躙しようとするだろう。
---
足並み揃わぬ家臣たち
アスカの指示で、屋敷内の文書――財務帳簿や契約に関わる書類――が続々と応接室へ運ばれる。執事のオーランドや会計係のイーヴァン、さらには古参の使用人たちが各々で探し回っているが、その動きには明らかな混乱が見られた。
というのも、レイヴンが独断で管理している書類が多く、会計係ですら把握していない支出や取引が存在することが判明したからだ。先代公爵の時代から続く闇契約は、さらにその上をいく複雑さを帯びており、誰一人として全貌を掴めていない。
さらにセシリアの存在も混乱に拍車をかける。彼女の部屋や私室に「秘匿された契約書類がある」という噂があるが、侍女や使用人レベルでは立ち入りを許されない。セシリア本人は姿を見せず、部下たちも行方をくらましている様子だ。
「公爵夫人、こちらの決算報告書ですが……どうも数字が合わない箇所が多くて。おそらく公爵様が独自に訂正を加えられたのかもしれませんが、経緯がわからなくて……。」
「わかりました、イーヴァン。とにかく今ある情報だけでもまとめましょう。彼らが提示している金額とどのくらい差があるかを確認するのが先決です。細部は後からでも精査できます。」
アスカはそう励ましながら、次々と運ばれる書類に目を通していく。まるで荒れ果てた草原に散らばる種を一つずつ拾い集めるような作業。正直、数時間で何がわかるとも思えない。
それでも、ここで投げ出せば公爵家は商会の思うままにされる。“白い結婚”の檻に閉じ込められたまま自分の人生まで奪われてしまう。アスカは唇を引き結び、時間との戦いに臨んだ。
---
思わぬ助力
昼に差しかかるころ、応接室の中は紙や帳簿が山積みとなり、使用人たちが行き交う混戦状態だった。アーヴィング商会の手代たちは、余裕を装いつつも「まだか」と苛立ちを示している。
そんなとき、ドアが開き、そこから一人の男がゆっくりと入ってきた。朝の出来事を聞きつけてやってきたのか、まるで時機を見計らったかのようだ。
――謎の男ではない。彼は以前、舞踏会のときにアスカとも面識がある伯爵――カルデール伯だった。王都の社交界では情報通として知られ、あちこちの貴族とのパイプを持つ人物だ。アスカにとっては、多少気難しいが、まったく信用できないわけでもない存在である。
「おや、これは騒々しいですな。何やら公爵家が一方的に責め立てられているように見えますが……。」
「カルデール伯……どうしてここに?」
アスカは驚きつつ、彼の来訪を歓迎すべきか迷う。だが、カルデール伯は軽く笑って杖をつきながら応接室を見回した。
「実は、王都の商会筋から“レイヴン公爵家が破綻寸前”だという噂を聞きましてね。もし本当にそうなら、私も困るのですよ。公爵家が消えてしまえば、多くの取引先が連鎖的に困窮しますからな。私自身、いささか商売に手を染めておりますので……」
「……つまり、助けに来てくださったと考えていいのでしょうか?」
すると伯爵は眉を上げてニヤリと笑う。
「“助け”というほど甘いものではありません。私にもメリットがなければ動きませんよ。ただ、公爵家に協力する形で“痛み分け”くらいにはできるかもしれない。少なくとも、アーヴィング商会が無茶をしないよう牽制する手段は持っています。」
たとえ下心があったとしても、現状でアスカが頼れる外部の人間は極めて限られている。こうなれば、多少のリスクを承知でカルデール伯の力を借りるしかない。アスカは深く一礼した。
「わかりました。もし伯爵がアーヴィング商会を牽制できるなら、ぜひご助力をお願いしたい。私たちも全力で返済の道を探りますので……。」
「ふむ、ではひとまず“時間”を稼ぎましょう。アーヴィング商会の連中と話をつけてみます。王都の商会連合を通じて“正式な差し押さえ”にかかるには、まだ手続きが必要なはず。そこを突きましょう。」
そう言うが早いか、カルデール伯は債権者のグループのほうへ足を運び、流麗な口調で話しかけ始めた。さすが社交界きっての外交術師ともいうべき言葉遣いで、男たちの警戒心をときほぐし、手続きの正当性を問いただす。
アスカはそれを見守りつつ、隣に立つオーランドに小声で指示する。
「伯爵が交渉している間に、私たちはさらに書類を洗い直しましょう。もしわずかな金額でも取り繕える方法があるなら、すぐに動かないと……。」
「承知しました、公爵夫人。イーヴァンにも声をかけておきます。何とか、一部だけでも支払いのメドを立てられれば……。」
こうして、カルデール伯の思わぬ登場で最悪の事態は一旦回避される可能性が出てきた。しかし、依然としてレイヴン公爵は戻らないまま。セシリアも姿を見せず、アーヴィング商会が一枚噛んだ債権額が消えるわけでもない。アスカの不安は募るばかりだった。
---
戻らぬ夫、揺れるセシリアの影
日が傾き始めたころ、カルデール伯の交渉により、一時的に商会側が“正式な差し押さえ”を実行するのを先延ばしにする暫定合意が成立した。アスカやオーランド、イーヴァンが必死に契約書類を照合して“一部は不当”と主張したことも大きい。
結果として、商会は今夜いっぱいは引き揚げ、明日の正午までに公爵家が「支払い計画」を提示することを条件に、強制執行を保留すると取り決めたのである。
アスカは応接室を見回し、まるで嵐が過ぎ去った後のように散乱した書類の山を見て、疲労感とともに大きく息をついた。まだ戦いは終わっていないが、少なくとも今夜中に屋敷が差し押さえられる最悪の惨劇は避けられた。
(でも、肝心の“返済計画”なんて、私たちだけで本当に立てられるの……?)
頭を抱えたい気分になる。レイヴン公爵がいればこそ、どこかから追加の融資を受けるなり、あるいは新たな契約を結ぶなり、何らかの方策を打ち出す道もあったかもしれない。しかし当人不在の今、アスカたちは文字どおり手探り状態だ。カルデール伯が資金援助を申し出るはずもないし、ましてやリュミエール家に金銭的余裕はほとんどない。
そのとき、使用人が慌てたように駆け寄ってきた。
「公爵夫人、大変です。セシリア様が別室でお待ちだと……“すぐに来なさい”と。」
「セシリアが……? こんなときに、何の用かしら。」
アスカは眉をひそめる。自ら姿を見せず、影で何かを操っていたセシリアが、どういう風の吹き回しで呼び出すのか。
一抹の不安を抱えつつ、彼女は重い足取りでセシリアの私室へ向かった。
---
セシリアとの対峙
セシリアの部屋は普段、彼女専用のサロンとして使われている。豪奢な調度品や香り高い花々が飾られ、まるで王宮の一室かと見紛うほど華やかな空間だ。しかし、その空気は薄く冷たい毒のような甘さを孕んでいる。
ドアを開けると、セシリアは窓辺に立っていた。金髪を美しくまとめ、高価そうなドレスに身を包んだ姿は絵になるが、その瞳にはどこか焦燥の色が宿っているようにも見えた。
「お呼びとのことでしたが……何かご用でしょうか、セシリア様。」
アスカが一礼すると、セシリアはくすりと笑みを浮かべながら振り返る。
「ええ、少し話がしたくてね。――あなた、このまま公爵家が没落してもいいの? それとも、どうにかして立て直したいのかしら?」
「……急に何の話ですか。今はまだ、私たちも必死に対策を考えている最中です。」
アスカは警戒を隠せずに答える。セシリアがこんな話題を振るのは、何らかの“取引”を持ちかけてくる前兆に違いない。
案の定、セシリアは窓際に置かれたテーブルから一枚の書類を拾い上げ、アスカの前でひらひらと揺らす。
「これね、アーヴィング商会が独自に用意している“再融資契約書”なの。もしレイヴンがサインしてくれれば、既存の債務をある程度減免して、新たな利子で改めて融資をしてくれるわ。そうすれば公爵家は破産を免れるかもしれない。」
「……そんな話があるなら、なぜ今まで黙っていたの?」
セシリアは目を細め、鼻で笑う。
「あなたたちがバタバタしているのを見物していたのよ。正直言って、公爵夫人のあなたがどこまで役に立つのか興味もあったし。――でも、結論から言えば、あなた一人が頑張っても所詮は時間稼ぎに過ぎないわね。ここで“私の提案”を飲んでくれれば、公爵家は助かる可能性が出てくるわ。」
「“提案”って、一体……。」
その言葉に重々しい響きを感じ、アスカは緊張感を高める。セシリアはゆっくりと歩み寄り、書類をアスカの手元に突きつけた。
「簡単なことよ。レイヴンがサインする前に、あなたがこの新契約に“保証人”として署名するの。そうすれば、公爵家としては“夫人も納得済みの契約”になるでしょう?」
「私が保証人に……!? そんな、利子がさらに膨れ上がる危険な契約に、何のメリットがあるの……?」
アスカの声が震える。セシリアの企みが単純ではないのは承知の上だが、ここまで強引な方法を提示してくるとは予想外だった。
セシリアは冷ややかに笑みを深める。
「メリットは“公爵家が一時的にでも救われる”こと。違えば、今のままでは今夜か明日にでも強制執行が始まるかもしれないのよ? これ以上、あのカルデール伯に頼っても、どうせお金は出してくれないわ。あなたが必死に集められる金額なんて、たかが知れているでしょう?」
「それは……そうかもしれません。でも、私が保証人になったら、リュミエール家まで巻き込まれる可能性が――」
「ええ、そうなるわね。でも、それがお父上イザークの望みでもあるのでしょう? “公爵家”と縁戚を結ぶことで、再びリュミエール家を栄光に導くと豪語していたじゃない。ならば、全力で協力するのが筋というものよ。」
言葉の端々に嘲笑の色がにじみ、アスカは怒りを覚える。セシリアが何を狙っているのかは明白だ。公爵家とリュミエール家を丸ごと借金の連帯責任に巻き込んで、最終的には自分がアーヴィング商会との取引を主導する立場に立つ――つまり、公爵家とリュミエール家の両方を支配下に収めようとしているのだろう。
一方で、レイヴンの不在を逆手に取ることで、アスカだけを“夫人としての義務”に追い詰め、無理矢理契約へ署名させるつもりに違いない。ここでイエスと言えば、確かに当面の破綻は避けられるかもしれない。だが、後々にはさらに厳しい取り立てが待ち受けるのは火を見るより明らかだ。
「ごめんなさい、セシリア様。その提案、私は受けるわけにはいきません。」
アスカは毅然とした調子で宣言する。どれほど厳しくとも、こんな借金地獄を引き継ぐ再契約に署名すれば、公爵家のみならず自分自身が完全に奴隷化されるも同然だ。
セシリアは目を細め、片眉を上げた。
「……そう。なら、勝手に破滅してちょうだい。私としては、最悪の場合でも“公爵家”がなくなれば、別の形でアーヴィング商会から利益を引き出すだけだけど?」
冷たい声。アスカは一瞬だけ言葉を失うものの、毅然とした態度を崩さない。
「ええ、あなたがどうしようと、それは自由よ。私はこの“白い結婚”を通じて、ただ従うだけの人形ではない。夫婦二人の合意なき契約は意味がないわ。……もし私を脅すなら、公開の場で争う覚悟があるのかしら?」
「貴族同士の恥晒しをするつもり? あなた、本当に覚悟があるの? ……いいわ、やってみなさい。私は楽しみにしているわよ。」
挑発とも取れる言葉を残し、セシリアは書類をテーブルに放り投げると、部屋の奥へ消えていった。背後に残されるのは、戦慄するような静寂だけ。
アスカはこみ上げる恐怖を抑えつつ、硬直した足を引きずるようにして部屋を後にする。
---
手掛かりを求めて
セシリアの部屋を出たアスカは、廊下を歩きながら息苦しさを覚えた。差し押さえの危機はひとまず先延ばしにできたが、根本的な解決策が見えていない。セシリアの提案を蹴った以上、今後はさらに苛烈な圧力を受けるだろう。
それでも、絶望に屈するわけにはいかない。アスカは再び執務室へ足を運び、机上に並ぶ書類を眺める。
そこには先日の地下書庫で得た契約の写しや、謎の男から提供された紙片がある。中には先代公爵の名で土地を手放した記録や、アーヴィング商会との裏取引の兆候が記されているものもあった。
セシリアやアーヴィング商会が握る“本当の契約書”と矛盾する点がもし見つかれば、それを盾に交渉を有利に進められるかもしれない。先代公爵が本当にどんな条件で闇契約を結んだのか、その整合性を崩せれば、こちらが一方的に負けることはないはず。
(レイヴン様はいつ戻ってくるの……。もし彼がいれば、何か情報を持っているかもしれないのに。)
だが、不在の夫を当てにしても仕方ない。アスカはイーヴァンやオーランドにも協力を仰ぎ、少しでも矛盾点を探そうと決意する。王都の法律や貴族の慣例を熟知した人材を呼び寄せるのも一案だ。
セシリアとの“第二ラウンド”に備え、できる限りの準備をしておく必要がある。
---
思わぬ訪問者、そして一筋の光
夕闇が迫るころ、屋敷の裏口からひっそりと入ってきた人影があった。アスカは廊下で侍女のリディアに呼び止められ、その人物と面会することになる。
そこに立っていたのは――またしてもあの“謎の男”だった。少し埃まみれの服装で、疲労の色が濃い。彼は周囲を警戒するように辺りを見回してから、アスカに低く声をかける。
「どうやら随分と騒ぎになっているようだな。アーヴィング商会が強硬手段を取り始めたか。……お前の顔を見れば、結果はだいたい想像がつく。」
「あなた……また勝手に屋敷に入ってきたの? そう何度も無事に済むと思わないで。」
怒りと警戒が入り混じったアスカの言葉に、男は肩をすくめる。
「俺としても危険は承知だ。だが、お前に伝えておきたい情報がある。――どうやらアーヴィング商会は“追加の締め付け”を早めるようだ。近々、公爵家の領地に直接手を突っ込み、収益源を抑えようとしているらしい。そっちが抵抗できなければ、いよいよ詰みだな。」
「領地を……。それって、つまり農地や鉱山を勝手に管理し始めるということ? そんなことを許せば、公爵家は完全に終わりじゃない!」
アスカが声を荒げると、男は手をひらひらと振る。
「落ち着け。だからこそ、お前に手を打つ時間を与えてやろうと思って来たんだ。もし、お前が“先代公爵の隠し資金”や“密約の弱点”を掴んでいれば、少なくとも商会に揺さぶりをかけられる。奴らが違法スレスレの取引をしている証拠を公にすれば、大きなダメージになるだろう。」
「先代の隠し資金……そんなもの、本当にあるの? 書庫には契約書しか見当たらなかったし……。」
「あるやもしれんし、ないやもしれん。だが、俺の耳には“先代公爵が王宮筋に隠していた宝飾品”や“海外との貿易利益を別口座にプールしていた”などの噂が入ってきている。真偽はわからんが、もし本当に残っているなら、アーヴィング商会への支払いの一部に充てることもできるだろう。……あるいは、その存在をネタに交渉するのも手だな。」
男の言葉に、アスカの心は大きく揺さぶられる。虚言かもしれない。だが、ほんのわずかな希望でもあるなら、掴んでおきたい気持ちが湧き上がる。
レイヴンがどこまで知っているのかはわからないが、彼が必死にアーヴィング商会と渡り合ってきた背景には、何かしらの“切り札”があった可能性も否定できない。
「でも、あなたは何のためにそんな情報を教えてくれるの? 私がそれを使って商会を牽制すれば、あなたにとっても都合がいいの?」
「まあね。俺にも狙いがある。アーヴィング商会やセシリアが好き勝手に権力を握るのは面白くない。もっと言えば、レイヴンがあまりに早く没落してくれても困るんだ。――お前の動き次第では、俺も多少は動きやすくなる。」
打算しか感じられない説明だが、背に腹は代えられないのが現実だ。アスカはしばし逡巡の末、目を伏せて問いかける。
「わかった。もし先代の隠し資金の手掛かりがあるなら、教えて。私も、もう時間がないの。」
「よし。詳しい話は長くなるから、いったん場所を移そう。このまま廊下で話すのはリスキーだ。……案内してくれ。」
彼の言葉にうなずき、アスカは周囲を警戒しながら少し離れた部屋へと男を連れ込む。自分でも危険だと理解しているが、今はもう後戻りはできない。
もし本当に“先代公爵の隠し資金”が存在するなら、それがこの絶体絶命の危機を打開する最後の光になるかもしれない。アスカは疲れた身体に鞭打ち、再び希望を見出そうと必死に足を進める。
---
第四章前編の幕引き:選択のとき
こうして、追い詰められつつある公爵家とアスカの状況は、さらに加速しながら混沌の度合いを深めていく。アーヴィング商会は差し押さえの手を強め、セシリアは新たな契約書でアスカを陥れようと画策し、レイヴン公爵は依然として行方知れず。
そんな中、アスカの前に再び現れた“謎の男”がもたらす『先代公爵の隠し資金』の噂は、一筋の光にも思えるが、同時に新たな火種でもある。もしそれが事実でも、アスカの行動次第ではさらなる混乱を生む危険がある。
彼女は「白い結婚」という檻から抜け出し、周囲を“ざまあ”と言わしめるほどの逆転劇を成し遂げられるのか。それとも、莫大な借金の重みに押し潰され、セシリアとアーヴィング商会に全てを奪われるのか――。
アスカは胸の内で、もう一度決意を固める。たとえ茨の道でも、自分の力で切り拓くしかない。何も知らずに従うだけでは、家族も未来も守れないのだ。
公爵家の運命を左右する“勝負のとき”が近づいている。闇に沈みそうなその道筋に、僅かな光が射しているのかもしれない――アスカはその微かな灯火を頼りに、さらなる行動へ移る覚悟を抱いていた。
冷たい朝の風が、中庭の草木をざわつかせる。公爵家の屋敷は一見すると静寂を保っているが、その内側ではいつ爆発してもおかしくない緊張感が漂っていた。
昨晩、謎の男がアスカにもたらした「先代公爵の隠し資金」の噂は、ほんのわずかな希望を灯している。しかし同時に、セシリアやアーヴィング商会の圧力はますます強まる一方だ。
屋敷が差し押さえられるまで、猶予はほとんど残っていない。レイヴン公爵の長き不在は続き、セシリアは新しい融資契約への署名を迫る姿勢を変えず、かといって今すぐ強制執行をかけるわけでもない。その曖昧な状況に、誰もが息苦しさを感じていた。
---
隠し財産を追う手がかり
夜明け前、アスカは侍女のリディアと二人、ひそやかに屋敷の外へ足を運んだ。謎の男の情報によれば、「先代公爵の隠し資金」は王都近郊の貸金庫か、あるいは旧離宮の宝物庫など、複数の候補地に分散している可能性があるという。
もちろん、その真偽は定かではない。だが、今のアスカには、どんな危うい希望でもすがらざるを得なかった。もしそれが実在し、融資の一部または債務の担保として差し出せるなら、アーヴィング商会に対して対抗策を講じることができるかもしれない。
「アスカ様、本当にお一人で行かれるのですか? 王都の外れにある“古い貸金庫”だなんて、治安も良くないと聞きますし……。私もご同行いたします!」
「ありがとう、リディア。でもあなたまで危険な目に合わせるわけにはいかない。ここは私が一人で行くわ。もし万一のことがあったら、あなたが屋敷を守って。オーランドやイーヴァンと協力して、“私がやろうとしたこと”を伝えてほしいの。」
リディアは不安そうに俯いたが、アスカの固い決意を感じ取り、言葉を失う。公爵夫人として――いいえ、一人の人間として、自分の意思で動いている彼女を止めることはできない。
アスカは黒いケープを羽織り、裏門から一人で馬車へ乗り込んだ。御者には最低限の説明だけをし、出発を促す。
先代公爵が残したという噂の隠し財産。捏造かもしれない。だが、そこにかけるしかないのだ。そう自らを奮い立たせ、夜明けの淡い闇を抜けるように馬車は王都の街道を走り出す。
---
王都近郊の貸金庫
目的地は王都の外れにある、古い金融業者の倉庫群と聞いている。そもそも公的に“銀行”と呼べるような施設が少ないこの時代、大金や宝飾品を預かる倉庫はほとんどが半闇のビジネスだ。
馬車を降り、ひっそりとした路地を進むと、そこには黒ずんだ煉瓦造りの建物が並んでいた。一見ただの倉庫街に見えるが、奥には一定の警備が敷かれ、許可のない者は近づくことすらできない。
アスカは屋敷で用意した「先代公爵の印章」が付いた古い書簡を握りしめ、警備兵に差し出す。この書簡こそが、唯一の“先代公爵の痕跡”として残っていたものだ。もしも本当に貸金庫を利用していたなら、この書簡にある暗号らしき文字列が鍵になる可能性が高い。
「……公爵家の印章? しかも随分と古いもののようだが、これは……。」
「先代の時代に作成された書簡です。もしここに預けられているものがあるなら、私が引き取りたい。公爵夫人として正式に申し出ます。」
半信半疑の警備兵たちは、やがて奥へと通すように指示を受け、アスカは倉庫の管理人と対峙することになった。
管理人は短く刈った髪と鋭い目つきを持つ中年男。彼もまたいかにも“裏の世界”で名を馳せていそうな雰囲気だが、アスカは怯まずに書簡を示し、先代公爵がどのような契約を交わしていたかを問う。
「……ああ、この印章は確かに昔、預かっていた口座名義のものに似ている。だが、ずいぶん前に失効したと聞いていたがね。まさか今になって、相続人が来るとは思わなかった。」
「相続……そうですね。先代公爵は既に亡くなっていますが、その息子である現公爵が存命です。私も正式な夫人です。正当な相続権があるはずです。」
管理人は細めた目をさらに眇め、書簡に書かれた暗号を判読し始める。暗号自体は古い数字や文字の羅列で、専門家でなければ解読が難しい。
息を殺して待つアスカ。数分後、管理人は低く唸ると、部下を呼び寄せて一言、短く告げる。
「倉庫の奥にある金庫番号……××番を確認しろ。だが、中身があるかどうかは知らんぞ。大昔に契約したまま放置されたと聞いていたからな。」
アスカは胸の奥で小さく期待と緊張が混ざり合うのを感じる。もし本当に残されていれば、ある程度の宝飾品や金貨が見つかるかもしれない。
---
開かれた金庫、その中身
薄暗い倉庫の通路を進み、頑丈そうな鉄扉の並ぶ区画へ。管理人の部下が鍵束を取り出し、一つ一つ照らし合わせながら「××番」の金庫を探す。
やがて扉が開けられると、中には埃をかぶった木箱が見えた。いくつも重ねられた小箱に、先代公爵の名を示す紋章がかすかに残っている。
アスカはランプの明かりをかざし、息を呑むようにして木箱を開けた。中から現れたのは――確かに宝飾品らしきものや金貨の袋。しかし、その量はアスカが想像していた“大逆転”を生むには少々心許ない。
(思ったより……多くはないわね。でも、何もないよりはずっといい。)
金貨の袋を手にし、ざっと重さを確認すると、確かにかなりの枚数が詰まっている。だが、先代公爵が抱えていた莫大な負債に比べれば、ここにある資金はわずかなものでしかない。
それでも、アーヴィング商会との交渉を進めるにあたって“当面の返済金”としては十分な価値があるかもしれない。あるいは、これを担保に新しい融資先を探す道も考えられる。
「(……助かった。本当に何もなかったら終わっていた。多少なりとも、時間と余裕を買えるかもしれない。)」
アスカは心中で安堵の息をつきつつ、さらに木箱の底を探る。すると、風化しかかった書類の束が出てきた。墨が薄れて一部しか読めないが、どうやら「先代公爵が海外商人と交わした輸入取引の権利書」のようだ。
これも時代遅れかもしれないが、もしまだ有効なら、アーヴィング商会と対等の立場で交渉できる材料になる可能性がある。少なくとも、商会が独占している海上貿易ルート以外の選択肢を探る糸口になるかもしれない。
(よし……これを持ち帰って、イーヴァンやカルデール伯にも相談してみよう。)
アスカは手早く箱の中身を整理し、管理人に最小限の保管料を支払い、契約者の“継承者”として中身を引き出す手続きを済ませた。多少の追加費用はかかったが、拒んでいる余裕はない。
---
帰路と不安
貸金庫を後にしたアスカは、いつもより重い手荷物を抱え、馬車に揺られながら王都の中心へ戻る。窓の外には午前の日差しが広がり、街の人々が活気よく行き交っている。しかし、彼女の心は決して晴れやかとはいかない。
先代公爵の隠し財産は予想よりも少なく、これだけで公爵家を救えるとはとても思えない。だが、まったくの無一文よりは数倍マシだ。アスカはこの金貨と古い権利書をどう使うか、必死に頭を巡らせる。
――そうするうちに、馬車の小窓から見える景色が少しずつ変化し、やがて公爵家の屋敷が遠目に見えてきた。屋敷の門前には数台の馬車が止まり、複数の人影が動き回っているようだ。どうやらアーヴィング商会が再び差し押さえの準備に来ているのかもしれない。
「……急いで!」
アスカは御者に声をかけ、馬車を早く門内に通してもらうよう依頼する。すると、門番が心配そうに駆け寄ってきた。
「公爵夫人、ちょうどよかった……! アーヴィング商会の面々が今日の正午に合わせて強制執行の手続きを進めようとしていまして……!」
「わかりました。私が対応します。すぐに応接室へ通してください。」
こうしてアスカは、結局のところ一睡もしていない状態で、再び“戦場”へ向かうこととなる。
---
最後の審判:応接室の激突
応接室の空気は張り詰めていた。アーヴィング商会の手代を中心に、十数名ほどの男たちが机を囲み、そこにセシリアも同席している。さらに、カルデール伯や執事のオーランド、会計係のイーヴァンも応対しているが、どうにも不利な状況にあるようだ。
そこへアスカが入ってきた瞬間、セシリアが待ちかねたように薄く笑みを浮かべる。
「まあ、ギリギリの到着ね、公爵夫人。もう少し遅ければ、あなた抜きで手続きを進めるところだったわ。」
「ご心配なく。こちらも用意があるの。」
アスカはケープの下から隠し財産の一部――金貨の入った袋と、先代公爵の権利書の束――を取り出し、テーブルの上へ置く。その瞬間、部屋の空気がわずかに変わった。
「これは……?」
「先代公爵がかつて契約していた海外商人との取引権、それからある程度の金貨です。すべて公爵家の正当な相続資産にあたると考えられます。これを“当面の返済金”として充てる形で、猶予をいただけませんか?」
アスカが静かにそう告げると、アーヴィング商会の男たちは顔を見合わせ、セシリアは目を細めて警戒を強める。
金貨の量は思っていたより多い。だが、すべてを加算しても、今日までの利息と元本全額に届くわけではない。すぐに完済が可能というほどの額ではないが、逆に言えば“一部返済を示せる”のは大きな前進だ。
「なるほど、公爵家がまだ隠し財産を持っていたとは驚きだ。だが、これで全額に及ぶわけではない。利子の再計算を踏まえれば、まだまだ足りないだろう?」
「承知しています。ですが、今ここで“強制執行”するよりも、返済計画を協議したほうがアーヴィング商会にとっても得策ではありませんか? さらに、この取引権を活かせば海外の商人から新たな支援を受けることが可能になるかもしれません。」
アスカの言葉に、男たちはざわつく。セシリアも不快そうに唇を曲げる。
実際、海外の取引権はアーヴィング商会が長らく独占してきた海路とは別のルートに関わるものらしい。これが本当に有効ならば、彼らが独占体制を維持してきた“海上貿易の利益”に対抗する手段となり得るのだ。
(ここが勝負どころ……!)
アスカは一息つき、さらに続ける。
「もし公爵家の権利で海外から融資を取り付けることができれば、アーヴィング商会への返済金は今よりも増えるはず。あなたたちとしても、今すぐ差し押さえであちこちの財産をバラ売りするより、よほど大きな利益が得られる可能性が高いでしょう? ――もちろん、そのためには少し猶予が必要ですわ。」
「……ふん。」
男たちの中でも特にリーダー格の者が、計算高そうに目を伏せ、頭の中で損得をシミュレートしているのがわかる。実際、貸し手としても、いきなり強制執行して公爵家を丸裸にしてしまうと、その後の継続的利益は見込めない。一方、一定の条件で再建を支援すれば、さらに利息が膨らむ可能性もある。
アスカは、そのわずかな利害の隙間をつくことで、“全面的な破綻”だけは回避したいと考えていた。
---
セシリアの猛反発
しかし、そんなアスカの策を阻むように、セシリアが机を叩いて声を上げる。
「ちょっと待って。そんな取引書類、いつの時代のものかもわからないじゃない。ましてや、そのルートが今も機能している保証もないわ。こんな怪しいものを担保にして、商会の判断を曖昧にさせるなんて、お門違いでしょう?」
「怪しいかどうかは、これから正式に確認すればいいのでは? セシリア様、あなたはアーヴィング商会にとって有益な取引しかしないと仰っていたわね。こちらの提案も、十分有益だと思いますが。」
アスカは一歩も退かない。昨夜、セシリアに「新融資契約」への署名を迫られたときとは違う。今はわずかとはいえ、先代の隠し資金と取引権という武器を手にしている。
セシリアは苛立ちを隠さず、商会の男たちに目を向ける。
「今こそ公爵家を抑えてしまえばいいのに。こんな時代遅れの書類に期待して、またズルズルと期限を延ばすなんて愚の骨頂よ。――いいの? もし海外の取引なんて一銭の価値も生まなかったら、商会だって完全に損をするわよ?」
「そのリスクも含めて、我々が判断する。セシリア様が口を挟むことではない。」
リーダー格の男が冷ややかにセシリアを制した。どうやら商会内部でも、“このまま公爵家を叩き潰す”派閥と、“ある程度再建させて利息を搾り取りたい”派閥が存在するらしい。セシリアは明らかに前者を推しているが、すべてを思いどおりにできるわけではない。
アスカは胸の奥でほっと息をつきつつ、しかし視線をゆるめない。セシリアは再び机を叩き、今度はアスカに向き直る。
「でも、あなただけではどうしようもないはずよ。肝心のレイヴン公爵はいつ戻ってくるの? 公爵が同意しない限り、勝手な交渉は無効になるんじゃなくて?」
「……レイヴン様は、必ず近いうちに戻ります。私が代理で進めた話は、あとで追認してもらうことも可能です。公爵夫人としての権限を行使しているだけ。」
セシリアは鼻で笑い、椅子から立ち上がる。
「結局、あなたは何もわかっていないのよ。レイヴンがいつ帰ってくるのか、本当に帰ってくるのか。……あの人はもう、ここには戻らないかもしれないわね。」
意味深な言葉。その背後にどんな事実が隠れているのか、アスカにはわからない。もしセシリアがレイヴンの動向を掴んでいるなら、それは大きな問題だ。だが、今ここで問い詰めても、不利になるだけ。アスカは冷静を装い、口をつぐんだ。
---
“猶予”を得る、しかし――
最終的な話し合いの結果、アーヴィング商会のリーダー格は「公爵家が提示する金貨と取引権を一旦受け入れ、一定期間だけ返済を猶予する」方針を示した。
この“一定期間”はごく短いもので、猶予というより「猶予兼、追加の保証締結期限」といった性質のものだ。しかし、今の公爵家としてはこれ以上を望めないのが現実。アスカは苦渋の思いでその条件を了承する。
決定的だったのは、あくまで商会の利害だ。即座に強制執行しても得られる利益は限定的だが、返済計画を立てつつ利子を積み重ねれば、更に大きな収益が見込める。そちらを選んだ形だ。セシリアは露骨に嫌そうな顔をしたが、商会内部の多数意見に押し切られたようだ。
(ほんの少しだけど、時間を稼げた。――この間に、私がもっと強力な手段を掴めば、公爵家の崩壊を防げるかもしれない……。)
アスカはそう自分に言い聞かせる。
商会の使者たちが書類の取り交わしを終え、帰り支度を整える中、セシリアも彼らに連れ立って部屋を出ていく。視線が合ったとき、冷たい瞳が突き刺さるように感じた。
「……やるじゃない、公爵夫人。けれど、あなたが必死にもがいても、最終的に勝者となるのは私よ。」
小声でそう囁き、セシリアは優雅な足取りで去っていった。
---
帰還の報せ:レイヴンの影
日が暮れる直前、ようやく屋敷に一つの知らせが届く。――レイヴン公爵の一行が王都の外れまで戻りつつあり、夜には屋敷に到着するという報せだ。
これまで長期不在のままだった主が、ようやく帰還する。使用人たちには安堵の空気が広がったが、同時にピリついた緊張も走る。あれほど逼迫した状況を主人不在で乗り越えることを強いられたのだから、誰もが“レイヴンの帰宅後にどうなるか”を想像してしまうのだ。
アスカもまた、朝から走り回り、今は疲労困憊の状態にある。それでもレイヴンの帰還を知ると、眠気が吹き飛ぶように意識が冴えた。やっと話せる。彼が何を考えていたのか、自分がこの苦境をどうやってつないできたのか、すべてをぶつけるべきときが来たのだ。
(もし彼が、セシリアと通じて家を捨てるつもりなら……私は本当にどうすればいいのだろう。でも、諦めるわけにはいかないわ。)
気持ちを整理しようと自室で一息ついていると、侍女のリディアが慌てて駆け込んできた。
「アスカ様、レイヴン公爵様のお迎えの準備を……と執事から連絡がありましたが、いかがなさいますか?」
「ええ。今は“完璧な夫人”を演じている余裕もないけれど、最低限の礼儀は尽くします。彼が戻り次第、私も会いたいと思っているの。」
アスカは深く息を吸い込み、鏡を覗いて服装を整える。先代公爵の隠し財産や権利書の存在、商会との危うい猶予契約、セシリアの動向――伝えるべきことは山のようにある。だが、レイヴンがそれをどう受け止めるのか、全く予想がつかない。
再会と衝突
夜が更ける頃、屋敷の門から馬車が入ってきた。レイヴン公爵の帰還だ。使用人たちが出迎えに出る中、アスカは廊下で待ち構えていた。
扉が開き、久方ぶりに見るレイヴンの姿は、どこかやつれたような気配をまとっている。それでも引き締まった面差しは変わらず、冷たく整った瞳がアスカに向けられた瞬間、胸がざわつく。
「……戻ったぞ。」
「お帰りなさいませ、レイヴン様。――長く留守にされていましたが、この間にアーヴィング商会が差し押さえを……危機一髪でした。セシリア様はさらに契約を迫ってきて……。私が対処しなくてはならない事態になっていたんです。」
矢継ぎ早に言葉を重ねるアスカに、レイヴンは小さく眉を寄せる。
「商会の動きは、おおよそ想像していた。……だが、お前がどこまで口出ししたのか。余計なことをされては困る。」
「余計? あのままだったら、今日にも屋敷が取り潰されていたかもしれないのに……あなたはどうするつもりだったの!?」
思わず声を張り上げるアスカ。今まで溜め込んできた不安や苛立ちが一気に噴出してしまう。
レイヴンは静かに廊下を歩き出し、彼女を遠ざけるように言う。
「セシリアから何か聞いたかもしれないが、俺の考えは変わらない。――家を守るためには、あの商会やセシリアを利用するしかないんだ。彼女がどんな思惑を持っていようと、今はそれを飲むしかない局面だった。……お前が勝手に動くほど、事態はさらに複雑になる。」
「勝手に動く? 私が何もせずに従っていれば、それこそ公爵家は彼女や商会の手に落ちるだけではないですか! 私は“夫人”として、少しでも家を守ろうと――」
「……俺が求めたのは、事を荒立てず黙っていてくれることだ。」
その冷酷な物言いに、アスカの胸は鋭く刺される。彼は最初からアスカを信用しておらず、“ただの飾り”として扱っていたとでも言わんばかりの態度だ。
しかし、アスカはもう引き下がらない。怒りを噛み締めながら、彼の前へ一歩踏み出す。
「あなたが私を信用しないなら、それでもいいわ。でも、私はもう黙っていても救われないことを知ったの。――先代公爵が交わした闇契約を背負って、どれだけ無理をしてきたのかは多少想像できる。でも、それであなたまで自滅するなら、私やこの屋敷の人たちはどうなるの? セシリアの提案を受け入れて、あなたは本当に守りたいものを守れるの?」
「……。」
レイヴンは答えず、険しい表情のまま沈黙する。もしかすると、彼もまた迷っているのかもしれない。アーヴィング商会との“契約上の逃れられない縛り”と、“セシリアが握る利益”――それに追い詰められているのは彼自身だろう。
そうした中、彼はふっと目を伏せ、言いにくそうに口を開いた。
「俺は……この家を潰したくない。先代公爵が積み上げた債務も、いつか俺自身が完済するつもりだった。だが、想定より早く商会が動き出し、セシリアも俺の計画を横取りする形で暗躍し始めた。……本来なら、その交渉をまとめるための出張だったが、思わぬ妨害が入り、遅くなった。」
「妨害……? 誰かがあなたの動きを阻んでいるってこと?」
「ああ、詳しいことはまだ話せない。だが、お前がここで奮闘していたのはわかったよ。――正直、驚いた。お前がこれほどしぶといとは思わなかった。」
レイヴンの言葉に、アスカは胸の痛みと同時に、かすかな安堵を覚える。せめて彼が自分の努力を認めてくれたのなら、救いがあるかもしれない。だが、問題は山積みだ。セシリアの契約、アーヴィング商会の猶予期限、そして先代公爵の闇契約――それらをどうまとめ上げるのか。
---
真実の全貌、揺れるセシリア
翌日、レイヴン公爵が帰還したという報を聞きつけてか、セシリアが早朝から屋敷を訪れた。彼女は豪奢なドレスを身に纏い、眷属の使用人たちを引き連れて、まるで勝ち誇ったような雰囲気を漂わせている。
アスカが応接室に通されたとき、そこにはレイヴンとセシリアが向かい合っていた。レイヴンは相変わらず冷静な面持ちだが、その背筋にはどこか緊張が走っている。セシリアは艶やかな笑みを浮かべ、テーブルの上に新たな契約書を広げた。
「ようやく帰ってきたのね、レイヴン。これが“私たち”が用意した新しい融資契約よ。あなたがサインしてくれれば、一切の問題が解決するわ。アーヴィング商会の総意で、特別な優遇措置も設けているの。」
「……どういう内容だ?」
「要は、これまでの債務を“まとめて再契約”という形にし、さらに追加の融資を施す。その代わり、利息は今までより少しだけ上がるわ。でも安心して。支払期間は延長されるし、今の資金繰りが回らない状況は一気に解消できるでしょう?」
言葉だけ聞けば悪くない話だが、もちろん裏があるのは明白だ。この契約を締結すれば、公爵家は実質的に商会の管理下に入り、下手をするとセシリアが“代理人”として全権を握る可能性すらある。
レイヴンは契約書を軽く捲り、ページの端で指を止める。そこには「もし期限内に返済が滞った場合、セシリア・○○が公爵家の運営管理を代行する」といった条項が小さく記されていた。
「……やはりな。これは事実上、公爵家の主導権をセシリアに移譲するようなものじゃないか。」
「細かい話はいいの。あなたが本当に家を守りたいなら、これにサインするだけで済むわ。アスカ公爵夫人のように必死にもがかなくても、一瞬で解決できる話よ。」
セシリアは薄く笑う。その瞳にはアスカへの挑発が宿っているようだが、同時にレイヴンへの執着もちらついている。
レイヴンは深く息を吐き、即答せずにアスカへちらりと視線を寄越す。アスカもまた、胸を刺すような緊張を抱えつつ、言葉を捜す。
「レイヴン様、待って。もしこれにサインすれば、本当に公爵家は取り戻せないところまで追い詰められるわ。あなたが背負ってきた苦労が、すべてセシリアの掌の上に乗るだけになってしまう。――私が持ち帰った先代の資金と取引権だって、まだ使い道があるはずよ。」
「そう。あの怪しいお宝と時代遅れの権利書ね?」
セシリアが嫌味たっぷりに口を挟む。
「レイヴン、あなたならわかるでしょう? 先代の書類なんて、今では法的拘束力が微妙だし、隠し財産だってそこまで大きい額じゃないのよ。そんな当てにならないものにすがるより、私の提示する契約で一気に解決するほうが賢明だわ。……それとも、あなたも“白い結婚”の妻に感化されて、甘い夢を見てるのかしら?」
鼻で笑うセシリア。しかし、その言葉を聞いた瞬間、レイヴンの瞳が鋭く光る。
「……お前は俺をどこまで見くびっている。先代が残した書類がどれほどの価値を持つか、俺は調べがついている。少なくとも、お前の契約書に飛びつくよりは、再建への可能性が高い。」
セシリアの表情が険しくなる。アスカは驚きを隠せない。レイヴンがこの件について把握しているなら、どうして今まで黙っていたのか。
すると彼は続ける。
「お前がここまで強引に事を進めるとは予想外だった。だが、今回の“不在”で、俺も確証を得た。――セシリア、お前は商会とつるんで公爵家だけでなく、俺自身をも排除しようとしているな。」
「何を馬鹿な……私はあなたを支援してきたでしょう? 海外の投資先だってあなたに情報を流して……!」
「それは表向きの話だ。裏ではアーヴィング商会の幹部と取引し、俺の管理外で資金を操作していた。俺が出張先で妨害に遭ったのも、お前から情報が流れていたからだろう?」
視界の端で、アスカは息を呑む。もしこれが真実なら、セシリアはレイヴンを助けているふりをしながら、あらゆる手を使って彼を“財政的に破綻させる”算段を進めていたことになる。
レイヴンは机に広げられた契約書をバサリと放り投げ、硬い声で告げる。
「その書類にサインする気はない。お前が商会を操って仕掛けてきても、俺は先代の書類と海外ルートで、別の道を開くつもりだ。――アスカが見つけ出した金貨や契約は一時しのぎかもしれないが、今は十分な時間を稼ぐ材料になる。」
セシリアは苦々しげに唇を噛み、アスカを睨みつける。
「……なるほど。あなたたち、“夫婦”で結託したわけね。まさか本当に成功すると思ってるの? アーヴィング商会も私も、そんな甘い誘いには乗らないわよ。」
「好きにしろ。俺たちの方も“白い結婚”なんて形式は、もうどうでもいいと思っている。だが、家を潰すわけにはいかない。」
レイヴンの口から自然に出てきた“俺たち”という言葉が、アスカの胸を強く打った。確かに今まで彼は冷淡で、アスカを“ただの飾り”としか扱ってこなかった。けれど、ここにきて二人は皮肉にも共闘する形になり、“夫婦”として初めて同じ方向を向き始めたのだ。
---
アスカの反撃、セシリアの破局
セシリアは苛立ちを露わにするが、ここで強行策を取っても部が悪いと判断したのか、契約書を回収して椅子から立つ。
その場に居合わせた商会の人間も、レイヴンの意思を知り、すぐには動きづらい。彼らとしては、もしレイヴン側が本当に海外ルートを確保し、先代の資金を追加拠出するなら、現状の融資プランでも十分利益が出る可能性があるからだ。セシリア個人の企みにわざわざ加担して混乱を招くリスクは取りたくないというわけだ。
こうして、セシリアは舌打ちを押し殺しながら退出し、公爵家内に広がる彼女の“私的な勢力”も徐々に撤退の動きを見せ始める。いずれ新たな策を講じてくるかもしれないが、現時点では大っぴらにレイヴンを攻撃できなくなった。
「ざまあ……とはまだ言えないけど、少なくともセシリアが好き勝手する状況からは一歩脱出できたわ。」
アスカは部屋を出ていくセシリアの背中を見送る。心の中では、完全勝利までは遠いものの、痛快な達成感がじわりと広がっていた。
セシリアは最後にアスカを振り返り、悔しそうな表情を浮かべて低く囁く。
「あなた、覚えていなさい。このまま終わると思ったら大間違いよ。公爵家とリュミエール家の破滅に巻き込まれても知らないんだから……。」
「勝手にどうぞ。少なくとも私は、あなたの“操り人形”になるつもりはない。自分の意志で、この家と未来を守ってみせるわ。」
その瞬間、二人の視線が鋭く交錯する。互いの勝敗はまだ決していない。それでも、今はアスカが一歩リードした形だ
---
エピローグ:白い結婚の終幕、そして――
セシリアが屋敷を去った後、レイヴンはアスカと二人きりになるために執務室へ足を運んだ。静まり返った室内には、まだ書類や帳簿が散乱したままだ。
先代から続く闇契約、セシリアの策略、アーヴィング商会の圧力――あまりにも多くの問題が残っている。それでも、そのどれもが“絶対に回避不可能”とは言い切れない段階まで来たのだ。
アスカは椅子に腰を下ろし、深い息を吐く。
「……本当なら、一度じっくり話したいことが山ほどあります。どうして私を信用してくれなかったのか、どうして勝手に行動されるのか、聞きたいことがいっぱい……。でも、今はそんな時間も惜しいわね。」
「済まない。お前にだけは、こんな重荷を背負わせたくなかった。……“白い結婚”とは名ばかりで、お前を家の道具にしている自覚はあった。だが俺も、そこまで余裕がなかったんだ。」
レイヴンの声に、ほんの僅かな苦悩が滲む。アスカはその表情を見つめ、複雑な感情に囚われる。彼が自分の心情を素直に口にするのは初めてに近い。
しばし沈黙が降りたのち、アスカは静かに言い放つ。
「これからは、私も“表のパートナー”として認めてほしい。セシリアみたいな影の女ではなく、正妻として、公爵家を立て直すために力を合わせましょう。今さら愛だの幸せだのと偽善を語るつもりはないけど、せめて手を取り合う関係にはなれるはずよ。……そうでなければ、もう私はこの結婚を続ける理由がありません。」
「……ああ。わかった。お前がそこまで言うなら、俺も隠し立てはやめよう。」
レイヴンはそう呟き、アスカの手を取る。冷たい指先が、どこか震えているようにも感じる。
皮肉にも“愛のない白い結婚”から始まった二人の関係は、今ようやく真の意味で並び立つ一歩を踏み出そうとしている。もちろん、和解や信頼に至るには多くの困難があるだろう。アーヴィング商会の脅威は消えていないし、セシリアが何か仕掛けてくる可能性も大いにある。
それでも、アスカは自分がここまで辿り着いたことに小さな誇りを感じていた。誰にも操られず、自分の頭で考えて自分の手で行動した結果が、こうして僅かながら道を開いているのだ。
(いつか、本当の意味で“ざまあ”と笑える日が来るのかもしれない。セシリアにも、アーヴィング商会にも、そして私を道具としてしか見なかったあの家族にも。)
思えば、リュミエール家の父や母も、アスカを完全に利用する形で公爵家へ送り込んだ。当初は反発もできなかったが、今の彼女は違う。
白い結婚という名の冷たい檻の中で、アスカは自ら立ち上がり、手探りながらも闇を照らす一筋の光を見出した。その光をさらに大きくするために――そして、もし望むならば、自らの幸せを勝ち取るために――彼女はこれからも戦い続けるだろう。
レイヴンが静かに口を開き、“すべてを話す”と告げる。先代公爵の死の真相、海外での取引や政治的な駆け引き、セシリアとの因縁――それらを明らかにすることで、二人は新たな一歩を踏み出す。
愛し合う夫婦とは程遠いかもしれない。だが、少なくとも互いを“力を合わせる相棒”として認め始めたこの瞬間、アスカははっきりと感じていた。――私はもう、誰の操り人形でもない。自分の意志で未来を選び、行動できる存在になれたのだ、と。
---
エンディングの気配――しかし物語は続く
こうして公爵家の“白い結婚”は、ある意味でその終幕を迎えた。アスカとレイヴンは形式的な夫婦から、一つの“同盟”へと関係を変え、セシリアをはじめとする数々の思惑に立ち向かう構えを見せる。
もちろん、すべてが解決したわけではない。アーヴィング商会との交渉は綱渡りのままだし、先代公爵の闇契約にはまだ未知の部分が多い。セシリアは一度退いたにすぎず、いつ再び牙を剥くかわからない。
だが、アスカに絶望はなかった。自分の手で切り開いてきた道の先に、かすかな光が見えている。もし最後まであきらめずに進めば、いずれは周囲を“ざまあ”と言わしめる逆転劇が待っているかもしれない。
誰かに与えられた幸せを待つのではなく、自分の足で未来を奪い取る。それが、彼女がこの“冷たい結婚”の檻の中で見つけ出した答えだった。
夜の静寂を破るように、レイヴンがアスカの名を呼ぶ。二人きりの執務室で向かい合い、ようやく互いの言葉を交わす準備が整った。
白い月光が窓から差し込み、まるで二人の結びつきを照らすように淡く輝いている。アスカは最後にもう一度、拳を握りしめて決意する。――これからも困難は尽きないけれど、私はもう一人ではない。少なくとも“公爵夫人アスカ”として、堂々と生き抜いてみせる。
こうして物語は、ひとまずの転機を迎えた。冷たい白い結婚は、“二人の同盟”を経て新たな段階に入り、セシリアやアーヴィング商会との戦いも、これから本格化していくに違いない。
だが、アスカはもう振り返らない。どんな障害があろうとも、彼女は決して折れはしない。やがて訪れる“大逆転”の日を夢見て――彼女は、深夜の窓辺からうっすらと光る星を見上げ、微かに微笑んだ。
13
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説

冷酷侯爵と政略結婚したら、実家がざまぁされました
鍛高譚
恋愛
「この結婚は、家のため。ただの政略結婚よ」
そう言い聞かせ、愛のない結婚を受け入れた公爵令嬢リゼット。
しかし、挙式後すぐに父が「婚約破棄しろ」と命じてきた!?
だが、夫であるアレクシス・フォン・シュヴァルツ侯爵は冷たく言い放つ。
「彼女を渡すつもりはない」
冷酷無慈悲と噂される侯爵が、なぜかリゼットを溺愛し始める!?
毎日甘やかされ、守られ、気づけば逃げ場なし!
さらに、父の不正が明るみに出て、公爵家は失墜――
リゼットを道具として利用しようとした者たちに、ざまぁの鉄槌が下される!
政略結婚から始まる、甘々溺愛ラブストーリー!
「愛なんてないはずなのに……どうしてこんなに大切にされるの?」
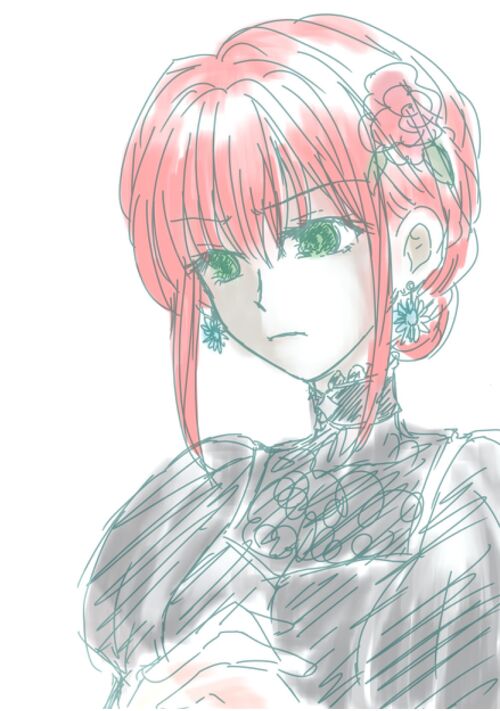
捨てられた悪役はきっと幸せになる
ariya
恋愛
ヴィヴィア・ゴーヴァン公爵夫人は少女小説に登場する悪役だった。
強欲で傲慢で嫌われ者、夫に捨てられて惨めな最期を迎えた悪役。
その悪役に転生していたことに気づいたヴィヴィアは、夫がヒロインと結ばれたら潔く退場することを考えていた。
それまでお世話になった為、貴族夫人としての仕事の一部だけでもがんばろう。
「ヴィヴィア、あなたを愛してます」
ヒロインに惹かれつつあるはずの夫・クリスは愛をヴィヴィアに捧げると言ってきて。
そもそもクリスがヴィヴィアを娶ったのは、王位継承を狙っている疑惑から逃れる為の契約結婚だったはずでは?
愛などなかったと思っていた夫婦生活に変化が訪れる。
※この作品は、人によっては元鞘話にみえて地雷の方がいるかもしれません。また、ヒーローがヤンデレ寄りですので苦手な方はご注意ください。

「君を愛することはない」と言われたので、私も愛しません。次いきます。 〜婚約破棄はご褒美です!
放浪人
恋愛
【「愛さない」と言ったのはあなたです。私はもっとハイスペックな次(夫)と幸せになりますので、どうぞお構いなく!】
侯爵令嬢リディアは、建国記念舞踏会の最中に、婚約者である王太子レオンハルトから婚約破棄を宣言される。 「君を愛することはない!」という王太子の言葉は、国中に響く『公的拒絶誓約』となってしまった。
しかし、リディアは泣かなかった。 「承知しました。私も愛しません。次いきます」 彼女は即座に撤退し、その場で慰謝料請求と名誉回復の手続きを開始する。その潔さと有能さに目をつけたのは、国の行政を牛耳る『氷の宰相』アシュ・ヴァレンシュタインだった。
「私の政治的盾になれ。条件は『恋愛感情の禁止』と『嘘がつけない契約』だ」
利害の一致した二人は、愛のない契約結婚を結ぶ。 はずだったのだが――『嘘がつけない契約』のせいで、冷徹なはずの宰相の本音が暴走! 「君を失うのは非合理だ(=大好きだ)」「君は私の光だ(=愛してる)」 隠せない溺愛と、最強の夫婦による論理的で容赦のない『ざまぁ』。
一方、リディアを捨てた王太子は「愛さない誓約」の呪いに苦しみ、自滅していく。 これは、悪役令嬢と呼ばれた女が、嘘のない真実の愛を手に入れ、国中を巻き込んで幸せになるまでの物語。

婚約破棄?結構ですわ。公爵令嬢は今日も優雅に生きております
鍛高譚
恋愛
婚約破棄された直後、階段から転げ落ちて前世の記憶が蘇った公爵令嬢レイラ・フォン・アーデルハイド。
彼女の前世は、ブラック企業で心身をすり減らして働いていたOLだった。――けれど、今は違う!
「復讐? 見返す? そんな面倒くさいこと、やってられませんわ」
「婚約破棄? そんなの大したことじゃありません。むしろ、自由になって最高ですわ!」
貴族の婚姻は家同士の結びつき――つまりビジネス。恋愛感情など二の次なのだから、破談になったところで何のダメージもなし。
それよりも、レイラにはやりたいことがたくさんある。ぶどう園の品種改良、ワインの販路拡大、新商品の開発、そして優雅なティータイム!
そう、彼女はただ「貴族令嬢としての特権をフル活用して、人生を楽しむ」ことを決めたのだ。
ところが、彼女の自由気ままな行動が、なぜか周囲をざわつかせていく。
婚約破棄した王太子はなぜか複雑な顔をし、貴族たちは彼女の事業に注目し始める。
そして、彼女が手がけた最高級ワインはプレミア化し、ついには王室から直々に取引の申し出が……!?
「はぁ……復讐しないのに、勝手に“ざまぁ”になってしまいましたわ」
復讐も愛憎劇も不要!
ただひたすらに自分の幸せを追求するだけの公爵令嬢が、気づけば最強の貴族になっていた!?
優雅で自由気ままな貴族ライフ、ここに開幕!

天然だと思ったギルド仲間が、実は策士で独占欲強めでした
星乃和花
恋愛
⭐︎完結済ー本編8話+後日談7話⭐︎
ギルドで働くおっとり回復役リィナは、
自分と似た雰囲気の“天然仲間”カイと出会い、ほっとする。
……が、彼は実は 天然を演じる策士だった!?
「転ばないで」
「可愛いって言うのは僕の役目」
「固定回復役だから。僕の」
優しいのに過保護。
仲間のはずなのに距離が近い。
しかも噂はいつの間にか——「軍師(彼)が恋してる説」に。
鈍感で頑張り屋なリィナと、
策を捨てるほど恋に負けていくカイの、
コメディ強めの甘々ギルド恋愛、開幕!
「遅いままでいい――置いていかないから。」

ぽっちゃり侯爵と大食い令嬢の甘い婚約生活
piyo
恋愛
女性秘書官として働きながら、“大食い令嬢”の異名を持つダニエラ。そんな彼女に、上司のガリウスがひとつの縁談を持ってくる。
相手は名門オウネル侯爵家の当主、キーレン・オウネル。
大変ふくよかな体形の彼は、自分と同じように食を楽しんでくれる相手を探していた。
一方のダニエラも、自分と同じくらいの食欲のある伴侶を求めていたため、お茶会を通じて二人は晴れて婚約者となる。
ゆっくりと距離を縮め、穏やかに愛を育んでいく二人だが、
結婚式の半年前、キーレンが交易交渉のため国外へ赴くことになり――
※なろうにも掲載しています

主人公の恋敵として夫に処刑される王妃として転生した私は夫になる男との結婚を阻止します
白雪の雫
ファンタジー
突然ですが質問です。
あなたは【真実の愛】を信じますか?
そう聞かれたら私は『いいえ!』『No!』と答える。
だって・・・そうでしょ?
ジュリアーノ王太子の(名目上の)父親である若かりし頃の陛下曰く「私と彼女は真実の愛で結ばれている」という何が何だか訳の分からない理屈で、婚約者だった大臣の姫ではなく平民の女を妃にしたのよ!?
それだけではない。
何と平民から王妃になった女は庭師と不倫して不義の子を儲け、その不義の子ことジュリアーノは陛下が側室にも成れない身分の低い女が産んだ息子のユーリアを後宮に入れて妃のように扱っているのよーーーっ!!!
私とジュリアーノの結婚は王太子の後見になって欲しいと陛下から土下座をされてまで請われたもの。
それなのに・・・ジュリアーノは私を後宮の片隅に追いやりユーリアと毎晩「アッー!」をしている。
しかも!
ジュリアーノはユーリアと「アッー!」をするにしてもベルフィーネという存在が邪魔という理由だけで、正式な王太子妃である私を車裂きの刑にしやがるのよ!!!
マジかーーーっ!!!
前世は腐女子であるが会社では働く女性向けの商品開発に携わっていた私は【夢色の恋人達】というBLゲームの、悪役と位置づけられている王太子妃のベルフィーネに転生していたのよーーーっ!!!
思い付きで書いたので、ガバガバ設定+矛盾がある+ご都合主義。
世界観、建築物や衣装等は古代ギリシャ・ローマ神話、古代バビロニアをベースにしたファンタジー、ベルフィーネの一人称は『私』と書いて『わたくし』です。

【完結】番としか子供が産まれない世界で
さくらもち
恋愛
番との間にしか子供が産まれない世界に産まれたニーナ。
何故か親から要らない子扱いされる不遇な子供時代に番と言う概念すら知らないまま育った。
そんなニーナが番に出会うまで
4話完結
出会えたところで話は終わってます。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















