3 / 3
3
しおりを挟む目を覚ましたシロは、自分がどこにいるのかわからなかった。
ふかふかで清潔なベッドで寝ていることに、途轍もない違和感を覚えた。シロはいつも物置きとして利用している小さな個室で、膝を抱えた体勢で寝ている。
どうして柔らかな布団に包まれているのだろう。
ぼうっとしているシロの頭を、誰かが撫でた。
びっくりして、シロは一瞬で目を覚ます。
ぱちぱちと瞬きするシロの顔を、優しく覗き込むのはエルノだ。彼はベッドに座り、こちらを見下ろしていた。
シロは自分の置かれた状況を思い出した。
「おはよう、シロ。と言っても、今は夜だけど」
「おは、よう……」
気絶するように眠ってしまったようだ。あれから随分時間が過ぎているのか、窓の外は真っ暗だ。
「ぐっすり眠ってたね」
「ご、ごめん、なさい……」
「気にしなくていいよ。色々あって疲れてたんだね」
エルノの微笑みを見上げながら、思い返してみる。
確かに、色々ありすぎる一日だった。ただぼんやりと過ごしてきた毎日と比べると、肉体的にも精神的にも余りにも負担が大きかった。
人族に殺されかけ、そしてエルノとの再会。シロとしては、「再会」という感じはしないのだが。
エルノはシロの頭を撫でつづけている。愛おしむような手付きで。
慣れなくて、シロはどうしていいのかわからない。
両親だって、シロにはほとんど触れることはなかった。それなのに、彼は躊躇することなく触れてくる。触れることに喜びを感じている。
エルノはシロを気味悪いと思わないのだろうか。狼族に対する憎悪や嫌悪を抱いていないのだろうか。シロを見つめる彼の視線からは、そういった感情は一切感じられない。
まるで大切なもののように扱われることを、嫌だとは思わなかった。嫌ではないが、嬉しくもない。シロが感じるのは、困惑や恐怖だ。
だから、彼の笑顔に微笑み返すことなどできなかった。
シロはゆっくりと上半身を起こした。そこで、自分が服を着ていることに気づく。
滑らかな手触りのシンプルなワンピースを身に付けていた。臀部に穴が開いていて、きちんと尻尾を通してある。濡れていた下肢はさっぱりしていて、下着も穿いていた。
当然、エルノが着せたのだろう。
「あの、ありがとう、服……」
「うん。シロの服も下着もたくさん用意してあるから、好きに着替えてね」
「……うん」
戸惑いを感じながらも、どうにか頷いた。
シロの衣類まで用意していたなんて。彼は本当に、完璧に準備を整えていたのだ。シロを、この家に迎えるために。
その執着は怖いくらいだ。一体なにが彼をここまでさせるのだろう。シロがどれほどのことを彼にしたのだというのだ。
おどおどと視線をさ迷わせるシロに、エルノの穏やかな声がかかる。
「お腹空いたよね。ご飯食べよう」
「え、あ……うん」
頷くと、エルノがシロを抱き上げた。そのまま歩き出す。
「あ、あの、私、自分で歩けるよ……?」
勇気を振り絞って伝えると、エルノはにっこり微笑んだ。
「もちろん、知ってるよ」
「…………」
シロを歩かせたくないのか、抱き上げるのが好きなのか、理由はわからないが彼は下ろす気はないようだ。シロは諦めて運ばれた。
移動した部屋で、椅子の上に下ろされた。一脚のテーブルに、二脚の椅子。どちらも新品のように綺麗だ。
「用意してくるから、少し待っててね」
言い置いて、エルノは離れていく。
シロは居心地の悪い思いをしながらじっとしていた。
盆に食事を乗せたエルノがすぐに戻ってくる。手に持った物をテーブルに置き、彼はまたシロを抱き上げた。
「わっ……」
「よっと……。驚かせてごめんね」
シロは椅子に腰かけたエルノの膝に座らされた。体が密着し、シロは狼狽する。
「あ、あの、エルノ……」
「うん?」
下ろしてほしい。でも、言えなかった。エルノの笑顔に有無を言わせないなにかを感じた。
「シロ?」
「な、なんでもない……」
「じゃあ食べようか」
エルノはスプーンを手に取り、スープを掬った。それを当然のようにシロの口に運ぶ。
「はい、あーん」
「…………」
「大丈夫。冷ましてあるから熱くないよ」
「えっと……」
「あーん。ほら、お口開けて?」
食事も自分でさせてもらえないのか。
色々と言いたいことはある。けれど。
怖いから逆らうことはできない。抵抗したとしても、力でエルノには敵わない。素直に従うしか、シロには道がなかった。
口を開けると、エルノは喜んでシロにスープを飲ませた。
シロにとって、記憶にある限り、はじめてのまともな食事だった。
具だくさんのスープは優しい味付けで、とても美味しかった。ふわふわのパンも、新鮮な野菜で彩られたサラダも、どれも驚くほど美味しい。
今まで主食が木の実だったので、大抵の食べ物は美味しく感じただろうが。
空腹が満たされ、シロはほっと息をつく。
食事を終え、背後のエルノを振り返った。
「ごちそうさま。美味しいご飯、ありがとう」
感謝を伝えると、エルノは嬉しそうに笑みを浮かべる。
「美味しいって言ってもらえてよかった。これから毎日、シロのためにご飯作るからね」
「う、ん……」
なんと答えていいのかわからず、曖昧に頷く。
本当に、これから二人きりの生活がはじまるのだろうか。
あまりにも唐突なことに、現実感が湧かない。
食器を片付けたエルノは、シロを抱え寝室へ移動した。シロを横抱きしたまま、ベッドに座る。
「そこにある本、好きに読んでね」
寝室には本棚があり、それを指してエルノは言う。
シロは気まずげに俯いた。
「ごめんなさい……。私、文字が読めないから……」
「そっか。じゃあ僕が教えるね」
嫌な顔もせず、エルノはシロに頬擦りした。
「嬉しいな。僕がシロに文字を教えてあげられるなんて」
本当に嬉しいことのように彼は言う。
普通は、面倒に思うのではないだろうか。別にシロに文字を教える義理も意味も、彼にはない。
エルノは後ろから抱き締めるようにして、シロに本を読み聞かせる。内容は、子供向けの童話みたいだ。
本の文字を指でなぞりながら、エルノはゆっくりと読んでいく。
彼の声は滑らかで、聞いていて心地いい。だんだんうとうとしてくる。
エルノの優しい声音に導かれるように、シロはいつの間にか眠っていた。
次に目を覚ますと、朝になっていた。
昨晩と同じように、ベッドに座ったエルノがシロを見ている。彼は眠ったのだろうか。まさか一晩中シロの寝顔を見ていたとは思わないが、でもその「まさか」が彼ならばあり得そうだった。
昨日からずっと、ほとんどシロから目を離していないのだ。だから、朝食のあとに彼が仕事に行くと言ったときは少なからず驚いた。
「ごめんね、シロには留守番しててほしいんだ」
「……うん」
「ほんとはシロを一人にしたくないんだけど、シロとの生活をつづけるには仕事をやめるわけにもいかなくて。寂しい思いをさせてごめんね」
別に寂しくはない、という本心は口には出さなかった。
「できるだけ早く帰ってくるからね。いい子で待ってて」
言いながら、エルノは椅子に座るシロを縄で縛る。余りにも自然な動作で椅子にくくりつけられ、シロはぎょっとする。
「ま、待って、なんで縛るの!?」
「危ないからだよ。こうしないと、シロが外に出ちゃうかもしれないでしょ。外は危険だからね。こうして動けないようにしておけば安心だよ」
少しも安心できる要素はない。
シロは焦った。留守番は少しも苦ではないが、拘束された状態でとなれば話は変わってくる。このまま放置されるなんてさすがに耐えられない。
シロは必死に訴えた。
「待ってよ、お願い、ほどいて! 私、ちゃんと留守番できるから!」
「だーめ。なにがあるかわからないからね」
寧ろ、なにかあった場合に動けないほうが余程危険なのではないだろうか。
「これじゃあ、動くこともできないよ! その……トイレにも行けないし……」
「トイレはここでしていいよ。帰ってきてから僕が片付けるから」
「はあ!? そ、そそ、そんなの嫌だよ!!」
とんでもないことを言われ、シロはかぶりを振って拒否した。
ここでエルノを説得できなければ、本当にそうなってしまう。
「お願い、エルノ! 私、おとなしくしてるから! ちゃんとエルノが帰ってくるの待ってるから! 外になんて出ない、どこにも行かない!! お願いだから、これはほどいて!」
「シロ……」
「エルノ、エルノ、お願い、こんなの嫌なの、エルノ……」
「そんなに可愛くお願いされたら、仕方ないね。確かに、衛生的にもよくないし。お昼ご飯も食べられないからね」
涙を浮かべながら懇願すると、漸くエルノが絆されてくれた。
可愛くしたつもりはないがそれで考えを変えてくれるのならば、シロはいくらでも媚びる。
縄をほどきながら、「ただし」とエルノはつづける。
「家の中では自由にしてていいけど、絶対に外に出ちゃだめだよ。もし、万が一誰かが来ても、なにがあっても、ドアを開けないこと」
シロはこくこくと首を上下に振る。
エルノの手が、シロの喉に伸ばされた。シロの細い首を握るように、彼の掌が触れる。
エルノは瞬きもせずにシロを見つめていた。彼の黒い双眸に捕らえられ、身動きがとれなくなる。狂気を孕んだ視線に、言いようのない恐怖を覚えた。
シロはごくりと喉を鳴らす。
「約束だよ、シロ。絶対に家から出ないで」
「…………うん」
「もし僕から離れようとしても、必ず捕まえるから。一度でも約束を破れば、二度と逃げられないように足の腱を切って鎖で繋ぐよ。わかったね?」
彼は本気だった。
逃げれば、彼は必ずシロを捜し出すだろう。そして捕まれば、シロは今度こそ完璧に監禁されることになる。
「シロ? 返事は?」
恐怖で声が出せず、どうにか頷くことで返事をする。
エルノはそれを咎めなかった。満足したように微笑む。
「いい子だね、シロ」
エルノがいなくなり、シロは深い溜め息を吐いた。
慣れない場所で過ごす時間はとても疲れる。
シロは部屋の隅で、膝を抱えて座った。
どうしてこんなことになったのだろう。
ぼんやりとそんなことを考える。
なぜ自分は今ここにいるのか。
疑問しかない。
エルノの狂気じみたシロへの執着が怖い。
シロはなにもしていないのに。
あのとき、自分は間違えたのだろうか。
迷子の子供など、無視すればよかったのだろうか。
人族など関わらず、あの場を離れるべきだったのだろうか。
あのとき彼に出会わなければ、シロは今、ここにはいなかった。
こんなことになるとわかっていたら、関わったりしなかった。
こんなことになるなんて、想像すらしていなかった。
シロにとっては、正直なところ、大した出来事でもなかったのだ。もちろん、それなりに衝撃的ではあった。
けれど、記憶から消去されることはなかったが、かといって思い出すこともなかった。あのとき出会った少年がどうしているかなど、一度も思い浮かべたこともない。
その程度のものだった。
でも、エルノは違った。
ここまで執着するようななにかを、シロに感じたのだ。
出会うべきじゃなかった。
シロと出会わなければ、エルノが同族を殺すこともなかっただろう。少なくとも、あの二人組の男はシロを見つけなければ殺されずに済んだはずだ。シロがうまく逃げきることができれば、ああはならなかった。
今更、悔やんでも遅い。
これから自分はどうすればいいのだろう。
どうするもこうするも、逃げられない以上、ここにいるしかないのだけれど。
逃げられたとしても、帰る場所などない。今頃、シロがいなくなったことを両親は喜んでいるはずだ。シロのせいで、彼らも辛い立場にあったのだから。原因がいなくなってほっとしていることだろう。
そう考えると、とてもじゃないが村に戻ることはできない。
それとも、シロがいなくなったことに気づいていないかもしれない。なにせ顔を合わせないのが普通だったのだから。
まだ気づいてなかったとしても、いずれは気づく。そしてシロが生きて戻れば、さぞがっかりするのだろう。
やはりもう、村には戻れない。
別に村での生活に未練があるわけではない。思い入れもなにもない。
かといって、ここでエルノと二人きりで生活することも、シロは望んでいない。
望んでいない、けれど。
シロが望んでも望まなくても、逃げられないのならどうしようもない。
抱えた膝に顔を埋める。
いつまでこの生活がつづくのだろう。
ぼんやりと考えながら、いつも森でそうしていたように、ただじっと時間が過ぎるのを待った。
それから、特に何事もなく日々が過ぎていった。
エルノは仕事へ行き、シロは家で彼の帰りを待つ。その繰り返しだ。
エルノの仕事の時間はバラバラだが、かといってそれがシロの生活に大きな影響をもたらすわけでもない。多少食事や入浴の時間が変わるだけだ。
彼はやたらとシロの世話を焼きたがる。そして体に触れたがる。
初日と同じように、家にいるときは彼がシロに食事を食べさせる。一緒に入浴し、シロの体は彼が洗う。そして毎晩ではないが、ベッドの上で隅々までシロの体を味わう。
二人きりで暮らしはじめて随分日が経ったが、シロはエルノの寝顔を見たことがない。いつもエルノに見つめられながらシロは眠りにつく。そして目を覚ますと彼は既に起きていて、シロを見つめているのだ。
シロが眠っている間に食事の準備などを済ませているのでずっと傍にいるわけではないようだが、まるで監視されているようで落ち着かなかった。
けれど、それも毎日繰り返されれば慣れてしまった。
そう、慣れるのだ。
エルノは基本的に優しい。シロの意見は無視されることが多いが、シロをぞんざいに扱うわけではない。シロに触れる手はいつも優しい。物騒なことを口にすることがあっても、シロが実際に暴力を振るわれたことは一度もない。
ここに連れて来られたばかりの頃はエルノに殺された二人の死体が頭にちらつくこともあったが、それもなくなった。
だからすっかり、エルノに対する恐怖も薄れていた。
つまり、慣れたのだ。
怖いと感じることがないわけではない。けれど、彼の顔色を窺ってびくびくすることはなかった。
結構簡単に慣れてしまうものなのだと、シロは感心した。
でも、狼族の村にいたときもそうだった。
見つかれば石を投げられ罵声を浴びせられる。痛くて辛くて悲しくて寂しくて、幼い頃は一人で泣いていた。けれどそれが当たり前の毎日がつづけば、そういった感情は徐々に薄れていった。慣れてしまえば、なにも感じなくなった。
だから、今の生活もずっとつづけば慣れるのだ。エルノと過ごす毎日が当たり前になる。
美味しいご飯。清潔で温かい寝床。手触りのいい衣服。
そして、愛情に満ちた優しさ、温もり。愛情と呼ぶには常軌を逸しているけれど。
生まれてはじめて与えられるものばかりで、まだ嬉しいと感じるよりも戸惑いの方が大きい。
でも、いつか、自分に向けられる彼の感情に喜びを感じる日が来るのだろうか。
そんな風に考えて、ふと思う。
今の生活が、この先ずっとつづくのだろうか。
そんな確証はない。
気づいて、シロは愕然とした。
そもそも、どうしてそんな当たり前のことに今まで気づかなかったのか。
エルノがシロに向ける感情が、この先も変わらないとは限らないということに。
シロは彼になにもしていない。シロにはなんの価値もない。与えられるだけで、与えたことなどない。
そんなシロに、エルノが愛想を尽かさないなどと思えるわけがない。
今はまだ、彼はシロに執着している。
でもいつか、シロのことなどいらなくなるかもしれない。
そうなれば、きっとあっさり捨てられるのだ。
このままずっと彼と一緒にいて。彼と過ごす時間に僅かでも幸せを感じるようになって。
そうなってしまったとき、彼に捨てられたら。
それは、死ぬよりも恐ろしいことなのではないか。
シロは急に怖くなった。
ここにいてはいけないと、強く思った。
手遅れになる前に、彼と離れるべきだ。
エルノは仕事に行っている。夕方に帰ってくると言っていた。今はまだ昼前で、だから、逃げられる。逃げなくてはいけない。
エルノから離れようとすれば、また必ず捕まえると彼は言った。
彼の目は本気で、だからシロは怯えた。彼からは逃げられないと思った。
でも、本当にそうだろうか。現実的に考えて、森に隠れてしまえば捜し出すことなど難しいはずだ。ましてや、森の中で動き回れば、いつ狼族と遭遇するかもわからない。そんな状況で人族の彼が行動するには、森の中は危険すぎる。
逃げようと思えば、逃げられるはずだ。
シロは震える足でドアに向かった。
一度も触れたことのない、玄関のドア。
手を伸ばす。カギを捻って開ける。
ドアノブを握り、回した。音を立てて、ドアを開く。
そこには、ここに来たときと変わらない森が広がっていた。
久しぶりに感じる、森の匂い。あんなに慣れ親しんでいたのに、酷く落ち着かない気持ちになる。
恐怖で竦みそうになる足を、ゆっくりと踏み出した。
不安を振り払うようにかぶりを振る。
なにも考えてはいけない。考えたら立ち止まってしまう。エルノの顔を思い出したら動けなくなってしまう。
シロは駆け出した。決して振り返らず、足を止めない。エルノと過ごした家から少しでも遠くを目指し、走りつづけた。
走って走って、やがて体力が尽きた。でも、まだもっと遠くへ行かなくては。時間はある。
シロは歩いて森の中を進んだ。そしていつの間にか、見慣れた場所を歩いていることに気づいた。ここはシロの知っている領域だ。
狼族の村が、この先にある。
シロの足は、そちらに向かった。ゆっくりと一歩ずつ、村に近づく。
行ってはいけないと思うのに、足が止まらない。
近づくにつれ、聞こえてくる同族達の声。
慎重に、見つからないように、シロは進んだ。そして視界に見えてくる、小さな村。
シロは足を止めた。木の陰から、村の様子を眺める。
シロの目が、両親の姿を捕らえた。
楽しそうに笑い合う、二人の姿。なんの憂いもなく、寄り添う姿。
そんな二人の姿を、シロははじめて見た。彼らの笑顔すら、自分は知らなかった。
踵を返し、村を離れる。ふらふらと、それから徐々に駆け足で。宛もなく、ただひたすら走りつづけた。どこへ向かっているのかもわからない。とにかく村から離れたかった。
疲れ果て、よろけて転ぶまでシロは走った。
うつ伏せに倒れ、荒い呼吸を繰り返す。
喉が痛い。足が痛い。胸が痛い。
どうしてショックを受けているのだろう。
わかっていたはずなのに。
両親にとってシロはいらない存在だった。邪魔な存在だった。
憎まれていた。疎まれていた。
わかっていたのに。
幸せそうな彼らを見て。シロのことなど微塵も気にかけていない、まるで最初からいなかったかのように、寧ろ今までよりもずっと仲睦まじく穏やかに過ごす二人を見て。
こんなにも、胸が痛い。
期待していたのだろうか。
少しはシロを思ってくれていると。ほんの少しでも、心配してもらえていると。
そんなわけがないのに。
シロがいなくなって、漸く二人は幸せになれたのだ。シロという存在が、二人を苦しめていたのだから。
わかっていたくせに、シロは怖くて死ねなかった。自分の命が惜しくて、二人を苦しめつづけた。
それなのに、幸せそうな二人の姿を見てショックを受けるなんて。
長い時間、シロはその場から動けなかった。漸く体を起こしたときには、日が落ちかけていた。
立ち上がり、よたよたと歩き出す。目的もなく、ただ足を動かした。
歩き疲れても、構わず森をさ迷いつづけた。
「シロ」
聞こえた声に、足を止める。
半ば放心状態だったシロは、近づく足音にも匂いにも気づかなかった。
振り返ると、エルノがいた。息を切らせながら、シロのもとへ来る。
シロはエルノを見上げた。
彼は微笑む。
「見つけた」
「どうして」
「必ず捕まえるって言ったはずだよ。僕は君を逃がす気はないよ」
「どうして」
「シロが好きだから」
「どうして……私なんか……」
両親にすら愛情を向けられなかったシロを、たった一度、幼い頃に出会っただけの彼が、好きだなんて言うのだ。
「私なんて、なんの価値もないのに……。子供の頃のことだって、私は大したことなんてしてない。エルノに好きになってもらえるようなことなんて、なんにもしてないのに……」
「シロにとっては、そうなのかもしれないね。でも、僕にとってはそうじゃないんだ。僕は確かにシロに助けられたんだよ。シロがどう思おうと、僕はそう思ってる」
「狼族で、気味の悪い白い毛色の私に、助けられたって……?」
「狼族であることは、僕にはどうでもいいよ。君が人でも狼でも、僕は好きになったから。白い耳と尻尾も、気味が悪いなんて思ったことはない。ふわふわの雪みたいで綺麗だとは思うけど」
「……そんなの、おかしいよ」
「うん、僕はおかしいんだ。だから、シロがなんと言おうと、泣いて嫌がったとしても、絶対にシロを逃がさない」
エルノの微笑は、ぞくりとするほど美しかった。
彼の狂気を感じて、シロは恐怖ではなく喜びのような感情を抱いた。
自分の浅ましさに嫌悪する。
それでもシロは、目の前の青年に甘え、縋ってしまう。
「逃がさなくていい……。だから、お願いだから、もし私がいらなくなったら、エルノが私を殺して……」
「僕がシロをいらなくなることなんてないけど、それがシロの望みなら叶えてあげる」
シロの瞳から涙が零れた。
悲しかったわけじゃない。嬉しかったわけでもない。ただ罪悪感に胸が痛んだ。
自分はエルノの気持ちを利用している。好きだと言ってくれた彼の気持ちを。
シロは一人が寂しいだけだ。怖くて自分で死ねないだけだ。
そこにエルノがいたから。シロは彼に委ねようとしている。
卑怯で、最低だ。
泣く資格もないのに、涙が止まらない。
涙に濡れるシロの頬を、エルノが拭う。
彼はまるで全てわかっているような、穏やかな笑顔でシロに言う。
「いいんだよ、シロ。君が傍にいてくれるなら、僕はそれでいいんだ。それだけでいい。他にはなにも望まない」
こんなどうしようもないシロを、笑いながら受け入れてしまう彼は、やはりおかしいのだ。
でも、シロはもう、彼から離れられない。
シロにはもう、彼しかいないから。
彼の狂気に捕らわれ、自分もまた狂っていくのだろうとシロは思った。
それを怖いと感じない時点で、既におかしくなっているのだろう。
エルノの笑顔を見つめながら、シロも同じように微笑んだ。
ドアが開き、エルノが中に入ってくる。
「ただいま、シロ」
「おかえり、エルノ」
ドアの前で待っていたシロは、笑顔で彼を出迎える。
腕を伸ばせば、エルノはすぐに抱き締めてくれた。
すりすりと彼の首筋に顔を埋めると、ふふ、と笑い声が耳を掠めた。
「可愛い、シロ。寂しかった?」
「うん」
素直に頷くと、更にぎゅうっと強く抱き締められた。
「お腹空いた? ご飯にしようか?」
「ご飯よりも、エルノにくっついていたい」
「シロは甘えん坊だね」
言いながら、エルノはシロを抱き上げる。そのまま寝室へ移動した。
シロをベッドに下ろし、エルノは紐で括って首に下げていたカギを服の中から取り出す。そのカギで、シロの足首に嵌められていた枷を外した。
エルノとの約束を破り家を出たシロを、彼は傷つけなかった。足の腱は切られなかったが、こうして枷で繋がれることになった。
そんなものをつけなくても既に逃げるつもりなどなかったが、シロはそれを受け入れた。足枷の鎖は長く、家の中は大体自由に歩き回れる。だからシロはいつも、鎖を引きずりながらエルノを出迎えにいくのだ。
仕事から帰ってきたエルノから、血の匂いがすることもあった。けれどそれを指摘したことはない。ただ匂いに気づいただけで、特に気にもしなかった。エルノ自身の血でないのなら、それでよかった。
枷を外した足首を、エルノが撫でる。
それだけで、シロの体は期待に震えた。
エルノに連れ戻されてから、どれくらいの日数が経過したのかシロは数えていない。あの日から毎日のように、数えきれないほど二人は体を重ねた。
最初は戸惑うばかりだったシロだが、今ではすっかり彼の与える快楽に溺れ、自分から求めるようになっていた。
「エルノ……」
ねだるように名前を呼べば、彼は喜んで口づけてくれる。
唇を重ねながら衣服を脱がされ、シロは生まれたままの姿をエルノに晒した。ここに来る前に比べると、随分肉付きがよくなった。
「今日はどこから可愛がってあげようか」
楽しそうに笑いながら、シロの獣耳をぱくりと口に咥える。
「ひゃんっ」
「シロはどこも敏感だよね。少しの刺激でもすぐに鳴き声を上げて」
「ふあっ、あっ、あんっ」
柔らかく歯を立てられ、びくびくっと体が跳ねる。もう片方の獣耳の内側を指先で撫でられ、くすぐったいような快感に甘い声を上げてしまう。
彼に抱かれつづけたシロの体は、容易く快楽を拾い上げる。
秘所から蜜が零れるのを感じ、疼きを慰めるように太股を擦り合わせた。
気づいたエルノが、くすりと笑う。けれどまだ、そこには触れてくれないようだ。
エルノが手を伸ばしたのは胸だった。小さな膨らみをむにむにと揉み、尖った乳首を優しく摘み上げる。
「ひんっ……んあ、あっ」
「シロのここ、少し大きくなったんじゃない? 僕が毎日弄ってるからかな」
「あっ、知らない、んん、はあっ」
指だけではなく唇でも愛撫され、シロは快感に身悶える。
「や、もうやぁっ、エルノ……っ」
「どうして? 気持ちいいよね」
「ん、そこばっかり、やなの、あぁっ」
「ここだけで一回イッてごらん」
「っやぁん、いじ、わる……うぅ」
「シロはここだけでもイけるよね。ほら、僕の名前を呼びながらイッて」
「んあっ、あ、えるの、えるのっ、んん……!!」
片方は強く吸い上げられ、もう片方は指で強く引っ張られ、シロは呆気なく達した。蜜口からどっと愛液が溢れる。
余韻にぴくぴくと体を震わせるシロを、エルノは愛しげに見下ろす。
「可愛い、シロ。シロはいい子だね。次はどうしてほしい? シロのしてほしいことしてあげるよ」
優しく囁かれ、シロはうつ伏せになった。上半身をぺたりとベッドに付け、腰を高く上げる。両手を伸ばして、膣穴を指で左右に広げて見せた。そこは蜜を滴らせ、彼の熱を求めてひくひくと開閉している。
はしたないおねだりも、もう何度も繰り返した。恥ずかしくて慣れることはないけれど、エルノが喜んでくれるのが嬉しかった。
「入れて、エルノ。エルノがほしいの……」
「いやらしくて可愛い。もう我慢できないの?」
「できない、エルノ、お願い、入れて」
「もちろん、可愛いシロのお願いだからね」
エルノはすぐに願いを叶えてくれた。
膣内に雄蕊を埋め込まれ、シロの体は歓喜に震える。
「あぁっ、あっ、エルノ、エルノ……っ」
「んっ、シロ……入れただけなのに、すごい、締め付けて……美味しそうに、食べてるみたいだね」
「だって、だって、気持ちいいのっ……ひぅっ、奥までいっぱいで、ぎゅうってしたら、中が、擦れて、あっ」
「はあっ……すごいね、ぎゅうぎゅうって僕のに吸い付いて……は、そんなに、気持ちいい……?」
「気持ちいい、んっ、エルノ、エルノ、あんっ」
「可愛い、シロ。いつも可愛いけど、気持ちよくなってるシロもほんとに可愛い」
エルノの息遣いで、彼が興奮していることが伝わってくる。
シロは今まで「可愛い」なんて言われたことがなかった。だから最初の頃、エルノの言う「可愛い」なんて言葉は信じていなかった。
でも今は、そう言われることが素直に嬉しいと思えた。
シロはもうすっかり、彼に飼い慣らされていた。
「きゃうっ、あ、だめ、そこ、触っちゃ……っ」
敏感な尻尾の付け根を撫でられ、シロは身を捩った。
「エルノ、だめっ」
「だめじゃないよ、気持ちいいでしょ」
「やぁっ、むずむずするの……っ」
「それが気持ちいいんだよ。ほら、尻尾が、はあっ、嬉しそうに揺れてるよ。シロの中も、んっ、気持ちよさそうにうねってる」
彼の言う通り、体は喜んでいた。
蜜を溢れさせながら、腰が動いてしまう。
「ね、シロ。気持ちいい、でしょ……っ」
「んあっ、あ、うん、エルノ、気持ちいい、気持ちいいの、エルノ、あぁっ」
シロを陥落させ、エルノは思う様尻尾を撫で回す。
もう片方の手でしっかりと腰を掴み、エルノは何度もシロの胎内を突いた。
陰茎が出し入れされるたびに、ぐちゅぐちゅと粘液が掻き出される。それはシロの内腿にまで溢れて伝った。
「あっ、エルノ、もう、いっちゃ……っ」
「うんっ、いいよ、シロ」
「えるの、あ、ああっ、えるの、いく、えるの……!!」
「っあ、くう……」
二人はほぼ同時に果てた。
彼の体液が腹の奥に注がれるのを感じ、シロの瞳はうっとりと蕩けた。
エルノの体が背中に覆い被さってくる。彼の重さと温もりに包まれると、なんとも言い表せない気持ちになった。
これが幸せなのだろうかと、シロはぼんやり考える。
「シロ、シロ、好きだよ」
「私も、好き……」
無意識に口をついて出る言葉が本心なのか、シロ自身にもわからない。
今までも何度か口にしたが、どれも無意識だった。
エルノにつられ、雰囲気に呑まれて言ってしまっただけなのか。それとも本心だからこそ、気持ちが言葉として溢れたのか。
わからないけれど、わからないままでもよかった。
きっとずっと、シロには自分の気持ちがわからない。
わからなくても、エルノから離れられないのだから。
エルノとこういった行為をした場合、一度で終わることは皆無だ。今日も、合間に食事は摂ったが何度も体を繋げた。もともと体力のないシロは、いつも終わったあとはぐったりして起き上がることができなくなる。
体を撫でるエルノの手の感触が心地いい。シロは目を閉じて微睡んでいた。
「シロ、可愛い、僕のシロ、僕だけのシロ」
半分眠った状態で、シロは彼の声を聞いていた。
「無理だったってわかってるけど、やっぱりもっと早く、君を迎えに行きたかった。ううん、出会ったときに、君をさらうことができたらよかったのに」
エルノの指がシロの体に残る傷跡を辿る。
シロの体には、無数の傷跡が残っていた。同族からの暴力によるものだ。けれどどれも小さくて、うっすらとしか見えないようなものだ。
シロは全く気にしていないが、彼はたまにこうして傷跡に触れる。だから目を閉じていてもわかった。
少しだけくすぐったいけれど、眠くて身動ぎもできない。
「もし出会ったときに君を同族から引き離せたら、君がこんなにたくさん、傷つくこともなかったのに」
目を閉じているので、エルノの表情はわからない。
彼の声音が、少しだけ低くなった気がした。
「今更、そんなこと考えてもどうにもならないけどね。どうしたってそんなことは不可能だったし」
シロに触れる彼の手は優しいのに、強い憤りが伝わってくる。
「でも、僕はどうしても許せないんだ。僕のシロをこんなに傷つけた奴らを。シロが報復なんて望んでないのは知ってるよ。シロがあいつらを恨んでないのも。だから、君は知らなくていい。僕の傍にいて、僕のことだけ考えていて」
ふと、血の匂いを思い出す。仕事から帰ってきたエルノが纏っていた、血の匂い。
けれどシロはそれ以上深く考えなかった。
余計なことは考えなくていい。エルノがいてくれれば、それだけでいい。
「大好きだよ、シロ」
優しい彼の声を耳にして、シロは穏やかな眠りに就いた。
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
読んでくださってありがとございます。
108
この作品は感想を受け付けておりません。
あなたにおすすめの小説





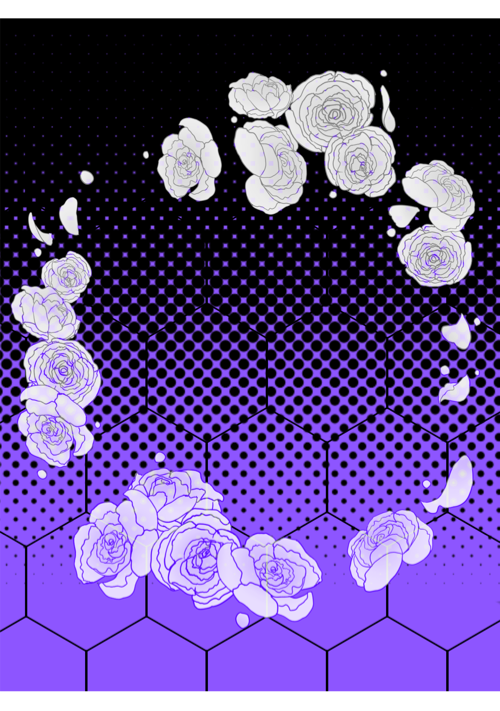
【ヤンデレ八尺様に心底惚れ込まれた貴方は、どうやら逃げ道がないようです】
一ノ瀬 瞬
恋愛
それは夜遅く…あたりの街灯がパチパチと
不気味な音を立て恐怖を煽る時間
貴方は恐怖心を抑え帰路につこうとするが…?

コワモテ軍人な旦那様は彼女にゾッコンなのです~新婚若奥様はいきなり大ピンチ~
二階堂まや♡電書「騎士団長との~」発売中
恋愛
政治家の令嬢イリーナは社交界の《白薔薇》と称される程の美貌を持ち、不自由無く華やかな生活を送っていた。
彼女は王立陸軍大尉ディートハルトに一目惚れするものの、国内で政治家と軍人は長年対立していた。加えて軍人は質実剛健を良しとしており、彼女の趣味嗜好とはまるで正反対であった。
そのためイリーナは華やかな生活を手放すことを決め、ディートハルトと無事に夫婦として結ばれる。
幸せな結婚生活を謳歌していたものの、ある日彼女は兄と弟から夜会に参加して欲しいと頼まれる。
そして夜会終了後、ディートハルトに華美な装いをしているところを見られてしまって……?

ホストな彼と別れようとしたお話
下菊みこと
恋愛
ヤンデレ男子に捕まるお話です。
あるいは最終的にお互いに溺れていくお話です。
御都合主義のハッピーエンドのSSです。
小説家になろう様でも投稿しています。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















