57 / 84
5.魔王城アカデミー
11話
しおりを挟む
その日の午後、シオンは魔王城の地下へと向かっていた。
つい最近まで地下室の存在を知らなかったが、今日はそこに用事がある。
長い廊下を歩いて、滅多に開かれない重たいドアを開ける。
ギギ、と軋んだような音を立てながらゆっくりとドアが動き、地下へと続く空間を思わせるひんやりとした空気が僅かに流れた。
長い間主を失っていたその空間に、ようやく明かりが灯されるようになって数日。
薄暗さはあるものの、地下へ続く階段は綺麗に掃き掃除され、光を宿すランプの油も新品に交換されている。
コツ、コツと、地下へ続く通路の壁に反響して靴音が響く。
それから少し歩いたところに、ドアがひとつ。
シオンはそのドアをノックして、中へと呼びかけた。
「シンシアさん、いらっしゃいますか?」
返事の代わりに、にゃーんという鳴き声が返ってくる。
「入りますね」
そろっとドアを開けると、足元にすかさず黒猫がすり寄ってくる。
最初は恐ろしいと感じるところもあったが、こうして顔を寄せてくる姿はどうやっても愛くるしい。
ぐるぐると鳴るあごの下を何度か撫でてやってから、シオンは部屋の奥へと向かった。
陰鬱な空気が漂っていた崖の上の洋館とは異なり、この地下の研究施設はこざっぱりとしている。
地下室の大半は研究施設にスペースを割いているが、その一部を改装してシンシアが私室として利用しているらしい。
荷物がまさに運び込まれたばかり、という様子だが、全体的にがらんとしていて物寂しさがあるのだ。
地上の光を取り入れられる窓の近くに、小さなテーブルセットが佇んでいる。
その上には、カップがふたつ。
シオンが来る前に、誰かがここを訪ねていたのだろうか。
「あら、お嬢さん」
艶を放つような声。
「シンシアさん、お邪魔しています」
そこには、丈の短い漆黒のワンピースの上から白衣を纏ったシンシアの姿があった。
(わあ、刺激的!)
タイトな生地が、彼女の豊満なボディラインを引き立てている。
シオンは自分の貧相な体を思い出して、なんだかいたたまれない気持ちになった。
「その後、変異モンスターの解析はどうかなと思いまして」
シオンの問いに、シンシアは気だるげな返事を返した。
「んー……そうねえ……蜘蛛の時もそうだけど、サンドワームのほうも結構雑な仕事をしているっていう印象ね」
私ならやらないわ、と言ってシンシアはフンと鼻を鳴らした。
彼女なりの美学に、何か反するところがあったのだろうか。
「雑、というと?」
「お嬢さんも言ってたけれど、蜘蛛に関しては変異が強すぎて体のバランスが崩れていたし……サンドワームの中、開けてみたけど、自分の毒で体を中から焼かれてる状態だったわよ」
中から焼かれる、という言葉にシオンは思わずぞっとした。
妙に狂暴で、傷を負わせても行動を止めなかったという証言もある。
もしかしたら、体内が毒素で汚染されているせいで暴れていたのかもしれない。
「こんな雑なやりかた、冗談でも私に疑いが向いたなんて失礼も甚だしいわよ」
シンシアは憮然とした表情で腕組みをした。
「面白そうなパーツを、とりあえずくっつけてみただけ、っていう感じ。適合するかは運だから、失敗も相応に発生してるでしょうね」
その目には侮蔑の色が滲んでいて、やはり彼女はマッドサイエンティストではなく医者なのだ、と感じさせる。
にゃあ、と鳴いてシンシアの方へと黒猫が駆け寄った。
この猫も、恐らくは彼女に命を救われた存在なのだろう。
「他の地域からも、別の変異体のうわさが聞こえてきているんです」
「そうでしょうね。この手の研究、やめ時が見つからないのよ。くじ引きみたいなものだもの」
美しくないわ、と頬を膨らませて、シンシアは猫を抱き上げた。
やめ時が見つからない、という言葉が、シオンの心に影を落とす。
変異体の出没が頻発するようになったら、世界はどうなってしまうのだろうか。
あの時、レヴィアスが背中に負った傷を思い出す。
手を伝った血の温かさと、青ざめていく彼の顔が頭の隅にこびりついて離れない。
「愉快犯か、何らかの思想を持っての行いなのか、半々ってところね」
「……目的があるとして、それは何なんでしょう」
「それを調べるのは私の仕事じゃないわよ。でも……」
ん、と赤く染まった唇を小さくとがらせ、シンシアが少し考える。
彼女の胸元で猫があくびをひとつ。
「単純に生物兵器として……もしくは、換金目的か、技術をもっと高等な生物に適用するための準備段階か……」
宙を見るような目をしながら、シンシアがブツブツと小さく呟く。
これは恐らくシンシアの癖なのだろう。
早すぎる思考が、口元から溢れるように流れ出る。
「もっと高等な生物……ですか」
ぞわ、と鳥肌が立つのを感じながら、シオンが呟いた。
「これまで見つかったのはサンドワームと蜘蛛でしょう? どちらも生物としては割と単純にできていて、自己修復力も高い。多少うまく適合しなくてもなあなあで生きてはいけそうな部類なのよ」
確かに、言われてみればその通りだ。
そして、次に噂が聞こえてきたのはパイロリザード。
彼らもまた、自己修復力が高い。
そして、サンドワームや蜘蛛と比較すると、シンシアが言う『高等な生物』に近づいているような気がする。
シオンはこわごわとシンシアへ問いかける。
「もし仮に、最終的な目標が人間や魔物に対する技術の適用なのだとしたら……?」
「まあ、出来なくはないでしょうね。……例えば、私がオリヴィエに施した手術のように。実際はもっと、大がかりでしょうけれど」
シンシアは自嘲気味に笑った。
人間や、魔物が、変異させられてしまう可能性がある。
それは想像しただけでひどく恐ろしく、シオンは恐怖に押し黙ってしまった。
「ありがとうございます。パイロリザードの件は討伐の運びになった際、改めて話をさせてください」
「はいはい、でもどこまで手伝うかは、私が決めることだからね」
少し鬱陶しそうな顔をされて、シオンは苦笑いする。
シンシアと猫に挨拶をして、足早に地下室を後にした。
「ふう……」
地上に戻り、シオンは食堂で貰ったオレンジジュースを飲みながら、ぷらぷらと魔王城内の広場を散歩していた。
ふと、以前カイレンに教えてもらったとっておきのビュースポットを思い出して、足を向ける。
ジュース一杯分の休憩をしよう、という気持ちになれたのは、最近のシオンにとっては大きな進歩だ。
人通りの多い道を抜け、食用の果樹が立ち並ぶエリアへと向かう。
作業中の小休憩用に設置されたものだろうが、小さなベンチとテーブルがいくつか並んでいる。
シオンはよいしょとそのベンチに腰かけて、伸びをした。
まだ色づく前の、青いリンゴの実がぽつぽつと木になっている。
時折聞こえる、プン、という蜂の羽音が、静寂に少しのアクセントを加えてくれた。
「やあ、昨日あんなことがあったのに不用心だね」
背後から突然声をかけられて、シオンはビクリと肩を震わせた。
振り返らなくてもわかる。
甘やかなこの声の持ち主は、ひとり。
「エリオルさん……」
名前を呟くと、エリオルはふわりと微笑んだ。
昨日見た狂気とは全く結びつかない、華やかで、清らかな笑顔だ。
今は、とにかくその美しさが恐ろしい。
思わずシオンはベンチから腰を上げ、ぎゅっと両手を握りしめてエリオルと向かいあった。
「なぜ魔王城に出入りを?」
「魔王には客として迎えられているよ。僕には天界とのパイプ役としての利用価値があるからね」
天界。
つまりは、天使が住まう、地上とは離れたところに存在する場所のことだと聞いた。
それでも、昨日のノイルの様子を思い出すと、こうも頻繁に魔王城に顔を出す理由がわからない。
まさか、本当に今でもレヴィアスの命を狙っているのだろうか?
警戒心をむき出しにして、シオンはぐっと身構えた。
「大丈夫、昨日と今日の目的は君じゃない」
エリオルが目を細めてニコリと笑った。
その言葉を信じていいのかどうかも、もはや疑わしい。
瞳の奥は、こちらをじっととらえて微動だにしていないのだから。
「シンシアが魔王城に戻ったと聞いたからね、挨拶に来たのさ」
シンシアの研究室に置かれていたふたつのカップと繋がった。
彼女が会っていたのは、エリオルだったのか。
思えば、港町で初めて出会った時もエリオルはオリヴィエの研究ノートを持っていた。
「シンシアさんとはお知り合いなんですか」
「オリヴィエの研究のファン、って言っただろう? あれは勿論本当、だからシンシアともぜひ話がしたかった」
エリオルは医学に興味があるということだろうか。
深く聞きたいような気もするが、このままふたりで会話をしていて良いのか、とシオンの頭の中で警鐘が鳴る。
「……心配しなくても、今、レヴィアスを殺すつもりはないよ」
エリオルは、シオンの目を見てそう囁いた。
真っすぐに見据えられて、シオンは思わず目を泳がせる。
「昨日は急に腕を掴んだりしてごめんね。仲直りをしよう」
奇妙なほど明るい口調で、エリオルはシオンに語り掛ける。
言い知れぬ恐怖に、シオンはその場から逃げだそうと後ずさりした。
それを許さない、というように、エリオルは言葉をつづけた。
「お詫びに、君が知らない、僕とレヴィアスのお話をしよう」
エリオルは流れるような所作で、シオンにベンチへと座る様に促す。
シオンは口を引き結んで、静かにベンチへと腰かけた。
つい最近まで地下室の存在を知らなかったが、今日はそこに用事がある。
長い廊下を歩いて、滅多に開かれない重たいドアを開ける。
ギギ、と軋んだような音を立てながらゆっくりとドアが動き、地下へと続く空間を思わせるひんやりとした空気が僅かに流れた。
長い間主を失っていたその空間に、ようやく明かりが灯されるようになって数日。
薄暗さはあるものの、地下へ続く階段は綺麗に掃き掃除され、光を宿すランプの油も新品に交換されている。
コツ、コツと、地下へ続く通路の壁に反響して靴音が響く。
それから少し歩いたところに、ドアがひとつ。
シオンはそのドアをノックして、中へと呼びかけた。
「シンシアさん、いらっしゃいますか?」
返事の代わりに、にゃーんという鳴き声が返ってくる。
「入りますね」
そろっとドアを開けると、足元にすかさず黒猫がすり寄ってくる。
最初は恐ろしいと感じるところもあったが、こうして顔を寄せてくる姿はどうやっても愛くるしい。
ぐるぐると鳴るあごの下を何度か撫でてやってから、シオンは部屋の奥へと向かった。
陰鬱な空気が漂っていた崖の上の洋館とは異なり、この地下の研究施設はこざっぱりとしている。
地下室の大半は研究施設にスペースを割いているが、その一部を改装してシンシアが私室として利用しているらしい。
荷物がまさに運び込まれたばかり、という様子だが、全体的にがらんとしていて物寂しさがあるのだ。
地上の光を取り入れられる窓の近くに、小さなテーブルセットが佇んでいる。
その上には、カップがふたつ。
シオンが来る前に、誰かがここを訪ねていたのだろうか。
「あら、お嬢さん」
艶を放つような声。
「シンシアさん、お邪魔しています」
そこには、丈の短い漆黒のワンピースの上から白衣を纏ったシンシアの姿があった。
(わあ、刺激的!)
タイトな生地が、彼女の豊満なボディラインを引き立てている。
シオンは自分の貧相な体を思い出して、なんだかいたたまれない気持ちになった。
「その後、変異モンスターの解析はどうかなと思いまして」
シオンの問いに、シンシアは気だるげな返事を返した。
「んー……そうねえ……蜘蛛の時もそうだけど、サンドワームのほうも結構雑な仕事をしているっていう印象ね」
私ならやらないわ、と言ってシンシアはフンと鼻を鳴らした。
彼女なりの美学に、何か反するところがあったのだろうか。
「雑、というと?」
「お嬢さんも言ってたけれど、蜘蛛に関しては変異が強すぎて体のバランスが崩れていたし……サンドワームの中、開けてみたけど、自分の毒で体を中から焼かれてる状態だったわよ」
中から焼かれる、という言葉にシオンは思わずぞっとした。
妙に狂暴で、傷を負わせても行動を止めなかったという証言もある。
もしかしたら、体内が毒素で汚染されているせいで暴れていたのかもしれない。
「こんな雑なやりかた、冗談でも私に疑いが向いたなんて失礼も甚だしいわよ」
シンシアは憮然とした表情で腕組みをした。
「面白そうなパーツを、とりあえずくっつけてみただけ、っていう感じ。適合するかは運だから、失敗も相応に発生してるでしょうね」
その目には侮蔑の色が滲んでいて、やはり彼女はマッドサイエンティストではなく医者なのだ、と感じさせる。
にゃあ、と鳴いてシンシアの方へと黒猫が駆け寄った。
この猫も、恐らくは彼女に命を救われた存在なのだろう。
「他の地域からも、別の変異体のうわさが聞こえてきているんです」
「そうでしょうね。この手の研究、やめ時が見つからないのよ。くじ引きみたいなものだもの」
美しくないわ、と頬を膨らませて、シンシアは猫を抱き上げた。
やめ時が見つからない、という言葉が、シオンの心に影を落とす。
変異体の出没が頻発するようになったら、世界はどうなってしまうのだろうか。
あの時、レヴィアスが背中に負った傷を思い出す。
手を伝った血の温かさと、青ざめていく彼の顔が頭の隅にこびりついて離れない。
「愉快犯か、何らかの思想を持っての行いなのか、半々ってところね」
「……目的があるとして、それは何なんでしょう」
「それを調べるのは私の仕事じゃないわよ。でも……」
ん、と赤く染まった唇を小さくとがらせ、シンシアが少し考える。
彼女の胸元で猫があくびをひとつ。
「単純に生物兵器として……もしくは、換金目的か、技術をもっと高等な生物に適用するための準備段階か……」
宙を見るような目をしながら、シンシアがブツブツと小さく呟く。
これは恐らくシンシアの癖なのだろう。
早すぎる思考が、口元から溢れるように流れ出る。
「もっと高等な生物……ですか」
ぞわ、と鳥肌が立つのを感じながら、シオンが呟いた。
「これまで見つかったのはサンドワームと蜘蛛でしょう? どちらも生物としては割と単純にできていて、自己修復力も高い。多少うまく適合しなくてもなあなあで生きてはいけそうな部類なのよ」
確かに、言われてみればその通りだ。
そして、次に噂が聞こえてきたのはパイロリザード。
彼らもまた、自己修復力が高い。
そして、サンドワームや蜘蛛と比較すると、シンシアが言う『高等な生物』に近づいているような気がする。
シオンはこわごわとシンシアへ問いかける。
「もし仮に、最終的な目標が人間や魔物に対する技術の適用なのだとしたら……?」
「まあ、出来なくはないでしょうね。……例えば、私がオリヴィエに施した手術のように。実際はもっと、大がかりでしょうけれど」
シンシアは自嘲気味に笑った。
人間や、魔物が、変異させられてしまう可能性がある。
それは想像しただけでひどく恐ろしく、シオンは恐怖に押し黙ってしまった。
「ありがとうございます。パイロリザードの件は討伐の運びになった際、改めて話をさせてください」
「はいはい、でもどこまで手伝うかは、私が決めることだからね」
少し鬱陶しそうな顔をされて、シオンは苦笑いする。
シンシアと猫に挨拶をして、足早に地下室を後にした。
「ふう……」
地上に戻り、シオンは食堂で貰ったオレンジジュースを飲みながら、ぷらぷらと魔王城内の広場を散歩していた。
ふと、以前カイレンに教えてもらったとっておきのビュースポットを思い出して、足を向ける。
ジュース一杯分の休憩をしよう、という気持ちになれたのは、最近のシオンにとっては大きな進歩だ。
人通りの多い道を抜け、食用の果樹が立ち並ぶエリアへと向かう。
作業中の小休憩用に設置されたものだろうが、小さなベンチとテーブルがいくつか並んでいる。
シオンはよいしょとそのベンチに腰かけて、伸びをした。
まだ色づく前の、青いリンゴの実がぽつぽつと木になっている。
時折聞こえる、プン、という蜂の羽音が、静寂に少しのアクセントを加えてくれた。
「やあ、昨日あんなことがあったのに不用心だね」
背後から突然声をかけられて、シオンはビクリと肩を震わせた。
振り返らなくてもわかる。
甘やかなこの声の持ち主は、ひとり。
「エリオルさん……」
名前を呟くと、エリオルはふわりと微笑んだ。
昨日見た狂気とは全く結びつかない、華やかで、清らかな笑顔だ。
今は、とにかくその美しさが恐ろしい。
思わずシオンはベンチから腰を上げ、ぎゅっと両手を握りしめてエリオルと向かいあった。
「なぜ魔王城に出入りを?」
「魔王には客として迎えられているよ。僕には天界とのパイプ役としての利用価値があるからね」
天界。
つまりは、天使が住まう、地上とは離れたところに存在する場所のことだと聞いた。
それでも、昨日のノイルの様子を思い出すと、こうも頻繁に魔王城に顔を出す理由がわからない。
まさか、本当に今でもレヴィアスの命を狙っているのだろうか?
警戒心をむき出しにして、シオンはぐっと身構えた。
「大丈夫、昨日と今日の目的は君じゃない」
エリオルが目を細めてニコリと笑った。
その言葉を信じていいのかどうかも、もはや疑わしい。
瞳の奥は、こちらをじっととらえて微動だにしていないのだから。
「シンシアが魔王城に戻ったと聞いたからね、挨拶に来たのさ」
シンシアの研究室に置かれていたふたつのカップと繋がった。
彼女が会っていたのは、エリオルだったのか。
思えば、港町で初めて出会った時もエリオルはオリヴィエの研究ノートを持っていた。
「シンシアさんとはお知り合いなんですか」
「オリヴィエの研究のファン、って言っただろう? あれは勿論本当、だからシンシアともぜひ話がしたかった」
エリオルは医学に興味があるということだろうか。
深く聞きたいような気もするが、このままふたりで会話をしていて良いのか、とシオンの頭の中で警鐘が鳴る。
「……心配しなくても、今、レヴィアスを殺すつもりはないよ」
エリオルは、シオンの目を見てそう囁いた。
真っすぐに見据えられて、シオンは思わず目を泳がせる。
「昨日は急に腕を掴んだりしてごめんね。仲直りをしよう」
奇妙なほど明るい口調で、エリオルはシオンに語り掛ける。
言い知れぬ恐怖に、シオンはその場から逃げだそうと後ずさりした。
それを許さない、というように、エリオルは言葉をつづけた。
「お詫びに、君が知らない、僕とレヴィアスのお話をしよう」
エリオルは流れるような所作で、シオンにベンチへと座る様に促す。
シオンは口を引き結んで、静かにベンチへと腰かけた。
0
あなたにおすすめの小説

凡夫転生〜異世界行ったらあまりにも普通すぎた件〜
小林一咲
ファンタジー
「普通がいちばん」と教え込まれてきた佐藤啓二は、日本の平均寿命である81歳で平凡な一生を終えた。
死因は癌だった。
癌による全死亡者を占める割合は24.6パーセントと第一位である。
そんな彼にも唯一「普通では無いこと」が起きた。
死後の世界へ導かれ、女神の御前にやってくると突然異世界への転生を言い渡される。
それも生前の魂、記憶や未来の可能性すらも次の世界へと引き継ぐと言うのだ。
啓二は前世でもそれなりにアニメや漫画を嗜んでいたが、こんな展開には覚えがない。
挙げ句の果てには「質問は一切受け付けない」と言われる始末で、あれよあれよという間に異世界へと転生を果たしたのだった。
インヒター王国の外、漁業が盛んな街オームで平凡な家庭に産まれ落ちた啓二は『バルト・クラスト』という新しい名を受けた。
そうして、しばらく経った頃に自身の平凡すぎるステータスとおかしなスキルがある事に気がつく――。
これはある平凡すぎる男が異世界へ転生し、その普通で非凡な力で人生を謳歌する物語である。

異世界でゆるゆるスローライフ!~小さな波乱とチートを添えて~
イノナかノかワズ
ファンタジー
助けて、刺されて、死亡した主人公。神様に会ったりなんやかんやあったけど、社畜だった前世から一転、ゆるいスローライフを送る……筈であるが、そこは知識チートと能力チートを持った主人公。波乱に巻き込まれたりしそうになるが、そこはのんびり暮らしたいと持っている主人公。波乱に逆らい、世界に名が知れ渡ることはなくなり、知る人ぞ知る感じに収まる。まぁ、それは置いといて、主人公の新たな人生は、温かな家族とのんびりした自然、そしてちょっとした研究生活が彩りを与え、幸せに溢れています。
*話はとてもゆっくりに進みます。また、序盤はややこしい設定が多々あるので、流しても構いません。
*他の小説や漫画、ゲームの影響が見え隠れします。作者の願望も見え隠れします。ご了承下さい。
*頑張って週一で投稿しますが、基本不定期です。
*本作の無断転載、無断翻訳、無断利用を禁止します。
小説家になろうにて先行公開中です。主にそっちを優先して投稿します。
カクヨムにても公開しています。
更新は不定期です。

『規格外の薬師、追放されて辺境スローライフを始める。〜作ったポーションが国家機密級なのは秘密です〜』
雛月 らん
ファンタジー
俺、黒田 蓮(くろだ れん)35歳は前世でブラック企業の社畜だった。過労死寸前で倒れ、次に目覚めたとき、そこは剣と魔法の異世界。しかも、幼少期の俺は、とある大貴族の私生児、アレン・クロイツェルとして生まれ変わっていた。
前世の記憶と、この世界では「外れスキル」とされる『万物鑑定』と『薬草栽培(ハイレベル)』。そして、誰にも知られていない規格外の莫大な魔力を持っていた。
しかし、俺は決意する。「今世こそ、誰にも邪魔されない、のんびりしたスローライフを送る!」と。
これは、スローライフを死守したい天才薬師のアレンと、彼の作る規格外の薬に振り回される異世界の物語。
平穏を愛する(自称)凡人薬師の、のんびりだけど実は波乱万丈な辺境スローライフファンタジー。

転生したみたいなので異世界生活を楽しみます
さっちさん
ファンタジー
又々、題名変更しました。
内容がどんどんかけ離れていくので…
沢山のコメントありがとうございます。対応出来なくてすいません。
誤字脱字申し訳ございません。気がついたら直していきます。
感傷的表現は無しでお願いしたいと思います😢
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
ありきたりな転生ものの予定です。
主人公は30代後半で病死した、天涯孤独の女性が幼女になって冒険する。
一応、転生特典でスキルは貰ったけど、大丈夫か。私。
まっ、なんとかなるっしょ。

家庭菜園物語
コンビニ
ファンタジー
お人好しで動物好きな最上悠は肉親であった祖父が亡くなり、最後の家族であり姉のような存在でもある黒猫の杏も、寿命から静かに息を引き取ろうとする。
「助けたいなら異世界に来てくれない」と少し残念な神様と出会う。
転移先では半ば強引に、死にかけていた犬を助けたことで、能力を失いそのひっそりとスローライフを送ることになってしまうが
迷い込んだ、訪問者次々とやってきて異世界で新しい家族や友人を作り、本人としてはほのぼのと家庭菜園を営んでいるが、小さな畑が世界には大きな影響を与えることになっていく。
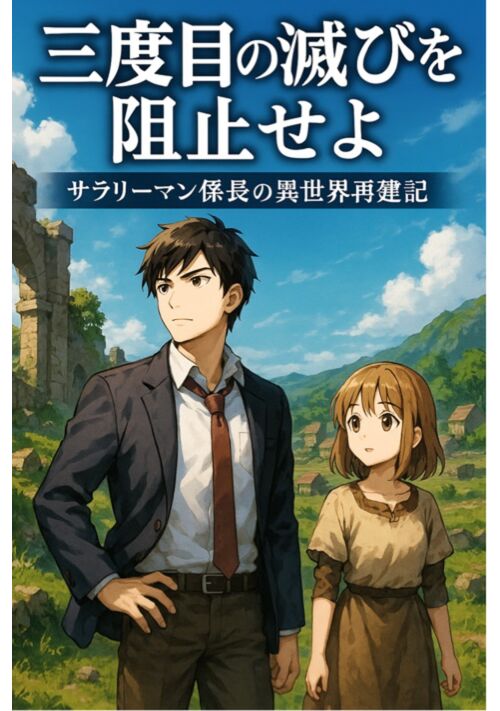
『三度目の滅びを阻止せよ ―サラリーマン係長の異世界再建記―』
KAORUwithAI
ファンタジー
45歳、胃薬が手放せない大手総合商社営業部係長・佐藤悠真。
ある日、横断歩道で子供を助け、トラックに轢かれて死んでしまう。
目を覚ますと、目の前に現れたのは“おじさんっぽい神”。
「この世界を何とかしてほしい」と頼まれるが、悠真は「ただのサラリーマンに何ができる」と拒否。
しかし神は、「ならこの世界は三度目の滅びで終わりだな」と冷徹に突き放す。
結局、悠真は渋々承諾。
与えられたのは“現実知識”と“ワールドサーチ”――地球の知識すら検索できる探索魔法。
さらに肉体は20歳に若返り、滅びかけの異世界に送り込まれた。
衛生観念もなく、食糧も乏しく、二度の滅びで人々は絶望の淵にある。
だが、係長として培った経験と知識を武器に、悠真は人々をまとめ、再び世界を立て直そうと奮闘する。
――これは、“三度目の滅び”を阻止するために挑む、ひとりの中年係長の異世界再建記である。

高校生の俺、異世界転移していきなり追放されるが、じつは最強魔法使い。可愛い看板娘がいる宿屋に拾われたのでもう戻りません
下昴しん
ファンタジー
高校生のタクトは部活帰りに突然異世界へ転移してしまう。
横柄な態度の王から、魔法使いはいらんわ、城から出ていけと言われ、いきなり無職になったタクト。
偶然会った宿屋の店長トロに仕事をもらい、看板娘のマロンと一緒に宿と食堂を手伝うことに。
すると突然、客の兵士が暴れだし宿はメチャクチャになる。
兵士に殴り飛ばされるトロとマロン。
この世界の魔法は、生活で利用する程度の威力しかなく、とても弱い。
しかし──タクトの魔法は人並み外れて、無法者も脳筋男もひれ伏すほど強かった。

転生魔竜~異世界ライフを謳歌してたら世界最強最悪の覇者となってた?~
アズドラ
ファンタジー
主人公タカトはテンプレ通り事故で死亡、運よく異世界転生できることになり神様にドラゴンになりたいとお願いした。 夢にまで見た異世界生活をドラゴンパワーと現代地球の知識で全力満喫! 仲間を増やして夢を叶える王道、テンプレ、モリモリファンタジー。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















