16 / 23
1.眠れる鴉を起こすのは
14.帰還報告
しおりを挟む
「随分と長い風呂だったな」
「あの悪臭と頑固な汚れに苦戦していたんですよ」
揶揄い気味にクレメンスがそういうと、リュディガーが疲弊した顔で返してきた。
当の本人であるヨシュカは悪びれず、からからと笑う。
その言葉を聞いてイグナーツは瞬時に距離を詰めてきた。
「待ってましたよ、殿下! カイラの実の使い方、ぜひお聞きしたかったんですよう。今回は木蔦病に見せかけるために使ったんですよね?ああ、その過程、ぜひ見たかったなぁ…。あ、でもまあ自分で試してみればいいのか…。それ人体に影響はないんですよね?まあ、あったらあったでそれは構わないんですけどね。あれ?でも?結構腕の辺りには跡が残ってますね。これ、残っちゃいます?って、ああああーっ、何するんですか、腐っても私は先輩ですよ?先輩は敬わなければいけないと学園で教わったでしょう!?」
矢継ぎ早に捲し立てるイグナーツの襟首を鷲掴みにして無理やり引き剥がしたのはミハエルだった。
「先輩などそれなりの言動をとって初めて敬われるものです。イグナーツ殿にはまず素養がありません」
結構辛辣な物言いにも関わらず、誰も止めることなかった。むしろ一同頷いて同意しているほどだった。そもそも受けた本人自体、ええ~と不満な声はあげつつも否定することはなかったのだから。
大体自身のことを「腐っても」などと表現するような人間だ。
「とりあえず腹に何か入れなさい。その間イグナーツは地下に赤ワインがいくつかあるから好きなものを持ってくるといい」
クレメンスが絶妙なタイミングでイグナーツの気をそらせる。
今すぐ確認したいことがあるのに、と、しばらくぶつぶつと呟いていたが、赤ワインの魅力に誘われるかのように地下へと降りて行った。
一息ついたところでウルリケはヨシュカの前まで進んだ。
ウルリケは上から下までじっくりと観察し、冷たく見下ろした。
そしてヨシュカも同じように、下から上までじっくりと品定めする。
互いが何も語らず、ただ、視線を交わす。
瞬時に張り詰めた空気に、周囲の人間は誰もが事の成り行きを黙って見届ける。
二人の間には立ち入れない張り詰めた空気が流れていた。
ウルリケの圧はかなり強い。初対面の人間ならば大抵は怯んでしまう。
そもそも外見上、一般的な女性の体躯に当てはまらない。男性並みの身体の大きさはそれだけでも十分圧を感じるだろうが、目の前にいるヨシュカはこれまた小鹿かと思わせるほどに華奢であった。
だがヨシュカは顔をそらすことも、後ずさることさえもなく、ウルリケと対峙していた。その視線は静かで、何を考えているのか読むことはできない。
長いこと視線を交わしていたものの、先に口火を切ったのはウルリケのほうだった。
「ようこそ北部へ」
この場の雰囲気に全く似つかわしくない、とってつけた様な歓迎の言葉に皆が拍子抜けする中、ヨシュカは満面の笑みを浮かべた。
「わざわざのお出迎え、感謝します。まずは貴方にお会いして確認しなければならないことが──」
笑みは浮かべているが、有無を言わせないような緊迫感を保ったままのヨシュカにウルリケは待ったをかけた。
「話はあとだ。まずは腹に何か入れろ」
「いや。はっきりさせておかないと。どうしても確認しなければならないことが──」
頑なな態度に業を煮やしたのか、あっという間に距離を詰め、首根っこをつかみ、それこそまるで子猫をつまむような所作でヨシュカをつまみ上げた。
「なんだ、随分ほそっこいな。こんなでよく追手を撒いてきたな」
あまりの扱いに、周囲が呆気にとられている中、最初に我に返って動いたのはリュディガーだった。
「母上、いくらなんでもそれは」
度が過ぎます。
そういう前にヨシュカを肩に担ぎ上げ、空いたもう片方の手でリュディガーを小脇に抱える。
「母上!」
どうして俺まで。
いまいち納得のいかない扱いに、抗議の声を上げるとウルリケは鼻で笑った。
「入ってくるときとてふらふらだったが、話している傍から今にも倒れそうではないか。そんなに話がしたければ喰いながらしろ」
あまりの悪臭に先に風呂で汚れを落とすところから始まったが、それと同じくらい空腹に耐えかねている状態だったことは間違いない。
この部屋に案内されている間、抑えきれない腹の虫の音に、案内していた侍女が笑いをこらえるのに必死だったくらいだ。
こうなったら、ウルリケを止められるものはいないとわかっているリュディガーは早々に抵抗する意思を放棄したが、意外なことにヨシュカは抵抗を試みる。
だからリュディガーは忠告する。
「一度こうと思ったら母上は絶対に人の意見など聴かない。あきらめてください」
リュディガーの進言に、ヨシュカはようやく動きを止めた。
席に着くや、三人は一気に食事に手を付けた。
食べながら報告という話ではあったが、腹を刺激するにおいには勝てず、とにかく腹におさめておさめて、ようやく落ち着いたところでミハエルが口を開いた。
「すみません……。すっかり食事に夢中になってしまって」
そのまま状況の説明に入ろうとしたところをクレメンスがやんわりと制する。
「気にするな。大抵は私の方で説明しておいた」
「いえ。ご当主様に対してあまりに不敬な態度でした」
本来ならば、そうした報告などは部下が取りまとめてするべきだ。当主代理も務める位置づけの人物にさせることではない。
末息子とはいえ、宰相家であるヴァルハイト家の者として、ミハエルが申し訳ないと思うことは当然なのだろう。
「本当に、お前は律儀で生真面目だな。そういうところは兄弟皆そっくりだ」
兄のことを口にされてミハエルはあいまいに笑った。
その笑いはウルリケの気持ちを憂いだものにするのに十分だったのだろう。
「カーティスのことは、残念だった」
簡素ではあるが、その一言に悲嘆と悔恨が含んでいることに皆が気が付いていた。
ウルリケの言葉にミハエルは首を振る。
それが兄が選んだ道なのならば、自分が口を出す権利はないと言わんばかりに。
「兄の最期は、ヨシュカ様から聞きました。ついでに常日頃どんな様子だったかも」
ヨシュカが話すカーティスは、ミハエルの記憶にある陽気で冗談の好きな青年そのものだった。
ヨシュカを逃がし、魔法士と対峙した時でさえも、笑って見送ったという。
「そうか」
短くそう答えるウルリケをミハエルはじっと見つめていた。
何か聞きたいことがあるのだろうと、その態度を見ていればわかった。
そしてその聞きたいことが何であるかも、大体は予想がつく。
しばらくからになった皿に目を向けながら、ミハエルはようやく口を開いた。
「ウルリケ様は、兄がお二人のもとにいたことをご存知だったのですか?」
「ああ」
責める口調ではなく、ただ流れる様に尋ねるミハエルに、淡々と返してきた。
そう答えられることは想像していたのだろう。薄く息を吐いているミハエルの苦渋を感じ取って、ウルリケが補足する。
「知っていたのはお前の父と私らだけだ」
「止めはしなかったのですか」
「そうしなければカーティスは生きていられないと判断したから」
ウルリケの回答は常に端的で、補足を伴わないことが多かった。だがミハエルにとってはその一言だけで十分だったようだ。
納得したかのように、悲しい顔で深く息を吐いた。
「──兄は、姉をとても大切に、していましたから。姉を失って、半狂乱になるくらい、愛していた」
ヴァルハイト家の二番目の息子の話はリュディガーでも知っている。
双子の姉を守り切れなかった自分に絶望し、護衛騎士を辞して北部に戻り、隠遁生活を送っていたと。
リュディガーが知りえる情報はその程度であったが、当事者であるミハエルにしてみたら、その心に去来するモノは多々あるだろう。
何とか自分の心の中を整理し、収めようとする姿は痛々しいくらいだった。
「カーティスがいなければ、俺は今この場にいなかったと思う」
誰もが口を噤み、重苦しい雰囲気を漂わせる中、はっきりと、なおかつ悲壮感を漂わせることなく伝えてきたのはヨシュカだった。
「最期のことだけじゃなくて、ね。長い間、そばにいてくれたから」
カーティスの選択は、悲しい結果になってしまったが、それでもその選択を悔いてくれるなとそう言っているかのようだった。
しみじみと、各自がカーティスについて淡い感傷に浸っていた時だった。
「公爵! ワイン、探したんですけどないんですよぉ。赤いのは確かにあるんですけど、この渋いのじゃなくて甘い、何というかフルーツっぽいアレが。あ、殿下! そうだ! カイラの実について聞きたいんですよー。まずはあの配合から聞いていいですかね?」
華々しく扉を開け、ワインの瓶2本抱えて戻ってきたのはイグナーツだった。
甘いワイン──おそらくサングリアのことかと思われるが、今はどんなワインかなどまったく気にしていない様子だった。
というよりも、ヨシュカを見た途端、カイラの実のことで頭がいっぱいになってワインのことなどすっかり忘れていることは明白だったからだ。
本当、空気を破壊してくる人だと半ば呆れ、でもこの時ばかりは感謝してもいいかなと思ったくらいだった。
イグナーツはというと、いつものごとく、距離感を測ることもなくずずいとヨシュカへと詰め寄る。
ヨシュカの隣に腰を下ろしていたリュディガーは剣呑な表情を浮かべて二人の間に割って入ろうとした。
だがそれをヨシュカ自身が軽く止める。
「説明するのは何も問題ないんだけど、ながーい話になっちゃいそうなんだよね」
「え、私はかまいませんよ? 一晩でも二晩でも」
「いや、正直それは無理」
「えぇ……。明日には実験に取り掛かりたいと思っていたのに」
傍若無人なイグナーツの言動にも大様に対応している姿はさすがというべきか。
「それより前に敵の詳細を把握しないとね」
会話の主導権を握り、話をしっかりと軌道修正させていく様をリュディガーは黙って見つめている。
幾分イグナーツが落ち着いたところで、ミハエルが立ち上がり、ずるずると自分の横へと連れていく。
このままヨシュカの隣に置いていたら碌なことにならないと踏んだのだろう。
そしてイグナーツは引きずられながらも口を止めることはしない。
「ああそっか。そうだね……。じゃあ! まず魔法士のこと教えてよ。間近で見たんでしょ? メッツァーハウンドは3体までだった? 持続時間とかも聞きたいなぁ」
強制的にミハエルの横に座らされ、ワインを目の前に置かれた。
さあ飲めと言わんばかりの状況を受けて、目の前のワインをぞんざいに開けて、手酌をし始めた。
イグナーツの関心事は常に自分の知識欲を満たす存在だ。
敵の正体を探りましょうといっているというのに、メッツァーハウンドに目が行くあたり、イグナーツらしい。
「顔は見た?」
「いや。なにかこう、変な仮面をかぶっていましたね」
ミハエルは同意を求めるようにヨシュカとリュディガーへと視線を向ける。
「隷属の仮面だよ。皇室所蔵の」
ヨシュカの即答にイグナーツも思い出したかのように付け加える。
「あー、なんかそんなのあったなぁ……。確か主従関係にある者同士で意識と魔力がやり取りできるんだよね、あれ」
意識と魔力、と言われて瞬時にクレメンスもミハエルも沈んだ表情を浮かべる。
「確かに、魔法士を媒介して我らに接触してきました」
「口調からは随分と内情に詳しい人物のようだった」
二人の報告にウルリケはグラスを置いて前に乗り出した。
「なにか特徴のある言動はなかったか?」
「隷属の仮面を使っていたということくらいしか……」
「相手も自分の正体を悟られないようにとあたりさわりのない物言いをしていたからな。──でも、もしかしたら昔、皇子にあったことがあるのかもしれない。昔と変わらぬブロンドか?と問いていたから」
確かにそんな物言いをしていた気もする。
「まぁ問題なのはしっかりと皇子の生存を確定させてしまったことだろうな」
クレメンスが悔しそうに言う。
「顔は認識された?」
「魔法士の方はしっかりと見ていたはずだ。媒介者の方はおそらくほんの2,3秒ほど」
「とらえられてからは?」
「魔法士は魔力も体力も枯渇していたようで、意識はなかったから認識はしていないかと思います」
実際、我らが捕らえたと同時、魔法士は倒れ込み、意識を取り戻すことはなかった。
それらを聞くとイグナーツは肩をすくめてさらりと言ってのけた。
「じゃあ『不幸中の幸い』ってことになるかも」
開けたワインはイグナーツの好みではなかったようで、ちょっと渋い顔をして、それでも口にする。
「生きていることがばれたのに?」
「魔法士はメッツァーハウンドを使役していたんでしょ? しかも3体。使役している間は知覚すべてがメッツァーハウンドに同化するんだ。犬は鼻は効けども視力は決して良くないからね。魔法士は多分正確には殿下──おっと失礼。ヨシュカ殿の顔を認識していないんじゃないかな」
それが当たっているとしても媒介者はしっかりとヨシュカを目視している。
ヨシュカ自身も『視られている』ことに気が付いたのだろう。だからあの時何の躊躇もなく目を切りつけた。
「仕方あるまい。こちらもいくつかの手がばれてしまったが、向こうも同じようなものだろう」
意外にもウルリケは鷹揚にそういった。
でもこちらに何か有力なネタがあっただろうかと反芻する。
「隷属の仮面とやらは皇室所蔵のものなんだろう?」
「それは確か」
クレメンスとヨシュカが同時に応えると、ウルリケは薄く笑う。
「シュトレイル家は物の管理についてはかなり厳格だ。それを簡単に使用できる立場にあるとなれば、おのずと答えは出てくるだろう?」
つまり今回の騒動には皇族もしくはそれに近しい者が関わっている。
その事実に予想はしていたものの、事の重要性に気がめいったことも事実だった。
「皇子を狙うということは、どう考えても皇位継承権を持っている者が関わっているだろうね」
ヨシュカは大きく伸びをして、これまた面倒そうにつぶやいた。
「まぁなぁ。俺も母さんもいずれは襲撃してくるだろうなとは予想していたんだよ。だから細心の注意を払って生活してきたし、襲撃直前まで居場所やらもろもろばれていたわけじゃないと思う。だからこそなんで今頃になってこんな攻勢をかけてきたのかそこがわからない」
少なくとも10年以上、皇女と皇子の捜索に関する目立った動きはなかったのに。
ヨシュカの素朴な疑問に対してウルリケはさらりと言ってのけた。
「そりゃあ女皇が危篤だからだろうな」
思わぬ事実にヨシュカが目を見張り、次の瞬間には納得がいったと言わんばかりの表情を浮かべた。
一瞬だけ浮かべたその顔は、背筋が凍り付くとはこういうことかと思わせるほどにぞっとするものだった。
「あの悪臭と頑固な汚れに苦戦していたんですよ」
揶揄い気味にクレメンスがそういうと、リュディガーが疲弊した顔で返してきた。
当の本人であるヨシュカは悪びれず、からからと笑う。
その言葉を聞いてイグナーツは瞬時に距離を詰めてきた。
「待ってましたよ、殿下! カイラの実の使い方、ぜひお聞きしたかったんですよう。今回は木蔦病に見せかけるために使ったんですよね?ああ、その過程、ぜひ見たかったなぁ…。あ、でもまあ自分で試してみればいいのか…。それ人体に影響はないんですよね?まあ、あったらあったでそれは構わないんですけどね。あれ?でも?結構腕の辺りには跡が残ってますね。これ、残っちゃいます?って、ああああーっ、何するんですか、腐っても私は先輩ですよ?先輩は敬わなければいけないと学園で教わったでしょう!?」
矢継ぎ早に捲し立てるイグナーツの襟首を鷲掴みにして無理やり引き剥がしたのはミハエルだった。
「先輩などそれなりの言動をとって初めて敬われるものです。イグナーツ殿にはまず素養がありません」
結構辛辣な物言いにも関わらず、誰も止めることなかった。むしろ一同頷いて同意しているほどだった。そもそも受けた本人自体、ええ~と不満な声はあげつつも否定することはなかったのだから。
大体自身のことを「腐っても」などと表現するような人間だ。
「とりあえず腹に何か入れなさい。その間イグナーツは地下に赤ワインがいくつかあるから好きなものを持ってくるといい」
クレメンスが絶妙なタイミングでイグナーツの気をそらせる。
今すぐ確認したいことがあるのに、と、しばらくぶつぶつと呟いていたが、赤ワインの魅力に誘われるかのように地下へと降りて行った。
一息ついたところでウルリケはヨシュカの前まで進んだ。
ウルリケは上から下までじっくりと観察し、冷たく見下ろした。
そしてヨシュカも同じように、下から上までじっくりと品定めする。
互いが何も語らず、ただ、視線を交わす。
瞬時に張り詰めた空気に、周囲の人間は誰もが事の成り行きを黙って見届ける。
二人の間には立ち入れない張り詰めた空気が流れていた。
ウルリケの圧はかなり強い。初対面の人間ならば大抵は怯んでしまう。
そもそも外見上、一般的な女性の体躯に当てはまらない。男性並みの身体の大きさはそれだけでも十分圧を感じるだろうが、目の前にいるヨシュカはこれまた小鹿かと思わせるほどに華奢であった。
だがヨシュカは顔をそらすことも、後ずさることさえもなく、ウルリケと対峙していた。その視線は静かで、何を考えているのか読むことはできない。
長いこと視線を交わしていたものの、先に口火を切ったのはウルリケのほうだった。
「ようこそ北部へ」
この場の雰囲気に全く似つかわしくない、とってつけた様な歓迎の言葉に皆が拍子抜けする中、ヨシュカは満面の笑みを浮かべた。
「わざわざのお出迎え、感謝します。まずは貴方にお会いして確認しなければならないことが──」
笑みは浮かべているが、有無を言わせないような緊迫感を保ったままのヨシュカにウルリケは待ったをかけた。
「話はあとだ。まずは腹に何か入れろ」
「いや。はっきりさせておかないと。どうしても確認しなければならないことが──」
頑なな態度に業を煮やしたのか、あっという間に距離を詰め、首根っこをつかみ、それこそまるで子猫をつまむような所作でヨシュカをつまみ上げた。
「なんだ、随分ほそっこいな。こんなでよく追手を撒いてきたな」
あまりの扱いに、周囲が呆気にとられている中、最初に我に返って動いたのはリュディガーだった。
「母上、いくらなんでもそれは」
度が過ぎます。
そういう前にヨシュカを肩に担ぎ上げ、空いたもう片方の手でリュディガーを小脇に抱える。
「母上!」
どうして俺まで。
いまいち納得のいかない扱いに、抗議の声を上げるとウルリケは鼻で笑った。
「入ってくるときとてふらふらだったが、話している傍から今にも倒れそうではないか。そんなに話がしたければ喰いながらしろ」
あまりの悪臭に先に風呂で汚れを落とすところから始まったが、それと同じくらい空腹に耐えかねている状態だったことは間違いない。
この部屋に案内されている間、抑えきれない腹の虫の音に、案内していた侍女が笑いをこらえるのに必死だったくらいだ。
こうなったら、ウルリケを止められるものはいないとわかっているリュディガーは早々に抵抗する意思を放棄したが、意外なことにヨシュカは抵抗を試みる。
だからリュディガーは忠告する。
「一度こうと思ったら母上は絶対に人の意見など聴かない。あきらめてください」
リュディガーの進言に、ヨシュカはようやく動きを止めた。
席に着くや、三人は一気に食事に手を付けた。
食べながら報告という話ではあったが、腹を刺激するにおいには勝てず、とにかく腹におさめておさめて、ようやく落ち着いたところでミハエルが口を開いた。
「すみません……。すっかり食事に夢中になってしまって」
そのまま状況の説明に入ろうとしたところをクレメンスがやんわりと制する。
「気にするな。大抵は私の方で説明しておいた」
「いえ。ご当主様に対してあまりに不敬な態度でした」
本来ならば、そうした報告などは部下が取りまとめてするべきだ。当主代理も務める位置づけの人物にさせることではない。
末息子とはいえ、宰相家であるヴァルハイト家の者として、ミハエルが申し訳ないと思うことは当然なのだろう。
「本当に、お前は律儀で生真面目だな。そういうところは兄弟皆そっくりだ」
兄のことを口にされてミハエルはあいまいに笑った。
その笑いはウルリケの気持ちを憂いだものにするのに十分だったのだろう。
「カーティスのことは、残念だった」
簡素ではあるが、その一言に悲嘆と悔恨が含んでいることに皆が気が付いていた。
ウルリケの言葉にミハエルは首を振る。
それが兄が選んだ道なのならば、自分が口を出す権利はないと言わんばかりに。
「兄の最期は、ヨシュカ様から聞きました。ついでに常日頃どんな様子だったかも」
ヨシュカが話すカーティスは、ミハエルの記憶にある陽気で冗談の好きな青年そのものだった。
ヨシュカを逃がし、魔法士と対峙した時でさえも、笑って見送ったという。
「そうか」
短くそう答えるウルリケをミハエルはじっと見つめていた。
何か聞きたいことがあるのだろうと、その態度を見ていればわかった。
そしてその聞きたいことが何であるかも、大体は予想がつく。
しばらくからになった皿に目を向けながら、ミハエルはようやく口を開いた。
「ウルリケ様は、兄がお二人のもとにいたことをご存知だったのですか?」
「ああ」
責める口調ではなく、ただ流れる様に尋ねるミハエルに、淡々と返してきた。
そう答えられることは想像していたのだろう。薄く息を吐いているミハエルの苦渋を感じ取って、ウルリケが補足する。
「知っていたのはお前の父と私らだけだ」
「止めはしなかったのですか」
「そうしなければカーティスは生きていられないと判断したから」
ウルリケの回答は常に端的で、補足を伴わないことが多かった。だがミハエルにとってはその一言だけで十分だったようだ。
納得したかのように、悲しい顔で深く息を吐いた。
「──兄は、姉をとても大切に、していましたから。姉を失って、半狂乱になるくらい、愛していた」
ヴァルハイト家の二番目の息子の話はリュディガーでも知っている。
双子の姉を守り切れなかった自分に絶望し、護衛騎士を辞して北部に戻り、隠遁生活を送っていたと。
リュディガーが知りえる情報はその程度であったが、当事者であるミハエルにしてみたら、その心に去来するモノは多々あるだろう。
何とか自分の心の中を整理し、収めようとする姿は痛々しいくらいだった。
「カーティスがいなければ、俺は今この場にいなかったと思う」
誰もが口を噤み、重苦しい雰囲気を漂わせる中、はっきりと、なおかつ悲壮感を漂わせることなく伝えてきたのはヨシュカだった。
「最期のことだけじゃなくて、ね。長い間、そばにいてくれたから」
カーティスの選択は、悲しい結果になってしまったが、それでもその選択を悔いてくれるなとそう言っているかのようだった。
しみじみと、各自がカーティスについて淡い感傷に浸っていた時だった。
「公爵! ワイン、探したんですけどないんですよぉ。赤いのは確かにあるんですけど、この渋いのじゃなくて甘い、何というかフルーツっぽいアレが。あ、殿下! そうだ! カイラの実について聞きたいんですよー。まずはあの配合から聞いていいですかね?」
華々しく扉を開け、ワインの瓶2本抱えて戻ってきたのはイグナーツだった。
甘いワイン──おそらくサングリアのことかと思われるが、今はどんなワインかなどまったく気にしていない様子だった。
というよりも、ヨシュカを見た途端、カイラの実のことで頭がいっぱいになってワインのことなどすっかり忘れていることは明白だったからだ。
本当、空気を破壊してくる人だと半ば呆れ、でもこの時ばかりは感謝してもいいかなと思ったくらいだった。
イグナーツはというと、いつものごとく、距離感を測ることもなくずずいとヨシュカへと詰め寄る。
ヨシュカの隣に腰を下ろしていたリュディガーは剣呑な表情を浮かべて二人の間に割って入ろうとした。
だがそれをヨシュカ自身が軽く止める。
「説明するのは何も問題ないんだけど、ながーい話になっちゃいそうなんだよね」
「え、私はかまいませんよ? 一晩でも二晩でも」
「いや、正直それは無理」
「えぇ……。明日には実験に取り掛かりたいと思っていたのに」
傍若無人なイグナーツの言動にも大様に対応している姿はさすがというべきか。
「それより前に敵の詳細を把握しないとね」
会話の主導権を握り、話をしっかりと軌道修正させていく様をリュディガーは黙って見つめている。
幾分イグナーツが落ち着いたところで、ミハエルが立ち上がり、ずるずると自分の横へと連れていく。
このままヨシュカの隣に置いていたら碌なことにならないと踏んだのだろう。
そしてイグナーツは引きずられながらも口を止めることはしない。
「ああそっか。そうだね……。じゃあ! まず魔法士のこと教えてよ。間近で見たんでしょ? メッツァーハウンドは3体までだった? 持続時間とかも聞きたいなぁ」
強制的にミハエルの横に座らされ、ワインを目の前に置かれた。
さあ飲めと言わんばかりの状況を受けて、目の前のワインをぞんざいに開けて、手酌をし始めた。
イグナーツの関心事は常に自分の知識欲を満たす存在だ。
敵の正体を探りましょうといっているというのに、メッツァーハウンドに目が行くあたり、イグナーツらしい。
「顔は見た?」
「いや。なにかこう、変な仮面をかぶっていましたね」
ミハエルは同意を求めるようにヨシュカとリュディガーへと視線を向ける。
「隷属の仮面だよ。皇室所蔵の」
ヨシュカの即答にイグナーツも思い出したかのように付け加える。
「あー、なんかそんなのあったなぁ……。確か主従関係にある者同士で意識と魔力がやり取りできるんだよね、あれ」
意識と魔力、と言われて瞬時にクレメンスもミハエルも沈んだ表情を浮かべる。
「確かに、魔法士を媒介して我らに接触してきました」
「口調からは随分と内情に詳しい人物のようだった」
二人の報告にウルリケはグラスを置いて前に乗り出した。
「なにか特徴のある言動はなかったか?」
「隷属の仮面を使っていたということくらいしか……」
「相手も自分の正体を悟られないようにとあたりさわりのない物言いをしていたからな。──でも、もしかしたら昔、皇子にあったことがあるのかもしれない。昔と変わらぬブロンドか?と問いていたから」
確かにそんな物言いをしていた気もする。
「まぁ問題なのはしっかりと皇子の生存を確定させてしまったことだろうな」
クレメンスが悔しそうに言う。
「顔は認識された?」
「魔法士の方はしっかりと見ていたはずだ。媒介者の方はおそらくほんの2,3秒ほど」
「とらえられてからは?」
「魔法士は魔力も体力も枯渇していたようで、意識はなかったから認識はしていないかと思います」
実際、我らが捕らえたと同時、魔法士は倒れ込み、意識を取り戻すことはなかった。
それらを聞くとイグナーツは肩をすくめてさらりと言ってのけた。
「じゃあ『不幸中の幸い』ってことになるかも」
開けたワインはイグナーツの好みではなかったようで、ちょっと渋い顔をして、それでも口にする。
「生きていることがばれたのに?」
「魔法士はメッツァーハウンドを使役していたんでしょ? しかも3体。使役している間は知覚すべてがメッツァーハウンドに同化するんだ。犬は鼻は効けども視力は決して良くないからね。魔法士は多分正確には殿下──おっと失礼。ヨシュカ殿の顔を認識していないんじゃないかな」
それが当たっているとしても媒介者はしっかりとヨシュカを目視している。
ヨシュカ自身も『視られている』ことに気が付いたのだろう。だからあの時何の躊躇もなく目を切りつけた。
「仕方あるまい。こちらもいくつかの手がばれてしまったが、向こうも同じようなものだろう」
意外にもウルリケは鷹揚にそういった。
でもこちらに何か有力なネタがあっただろうかと反芻する。
「隷属の仮面とやらは皇室所蔵のものなんだろう?」
「それは確か」
クレメンスとヨシュカが同時に応えると、ウルリケは薄く笑う。
「シュトレイル家は物の管理についてはかなり厳格だ。それを簡単に使用できる立場にあるとなれば、おのずと答えは出てくるだろう?」
つまり今回の騒動には皇族もしくはそれに近しい者が関わっている。
その事実に予想はしていたものの、事の重要性に気がめいったことも事実だった。
「皇子を狙うということは、どう考えても皇位継承権を持っている者が関わっているだろうね」
ヨシュカは大きく伸びをして、これまた面倒そうにつぶやいた。
「まぁなぁ。俺も母さんもいずれは襲撃してくるだろうなとは予想していたんだよ。だから細心の注意を払って生活してきたし、襲撃直前まで居場所やらもろもろばれていたわけじゃないと思う。だからこそなんで今頃になってこんな攻勢をかけてきたのかそこがわからない」
少なくとも10年以上、皇女と皇子の捜索に関する目立った動きはなかったのに。
ヨシュカの素朴な疑問に対してウルリケはさらりと言ってのけた。
「そりゃあ女皇が危篤だからだろうな」
思わぬ事実にヨシュカが目を見張り、次の瞬間には納得がいったと言わんばかりの表情を浮かべた。
一瞬だけ浮かべたその顔は、背筋が凍り付くとはこういうことかと思わせるほどにぞっとするものだった。
0
あなたにおすすめの小説

愛してやまなかった婚約者は俺に興味がない
了承
BL
卒業パーティー。
皇子は婚約者に破棄を告げ、左腕には新しい恋人を抱いていた。
青年はただ微笑み、一枚の紙を手渡す。
皇子が目を向けた、その瞬間——。
「この瞬間だと思った。」
すべてを愛で終わらせた、沈黙の恋の物語。
IFストーリーあり
誤字あれば報告お願いします!
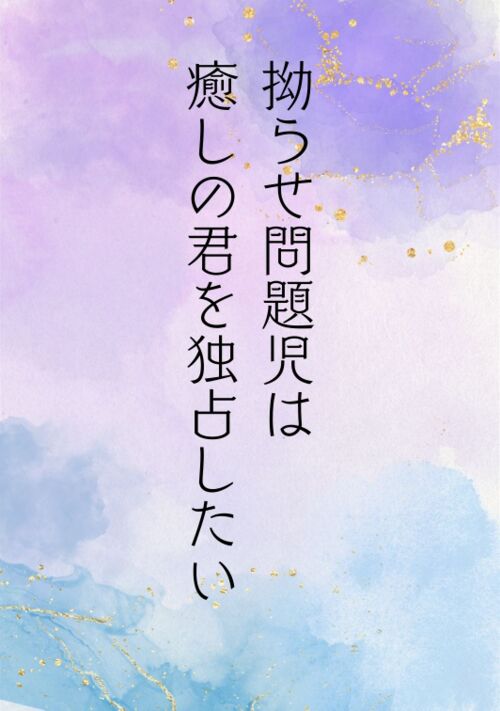
拗らせ問題児は癒しの君を独占したい
結衣可
BL
前世で限界社畜として心をすり減らした青年は、異世界の貧乏子爵家三男・セナとして転生する。王立貴族学院に奨学生として通う彼は、座学で首席の成績を持ちながらも、目立つことを徹底的に避けて生きていた。期待されることは、壊れる前触れだと知っているからだ。
一方、公爵家次男のアレクシスは、魔法も剣術も学年トップの才能を持ちながら、「何も期待されていない」立場に嫌気がさし、問題児として学院で浮いた存在になっていた。
補習課題のペアとして出会った二人。
セナはアレクシスを特別視せず、恐れも媚びも見せない。その静かな態度と、美しい瞳に、アレクシスは強く惹かれていく。放課後を共に過ごすうち、アレクシスはセナを守りたいと思い始める。
身分差と噂、そしてセナが隠す“癒やしの光魔法”。
期待されることを恐れるセナと、期待されないことに傷つくアレクシスは、すれ違いながらも互いを唯一の居場所として見つけていく。
これは、静かに生きたい少年と、選ばれたかった少年が出会った物語。

番を拒み続けるΩと、執着を隠しきれないαが同じ学園で再会したら逃げ場がなくなった話 ――優等生αの過保護な束縛は恋か支配か
雪兎
BL
第二性が存在する世界。
Ωであることを隠し、平穏な学園生活を送ろうと決めていた転校生・湊。
しかし入学初日、彼の前に現れたのは――
幼い頃に「番になろう」と言ってきた幼馴染のα・蓮だった。
成績優秀、容姿端麗、生徒から絶大な信頼を集める完璧なα。
だが湊だけが知っている。
彼が異常なほど執着深いことを。
「大丈夫、全部管理してあげる」
「君が困らないようにしてるだけだよ」
座席、時間割、交友関係、体調管理。
いつの間にか整えられていく環境。
逃げ場のない距離。
番を拒みたいΩと、手放す気のないα。
これは保護か、それとも束縛か。
閉じた学園の中で、二人の関係は静かに歪み始める――。

カランコエの咲く所で
mahiro
BL
先生から大事な一人息子を託されたイブは、何故出来損ないの俺に大切な子供を託したのかと考える。
しかし、考えたところで答えが出るわけがなく、兎に角子供を連れて逃げることにした。
次の瞬間、背中に衝撃を受けそのまま亡くなってしまう。
それから、五年が経過しまたこの地に生まれ変わることができた。
だが、生まれ変わってすぐに森の中に捨てられてしまった。
そんなとき、たまたま通りかかった人物があの時最後まで守ることの出来なかった子供だったのだ。

【完結】第三王子、ただいま輸送中。理由は多分、大臣です
ナポ
BL
ラクス王子、目覚めたら馬車の中。
理由は不明、手紙一通とパン一個。
どうやら「王宮の空気を乱したため、左遷」だそうです。
そんな理由でいいのか!?
でもなぜか辺境での暮らしが思いのほか快適!
自由だし、食事は美味しいし、うるさい兄たちもいない!
……と思いきや、襲撃事件に巻き込まれたり、何かの教祖にされたり、ドタバタと騒がしい!!


君に望むは僕の弔辞
爺誤
BL
僕は生まれつき身体が弱かった。父の期待に応えられなかった僕は屋敷のなかで打ち捨てられて、早く死んでしまいたいばかりだった。姉の成人で賑わう屋敷のなか、鍵のかけられた部屋で悲しみに押しつぶされかけた僕は、迷い込んだ客人に外に出してもらった。そこで自分の可能性を知り、希望を抱いた……。
全9話
匂わせBL(エ◻︎なし)。死ネタ注意
表紙はあいえだ様!!
小説家になろうにも投稿

分厚いメガネ令息の非日常
餅粉
BL
「こいつは俺の女だ。手を出したらどうなるかわかるよな」
「シノ様……素敵!」
おかしい。おかしすぎる!恥ずかしくないのか?高位貴族が平民の女学生に俺の女ってしかもお前は婚約者いるだろうが!!
その女学生の周りにはお慕いしているであろう貴族数名が立っていた。
「ジュリーが一番素敵だよ」
「そうだよ!ジュリーが一番可愛いし美人だし素敵だよ!!」
「……うん。ジュリーの方が…素敵」
ほんと何この状況、怖い!怖いすぎるぞ!あと妙にキモい
「先輩、私もおかしいと思います」
「だよな!」
これは真面目に学生生活を送ろうとする俺の日常のお話
※長くなりそうでしたら長編へ変更します。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















