12 / 32
秋暁、胸の奥が騒ぐとき(1)
しおりを挟む
高守柚瑠の自宅兼拠点に、場違いなほど厳かな気配が流れ込んできたのは、ちょうど依頼帰りで一息ついていた夕方のことだった。
「……柚瑠、お前んとこの結界、ゆるいな。見逃してやるけど」
突然、玄関をくぐってきたのは、和装に身を包んだ精悍な中年の男――高守玲音。柚瑠の遠縁にあたる親戚で、霊媒の世界では知る人ぞ知る凄腕だった。
「玲音さん……なんで急に?」
「ちょいと“良い素材”を見つけたからな。スカウトに来ただけだよ」
玲音の視線がすっと横に向けられる。そこには、キッチンで湯を沸かしていた律がいた。
「無我律くん。君、なかなか素質あるな。精神の揺らぎが少ない。霊との距離感も見事だ。柚瑠に使われてるより、もっと上で鍛えたほうがいい」
「……は?」
柚瑠は、手にしていたマグカップを落としそうになった。律もまた驚いた顔で目を瞬かせている。
「俺なんか、まだ未熟ですし、柚瑠さんの助手で……」
「だからこそ惜しい。高守家の名のもと、正式に助手として迎える。どうだ、考えておいてくれ」
玲音はそれだけ言い残すと、置き手紙のように名刺をテーブルに置き、さっさと玄関を出ていった。
――気まずい沈黙が落ちた。
「……柚瑠さん。俺、ちょっと外の空気吸ってきます」
そう言って出ていく律の背中を、柚瑠は呆然と見送った。
胸がざわつく。
助手だから、必要なんだ。
ずっとそばにいて、助けてくれて。僕はアイツがいなきゃ――いや、でも、それだけか?
(行くなよ……)
気づけば、柚瑠は玄関を飛び出していた。
律の背中を見つけたのは、角を曲がった小さな公園のあたりだった。風が、ふたりの間を吹き抜けていく。
「律!!」
呼ばれて、律が振り向く。
「……柚瑠さん?」
「……行くな。あんなスカウト、断れ。僕には、おまえが必要だ」
柚瑠の声は震えていた。自分でも、自分の感情の正体がわからなかった。
「僕は……おまえが助手だから?相棒だから?……それとも、ただ……」
「――俺は」
律が一歩、柚瑠に近づいた。その目には、もう迷いがなかった。
「俺は、柚瑠さんのことを、“好き”って意味で好きです」
柚瑠の息が止まった。
「助手としてじゃなくて、人として。男として、恋愛感情として。ずっと前から、俺は、柚瑠さんが……」
風が止まり、時間が凍るようだった。
「……わかんないんだよ」
柚瑠の声が小さく漏れる。
「僕の“必要”って気持ちが、おまえの言う“好き”と同じなのか、まだ……」
「それで、いいです」
律の声は静かだった。
「気づいてもらえただけで、今日は十分です」
その声に、柚瑠は目を伏せたまま、ぎゅっと拳を握りしめた。
“律を、失いたくない”――その気持ちだけは、確かだった。
---
夜の風が、ふたりの間をそっとすり抜ける。
律の告白を受けてから、柚瑠は一言も発していなかった。沈黙を破ったのは、意外にも律のほうだった。
「すみません……俺、勝手でしたよね」
「……バカ」
柚瑠がぽつりと呟いた。
「謝るくらいなら、言うなよ。そんな顔して、謝るなよ」
「……はい」
律が苦笑し、目を伏せる。その横顔を見て、柚瑠は心の奥底がかき乱されるような感覚に襲われていた。
助手としての信頼。戦友としての絆。そして、それを超える感情。
「……正直、まだ答えは出せない」
やっとの思いで口を開く。
「だけど、律がいなくなるって想像したら、息ができないくらい苦しくなった。それは、嘘じゃない」
律が目を上げる。柚瑠の言葉を、ひとつ残らず受け止めるように、まっすぐに。
「だったら、俺は待ちます。何年でも、何回でも、柚瑠さんの隣に立ち続けて……“好き”を証明してみせます」
「……めんどくせえな、おまえは」
柚瑠は、ようやく少しだけ口元を緩めた。
「でも……そばにいろ。今だけじゃねぇ。これからも、ずっと」
その言葉に、律の瞳が震える。
「はい」
「助手として――って、今は言っとく」
「はい。……でも、いつかそれが“恋人として”に変わることを願って、俺はそばにいます」
柚瑠は、何も返さなかった。
けれど、隣に並んで歩き出したその歩幅は、さっきより確かに近づいていた。
沈黙の中に芽生えた感情の輪郭は、まだぼやけていた。
それでも――それはたしかに、恋のはじまりだった。
---
「わあ……すっごい、人」
ライトアップされた城跡公園は、まさに秋の見頃。燃えるような赤や黄の紅葉が夜のとばりに照らされ、どこか現実離れした空間をつくっていた。
境内跡に沿って続く石畳の小道には、出店の屋台と観光客がずらりと並んでいる。
「おい黒川、あれ! 焼きだんご! 食っていこうぜ!」
「……因幡先生。除霊前なので、まず状況確認を優先していただけると……」
「なーに言ってんだよ、どうせ対象は深夜にしか出ないって言ってたじゃん? ちょっとくらい楽しんでもバチ当たんねーよ。な?」
「たしかに、報告では深夜帯限定の霊出没。今のうちに腹ごしらえしておくのも、合理的判断ですね」
横から律が口を挟んでくる。
「というわけで、律。僕はあれ食いたい。たい焼き」
「……はいはい、結局食べたいだけですね」
そしてその数分後――。
「うめぇぇ……あっ、因幡、次たこ焼きいこうぜ」
「いや、俺は唐揚げ。いや、串焼きも捨てがたいな……」
「ちょっと、君たち本当に仕事のつもりで来てる?」
「ああ? 腹が減ってはなんとやら、ってやつだろ。な、柚瑠」
「まったくだ。食わずして霊と向き合うとか正気の沙汰じゃない」
「「どっちが大食いか決着つけてやるよ!!!」」
ふたりの大人たちが、火花を散らしてコロッケと焼きそばに挑む横で、助手ふたりはほぼ無表情だった。
「……このふたり、似てますね」
「……ほんと、それな。胃袋だけでなくてテンションの上がり方も一緒だよ」
黒川と律はそれぞれのパートナーに紙ナプキンを差し出しながら、なんとも言えない溜め息をついた。
---
食い倒れの宴が一段落し、人混みの熱が落ち着く頃――。
一同は、城跡の裏手、観光客の流れから少し外れた川沿いの小道にいた。
風の音が紅葉を揺らし、時折、すすり泣くような声が混ざる。
「ここだな。霊が出るのは」
因幡が低く呟き、文庫本を開いた。
「どうやら、城落ちの夜、愛しい人を残して命を絶った侍女の霊らしいな……その執着が、時折現世を彷徨うらしい」
「愛と未練、か。因幡、朗読に入れ」
柚瑠は小さく印を切りながら、川沿いの空気を結界で満たしていく。
「よし、いくぞ。……“白銀の指が私の喉元をなぞった瞬間、私はただ快楽に喘ぐだけの存在になっていた……”」
柚瑠と律が同時に顔をしかめる。
「またそれか……!」
「毎度のことだけど、なんで除霊で官能朗読なんだろう……」
夜気がふるえた瞬間、木の陰から、朧げな人影が姿を現す。
泣き濡れた瞳、裾のほどけた白無垢。
怨念というより、深い悲しみがその身にまとわりついていた。
「うわっ……出た」
「大丈夫、こっち来るぞ。因幡、もう一段階感情込めて!」
> 「“彼の舌先が私の耳の奥まで届いた瞬間、すべてが崩壊して……”」
呻きとともに、霊の輪郭がふるえる。
柚瑠がすかさず最後の結界を仕上げると、霊はすっと涙を残して、紅葉の風に溶けていった。
ふわりと舞った一枚の紅葉が、因幡の足元に落ちる。
「……やれやれ。やっぱこのスタイル、間違ってねぇな」
「俺には間違ってるようにしか思えないんですが……」
黒川はため息をつきながら、因幡に上着を掛けた。風が冷たくなっていた。
一方その隣では、柚瑠がふいに言った。
「なぁ律。次のイベント飯、なにがあったっけ?」
「……もう、除霊が終わって安心した瞬間にこれなんだから……」
ふたりのコンビが静かに笑い合い、帰り道へと歩き出す。
紅葉の名残と、過ぎた怨念と。
そして、少しずつ育ち始めた4人の関係だけが、秋の城跡に静かに残されていた――。
---
除霊から戻ったあとの、深夜の静かな時間。
黒川のアパートの部屋は灯りを落とし、間接照明だけがほのかに空間を照らしていた。
「はぁ……今日はさすがに、疲れましたね」
ソファに深く腰を沈めた黒川が、小さく伸びをした。
すでにシャワーは浴び終えていて、ゆるく乾かした髪からは微かに柑橘系の香りが漂っていた。
部屋着のパーカーの袖を無意識にいじる手つきが、今日のことを反芻している証拠だった。
「まあな。……あの亡霊の最後のひとこと、気になるな」
キッチンからマグカップを2つ持ってきた因幡が、黒川の隣に腰を下ろす。
差し出されたカップには、薄く淹れたカモミールティー。
眠る前の静けさが、ふたりを自然に寄り添わせていた。
「“来世でまた、会えますように”――でしたね」
黒川が、ぽつりと呟く。
それは亡霊が光へ還る直前、消え入りそうな声でこぼした願いだった。
「愛してた人に再び会えるように、か。執着じゃなく、願いとして残ったんだな。……おまえは、信じるか? 来世とか、運命とか」
因幡がマグを片手に、ふと横目で黒川を見やった。
黒川は、答えに少しだけ間を置いた。
そして、柔らかく笑ってこう返す。
「……誰かを強く想う気持ちが、何かを超えることがあるなら。信じたいです。叶わなくても、願っていたい……って思うくらい、大切な人がいるなら」
その横顔には、熱も告白もない。ただ、少しだけ切なさを孕んだ穏やかな静けさがある。
だけど因幡は、その言葉の向かう先を、薄々気付いていた。
(……俺のことか?)
気付かないふり。
ずっとしてきた。
黒川が、誰よりも自分の言葉を信じ、支えてくれていること。
傍にいる理由が、ただの“助手”ではないこと――。
それを、ずっとわかっていながら、気付かないふりをしていた。
でも。
「……黒川」
「はい?」
因幡は何気ないような顔で、黒川の頭をぽんと撫でた。
唐突で、あまりにも優しくて、黒川の瞳が揺れる。
「……あんまり、そういう顔すんな。夜だし、変な気起こすだろ」
「……!」
赤くなる耳を隠すように、黒川はマグカップを持ち直した。
笑ってごまかすのは得意だったはずなのに、今夜はちょっと無理だった。
「すみません。気をつけます」
「いや、……気にすんな。おまえのそういうとこ、俺は……」
言いかけて、因幡は言葉を切った。
(好きだよ。……とか、今さら言えるかよ)
そんな自分に小さく舌打ちしながら、マグカップに口をつける。
静けさが戻る。
けれど、それはどこか心地いい緊張を孕んだ沈黙だった。
部屋の窓の外では、夜風が赤く色づいた葉を揺らしていた。
---
夜中。
窓の外では風が紅葉を揺らし、さらさらと乾いた音を立てていた。
その音の中に、かすかな声が混じった。
「やだ……いかないで、柚瑠さん……っ……」
寝返りを打った布団の中で、律は眉を寄せ、小さく震えていた。
夢のなかで何かにすがるように、誰かの名前を呼んでいる。
――柚瑠が、遠ざかっていく。
何も言わず、ただ背を向けて歩いていく。
呼んでも、手を伸ばしても、届かない。
胸を裂くような喪失感だけが、律の中に残った。
「――っ……!!」
びくん、と身体を起こして、律は夢から飛び起きた。
視界がにじんで、呼吸がうまくできない。
何が現実で、何が夢だったのか、その境目が曖昧なまま、目から涙が溢れ続けた。
「律……?」
低く優しい声が、すぐ横から聞こえた。
柚瑠だった。
隣の布団に背中合わせに寝ていた彼が、律の異変に気付いて目を覚ましていた。
「どうした、苦しい夢?」
律は何も答えられず、ただ小さく頷いた。
こぼれ落ちた涙が、シーツに滲んでいく。
柚瑠はそっと起き上がると、律の背中に腕をまわして、その身体を抱き寄せた。
「大丈夫。……僕はここにいる」
律の額が、柚瑠の胸元に触れる。
そのぬくもりに、律はようやく少しだけ呼吸を取り戻す。
「……夢の中で、柚瑠さんが、俺のこと嫌いになって、……どこかに行ってしまって……呼んでも、追いかけても、何にも届かなくて……」
震える声でこぼす律に、柚瑠は何も言わず、ただ優しく背を撫でた。
まるで小さな子どもをあやすような仕草だった。
「律。よく聞いて」
柚瑠は少しだけ体を離し、律の頬に手を添えて、まっすぐ目を見る。
「僕は、おまえが泣くほど不安になるような、そんな夢に負けないくらい、ちゃんとここにいる。……おまえを嫌いになるなんて、ありえない。おまえは、僕にとってただの助手じゃない。大事な存在だ」
律の唇がわなないた。
喉の奥から、嗚咽がこぼれそうになったその瞬間、柚瑠がもう一度、強く抱きしめる。
「……僕は、どこにも行かない。律、おまえの傍にいるよ。これからもずっと」
その言葉に、律の手がゆっくりと柚瑠の背に回った。
ぬくもりにすがるように、静かに、でもしっかりと。
「……柚瑠さん、……ありがとうございます」
涙のにじんだ声に、柚瑠は「バカ」とだけ囁いて、律の髪を撫でた。
夜の風が、ふたりのいる部屋の外を通り過ぎていく。
けれど、ここにはもう何の不安もなかった。
寄り添う温もりと、互いを求める想いだけが、確かにそこにあった。
---
夜が明け始める頃、律はようやくうとうととした浅い眠りに落ちていた。
窓のカーテンの隙間から、やわらかな朝の光が差し込んでいる。
部屋の空気はしんと静かで、聞こえるのは鳥のさえずりと、隣にいる誰かの穏やかな呼吸。
律は薄く目を開けた。
まぶたの裏にまだ残っていた夢の影は、今ではもうどこにもなかった。
隣にいる柚瑠の腕の中で目覚めた朝――
それは信じられないほど、あたたかくて、安心できる空間だった。
「……起きてたのか?」
不意に、低い声が頭の上から落ちてくる。
「っ……柚瑠さん、起こしちゃいましたか?」
「ん。目が覚めたら、おまえが俺の腕を掴んで離してくれなかっただけだ。寝苦しいかと思ったけど……まぁ、悪くなかった」
小さな冗談めいた言い回しに、律は頬を赤らめた。
昨夜の夢のことを思い出して胸がちくりと痛むけれど、柚瑠のぬくもりはそれをそっと包み込んでくれる。
「……あの、昨日は……すみませんでした。変な夢で取り乱して……」
「謝るなよ、律。怖い夢くらい見るもんだ。誰だって」
そう言って、柚瑠はゆっくり起き上がり、寝癖のついた髪を指先で整えながら、カップを手に取る。
「……コーヒー、淹れるけど飲むか?」
「はい、ぜひ……」
律もゆっくりと身体を起こした。
すぐ隣にある日常。
その中に柚瑠がいて、笑っていて、名前を呼んでくれている。
それだけで、律の胸の奥がじんわりとあたたまる。
小さなテーブルで、柚瑠が差し出したカップを受け取る。
そこに注がれた黒い液体は、ほんのり香ばしくて、鼻をくすぐった。
「甘くしてる。おまえ、苦いのダメだろ」
「……ありがとうございます」
さりげない気遣いに、律の心はまた少しだけ強くなれた気がした。
一口飲むと、ちょうどいい甘さと温度に、思わず頬がゆるむ。
「……なんか、こういう朝って、すごく……幸せですね」
ぽつりと漏れた律の言葉に、柚瑠は一瞬カップを口に運ぶ手を止めた。
だが、それをすぐに誤魔化すようにふっと笑う。
「何だそれ。夢見が悪かったやつの台詞には聞こえねえな」
「ふふっ……」
ふたりは顔を見合わせて笑った。
照れ隠しと、安堵と、静かな喜びがそこに混ざっていた。
昨日の夢はもう過去。
この朝は、確かな“今”として、ふたりの心に刻まれていく。
小さな朝のテーブルに、寄り添うふたりの距離が、昨日よりも少しだけ近くなっていた。
「……柚瑠、お前んとこの結界、ゆるいな。見逃してやるけど」
突然、玄関をくぐってきたのは、和装に身を包んだ精悍な中年の男――高守玲音。柚瑠の遠縁にあたる親戚で、霊媒の世界では知る人ぞ知る凄腕だった。
「玲音さん……なんで急に?」
「ちょいと“良い素材”を見つけたからな。スカウトに来ただけだよ」
玲音の視線がすっと横に向けられる。そこには、キッチンで湯を沸かしていた律がいた。
「無我律くん。君、なかなか素質あるな。精神の揺らぎが少ない。霊との距離感も見事だ。柚瑠に使われてるより、もっと上で鍛えたほうがいい」
「……は?」
柚瑠は、手にしていたマグカップを落としそうになった。律もまた驚いた顔で目を瞬かせている。
「俺なんか、まだ未熟ですし、柚瑠さんの助手で……」
「だからこそ惜しい。高守家の名のもと、正式に助手として迎える。どうだ、考えておいてくれ」
玲音はそれだけ言い残すと、置き手紙のように名刺をテーブルに置き、さっさと玄関を出ていった。
――気まずい沈黙が落ちた。
「……柚瑠さん。俺、ちょっと外の空気吸ってきます」
そう言って出ていく律の背中を、柚瑠は呆然と見送った。
胸がざわつく。
助手だから、必要なんだ。
ずっとそばにいて、助けてくれて。僕はアイツがいなきゃ――いや、でも、それだけか?
(行くなよ……)
気づけば、柚瑠は玄関を飛び出していた。
律の背中を見つけたのは、角を曲がった小さな公園のあたりだった。風が、ふたりの間を吹き抜けていく。
「律!!」
呼ばれて、律が振り向く。
「……柚瑠さん?」
「……行くな。あんなスカウト、断れ。僕には、おまえが必要だ」
柚瑠の声は震えていた。自分でも、自分の感情の正体がわからなかった。
「僕は……おまえが助手だから?相棒だから?……それとも、ただ……」
「――俺は」
律が一歩、柚瑠に近づいた。その目には、もう迷いがなかった。
「俺は、柚瑠さんのことを、“好き”って意味で好きです」
柚瑠の息が止まった。
「助手としてじゃなくて、人として。男として、恋愛感情として。ずっと前から、俺は、柚瑠さんが……」
風が止まり、時間が凍るようだった。
「……わかんないんだよ」
柚瑠の声が小さく漏れる。
「僕の“必要”って気持ちが、おまえの言う“好き”と同じなのか、まだ……」
「それで、いいです」
律の声は静かだった。
「気づいてもらえただけで、今日は十分です」
その声に、柚瑠は目を伏せたまま、ぎゅっと拳を握りしめた。
“律を、失いたくない”――その気持ちだけは、確かだった。
---
夜の風が、ふたりの間をそっとすり抜ける。
律の告白を受けてから、柚瑠は一言も発していなかった。沈黙を破ったのは、意外にも律のほうだった。
「すみません……俺、勝手でしたよね」
「……バカ」
柚瑠がぽつりと呟いた。
「謝るくらいなら、言うなよ。そんな顔して、謝るなよ」
「……はい」
律が苦笑し、目を伏せる。その横顔を見て、柚瑠は心の奥底がかき乱されるような感覚に襲われていた。
助手としての信頼。戦友としての絆。そして、それを超える感情。
「……正直、まだ答えは出せない」
やっとの思いで口を開く。
「だけど、律がいなくなるって想像したら、息ができないくらい苦しくなった。それは、嘘じゃない」
律が目を上げる。柚瑠の言葉を、ひとつ残らず受け止めるように、まっすぐに。
「だったら、俺は待ちます。何年でも、何回でも、柚瑠さんの隣に立ち続けて……“好き”を証明してみせます」
「……めんどくせえな、おまえは」
柚瑠は、ようやく少しだけ口元を緩めた。
「でも……そばにいろ。今だけじゃねぇ。これからも、ずっと」
その言葉に、律の瞳が震える。
「はい」
「助手として――って、今は言っとく」
「はい。……でも、いつかそれが“恋人として”に変わることを願って、俺はそばにいます」
柚瑠は、何も返さなかった。
けれど、隣に並んで歩き出したその歩幅は、さっきより確かに近づいていた。
沈黙の中に芽生えた感情の輪郭は、まだぼやけていた。
それでも――それはたしかに、恋のはじまりだった。
---
「わあ……すっごい、人」
ライトアップされた城跡公園は、まさに秋の見頃。燃えるような赤や黄の紅葉が夜のとばりに照らされ、どこか現実離れした空間をつくっていた。
境内跡に沿って続く石畳の小道には、出店の屋台と観光客がずらりと並んでいる。
「おい黒川、あれ! 焼きだんご! 食っていこうぜ!」
「……因幡先生。除霊前なので、まず状況確認を優先していただけると……」
「なーに言ってんだよ、どうせ対象は深夜にしか出ないって言ってたじゃん? ちょっとくらい楽しんでもバチ当たんねーよ。な?」
「たしかに、報告では深夜帯限定の霊出没。今のうちに腹ごしらえしておくのも、合理的判断ですね」
横から律が口を挟んでくる。
「というわけで、律。僕はあれ食いたい。たい焼き」
「……はいはい、結局食べたいだけですね」
そしてその数分後――。
「うめぇぇ……あっ、因幡、次たこ焼きいこうぜ」
「いや、俺は唐揚げ。いや、串焼きも捨てがたいな……」
「ちょっと、君たち本当に仕事のつもりで来てる?」
「ああ? 腹が減ってはなんとやら、ってやつだろ。な、柚瑠」
「まったくだ。食わずして霊と向き合うとか正気の沙汰じゃない」
「「どっちが大食いか決着つけてやるよ!!!」」
ふたりの大人たちが、火花を散らしてコロッケと焼きそばに挑む横で、助手ふたりはほぼ無表情だった。
「……このふたり、似てますね」
「……ほんと、それな。胃袋だけでなくてテンションの上がり方も一緒だよ」
黒川と律はそれぞれのパートナーに紙ナプキンを差し出しながら、なんとも言えない溜め息をついた。
---
食い倒れの宴が一段落し、人混みの熱が落ち着く頃――。
一同は、城跡の裏手、観光客の流れから少し外れた川沿いの小道にいた。
風の音が紅葉を揺らし、時折、すすり泣くような声が混ざる。
「ここだな。霊が出るのは」
因幡が低く呟き、文庫本を開いた。
「どうやら、城落ちの夜、愛しい人を残して命を絶った侍女の霊らしいな……その執着が、時折現世を彷徨うらしい」
「愛と未練、か。因幡、朗読に入れ」
柚瑠は小さく印を切りながら、川沿いの空気を結界で満たしていく。
「よし、いくぞ。……“白銀の指が私の喉元をなぞった瞬間、私はただ快楽に喘ぐだけの存在になっていた……”」
柚瑠と律が同時に顔をしかめる。
「またそれか……!」
「毎度のことだけど、なんで除霊で官能朗読なんだろう……」
夜気がふるえた瞬間、木の陰から、朧げな人影が姿を現す。
泣き濡れた瞳、裾のほどけた白無垢。
怨念というより、深い悲しみがその身にまとわりついていた。
「うわっ……出た」
「大丈夫、こっち来るぞ。因幡、もう一段階感情込めて!」
> 「“彼の舌先が私の耳の奥まで届いた瞬間、すべてが崩壊して……”」
呻きとともに、霊の輪郭がふるえる。
柚瑠がすかさず最後の結界を仕上げると、霊はすっと涙を残して、紅葉の風に溶けていった。
ふわりと舞った一枚の紅葉が、因幡の足元に落ちる。
「……やれやれ。やっぱこのスタイル、間違ってねぇな」
「俺には間違ってるようにしか思えないんですが……」
黒川はため息をつきながら、因幡に上着を掛けた。風が冷たくなっていた。
一方その隣では、柚瑠がふいに言った。
「なぁ律。次のイベント飯、なにがあったっけ?」
「……もう、除霊が終わって安心した瞬間にこれなんだから……」
ふたりのコンビが静かに笑い合い、帰り道へと歩き出す。
紅葉の名残と、過ぎた怨念と。
そして、少しずつ育ち始めた4人の関係だけが、秋の城跡に静かに残されていた――。
---
除霊から戻ったあとの、深夜の静かな時間。
黒川のアパートの部屋は灯りを落とし、間接照明だけがほのかに空間を照らしていた。
「はぁ……今日はさすがに、疲れましたね」
ソファに深く腰を沈めた黒川が、小さく伸びをした。
すでにシャワーは浴び終えていて、ゆるく乾かした髪からは微かに柑橘系の香りが漂っていた。
部屋着のパーカーの袖を無意識にいじる手つきが、今日のことを反芻している証拠だった。
「まあな。……あの亡霊の最後のひとこと、気になるな」
キッチンからマグカップを2つ持ってきた因幡が、黒川の隣に腰を下ろす。
差し出されたカップには、薄く淹れたカモミールティー。
眠る前の静けさが、ふたりを自然に寄り添わせていた。
「“来世でまた、会えますように”――でしたね」
黒川が、ぽつりと呟く。
それは亡霊が光へ還る直前、消え入りそうな声でこぼした願いだった。
「愛してた人に再び会えるように、か。執着じゃなく、願いとして残ったんだな。……おまえは、信じるか? 来世とか、運命とか」
因幡がマグを片手に、ふと横目で黒川を見やった。
黒川は、答えに少しだけ間を置いた。
そして、柔らかく笑ってこう返す。
「……誰かを強く想う気持ちが、何かを超えることがあるなら。信じたいです。叶わなくても、願っていたい……って思うくらい、大切な人がいるなら」
その横顔には、熱も告白もない。ただ、少しだけ切なさを孕んだ穏やかな静けさがある。
だけど因幡は、その言葉の向かう先を、薄々気付いていた。
(……俺のことか?)
気付かないふり。
ずっとしてきた。
黒川が、誰よりも自分の言葉を信じ、支えてくれていること。
傍にいる理由が、ただの“助手”ではないこと――。
それを、ずっとわかっていながら、気付かないふりをしていた。
でも。
「……黒川」
「はい?」
因幡は何気ないような顔で、黒川の頭をぽんと撫でた。
唐突で、あまりにも優しくて、黒川の瞳が揺れる。
「……あんまり、そういう顔すんな。夜だし、変な気起こすだろ」
「……!」
赤くなる耳を隠すように、黒川はマグカップを持ち直した。
笑ってごまかすのは得意だったはずなのに、今夜はちょっと無理だった。
「すみません。気をつけます」
「いや、……気にすんな。おまえのそういうとこ、俺は……」
言いかけて、因幡は言葉を切った。
(好きだよ。……とか、今さら言えるかよ)
そんな自分に小さく舌打ちしながら、マグカップに口をつける。
静けさが戻る。
けれど、それはどこか心地いい緊張を孕んだ沈黙だった。
部屋の窓の外では、夜風が赤く色づいた葉を揺らしていた。
---
夜中。
窓の外では風が紅葉を揺らし、さらさらと乾いた音を立てていた。
その音の中に、かすかな声が混じった。
「やだ……いかないで、柚瑠さん……っ……」
寝返りを打った布団の中で、律は眉を寄せ、小さく震えていた。
夢のなかで何かにすがるように、誰かの名前を呼んでいる。
――柚瑠が、遠ざかっていく。
何も言わず、ただ背を向けて歩いていく。
呼んでも、手を伸ばしても、届かない。
胸を裂くような喪失感だけが、律の中に残った。
「――っ……!!」
びくん、と身体を起こして、律は夢から飛び起きた。
視界がにじんで、呼吸がうまくできない。
何が現実で、何が夢だったのか、その境目が曖昧なまま、目から涙が溢れ続けた。
「律……?」
低く優しい声が、すぐ横から聞こえた。
柚瑠だった。
隣の布団に背中合わせに寝ていた彼が、律の異変に気付いて目を覚ましていた。
「どうした、苦しい夢?」
律は何も答えられず、ただ小さく頷いた。
こぼれ落ちた涙が、シーツに滲んでいく。
柚瑠はそっと起き上がると、律の背中に腕をまわして、その身体を抱き寄せた。
「大丈夫。……僕はここにいる」
律の額が、柚瑠の胸元に触れる。
そのぬくもりに、律はようやく少しだけ呼吸を取り戻す。
「……夢の中で、柚瑠さんが、俺のこと嫌いになって、……どこかに行ってしまって……呼んでも、追いかけても、何にも届かなくて……」
震える声でこぼす律に、柚瑠は何も言わず、ただ優しく背を撫でた。
まるで小さな子どもをあやすような仕草だった。
「律。よく聞いて」
柚瑠は少しだけ体を離し、律の頬に手を添えて、まっすぐ目を見る。
「僕は、おまえが泣くほど不安になるような、そんな夢に負けないくらい、ちゃんとここにいる。……おまえを嫌いになるなんて、ありえない。おまえは、僕にとってただの助手じゃない。大事な存在だ」
律の唇がわなないた。
喉の奥から、嗚咽がこぼれそうになったその瞬間、柚瑠がもう一度、強く抱きしめる。
「……僕は、どこにも行かない。律、おまえの傍にいるよ。これからもずっと」
その言葉に、律の手がゆっくりと柚瑠の背に回った。
ぬくもりにすがるように、静かに、でもしっかりと。
「……柚瑠さん、……ありがとうございます」
涙のにじんだ声に、柚瑠は「バカ」とだけ囁いて、律の髪を撫でた。
夜の風が、ふたりのいる部屋の外を通り過ぎていく。
けれど、ここにはもう何の不安もなかった。
寄り添う温もりと、互いを求める想いだけが、確かにそこにあった。
---
夜が明け始める頃、律はようやくうとうととした浅い眠りに落ちていた。
窓のカーテンの隙間から、やわらかな朝の光が差し込んでいる。
部屋の空気はしんと静かで、聞こえるのは鳥のさえずりと、隣にいる誰かの穏やかな呼吸。
律は薄く目を開けた。
まぶたの裏にまだ残っていた夢の影は、今ではもうどこにもなかった。
隣にいる柚瑠の腕の中で目覚めた朝――
それは信じられないほど、あたたかくて、安心できる空間だった。
「……起きてたのか?」
不意に、低い声が頭の上から落ちてくる。
「っ……柚瑠さん、起こしちゃいましたか?」
「ん。目が覚めたら、おまえが俺の腕を掴んで離してくれなかっただけだ。寝苦しいかと思ったけど……まぁ、悪くなかった」
小さな冗談めいた言い回しに、律は頬を赤らめた。
昨夜の夢のことを思い出して胸がちくりと痛むけれど、柚瑠のぬくもりはそれをそっと包み込んでくれる。
「……あの、昨日は……すみませんでした。変な夢で取り乱して……」
「謝るなよ、律。怖い夢くらい見るもんだ。誰だって」
そう言って、柚瑠はゆっくり起き上がり、寝癖のついた髪を指先で整えながら、カップを手に取る。
「……コーヒー、淹れるけど飲むか?」
「はい、ぜひ……」
律もゆっくりと身体を起こした。
すぐ隣にある日常。
その中に柚瑠がいて、笑っていて、名前を呼んでくれている。
それだけで、律の胸の奥がじんわりとあたたまる。
小さなテーブルで、柚瑠が差し出したカップを受け取る。
そこに注がれた黒い液体は、ほんのり香ばしくて、鼻をくすぐった。
「甘くしてる。おまえ、苦いのダメだろ」
「……ありがとうございます」
さりげない気遣いに、律の心はまた少しだけ強くなれた気がした。
一口飲むと、ちょうどいい甘さと温度に、思わず頬がゆるむ。
「……なんか、こういう朝って、すごく……幸せですね」
ぽつりと漏れた律の言葉に、柚瑠は一瞬カップを口に運ぶ手を止めた。
だが、それをすぐに誤魔化すようにふっと笑う。
「何だそれ。夢見が悪かったやつの台詞には聞こえねえな」
「ふふっ……」
ふたりは顔を見合わせて笑った。
照れ隠しと、安堵と、静かな喜びがそこに混ざっていた。
昨日の夢はもう過去。
この朝は、確かな“今”として、ふたりの心に刻まれていく。
小さな朝のテーブルに、寄り添うふたりの距離が、昨日よりも少しだけ近くなっていた。
0
あなたにおすすめの小説
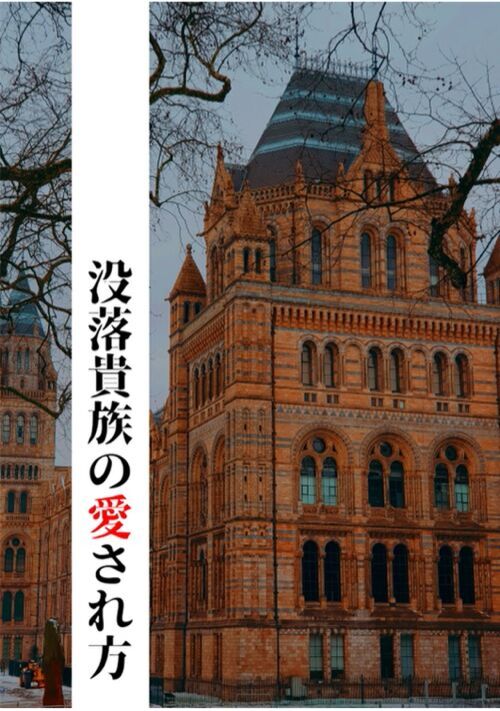
没落貴族の愛され方
シオ
BL
魔法が衰退し、科学技術が躍進を続ける現代に似た世界観です。没落貴族のセナが、勝ち組貴族のラーフに溺愛されつつも、それに気付かない物語です。
※攻めの女性との絡みが一話のみあります。苦手な方はご注意ください。


【完結】極貧イケメン学生は体を売らない。【番外編あります】
紫紺
BL
貧乏学生をスパダリが救済!?代償は『恋人のフリ』だった。
相模原涼(さがみはらりょう)は法学部の大学2年生。
超がつく貧乏学生なのに、突然居酒屋のバイトをクビになってしまった。
失意に沈む涼の前に現れたのは、ブランドスーツに身を包んだイケメン、大手法律事務所の副所長 城南晄矢(じょうなんみつや)。
彼は涼にバイトしないかと誘うのだが……。
※番外編を公開しました(2024.10.21)
生活に追われて恋とは無縁の極貧イケメンの涼と、何もかもに恵まれた晄矢のラブコメBL。二人の気持ちはどっちに向いていくのか。
※本作品中の公判、判例、事件等は全て架空のものです。完全なフィクションであり、参考にした事件等もございません。拙い表現や現実との乖離はどうぞご容赦ください。

【完結】※セーブポイントに入って一汁三菜の夕飯を頂いた勇者くんは体力が全回復します。
きのこいもむし
BL
ある日突然セーブポイントになってしまった自宅のクローゼットからダンジョン攻略中の勇者くんが出てきたので、一汁三菜の夕飯を作って一緒に食べようねみたいなお料理BLです。
自炊に目覚めた独身フリーターのアラサー男子(27)が、セーブポイントの中に入ると体力が全回復するタイプの勇者くん(19)を餌付けしてそれを肴に旨い酒を飲むだけの逆異世界転移もの。
食いしん坊わんこのローグライク系勇者×料理好きのセーブポイント系平凡受けの超ほんわかした感じの話です。

仮面の王子と優雅な従者
emanon
BL
国土は小さいながらも豊かな国、ライデン王国。
平和なこの国の第一王子は、人前に出る時は必ず仮面を付けている。
おまけに病弱で無能、醜男と専らの噂だ。
しかしそれは世を忍ぶ仮の姿だった──。
これは仮面の王子とその従者が暗躍する物語。

宵にまぎれて兎は回る
宇土為名
BL
高校3年の春、同級生の名取に告白した冬だったが名取にはあっさりと冗談だったことにされてしまう。それを否定することもなく卒業し手以来、冬は親友だった名取とは距離を置こうと一度も連絡を取らなかった。そして8年後、勤めている会社の取引先で転勤してきた名取と8年ぶりに再会を果たす。再会してすぐ名取は自身の結婚式に出席してくれと冬に頼んできた。はじめは断るつもりだった冬だが、名取の願いには弱く結局引き受けてしまう。そして式当日、幸せに溢れた雰囲気に疲れてしまった冬は式場の中庭で避難するように休憩した。いまだに思いを断ち切れていない自分の情けなさを反省していると、そこで別の式に出席している男と出会い…

悪役令嬢の兄でしたが、追放後は参謀として騎士たちに囲まれています。- 第3巻 - 甘美な檻と蹂躙の獣
大の字だい
BL
失われかけた家名を再び背負い、王都に戻った参謀レイモンド。
軍務と政務に才知を振るう彼の傍らで、二人の騎士――冷徹な支配で従わせようとする副団長ヴィンセントと、嗜虐的な激情で乱そうとする隊長アルベリック――は、互いに牙を剥きながら彼を奪い合う。
支配か、激情か。安堵と愉悦の狭間で揺らぐ心と身体は、熱に縛られ、疼きに飲まれていく。
恋か、依存か、それとも破滅か――。
三者の欲望が交錯する先に、レイモンドが見出すものとは。
第3幕。
それぞれが、それぞれに。

血のつながらない弟に誘惑されてしまいました。【完結】
まつも☆きらら
BL
突然できたかわいい弟。素直でおとなしくてすぐに仲良くなったけれど、むじゃきなその弟には実は人には言えない秘密があった。ある夜、俺のベッドに潜り込んできた弟は信じられない告白をする。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















