8 / 27
8.
しおりを挟む
ロアンヌは、新婚旅行での最初の逗留ちであるクロイセンで、父公爵にロバートからロミオメールが届いていることについて相談する。
「なに!?それは、本当か?」
「これがそうなのですけど、最初に来たときは、出産した日の朝で、この手紙を見た途端、陣痛が起きてしまって、一時はどうなることかと思いましたわ」
「なんだ子供じみた内容の手紙だな。でも、出産前に見せられたら、気になって王子も早く出てきたいと思ったんだろうね」
「で、次に来たのがコレで、気持ち悪くて鳥肌が立ってしまいましたわ」
「とてもロバートの奴が欠けるような文面ではないな。それによく、こんな気持ち悪い文章を思いつくものだな。ロロ……愛しているよ。げー!気持ち悪い!それだけでもたいがいにしろというのに、今すぐ王家を出ろ?などとバカげたことをほざきやがって。何様になったつもりだ!だいたい、ロロというのは、ロバートが舌足らずでうまく発音できなかったから、付いたあだ名だというのに……、ん?待てよ?」
「お父様、どうかなさったの?」
「いや、……関係ないと思うのだが、もう一人ロアンヌのことをロロ呼びしていた奴がいたなぁと思い出してさ」
「えっえー!それは、一体どなたのことでございましょうか?わたくしには、まるっきり記憶が抜け落ちていて……」
「そうかもしれんな。あれはロアンヌが3歳の頃か、……いや、それよりももっと小さいときのことだったか?王都のタウンハウスの向かい側に住んでいたモントリオール伯爵家の姉弟がおってな。その兄弟がロアンヌのことをロロ呼びしていたということを思い出したんだよ」
「お父様、その話を詳しく教えていただけますか?リチャード様と一緒にもう一度、最初からお聞かせ願いたいのです」
ロアンヌは、急き立てるようにリチャードに事の仔細を言い、今一度、父の話を一緒に聞いてくれるように頼みこむ。
リチャードもその話に興味を示し、二人でじっくりと話を聞くことに同意する。
「モントリオール家は当時、大きな商会を経営していたのだが、仕入れた商品のうちに密輸の疑いをかけられたことがあり、伯爵様は、逮捕され、拷問をされた挙句、獄中で亡くなってしまわれたのだ。伯爵夫人は、何度も「主人は無実です」と訴えられたのだが、お聞き届けにならず。それどころか、国家反逆罪の汚名を着せられ、伯爵夫人も投獄されたばかりか、やはり獄中で亡くなられてしまった。毒殺されたという噂もあったが、真偽のほどはわからずじまいで。それで商会ごと、お取りつぶしの憂き目に遭って、とうとう一家離散してしまったそうだ。幼い姉弟は、遠縁に当たる者に引き取られていったと聞いたよ」
「その姉弟の行方を知っている者はおらぬのか?」
「王城の記録に残っているのではございませんか?仮にも伯爵家の一族が遠縁に引き取られたとしても、まったく素性が知れないもののところへは引き取れませんでしょうに」
「名前は覚えておらぬか?」
「えっと、確か姉の方はカトリーヌとか申したように記憶して、弟は、なんという名前でしたでしょうか……、少しお待ちを……」
父は、裏庭で作業をしていた執事を連れてくる。
「旦那様、お呼びでございましょうか?」
「うむ。今から16、7年ぐらい前になろうか。王都のタウンハウスの向かい側に遭ったモントリオール商会のことを覚えているだろうか?」
「ええ。ええ。よく、覚えておりますとも、家内は、あそこの日傘を大層、気に入りまして、日傘はモントリオールのものでないと承知してくれませんでした」
「それでは、当時、あの店の主人の子供の名前はどうであったか?姉の方は、カトリーヌだったと思うのだが……、弟の方の名前が思い出せなくてな」
「ああ、あの目がクリクリしていた可愛らしい坊ちゃんのことですな、あの子は確か、私の甥っ子と同じ名前だったもので、ジョーンズと申しましたよ。ロアンヌお嬢様よりひとつばかり年上で、ええ。ええ。よく覚えておりますとも」
「そうか。なら、あの姉弟がどこの親類に預けられたか存じておるか?」
「いやぁ、そこまでは……、ですが、当時の執事と今でも、連絡を取り合っておりますので、ひょっとすれば、セバスチャンが何か覚えておいでかもしれません。ああ、でも、確か、オセアニアへ行くと言っていたような気がします」
「そうか。ご苦労、よく思い出してくれた。礼を言うぞ」
「いえいえ、滅相もございません。お役に立てて幸甚でございます」
「お聞きの通りでございます。殿下は、モントリオールの姉弟がこの妙な手紙を書いたと思われるのでございますか?」
「いや、そこまではまだ……、でも同期としては十分すぎるぐらいあるだろう?」
「親と家を失った恨みでございますか?」
「うん。それもあるな。それに17年前の事件の真相も今一度、洗い直さなければならないと思っている。早速、手配しよう」
リチャードは、羊紙にサラサラと17年前のことをしたため、それを使いの者に渡す。
「必ず、この手紙を父上と宰相に見せるのだ。頼んだぞ」
「御意」
久しぶりの領地の風は、新婚の二人の頬を優しく撫で、少しだけ心が軽くなったような気がした。
「なに!?それは、本当か?」
「これがそうなのですけど、最初に来たときは、出産した日の朝で、この手紙を見た途端、陣痛が起きてしまって、一時はどうなることかと思いましたわ」
「なんだ子供じみた内容の手紙だな。でも、出産前に見せられたら、気になって王子も早く出てきたいと思ったんだろうね」
「で、次に来たのがコレで、気持ち悪くて鳥肌が立ってしまいましたわ」
「とてもロバートの奴が欠けるような文面ではないな。それによく、こんな気持ち悪い文章を思いつくものだな。ロロ……愛しているよ。げー!気持ち悪い!それだけでもたいがいにしろというのに、今すぐ王家を出ろ?などとバカげたことをほざきやがって。何様になったつもりだ!だいたい、ロロというのは、ロバートが舌足らずでうまく発音できなかったから、付いたあだ名だというのに……、ん?待てよ?」
「お父様、どうかなさったの?」
「いや、……関係ないと思うのだが、もう一人ロアンヌのことをロロ呼びしていた奴がいたなぁと思い出してさ」
「えっえー!それは、一体どなたのことでございましょうか?わたくしには、まるっきり記憶が抜け落ちていて……」
「そうかもしれんな。あれはロアンヌが3歳の頃か、……いや、それよりももっと小さいときのことだったか?王都のタウンハウスの向かい側に住んでいたモントリオール伯爵家の姉弟がおってな。その兄弟がロアンヌのことをロロ呼びしていたということを思い出したんだよ」
「お父様、その話を詳しく教えていただけますか?リチャード様と一緒にもう一度、最初からお聞かせ願いたいのです」
ロアンヌは、急き立てるようにリチャードに事の仔細を言い、今一度、父の話を一緒に聞いてくれるように頼みこむ。
リチャードもその話に興味を示し、二人でじっくりと話を聞くことに同意する。
「モントリオール家は当時、大きな商会を経営していたのだが、仕入れた商品のうちに密輸の疑いをかけられたことがあり、伯爵様は、逮捕され、拷問をされた挙句、獄中で亡くなってしまわれたのだ。伯爵夫人は、何度も「主人は無実です」と訴えられたのだが、お聞き届けにならず。それどころか、国家反逆罪の汚名を着せられ、伯爵夫人も投獄されたばかりか、やはり獄中で亡くなられてしまった。毒殺されたという噂もあったが、真偽のほどはわからずじまいで。それで商会ごと、お取りつぶしの憂き目に遭って、とうとう一家離散してしまったそうだ。幼い姉弟は、遠縁に当たる者に引き取られていったと聞いたよ」
「その姉弟の行方を知っている者はおらぬのか?」
「王城の記録に残っているのではございませんか?仮にも伯爵家の一族が遠縁に引き取られたとしても、まったく素性が知れないもののところへは引き取れませんでしょうに」
「名前は覚えておらぬか?」
「えっと、確か姉の方はカトリーヌとか申したように記憶して、弟は、なんという名前でしたでしょうか……、少しお待ちを……」
父は、裏庭で作業をしていた執事を連れてくる。
「旦那様、お呼びでございましょうか?」
「うむ。今から16、7年ぐらい前になろうか。王都のタウンハウスの向かい側に遭ったモントリオール商会のことを覚えているだろうか?」
「ええ。ええ。よく、覚えておりますとも、家内は、あそこの日傘を大層、気に入りまして、日傘はモントリオールのものでないと承知してくれませんでした」
「それでは、当時、あの店の主人の子供の名前はどうであったか?姉の方は、カトリーヌだったと思うのだが……、弟の方の名前が思い出せなくてな」
「ああ、あの目がクリクリしていた可愛らしい坊ちゃんのことですな、あの子は確か、私の甥っ子と同じ名前だったもので、ジョーンズと申しましたよ。ロアンヌお嬢様よりひとつばかり年上で、ええ。ええ。よく覚えておりますとも」
「そうか。なら、あの姉弟がどこの親類に預けられたか存じておるか?」
「いやぁ、そこまでは……、ですが、当時の執事と今でも、連絡を取り合っておりますので、ひょっとすれば、セバスチャンが何か覚えておいでかもしれません。ああ、でも、確か、オセアニアへ行くと言っていたような気がします」
「そうか。ご苦労、よく思い出してくれた。礼を言うぞ」
「いえいえ、滅相もございません。お役に立てて幸甚でございます」
「お聞きの通りでございます。殿下は、モントリオールの姉弟がこの妙な手紙を書いたと思われるのでございますか?」
「いや、そこまではまだ……、でも同期としては十分すぎるぐらいあるだろう?」
「親と家を失った恨みでございますか?」
「うん。それもあるな。それに17年前の事件の真相も今一度、洗い直さなければならないと思っている。早速、手配しよう」
リチャードは、羊紙にサラサラと17年前のことをしたため、それを使いの者に渡す。
「必ず、この手紙を父上と宰相に見せるのだ。頼んだぞ」
「御意」
久しぶりの領地の風は、新婚の二人の頬を優しく撫で、少しだけ心が軽くなったような気がした。
10
あなたにおすすめの小説


さようならの定型文~身勝手なあなたへ
宵森みなと
恋愛
「好きな女がいる。君とは“白い結婚”を——」
――それは、夢にまで見た結婚式の初夜。
額に誓いのキスを受けた“その夜”、彼はそう言った。
涙すら出なかった。
なぜなら私は、その直前に“前世の記憶”を思い出したから。
……よりによって、元・男の人生を。
夫には白い結婚宣言、恋も砕け、初夜で絶望と救済で、目覚めたのは皮肉にも、“現実”と“前世”の自分だった。
「さようなら」
だって、もう誰かに振り回されるなんて嫌。
慰謝料もらって悠々自適なシングルライフ。
別居、自立して、左団扇の人生送ってみせますわ。
だけど元・夫も、従兄も、世間も――私を放ってはくれないみたい?
「……何それ、私の人生、まだ波乱あるの?」
はい、あります。盛りだくさんで。
元・男、今・女。
“白い結婚からの離縁”から始まる、人生劇場ここに開幕。
-----『白い結婚の行方』シリーズ -----
『白い結婚の行方』の物語が始まる、前のお話です。
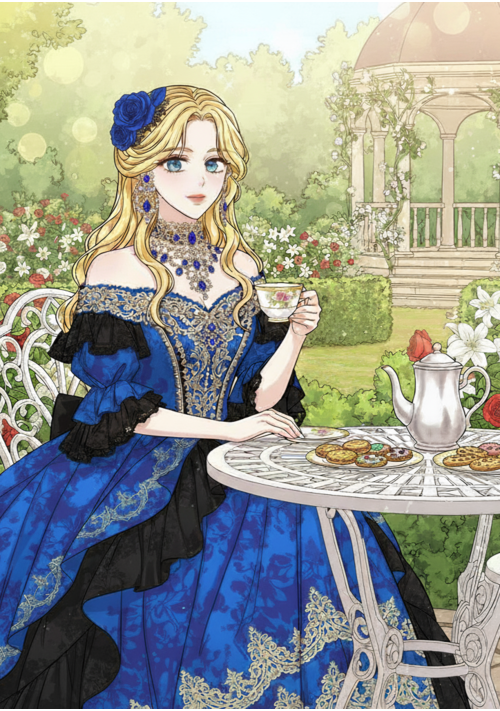
あなた方の愛が「真実の愛」だと、証明してください
こじまき
恋愛
【全3話】公爵令嬢ツェツィーリアは、婚約者である公爵令息レオポルドから「真実の愛を見つけたから婚約破棄してほしい」と言われてしまう。「そう言われては、私は身を引くしかありませんわね。ただし最低限の礼儀として、あなた方の愛が本当に真実の愛だと証明していただけますか?」

悪役令嬢は殿下の素顔がお好き
香澄京耶
恋愛
王太子の婚約者アメリアは、 公衆の場で婚約破棄される夢を見たことをきっかけに、自ら婚約解消を申し出る。
だが追い詰められた王太子、ギルバートは弱さと本心を曝け出してしまい――。
悪役令嬢と、素直になれない王太子の“逆転”ラブコメディ。

泣きたいくらい幸せよ アインリヒside
仏白目
恋愛
泣きたいくらい幸せよ アインリヒside
婚約者の妹、彼女に初めて会った日は季節外れの雪の降る寒い日だった
国と国の繋がりを作る為に、前王の私の父が結んだ婚約、その父が2年前に崩御して今では私が国王になっている
その婚約者が、私に会いに我が国にやってくる
*作者ご都合主義の世界観でのフィクションです

行き場を失った恋の終わらせ方
当麻月菜
恋愛
「君との婚約を白紙に戻してほしい」
自分の全てだったアイザックから別れを切り出されたエステルは、どうしてもこの恋を終わらすことができなかった。
避け続ける彼を求めて、復縁を願って、あの日聞けなかった答えを得るために、エステルは王城の夜会に出席する。
しかしやっと再会できた、そこには見たくない現実が待っていて……
恋の終わりを見届ける貴族青年と、行き場を失った恋の中をさ迷う令嬢の終わりと始まりの物語。
※他のサイトにも重複投稿しています。

断る――――前にもそう言ったはずだ
鈴宮(すずみや)
恋愛
「寝室を分けませんか?」
結婚して三年。王太子エルネストと妃モニカの間にはまだ子供が居ない。
周囲からは『そろそろ側妃を』という声が上がっているものの、彼はモニカと寝室を分けることを拒んでいる。
けれど、エルネストはいつだって、モニカにだけ冷たかった。
他の人々に向けられる優しい言葉、笑顔が彼女に向けられることない。
(わたくし以外の女性が妃ならば、エルネスト様はもっと幸せだろうに……)
そんな時、侍女のコゼットが『エルネストから想いを寄せられている』ことをモニカに打ち明ける。
ようやく側妃を娶る気になったのか――――エルネストがコゼットと過ごせるよう、私室で休むことにしたモニカ。
そんな彼女の元に、護衛騎士であるヴィクトルがやってきて――――?

あなたが幸せになるために
月山 歩
恋愛
幼い頃から共に育った二人は、互いに想い合いながらも、王子と平民という越えられない身分の壁に阻まれ、結ばれることは叶わない。
やがて王子の婚姻が目前に迫ると、オーレリアは決意する。
自分の存在が、最愛の人を不貞へと追い込む姿だけは、どうしても見たくなかったから。
彼女は最後に、二人きりで静かな食事の時間を過ごし、王子の前から姿を消した。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















