1 / 4
1
しおりを挟む
『土曜日の夜は空いてるか? クイーンズ・ホールでドビュッシーの公演があるんだけど、一緒にどうかな』
もしこれが気の置けない学友から届いた手紙なら、迷わずYesと返しただろう。ついでに夕食を取ることも提案し、我が家に一泊するよう勧めたはずだ。
あるいは、大学の恩師が自分の娘を誘わせるために送ってきたものなら、やはり同様にYesと書くほかなかっただろう。罪なき淑女に恥をかかせるのは本意ではない。Noを突きつけられるのは男であるべきというのがこの国の主張だ。
しかし、私はYesを躊躇していた。
『──敬意を込めて。エリオット・G・ハーバート』
差出人の姿を思い描くように、冒頭からサインまでを幾度も読み返して、ついにペン先を便箋に下ろす。声をかけてくれたことへの感謝と、その日は姪との先約があって出掛けてしまうという言い訳を添えて──大いに迂遠なNoを綴るために。
「ねえグレイ、あなた本気でビオラの誕生日会に行かないつもり? 叔父さまのためにソナチネを弾きますって手紙に書いてあるのに」
母親の呼び声が手を止めさせた。壁の向こうから手元を覗いていたかのようなタイミングだった。扉は開けず、顔も上げずに、ペン軸で頬を叩きつつ返事をする。
「行かないよ、レティが嫌がるだろうから。彼女、グレイ・バーソロミュー・サヴィルがいくつになっても独り身なのはよからぬ趣味があるせいじゃないかと疑ってる」
「どういうこと?」
「一家に潜む小児性愛者によって、かわいい盛りの我が子が脅かされるかもしれないと警戒してるんだ」
「まあ、やだあの子ったら! ビオラが大事なのはわかるけど、冗談でも言っていいこと悪いことがあるわ。弟をそんなふうに侮辱するのは許しませんとお母さんから伝えておきます。あなただって疚しいことは何もないんでしょう、グレイ?」
「これ以上ないほど清廉潔白さ」
少なくとも、その疑念に関しては。心休まる土曜の夜に、6歳になる姪のご機嫌取りで疲弊せずに済むのはむしろ喜ばしい。
そう。揺るぎなきこの大地を蹴り、わざわざ波立つ海に飛び込むなんて馬鹿な真似はするものではない。けれど海というのは恐ろしくも美しく、時に人を魅了して、抗うすべを奪い去るのだ。
くだらない言葉を紡いでいる間に便箋には大きなインク染みができてしまったので、私はそれを破り捨て、Yesと書くべきかどうか悩むところからやり直す羽目になった。
「何だ、いるじゃないか!」
どうにかこうにか迂遠なNoを送りつけたにもかかわらず、霧雨が灰色の街を濡らす土曜日の夕方、エリオット・ギルバート・ハーバートは満面の笑みとともにサヴィル家の玄関に飛び込んできた。
陽光を吸った金の髪も、地中海の青さが煌めく瞳も、このロンドンには眩しすぎる。閊える喉、騒ぐ胸。気の利かない挨拶を返すのにさえ時間を要した。
「やあ、ハーバート……思ってたより早く解放されたんだよ。君こそ、なぜここに?」
相手はオックスフォードが卒業させることを渋ったほどの優等生だ、手紙の意味が呑み込めなかったわけはない。イレギュラーな事態に賭けて立ち寄ったのか、最初から嘘を見抜いていたか。どちらにせよ、私が彼をその他大勢の人間と同じように遇することができないのは、こうして私の意思に反して真実を突きつけてくるところにも原因がある。
会ってしまえば明白だ。私はこの聡く美しい友人に会いたかった。それゆえに、会うことを避けていたのだ。
腹の内はどうあれ、何も知らない純真な少年のように相好を崩し、ハーバートは額に張りつく前髪を掻き上げてみせる。
「ロンドンでの仕事は済んだものの、ひとりで音楽を聴く気分じゃなかったから、帰る前に確かめにきたんだ。何らかの事情で君が在宅してるかもしれないと期待してね。そしたらどうだ、僕も運がいいらしい。ああ、体調が悪いわけじゃないよな? 寝ていたように見えるが」
「大丈夫。移動の疲れが出て、うたた寝をしてただけだ」
「よかった。着替えられるか? もちろん、君が姪っ子の初々しい演奏の余韻に浸りたいなら無理にとは言わないぜ」
茶目っ気たっぷりに目を光らせる彼に袖を引かれ、なお首を横に振れるほど、私の心は冷徹に出来てはいない。ベルガモットとジャスミンが香る爽やかなコロンも、奥深くに仕舞い込んだYesを引きずり出すには酷く効果的だった。
気品溢れる白皙の青年と並んでも恥ずかしくないよう、寝起きの独身男から身分相応の紳士に変身する時間である。彼の世話を使用人に任せ、私は階上の自室に向かった。
もしこれが気の置けない学友から届いた手紙なら、迷わずYesと返しただろう。ついでに夕食を取ることも提案し、我が家に一泊するよう勧めたはずだ。
あるいは、大学の恩師が自分の娘を誘わせるために送ってきたものなら、やはり同様にYesと書くほかなかっただろう。罪なき淑女に恥をかかせるのは本意ではない。Noを突きつけられるのは男であるべきというのがこの国の主張だ。
しかし、私はYesを躊躇していた。
『──敬意を込めて。エリオット・G・ハーバート』
差出人の姿を思い描くように、冒頭からサインまでを幾度も読み返して、ついにペン先を便箋に下ろす。声をかけてくれたことへの感謝と、その日は姪との先約があって出掛けてしまうという言い訳を添えて──大いに迂遠なNoを綴るために。
「ねえグレイ、あなた本気でビオラの誕生日会に行かないつもり? 叔父さまのためにソナチネを弾きますって手紙に書いてあるのに」
母親の呼び声が手を止めさせた。壁の向こうから手元を覗いていたかのようなタイミングだった。扉は開けず、顔も上げずに、ペン軸で頬を叩きつつ返事をする。
「行かないよ、レティが嫌がるだろうから。彼女、グレイ・バーソロミュー・サヴィルがいくつになっても独り身なのはよからぬ趣味があるせいじゃないかと疑ってる」
「どういうこと?」
「一家に潜む小児性愛者によって、かわいい盛りの我が子が脅かされるかもしれないと警戒してるんだ」
「まあ、やだあの子ったら! ビオラが大事なのはわかるけど、冗談でも言っていいこと悪いことがあるわ。弟をそんなふうに侮辱するのは許しませんとお母さんから伝えておきます。あなただって疚しいことは何もないんでしょう、グレイ?」
「これ以上ないほど清廉潔白さ」
少なくとも、その疑念に関しては。心休まる土曜の夜に、6歳になる姪のご機嫌取りで疲弊せずに済むのはむしろ喜ばしい。
そう。揺るぎなきこの大地を蹴り、わざわざ波立つ海に飛び込むなんて馬鹿な真似はするものではない。けれど海というのは恐ろしくも美しく、時に人を魅了して、抗うすべを奪い去るのだ。
くだらない言葉を紡いでいる間に便箋には大きなインク染みができてしまったので、私はそれを破り捨て、Yesと書くべきかどうか悩むところからやり直す羽目になった。
「何だ、いるじゃないか!」
どうにかこうにか迂遠なNoを送りつけたにもかかわらず、霧雨が灰色の街を濡らす土曜日の夕方、エリオット・ギルバート・ハーバートは満面の笑みとともにサヴィル家の玄関に飛び込んできた。
陽光を吸った金の髪も、地中海の青さが煌めく瞳も、このロンドンには眩しすぎる。閊える喉、騒ぐ胸。気の利かない挨拶を返すのにさえ時間を要した。
「やあ、ハーバート……思ってたより早く解放されたんだよ。君こそ、なぜここに?」
相手はオックスフォードが卒業させることを渋ったほどの優等生だ、手紙の意味が呑み込めなかったわけはない。イレギュラーな事態に賭けて立ち寄ったのか、最初から嘘を見抜いていたか。どちらにせよ、私が彼をその他大勢の人間と同じように遇することができないのは、こうして私の意思に反して真実を突きつけてくるところにも原因がある。
会ってしまえば明白だ。私はこの聡く美しい友人に会いたかった。それゆえに、会うことを避けていたのだ。
腹の内はどうあれ、何も知らない純真な少年のように相好を崩し、ハーバートは額に張りつく前髪を掻き上げてみせる。
「ロンドンでの仕事は済んだものの、ひとりで音楽を聴く気分じゃなかったから、帰る前に確かめにきたんだ。何らかの事情で君が在宅してるかもしれないと期待してね。そしたらどうだ、僕も運がいいらしい。ああ、体調が悪いわけじゃないよな? 寝ていたように見えるが」
「大丈夫。移動の疲れが出て、うたた寝をしてただけだ」
「よかった。着替えられるか? もちろん、君が姪っ子の初々しい演奏の余韻に浸りたいなら無理にとは言わないぜ」
茶目っ気たっぷりに目を光らせる彼に袖を引かれ、なお首を横に振れるほど、私の心は冷徹に出来てはいない。ベルガモットとジャスミンが香る爽やかなコロンも、奥深くに仕舞い込んだYesを引きずり出すには酷く効果的だった。
気品溢れる白皙の青年と並んでも恥ずかしくないよう、寝起きの独身男から身分相応の紳士に変身する時間である。彼の世話を使用人に任せ、私は階上の自室に向かった。
0
あなたにおすすめの小説


勇者様への片思いを拗らせていた僕は勇者様から溺愛される
八朔バニラ
BL
蓮とリアムは共に孤児院育ちの幼馴染。
蓮とリアムは切磋琢磨しながら成長し、リアムは村の勇者として祭り上げられた。
リアムは勇者として村に入ってくる魔物退治をしていたが、だんだんと疲れが見えてきた。
ある日、蓮は何者かに誘拐されてしまい……
スパダリ勇者×ツンデレ陰陽師(忘却の術熟練者)

僕の幸せは
春夏
BL
【完結しました】
【エールいただきました。ありがとうございます】
【たくさんの“いいね”ありがとうございます】
【たくさんの方々に読んでいただけて本当に嬉しいです。ありがとうございます!】
恋人に捨てられた悠の心情。
話は別れから始まります。全編が悠の視点です。

【完】君に届かない声
未希かずは(Miki)
BL
内気で友達の少ない高校生・花森眞琴は、優しくて完璧な幼なじみの長谷川匠海に密かな恋心を抱いていた。
ある日、匠海が誰かを「そばで守りたい」と話すのを耳にした眞琴。匠海の幸せのために身を引こうと、クラスの人気者・和馬に偽の恋人役を頼むが…。
すれ違う高校生二人の不器用な恋のお話です。
執着囲い込み☓健気。ハピエンです。

林檎を並べても、
ロウバイ
BL
―――彼は思い出さない。
二人で過ごした日々を忘れてしまった攻めと、そんな彼の行く先を見守る受けです。
ソウが目を覚ますと、そこは消毒の香りが充満した病室だった。自分の記憶を辿ろうとして、はたり。その手がかりとなる記憶がまったくないことに気付く。そんな時、林檎を片手にカーテンを引いてとある人物が入ってきた。
彼―――トキと名乗るその黒髪の男は、ソウが事故で記憶喪失になったことと、自身がソウの親友であると告げるが…。

何故よりにもよって恋愛ゲームの親友ルートに突入するのか
風
BL
平凡な学生だったはずの俺が転生したのは、恋愛ゲーム世界の“王子”という役割。
……けれど、攻略対象の女の子たちは次々に幸せを見つけて旅立ち、
気づけば残されたのは――幼馴染みであり、忠誠を誓った騎士アレスだけだった。
「僕は、あなたを守ると決めたのです」
いつも優しく、忠実で、完璧すぎるその親友。
けれど次第に、その視線が“友人”のそれではないことに気づき始め――?
身分差? 常識? そんなものは、もうどうでもいい。
“王子”である俺は、彼に恋をした。
だからこそ、全部受け止める。たとえ、世界がどう言おうとも。
これは転生者としての使命を終え、“ただの一人の少年”として生きると決めた王子と、
彼だけを見つめ続けた騎士の、
世界でいちばん優しくて、少しだけ不器用な、じれじれ純愛ファンタジー。

オメガはオメガらしく生きろなんて耐えられない
子犬一 はぁて
BL
「オメガはオメガらしく生きろ」
家を追われオメガ寮で育ったΩは、見合いの席で名家の年上αに身請けされる。
無骨だが優しく、Ωとしてではなく一人の人間として扱ってくれる彼に初めて恋をした。
しかし幸せな日々は突然終わり、二人は別れることになる。
5年後、雪の夜。彼と再会する。
「もう離さない」
再び抱きしめられたら、僕はもうこの人の傍にいることが自分の幸せなんだと気づいた。
彼は温かい手のひらを持つ人だった。
身分差×年上アルファ×溺愛再会BL短編。
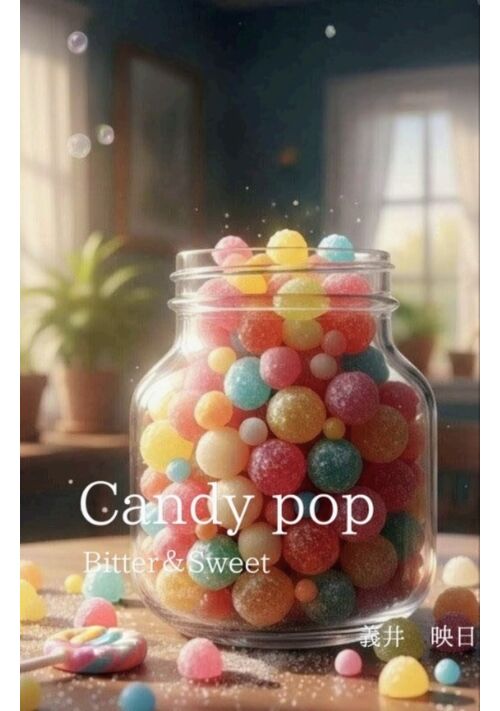
Candy pop〜Bitter&Sweet
義井 映日
BL
「完璧な先輩」が壊れるまで、カウントはもう、とっくに『0』を過ぎていた。
「185cmの看板男」が、たった一人の恋人の前で理性を失う。
三ヶ月の禁欲を経て、その愛は甘く、激しく、暴走する――。
「あらすじ」
大学の「看板男」こと安達大介は、後輩の一之瀬功(こう)を溺愛している。
ついに迎えた初めての夜。しかし、安達の圧倒的な「雄」の迫力に、功は本能的な恐怖で逃げ出してしまう。
「――お前は俺を狂わせる毒だと思ってた」
絶望した安達と、愛しているのに身体が竦む功。
三ヶ月の「じれったい禁欲生活」を経て、看板男の仮面が剥がれるとき、世界で一番甘い夜が始まる。
★本編全6話に加え、季節を巡る濃密な番外編1本も公開中!近日最新エピソードも追加予定!
(2月の看病編/3月のホワイトデー編公開予定です)
お話が気に入った、面白かった、と思ってくださったら、お気に入り登録、いいね、をお願い致します!
作者の励みになります!!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















