1 / 30
黒猫
しおりを挟む
僕は猫が好きだ。
小さい頃は、家で1匹の黒猫を飼っていた。クロと呼んでいたその黒猫は毛並みが良かった。例のごとく親が家にいる時間が短い僕に取って、彼は家族そのもの。
いつも一緒に寝ていた。彼は、サッカーをする時もピアノを弾く時もいっしょだったが、料理を作っている時だけはどこにも見当たらず、餌もほとんど食べない少し不思議な猫だった。
僕が小学4年生の時。彼が死んだ。
僕が、散歩から帰ってきたクロを驚かそうと大きな声を出して玄関から飛び出すと、クロは後ろへと跳んだ。なんの因果かその刹那、1台の車が走ってきてクロをはねた。
おそらく即死だったのだろう。無惨なクロの姿を見て彼が2度と動かなくなることを悟り、視界が暗くなった。
目が覚めると、僕は見覚えのある自分の部屋に横たわっていた。
「あ、目覚めた?ごめんなさい。家、勝手に上がらせてもらったわ。」
僕の横には女の子がいた。長い黒髪がきれいだった。僕より1、2歳年上だろうか、雰囲気と良い話し方といい大人っぽく、優しそう。でも、僕は彼女を拒絶した。
「帰って下さい。一人にしてください。」
「まぁそうなるよね。今日はごめんなさい・・・また来るよ。」
「いえ、悪いのは僕です。もう来なくていいです。迷惑かけてこちらこそすいませんでした。」
それからの僕はなにか抜け殻のようだったのだろう。幼馴染の凛人や結季とも一緒に行動しなくなり、一人でいることを好んだ。後の凛人曰く「目に光が宿ってなかった。」
新しい猫を飼うかと親に聞かれた時は、おそらく人生で1番怒った。彼の代わりになるものなんかなかった。
こんな僕を、あの時の女性は週1、2回見に来ていた。何をするでもなく、ただ横に居るだけ。1時間ほどしたら帰っていく。最初は嫌だった。意味分からなかった。でも、徐々に落ち着いてきて、横に居てもらえることが少し心地よくなってきた。
そして、あの事故から、3ヶ月ほどたった頃。
彼女が久しぶりに口を開いた。
「泣いてもいいんだよ。偉そうかもしれないけど、私にできることはこのくらいだから。」
そう言って抱きしめてくれた。
名前も知らない人。それでも、長らく触れていなかった、生き物の温もり。涙が自ずと溢れてきた。
「ピアノもサッカーも料理も勉強も全部捨てて考えた。クロはしあわせだったのかなって。クロは僕と居てよかったのかなって。」
泣きじゃくりながら必死に一つ一つの言葉を紡ぎだす。
「クロは幸せだったよ。そして、今も幸せだよ。」
「なんで?」
「だって、自分の死をずっと考えてくれる友達に出会えたんだから。きっと どこかで見守ってくれてる。だからもう泣かないで。クロも悲しむよ。君ができるのは、クロのためにも一生懸命生きる事。」
そんなこと考えた事もなかった。胸の奥から様々な物が溢れ出してきて、涙が止まらない。
「ありがとう。お姉さん。僕頑張る。」
4ヶ月ぶりに笑えた。
僕の顔を見て安心したような顔をするその女性。彼女の目からも涙が零れていた。
「実は、遠いところに引っ越すんだ。だから、引っ越す前に君に元気になってもらいたかった。僕が遠いところにいても、君の名前を聞けるよう、頑張ってね。いつかきっとまた会えるから。約束しよ。」
そう言って帰っていった。結局彼女の消息は絶え、今も何処にいるかは分からない。
は彼女の言葉通り頑張った。ピアノもサッカーも。変化は大きかった。全国大会にも出て、観覧席を必死に見回した覚えもある。それでも、今心の底から笑えているかは分からない。
16歳になった今でも、彼女の温もりは確かに覚えている。
そして、彼女が誰だったのかはわからない。
小さい頃は、家で1匹の黒猫を飼っていた。クロと呼んでいたその黒猫は毛並みが良かった。例のごとく親が家にいる時間が短い僕に取って、彼は家族そのもの。
いつも一緒に寝ていた。彼は、サッカーをする時もピアノを弾く時もいっしょだったが、料理を作っている時だけはどこにも見当たらず、餌もほとんど食べない少し不思議な猫だった。
僕が小学4年生の時。彼が死んだ。
僕が、散歩から帰ってきたクロを驚かそうと大きな声を出して玄関から飛び出すと、クロは後ろへと跳んだ。なんの因果かその刹那、1台の車が走ってきてクロをはねた。
おそらく即死だったのだろう。無惨なクロの姿を見て彼が2度と動かなくなることを悟り、視界が暗くなった。
目が覚めると、僕は見覚えのある自分の部屋に横たわっていた。
「あ、目覚めた?ごめんなさい。家、勝手に上がらせてもらったわ。」
僕の横には女の子がいた。長い黒髪がきれいだった。僕より1、2歳年上だろうか、雰囲気と良い話し方といい大人っぽく、優しそう。でも、僕は彼女を拒絶した。
「帰って下さい。一人にしてください。」
「まぁそうなるよね。今日はごめんなさい・・・また来るよ。」
「いえ、悪いのは僕です。もう来なくていいです。迷惑かけてこちらこそすいませんでした。」
それからの僕はなにか抜け殻のようだったのだろう。幼馴染の凛人や結季とも一緒に行動しなくなり、一人でいることを好んだ。後の凛人曰く「目に光が宿ってなかった。」
新しい猫を飼うかと親に聞かれた時は、おそらく人生で1番怒った。彼の代わりになるものなんかなかった。
こんな僕を、あの時の女性は週1、2回見に来ていた。何をするでもなく、ただ横に居るだけ。1時間ほどしたら帰っていく。最初は嫌だった。意味分からなかった。でも、徐々に落ち着いてきて、横に居てもらえることが少し心地よくなってきた。
そして、あの事故から、3ヶ月ほどたった頃。
彼女が久しぶりに口を開いた。
「泣いてもいいんだよ。偉そうかもしれないけど、私にできることはこのくらいだから。」
そう言って抱きしめてくれた。
名前も知らない人。それでも、長らく触れていなかった、生き物の温もり。涙が自ずと溢れてきた。
「ピアノもサッカーも料理も勉強も全部捨てて考えた。クロはしあわせだったのかなって。クロは僕と居てよかったのかなって。」
泣きじゃくりながら必死に一つ一つの言葉を紡ぎだす。
「クロは幸せだったよ。そして、今も幸せだよ。」
「なんで?」
「だって、自分の死をずっと考えてくれる友達に出会えたんだから。きっと どこかで見守ってくれてる。だからもう泣かないで。クロも悲しむよ。君ができるのは、クロのためにも一生懸命生きる事。」
そんなこと考えた事もなかった。胸の奥から様々な物が溢れ出してきて、涙が止まらない。
「ありがとう。お姉さん。僕頑張る。」
4ヶ月ぶりに笑えた。
僕の顔を見て安心したような顔をするその女性。彼女の目からも涙が零れていた。
「実は、遠いところに引っ越すんだ。だから、引っ越す前に君に元気になってもらいたかった。僕が遠いところにいても、君の名前を聞けるよう、頑張ってね。いつかきっとまた会えるから。約束しよ。」
そう言って帰っていった。結局彼女の消息は絶え、今も何処にいるかは分からない。
は彼女の言葉通り頑張った。ピアノもサッカーも。変化は大きかった。全国大会にも出て、観覧席を必死に見回した覚えもある。それでも、今心の底から笑えているかは分からない。
16歳になった今でも、彼女の温もりは確かに覚えている。
そして、彼女が誰だったのかはわからない。
0
あなたにおすすめの小説
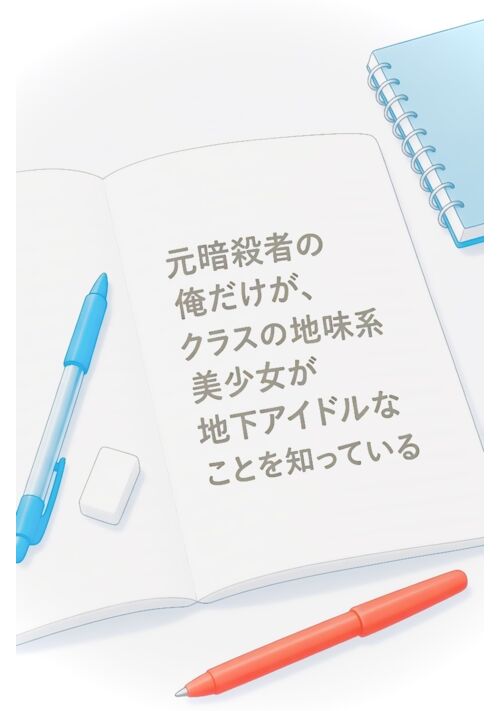
元暗殺者の俺だけが、クラスの地味系美少女が地下アイドルなことを知っている
甘酢ニノ
恋愛
クラス一の美少女・強羅ひまりには、誰にも言えない秘密がある。
実は“売れない地下アイドル”として活動しているのだ。
偶然その正体を知ってしまったのは、無愛想で怖がられがちな同級生・兎山類。
けれど彼は、泣いていたひまりをそっと励ましたことも忘れていて……。
不器用な彼女の願いを胸に、類はひまりの“支え役”になっていく。
真面目で不器用なアイドルと、寡黙だけど優しい少年が紡ぐ、
少し切なくて甘い青春ラブコメ。

商人の男と貴族の女~婚約破棄から始まる成り上がり~
葉月奈津・男
恋愛
「あなたとの婚約、破棄させていただきます!」
王立学院の舞踏会。
全校生徒が見守る中、商家の三男カロスタークは、貴族令嬢セザールから一方的に婚約破棄を突きつけられる。
努力も誠意も、すべて「退屈だった」の一言で切り捨てられ、彼女は王子様気取りの子爵家の三男と新たな婚約を宣言する。
だが、カロスタークは折れなかった。
「商人の子せがれにだって、意地はあるんだ!」
怒りと屈辱を胸に、彼は商人としての才覚を武器に、静かなる反撃を開始する。
舞踏会の翌日、元婚約者の実家に突如として訪れる債権者たち。
差し押さえ、債権買収、そして“後ろ盾”の意味を思い知らせる逆襲劇が幕を開ける!
これは、貴族社会の常識を覆す、ひとりの青年の成り上がりの物語。
誇りを踏みにじられた男が、金と知恵で世界を変える――!

現実とサキュバスのあいだで ――夢で告白した相手が、同居を始めた話
そう
青春
ある日家に突然現れた謎のサキュバスのホルさん!
好感度はMAXなようで流されるがまま主人公はホルさんと日常を過ごします。
ほのぼのラブコメというか日常系小説
オチなどはなく、ただひたすらにまったりします
挿絵や文章にもAIを使用しております。
苦手な方はご注意ください。

むっつり金持ち高校生、巨乳美少女たちに囲まれて学園ハーレム
ピコサイクス
青春
顔は普通、性格も地味。
けれど実は金持ちな高校一年生――俺、朝倉健斗。
学校では埋もれキャラのはずなのに、なぜか周りは巨乳美女ばかり!?
大学生の家庭教師、年上メイド、同級生ギャルに清楚系美少女……。
真面目な御曹司を演じつつ、内心はむっつりスケベ。

俺をフッた幼馴染が、トップアイドルになって「もう一度やり直したい」と言ってきた
夏見ナイ
恋愛
平凡な大学生・藤堂蓮には忘れられない過去がある。高校時代、告白した幼馴染の星宮瑠奈に「アイドルになるから」とこっ酷くフラれたことだ。
数年後、瑠奈は国民的アイドル『LUNA』として輝いていた。遠い世界の住人になった彼女との再会なんて、あるはずもなかった――そう、変装した彼女が俺の前に現れ、「もう一度やり直したい」と泣きつくまでは。
トップアイドルの立場を使い強引に迫る元幼馴染と、過去の傷。揺れ動く俺の日常を照らしてくれたのは、俺の才能を信じてくれる後輩・朝霧陽葵の存在だった。
俺をフッた幼馴染か、俺を支える後輩か。過去の清算と未来の選択を描く、ほろ苦くも甘い、逆転ラブコメディ、開幕。

黒に染まった華を摘む
馬場 蓮実
青春
夏の終わりに転校してきたのは、忘れられない初恋の相手だった——。
高須明希は、人生で“二番目”に好きになった相手——河西栞に密かに想いを寄せている。
「夏休み明けの初日。この席替えで、彼女との距離を縮めたい。話すきっかけがほしい——」
そんな願いを胸に登校したその朝、クラスに一人の転校生がやってくる。
彼女の名は、立石麻美。
昔の面影を残しながらも、まるで別人のような気配をまとう彼女は——明希にとって、忘れられない“初恋の人”だった。
この再会が、静かだった日常に波紋を広げていく。
その日の放課後。
明希は、"性の衝動"に溺れる自身の姿を、麻美に見られてしまう——。
塞がっていた何かが、ゆっくりと崩れはじめる。
そして鬱屈した青春は、想像もしていなかった熱と痛みを帯びて動き出す。
すべてに触れたとき、
明希は何を守り、何を選ぶのか。
光と影が交錯する、“遅れてきた”ひと夏の物語。

SSS級の絶世の超絶美少女達がやたらと俺にだけ見え見えな好意を寄せてくる件について。〜絶対に俺を攻略したいSSS級の美少女たちの攻防戦〜
沢田美
恋愛
「ごめんね、八杉くん」
中学三年の夏祭り。一途な初恋は、花火と共に儚く散った。
それ以来、八杉裕一(やすぎ・ゆういち)は誓った。「高校では恋愛なんて面倒なものとは無縁の、平穏なオタク生活を送る」と。
だが、入学した紫水高校には《楽園の世代》と呼ばれる四人のSSS級美少女――通称《四皇》が君臨していた。
• 距離感バグり気味の金髪幼馴染・神行胱。
• 圧倒的カリスマで「恋の沼」に突き落とす銀髪美少女・銀咲明日香。
• 無自覚に男たちの初恋を奪う、おっとりした「女神」・足立模。
• オタクにも優しい一万年に一人の最高ギャル・川瀬優里。
恋愛から距離を置きたい裕一の願いも虚しく、彼女たちはなぜか彼にだけ、見え見えな好意を寄せ始める。
教室での「あーん」に、放課後のアニメイトでの遭遇、さらには女神からの「一緒にホラー漫画を買いに行かない?」というお誘いまで。
「俺の身にもなれ! 荷が重すぎるんだよ!」
鋼の意志でスルーしようとする裕一だが、彼女たちの純粋で猛烈なアプローチは止まらない。
恋愛拒否気味な少年と、彼を絶対に攻略したい最強美少女たちの、ちょっと面倒で、でも最高に心地よい「激推し」ラブコメ、開幕!

中1でEカップって巨乳だから熱く甘く生きたいと思う真理(マリー)と小説家を目指す男子、光(みつ)のラブな日常物語
jun( ̄▽ ̄)ノ
大衆娯楽
中1でバスト92cmのブラはEカップというマリーと小説家を目指す男子、光の日常ラブ
★作品はマリーの語り、一人称で進行します。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















