10 / 30
10
しおりを挟む
「おおっ! 帰ってきたぞ!」
村の男が、大きな声で叫んだ。
「どうだったんだ、蜂蜜は!?」
村に着くと、私たちの帰りを待っていた村人たちが興奮した様子で駆け寄ってきた。
彼らの視線は、私たちが抱えている大きな壺に釘付けになっている。
「ええ、見てちょうだい。この通りよ」
私はにっこりと微笑み、カイたちと一緒に壺の蓋を開けてみせた。
夕日を浴びて、中の蜂蜜が黄金色にキラキラと輝く。
蜜蝋の塊が浮かんだ、甘く濃厚な香りがふわっと広がった。
「「「うおおおおおおっ!!!」」」
その瞬間、村中に今日一番の地響きのような大歓声が巻き起こった。
村人たちは、信じられないものを見るような目で壺の中を覗き込む。
そして、口々に感動の言葉を叫んでいた。
「すごい……本当に蜂蜜だ!」
「こんなにたくさんの蜂蜜、見たことねえ!」
「リゼット様、本当に採ってきなさったのか……!」
アルフレッドが、感動で胸がいっぱいになった様子で私のそばにやってきた。
その目には、うっすらと涙が浮かんでいる。
「お嬢様、ご無事で……! そして、またしてもこのような奇跡を……!」
「だから、奇跡じゃないのよ、アルフレッド。さあ、みんな、これを村に運びましょう。これから、この宝物をもっと素敵なものに変身させるわ」
私の言葉に、村人たちは再び「おおーっ!」と歓声を上げた。
彼らは、喜んで壺を運ぶのを手伝ってくれた。
広場の中央に壺が置かれると、村人たちはまるで祭りのようにその周りに集まってきた。
特に子供たちは、早く舐めてみたくてうずうずしているようだ。
「さあ、まずはこの蜜を、食べやすいように綺麗にするわよ」
私は、大きな布を広げた。
その上に、蜜蝋ごと蜂蜜を移していく。
そして、その布で蜂蜜を包み込み、上からゆっくりと重石を乗せて圧力をかけた。
「こうすることで、蜜と巣を作っている蝋(ろう)を分けることができるの」
私の説明に、村人たちは興味津々で見守っている。
布の隙間から、とろりとした純粋な蜂蜜だけがゆっくりと染み出してきた。
下の受け皿に、黄金の液体が溜まっていく。
不純物が取り除かれた蜂蜜は、まるで溶かした宝石のように透き通り輝いていた。
「うわあ……綺麗だ……」
誰かが、うっとりと呟いた。
やがて、受け皿がいっぱいになる頃にはすっかり蜜が搾り取られた。
布の中には、白っぽい蝋の塊だけが残る。
「さあ、できたわよ。みんな、指を綺麗にして、少しだけ舐めてみて」
私がそう言うと、待ちかねていた子供たちがわっと受け皿に殺到した。
彼らは、恐る恐る指先に蜂蜜をつけぺろりと舐める。
その瞬間、子供たちの顔がぱあっと輝いた。
「あ……あまい!」
一人の少年が、目を見開いて叫んだ。
「おいしいー!」
今まで味わったことのない、濃厚で花の香りがする甘さ。
その感動的な美味しさに、子供たちは言葉を失う。
ただ、何度も指を舐めていた。
その様子を見ていた大人たちも、次々と蜂蜜を味わい始める。
一人の老婆が、指についた蜜をそっと口に運んだ。
「こ、これは……!」
「なんて甘さだ……天国の味か……」
長年の貧しい生活で、甘いものなど口にする機会がなかった村人たち。
彼らにとって、この蜂蜜の味は衝撃的だった。
あまりの美味しさに、その場に泣き崩れる老婆さえいる。
広場は、幸福なため息と喜びの声で満たされていた。
私も、指についた蜂蜜を舐めてみる。
うん、美味しい。
様々な花の蜜が混ざり合った、複雑で豊かな風味だ。
この土地の自然が、そのまま凝縮されているようだった。
「リゼット様、こっちの塊はどうするんだ?」
カイが、布に残った蜜蝋の塊を指差して尋ねた。
それは、蜂蜜を搾った後の残りかすに見える。
「ふふ、カイ。それはね、もう一つのお楽しみよ。これも、私たちの暮らしを豊かにしてくれる大切な宝物なの」
私はにっこりと笑い、蜜蝋の塊を手に取った。
「この蝋を溶かして、糸を浸して固めればとても明るくて長持ちする『ロウソク』が作れるわ。今みたいに、すぐに燃え尽きてしまう松明よりもずっと便利よ」
私は、ロウソクがもたらす未来を語った。
「すすだらけになる油のランプよりも、クリーンで安全なの」
「ロ、ロウソク……?」
村人たちは、初めて聞く言葉に目を丸くしている。
「ええ、それにこの蝋を布に塗れば水を弾くようになるわ。雨合羽だって作れるかもしれない」
私の説明に、村人たちの驚きはさらに大きくなった。
甘い蜜だけでなく、あの巣の塊にまでそんな使い道があったなんて。
彼らは、想像もしていなかったのだ。
「すげえ……蜂の巣って、捨てるところが一つもねえんだな……」
カイが、心底感心したように呟いた。
自然の中にあるものは、何一つ無駄なものはない。
昔の人は、そうやって自然と共存しその恵みを余すところなく利用してきたのだ。
「さて、それじゃあ、約束通りお菓子を作りましょうか」
私は、搾りたての蜂蜜と先日収穫した『森の恵み』のナッツを用意した。
まず、ナッツを粗く砕き熱した鍋で軽く煎る。
香ばしい匂いが漂い始めると、村人たちがごくりと喉を鳴らした。
食欲をそそる、たまらない香りだ。
次に、別の鍋に蜂蜜を入れ弱火でゆっくりと煮詰めていく。
甘い香りが、さらに濃厚になって広場に満ちていった。
蜂蜜がフツフツと泡立ち、少し色づいてきたところで煎ったナッツを加える。
そして、素早く混ぜ合わせた。
「これを、平らな石板の上に広げて、冷まして固めるのよ」
熱い蜂蜜とナッツを石板に広げると、あっという間に甘い香りの板が出来上がった。
まだ温かいうちに、ナイフで食べやすい大きさに切れ目を入れていく。
私は、このお菓子を『森の恵みの蜂蜜がらめ』と名付けた。
「さあ、出来立てよ。火傷しないように、気をつけて食べてね」
私がそう言うと、またしても子供たちが真っ先に手を伸ばした。
カリカリとしたナッツの食感と、香ばしさ。
そして、凝縮された蜂蜜の濃厚な甘さ。
それは、彼らが今まで食べたどんなものよりも美味しくて、贅沢な味だった。
「おいしい!」
「こんな美味しいお菓子、初めて食べた!」
子供たちの歓声に、大人たちも笑顔になる。
この村に、初めて「おやつ」という文化が生まれた瞬間だった。
人々は、ただお腹を満たすためだけでなく人生を楽しむための食事を初めて知ったのだ。
その日の夜、村では再び宴が開かれた。
もちろん、主役は蜂蜜と蜂蜜で作ったお菓子だ。
そして、私が早速作ってみせた蜜蝋のロウソクが、宴の席を優しく照らしていた。
ロウソクの炎は、松明のようにパチパチと音を立てることもない。
油のランプのように、煙たい匂いを出すこともない。
静かに、そして明るく村人たちの笑顔を照らし出している。
「この灯り……なんだか、心が安らぐなあ」
長老が、ロウソクの炎を見つめながらしみじみと呟いた。
その言葉に、皆が頷く。
穏やかな光は、人々の心を温かく包み込んでいた。
私は、蜂蜜がらめを頬張りながら満ち足りた気持ちでその光景を眺めていた。
家が建ち、水路が通り食料が安定した。
そして、甘いお菓子と穏やかな灯りが生まれた。
この村は、私が来た頃とは比べ物にならないほど豊かになった。
だけど、これで終わりじゃない。
野生の蜂の巣に頼るのではなく、村で蜂を飼う「養蜂」を始めればいい。
そうすれば、もっと安定して蜂蜜が手に入るようになる。
蜂蜜は村の特産品として、他の村や町との交易にも使えるかもしれない。
(交易……か)
もし、外の世界と交易ができるようになればこの村にはないものが手に入る。
例えば、塩。
鉄の道具。
もっと多様な作物の種。
村の可能性は、さらに大きく広がっていくはずだ。
「リゼット様、何を考えてるんだい?」
隣に座っていたカイが、不思議そうな顔で私の顔を覗き込んできた。
「ううん、この村の、これからのことを少しだけね」
私は微笑んで、ロウソクの炎に照らされた彼の顔を見つめた。
「カイ、蜂をね、村で飼うことはできると思う?」
「蜂を……飼う?」
カイは、鳩が豆鉄砲を食ったような顔をしている。
私の頭の中には、もう次の計画がロウソクの灯りのように、はっきりと見え始めていた。
私の突拍子もない提案に、カイはしばらく口をあんぐりと開けていた。
しかし、やがて何かを理解したようにその目に好奇心の光を宿した。
「……あんたが言うなら、できるんだろうな。次は、どうやって蜂を捕まえてくるんだ?」
彼の返事に、私は満足して頷いた。
この村の人々は、もう「できない」とは考えない。
どうすれば「できる」のかを、一緒に考えてくれる仲間になってくれたのだ。
村の男が、大きな声で叫んだ。
「どうだったんだ、蜂蜜は!?」
村に着くと、私たちの帰りを待っていた村人たちが興奮した様子で駆け寄ってきた。
彼らの視線は、私たちが抱えている大きな壺に釘付けになっている。
「ええ、見てちょうだい。この通りよ」
私はにっこりと微笑み、カイたちと一緒に壺の蓋を開けてみせた。
夕日を浴びて、中の蜂蜜が黄金色にキラキラと輝く。
蜜蝋の塊が浮かんだ、甘く濃厚な香りがふわっと広がった。
「「「うおおおおおおっ!!!」」」
その瞬間、村中に今日一番の地響きのような大歓声が巻き起こった。
村人たちは、信じられないものを見るような目で壺の中を覗き込む。
そして、口々に感動の言葉を叫んでいた。
「すごい……本当に蜂蜜だ!」
「こんなにたくさんの蜂蜜、見たことねえ!」
「リゼット様、本当に採ってきなさったのか……!」
アルフレッドが、感動で胸がいっぱいになった様子で私のそばにやってきた。
その目には、うっすらと涙が浮かんでいる。
「お嬢様、ご無事で……! そして、またしてもこのような奇跡を……!」
「だから、奇跡じゃないのよ、アルフレッド。さあ、みんな、これを村に運びましょう。これから、この宝物をもっと素敵なものに変身させるわ」
私の言葉に、村人たちは再び「おおーっ!」と歓声を上げた。
彼らは、喜んで壺を運ぶのを手伝ってくれた。
広場の中央に壺が置かれると、村人たちはまるで祭りのようにその周りに集まってきた。
特に子供たちは、早く舐めてみたくてうずうずしているようだ。
「さあ、まずはこの蜜を、食べやすいように綺麗にするわよ」
私は、大きな布を広げた。
その上に、蜜蝋ごと蜂蜜を移していく。
そして、その布で蜂蜜を包み込み、上からゆっくりと重石を乗せて圧力をかけた。
「こうすることで、蜜と巣を作っている蝋(ろう)を分けることができるの」
私の説明に、村人たちは興味津々で見守っている。
布の隙間から、とろりとした純粋な蜂蜜だけがゆっくりと染み出してきた。
下の受け皿に、黄金の液体が溜まっていく。
不純物が取り除かれた蜂蜜は、まるで溶かした宝石のように透き通り輝いていた。
「うわあ……綺麗だ……」
誰かが、うっとりと呟いた。
やがて、受け皿がいっぱいになる頃にはすっかり蜜が搾り取られた。
布の中には、白っぽい蝋の塊だけが残る。
「さあ、できたわよ。みんな、指を綺麗にして、少しだけ舐めてみて」
私がそう言うと、待ちかねていた子供たちがわっと受け皿に殺到した。
彼らは、恐る恐る指先に蜂蜜をつけぺろりと舐める。
その瞬間、子供たちの顔がぱあっと輝いた。
「あ……あまい!」
一人の少年が、目を見開いて叫んだ。
「おいしいー!」
今まで味わったことのない、濃厚で花の香りがする甘さ。
その感動的な美味しさに、子供たちは言葉を失う。
ただ、何度も指を舐めていた。
その様子を見ていた大人たちも、次々と蜂蜜を味わい始める。
一人の老婆が、指についた蜜をそっと口に運んだ。
「こ、これは……!」
「なんて甘さだ……天国の味か……」
長年の貧しい生活で、甘いものなど口にする機会がなかった村人たち。
彼らにとって、この蜂蜜の味は衝撃的だった。
あまりの美味しさに、その場に泣き崩れる老婆さえいる。
広場は、幸福なため息と喜びの声で満たされていた。
私も、指についた蜂蜜を舐めてみる。
うん、美味しい。
様々な花の蜜が混ざり合った、複雑で豊かな風味だ。
この土地の自然が、そのまま凝縮されているようだった。
「リゼット様、こっちの塊はどうするんだ?」
カイが、布に残った蜜蝋の塊を指差して尋ねた。
それは、蜂蜜を搾った後の残りかすに見える。
「ふふ、カイ。それはね、もう一つのお楽しみよ。これも、私たちの暮らしを豊かにしてくれる大切な宝物なの」
私はにっこりと笑い、蜜蝋の塊を手に取った。
「この蝋を溶かして、糸を浸して固めればとても明るくて長持ちする『ロウソク』が作れるわ。今みたいに、すぐに燃え尽きてしまう松明よりもずっと便利よ」
私は、ロウソクがもたらす未来を語った。
「すすだらけになる油のランプよりも、クリーンで安全なの」
「ロ、ロウソク……?」
村人たちは、初めて聞く言葉に目を丸くしている。
「ええ、それにこの蝋を布に塗れば水を弾くようになるわ。雨合羽だって作れるかもしれない」
私の説明に、村人たちの驚きはさらに大きくなった。
甘い蜜だけでなく、あの巣の塊にまでそんな使い道があったなんて。
彼らは、想像もしていなかったのだ。
「すげえ……蜂の巣って、捨てるところが一つもねえんだな……」
カイが、心底感心したように呟いた。
自然の中にあるものは、何一つ無駄なものはない。
昔の人は、そうやって自然と共存しその恵みを余すところなく利用してきたのだ。
「さて、それじゃあ、約束通りお菓子を作りましょうか」
私は、搾りたての蜂蜜と先日収穫した『森の恵み』のナッツを用意した。
まず、ナッツを粗く砕き熱した鍋で軽く煎る。
香ばしい匂いが漂い始めると、村人たちがごくりと喉を鳴らした。
食欲をそそる、たまらない香りだ。
次に、別の鍋に蜂蜜を入れ弱火でゆっくりと煮詰めていく。
甘い香りが、さらに濃厚になって広場に満ちていった。
蜂蜜がフツフツと泡立ち、少し色づいてきたところで煎ったナッツを加える。
そして、素早く混ぜ合わせた。
「これを、平らな石板の上に広げて、冷まして固めるのよ」
熱い蜂蜜とナッツを石板に広げると、あっという間に甘い香りの板が出来上がった。
まだ温かいうちに、ナイフで食べやすい大きさに切れ目を入れていく。
私は、このお菓子を『森の恵みの蜂蜜がらめ』と名付けた。
「さあ、出来立てよ。火傷しないように、気をつけて食べてね」
私がそう言うと、またしても子供たちが真っ先に手を伸ばした。
カリカリとしたナッツの食感と、香ばしさ。
そして、凝縮された蜂蜜の濃厚な甘さ。
それは、彼らが今まで食べたどんなものよりも美味しくて、贅沢な味だった。
「おいしい!」
「こんな美味しいお菓子、初めて食べた!」
子供たちの歓声に、大人たちも笑顔になる。
この村に、初めて「おやつ」という文化が生まれた瞬間だった。
人々は、ただお腹を満たすためだけでなく人生を楽しむための食事を初めて知ったのだ。
その日の夜、村では再び宴が開かれた。
もちろん、主役は蜂蜜と蜂蜜で作ったお菓子だ。
そして、私が早速作ってみせた蜜蝋のロウソクが、宴の席を優しく照らしていた。
ロウソクの炎は、松明のようにパチパチと音を立てることもない。
油のランプのように、煙たい匂いを出すこともない。
静かに、そして明るく村人たちの笑顔を照らし出している。
「この灯り……なんだか、心が安らぐなあ」
長老が、ロウソクの炎を見つめながらしみじみと呟いた。
その言葉に、皆が頷く。
穏やかな光は、人々の心を温かく包み込んでいた。
私は、蜂蜜がらめを頬張りながら満ち足りた気持ちでその光景を眺めていた。
家が建ち、水路が通り食料が安定した。
そして、甘いお菓子と穏やかな灯りが生まれた。
この村は、私が来た頃とは比べ物にならないほど豊かになった。
だけど、これで終わりじゃない。
野生の蜂の巣に頼るのではなく、村で蜂を飼う「養蜂」を始めればいい。
そうすれば、もっと安定して蜂蜜が手に入るようになる。
蜂蜜は村の特産品として、他の村や町との交易にも使えるかもしれない。
(交易……か)
もし、外の世界と交易ができるようになればこの村にはないものが手に入る。
例えば、塩。
鉄の道具。
もっと多様な作物の種。
村の可能性は、さらに大きく広がっていくはずだ。
「リゼット様、何を考えてるんだい?」
隣に座っていたカイが、不思議そうな顔で私の顔を覗き込んできた。
「ううん、この村の、これからのことを少しだけね」
私は微笑んで、ロウソクの炎に照らされた彼の顔を見つめた。
「カイ、蜂をね、村で飼うことはできると思う?」
「蜂を……飼う?」
カイは、鳩が豆鉄砲を食ったような顔をしている。
私の頭の中には、もう次の計画がロウソクの灯りのように、はっきりと見え始めていた。
私の突拍子もない提案に、カイはしばらく口をあんぐりと開けていた。
しかし、やがて何かを理解したようにその目に好奇心の光を宿した。
「……あんたが言うなら、できるんだろうな。次は、どうやって蜂を捕まえてくるんだ?」
彼の返事に、私は満足して頷いた。
この村の人々は、もう「できない」とは考えない。
どうすれば「できる」のかを、一緒に考えてくれる仲間になってくれたのだ。
161
あなたにおすすめの小説

役立たずと追放された聖女は、第二の人生で薬師として静かに輝く
腐ったバナナ
ファンタジー
「お前は役立たずだ」
――そう言われ、聖女カリナは宮廷から追放された。
癒やしの力は弱く、誰からも冷遇され続けた日々。
居場所を失った彼女は、静かな田舎の村へ向かう。
しかしそこで出会ったのは、病に苦しむ人々、薬草を必要とする生活、そして彼女をまっすぐ信じてくれる村人たちだった。
小さな治療を重ねるうちに、カリナは“ただの役立たず”ではなく「薬師」としての価値を見いだしていく。

刷り込みで竜の母親になった私は、国の運命を預かることになりました。繁栄も滅亡も、私の導き次第で決まるようです。
木山楽斗
ファンタジー
宿屋で働くフェリナは、ある日森で卵を見つけた。
その卵からかえったのは、彼女が見たことがない生物だった。その生物は、生まれて初めて見たフェリナのことを母親だと思ったらしく、彼女にとても懐いていた。
本物の母親も見当たらず、見捨てることも忍びないことから、フェリナは謎の生物を育てることにした。
リルフと名付けられた生物と、フェリナはしばらく平和な日常を過ごしていた。
しかし、ある日彼女達の元に国王から通達があった。
なんでも、リルフは竜という生物であり、国を繁栄にも破滅にも導く特別な存在であるようだ。
竜がどちらの道を辿るかは、その母親にかかっているらしい。知らない内に、フェリナは国の運命を握っていたのだ。
※この作品は「小説家になろう」「カクヨム」「アルファポリス」にも掲載しています。
※2021/09/03 改題しました。(旧題:刷り込みで竜の母親になった私は、国の運命を預かることになりました。)

追放された回復術師は、なんでも『回復』できて万能でした
新緑あらた
ファンタジー
死闘の末、強敵の討伐クエストを達成した回復術師ヨシュアを待っていたのは、称賛の言葉ではなく、解雇通告だった。
「ヨシュア……てめえはクビだ」
ポーションを湯水のように使える最高位冒険者になった彼らは、今まで散々ポーションの代用品としてヨシュアを利用してきたのに、回復術師は不要だと考えて切り捨てることにしたのだ。
「ポーションの下位互換」とまで罵られて気落ちしていたヨシュアだったが、ブラックな労働をしいるあのパーティーから解放されて喜んでいる自分に気づく。
危機から救った辺境の地方領主の娘との出会いをきっかけに、彼の世界はどんどん広がっていく……。
一方、Sランク冒険者パーティーはクエストの未達成でどんどんランクを落としていく。
彼らは知らなかったのだ、ヨシュアが彼らの傷だけでなく、状態異常や武器の破損など、なんでも『回復』していたことを……。

タダ働きなので待遇改善を求めて抗議したら、精霊達から『破壊神』と怖れられています。
渡里あずま
ファンタジー
出来損ないの聖女・アガタ。
しかし、精霊の加護を持つ新たな聖女が現れて、王子から婚約破棄された時――彼女は、前世(現代)の記憶を取り戻した。
「それなら、今までの報酬を払って貰えますか?」
※※※
虐げられていた子が、モフモフしながらやりたいことを探す旅に出る話です。
※重複投稿作品※
表紙の使用画像は、AdobeStockのものです。

【完結】特別な力で国を守っていた〈防国姫〉の私、愚王と愚妹に王宮追放されたのでスパダリ従者と旅に出ます。一方で愚王と愚妹は破滅する模様
岡崎 剛柔
ファンタジー
◎第17回ファンタジー小説大賞に応募しています。投票していただけると嬉しいです
【あらすじ】
カスケード王国には魔力水晶石と呼ばれる特殊な鉱物が国中に存在しており、その魔力水晶石に特別な魔力を流すことで〈魔素〉による疫病などを防いでいた特別な聖女がいた。
聖女の名前はアメリア・フィンドラル。
国民から〈防国姫〉と呼ばれて尊敬されていた、フィンドラル男爵家の長女としてこの世に生を受けた凛々しい女性だった。
「アメリア・フィンドラル、ちょうどいい機会だからここでお前との婚約を破棄する! いいか、これは現国王である僕ことアントン・カスケードがずっと前から決めていたことだ! だから異議は認めない!」
そんなアメリアは婚約者だった若き国王――アントン・カスケードに公衆の面前で一方的に婚約破棄されてしまう。
婚約破棄された理由は、アメリアの妹であったミーシャの策略だった。
ミーシャはアメリアと同じ〈防国姫〉になれる特別な魔力を発現させたことで、アントンを口説き落としてアメリアとの婚約を破棄させてしまう。
そしてミーシャに骨抜きにされたアントンは、アメリアに王宮からの追放処分を言い渡した。
これにはアメリアもすっかり呆れ、無駄な言い訳をせずに大人しく王宮から出て行った。
やがてアメリアは天才騎士と呼ばれていたリヒト・ジークウォルトを連れて〈放浪医師〉となることを決意する。
〈防国姫〉の任を解かれても、国民たちを守るために自分が持つ医術の知識を活かそうと考えたのだ。
一方、本物の知識と実力を持っていたアメリアを王宮から追放したことで、主核の魔力水晶石が致命的な誤作動を起こしてカスケード王国は未曽有の大災害に陥ってしまう。
普通の女性ならば「私と婚約破棄して王宮から追放した報いよ。ざまあ」と喜ぶだろう。
だが、誰よりも優しい心と気高い信念を持っていたアメリアは違った。
カスケード王国全土を襲った未曽有の大災害を鎮めるべく、すべての原因だったミーシャとアントンのいる王宮に、アメリアはリヒトを始めとして旅先で出会った弟子の少女や伝説の魔獣フェンリルと向かう。
些細な恨みよりも、〈防国姫〉と呼ばれた聖女の力で国を救うために――。

召喚失敗!?いや、私聖女みたいなんですけど・・・まぁいっか。
SaToo
ファンタジー
聖女を召喚しておいてお前は聖女じゃないって、それはなくない?
その魔道具、私の力量りきれてないよ?まぁ聖女じゃないっていうならそれでもいいけど。
ってなんで地下牢に閉じ込められてるんだろ…。
せっかく異世界に来たんだから、世界中を旅したいよ。
こんなところさっさと抜け出して、旅に出ますか。

オネエ伯爵、幼女を拾う。~実はこの子、逃げてきた聖女らしい~
雪丸
ファンタジー
アタシ、アドルディ・レッドフォード伯爵。
突然だけど今の状況を説明するわ。幼女を拾ったの。
多分年齢は6~8歳くらいの子。屋敷の前にボロ雑巾が落ちてると思ったらびっくり!人だったの。
死んでる?と思ってその辺りに落ちている木で突いたら、息をしていたから屋敷に運んで手当てをしたのよ。
「道端で倒れていた私を助け、手当を施したその所業。賞賛に値します。(盛大なキャラ作り中)」
んま~~~尊大だし図々しいし可愛くないわ~~~!!
でも聖女様だから変な扱いもできないわ~~~!!
これからアタシ、どうなっちゃうのかしら…。
な、ラブコメ&ファンタジーです。恋の進展はスローペースです。
小説家になろう、カクヨムにも投稿しています。(敬称略)
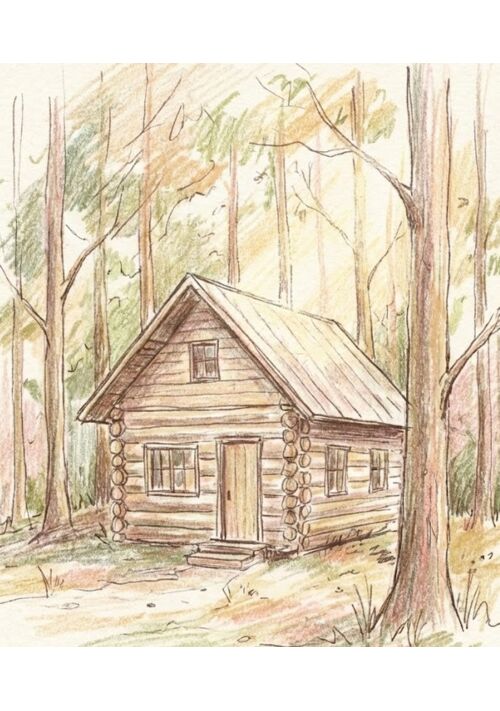
『捨てられシスターと傷ついた獣の修繕日誌』~「修理が遅い」と追放されたけど、DIY知識チートで壊れた家も心も直して、幸せな家庭を築きます
エリモコピコット
ファンタジー
【12/6 日間ランキング17位!】
「魔法で直せば一瞬だ。お前の手作業は時間の無駄なんだよ」
そう言われて勇者パーティを追放されたシスター、エリス。
彼女の魔法は弱く、派手な活躍はできない。 けれど彼女には、物の声を聞く『構造把握』の力と、前世から受け継いだ『DIY(日曜大工)』の知識があった。
傷心のまま辺境の村「ココン」に流れ着いた彼女は、一軒のボロ家と出会う。 隙間風だらけの壁、腐りかけた床。けれど、エリスは目を輝かせた。
「直せる。ここを、世界で一番温かい『帰る場所』にしよう!」
釘を使わない頑丈な家具、水汲み不要の自動ポンプ、冬でもポカポカの床暖房。
魔法文明が見落としていた「手間暇かけた技術」は、不便な辺境生活を快適な楽園へと変えていく。
やがてその温かい家には、 傷ついた銀髪の狼少女や、 素直になれないツンデレ黒猫、 人見知りな犬耳の鍛冶師が集まってきて――。
「エリス姉、あったか~い……」「……悔しいけど、この家から出られないわね」
これは、不器用なシスターが、壊れた家と、傷ついた心を修繕していく物語。 優しくて温かい、手作りのスローライフ・ファンタジー!
(※一方その頃、メンテナンス係を失った勇者パーティの装備はボロボロになり、冷たい野営で後悔の日々を送るのですが……それはまた別のお話)
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















