80 / 357
双子
弐
しおりを挟む1999年、春。
わくたかむの社敷地内の最奥にある、ひと気のない小さな離れの廊下を歩く小さな人影があった。
白衣に白袴姿のその子供は、何度も鼻をすすり目尻を強く擦りながら歩き続ける。最奥の部屋にたどり着いて障子の前に立つと、中から衣擦れの音がした。
「薫……? どうしたの、入っておいで」
中から声を掛けられて、薫はそっと障子を引いた。
開け放たれた縁側からふわりと桃の花びらが舞い込む部屋の中に、布団の上に座る女性がいる。
「ふふ、また泣いてるの?」
目を細めて両手を差し出せば、薫は駆け寄ってその胸に飛び込んだ。
「お母さん……っ! もうやだ……!」
火がついたように泣き出した子供を何も言わずに抱きしめる。
「まだお稽古の時間でしょ? 逃げ出してきたの?」
「だって、だって、痛いんだもん……! 血でたの、もうヤダっ!」
「どこ? みせて」
泣きじゃくりながら自分で袴をまくって見せた薫に眉根を寄せた。
まだ小さく細い二の腕を刃物で切った様な痛々しい切り傷がある。それだけではなく、治りかけの青アザや蚯蚓脹れが至る所にある。
痛々しいその傷跡を労わるようにそっと撫でた。
絆創膏を貼ってやれば、また胸に顔を埋める。
「いつものやって……」
唇を尖らせてそうねだる姿に微笑む。
「ふふ、はいはい。……痛いの痛いの、飛んでいけ。痛いの痛いの、飛んでいけ」
優しく背を叩きながら囁くように言葉を紡ぐ。
この声でこの子の痛みが和らぎますように。
自分に特別な力は無いけれど精一杯そんな気持ちを込めて囁く。
暫くそうしているうちに、安らかな寝息が聞こえ始める。そっと顔を覗き込めばあどけない寝顔があった。自分の布団に寝転がらせてそっと腹に布団をかける。
ちょうどその時、廊下側の障子に人影がさして、すっと開いた。
「幸?」
「隆永さん」
「またここに逃げ込んでたのか」
心地よさそうにすやすやと眠る姿に険しい顔をした隆永は息を吐いて歩み寄った。
「ここに逃げてくれば、助けてもらえると思ってるのよ」
「甘やかしちゃダメだっていったろ。薫には必要な事なんだ」
そうは言いつつ、隆永がいつも薫が疲れて眠った後に様子を見に来ていることを知っている。
「ふふ、分かってるよ。でも、薫を甘やかしてくれる大人も必要だと思うから」
そう笑って薫の頭をそっと撫でる。呆れたように息を吐いた隆永は、幸の隣に腰を下ろした。
「起きてて平気?」
「うん。今日は調子いいみたい。最近は薫も落ち着いてるし」
「でもそろそろ形代は変えようか」
「ありがとう」
うん、とひとつ頷いて隆永は箪笥の引き出しから薄い桐の箱を取り出す。その背中を見つめながら、幸は双子が産まれた日のことを思い出した。
自分は気を失う直前に、次男の薫を無事出産することが出来たらしい。
しかし長男の芽に言祝ぎが偏ったことで、薫の存在自体が呪になってしまい、自分は呪いにあてられた。けれど今こうして生きていられるのは、全て隆永のおかげだった。
隆永が毎晩奏上してくれていた安産祈願祝詞は、言葉通り出産の安全を願う祝詞だった。それに加えて、形代と呼ばれる人の形を模して切った和紙を用意していたことで、一命を取り留めたのだ。
形代は人の身代りになって罪や穢を移す道具、幸が被った呪いを形代に移すことが出来たからだ。
上手くいくかどうかは最後まで分からなかった、と目が覚めた時に隆永は泣いてそう言った。
今はまだ赤ん坊だから形代に移すことで何とかなった。けれど子供が成長するにつれ、呪の総量も増えていく。いち早く自分自信で呪を抑えられるようにならなければいけない。薫は誰よりも苦労するだろう。
隆永の言った通り、生まれてすぐに薫は敷地の一番奥にある離れへと移された。
勿論幸もついて行こうとしたけれど、薫から受けた呪いの後遺症で布団から起き上がれず、薫を腕にだけたのは出産してから十日も過ぎた日の事だった。
まだ一人で歩けない幸は隆永に付き添われて離へと向かった。
「まだ赤ん坊だから、俺や真言ならなんとか対処できる。けれど幸は俺が渡した形代の容量が超えた瞬間、またあの時みたいになるかもしれない」
あの時というのは、きっと薫を産んだ瞬間のことだろう。あの時感じた今までに味わったことの無いような感覚は、いつまでも忘れなれないだろう。
「薫と過ごせるのは、十分が限界だ」
その言葉を聞きながら、小さな子供布団にくるまってあどけない表情で眠る薫を抱き上げた。
温かい。優しい匂いがする。
目元は隆永に、鼻と口は自分に似ている気がする。何より兄弟の芽と瓜二つの顔立ちだった。
「……私も薫と離れに住む」
その言葉に隆永は目を剥いた。
「……さっきの俺の話を聞いた上でそう言ってるんだよね」
「うん、そう。聞いた上で決めた、私は薫とここに住む」
「薫と一緒に暮らせば、幸の身体はずっとそのままなんだよ。大きくなれば呪も増していく。俺の形代だった全てを賄い切れる訳じゃないんだ……!」
隆永が声を荒らげた。その声に目が覚めたのか薫が頼りない声で泣き始める。慌てて幸から受け取ろうとして、幸は胸に薫を抱きしめた。隆永が歯を食いしばる。
「芽にも幸が必要なんだよ……」
「分かってる。もちろん芽も同じくらい愛情を注ぐし寂しい思いはさせない。でも薫には私しかいないの。こんなにも寂しい場所で、一人きりになんて出来ない……! だから許して……ッ」
自分が頼めば、隆永が拒否できないのを知っていてそう言った。案の定隆永はひどく顔を歪めて俯く。そんな隆永の肩にもたれかかった。
「いつも、心配ばっかりかけてごめんね」
「分かってるなら、少しは俺の気持ちも汲んでよ」
「……ん、ごめんね」
その日から、幸は薫と離れで、隆永は母屋で芽と暮らすようになった。
そして薫が三歳になった歳から、隆永のもとで呪を抑える稽古が始まった。詳しい事は教えて貰えないが、毎日泣きながら帰ってきては身体中に生傷を作ってくる薫の様子から、生易しいものでは無いことは分かった。
薫に取っては必要な事で、隆永が心を鬼にして接していることも分かっている。ただ幼い薫がそれを理解できるはずもなく、それが幸にとっては心苦しかった。
「────隆永さん、いつもごめんね。ありがとう」
薫の腹を優しく叩きながらそうこぼす。
「二人の子供だよ。当たり前の事をしてるだけだから」
隆永は薫の頬に残る涙のあとを拭って微笑んだ。
「────でねでね、お母さん。真言がね、もうこんな事もできるようになったんですかってびっくりしたんだよね」
「そうなの、芽はすごいねぇ」
「でしょ、すごいでしょ?」
ある日の昼下がり、母屋から離れへ遊びに来ていた芽は幸の膝の上で楽しげに今朝あった事を話していた。
幸が布団から起き上がれない体になってしまい、芽は母親に会うためにこうして毎日離れへ訪れている。
母屋で隆永の祖父母に育てられている芽は、何不自由なくすくすくと成長している。明るく朗らかで、他人の気持ちに聡い子に育った。持ち前の言祝ぎの多さや飲み込みの速さから、真言にいろいろと教わっているらしい。
唯一まだ、なぜ離れて暮らさなければならないのかと帰り際に離れ難くて泣いて訴える芽には訳を話せていない。
「明日からね、"やまとまい"もおしえてもらうんだよ」
「今度お母さんにもみせてね」
「いいよ!」
その時廊下側の障子が開いて薫が顔をのぞかせた。幸と芽が振り返る。
「薫、おかえり。あちゃー、また泣いてるの」
いつもならそのまま幸の腕の中へ走ってくる薫だが、芽の姿を見つけてぐっとそれを堪える。
「薫どうしたの? 泣いてるの? どっかいたい?」
幸の膝から降りた芽が薫の元へ駆け寄った。顔を覗き込まれて、薫はふいと目をそらす。
「泣いてない。いたくない……」
「そっかぁ。薫は我慢できてえらいねぇ」
芽に頭を撫でられて、堪えていた涙が零れた薫は「うん」と頷いた。
二人のやり取りを目を細めて見守っていた幸は「そうだ」と声を上げる。
「二人とも。おじいちゃんからお菓子が届いたから、一緒に食べよっか」
「おじいちゃんのお菓子!」
「薫、そこの棚から取ってくれる?」
涙を拭った薫は「うん」と頷いた。
縁側に三人並んで、幸の実家から届いた練り切りを頬張る。
「薫、おいしい?」
「ん……」
「じゃあ僕のもあげるね」
自分のを割って差し出した芽に、薫は恐る恐る手を差し出した。
「お利口さんな芽にはお母さんの分をあげる」
「やった! 僕おじいちゃんの家に住もうかなぁ。そしたらお菓子たべほうだいだもん。それに、薫もお母さんもずっとにこにこでしょ?」
「ふふ、今度おじいちゃんにお願いしてみたら?」
「おじいちゃん家にもに家鳴がいるなら住んでもいいかな~」
機嫌よくそう言った芽に目尻を下げる。その横に座る薫は目を伏せて遠くを見つめていた。
「薫は家鳴すき?」
「……見たことない」
「そうなの? どこにでもいるよ。こんどつれてこようか?」
「いい。僕がちかよると……ころしちゃうから」
「へんなの。それならお母さんも僕もしんじゃうのにね」
何気ないその一言に薫の表情がいっそう陰る。幼いながらにそれを感じとった芽が、戸惑いながらも話題を変える。
「薫はお父さんになにをならってるの? 僕は真言に"はらえことば"ならったよ!」
「……"しゅ"のおさえかた」
「へぇー! いいなぁ薫は。僕もお父さんにおしえてもらいたいなぁ」
幸が止めるよりも先に薫の表情が強ばった。「芽」と諭すように名前を呼べば、芽は不思議そうに首を傾げた。
「でも次の春からはいっしょにお稽古できるね。薫も"しんしゅう"にいくでしょ!」
「芽……!」
窘めるように名前を呼ばれたことに芽は目をキョトンとさせた。
「しんしゅうって……なに?」
「薫、あのね────」
「学校だよ! "シンショク"になるための勉強をするところだよ。友だちもいっぱいいて、お祭りもあるんだよ! 六歳になったらみんな行くって、真言いってたもん」
薫が大きく目を見開く。
「お母さん、僕も"しんしゅう"行くの……?」
「あ……あのね、薫」
「僕も六歳になるから、芽といっしょにいくの? そしたらお父さんのお稽古も終わりだよね……!」
瞳を輝かせて自分を見上げる薫にすぐに言葉が出なかった。こんなにも明るい声を出した薫は久しぶりだったからだ。
「そう、だね。薫も、神修に通えるようになるよ。ただ、芽と一緒に来年から通うのは、難しいの」
また薫の表情に影がさした。
幼い頃から感情を言葉に出さないように何度も言い聞かせてきた。それは薫自身や周囲の人たちを守るためでもあるけれど、こうして幼いながらに感情をこらえる姿にはいつも切なくなる。
「……どうして?」
必死に感情を押し殺した声で薫が尋ねた。
「お父さんとのお稽古がまだもう少し必要なんだって、それが全部終わったら、芽と通えるようになるよ」
「もう少しって、どれくらい?」
「それは────」
薫がひどく顔を歪める。
「薫……? どうしたの? やっぱりどっかいたい?」
不安げに手を差し出した芽の手を弾いた。
「────もう嫌だ」
薫の声色が変わったその瞬間、幸は身体中の肌が粟立つのを感じた。正面から首を絞められるような息苦しさに目を見開く。
間違いなく薫の言霊だった。
「どうして、どうして僕だけいつも」
「くゆ、る……駄目、それ以上言っちゃ────」
「いたいのも、もういやだ。全部、全部いやだ」
幸は咄嗟に芽の背中を突き飛ばした。数歩前に倒れ込んだ芽は何事かと目を瞬かせる。
「母屋に帰りなさい……ッ!」
幸は薫を胸に抱きしめてそう叫んだ。
突然怒鳴られたことと突き飛ばされて膝を擦りむいた痛みに、芽は顔を歪める。「早く!」幸にもう一度怒鳴られて、わっと泣き出した芽は転がるように走り出した。
その背中が見えなくなって、幸は薫を強く抱きしめる。
「薫、落ち着いて。大丈夫よ、大丈夫……」
「もういやだ、もういやだ! だいきらい、お父さんもお母さんも、芽も、みんなだいきらいッ!」
体の中を蝕むような激しい痛みを堪えながら薫をこれでもかと抱きしめた。
「ごめんね、薫……ごめんね……」
私が二人を、ちゃんと産んであげられなかったから。でも薫には苦しい未来が待っていると分かっていても、どうしてもあなたに会いたかったの。
薫の小さな手が自分を叩いた。痛くないはずなのに、その度に胸に棘が突き刺さるような痛みが走る。
泣き疲れて眠りにつくまでずっと抱きしめ続けて、薫から寝息が聞こえ始めて顔をのぞき込む。泣き腫らして赤くなった目が切ない。
ごめんね、とその瞼に口付けた。
「────幸!? さっき芽から聞いて……ッ、何があったの!」
芽から話を聞いた隆永が転がるように部屋へ入ってきた。その声を聞いて安心したのか、幸は意識を手放した。
目が覚めると自分にあてがわれた部屋で眠っていた薫は、ぼんやりと天井を眺めてからゆっくりと体を起こした。
障子の隙間から見えた空には月が出ていて、冬の名残を感じる冷たい風がそよそよと吹いていた。
「お母さん……?」
いつも眠る時は幸の部屋に布団を敷いて隣で眠っていた。自分の部屋で眠る時は、幸の具合が悪い時だけだ。
離れの中は静まり返っている。
眠る前のことを思い出した。
『お父さんもお母さんも、芽も、みんなだいきらいッ!』
幸の胸の中で確かにそう叫んだ。
その瞬間、ハッと口を抑えた。
覚えているいちばん古い記憶にすらある、嫌という程隆永から聞かされて続けた言葉が脳裏を過った。
『腹が立った時や悲しい時、その気持ちのままに言葉を発してはいけない。もし薫がそうしてしまえば、周りの人を傷つける事になるからだよ』
「僕……」
稽古が痛くて怖くて嫌で、お母さんのお膝で話してる芽が羨ましくて、学校に行ける芽に腹が立って、それで────。
お父さんはちょっと怖いけど嫌いだなんて思ってない、お母さんも大好きだ。芽も、いつも優しくしてくれるのが凄く嬉しい。なのに、僕は。
気持ちをそのまま言葉にした。お母さんにぶつけてしまった。
だから、お母さんは一緒に寝れなくなったの? 僕のせいで、お母さんを傷つけた?
一番してはいけないとあれほど言い聞かせられてきたことをしてしまったんだ。
はたはたと布団の上に涙が零れた。どうしよう、と顔を歪めたその時「薫……?」と控えめに名前を呼ぶ声が聞こえた。縁側の方の障子に小さな人影がかかっていた。
「薫……? おきてる?」
涙を拭いながら布団から抜け出して障子を開けると、芽がそこに立っていた。目元を赤くした芽はすんと鼻を啜って薫を見た。
「薫、ごめんね……っ!」
突然の謝罪に目を瞬かせた。
「真言からきいたの。どうして薫がお父さんとお稽古してて、いっしょに母屋に住めないのか」
「あ……」
「僕、薫の気持ちもかんがえずに、薫をかなしませること言った」
芽は大粒の涙をぽろぽろとこぼした。
芽が自分の前で泣いているのを初めて見た。
いつも芽は笑っていて、泣くのは自分だったから。自分がないていると一目散に駆けつけてきて「どうしたの? 大丈夫?」と声をかけてくれた。
つられるように涙がこぼれた。
「薫……? どうしたの? 大丈夫? 僕がいじわるなこと言ったから?」
「ちが、う」
「なら泣かないでよぉ……」
芽はぽろぽろと涙を零しながら自分の袖を薫の顔に押し当てた。ごしごしと零れる涙を拭えば「いたい」と薫が声を上げる。
「これ食べて。あのね、甘いものたべると、言霊の力が元に戻るの。だから薫の言祝ぎももどるかもしれない」
ポケットからくるまったハンカチを取り出した芽は手のひらの上で結び目を解く。ハンカチの上にちょこんと乗せられたそれを薫の口に突っ込んだ。
あまりにも突然のことに目を白黒させた薫はやがてそれが口の中でじんわり溶けていくのに気が付いた。
「こんぺいとうだよ、青女房にもらったの」
「あおにょうぼう……?」
「ひとの姿の妖怪だよ、歯がまっくろの。夜の社頭でお菓子うっててね、遊びに行くといつもくれるの」
全部あげる、と薫の手に押し付けた。
「ごめんね、薫。嫌いになった……?」
「……なってない」
「良かったぁ……。僕は薫のこと大好きだよ」
小さな手で頭を撫でられた。芽はとても安心したように嬉しそうに笑った。
「あのね、学校行ってもね、たまに帰ってこれるから、その時に"しんしゅう"で習ったこと、薫におしえるね。そしたら薫も、学校いってるのと一緒でしょ?」
「いいの……?」
「うん。こんぺいとうも持ってくるね、これすき?」
「ん……すき」
「ふふ、僕もすき」
二人は顔を見合せて笑った。
「僕、たくさん勉強する。そしたら薫が泣かなくてもいいように、なるでしょ? 僕がずっとずっと、守ってあげるからね」
小指を差し出した芽に少し戸惑った薫。芽は薫の手を取って無理やり小指を絡めた。
「約束だよ」
そしてその次の年の春、芽は神修の初等部へ入学した。
3
あなたにおすすめの小説

あやかし警察おとり捜査課
紫音みけ🐾書籍発売中
キャラ文芸
※第7回キャラ文芸大賞にて奨励賞を受賞しました。応援してくださった皆様、ありがとうございました。
【あらすじ】
二十三歳にして童顔・低身長で小中学生に見間違われる青年・栗丘みつきは、出世の見込みのない落ちこぼれ警察官。
しかしその小さな身に秘められた身体能力と、この世ならざるもの(=あやかし)を認知する霊視能力を買われた彼は、あやかし退治を主とする部署・特例災害対策室に任命され、あやかしを誘き寄せるための囮捜査に挑む。
反りが合わない年下エリートの相棒と、狐面を被った怪しい上司と共に繰り広げる退魔ファンタジー。

神戸・栄町 困り顔店主の謎解き紅茶専門店
hana*
キャラ文芸
レトロな建物が立ち並ぶ、神戸・栄町。
カフェ激戦区とも呼ばれるこの町の、とあるビルの2階でひっそりと営業している紅茶専門店には、長身でイケメンでいつもにこやかで誰にでも親切、なのになぜかいつもトラブルを招き寄せるという困った体質の店主がいる。
店に訪れるのは、婚約破棄された会社員、紅茶嫌いのカップル、不穏な女子大生のグループ……。
困り顔店主が、お客さんのお悩みを紅茶の香りとともにほわっと解決!?

郷守の巫女、夜明けの嫁入り
春ノ抹茶
キャラ文芸
「私の妻となり、暁の里に来ていただけませんか?」
「はい。───はい?」
東の果ての“占い娘”の噂を聞きつけ、彗月と名乗る美しい男が、村娘・紬の元にやってきた。
「古来より現世に住まう、人ならざるものの存在を、“あやかし”と言います。」
「暁の里は、あやかしと人間とが共存している、唯一の里なのです。」
近年、暁の里の結界が弱まっている。
結界を修復し、里を守ることが出来るのは、“郷守の巫女”ただ一人だけ。
郷守の巫女たる魂を持って生まれた紬は、その運命を受け入れて、彗月の手を取ることを決めた。
暁の里に降り立てば、そこには異様な日常がある。
あやかしと人間が当たり前のように言葉を交わし、共に笑い合っている。
里の案内人は扇子を広げ、紬を歓迎するのであった。
「さあ、足を踏み入れたが始まり!」
「此処は、人と人ならざるものが共に暮らす、現世に類を見ぬ唯一の地でございます」
「人の子あやかし。異なる種が手を取り合うは、夜明けの訪れと言えましょう」
「夢か現か、神楽に隠れたまほろばか」
「──ようこそ、暁の里へ!」

月華後宮伝
織部ソマリ
キャラ文芸
★10/30よりコミカライズが始まりました!どうぞよろしくお願いします!
◆神託により後宮に入ることになった『跳ねっ返りの薬草姫』と呼ばれている凛花。冷徹で女嫌いとの噂がある皇帝・紫曄の妃となるのは気が進まないが、ある目的のために月華宮へ行くと心に決めていた。凛花の秘めた目的とは、皇帝の寵を得ることではなく『虎に変化してしまう』という特殊すぎる体質の秘密を解き明かすこと! だが後宮入り早々、凛花は紫曄に秘密を知られてしまう。しかし同じく秘密を抱えている紫曄は、凛花に「抱き枕になれ」と予想外なことを言い出して――?
◆第14回恋愛小説大賞【中華後宮ラブ賞】受賞。ありがとうございます!
◆旧題:月華宮の虎猫の妃は眠れぬ皇帝の膝の上 ~不本意ながらモフモフ抱き枕を拝命いたします~

転職したら陰陽師になりました。〜チートな私は最強の式神を手に入れる!〜
万実
キャラ文芸
う、嘘でしょ。
こんな生き物が、こんな街の真ん中に居ていいの?!
私の目の前に現れたのは二本の角を持つ鬼だった。
バイトを首になった私、雪村深月は新たに見つけた職場『赤星探偵事務所』で面接の約束を取り付ける。
その帰り道に、とんでもない事件に巻き込まれた。
鬼が現れ戦う羽目に。
事務所の職員の拓斗に助けられ、鬼を倒したものの、この人なんであんな怖いのと普通に戦ってんの?
この事務所、表向きは『赤星探偵事務所』で、その実態は『赤星陰陽師事務所』だったことが判明し、私は慄いた。
鬼と戦うなんて絶対にイヤ!怖くて死んじゃいます!
一度は辞めようと思ったその仕事だけど、超絶イケメンの所長が現れ、ミーハーな私は彼につられて働くことに。
はじめは石を投げることしかできなかった私だけど、式神を手に入れ、徐々に陰陽師としての才能が開花していく。
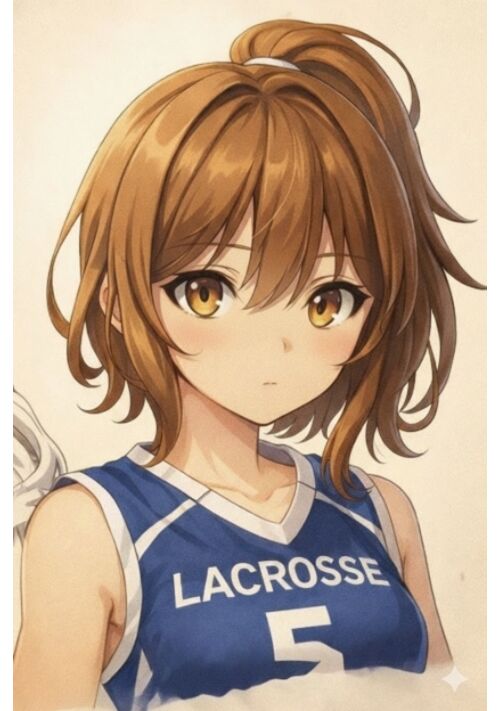
私の守護霊さん『ラクロス編』
Masa&G
キャラ文芸
本作は、本編『私の守護霊さん』の番外編です。
本編では描ききれなかった「ラクロス編」を、単独でも読める形でお届けします。番外編だけでも内容はわかりますが、本編を先に読んでいただくと、より物語に入り込みやすくなると思います。
「絶対にレギュラーを取って、東京代表に行きたい――」
そんな想いを胸に、宮司彩音は日々ラクロスの練習に明け暮れている。
同じポジションには、絶対的エースアタッカー・梶原真夏。埋まらない実力差に折れそうになる彩音のそばには、今日も無言の相棒・守護霊さんがいた。
守護霊さんの全力バックアップのもと、彩音の“レギュラー奪取&東京代表への挑戦”が始まる──。

あやかし家族 〜五人の兄と愛され末妹〜
南 鈴紀
キャラ文芸
妖狩りにより両親を奪われ、囚われの身となった半妖の少女・鈴音は浄化の狐火を利用するだけの道具のように扱われていた。呪いにより成長は止まり、容姿も思考も幼いまま、感情が消え失せてもなおただ生かされるままに生きていた。
しかし妖保護部隊本部第一部隊との出会いにより、鈴音の止まっていた時間が動き出す。
掴みどころはないが頼れる氏神・雅仁、兄には厳しいが弟妹には優しい狼の妖・千里、人間嫌いだが人当たりの良い振りが得意な人間・遥杜、可愛いもの好きで元気いっぱいの猫又・鴇羽、大人しいが思いやりに溢れる猫又・瑠璃。
五人の兄と過ごす時間の中で、無いものだらけだった鈴音にもやがて大切なものが増えていく。
妖×家族の心温まる和風ファンタジー。

あまりさんののっぴきならない事情
菱沼あゆ
キャラ文芸
強引に見合い結婚させられそうになって家出し、憧れのカフェでバイトを始めた、あまり。
充実した日々を送っていた彼女の前に、驚くような美形の客、犬塚海里《いぬづか かいり》が現れた。
「何故、こんなところに居る? 南条あまり」
「……嫌な人と結婚させられそうになって、家を出たからです」
「それ、俺だろ」
そーですね……。
カフェ店員となったお嬢様、あまりと常連客となった元見合い相手、海里の日常。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















