40 / 52
誘拐少女と探偵
8話
しおりを挟む
紅坂さんは車を発進すると、ようやく話してくれた。
鍵の偽造や諸々の情報については、情報屋と呼ばれる紅坂さんの義兄弟から仕入れたのだという。昨日のうちにゼンマイから得た記憶を情報屋へと伝え、マンションの特定から合鍵の作成まで行ってくれたのだそうだ。驚きの速さだ。
これから向かうマンションについても、簡単な情報は調べてくれていたらしい。住んでいるのは父と子の二人家族で、二人ともここ最近姿を見かけないという。
家の中に引きこもっているのかといえばそうでもないようで、夜になっても明かりは点かないらしい。父親に借金があったことから、近所では夜逃げしたのではという噂が流れているとのことだった。
しばらくしてたどり着いたのは十階建てのマンションだった。
外装はきれいではないが、かといって汚くもない。築年数は二十数年といったところだろう。ただ、周りに並ぶマンションはどれも大きく、最近建てられたもののようだ。そんな新築物件に囲まれているせいか、相対的に貧相な印象を受ける。
紅坂さんは住民用の駐車場に堂々と車を止めると、迷いなくマンションの中へ足を進める。ここの住人だと言わんばかりの態度であった。僕は彼女の後ろを恐る恐るついて行く。
エントランスの先にはエレベーターがあり、中に乗り込む。僕が入るのを確認すると紅坂さんは七階のボタンを押した。扉が閉まりエレベーターが上へ動き出す。すると、それまで黙っていた紅坂さんが口を開いた。
「郵便受けを見た?」
「見てませんけど」
「真雪くんも探偵の助手なんだから、常に周囲に注意を払わなきゃ。まあ、お説教は時間があるときにするとして、エントランスにあった七〇三号室の郵便受けね、郵便物が外まで溢れ返ってたの。やっぱり住人は戻っていないみたいだね」
「ということは、このまま突入するということですか?」
「もちろん」
エレベーターが目的の階に着くと、電子音とともにドアが開いた。住人に見知らぬ人間がマンション内にいることを見とがめられるのではないかという不安があったが、あいにく降りた階に人影はなかった。
廊下を進み、手前から三つ目の七〇三号室というプレートが付いた扉の前で立ち止まる。紅坂さんは二度インターホンを押し、室内からの反応がないことを確認すると、例の偽造した鍵を取り出し、迷いなく鍵穴へ差し込んだ。カチャリと錠の下りる音がするのを僕は固唾をのんで見守っていた。
紅坂さんと目が合う。「行くよ」と視線で訴えてくる彼女に無言で頷くと、僕らは室内へ足を踏み入れた。
午前中にも関わらず、室内は薄暗かった。玄関から伸びる廊下には左右と正面に三つの扉があり、そのうち正面の扉だけ半分ほど開いている。紅坂さんは靴を脱ぐと、正面の扉へと向かう。僕も彼女に後に続いて歩き出したとき、突然身体が強張った。自分の意思に反して身体が動くことを拒む。
紅坂さんが振り返り、身動きできずにいる僕に「どうしたの?」と問いかけてくる。自分でも理由がわからず何も言えずにいると、開け放たれた扉の向こうから物音がした。僕と紅坂さんは反射的に音がした方向を見る。緊張が場を支配し、心臓が早鐘を打つ。
隣に住む人が出した音であれば問題ない。だがもしも音の出所が室内だとしたら、この部屋には誰か人がいるということになる。
生唾を飲み込むのさえ躊躇われる静寂の中、紅坂さんは足音を忍ばせて中へ進んでいく。ここで立ち尽くしているわけにもいかず、僕も細心の注意を払い歩を進める。いつのまにか身体は動くようになっていた。
扉の先はダイニングとリビングが一対の部屋になっていた。ダイニングテーブルの上には、醤油などの調味料が並べられており、椅子が二つ置かれている。その奥のリビングにはこたつ机とテレビがある。置かれている家具などは総じて古いもののようだが、片付けが行き届いているため小綺麗な印象を受ける。
紅坂さんはテーブルの下やテレビデッキと壁の隙間などを素早く確認していた。誰か隠れていないかを確認したのだろう。
しかし人影は見つからず、僕たちの目線は一つの扉に集まった。先ほど僕たちが入ってきたもの以外に、この部屋にはもう一つ横にスライドさせるタイプの扉があった。もし誰かがいるとすれば、可能性はここ以外にない。紅坂さんは躊躇することなく扉を開けた。
「あれー?」
紅坂さんが間の抜けた声をあげたまま部屋の前で立ち止まる。
たまらず紅坂さんの肩越しに部屋を覗き込んだ僕は絶句した。
そこには細い腕に手錠を掛けられた幼い少女がいた。
鍵の偽造や諸々の情報については、情報屋と呼ばれる紅坂さんの義兄弟から仕入れたのだという。昨日のうちにゼンマイから得た記憶を情報屋へと伝え、マンションの特定から合鍵の作成まで行ってくれたのだそうだ。驚きの速さだ。
これから向かうマンションについても、簡単な情報は調べてくれていたらしい。住んでいるのは父と子の二人家族で、二人ともここ最近姿を見かけないという。
家の中に引きこもっているのかといえばそうでもないようで、夜になっても明かりは点かないらしい。父親に借金があったことから、近所では夜逃げしたのではという噂が流れているとのことだった。
しばらくしてたどり着いたのは十階建てのマンションだった。
外装はきれいではないが、かといって汚くもない。築年数は二十数年といったところだろう。ただ、周りに並ぶマンションはどれも大きく、最近建てられたもののようだ。そんな新築物件に囲まれているせいか、相対的に貧相な印象を受ける。
紅坂さんは住民用の駐車場に堂々と車を止めると、迷いなくマンションの中へ足を進める。ここの住人だと言わんばかりの態度であった。僕は彼女の後ろを恐る恐るついて行く。
エントランスの先にはエレベーターがあり、中に乗り込む。僕が入るのを確認すると紅坂さんは七階のボタンを押した。扉が閉まりエレベーターが上へ動き出す。すると、それまで黙っていた紅坂さんが口を開いた。
「郵便受けを見た?」
「見てませんけど」
「真雪くんも探偵の助手なんだから、常に周囲に注意を払わなきゃ。まあ、お説教は時間があるときにするとして、エントランスにあった七〇三号室の郵便受けね、郵便物が外まで溢れ返ってたの。やっぱり住人は戻っていないみたいだね」
「ということは、このまま突入するということですか?」
「もちろん」
エレベーターが目的の階に着くと、電子音とともにドアが開いた。住人に見知らぬ人間がマンション内にいることを見とがめられるのではないかという不安があったが、あいにく降りた階に人影はなかった。
廊下を進み、手前から三つ目の七〇三号室というプレートが付いた扉の前で立ち止まる。紅坂さんは二度インターホンを押し、室内からの反応がないことを確認すると、例の偽造した鍵を取り出し、迷いなく鍵穴へ差し込んだ。カチャリと錠の下りる音がするのを僕は固唾をのんで見守っていた。
紅坂さんと目が合う。「行くよ」と視線で訴えてくる彼女に無言で頷くと、僕らは室内へ足を踏み入れた。
午前中にも関わらず、室内は薄暗かった。玄関から伸びる廊下には左右と正面に三つの扉があり、そのうち正面の扉だけ半分ほど開いている。紅坂さんは靴を脱ぐと、正面の扉へと向かう。僕も彼女に後に続いて歩き出したとき、突然身体が強張った。自分の意思に反して身体が動くことを拒む。
紅坂さんが振り返り、身動きできずにいる僕に「どうしたの?」と問いかけてくる。自分でも理由がわからず何も言えずにいると、開け放たれた扉の向こうから物音がした。僕と紅坂さんは反射的に音がした方向を見る。緊張が場を支配し、心臓が早鐘を打つ。
隣に住む人が出した音であれば問題ない。だがもしも音の出所が室内だとしたら、この部屋には誰か人がいるということになる。
生唾を飲み込むのさえ躊躇われる静寂の中、紅坂さんは足音を忍ばせて中へ進んでいく。ここで立ち尽くしているわけにもいかず、僕も細心の注意を払い歩を進める。いつのまにか身体は動くようになっていた。
扉の先はダイニングとリビングが一対の部屋になっていた。ダイニングテーブルの上には、醤油などの調味料が並べられており、椅子が二つ置かれている。その奥のリビングにはこたつ机とテレビがある。置かれている家具などは総じて古いもののようだが、片付けが行き届いているため小綺麗な印象を受ける。
紅坂さんはテーブルの下やテレビデッキと壁の隙間などを素早く確認していた。誰か隠れていないかを確認したのだろう。
しかし人影は見つからず、僕たちの目線は一つの扉に集まった。先ほど僕たちが入ってきたもの以外に、この部屋にはもう一つ横にスライドさせるタイプの扉があった。もし誰かがいるとすれば、可能性はここ以外にない。紅坂さんは躊躇することなく扉を開けた。
「あれー?」
紅坂さんが間の抜けた声をあげたまま部屋の前で立ち止まる。
たまらず紅坂さんの肩越しに部屋を覗き込んだ僕は絶句した。
そこには細い腕に手錠を掛けられた幼い少女がいた。
0
あなたにおすすめの小説

クラスで1番の美少女のことが好きなのに、なぜかクラスで3番目に可愛い子に絡まれる
グミ食べたい
青春
高校一年生の高居宙は、クラスで一番の美少女・一ノ瀬雫に一目惚れし、片想い中。
彼女と仲良くなりたい一心で高校生活を送っていた……はずだった。
だが、なぜか隣の席の女子、三間坂雪が頻繁に絡んでくる。
容姿は良いが、距離感が近く、からかってくる厄介な存在――のはずだった。
「一ノ瀬さんのこと、好きなんでしょ? 手伝ってあげる」
そう言って始まったのは、恋の応援か、それとも別の何かか。
これは、一ノ瀬雫への恋をきっかけに始まる、
高居宙と三間坂雪の、少し騒がしくて少し甘い学園ラブコメディ。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。
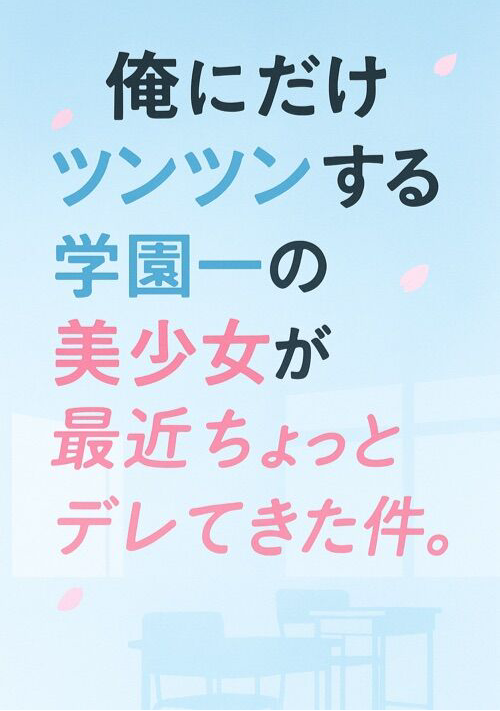
俺にだけツンツンする学園一の美少女が、最近ちょっとデレてきた件。
甘酢ニノ
恋愛
彼女いない歴=年齢の高校生・相沢蓮。
平凡な日々を送る彼の前に立ちはだかるのは──
学園一の美少女・黒瀬葵。
なぜか彼女は、俺にだけやたらとツンツンしてくる。
冷たくて、意地っ張りで、でも時々見せるその“素”が、どうしようもなく気になる。
最初はただの勘違いだったはずの関係。
けれど、小さな出来事の積み重ねが、少しずつ2人の距離を変えていく。
ツンデレな彼女と、不器用な俺がすれ違いながら少しずつ近づく、
焦れったくて甘酸っぱい、青春ラブコメディ。

黒に染まった華を摘む
馬場 蓮実
青春
夏の終わりに転校してきたのは、忘れられない初恋の相手だった——。
高須明希は、人生で“二番目”に好きになった相手——河西栞に密かに想いを寄せている。
「夏休み明けの初日。この席替えで、彼女との距離を縮めたい。話すきっかけがほしい——」
そんな願いを胸に登校したその朝、クラスに一人の転校生がやってくる。
彼女の名は、立石麻美。
昔の面影を残しながらも、まるで別人のような気配をまとう彼女は——明希にとって、忘れられない“初恋の人”だった。
この再会が、静かだった日常に波紋を広げていく。
その日の放課後。
明希は、"性の衝動"に溺れる自身の姿を、麻美に見られてしまう——。
塞がっていた何かが、ゆっくりと崩れはじめる。
そして鬱屈した青春は、想像もしていなかった熱と痛みを帯びて動き出す。
すべてに触れたとき、
明希は何を守り、何を選ぶのか。
光と影が交錯する、“遅れてきた”ひと夏の物語。

彼女に振られた俺の転生先が高校生だった。それはいいけどなんで元カノ達まで居るんだろう。
遊。
青春
主人公、三澄悠太35才。
彼女にフラれ、現実にうんざりしていた彼は、事故にあって転生。
……した先はまるで俺がこうだったら良かったと思っていた世界を絵に書いたような学生時代。
でも何故か俺をフッた筈の元カノ達も居て!?
もう恋愛したくないリベンジ主人公❌そんな主人公がどこか気になる元カノ、他多数のドタバタラブコメディー!
ちょっとずつちょっとずつの更新になります!(主に土日。)
略称はフラれろう(色とりどりのラブコメに精一杯の呪いを添えて、、笑)

隣の家の幼馴染と転校生が可愛すぎるんだが
akua034
恋愛
隣に住む幼馴染・水瀬美羽。
毎朝、元気いっぱいに晴を起こしに来るのは、もう当たり前の光景だった。
そんな彼女と同じ高校に進学した――はずだったのに。
数ヶ月後、晴のクラスに転校してきたのは、まさかの“全国で人気の高校生アイドル”黒瀬紗耶。
平凡な高校生活を過ごしたいだけの晴の願いとは裏腹に、
幼馴染とアイドル、二人の存在が彼の日常をどんどんかき回していく。
笑って、悩んで、ちょっとドキドキ。
気づけば心を奪われる――
幼馴染 vs 転校生、青春ラブコメの火蓋がいま切られる!

怪我でサッカーを辞めた天才は、高校で熱狂的なファンから勧誘責めに遭う
もぐのすけ
青春
神童と言われた天才サッカー少年は中学時代、日本クラブユースサッカー選手権、高円宮杯においてクラブを二連覇させる大活躍を見せた。
将来はプロ確実と言われていた彼だったが中学3年のクラブユース選手権の予選において、選手生命が絶たれる程の大怪我を負ってしまう。
サッカーが出来なくなることで激しく落ち込む彼だったが、幼馴染の手助けを得て立ち上がり、高校生活という新しい未来に向かって歩き出す。
そんな中、高校で中学時代の高坂修斗を知る人達がここぞとばかりに部活や生徒会へ勧誘し始める。
サッカーを辞めても一部の人からは依然として評価の高い彼と、人気な彼の姿にヤキモキする幼馴染、それを取り巻く友人達との刺激的な高校生活が始まる。

むっつり金持ち高校生、巨乳美少女たちに囲まれて学園ハーレム
ピコサイクス
青春
顔は普通、性格も地味。
けれど実は金持ちな高校一年生――俺、朝倉健斗。
学校では埋もれキャラのはずなのに、なぜか周りは巨乳美女ばかり!?
大学生の家庭教師、年上メイド、同級生ギャルに清楚系美少女……。
真面目な御曹司を演じつつ、内心はむっつりスケベ。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















