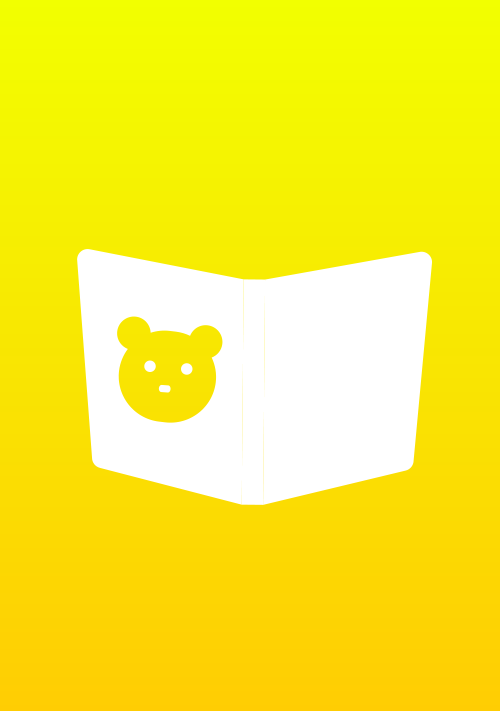13 / 23
川下りにて
しおりを挟む
トーナメントまであと数週間というある日。グラジオ、ロベリア両王家の交流機会として、川下りが催されることになった。グラジオで最も大きい大河の上流、流れの緩やかな場所で両国の王侯貴族たちが舟に乗る順番を待っている。
薄手のカーテンがかけられ、たくさんの花が飾られた舟たちは、まるで水に浮く花籠のようだ。薄紫色に染まった夕暮れの中、アリシアはバーベナの手をひきつつ、ガーネットと護衛の兵とともに船に乗り込む。若い二人の邪魔はせぬようにとの計らいで、この舟には他の王族も貴族も乗っていない。
舟に腰を落ち着けると、バーベナは楽しそうにあちこちに視線をやり、用意された菓子を細かく砕くと、舟の外に撒き始めた。
「何をしているのバーベナ」
アリシアがそう問えば、バーベナは含みのある表情で答える。
「お魚に餌をあげているの」
ふふ、とイタズラな笑みを浮かべるバーベナはとても可愛らしい。この人物があんなに勇ましい立ち回りをする男だとは、誰も信じないだろう。
めんどくさいだのなんだの言いながら、彼はあれから毎晩、アリシアに稽古をつけてくれている。
「……バーベナ、近い」
「あら王子、夫婦になるのですから、こういう距離感にも慣れていかないと」
魚に餌をやるのに飽きると、バーベナはアリシアに体を寄せてきた。
カサブランカの香りが鼻をくすぐる。バーベナの香水の匂いだ。女の自分よりもいい匂いがする気がする。だけど預けられた体にはしっかりと筋肉がついていて、異性であることを意識させられる。
伸びてきた手がアリシアの頬に触れた。微笑みかけられれば、紫の瞳から目を離すことができない。
アリシアが頬を染め、困った顔をすれば、バーベナは悪女のような笑顔を向け、顔を寄せてくる。
「このほうが内緒話もしやすいだろ」
「まあ、そうだけどさ」
耳に囁かれる声がくすぐったい。心臓の鼓動がうるさくなり響いている。
額にキスをされたあの日から、バーベナは隙あらばアリシアに触れてくるようになった。まるで本物の恋人のような振る舞いに、翻弄されっぱなしで。硬直して動けなくなれば、「アリシアは俺に触ってくれないの?」と拗ねた顔をされる。
気を紛らわそうと川の方に目を向ければ、花に彩られた他の王族が乗った舟が、幾つも川面を滑って行くのが見える。小舟に乗ったランプが朧げな光で辺りを照し、幻想的な風景を演出していた。
「アラン王子。今宵は月が綺麗ですね。ロベリアの果実酒を用意させましたの。月を眺めながら一緒にお召しになりませんか」
「……もらおう」
女声で言うバーベナに、極力王子を意識した返答で応える。だがやはり違和感があるらしい。目の前にいる彼は頬を膨らませ、必死に笑いを堪えている。
自分が姫で、彼が王子だったら、もっとロマンチックだったのにな、とアリシアは思う。ノアのせいで男性とデートをする機会は一生奪われてしまったが、本当なら一度くらい甘酸っぱい体験をしてみたかった。
細かな金の装飾が入ったガラスのワイングラスに、赤い果実酒をガーネットが注ぐ。それをバーベナが受け取ると、彼は何を思ったか、ぐいと腕を伸ばしてグラスを船の外に出し、餌をもらえると思って水面で口をパクパクとさせている魚向けて中身を流す。
ギョッとして川面に目をやれば、魚が腹を見せて水面に浮き上がってくるところだった。
「毒だな」
ボソリとそう言ったバーベナの言葉に反応し、アリシアも小声で答える。
「えっ! お酒で死んだんじゃなくて?」
「酒で即死はねえだろ。相当強い毒が入ってたんだと思う。あぶねー。このままあんたに飲ませてたら、俺が殺人犯になるところだ」
「いったい誰が……」
酒をついだのは同じ舟に乗っているガーネットだ。だが彼女はバーベナの協力者である。ではグラスを用意した人間の仕業だろうか。眉間に皺寄せ、頭を捻りながら、ふと視線を川岸に向けた、その時。
「バーベナ、伏せて!」
弓を構えた男がこちらを狙っているのが見えた。咄嗟にアリシアは足を舟縁にかけ、剣を抜く。直後に飛んできた弓矢を、全身の神経を集中させて薙ぎ払った。
「川岸の木の上に怪しい男がいる! 弓矢を持っているぞ!」
アリシアがそう叫べば、慌ただしく兵士がその場に向かっていく。
不審者はすぐに捕まったが、捕えられた男は毒を飲んでおり、尋問をする前に死んでしまった。
そして悪いことに、男はロベリアの鎧を纏っていたのだ。
薄手のカーテンがかけられ、たくさんの花が飾られた舟たちは、まるで水に浮く花籠のようだ。薄紫色に染まった夕暮れの中、アリシアはバーベナの手をひきつつ、ガーネットと護衛の兵とともに船に乗り込む。若い二人の邪魔はせぬようにとの計らいで、この舟には他の王族も貴族も乗っていない。
舟に腰を落ち着けると、バーベナは楽しそうにあちこちに視線をやり、用意された菓子を細かく砕くと、舟の外に撒き始めた。
「何をしているのバーベナ」
アリシアがそう問えば、バーベナは含みのある表情で答える。
「お魚に餌をあげているの」
ふふ、とイタズラな笑みを浮かべるバーベナはとても可愛らしい。この人物があんなに勇ましい立ち回りをする男だとは、誰も信じないだろう。
めんどくさいだのなんだの言いながら、彼はあれから毎晩、アリシアに稽古をつけてくれている。
「……バーベナ、近い」
「あら王子、夫婦になるのですから、こういう距離感にも慣れていかないと」
魚に餌をやるのに飽きると、バーベナはアリシアに体を寄せてきた。
カサブランカの香りが鼻をくすぐる。バーベナの香水の匂いだ。女の自分よりもいい匂いがする気がする。だけど預けられた体にはしっかりと筋肉がついていて、異性であることを意識させられる。
伸びてきた手がアリシアの頬に触れた。微笑みかけられれば、紫の瞳から目を離すことができない。
アリシアが頬を染め、困った顔をすれば、バーベナは悪女のような笑顔を向け、顔を寄せてくる。
「このほうが内緒話もしやすいだろ」
「まあ、そうだけどさ」
耳に囁かれる声がくすぐったい。心臓の鼓動がうるさくなり響いている。
額にキスをされたあの日から、バーベナは隙あらばアリシアに触れてくるようになった。まるで本物の恋人のような振る舞いに、翻弄されっぱなしで。硬直して動けなくなれば、「アリシアは俺に触ってくれないの?」と拗ねた顔をされる。
気を紛らわそうと川の方に目を向ければ、花に彩られた他の王族が乗った舟が、幾つも川面を滑って行くのが見える。小舟に乗ったランプが朧げな光で辺りを照し、幻想的な風景を演出していた。
「アラン王子。今宵は月が綺麗ですね。ロベリアの果実酒を用意させましたの。月を眺めながら一緒にお召しになりませんか」
「……もらおう」
女声で言うバーベナに、極力王子を意識した返答で応える。だがやはり違和感があるらしい。目の前にいる彼は頬を膨らませ、必死に笑いを堪えている。
自分が姫で、彼が王子だったら、もっとロマンチックだったのにな、とアリシアは思う。ノアのせいで男性とデートをする機会は一生奪われてしまったが、本当なら一度くらい甘酸っぱい体験をしてみたかった。
細かな金の装飾が入ったガラスのワイングラスに、赤い果実酒をガーネットが注ぐ。それをバーベナが受け取ると、彼は何を思ったか、ぐいと腕を伸ばしてグラスを船の外に出し、餌をもらえると思って水面で口をパクパクとさせている魚向けて中身を流す。
ギョッとして川面に目をやれば、魚が腹を見せて水面に浮き上がってくるところだった。
「毒だな」
ボソリとそう言ったバーベナの言葉に反応し、アリシアも小声で答える。
「えっ! お酒で死んだんじゃなくて?」
「酒で即死はねえだろ。相当強い毒が入ってたんだと思う。あぶねー。このままあんたに飲ませてたら、俺が殺人犯になるところだ」
「いったい誰が……」
酒をついだのは同じ舟に乗っているガーネットだ。だが彼女はバーベナの協力者である。ではグラスを用意した人間の仕業だろうか。眉間に皺寄せ、頭を捻りながら、ふと視線を川岸に向けた、その時。
「バーベナ、伏せて!」
弓を構えた男がこちらを狙っているのが見えた。咄嗟にアリシアは足を舟縁にかけ、剣を抜く。直後に飛んできた弓矢を、全身の神経を集中させて薙ぎ払った。
「川岸の木の上に怪しい男がいる! 弓矢を持っているぞ!」
アリシアがそう叫べば、慌ただしく兵士がその場に向かっていく。
不審者はすぐに捕まったが、捕えられた男は毒を飲んでおり、尋問をする前に死んでしまった。
そして悪いことに、男はロベリアの鎧を纏っていたのだ。
応援ありがとうございます!
0
お気に入りに追加
6
1 / 2
この作品を読んでいる人はこんな作品も読んでいます!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる