14 / 21
第三章 出版
夏①
しおりを挟む
2 夏
雲が流れていくように、月日も流れていった。最近は六月も、容赦なく夏が襲い掛かる。
あれからまた一ヵ月ほど経ったが、奏さんとは会っていない。レポートなどは提出しに来ているようだったので、最低限の生活は保てているようだったが、話しかけることはできなかった。
むしろ今は、私の生活の方が危ないかもしれない。
「本日のゲストは、最近ネット上で話題の恋愛小説の作者・五木あおいさんです!」
「よろしくお願いしまーす!」
正午になって漸く起床し、そのまま無意識に点けていたテレビから、聞き覚えのある名前と、聞き覚えのない声が流れてきた。
「本日はお忙しいところ、わざわざお越しくださいまして、本当にありがとうございます!」
「いえいえ~! 私もテレビに出られるなんて思ってなかったので、本当に嬉しいです!」
もはや、チャンネルを変える気力も、テレビを消してベッドに舞い戻る気力もない。このような状態になっている一番の原因を目の当たりにしても、全くもって感情が動かない。
この一ヵ月、私は体調を崩し、ずっとこんな調子だった。講義は休みがちになり、バイトも何回か休んだ。しかもその流れというか勢いで、何一つ不満のなかったそのバイト先を辞めるまでに至った。そのため先輩とは会いづらくなり、同じ学科の友人とも、段々と距離を置くようになってしまった。一度実家に帰るという選択肢もあったが、そもそも今は、アパートから出る気にならなかった。
「五木さんの小説、私も読ませていただきました! 本当に素晴らしい作品ですね!」
「そんなー、それほどでもないですよ~」
「今度、書籍化もされるそうですね?」
「そうなんですよ~。まだだいぶ先なんですけど、本当に、読者の皆様のお陰です!」
止めには、大槻さんから連絡がきた。もう内容は見当がついていると思うが、追い打ちのように、今度の冬に出版が決まったと言われた。
「主人公は男性ですが、とても心理描写が繊細で衝撃を受けました! その点については難しい部分もありました?」
「ええ、そうですね。やはり異性の心の内を描くのは難しかったですけど、そこは今までの経験とか、いろんな作品を参考にして、なんとか形にすることができました!」
「そうなんですね! それにしても、男女問わずあそこまで共感を呼ぶ文章を書けるのは、日本でも五木さんくらいじゃないでしょうか!?」
彼女と同い年くらいの女性のインタビュアーが、目を輝かせて作品を絶賛する。正直自分でもそれは言い過ぎだと思ったが、当の五木あおいは、何食わぬ顔で絶賛を自分のものにしている。
「執筆していたときは、どのような心境だったのでしょうか?」
思わず、耳だけ傾けていた画面の方に目を向ける。メイクはメディア用の厚いもので覆われ、渋谷や原宿の特集で取り上げられてもおかしくないほどの雰囲気だった。ある意味、それが作品の繊細さとのギャップを生み、違う意味での人気が出そうな気配すらある。実際、一部のファンからはアイドル的存在になっているという話も聞いた。おそらく本人も、そういう扱われ方は満更でもないのだろう。
「正直夢中になって書いていたのであまり覚えていませんが、とにかく、人々に希望を届けたいという一心でした。同じような心境の人の心の支えになりたい、優しい気持ちを全面に表現することで、少しでも世の中全体が優しくなってほしい、そういうことを考えて書いていたのは、よく憶えています!」
自分の中で信じてきた何かが、音を立てて崩れ去っていく。もし何か一つの感情で言い表すなら、それは「怒」ではなく、純粋な「哀」だった。
私が信じていたものが、私を奮い立たせてくれたものが、こんな歪んだ形で利用されている。作品が良ければ作者なんて誰でもいい、自分で発した言葉が、狼の刃のように鋭いブーメランとなって、私を突き刺す。
しかし、私にはどうすることもできない。いくら哀しんだって、あの小説を完成させると誓った決意も、奏さんと過ごしたしっちゃかめっちゃかな日々も、尊さんへの恩返しの想いも、そして、小説が好きだという純粋な心も、もう私には戻ってこない。私の前にあるのは、ただの現実だ。五木あおいが発表した『月が、綺麗ですね。』が人気を博し、出版が決まり、一方私たちに残ったのは、ただ時間と手間を消費した無意義な一年間だった。
いや、違う。尊さんは「無駄なことには決してならない」と言ってくれた。
そうだ。あの作品が完成した冬の日、「月が、綺麗ですね。」の言葉が私たちの作品にピッタリ嵌ったあの情動は、今でも私の中に燃え続けている。今でも、私の心を震え上がらせる。作品はもちろん読者のためでもあるが、自分たちの、作者自身に希望を届ける力だってあるはずだ。何しろ作者とは、その作品を世界中の誰よりも愛する、読者の一人に違いないのだから。
「最後に一つだけいいですか?」
インタビューのコーナーも終わりに差し掛かったところで、五木あおいが改まって声を上げた。
「本当は言いたくなかったのですが、私はある人物から、作品について謂れのない言いがかりをつけられています」
再び自分の中で、湧き上がった何かが崩れ去った。
「言いがかり? どういうことでしょうか?」
「今は詳しいことは言えませんが、簡単に言うと、証拠もないのに私を泥棒扱いする人間がいます。彼らの誹謗中傷に対して、私は断固として戦う姿勢です。もし私を応援してくれるのならば、私と一緒に戦ってくれないでしょうか?」
「それは酷いですね! そんな人間、むしろその人自身が泥棒ですよ! もちろん私は五木さんの味方です! 次回作も楽しみにしてます!」
得意げな顔でカメラを見つめる五木あおいと目が合う。
ああ、私は泥棒なんだ。私たちは、『月が、綺麗ですね。』を愛する人々にとって、憎むべき存在なんだ。
なんで、こうなってしまったんだろう。なんで、こんな気持ちに苦しめられなくてはならないのだろう。それもこれも、あの日、あの部室の前まで行き、ドアを開けてしまったから、なのだろうか。あんなことをしなければ、今でも私は普通の大学生活を送り、普通の日常を送れていた、のだろうか。
とにかく今は何もする気になれない。何かをするにしても、上手くいく気がしない。日常生活も、小説のことも、奏さんとの関係も、何もかも、私の掌からは落ちてしまった。それならいっそ、もう何もかもリセットして、こんな泥沼の世界など忘れて、地元で一からやり直そう。それだって、私の背中を押してくれた人たちは、きっと認めてくれる。そんな人がまさか、この世界にいるとは思えないが。
そんなこんなで、いよいよ限界の底が顔を覗かせ始めたある日曜の昼下がり、突然、スマートフォンが鳴った。
「……はい、もしもし?」
知らない番号からの電話に、警戒した声が出る。
「夏目! 久しぶりだな! 元気だったか!?」
約一年ぶりに聞いたその声は、誰よりも元気で、誰よりも、輝いていた。
「もしかして、先生……?」
もう二度と聞くことなどないと思っていた、あの、清々しい声。
「ごめんな、いきなりかけちゃって。この前西野とも話したんだが、あいつから番号聞いて、元気かなーなんて思って声聞きたくなったんだよ。今、話しても大丈夫か?」
「え、あ、はい! もちろん!」
思わず慌てた声を出してしまう。
「ありがとな! ところで西野から聞いたんだが、夏目、小説書いてるんだって!? すごいじゃないか!」
「え、いやそんな、書いてるだけですし、それに人に見せられるようなものじゃ……」
「そんなことないよ。夏目、進路相談のときに言ってただろう? 将来は小説家になりたいって。正直あのときはビックリしたけど、でもあのときの夏目は本気だって伝わったから、俺、ずっと楽しみにしてたんだ! だから今、実際に小説書いてるって聞いて、すごく嬉しいんだよ!」
「先生……」
あんな一言を覚えてくれていたのもそうだし、この世界に一人でも、本当に私の背中を押してくれる人がいるって聞いただけで、涙腺が崩れそうになる。それが、お世辞だとわかっていても。
「それと、西野のこと、本当にありがとな。本人の前じゃ言えないが、正直、西野が東京行くって聞いて、すごく心配してたんだ。ほら、あいつって、なんて言うか、良い子すぎるだろ? だから色々とトラブル巻き込まれるんじゃないかって心配だったんだけど、夏目が色々助けてくれたって聞いて、本当に嬉しかったよ!」
高校の頃は、全員に同じように愛嬌を振り撒いているなんて卑屈な印象を抱いていたけど、いざ彼の元を離れてみると、彼の凄さがわかる。
先生は本当に、生徒一人一人に向き合って、一人一人のことを考えてくれる、先生の鏡みたいな人なのだと、今になって気付く。
「今はボランティアで忙しいらしいけど、近いうちに会ってやれよ! 西野、本当に夏目に会いたがってたぞ!」
実を言うと、美月から会わないかという連絡は時々来ていた。しかしその度に、適当な嘘をついて、小さな聖域を守ろうとしていた。
「とにかく、今日は話せてよかったよ! これからも小説、頑張るんだぞ! 楽しみにしてるから!」
待って。まだ、私を置いていかないで。
「何か不安とか心配事があるなら、いつでも頼ってくれ! いつでも相談乗るから!」
不安も心配事も、たくさんある。相談したいことも、たくさんある。
それなのに、声が出ない。一番頼りたいときに、一番頼りたい人に、伝えられない。
「ん? 夏目? どうした? ……泣いてるのか?」
これが、最後のチャンスだ。
「……先生」
私が思い描いた未来に辿り着くための、最後の、ターニングポイントだ。
「助けて、ください……」
「……そうか。そんなことがあったのか」
一年ぶりに瞳に映ったその姿は、相変わらず、清々しい。
「それで最近は、どうしてるんだ?」
「……何もしてません。大学も休んで、バイトも辞めて、外にもほとんど出てないです」
「小説も、書いてないのか?」
「……すみません」
「謝ることじゃないよ」
そう言うと先生は、肩に手を置いてくれた。
今、私と先生は、調布にあるファミレスで、向かい合って座っている。あの電話の後、そのまま私に会いに行くと言ってくれたときはさすがに嘘かと思ったが、先生は今年の春から横浜の高校に転任になったらしく、そのため現在はこちらの方に住んでおり、私に会うのに支障はないとのことだった。だとしても、美月といい、久しぶりに電話で話した相手にその日のうちに会おうというのは、さすがの行動力だと感心する。
「奏くんという男の子とも、最近は連絡取ってないのか?」
「……はい。正直、生きているかどうかもわかりません。彼も私にそう思ってると思いますけど」
「そ、そうなのか」
奏さんとのいつものやり取りの癖が出てしまい、若干引かれてしまった。
休日午後のファミレスは思ったより空いており、学生らしき姿もちらほらとあったが、それでも相対的に見れば疎らだった。ちなみに場所が調布になったのは、先生は私のアパートの最寄り駅まで来てくれると言ってくれたが、ご存知の通り、ウチの周りには久しぶりに会う相手を迎えられるお店がほとんどないため、近くのまあまあ大きい駅である調布で手を打つ運びとなった。
「正直、その小説が話題になってることは知らなかったから、あまり立ち入ったことは言えないが、……それにしても酷い話だな。その作家の女と詐欺師の男って奴らは」
「……先生は、信じてくれるんですか?」
「え?」
「だって、私たちが書いたなんて証拠、全くないんですよ? あるのは執筆途中のデータぐらいで、……それも作品が世に出ていれば誰にでも作れるなんて言われて、それで……」
「信じるに決まってるだろ?」
俯いてもいても、先生が真っ直ぐ私を見ているのがわかる。
「夏目は嘘をつくような人間じゃないってことぐらい、俺どころか、君の周りのみんなが知ってるよ」
「先生……」
「それに、君は今、本当に苦しんでいる。そんな感情を心の底から持っている人間が、嘘をついてまでその小説を奪おうなんて考えるはずないだろう? そんな人間がいるとすれば、それこそその詐欺師たちみたいな、人の心が理解できない人間だ。そんな奴らと君が対極にいるってことぐらい、俺は君と出会ったときから知ってるから」
「人の、心……」
前に尊さんが言っていたことが、頭を掠める。
「大丈夫だ。夏目、俺も君たちに全面的に協力する。だから夏目も、もう一回、頑張ってみないか?」
尊さんを心の底から尊敬している気持ちと、どこか重なっている。
「……はい! 先生、私、もう一回頑張りたいです!」
「そうか! ありがとう、夏目」
尊さんの人を包み込むような優しさと、どこか、似ている。
「じゃあ、とりあえず作戦会議だな。そうか、証拠か。……今少し思いついたんだが、奏くんには思い出させるようで悪いんだけど、当時にその小説の画像みたいなものって、出回ったとか聞いてないか?」
「え?」
「ほら、最近はLINEとかでそういうのが拡散されるんだろう? 話聞いただけだと物理的に回し読みされただけかもしれないけど、もし画像とか写真で出回ったなら、データさえ残っていれば証拠になるんじゃないか?」
「なるほど」
その着眼点に関しては、私はどこか避けて考えてしまっていた。
それについて考えていると、奏さんの嫌な思い出が、私の神経を乗っ取ってしまいそうになったから。
「それに関しては、たぶん当時その場にいた人たちじゃないとわからないと思います」
「そうか……。そういえば、夏目のサークルのもう一人の先輩も奏くんと同じ高校なんだろう? 彼なら何かわからないかな?」
「どう、ですかね。尊さんは当時は別のクラスだったらしいので、そこまではわからないかもです」
「そうか……。ん? 今、名前、尊くんって言ったか?」
「え? あ、はい」
先生は何かを思い浮かべ、顎に手を当てた。
「ということは、その彼も中明大学で、今年から就職したってことだよな?」
「そう、ですね」
「参考までに、差し支えなければ彼のフルネーム訊いてもいいか?」
「あ、えっと、柳井尊、さん、だったと思います」
「……すごいよ。こんな偶然もあるんだな」
「え?」
事情が呑み込めず、視線が右往左往する。
「尊くん、俺、知ってるよ。ていうか、この前会ったばかりだ」
「え!? ええー!!」
図らずも、周りの注目を集めるほどの声が出た。
「すごい偶然だよ! こんなことってあるんだな!」
色々な箇所を抑えつつ、奇跡を身体に流し込む。
「ちなみに、どこで知り合われたんですか!?」
「ああ、彼、この前ウチの高校に取材に来たんだよ。まだ研修中だったらしくて色々やらされてたんだけど、その分俺たちと接する機会も多くてさ。彼、すごく面白いだろ? だから生徒ともすぐ仲良くなって、俺もたくさん話したんだよ。大学訊いたら中明大学って言うんで、前の学校の生徒が去年入ったから会ってるかもなんて話もして、もちろん夏目のことだけど、しかし、こんな奇跡みたいなことってあるんだな!」
紛うことなき、尊さんだ。
先ほどから感じていた彼の幻影は、もしかしたら、天使の施しだったのかもしれない。
「そうか、そうかそうか。尊くんは夏目の先輩だったのか」
「はい。それも、とてもお世話になって、本当に、とても尊敬している人なんです! 今の私があるのも、あの人がいなかったらありえないくらい!」
「そうか。彼は、君の恩人なんだな」
先生は大きく頷き、息を目一杯吸いこんだ。
「よし、決めた。改めて、作戦会議をやろう!」
「え?」
そのがっしりとした身体を使い、今までで一番、明るい声で言った。
「俺に、良い作戦がある!」
雲が流れていくように、月日も流れていった。最近は六月も、容赦なく夏が襲い掛かる。
あれからまた一ヵ月ほど経ったが、奏さんとは会っていない。レポートなどは提出しに来ているようだったので、最低限の生活は保てているようだったが、話しかけることはできなかった。
むしろ今は、私の生活の方が危ないかもしれない。
「本日のゲストは、最近ネット上で話題の恋愛小説の作者・五木あおいさんです!」
「よろしくお願いしまーす!」
正午になって漸く起床し、そのまま無意識に点けていたテレビから、聞き覚えのある名前と、聞き覚えのない声が流れてきた。
「本日はお忙しいところ、わざわざお越しくださいまして、本当にありがとうございます!」
「いえいえ~! 私もテレビに出られるなんて思ってなかったので、本当に嬉しいです!」
もはや、チャンネルを変える気力も、テレビを消してベッドに舞い戻る気力もない。このような状態になっている一番の原因を目の当たりにしても、全くもって感情が動かない。
この一ヵ月、私は体調を崩し、ずっとこんな調子だった。講義は休みがちになり、バイトも何回か休んだ。しかもその流れというか勢いで、何一つ不満のなかったそのバイト先を辞めるまでに至った。そのため先輩とは会いづらくなり、同じ学科の友人とも、段々と距離を置くようになってしまった。一度実家に帰るという選択肢もあったが、そもそも今は、アパートから出る気にならなかった。
「五木さんの小説、私も読ませていただきました! 本当に素晴らしい作品ですね!」
「そんなー、それほどでもないですよ~」
「今度、書籍化もされるそうですね?」
「そうなんですよ~。まだだいぶ先なんですけど、本当に、読者の皆様のお陰です!」
止めには、大槻さんから連絡がきた。もう内容は見当がついていると思うが、追い打ちのように、今度の冬に出版が決まったと言われた。
「主人公は男性ですが、とても心理描写が繊細で衝撃を受けました! その点については難しい部分もありました?」
「ええ、そうですね。やはり異性の心の内を描くのは難しかったですけど、そこは今までの経験とか、いろんな作品を参考にして、なんとか形にすることができました!」
「そうなんですね! それにしても、男女問わずあそこまで共感を呼ぶ文章を書けるのは、日本でも五木さんくらいじゃないでしょうか!?」
彼女と同い年くらいの女性のインタビュアーが、目を輝かせて作品を絶賛する。正直自分でもそれは言い過ぎだと思ったが、当の五木あおいは、何食わぬ顔で絶賛を自分のものにしている。
「執筆していたときは、どのような心境だったのでしょうか?」
思わず、耳だけ傾けていた画面の方に目を向ける。メイクはメディア用の厚いもので覆われ、渋谷や原宿の特集で取り上げられてもおかしくないほどの雰囲気だった。ある意味、それが作品の繊細さとのギャップを生み、違う意味での人気が出そうな気配すらある。実際、一部のファンからはアイドル的存在になっているという話も聞いた。おそらく本人も、そういう扱われ方は満更でもないのだろう。
「正直夢中になって書いていたのであまり覚えていませんが、とにかく、人々に希望を届けたいという一心でした。同じような心境の人の心の支えになりたい、優しい気持ちを全面に表現することで、少しでも世の中全体が優しくなってほしい、そういうことを考えて書いていたのは、よく憶えています!」
自分の中で信じてきた何かが、音を立てて崩れ去っていく。もし何か一つの感情で言い表すなら、それは「怒」ではなく、純粋な「哀」だった。
私が信じていたものが、私を奮い立たせてくれたものが、こんな歪んだ形で利用されている。作品が良ければ作者なんて誰でもいい、自分で発した言葉が、狼の刃のように鋭いブーメランとなって、私を突き刺す。
しかし、私にはどうすることもできない。いくら哀しんだって、あの小説を完成させると誓った決意も、奏さんと過ごしたしっちゃかめっちゃかな日々も、尊さんへの恩返しの想いも、そして、小説が好きだという純粋な心も、もう私には戻ってこない。私の前にあるのは、ただの現実だ。五木あおいが発表した『月が、綺麗ですね。』が人気を博し、出版が決まり、一方私たちに残ったのは、ただ時間と手間を消費した無意義な一年間だった。
いや、違う。尊さんは「無駄なことには決してならない」と言ってくれた。
そうだ。あの作品が完成した冬の日、「月が、綺麗ですね。」の言葉が私たちの作品にピッタリ嵌ったあの情動は、今でも私の中に燃え続けている。今でも、私の心を震え上がらせる。作品はもちろん読者のためでもあるが、自分たちの、作者自身に希望を届ける力だってあるはずだ。何しろ作者とは、その作品を世界中の誰よりも愛する、読者の一人に違いないのだから。
「最後に一つだけいいですか?」
インタビューのコーナーも終わりに差し掛かったところで、五木あおいが改まって声を上げた。
「本当は言いたくなかったのですが、私はある人物から、作品について謂れのない言いがかりをつけられています」
再び自分の中で、湧き上がった何かが崩れ去った。
「言いがかり? どういうことでしょうか?」
「今は詳しいことは言えませんが、簡単に言うと、証拠もないのに私を泥棒扱いする人間がいます。彼らの誹謗中傷に対して、私は断固として戦う姿勢です。もし私を応援してくれるのならば、私と一緒に戦ってくれないでしょうか?」
「それは酷いですね! そんな人間、むしろその人自身が泥棒ですよ! もちろん私は五木さんの味方です! 次回作も楽しみにしてます!」
得意げな顔でカメラを見つめる五木あおいと目が合う。
ああ、私は泥棒なんだ。私たちは、『月が、綺麗ですね。』を愛する人々にとって、憎むべき存在なんだ。
なんで、こうなってしまったんだろう。なんで、こんな気持ちに苦しめられなくてはならないのだろう。それもこれも、あの日、あの部室の前まで行き、ドアを開けてしまったから、なのだろうか。あんなことをしなければ、今でも私は普通の大学生活を送り、普通の日常を送れていた、のだろうか。
とにかく今は何もする気になれない。何かをするにしても、上手くいく気がしない。日常生活も、小説のことも、奏さんとの関係も、何もかも、私の掌からは落ちてしまった。それならいっそ、もう何もかもリセットして、こんな泥沼の世界など忘れて、地元で一からやり直そう。それだって、私の背中を押してくれた人たちは、きっと認めてくれる。そんな人がまさか、この世界にいるとは思えないが。
そんなこんなで、いよいよ限界の底が顔を覗かせ始めたある日曜の昼下がり、突然、スマートフォンが鳴った。
「……はい、もしもし?」
知らない番号からの電話に、警戒した声が出る。
「夏目! 久しぶりだな! 元気だったか!?」
約一年ぶりに聞いたその声は、誰よりも元気で、誰よりも、輝いていた。
「もしかして、先生……?」
もう二度と聞くことなどないと思っていた、あの、清々しい声。
「ごめんな、いきなりかけちゃって。この前西野とも話したんだが、あいつから番号聞いて、元気かなーなんて思って声聞きたくなったんだよ。今、話しても大丈夫か?」
「え、あ、はい! もちろん!」
思わず慌てた声を出してしまう。
「ありがとな! ところで西野から聞いたんだが、夏目、小説書いてるんだって!? すごいじゃないか!」
「え、いやそんな、書いてるだけですし、それに人に見せられるようなものじゃ……」
「そんなことないよ。夏目、進路相談のときに言ってただろう? 将来は小説家になりたいって。正直あのときはビックリしたけど、でもあのときの夏目は本気だって伝わったから、俺、ずっと楽しみにしてたんだ! だから今、実際に小説書いてるって聞いて、すごく嬉しいんだよ!」
「先生……」
あんな一言を覚えてくれていたのもそうだし、この世界に一人でも、本当に私の背中を押してくれる人がいるって聞いただけで、涙腺が崩れそうになる。それが、お世辞だとわかっていても。
「それと、西野のこと、本当にありがとな。本人の前じゃ言えないが、正直、西野が東京行くって聞いて、すごく心配してたんだ。ほら、あいつって、なんて言うか、良い子すぎるだろ? だから色々とトラブル巻き込まれるんじゃないかって心配だったんだけど、夏目が色々助けてくれたって聞いて、本当に嬉しかったよ!」
高校の頃は、全員に同じように愛嬌を振り撒いているなんて卑屈な印象を抱いていたけど、いざ彼の元を離れてみると、彼の凄さがわかる。
先生は本当に、生徒一人一人に向き合って、一人一人のことを考えてくれる、先生の鏡みたいな人なのだと、今になって気付く。
「今はボランティアで忙しいらしいけど、近いうちに会ってやれよ! 西野、本当に夏目に会いたがってたぞ!」
実を言うと、美月から会わないかという連絡は時々来ていた。しかしその度に、適当な嘘をついて、小さな聖域を守ろうとしていた。
「とにかく、今日は話せてよかったよ! これからも小説、頑張るんだぞ! 楽しみにしてるから!」
待って。まだ、私を置いていかないで。
「何か不安とか心配事があるなら、いつでも頼ってくれ! いつでも相談乗るから!」
不安も心配事も、たくさんある。相談したいことも、たくさんある。
それなのに、声が出ない。一番頼りたいときに、一番頼りたい人に、伝えられない。
「ん? 夏目? どうした? ……泣いてるのか?」
これが、最後のチャンスだ。
「……先生」
私が思い描いた未来に辿り着くための、最後の、ターニングポイントだ。
「助けて、ください……」
「……そうか。そんなことがあったのか」
一年ぶりに瞳に映ったその姿は、相変わらず、清々しい。
「それで最近は、どうしてるんだ?」
「……何もしてません。大学も休んで、バイトも辞めて、外にもほとんど出てないです」
「小説も、書いてないのか?」
「……すみません」
「謝ることじゃないよ」
そう言うと先生は、肩に手を置いてくれた。
今、私と先生は、調布にあるファミレスで、向かい合って座っている。あの電話の後、そのまま私に会いに行くと言ってくれたときはさすがに嘘かと思ったが、先生は今年の春から横浜の高校に転任になったらしく、そのため現在はこちらの方に住んでおり、私に会うのに支障はないとのことだった。だとしても、美月といい、久しぶりに電話で話した相手にその日のうちに会おうというのは、さすがの行動力だと感心する。
「奏くんという男の子とも、最近は連絡取ってないのか?」
「……はい。正直、生きているかどうかもわかりません。彼も私にそう思ってると思いますけど」
「そ、そうなのか」
奏さんとのいつものやり取りの癖が出てしまい、若干引かれてしまった。
休日午後のファミレスは思ったより空いており、学生らしき姿もちらほらとあったが、それでも相対的に見れば疎らだった。ちなみに場所が調布になったのは、先生は私のアパートの最寄り駅まで来てくれると言ってくれたが、ご存知の通り、ウチの周りには久しぶりに会う相手を迎えられるお店がほとんどないため、近くのまあまあ大きい駅である調布で手を打つ運びとなった。
「正直、その小説が話題になってることは知らなかったから、あまり立ち入ったことは言えないが、……それにしても酷い話だな。その作家の女と詐欺師の男って奴らは」
「……先生は、信じてくれるんですか?」
「え?」
「だって、私たちが書いたなんて証拠、全くないんですよ? あるのは執筆途中のデータぐらいで、……それも作品が世に出ていれば誰にでも作れるなんて言われて、それで……」
「信じるに決まってるだろ?」
俯いてもいても、先生が真っ直ぐ私を見ているのがわかる。
「夏目は嘘をつくような人間じゃないってことぐらい、俺どころか、君の周りのみんなが知ってるよ」
「先生……」
「それに、君は今、本当に苦しんでいる。そんな感情を心の底から持っている人間が、嘘をついてまでその小説を奪おうなんて考えるはずないだろう? そんな人間がいるとすれば、それこそその詐欺師たちみたいな、人の心が理解できない人間だ。そんな奴らと君が対極にいるってことぐらい、俺は君と出会ったときから知ってるから」
「人の、心……」
前に尊さんが言っていたことが、頭を掠める。
「大丈夫だ。夏目、俺も君たちに全面的に協力する。だから夏目も、もう一回、頑張ってみないか?」
尊さんを心の底から尊敬している気持ちと、どこか重なっている。
「……はい! 先生、私、もう一回頑張りたいです!」
「そうか! ありがとう、夏目」
尊さんの人を包み込むような優しさと、どこか、似ている。
「じゃあ、とりあえず作戦会議だな。そうか、証拠か。……今少し思いついたんだが、奏くんには思い出させるようで悪いんだけど、当時にその小説の画像みたいなものって、出回ったとか聞いてないか?」
「え?」
「ほら、最近はLINEとかでそういうのが拡散されるんだろう? 話聞いただけだと物理的に回し読みされただけかもしれないけど、もし画像とか写真で出回ったなら、データさえ残っていれば証拠になるんじゃないか?」
「なるほど」
その着眼点に関しては、私はどこか避けて考えてしまっていた。
それについて考えていると、奏さんの嫌な思い出が、私の神経を乗っ取ってしまいそうになったから。
「それに関しては、たぶん当時その場にいた人たちじゃないとわからないと思います」
「そうか……。そういえば、夏目のサークルのもう一人の先輩も奏くんと同じ高校なんだろう? 彼なら何かわからないかな?」
「どう、ですかね。尊さんは当時は別のクラスだったらしいので、そこまではわからないかもです」
「そうか……。ん? 今、名前、尊くんって言ったか?」
「え? あ、はい」
先生は何かを思い浮かべ、顎に手を当てた。
「ということは、その彼も中明大学で、今年から就職したってことだよな?」
「そう、ですね」
「参考までに、差し支えなければ彼のフルネーム訊いてもいいか?」
「あ、えっと、柳井尊、さん、だったと思います」
「……すごいよ。こんな偶然もあるんだな」
「え?」
事情が呑み込めず、視線が右往左往する。
「尊くん、俺、知ってるよ。ていうか、この前会ったばかりだ」
「え!? ええー!!」
図らずも、周りの注目を集めるほどの声が出た。
「すごい偶然だよ! こんなことってあるんだな!」
色々な箇所を抑えつつ、奇跡を身体に流し込む。
「ちなみに、どこで知り合われたんですか!?」
「ああ、彼、この前ウチの高校に取材に来たんだよ。まだ研修中だったらしくて色々やらされてたんだけど、その分俺たちと接する機会も多くてさ。彼、すごく面白いだろ? だから生徒ともすぐ仲良くなって、俺もたくさん話したんだよ。大学訊いたら中明大学って言うんで、前の学校の生徒が去年入ったから会ってるかもなんて話もして、もちろん夏目のことだけど、しかし、こんな奇跡みたいなことってあるんだな!」
紛うことなき、尊さんだ。
先ほどから感じていた彼の幻影は、もしかしたら、天使の施しだったのかもしれない。
「そうか、そうかそうか。尊くんは夏目の先輩だったのか」
「はい。それも、とてもお世話になって、本当に、とても尊敬している人なんです! 今の私があるのも、あの人がいなかったらありえないくらい!」
「そうか。彼は、君の恩人なんだな」
先生は大きく頷き、息を目一杯吸いこんだ。
「よし、決めた。改めて、作戦会議をやろう!」
「え?」
そのがっしりとした身体を使い、今までで一番、明るい声で言った。
「俺に、良い作戦がある!」
0
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

クラスのマドンナがなぜか俺のメイドになっていた件について
沢田美
恋愛
名家の御曹司として何不自由ない生活を送りながらも、内気で陰気な性格のせいで孤独に生きてきた裕貴真一郎(ゆうき しんいちろう)。
かつてのいじめが原因で、彼は1年間も学校から遠ざかっていた。
しかし、久しぶりに登校したその日――彼は運命の出会いを果たす。
現れたのは、まるで絵から飛び出してきたかのような美少女。
その瞳にはどこかミステリアスな輝きが宿り、真一郎の心をかき乱していく。
「今日から私、あなたのメイドになります!」
なんと彼女は、突然メイドとして彼の家で働くことに!?
謎めいた美少女と陰キャ御曹司の、予測不能な主従ラブコメが幕を開ける!
カクヨム、小説家になろうの方でも連載しています!

迷子を助けたら生徒会長の婚約者兼女の子のパパになったけど別れたはずの彼女もなぜか近づいてくる
九戸政景
恋愛
新年に初詣に来た父川冬矢は、迷子になっていた頼母木茉莉を助け、従姉妹の田母神真夏と知り合う。その後、真夏と再会した冬矢は真夏の婚約者兼茉莉の父親になってほしいと頼まれる。
※こちらは、カクヨムやエブリスタでも公開している作品です。

至れり尽くせり!僕専用メイドの全員が溺愛してくる件
こうたろ
青春
普通の大学生・佐藤健太は目覚めると、自宅が豪華な洋館に変わり10人の美人メイドたちに「お目覚めですか、ご主人様?」と一斉に迎えられる。いつの間にか彼らの“専属主人”になっていた健太は戸惑う間もなく、朝から晩までメイドたちの超至れり尽くせりな奉仕を受け始める。

わたしの下着 母の私をBBA~と呼ぶことのある息子がまさか...
MisakiNonagase
青春
39才の母・真知子は息子が私の下着を持ち出していることに気づいた。
ネットで同様の事象がないか調べると、案外多いようだ。
さて、真知子は息子を問い詰める? それとも気づかないふりを続けてあげるか?
そのほかに外伝も綴りました。

まずはお嫁さんからお願いします。
桜庭かなめ
恋愛
高校3年生の長瀬和真のクラスには、有栖川優奈という女子生徒がいる。優奈は成績優秀で容姿端麗、温厚な性格と誰にでも敬語で話すことから、学年や性別を問わず人気を集めている。和真は優奈とはこの2年間で挨拶や、バイト先のドーナッツ屋で接客する程度の関わりだった。
4月の終わり頃。バイト中に店舗の入口前の掃除をしているとき、和真は老齢の男性のスマホを見つける。その男性は優奈の祖父であり、日本有数の企業グループである有栖川グループの会長・有栖川総一郎だった。
総一郎は自分のスマホを見つけてくれた和真をとても気に入り、孫娘の優奈とクラスメイトであること、優奈も和真も18歳であることから優奈との結婚を申し出る。
いきなりの結婚打診に和真は困惑する。ただ、有栖川家の説得や、優奈が和真の印象が良く「結婚していい」「いつかは両親や祖父母のような好き合える夫婦になりたい」と思っていることを知り、和真は結婚を受け入れる。
デート、学校生活、新居での2人での新婚生活などを経て、和真と優奈の距離が近づいていく。交際なしで結婚した高校生の男女が、好き合える夫婦になるまでの温かくて甘いラブコメディ!
※特別編7が完結しました!(2026.1.29)
※小説家になろうとカクヨムでも公開しています。
※お気に入り登録、感想をお待ちしております。
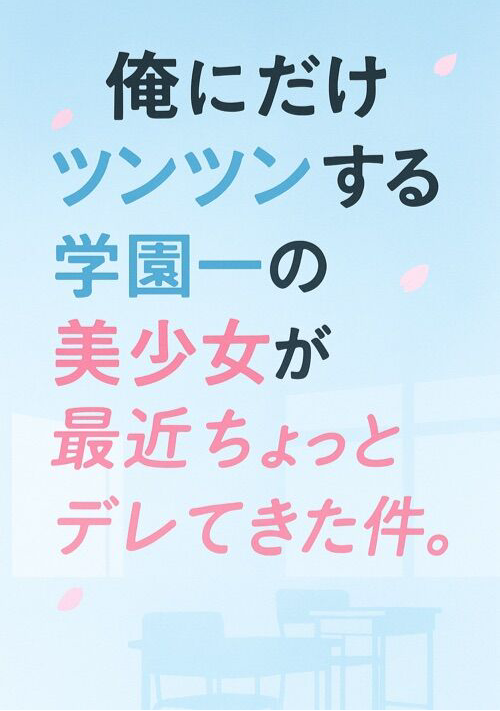
俺にだけツンツンする学園一の美少女が、最近ちょっとデレてきた件。
甘酢ニノ
恋愛
彼女いない歴=年齢の高校生・相沢蓮。
平凡な日々を送る彼の前に立ちはだかるのは──
学園一の美少女・黒瀬葵。
なぜか彼女は、俺にだけやたらとツンツンしてくる。
冷たくて、意地っ張りで、でも時々見せるその“素”が、どうしようもなく気になる。
最初はただの勘違いだったはずの関係。
けれど、小さな出来事の積み重ねが、少しずつ2人の距離を変えていく。
ツンデレな彼女と、不器用な俺がすれ違いながら少しずつ近づく、
焦れったくて甘酸っぱい、青春ラブコメディ。

友達の妹が、入浴してる。
つきのはい
恋愛
「交換してみない?」
冴えない高校生の藤堂夏弥は、親友のオシャレでモテまくり同級生、鈴川洋平にバカげた話を持ちかけられる。
それは、お互い現在同居中の妹達、藤堂秋乃と鈴川美咲を交換して生活しようというものだった。
鈴川美咲は、美男子の洋平に勝るとも劣らない美少女なのだけれど、男子に嫌悪感を示し、夏弥とも形式的な会話しかしなかった。
冴えない男子と冷めがちな女子の距離感が、二人暮らしのなかで徐々に変わっていく。
そんなラブコメディです。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















