47 / 80
夜会と視線 3
しおりを挟む
シェルニティは、顔を上げているが、やはり緊張しているようだ。
彼の腕にかけた手に、力が入っている。
その手に、彼女に貸していないほうの手を乗せ、微笑んでみせた。
シェルニティも、微笑み返してくる。
人の目など気にする必要はない。
彼は、そう言ったが、本人にとって、それが難しいことだとは、わかっていた。
まるきり気にせずにいる、ということはできないだろう。
だとしても、シェルニティは、精一杯、頑張っている。
今まで、実践することはなかったらしいが、さすがに、きっちりとした貴族教育を受けているのがわかるくらい、堂々としていた。
「こ、公爵様」
転がるようにして駆け寄ってきたのは、イノックエルだ。
彼が贈ったタイピンをつけている。
隣にいる妻、すなわちシェルニティの母も、髪飾りをつけていた。
薄く透明感のある紫の宝石が、それぞれに、はめこまれている。
シェルニティに話した通り、お手製の宝石だ。
地中深くから取り出した素材に圧力を加え鉱石とし、それを原石に造った。
空気や砂礫からでも、彼は、魔術を使い、素材にすることができるのだ。
実際、どんな高級店で売られている宝石より、希少価値は高い。
さりとて、売るつもりで造ったことがないため「相場」はないのだけれども。
「やあ、イノックエル。ロゼッティは、初めて顔を合わせるね」
「は、はい……む、娘が、お世話になって、おります……」
耳をすませていなければ聞こえないほど、小さな声で、シェルニティの母親が、頭を下げる。
瞳の色や顔立ちは、なんとなくシェルニティに似ていた。
ただ、赤毛の髪や雰囲気は、まったく似ていない。
イノックエルと似たところと言えば、耳の形くらいだし。
(彼女は、過去の様々な血筋から、いいところを選りすぐって産まれたのかもしれないな。とても、この2人の血だけとは思えない)
血の流れには、不思議なものがある。
彼自身が、それを、身を持って体験していた。
子は親に似るものではあるが、それ以外の要素も複雑に絡み合っている。
どこで、過去からの血が呼び覚まされるか、わからないのだ。
「お世話なんてしちゃいないさ。彼女といると、毎日が楽しくてね。ここ数年の鬱々とした気分が吹き飛んでしまったよ」
「そ、そう仰っていただけると、私どもも、嬉しく……」
2人は、彼の隣にシェルニティがいるにもかかわらず、見ようとしていない。
ちきっと苛立ちが走るが、我慢する。
せっかくの夜だ。
2人に冷や汗をかかせて終わりにする気はなかった。
「いい夜だ、そう思うだろう、イノックエル」
「ええ、はい、もちろん……」
「私たちのことは気にせず、楽しむがいいよ。私たちも、そうするのでね」
言って、シェルニティの額に軽く口づける。
それから、2人に、軽く首を傾けてみせた。
イノックエルは、さすがに敏感だ。
彼の「失せろ」という合図を察し、妻と連れ立って、そそくさと離れて行く。
(不愉快な男ではあるが、察しがいいのだけは取柄と言えるな)
隣からの視線に、彼はシェルニティのほうに顔を向けた。
彼女は、彼を見上げている。
「どうかしたかい?」
「2人とも、私に、なにも仰らなかったわ」
「挨拶がなかったのは、確かだね」
「いえ、違うの。夜会に出るなんてって、叱られるとばかり思っていたから」
彼は、左手を伸ばし、指先で、彼女の右頬を撫でる。
周囲の目などおかまいなしだ。
実際、本当に気にしていない。
というより、気にしたことがない。
彼は、人目を気にするのではなく、人目を意識する。
どう見られているかではなく、どう見せるか。
さりとて、今は、それすら、どうでもよかった。
単に、シェルニティを安心させたいと思っている。
「シェリー、きみのご両親も、わかってくれたのじゃないかな? きみを閉じ込めておく理由なんてないってことをね」
「それなら、この先も叱られることはない?」
「ないよ。きっとね」
絶対に、ない。
あの2人は、それを理解したはずだ。
彼らに渡した「品」が、否応なく、思い出させるに違いない。
シェルニティは、ジョザイア・ローエルハイドのお気に入りである、と。
あれらは、それも「込み」なのだ。
娘という以上に、心に刻まれたことだろう。
叱るどころか、彼女の願いを退けることすら、できはしない。
「ところで、まずは1曲、どうだい?」
イノックエルが挨拶に来たことで、このあと、続々と、人が集まってくるのは、目に見えていた。
基本的に、ローエルハイドは表に出ない主義だ。
彼にしても、それこそ「お忍び」でなければ、夜会にもサロンにも出入りはしていなかった。
自らの素の姿を晒して、夜会に出たのは、初めてのことでもある。
貴族らは、これが「特異な状況」だとわかっているだろう。
今後、あるかどうか、一生に1度の機会になるかもしれないのだ。
こぞって、挨拶に来るのは当然の成り行きと言えた。
とはいえ、彼にすれば、主役は、彼ではない。
しかも、ブレインバーグ夫妻と似たり寄ったりの態度しか示さないのも、容易に予測できる。
シェルニティを無視され続けると、さすがに苛立ちを抑えきれる自信がなかった。
そのため、挨拶は抜きで、ダンスホールに行きたかったのだ。
彼女とのダンスを、彼は、本気で楽しみにしていたので。
そもそも、シェルニティに、楽しませるとの、約束もしている。
彼女が「いない者」のように扱われたのでは、楽しめるはずがなかった。
「さあ、おいで」
腕にかかっていた彼女の手を取り、ダンスホールに移動する。
後ろから、ぞろぞろとついてくる招待客は、無視した。
分かり易く、拒絶の意思を背中で表す。
それにより、彼らは、ついてきはしても、話しかけてはこなかった。
シェルニティの手を握り、ダンスホールの中央に立つ。
流れ始めた曲に、彼女の顔が、わずかに曇った。
前奏だけで、曲調が速いのが、わかる。
「これは、ワルツではないわね?」
「クイックのようだな」
「知らなくはないけれど、通り一遍しか習っていないの」
「知っているのなら平気さ。割に、楽しいものだよ、明るい曲が多いからね」
おそらく、クリフォードの嫌がらせだ。
ホールに入ってきた時には、ワルツの曲が流れていたのを耳にしている。
クイックステップは、最近の流行りではあるが、まだ夜会で踊ることは少ない。
シェルニティが踊れないと見込んで、曲を差し替えさせたのだろう。
「いいじゃないか。形にはこだわらずに、楽しくやろう」
「そうね。せっかく来たのだし、初めてのダンスですもの」
シェルニティの手が、彼の肩に軽くそえられる。
彼も、腕を回し、彼女の背を支えた。
視線を合わせ、互いに、にっこりする。
同時に、足を踏み出した。
彼の腕にかけた手に、力が入っている。
その手に、彼女に貸していないほうの手を乗せ、微笑んでみせた。
シェルニティも、微笑み返してくる。
人の目など気にする必要はない。
彼は、そう言ったが、本人にとって、それが難しいことだとは、わかっていた。
まるきり気にせずにいる、ということはできないだろう。
だとしても、シェルニティは、精一杯、頑張っている。
今まで、実践することはなかったらしいが、さすがに、きっちりとした貴族教育を受けているのがわかるくらい、堂々としていた。
「こ、公爵様」
転がるようにして駆け寄ってきたのは、イノックエルだ。
彼が贈ったタイピンをつけている。
隣にいる妻、すなわちシェルニティの母も、髪飾りをつけていた。
薄く透明感のある紫の宝石が、それぞれに、はめこまれている。
シェルニティに話した通り、お手製の宝石だ。
地中深くから取り出した素材に圧力を加え鉱石とし、それを原石に造った。
空気や砂礫からでも、彼は、魔術を使い、素材にすることができるのだ。
実際、どんな高級店で売られている宝石より、希少価値は高い。
さりとて、売るつもりで造ったことがないため「相場」はないのだけれども。
「やあ、イノックエル。ロゼッティは、初めて顔を合わせるね」
「は、はい……む、娘が、お世話になって、おります……」
耳をすませていなければ聞こえないほど、小さな声で、シェルニティの母親が、頭を下げる。
瞳の色や顔立ちは、なんとなくシェルニティに似ていた。
ただ、赤毛の髪や雰囲気は、まったく似ていない。
イノックエルと似たところと言えば、耳の形くらいだし。
(彼女は、過去の様々な血筋から、いいところを選りすぐって産まれたのかもしれないな。とても、この2人の血だけとは思えない)
血の流れには、不思議なものがある。
彼自身が、それを、身を持って体験していた。
子は親に似るものではあるが、それ以外の要素も複雑に絡み合っている。
どこで、過去からの血が呼び覚まされるか、わからないのだ。
「お世話なんてしちゃいないさ。彼女といると、毎日が楽しくてね。ここ数年の鬱々とした気分が吹き飛んでしまったよ」
「そ、そう仰っていただけると、私どもも、嬉しく……」
2人は、彼の隣にシェルニティがいるにもかかわらず、見ようとしていない。
ちきっと苛立ちが走るが、我慢する。
せっかくの夜だ。
2人に冷や汗をかかせて終わりにする気はなかった。
「いい夜だ、そう思うだろう、イノックエル」
「ええ、はい、もちろん……」
「私たちのことは気にせず、楽しむがいいよ。私たちも、そうするのでね」
言って、シェルニティの額に軽く口づける。
それから、2人に、軽く首を傾けてみせた。
イノックエルは、さすがに敏感だ。
彼の「失せろ」という合図を察し、妻と連れ立って、そそくさと離れて行く。
(不愉快な男ではあるが、察しがいいのだけは取柄と言えるな)
隣からの視線に、彼はシェルニティのほうに顔を向けた。
彼女は、彼を見上げている。
「どうかしたかい?」
「2人とも、私に、なにも仰らなかったわ」
「挨拶がなかったのは、確かだね」
「いえ、違うの。夜会に出るなんてって、叱られるとばかり思っていたから」
彼は、左手を伸ばし、指先で、彼女の右頬を撫でる。
周囲の目などおかまいなしだ。
実際、本当に気にしていない。
というより、気にしたことがない。
彼は、人目を気にするのではなく、人目を意識する。
どう見られているかではなく、どう見せるか。
さりとて、今は、それすら、どうでもよかった。
単に、シェルニティを安心させたいと思っている。
「シェリー、きみのご両親も、わかってくれたのじゃないかな? きみを閉じ込めておく理由なんてないってことをね」
「それなら、この先も叱られることはない?」
「ないよ。きっとね」
絶対に、ない。
あの2人は、それを理解したはずだ。
彼らに渡した「品」が、否応なく、思い出させるに違いない。
シェルニティは、ジョザイア・ローエルハイドのお気に入りである、と。
あれらは、それも「込み」なのだ。
娘という以上に、心に刻まれたことだろう。
叱るどころか、彼女の願いを退けることすら、できはしない。
「ところで、まずは1曲、どうだい?」
イノックエルが挨拶に来たことで、このあと、続々と、人が集まってくるのは、目に見えていた。
基本的に、ローエルハイドは表に出ない主義だ。
彼にしても、それこそ「お忍び」でなければ、夜会にもサロンにも出入りはしていなかった。
自らの素の姿を晒して、夜会に出たのは、初めてのことでもある。
貴族らは、これが「特異な状況」だとわかっているだろう。
今後、あるかどうか、一生に1度の機会になるかもしれないのだ。
こぞって、挨拶に来るのは当然の成り行きと言えた。
とはいえ、彼にすれば、主役は、彼ではない。
しかも、ブレインバーグ夫妻と似たり寄ったりの態度しか示さないのも、容易に予測できる。
シェルニティを無視され続けると、さすがに苛立ちを抑えきれる自信がなかった。
そのため、挨拶は抜きで、ダンスホールに行きたかったのだ。
彼女とのダンスを、彼は、本気で楽しみにしていたので。
そもそも、シェルニティに、楽しませるとの、約束もしている。
彼女が「いない者」のように扱われたのでは、楽しめるはずがなかった。
「さあ、おいで」
腕にかかっていた彼女の手を取り、ダンスホールに移動する。
後ろから、ぞろぞろとついてくる招待客は、無視した。
分かり易く、拒絶の意思を背中で表す。
それにより、彼らは、ついてきはしても、話しかけてはこなかった。
シェルニティの手を握り、ダンスホールの中央に立つ。
流れ始めた曲に、彼女の顔が、わずかに曇った。
前奏だけで、曲調が速いのが、わかる。
「これは、ワルツではないわね?」
「クイックのようだな」
「知らなくはないけれど、通り一遍しか習っていないの」
「知っているのなら平気さ。割に、楽しいものだよ、明るい曲が多いからね」
おそらく、クリフォードの嫌がらせだ。
ホールに入ってきた時には、ワルツの曲が流れていたのを耳にしている。
クイックステップは、最近の流行りではあるが、まだ夜会で踊ることは少ない。
シェルニティが踊れないと見込んで、曲を差し替えさせたのだろう。
「いいじゃないか。形にはこだわらずに、楽しくやろう」
「そうね。せっかく来たのだし、初めてのダンスですもの」
シェルニティの手が、彼の肩に軽くそえられる。
彼も、腕を回し、彼女の背を支えた。
視線を合わせ、互いに、にっこりする。
同時に、足を踏み出した。
11
あなたにおすすめの小説

婚約者の命令により魔法で醜くなっていた私は、婚約破棄を言い渡されたので魔法を解きました
天宮有
恋愛
「貴様のような醜い者とは婚約を破棄する!」
婚約者バハムスにそんなことを言われて、侯爵令嬢の私ルーミエは唖然としていた。
婚約が決まった際に、バハムスは「お前の見た目は弱々しい。なんとかしろ」と私に言っていた。
私は独自に作成した魔法により太ることで解決したのに、その後バハムスは婚約破棄を言い渡してくる。
もう太る魔法を使い続ける必要はないと考えた私は――魔法を解くことにしていた。

五年後、元夫の後悔が遅すぎる。~娘が「パパ」と呼びそうで困ってます~
放浪人
恋愛
「君との婚姻は無効だ。実家へ帰るがいい」
大聖堂の冷たい石畳の上で、辺境伯ロルフから突然「婚姻は最初から無かった」と宣告された子爵家次女のエリシア。実家にも見放され、身重の体で王都の旧市街へ追放された彼女は、絶望のどん底で愛娘クララを出産する。
生き抜くために針と糸を握ったエリシアは、持ち前の技術で不思議な力を持つ「祝布(しゅくふ)」を織り上げる職人として立ち上がる。施しではなく「仕事」として正当な対価を払い、決して土足で踏み込んでこない救恤院の監督官リュシアンの温かい優しさに触れエリシアは少しずつ人間らしい心と笑顔を取り戻していった。
しかし五年後。辺境を襲った疫病を救うための緊急要請を通じ、エリシアは冷酷だった元夫ロルフと再会してしまう。しかも隣にいる娘の青い瞳は彼と瓜二つだった。
「すまない。私は父としての責任を果たす」
かつての合理主義の塊だった元夫は、自らの過ちを深く悔い、家の権益を捨ててでも母子を守る「強固な盾」になろうとする。娘のクララもまた、危機から救ってくれた彼を「パパ」と呼び始めてしまい……。
だが、どんなに後悔されても、どんなに身を挺して守られても、一度完全に壊された関係が元に戻ることは絶対にない。エリシアが真の伴侶として選ぶのは、凍えた心を溶かし、温かい日常を共に歩んでくれたリュシアンただ一人だった。
これは、全てを奪われた一人の女性が母として力強く成長し誰にも脅かされることのない「本物の家族」と「静かで確かな幸福」を自分の手で選び取るまでの物語。

わたくしが社交界を騒がす『毒女』です~旦那様、この結婚は離婚約だったはずですが?
澤谷弥(さわたに わたる)
恋愛
※完結しました。
離婚約――それは離婚を約束した結婚のこと。
王太子アルバートの婚約披露パーティーで目にあまる行動をした、社交界でも噂の毒女クラリスは、辺境伯ユージーンと結婚するようにと国王から命じられる。
アルバートの側にいたかったクラリスであるが、国王からの命令である以上、この結婚は断れない。
断れないのはユージーンも同じだったようで、二人は二年後の離婚を前提として結婚を受け入れた――はずなのだが。
毒女令嬢クラリスと女に縁のない辺境伯ユージーンの、離婚前提の結婚による空回り恋愛物語。
※以前、短編で書いたものを長編にしたものです。
※蛇が出てきますので、苦手な方はお気をつけください。

契約妻に「愛さない」と言い放った冷酷騎士、一分後に彼女の健気さが性癖に刺さって理性が崩壊した件
水月
恋愛
冷酷騎士様の「愛さない」は一分も持たなかった件の旦那様視点短編となります。
「君を愛するつもりはない」
結婚初夜、帝国最強の冷酷騎士ヴォルフラム・ツヴァルト公爵はそう言い放った。
出来損ないと蔑まれ、姉の代わりの生贄として政略結婚に差し出されたリーリア・ミラベルにとって、それはむしろ救いだった。
愛を期待されないのなら、失望させることもない。
契約妻として静かに役目を果たそうとしたリーリアは、緩んだ軍服のボタンを自らの銀髪と微弱な強化魔法で直す。
ただ「役に立ちたい」という一心だった。
――その瞬間。
冷酷騎士の情緒が崩壊した。
「君は、自分の価値を分かっていない」
開始一分で愛さない宣言は撤回。
無自覚に自己評価が低い妻に、激重独占欲を発症した最強騎士が爆誕する。

王太子様お願いです。今はただの毒草オタク、過去の私は忘れて下さい
シンさん
恋愛
ミリオン侯爵の娘エリザベスには秘密がある。それは本当の侯爵令嬢ではないという事。
お花や薬草を売って生活していた、貧困階級の私を子供のいない侯爵が養子に迎えてくれた。
ずっと毒草と共に目立たず生きていくはずが、王太子の婚約者候補に…。
雑草メンタルの毒草オタク侯爵令嬢と
王太子の恋愛ストーリー
☆ストーリーに必要な部分で、残酷に感じる方もいるかと思います。ご注意下さい。
☆毒草名は作者が勝手につけたものです。
表紙 Bee様に描いていただきました
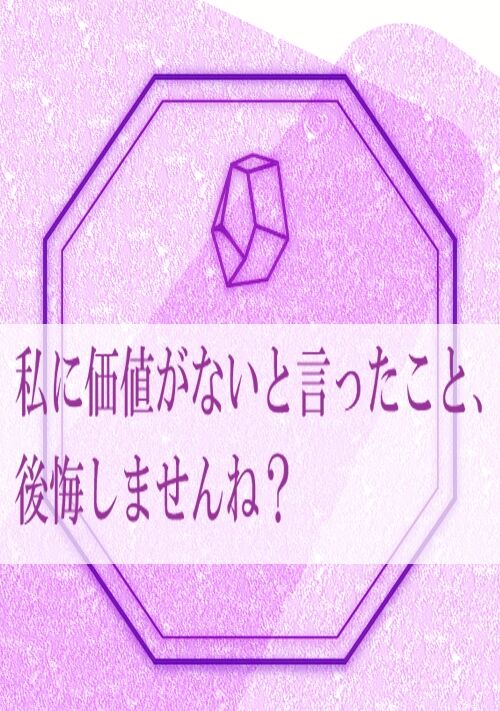
私に価値がないと言ったこと、後悔しませんね?
みこと。
恋愛
鉛色の髪と目を持つクローディアは"鉱石姫"と呼ばれ、婚約者ランバートからおざなりに扱われていた。
「俺には"宝石姫"であるタバサのほうが相応しい」そう言ってランバートは、新年祭のパートナーに、クローディアではなくタバサを伴う。
(あんなヤツ、こっちから婚約破棄してやりたいのに!)
現代日本にはなかった身分差のせいで、伯爵令嬢クローディアは、侯爵家のランバートに逆らえない。
そう、クローディアは転生者だった。現代知識で鉱石を扱い、カイロはじめ防寒具をドレス下に仕込む彼女は、冷えに苦しむ他国の王女リアナを助けるが──。
なんとリアナ王女の正体は、王子リアンで?
この出会いが、クローディアに新しい道を拓く!
※小説家になろう様でも「私に価値がないと言ったこと、後悔しませんね? 〜不実な婚約者を見限って。冷え性令嬢は、熱愛を希望します」というタイトルで掲載しています。

契約結婚の相手が優しすぎて困ります
みみぢあん
恋愛
ペルサル伯爵の婚外子リアンナは、学園に通い淑女の教育を受けているが、帰宅すれば使用人のような生活をおくっていた。 学園の卒業が近くなったある日、リアンナは父親と変わらない年齢の男爵との婚約が決まる。 そんなリアンナにフラッドリー公爵家の後継者アルベールと契約結婚をしないかと持ちかけられた。

私を家から追い出した妹達は、これから後悔するようです
天宮有
恋愛
伯爵令嬢の私サフィラよりも、妹エイダの方が優秀だった。
それは全て私の力によるものだけど、そのことを知っているのにエイダは姉に迷惑していると言い広めていく。
婚約者のヴァン王子はエイダの発言を信じて、私は婚約破棄を言い渡されてしまう。
その後、エイダは私の力が必要ないと思い込んでいるようで、私を家から追い出す。
これから元家族やヴァンは後悔するけど、私には関係ありません。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















