25 / 85
情事 の 嫉妬
しおりを挟む
上品な薄味の椀物。季節の野菜の炊き上げ。上品に盛られた刺身。日本酒は飲み慣れていないせいか、頬が赤くなるようだった。
しかし目の前の桐彦さんは顔色一つ変えず酒を飲んでいた。やはり強いんだな。
でも何だろう。味気のない食事だ。
そんなにショックだったの?息吹に家族があったことが。私と寝たのは、ただの行為だったのかもしれないってことが。
確かに私も、彼も「愛している」とか「好き」とか言わなかった。ただくっついていたい。触れいていたいという感情だけだった。まるで獣だ。
その間には「愛」なんてモノはなかった。
料亭を出ると、いつものように黒塗りの車に乗り込んだ。もう夜も更けている。いつもだったら、お風呂に入ってビールを飲んで……そんな時間だった。
「六花。ワタシの部屋で酒を飲み直すぞ。」
それがどんな意味なのか知らない訳じゃない。恥ずかしがっているわけじゃないのだ。
「……はい。」
これでいいのかもしれない。息吹には帰るべき家族がいて、私には桐彦さんがいる。記憶をなくす前、きっとこれが自然の形だったのだ。
「素直だな。」
「……抵抗しても連れて行くのでしょう?」
その言葉に、彼は笑っていた。
流れる景色が、早い。彼が早くホテルに着きたいのかもしれない。
ワインを注がれて、それを飲んでいる。
目の前には桐彦さんは電話がかかってベッドルームへ行ってしまった。何か私には言えない話をしているのかもしれないが、その話に私が首を突っ込んでもしょうがない。
やがてベッドルームから桐彦さんが戻ってきた。彼はたったままワインを一口飲むと、テレビの電源を入れた。そこに写ったのはくだらないお笑い番組だった。
またボタンを押すと、今度は真っ暗な画面になる。そして次に映し出されたのは、荒い画像だが二人の男と女のようだった。裸になり、どうやらセックスをしているようだ。
「何を見せてるんですか。」
「よく見ろ。」
男の声に聞き覚えがあった。そして女の声も。
「……。」
一気に酔いが醒めたような気がした。
「どこで……これを?」
「よく写っているな。最近の盗撮機は。」
「消してください。」
それは私と息吹の映像だった。角度からして、おそらくあの喪服に付いていたのだろう。
「消す?どうしてだ。」
「こんな映像残しておくようなものではないから……。」
「違うだろう。」
すると彼はソファに座っている私の前にたった。そして腰を屈め、私の視線と合わせる。
「後ろめたさじゃないのか。」
「……。」
「お前にはワタシがいる。息吹には妻がいる。もっともそれはさっき知ったのかもしれないが……。この時点でもお前も息吹も、ワタシが何なのか知っていたはずだ。だから後ろめたいと思っていたのだろう。」
「……私……。」
あなたと好きで夫婦になっているわけじゃないんだろう。それを言いたかったけれど、言えるわけがなかった。
「奴とのずいぶんセックスは気持ちよかったようだな。」
「そんな言い方はやめてください。」
「事実だろう。息吹もずいぶんお前の具合がいいようだな。こんな表情は初めて見る。」
相変わらずテレビの画面に私たちの映像が流れている。
「もういいから……消してください。」
すると彼はそのテレビの画面を消した。そして再び私に近づく。
「言っておくが、ワタシは嫉妬などしない。お前も息吹以外にもセックスをした相手がいるのも知っているし。」
「……昔のことです。」
「マグロと言われていたな。」
「……。」
確かにセックスをして気持ちいいと思えることはなかった。ただの肉と、ただの穴。そうとしか思えなかった。だけど息吹とは違った。
離れたくない。もっとくっついっていたい。その感情が私を会館におぼれさせた。そう思える。
不意に、彼が私の唇にキスをした。もう抵抗はしなかった。抵抗しても無駄だ。
息をつけれないほど激しいキスの後、私は抱き抱えられた。
「シャワー浴びたい。」
「後でな。」
ベッドルームに連れ込まれ、その大きくふかふかのベッドに投げ込まれた。
その私の上に桐彦さんがのしかかり、また唇に触れた。そしてブラウスのボタンをはずしていく。
「どの女よりも綺麗だな。」
普段の桐彦さんなら絶対言わない台詞だろう。女性ならきっと嬉しいと思うのだろうが、今の私に話にも響かなかった。
だけど体は悲しいくらい反応する。
責められているその部位一つ一つが悲鳴を上げるように、赤く染まっていく。
お互いに裸になり改めて一つになったとき、私はついに声を上げてしまった。それがどうしても息吹にとって裏切りになっていると思いながら。
それでも私はその快感に逆らうことは出来なかった。
「どの女よりも具合がいい。昔と変わらないな。」
広いバスタブに、お湯をためて二人で浸かっていた。私は桐彦さんに抱き抱えられるようにして、湯船に浸かっている。
「わからないわ。私……こんなになったのは初めてで……。」
結局私はすこし気絶していたようで、気がついたら湯船に浸かっていたのだ。
「人間ではお前の良さがわからなかったようだな。」
「……そんな……モノなんですか。」
魔物だから、だから息吹ともこんなに乱れてしまったのか。
違う。違う。何かが違う。
すると彼の手が私の胸に触れてきた。唇も首筋に這ってくる。
「桐彦さん……こんなところで……。」
「何回でもしたい。」
敏感になっているそれを、弄ぶように彼は私を味わっていた。
しかし目の前の桐彦さんは顔色一つ変えず酒を飲んでいた。やはり強いんだな。
でも何だろう。味気のない食事だ。
そんなにショックだったの?息吹に家族があったことが。私と寝たのは、ただの行為だったのかもしれないってことが。
確かに私も、彼も「愛している」とか「好き」とか言わなかった。ただくっついていたい。触れいていたいという感情だけだった。まるで獣だ。
その間には「愛」なんてモノはなかった。
料亭を出ると、いつものように黒塗りの車に乗り込んだ。もう夜も更けている。いつもだったら、お風呂に入ってビールを飲んで……そんな時間だった。
「六花。ワタシの部屋で酒を飲み直すぞ。」
それがどんな意味なのか知らない訳じゃない。恥ずかしがっているわけじゃないのだ。
「……はい。」
これでいいのかもしれない。息吹には帰るべき家族がいて、私には桐彦さんがいる。記憶をなくす前、きっとこれが自然の形だったのだ。
「素直だな。」
「……抵抗しても連れて行くのでしょう?」
その言葉に、彼は笑っていた。
流れる景色が、早い。彼が早くホテルに着きたいのかもしれない。
ワインを注がれて、それを飲んでいる。
目の前には桐彦さんは電話がかかってベッドルームへ行ってしまった。何か私には言えない話をしているのかもしれないが、その話に私が首を突っ込んでもしょうがない。
やがてベッドルームから桐彦さんが戻ってきた。彼はたったままワインを一口飲むと、テレビの電源を入れた。そこに写ったのはくだらないお笑い番組だった。
またボタンを押すと、今度は真っ暗な画面になる。そして次に映し出されたのは、荒い画像だが二人の男と女のようだった。裸になり、どうやらセックスをしているようだ。
「何を見せてるんですか。」
「よく見ろ。」
男の声に聞き覚えがあった。そして女の声も。
「……。」
一気に酔いが醒めたような気がした。
「どこで……これを?」
「よく写っているな。最近の盗撮機は。」
「消してください。」
それは私と息吹の映像だった。角度からして、おそらくあの喪服に付いていたのだろう。
「消す?どうしてだ。」
「こんな映像残しておくようなものではないから……。」
「違うだろう。」
すると彼はソファに座っている私の前にたった。そして腰を屈め、私の視線と合わせる。
「後ろめたさじゃないのか。」
「……。」
「お前にはワタシがいる。息吹には妻がいる。もっともそれはさっき知ったのかもしれないが……。この時点でもお前も息吹も、ワタシが何なのか知っていたはずだ。だから後ろめたいと思っていたのだろう。」
「……私……。」
あなたと好きで夫婦になっているわけじゃないんだろう。それを言いたかったけれど、言えるわけがなかった。
「奴とのずいぶんセックスは気持ちよかったようだな。」
「そんな言い方はやめてください。」
「事実だろう。息吹もずいぶんお前の具合がいいようだな。こんな表情は初めて見る。」
相変わらずテレビの画面に私たちの映像が流れている。
「もういいから……消してください。」
すると彼はそのテレビの画面を消した。そして再び私に近づく。
「言っておくが、ワタシは嫉妬などしない。お前も息吹以外にもセックスをした相手がいるのも知っているし。」
「……昔のことです。」
「マグロと言われていたな。」
「……。」
確かにセックスをして気持ちいいと思えることはなかった。ただの肉と、ただの穴。そうとしか思えなかった。だけど息吹とは違った。
離れたくない。もっとくっついっていたい。その感情が私を会館におぼれさせた。そう思える。
不意に、彼が私の唇にキスをした。もう抵抗はしなかった。抵抗しても無駄だ。
息をつけれないほど激しいキスの後、私は抱き抱えられた。
「シャワー浴びたい。」
「後でな。」
ベッドルームに連れ込まれ、その大きくふかふかのベッドに投げ込まれた。
その私の上に桐彦さんがのしかかり、また唇に触れた。そしてブラウスのボタンをはずしていく。
「どの女よりも綺麗だな。」
普段の桐彦さんなら絶対言わない台詞だろう。女性ならきっと嬉しいと思うのだろうが、今の私に話にも響かなかった。
だけど体は悲しいくらい反応する。
責められているその部位一つ一つが悲鳴を上げるように、赤く染まっていく。
お互いに裸になり改めて一つになったとき、私はついに声を上げてしまった。それがどうしても息吹にとって裏切りになっていると思いながら。
それでも私はその快感に逆らうことは出来なかった。
「どの女よりも具合がいい。昔と変わらないな。」
広いバスタブに、お湯をためて二人で浸かっていた。私は桐彦さんに抱き抱えられるようにして、湯船に浸かっている。
「わからないわ。私……こんなになったのは初めてで……。」
結局私はすこし気絶していたようで、気がついたら湯船に浸かっていたのだ。
「人間ではお前の良さがわからなかったようだな。」
「……そんな……モノなんですか。」
魔物だから、だから息吹ともこんなに乱れてしまったのか。
違う。違う。何かが違う。
すると彼の手が私の胸に触れてきた。唇も首筋に這ってくる。
「桐彦さん……こんなところで……。」
「何回でもしたい。」
敏感になっているそれを、弄ぶように彼は私を味わっていた。
0
あなたにおすすめの小説

距離感ゼロ〜副社長と私の恋の攻防戦〜
葉月 まい
恋愛
「どうするつもりだ?」
そう言ってグッと肩を抱いてくる
「人肌が心地良くてよく眠れた」
いやいや、私は抱き枕ですか!?
近い、とにかく近いんですって!
グイグイ迫ってくる副社長と
仕事一筋の秘書の
恋の攻防戦、スタート!
✼••┈•• ♡ 登場人物 ♡••┈••✼
里見 芹奈(27歳) …神蔵不動産 社長秘書
神蔵 翔(32歳) …神蔵不動産 副社長
社長秘書の芹奈は、パーティーで社長をかばい
ドレスにワインをかけられる。
それに気づいた副社長の翔は
芹奈の肩を抱き寄せてホテルの部屋へ。
海外から帰国したばかりの翔は
何をするにもとにかく近い!
仕事一筋の芹奈は
そんな翔に戸惑うばかりで……

【完結】退職を伝えたら、無愛想な上司に囲われました〜逃げられると思ったのが間違いでした〜
来栖れいな
恋愛
逃げたかったのは、
疲れきった日々と、叶うはずのない憧れ――のはずだった。
無愛想で冷静な上司・東條崇雅。
その背中に、ただ静かに憧れを抱きながら、
仕事の重圧と、自分の想いの行き場に限界を感じて、私は退職を申し出た。
けれど――
そこから、彼の態度は変わり始めた。
苦手な仕事から外され、
負担を減らされ、
静かに、けれど確実に囲い込まれていく私。
「辞めるのは認めない」
そんな言葉すらないのに、
無言の圧力と、不器用な優しさが、私を縛りつけていく。
これは愛?
それともただの執着?
じれじれと、甘く、不器用に。
二人の距離は、静かに、でも確かに近づいていく――。
無愛想な上司に、心ごと囲い込まれる、じれじれ溺愛・執着オフィスラブ。
※この物語はフィクションです。
登場する人物・団体・名称・出来事などはすべて架空であり、実在のものとは一切関係ありません。

〜仕事も恋愛もハードモード!?〜 ON/OFF♡オフィスワーカー
i.q
恋愛
切り替えギャップ鬼上司に翻弄されちゃうオフィスラブ☆
最悪な失恋をした主人公とONとOFFの切り替えが激しい鬼上司のオフィスラブストーリー♡
バリバリのキャリアウーマン街道一直線の爽やか属性女子【川瀬 陸】。そんな陸は突然彼氏から呼び出される。出向いた先には……彼氏と見知らぬ女が!? 酷い失恋をした陸。しかし、同じ職場の鬼課長の【榊】は失恋なんてお構いなし。傷が乾かぬうちに仕事はスーパーハードモード。その上、この鬼課長は————。
数年前に執筆して他サイトに投稿してあったお話(別タイトル。本文軽い修正あり)

出逢いがしらに恋をして 〜一目惚れした超イケメンが今日から上司になりました〜
泉南佳那
恋愛
高橋ひよりは25歳の会社員。
ある朝、遅刻寸前で乗った会社のエレベーターで見知らぬ男性とふたりになる。
モデルと見まごうほど超美形のその人は、その日、本社から移動してきた
ひよりの上司だった。
彼、宮沢ジュリアーノは29歳。日伊ハーフの気鋭のプロジェクト・マネージャー。
彼に一目惚れしたひよりだが、彼には本社重役の娘で会社で一番の美人、鈴木亜矢美の花婿候補との噂が……
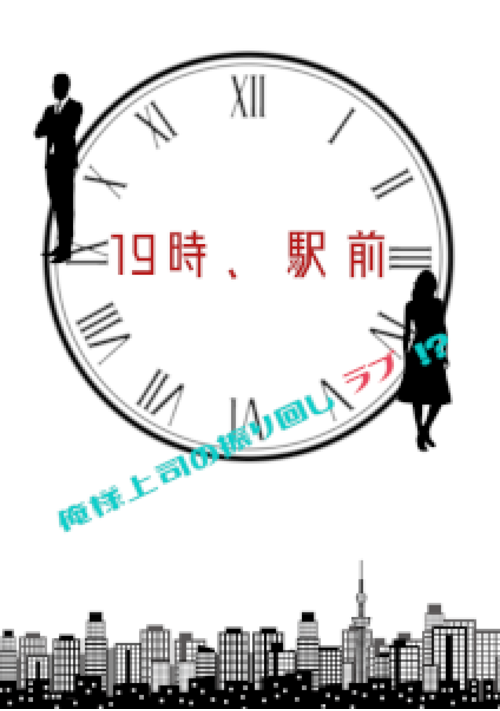
19時、駅前~俺様上司の振り回しラブ!?~
霧内杳/眼鏡のさきっぽ
恋愛
【19時、駅前。片桐】
その日、机の上に貼られていた付箋に戸惑った。
片桐っていうのは隣の課の俺様課長、片桐課長のことでいいんだと思う。
でも私と片桐課長には、同じ営業部にいるってこと以外、なにも接点がない。
なのに、この呼び出しは一体、なんですか……?
笹岡花重
24歳、食品卸会社営業部勤務。
真面目で頑張り屋さん。
嫌と言えない性格。
あとは平凡な女子。
×
片桐樹馬
29歳、食品卸会社勤務。
3課課長兼部長代理
高身長・高学歴・高収入と昔の三高を満たす男。
もちろん、仕事できる。
ただし、俺様。
俺様片桐課長に振り回され、私はどうなっちゃうの……!?

腹黒上司が実は激甘だった件について。
あさの紅茶
恋愛
私の上司、坪内さん。
彼はヤバいです。
サラサラヘアに甘いマスクで笑った顔はまさに王子様。
まわりからキャーキャー言われてるけど、仕事中の彼は腹黒悪魔だよ。
本当に厳しいんだから。
ことごとく女子を振って泣かせてきたくせに、ここにきて何故か私のことを好きだと言う。
マジで?
意味不明なんだけど。
めっちゃ意地悪なのに、かいま見える優しさにいつしか胸がぎゅっとなってしまうようになった。
素直に甘えたいとさえ思った。
だけど、私はその想いに応えられないよ。
どうしたらいいかわからない…。
**********
この作品は、他のサイトにも掲載しています。

灰かぶりの姉
吉野 那生
恋愛
父の死後、母が連れてきたのは優しそうな男性と可愛い女の子だった。
「今日からあなたのお父さんと妹だよ」
そう言われたあの日から…。
* * *
『ソツのない彼氏とスキのない彼女』のスピンオフ。
国枝 那月×野口 航平の過去編です。

子持ち愛妻家の極悪上司にアタックしてもいいですか?天国の奥様には申し訳ないですが
霧内杳/眼鏡のさきっぽ
恋愛
胸がきゅんと、甘い音を立てる。
相手は、妻子持ちだというのに。
入社して配属一日目。
直属の上司で教育係だって紹介された人は、酷く人相の悪い人でした。
中高大と女子校育ちで男性慣れしてない私にとって、それだけでも恐怖なのに。
彼はちかよんなオーラバリバリで、仕事の質問すらする隙がない。
それでもどうにか仕事をこなしていたがとうとう、大きなミスを犯してしまう。
「俺が、悪いのか」
人のせいにするのかと叱責されるのかと思った。
けれど。
「俺の顔と、理由があって避け気味なせいだよな、すまん」
あやまってくれた彼に、胸がきゅんと甘い音を立てる。
相手は、妻子持ちなのに。
星谷桐子
22歳
システム開発会社営業事務
中高大女子校育ちで、ちょっぴり男性が苦手
自分の非はちゃんと認める子
頑張り屋さん
×
京塚大介
32歳
システム開発会社営業事務 主任
ツンツンあたまで目つき悪い
態度もでかくて人に恐怖を与えがち
5歳の娘にデレデレな愛妻家
いまでも亡くなった妻を愛している
私は京塚主任を、好きになってもいいのかな……?
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















