257 / 870
ブイヤベース
256
しおりを挟む
打ち合わせが終わり、靖は立ち上がると時計を見た。外は暗くなっている。そろそろ帰社をしないと、上司から口やかましく言われるだろう。それで無くても靖はお人好しらしく、作家にずっと付いていると噂があるのだ。そんな時代では無いのだからと言うのが、上司の口癖だったが叔父に聞けば今も昔も変わらないと言うことだった。それはきっとバンドとレコード会社の担当でも同じ事だろう。
「じゃあ、俺帰るわ。お茶、ご馳走様でした。」
「いいや。良い詩集になりそうだ。ますます女っていうイメージが付くな。」
「かもしれないな。」
二人は笑い合いながら玄関へ向かう。その時、玄関のドアが開いた。そこには沙菜の姿がある。
「あら。藤枝君。来てたんだ。」
「どうも。お邪魔さん。」
「ご飯でも食べていけば良いのに。どうせ今日何人か別に来るんだから。」
「いいや。会社に帰らないと。」
「堅いよねぇ。」
「沙菜。お前が作るんじゃ無いだろ?」
芹はそういうと、沙菜は頬を膨らませる。だがすぐに靖の方を見上げて言った。
「今度、デートしない?」
靖は見た目は良い感じがする。すらっと背が高く、体育会系特有のがっちりした体をしていて、沙菜の好きなタイプだ。だからそういう風に声をかけたのだろう。
「え?」
だが見た目とは違い靖はうぶな方で、こういう誘いは苦手にしている。まだ女性と付き合ったことも無いのだ。
それがわかっている芹は呆れたように言う。
「沙菜とデートなんかしたら、骨ごとしゃぶられるぞ。」
「何よ。優しくしてあげるってのに。」
こっちの方がよっぽどカップルに見えるが、ただの同居人だという。そして芹が付き合っているのは、この沙菜の双子の姉である元々芹の担当をしていたレコード会社の人なのだ。
初めて見たときには堅くて、隙の無い人だと思った。だが芹に言わせると、その隙がふと無くなるときがあるのだという。それがとてつもなく可愛いのだ。
のろけ話に「はいはい」と軽く受け流すしか無かった。自分にはまだそんな経験が無いのだから。
そして家を出ると駅の方向へ向かう。すると向こうから見覚えのある人達が歩いてきていた。三人の男女。女性は沙夜だった。そして男のうちの一人は「二藍」のギタリストだ。そしてもう一人はわからない。見たことが無い人だと思う。
沙夜も靖に気がついて少し笑う。
「藤枝さん。今晩は。渡先生のところですか。」
「えぇ。二冊目の詩集の外装デザインが出来たので、見てもらおうかと。」
「帯は誰が書いてもらうんですか?」
「荒田夕先生が。」
「へぇ……著名人ですね。」
「荒田先生は渡先生のファンなんですよ。是非書かせて欲しいとこちらがお願いする前に頼まれました。」
「だったら内容もそれなりでは無いといけませんねぇ。」
「プレッシャーかけないでくださいよ。」
そうだった。沙夜はもうあまり関わっていないが「渡摩季」という作詞家の担当もしていたのだ。今は出版社に籍があるらしく、この男が担当を引き継いだのだろう。奏太はそう思いながら、藤枝靖を見ていた。ずいぶん若い男で、沙夜よりも年下だろう。大学を出たばかりと言った感じに見える。
その視線に気がついたのだろう。靖は一緒に居る純や奏太にも挨拶をする。
「初めましてですかね。文芸誌の担当をしてます藤枝と申します。」
「よろしく。」
「文芸誌か。」
二人は名刺を受け取ると、その名前を見る。そして出版社名を見て純は納得したように頷いた。
「石森さんのところの?」
「えぇ。」
「明日俺、そっちに行く用事があってさ。」
「え?そうなんですか?」
沙夜は少し頷いて言う。
「ギター雑誌にタブ譜の監修を頼まれてさ。そのチェック。」
「そう言えば夏目さんは、ギターの教則本なんかも頼まれていたのよ。」
「沙夜さん。それはまた今度にしてくれる?」
「そうね。」
自分の実力のなさが、浮き彫りになったのだ。また基礎を見直そうと思う。基礎を教えれる立場では無いと思っているのだ。
「渡摩季もこの辺に住んでるのか。」
奏太はそう呟くと、靖はしまったと内心思っていた。沙夜が居ることで気が緩んでしまったのだろう。住んでいるところなんかも知られたくなかったのに。
だが沙夜は少し頷いて言う。
「えぇ。この辺。」
「お前、この辺まで通ってたのか。ご苦労だよな。」
「家に忘れ物をしたときには便利だったけれどね。」
「小学生かよ。」
奏太はそういって少し笑う。上機嫌なのは、おそらく家に来ても良いと言われたからだろう。
翔は少し遅くなるが、奏太の居る時間に帰ってくると言う。翔は翔で覚悟をしていたのかもしれない。
純は手土産にパンを買った。レコード会社の近くにある評判の良いパン屋の食パンだった。ちゃんと箱に入っていてまるでケーキのようだと思う。
そして奏太はケーキを買ってきた。それは駅の近くにある洋菓子店のモノで、ロールケーキが美味しいのだ。甘い物が苦手な人はいないと沙夜から聞いて、それを選んだのだが思ったよりも大きくて四人暮らしには持て余すかもしれないと思っていた。だが純は酒よりも甘い物が好きだったので、都合が良いと思う。
「ロールケーキってコーヒー風味とかもあるんだな。」
「ロールケーキって海外には無いの?」
「あるのはあるけど、俺、あまり進んで甘い物を食うわけじゃ無いし。」
「そう言えば前にビクトリアケーキを食べるときも、そこまで好きじゃ無いって言ってたか。」
「砂糖の塊じゃん。」
身も蓋もない言い方だ。沙夜はそう思いながら家の前で足を止める。
「ここよ。」
「一戸建て?」
平屋で広そうな家だ。門の向こうには庭も見える。だが洗濯するための物干し台が置かれていて、どちらかというと広いが庶民的な普通の家に見える。
「えぇ。間借りをしているって言ったでしょう?」
四人暮らしくらいならこれくらいで十分かもしれない。そう思いながら、奏太と純はその門をくぐる。郵便物のチェックをして、沙夜はその家のドアを開けた。
中は普通の家だと思う。特に汚れても無いし、掃除も行き届いている。埃すら見えない。
「ただいま。」
沙夜はそう言って靴を脱ぐ。
「お邪魔します。」
「します。」
純と奏太もそう言って靴を脱ぐと、沙夜は二人をリビングの方へ案内した。広めのリビングで、テーブルとテレビ、ソファ。台所とその前にはカウンターがある。
「夏目さん。上着は掛けておく?」
「そうしようかな。ハンガー貸して。」
「はい。はい。」
本当に沙夜はここに住んでいるのだろう。迷うこと無く押し入れなんかの中からハンガーを取りだした。
「お帰り。」
振り向くとそこには沙菜の姿がある。前にK町で見た派手な格好などでは無いしおそらくすっぴんなのだろう。眉毛が半分くらいしか無い。
沙夜は妹と住んでいると言っていた。だからおそらく同居人の一人なのだ。奏太はそう思って軽く頭を下げる。
「あなたはもう帰っていたの?」
「うん。明日イベントだから、肌の調子を良くしたくてさ。さっさと食べてお風呂に入ってさっさと寝るわ。あぁ。夏目さんと……トイレの。」
そういわれて奏太はむっとしたように沙菜に言う。こちらが低姿勢に出てるのに、その言い草は無いと思ったのだ。
「望月奏太だよ。」
「望月奏太?あぁ、姉さんが出てたコンクールでグランプリを取った?へぇ。姉さんは入選止まりだったのにね。今は姉さんの下になるんだ。」
わざと沙菜はそういっているようにしか聞こえない。奏太の頭に血が上りやすいのはわかる。だから怒らせて帰らせようとしているのだ。だがそれに文句を奏太が言う前に沙夜が声をかける。
「沙菜。失礼よ。」
その言葉に沙菜は肩をすくませた。おそらく翔だって芹だってこの男は嫌がるだろう。翔に会う前に帰らせたいと思っている沙菜の気持ちはわからないのだろうか。
「あんたはAV女優だろ?サディストな女王様役が多いか。」
「そうね。あんたも金○蹴られたい?」
純はその会話に思わず一歩引いた。沙菜がそういう女優なのはわかっているが、ここまで露骨にそんな話をしたことは無いから。
困ったように沙夜を見ると、沙夜は呆れたように純に話しかける。
「あまり相手にしないで。今からご飯を作るから、適当に過ごしてくれても良いわ。」
その時リビングのドアが開いた。そこからやってきたのは芹の姿だった。沙夜を見て少し笑う。
「お帰り。」
「ただいま。さっき藤枝さんに会ったわ。」
「あぁ。ライターの記事を見てもらってた。そのあと渡先生のところにも行ったんだろ。」
渡摩季だと言うことは純は知らない。ただライターの草壁だと言うことは知っている。だからわざとその名前を出したのだ。そしてちらっと奏太の方を見る。だがふっと視線をそらせた。藤枝には気にする必要は無いと言われたモノの、いざ対面すると口からは文句しか出てきそうに無かったからだ。
「じゃあ、俺帰るわ。お茶、ご馳走様でした。」
「いいや。良い詩集になりそうだ。ますます女っていうイメージが付くな。」
「かもしれないな。」
二人は笑い合いながら玄関へ向かう。その時、玄関のドアが開いた。そこには沙菜の姿がある。
「あら。藤枝君。来てたんだ。」
「どうも。お邪魔さん。」
「ご飯でも食べていけば良いのに。どうせ今日何人か別に来るんだから。」
「いいや。会社に帰らないと。」
「堅いよねぇ。」
「沙菜。お前が作るんじゃ無いだろ?」
芹はそういうと、沙菜は頬を膨らませる。だがすぐに靖の方を見上げて言った。
「今度、デートしない?」
靖は見た目は良い感じがする。すらっと背が高く、体育会系特有のがっちりした体をしていて、沙菜の好きなタイプだ。だからそういう風に声をかけたのだろう。
「え?」
だが見た目とは違い靖はうぶな方で、こういう誘いは苦手にしている。まだ女性と付き合ったことも無いのだ。
それがわかっている芹は呆れたように言う。
「沙菜とデートなんかしたら、骨ごとしゃぶられるぞ。」
「何よ。優しくしてあげるってのに。」
こっちの方がよっぽどカップルに見えるが、ただの同居人だという。そして芹が付き合っているのは、この沙菜の双子の姉である元々芹の担当をしていたレコード会社の人なのだ。
初めて見たときには堅くて、隙の無い人だと思った。だが芹に言わせると、その隙がふと無くなるときがあるのだという。それがとてつもなく可愛いのだ。
のろけ話に「はいはい」と軽く受け流すしか無かった。自分にはまだそんな経験が無いのだから。
そして家を出ると駅の方向へ向かう。すると向こうから見覚えのある人達が歩いてきていた。三人の男女。女性は沙夜だった。そして男のうちの一人は「二藍」のギタリストだ。そしてもう一人はわからない。見たことが無い人だと思う。
沙夜も靖に気がついて少し笑う。
「藤枝さん。今晩は。渡先生のところですか。」
「えぇ。二冊目の詩集の外装デザインが出来たので、見てもらおうかと。」
「帯は誰が書いてもらうんですか?」
「荒田夕先生が。」
「へぇ……著名人ですね。」
「荒田先生は渡先生のファンなんですよ。是非書かせて欲しいとこちらがお願いする前に頼まれました。」
「だったら内容もそれなりでは無いといけませんねぇ。」
「プレッシャーかけないでくださいよ。」
そうだった。沙夜はもうあまり関わっていないが「渡摩季」という作詞家の担当もしていたのだ。今は出版社に籍があるらしく、この男が担当を引き継いだのだろう。奏太はそう思いながら、藤枝靖を見ていた。ずいぶん若い男で、沙夜よりも年下だろう。大学を出たばかりと言った感じに見える。
その視線に気がついたのだろう。靖は一緒に居る純や奏太にも挨拶をする。
「初めましてですかね。文芸誌の担当をしてます藤枝と申します。」
「よろしく。」
「文芸誌か。」
二人は名刺を受け取ると、その名前を見る。そして出版社名を見て純は納得したように頷いた。
「石森さんのところの?」
「えぇ。」
「明日俺、そっちに行く用事があってさ。」
「え?そうなんですか?」
沙夜は少し頷いて言う。
「ギター雑誌にタブ譜の監修を頼まれてさ。そのチェック。」
「そう言えば夏目さんは、ギターの教則本なんかも頼まれていたのよ。」
「沙夜さん。それはまた今度にしてくれる?」
「そうね。」
自分の実力のなさが、浮き彫りになったのだ。また基礎を見直そうと思う。基礎を教えれる立場では無いと思っているのだ。
「渡摩季もこの辺に住んでるのか。」
奏太はそう呟くと、靖はしまったと内心思っていた。沙夜が居ることで気が緩んでしまったのだろう。住んでいるところなんかも知られたくなかったのに。
だが沙夜は少し頷いて言う。
「えぇ。この辺。」
「お前、この辺まで通ってたのか。ご苦労だよな。」
「家に忘れ物をしたときには便利だったけれどね。」
「小学生かよ。」
奏太はそういって少し笑う。上機嫌なのは、おそらく家に来ても良いと言われたからだろう。
翔は少し遅くなるが、奏太の居る時間に帰ってくると言う。翔は翔で覚悟をしていたのかもしれない。
純は手土産にパンを買った。レコード会社の近くにある評判の良いパン屋の食パンだった。ちゃんと箱に入っていてまるでケーキのようだと思う。
そして奏太はケーキを買ってきた。それは駅の近くにある洋菓子店のモノで、ロールケーキが美味しいのだ。甘い物が苦手な人はいないと沙夜から聞いて、それを選んだのだが思ったよりも大きくて四人暮らしには持て余すかもしれないと思っていた。だが純は酒よりも甘い物が好きだったので、都合が良いと思う。
「ロールケーキってコーヒー風味とかもあるんだな。」
「ロールケーキって海外には無いの?」
「あるのはあるけど、俺、あまり進んで甘い物を食うわけじゃ無いし。」
「そう言えば前にビクトリアケーキを食べるときも、そこまで好きじゃ無いって言ってたか。」
「砂糖の塊じゃん。」
身も蓋もない言い方だ。沙夜はそう思いながら家の前で足を止める。
「ここよ。」
「一戸建て?」
平屋で広そうな家だ。門の向こうには庭も見える。だが洗濯するための物干し台が置かれていて、どちらかというと広いが庶民的な普通の家に見える。
「えぇ。間借りをしているって言ったでしょう?」
四人暮らしくらいならこれくらいで十分かもしれない。そう思いながら、奏太と純はその門をくぐる。郵便物のチェックをして、沙夜はその家のドアを開けた。
中は普通の家だと思う。特に汚れても無いし、掃除も行き届いている。埃すら見えない。
「ただいま。」
沙夜はそう言って靴を脱ぐ。
「お邪魔します。」
「します。」
純と奏太もそう言って靴を脱ぐと、沙夜は二人をリビングの方へ案内した。広めのリビングで、テーブルとテレビ、ソファ。台所とその前にはカウンターがある。
「夏目さん。上着は掛けておく?」
「そうしようかな。ハンガー貸して。」
「はい。はい。」
本当に沙夜はここに住んでいるのだろう。迷うこと無く押し入れなんかの中からハンガーを取りだした。
「お帰り。」
振り向くとそこには沙菜の姿がある。前にK町で見た派手な格好などでは無いしおそらくすっぴんなのだろう。眉毛が半分くらいしか無い。
沙夜は妹と住んでいると言っていた。だからおそらく同居人の一人なのだ。奏太はそう思って軽く頭を下げる。
「あなたはもう帰っていたの?」
「うん。明日イベントだから、肌の調子を良くしたくてさ。さっさと食べてお風呂に入ってさっさと寝るわ。あぁ。夏目さんと……トイレの。」
そういわれて奏太はむっとしたように沙菜に言う。こちらが低姿勢に出てるのに、その言い草は無いと思ったのだ。
「望月奏太だよ。」
「望月奏太?あぁ、姉さんが出てたコンクールでグランプリを取った?へぇ。姉さんは入選止まりだったのにね。今は姉さんの下になるんだ。」
わざと沙菜はそういっているようにしか聞こえない。奏太の頭に血が上りやすいのはわかる。だから怒らせて帰らせようとしているのだ。だがそれに文句を奏太が言う前に沙夜が声をかける。
「沙菜。失礼よ。」
その言葉に沙菜は肩をすくませた。おそらく翔だって芹だってこの男は嫌がるだろう。翔に会う前に帰らせたいと思っている沙菜の気持ちはわからないのだろうか。
「あんたはAV女優だろ?サディストな女王様役が多いか。」
「そうね。あんたも金○蹴られたい?」
純はその会話に思わず一歩引いた。沙菜がそういう女優なのはわかっているが、ここまで露骨にそんな話をしたことは無いから。
困ったように沙夜を見ると、沙夜は呆れたように純に話しかける。
「あまり相手にしないで。今からご飯を作るから、適当に過ごしてくれても良いわ。」
その時リビングのドアが開いた。そこからやってきたのは芹の姿だった。沙夜を見て少し笑う。
「お帰り。」
「ただいま。さっき藤枝さんに会ったわ。」
「あぁ。ライターの記事を見てもらってた。そのあと渡先生のところにも行ったんだろ。」
渡摩季だと言うことは純は知らない。ただライターの草壁だと言うことは知っている。だからわざとその名前を出したのだ。そしてちらっと奏太の方を見る。だがふっと視線をそらせた。藤枝には気にする必要は無いと言われたモノの、いざ対面すると口からは文句しか出てきそうに無かったからだ。
0
あなたにおすすめの小説

熟女愛好家ユウスケの青春(熟女漁り)
MisakiNonagase
現代文学
高校まで勉強一筋で大学デビューをしたユウスケは家庭教師の教え子の母親と不倫交際するが、彼にとって彼女とが初の男女交際。そこでユウスケは自分が熟女好きだと自覚する。それからユウスケは戦略と実戦を重ねて、清潔感と聞き上手を武器にたくさんの熟女と付き合うことになるストーリーです。

ちょっと大人な物語はこちらです
神崎未緒里
恋愛
本当にあった!?かもしれない
ちょっと大人な短編物語集です。
日常に突然訪れる刺激的な体験。
少し非日常を覗いてみませんか?
あなたにもこんな瞬間が訪れるかもしれませんよ?
※本作品ではGemini PRO、Pixai.artで作成した生成AI画像ならびに
Pixabay並びにUnsplshのロイヤリティフリーの画像を使用しています。
※不定期更新です。
※文章中の人物名・地名・年代・建物名・商品名・設定などはすべて架空のものです。



旧校舎の地下室
守 秀斗
恋愛
高校のクラスでハブられている俺。この高校に友人はいない。そして、俺はクラスの美人女子高生の京野弘美に興味を持っていた。と言うか好きなんだけどな。でも、京野は美人なのに人気が無く、俺と同様ハブられていた。そして、ある日の放課後、京野に俺の恥ずかしい行為を見られてしまった。すると、京野はその事をバラさないかわりに、俺を旧校舎の地下室へ連れて行く。そこで、おかしなことを始めるのだったのだが……。


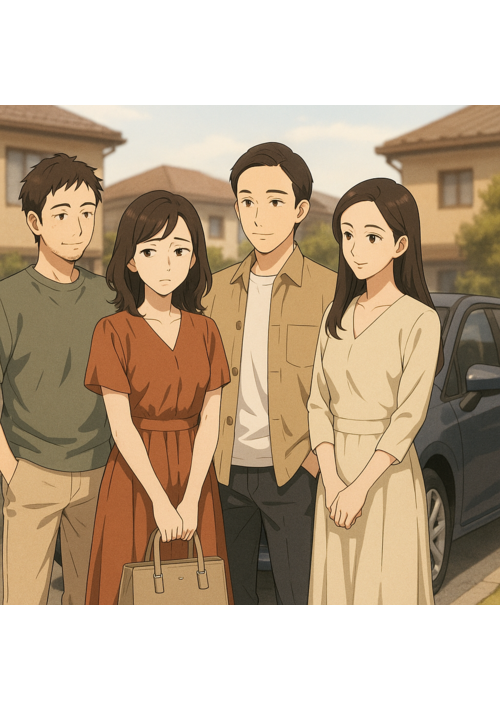
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















