10 / 20
(10)
器楽部
しおりを挟む新学期が始まってから数日、ユルミの「わー、遅刻するー」から始まる朝の日常に変わりはなかった。今日も白蟻がいっぱい落ちてうろちょろするのを眺めつつ、爺さんの出すハイカロリーな朝食を平らげた。
「行ってきまーす」
玄関から飛び出そうとしているとシメゾウ爺さんが楽器の黒いケースを持って来た。
「今日から器楽部が始まるんじゃろ。」
「そうだったー、ありがとう爺ちゃん。」
ユルミは器楽部でコルネットを吹く。コルネットはトランペットに似ているけれど、トランペットよりも短くて子供でも持ちやすい。それを受け取って学校へ急いだ。
学校に着くと学級委員長の倉田クラリがユルミを見て嫌な顔をした。
「ユルミ、あんたちゃんとシャワーしてる?」
「もちろんだよー」
「おかしいわねぇ、頭がフケだらけだわよ。」
ユルミは髪の毛にくっついていた白い粒をつまんで言った。
「ああこれ、白蟻だー。毎朝天井から降ってきて髪に紛れ込んじゃうんだよー」
「変なもん頭で飼ってんじゃないわよ、気持ち悪いわねぇ。」
「毎週日曜日にはちゃんとシャワーするから大丈夫だよー」
「なんですってぇ!毎週じゃなくて毎日洗いなさいよ、毎日!」
「えぇー面倒くさいよー。ムズムズ痒いけど私ってほら、我慢強い子だからさー」
「なにが我慢強い子よ、偉い子みたいに言うんじゃないわよ!」
「あははー」
ユルミは勉強が苦手なので授業中はウトウトして過ごすことが多い。今日の午前中もウトウトしていたが、どうにかよだれを垂らす前にお昼になった。給食の時間になると、休んでいる人の分まで食べたり、好き嫌いのある人の所を回って嫌いなものを引き受けたりする。そして食べ終わると、
「ダイエットしてるから食べる量減らしてるんだよー」
と言う。みんなが心の中でツッコむ。
(減らしてそれかよっ)))
そんないつも通りのお昼だった。午後が体育なら活躍の機会もあったけれど、残念ながら今日の時間割は算数だった。先生が問題の説明をしていると、不意にユルミが大声を上げた。
「出来たーっ!」
「おお根地、算数苦手なのに良くやった、偉いぞぉ」
嬉しそうにノートを掲げるユルミ。
「うん見てよー、とうとう算数って漢字で書けたよー」
ノートにでかでかと"算数"と書いてある。よく見ると"算"の字の目が日になっていた。
「え、あ、うん。」
先生は何か言いかけたが、ユルミの達成感に満ちた笑顔を見てやめておいた。
「よーし、その調子で頑張れ。」
「うん!でもこれ以上頑張ったらノーベル賞になっちゃうよー、あはは」
「じゃあ未来のノーベル賞、この算数の問題も考えてみようか?」
黒板には、「1分で4ペロリのマサオ君は20分で何ペロリンか?」という問題が書いてある。
「先生、質問」
「何だ、根地」
「20分って、何分?」
「あ、うん、根地はちょっと疲れてるみたいだな。しばらく寝てていいぞぉ。他に誰か解ける人~?」
という具合に今日も平和な時間が過ぎていく。みんなも問題を解いたり解いていなかったりした。ピヨン・メチは広げたノートにピラミッドみたいな三角形を大きくいくつも描いていた。大きすぎてノートから机にはみ出した三角形もあった。描き終わると寝ているユルミを見ていたがいつの間にかいなくなっていた。
放課後、音楽室で新学期最初の"器楽部"があった。器楽部といっても楽器の演奏は少しだけ、その実態は帰ってもその時刻、家に親がいない子を預かる学童保育だった。正式に学童保育とすれば公的な補助が入る分、こまごまとした法律に縛られる。学校の理事長、ミセス堀田はそういう決まりごとが嫌いだった。学校の運営は裕福な旦那さんからの出資があるので補助が無くても問題ない。旦那さんの堀田カネミツ氏は、金銀財宝を掘り当てたトレジャーハンターで、一獲千金を3回くらい成し遂げた資産家だった。ミセス堀田はピアノを弾くし、楽器が好きだったので"器楽部"を作り、子供の放課後の居場所として音楽室を開放したのだった。音楽室はステージを備えた講堂のように大きな教室だった。
さてその放課後、音楽室では学年ごとの集まりが出来てガヤガヤしていた。4年生のグループのところへ倉田クラリがヒララを連れてやって来た。4年生にはクラリたちのいる桃組の他に、桜組があって、今日は桜組から古戸フクヨと太田タクゾウが来ていた。
「桜組の二人は知らないかもしれないけど、この子はこの前桃組に転校して来た小森ヒララさん。今帰っても病気のお父さんは寝てるって言うから誘ってみたのよ。」
ヒララはいつものように口をほとんど開かず、しわがれた声でゆっくり挨拶した。
「小森なのだ。よろしくなのだ。ギシ」
古戸フクヨはフルートを片手に挨拶を返した。
「は、はじめまして。古戸です、よろしくね。」
隣のクラスに小柄で風変わりな転校生が来たのは知っていたが、間近で見ると少しどきっとした。桜組のもう一人は男子だった。
「僕は太田タクゾウ。太鼓叩いてるんだ。小森さんの事は噂で聞いてるよ。転校早々、柿田イシオをやっつけたって。」
横で古戸フクヨがうなずいた。
「そうそう、私も聞いた。実際柿田くんあれ以来喧嘩してないし。黒魔術で呪いをかけた、って言ってる子もいるわ。」
「僕はそんな話信じてなかったけど、こうして小森さんと会ったら、そうなのかも、って思えてきたよ。」
「そう、私もそう思った。その黒いマント、すごく魔女っぽいもの。」
初対面の古戸フクヨと太田タクゾウがそういうのを聞いてクラリも改めてヒララを観察した。
「そうよねぇ、最近見慣れてきてたけど、ヒララあんたちょっと不気味だわよ。」
横で聞いていた萩知トオルが片方の眉をちょっと上げる。
「初対面の2人がもし思っていても言わないことを倉田さん、あなたという人は。」
しかし言われたヒララは気にしていなかった。
「ギッシッシ、魔術も呪いも無いのだ。あの日校内を案内してもらってる途中、柿田クンが貧血になって保健室に行っただけなのだ。」
何でもない事として話している所へ、子分Bが駆け込んできた。
「姐さん、姐さん、大変でやんす。柿田親ビンが上級生3人組から呼び出されたでやんす。」
「ギシ?姐さん?子分Bクン、人違いじゃないのかな?」
「もう、冗談はよしてくださいよ。親ビンがまた喧嘩して怪我でもしちゃいけないから何かあったら真っ先に知らせるように、って姐さんが言ったんじゃないっすか。」
と、子分Bは上級生からの呼び出し状を差し出した。その場の4人がヒララがどうするのかじっと見ている。しょうがないのでヒララは呼び出し状を受け取って目を通した。
「ギシギシなになにえーと、」
今夜8時にハマオーツ神社の裏へ来い、と書いてある。
「了解したのだ。あたしが代わりに行くから柿田クンには知らせなくていいのだギシ。」
「姐さんに行ってもらえるなら安心でやんす。いや~姐さんが親ビンを心配してくれて嬉しいっす。」
威勢のいい子分Aと違い、子分Bは親分に無茶な喧嘩は控えて欲しいと思っていた。でもヒララが心配していたのは別のことだった。
「ギッシッシ、もし柿田が喧嘩して血が出たりしたらもったいないのだ。あいつの血は一滴残らずあたしのものなのだ。」
「え?血がどうしたでやんす?」
「なんでもないのだ。ギシシ」
ともあれ子分Bは安心して帰っていった。
「で、あんたどうするつもりなのよ?」
クラリの質問をはぐらかすようにヒララはマントをいじりいじり言った。
「仲良くするよう説得するギシ。あたし、柿田クンのことが好きみたいなのギシ。」
聞いたクラリは鼻で笑った。
「あんたウソくさいにも程があるわよ。」
「冗談なのだ。」
とそこへユルミが駆けて来た。
「クラリちゃーん、置いてくなんてひどいよー」
口の端に昼寝のよだれの跡が付いている。
「目が覚めたら誰もいなくなってて慌てたよー。授業が終わったらちゃんと起こしてよー」
クラリが両手を腰に当てて脱力した。
「はぁ、普通は"授業が始まったら起こしてよ"って言うもんよ。あんたがあんまり気持ち良さそうに熟睡してたからそっとしといてあげたのよ。」
「あー、ヒララちゃんも来てたんだー」
「人の話を聞きなさいよ。」
聞いてなかった。
「ねえみんなこれ見てよー」
黒い楽器ケースをすっと机の上に置いた。今朝シメゾウ爺さんに渡されたものだ。
「まぁ、初日からコルネットを持ってくるなんてあんたらしくないわね。」
「違うんだよー、中身が違うんだよー」
そう言われてクラリは黒いケースをまじまじと見た。
「中身が違うって?」
「入ってるのがコルネットじゃないんだよー」
「じゃあ何なのよ。」
ユルミはパチンと留め金を外してケースを開けた。
「あっ」
入っていたのはコルネットじゃなくてチョココルネだった。楽器用のクッション材も外されて、美味しそうなチョココルネがたくさんきっちり詰められている。
「爺ちゃんのいたずらにも困ったもんだよー」
クラリが甘い香りに自然と笑顔になっている。
「いいお爺さんじゃないのぉ。もちろん私の分もあるわよね?」
「うん、みんなで食べよー」
横で自己紹介の続きをしていたヒララと古戸さんと太田くんも呼んでチョココルネを配った。
「僕たちも貰っちゃっていいの?」
「どうぞどうぞー」
萩知トオルも一つ受け取って言った。
「みなさんがチョココルネを持ったところでお約束の質問があるのですが。」
コルネを少し持ち上げて、
「太い方から食べる派ですか?それとも細い方から食べる派でしょうか。ちなみに私は細い方から食べる派です。」
と、細い方をかじった。
「私は太い方からパクっといくわよ。」
と言ってクラリは太い方にぱくついた。
「僕も太い方から食べる派だな。」
と、太田タクゾウも後に続いた。
「あ、ごめん、もう食べちゃったー」
ユルミは何も考えないで手に持った時の向きにまかせる派だった。
「私は細い方からかな。」
と、古戸フクヨは細い方を上品にちぎった。
「ギシシ、あたしは真ん中から吸う派なのだケケケ」
その場の流れに乗せられたヒララは口を大きく開けて鋭い牙をむき出しにすると、チョココルネの真ん中に噛み付いた。そして吸った。
チュウチュウ
みんながぽかーんとヒララを見ている。
「し、しまったギシ」
慌てて口を閉じて牙を隠してももう遅い。倉田クラリがヒララをビシッと指差した。
「あ、あんた今の何なのよっ!」
「なんのことなのだ、ギシ?」
「さっきの牙みたいな歯のことよ!」
「出っ歯なのだギシ。」
「いいからちょっと口を開けてみなさいよっ。」
「ギシ、恥ずかしいから嫌なのだ。」
ユルミがそーっとヒララの背後に回って脇をこちょぐった。
「こちょこちょー」
「ギッシッシ、ケッケッケッ」
思わず笑って口を開け、鋭い牙があらわになった。
「何よその牙っ、あんた一体何者なのよ!」
「八重歯が長めの、ただのかわいい女の子なのだ。」
「長めにも程があるわよ、そんなのまるで悪魔か吸…」
吸血鬼と言いかけた倉田クラリを太田タクゾウが止めた。
「倉田さん、人の容姿をあげつらうのは良くないよ。本人が気にして隠したがっているじゃないか。」
ヒララは口元を両手で隠し、悲しげな顔をして見せた。
「学級委員ちょのクラリがいじめるのだ。」
と言って心で舌を出す。ヒララが転校してきたその日に彼女の歯に魅了された萩知トオルも黙っていない。ヒララが口元を隠していた両手をそっと開いて言った。
「倉田さん、よく見て下さい、この真珠のように美しい小森さんの歯を。この芸術的な輝きの中に魔性を見るとは、あなたの感性は少々ひねくれているのではないでしょうか。そして小森さん、その歯はあなたの素敵な個性です。恥ずかしがって隠してしまうなんてもったいない、実にもったいない。私にだけでいいので時々ちょっと見せて下さい。」
長ゼリフの最後に変な願望を入れてきた。優しい古戸フクヨも親身になって声をかける。
「私は歯並びが悪くて矯正歯科に通った事があるの。もし良かったら紹介できると思うわ。」
「いや、そういう事じゃないギシが…」
「そうかー、歯を隠したくて腹話術みたいに変なしゃべり方してたんだー。別に見えてもいいよー、気にしないよー」
そう言うユルミは自分の口のまわりがチョコだらけなのも気にしていない。クラリがきまり悪そうにヒララに言った。
「分かったわよ。あんたの牙、じゃなくて八重歯がどんなでも私がとやかく言う事じゃなかったわよ。だから普通に口開けて喋ったらいいんじゃないの?」
「ほほう、これは一種のツンデレでしょうか。」
「萩知トオル、あんたバカなこと言ってると耳にクラリネット突っ込んでピーピー鳴らすわよ!」
ヒララにとってこの展開は意外だった。
「牙が見えてもいいギシか?」
人間界で吸血コウモリだとバレたらただでは済まない、そう母上に聞かされていたので一生懸命牙も隠してきたのだ。それを見られて焦ったのに、案外そうでもなさそうだ。むしろ気遣われるとは。
「委員ちょ、ありがとう、ありがとうなのだ。」
「ちょっとやめなさいよ、あんたに感謝されても気持ち悪いわよ。」
クラリの手を取るヒララの指は、筋張っていて細長い。
「ん?ヒララあんた今さっき、自分で牙って言わなかった?」
「言ってないのだ。八重歯の出っ歯なのだギシ。」
口を開けてしゃべっても、ギシッときしむのはもう癖になっているのだった。萩知トオルがずっと聞きたかったことを質問した。
「小森さん、どのように歯磨きすればそのように美しい歯になれるのか教えて欲しいのですが。」
「歯磨きなんてしたことないのだギシ。」
「またまた御冗談を。」
「ほんとなのだ。口の中の虫がキレイにしてくれるから歯磨きなんてしなくていいのだギシ。」
そう言うとヒララは口の中から寄生虫をつまみ出して手のひらに乗せた。糸くずみたいに小さなミミズっぽいのがウネウネしている。萩知トオルだけでなく全員がぎょっとして固まった。
「たくさんいるから何匹か分けてあげてもいいんだけどぉ、間接キスになっちゃうからどうしよっかな~、なのだ。ギシシ」
おどけるように言うヒララ。トオルは誰にともなく宣言した。
「私、萩知トオルは今後もキシリトール配合歯磨きセットで歯磨きを頑張ることにいたします。」
実はヒララが噛み付いたときに麻酔効果があったり、刺し傷がすぐに塞がるのは、この虫の出す分泌液のせいなのだった。
さて、放課後もある程度時間が過ぎて器楽部の参加者が揃い、あちこちで楽器の音が聞こえ始めた。
ぷあ~、ジャンジャカ、どどどん、ピーヒョロロ
吹奏楽部と軽音部と暇つぶし部が混ざったような状態だった。器楽部と言っても目的が学童保育なので音楽的指導が出来る顧問はいない。手の空いている先生が様子を見に来るのだが、今日は給食のおばちゃんが来ていた。割烹着を着た、恰幅のいい貫禄のおばちゃんだ。
「みんなちゃんと食べてるかい?」
子供たちを見て回り、健康状態に気を配っている。ユルミたち4年生の所にも回って来た。一人ずつ健康そうなのを確認していくと、やっぱりヒララに目が留まる。
「おやまあ一体全体どうしたっていうんだい、漂白剤を飲んだミドリムシみたいな顔色じゃないか。」
両手でヒララの腕や胴体を触ってみる。
「こりゃ完全に発育不良だね、栄養が足りてないから背も伸びないんだねぇ。マントを羽織って筋張った体を隠すなんて切ないじゃないかい、まったくねぇ。」
「ギシ?あたしにとってはこれが普通なのだ。」
「いいんだよ、ここに来るのは親がいなかったり何かしら家庭の事情を抱えてる子も多いことくらい知ってるさ。だから何も聞かないけどさ、あたしゃ給食のおばちゃんだ、食べ物に関しては頼ってくれていいんだよ。家で食べさせてもらえない時は遠慮なく給食室に来るんだよ、いいかい?」
「え、あ、分かったのだ。(思い込みが激しいおばちゃんなのだギシ)」
「ところで4年生といえば、柿田さんちの息子が貧血で倒れたって聞いて、あたしゃたまげたねぇ。」
「どうしてなのだ?」
「柿田さんちの柿田鮮魚店からは、いつも給食用に活きの良い魚をいっぱい入れてもらってるんだよ。あそこの息子はたくさん魚を食べて育った健康優良児なんだ、それが貧血だってんだからビックリさね。」
「ギシ、柿田クンは元気が有り余るくらいだったし、みんなも不思議がっているのだ。」
もっともそう言うヒララは血を吸った本人なので不思議がってはいない。おばちゃんの話を聞いて、イシオの血が美味しい理由も分かった。
(肉より魚を食べて血液サラサラなのだ。喧嘩とかで適度な運動もバッチリ、コレステロールが控えめなのだなきっと)
「あたしゃそろそろ5年生の様子を見に行くとするよ。何かあったら給食室へおいで。」
おばちゃんは上級生のグループへ向かって行った。
倉田クラリがパパから貰ったクラリネットを取り出した。
「さあ、少しは器楽部らしい事もしておこうかしら。」
ポーポポー♪
壊れて出ない音は無い。
「私も久し振りにフルート吹いてみようかな。」
古戸フクヨはフルートを吹いた。
フォーフォフォー♪
「じゃあ僕も」
太田タクゾウが小太鼓を叩いた。
トントコドン
「では私も」
萩知トオルはトライアングルを鳴らした。
ちーーん
これでチンドン屋が完成した。
ちんちんドンドンちんドンドン、ポーポーフォーフォーちーーん♪
クラリを先頭にして、4人はチンドンしながら他のグループの間を練り歩いた。ユルミは踊りながら列について行き、見物人からお菓子をもらってはポケットに入れている。
「なんて自由な連中なのだ、ギシ」
戻って来たユルミはパンパンに膨らんだポケットからチョコやキャンディをガラガラと出した。ユルミは服を選ぶときポケットが大きいかどうかで決める。古戸・太田の桜組コンビは、給食のおばちゃんが置いていった大型ポットから、冷えたお茶をコップに注ぐ。人数分をトレーに乗せて運んできた。古戸がヒララにもお茶を配る。
「小森さん、器楽部に来てみてどうだった?」
「まぁまぁなのだ。」
「小森さんも何か楽器してみない?倉庫に行けば何かあると思うわ。」
太田タクゾウが小太鼓をトンと叩いた。
「僕の太鼓も器楽部の備品なんだ。」
ユルミがヒララの胸元を指差した。
「ピァアちゅあん、…」
「あんた、チョコバーかじりながら喋るのやめなさいよ。」
クラリに言われてモグモグごっくんした。
「ヒララちゃん、いつも首から下げてる小さい笛、吹いてみてよー」
言い終わるとチョコだらけの口にチョコバーの残りをグイッと押し込んだ。ヒララはネックレスのように下げていた小さな笛を外してみんなに見せた。クラリが目を丸くした。
「これって笛だったの!アクセサリーだと思ってたわよ。」
クラリがそう言うのも無理はない。その黒い笛は単3電池くらいの大きさしかなかった。
「母上の形見なのだ。」
みんなのまぶたの力が少し抜けた。
「大事なものなんだね。 」
太田くんの語尾にはしみじみとした余白があった。その余白のあと、萩知トオルも深呼吸して言った。
「お母様の形見をいつも身に付けていたんですね。」
フルート吹きの古戸さんは興味深げに笛の形を見る。
「すごく小さいのね。鳥笛か犬笛みたい。」
「吹く時はこうするのだ。」
ヒララが笛の両端を持って引っ張ると、スルスルとアンテナのように4段伸びて、20センチ位になった。
「母上のように上手に吹けないのだ。」
横に構えて、筋張った細長い指でいくつかあいている穴を塞ぎ、息を吹き込んだ。
・・・・・
音は出なかった。
クラリがヒララの肩をぽんっと叩いた。
「練習してればいつかお母さんみたいに吹けるようになるわよ。」
古戸フクヨも改めて笛をまじまじと見た。
「そうね、ピッコロよりずっと小さいし、難しいんだと思う。」
ヒララはみんなの反応から思い出した。
「そういえば人間には超音波は聞こえないのだったギシ。」
「超音波?」
「なんでもないのだ。」
いつの間にか音楽室にいたピヨン・メチが窓ガラスを人差し指でコツコツ叩いた。
「黒り飛んでり。」
ヒララの笛を聞いたコウモリたちが何処からともなく飛んで来て、赤い夕焼け空をヒラヒラと舞っていた。ヒララが笛を縮めて首から下げると、コウモリたちはまた何処かへと飛び去っていった。ピヨン・メチもカスタネットをカタカタしながら何処かへ行ってしまった。
「僕はそろそろ帰るよ。」
「私も帰ろうかな。母さん帰って来る時間だから。」
太田タクゾウは小太鼓を倉庫に片付けに行き、古戸フクヨもフルートをガーゼで拭いてケースに収めた。
「私も帰ろっかなー今日は楽しかったよー。」
ユルミは口の周りがまだチョコだ。萩知トオルがトライアングルをカバンにしまって言った。
「では本日はお開きとしましょうか。」
彼のトライアングルは、知恵の輪みたいにややこしい曲がり方をした自作オリジナルだった。古戸フクヨのフルートは親戚の卒業生から譲り受けたものらしい。ユルミが持って来るはずだったコルネットは、シメゾウ爺さんが発掘したものだった。ピヨン・メチのカスタネットは赤と青の一般的なもので、どこから持って来たのかは分からない。
「じゃあまた明日~」」」」」
4年生のグループは解散し、それぞれ帰っていった。その日は、夜にハマオーツ神社の裏で3人が貧血になって病院に運ばれた以外、特に何もなく過ぎていった。
「ギッシッシ」
0
あなたにおすすめの小説

14歳で定年ってマジ!? 世界を変えた少年漫画家、再起のノート
谷川 雅
児童書・童話
この世界、子どもがエリート。
“スーパーチャイルド制度”によって、能力のピークは12歳。
そして14歳で、まさかの《定年》。
6歳の星野幸弘は、将来の夢「世界を笑顔にする漫画家」を目指して全力疾走する。
だけど、定年まで残された時間はわずか8年……!
――そして14歳。夢は叶わぬまま、制度に押し流されるように“退場”を迎える。
だが、そんな幸弘の前に現れたのは、
「まちがえた人間」のノートが集まる、不思議な図書室だった。
これは、間違えたままじゃ終われなかった少年たちの“再スタート”の物語。
描けなかった物語の“つづき”は、きっと君の手の中にある。

笑いの授業
ひろみ透夏
児童書・童話
大好きだった先先が別人のように変わってしまった。
文化祭前夜に突如始まった『笑いの授業』――。
それは身の毛もよだつほどに怖ろしく凄惨な課外授業だった。
伏線となる【神楽坂の章】から急展開する【高城の章】。
追い詰められた《神楽坂先生》が起こした教師としてありえない行動と、その真意とは……。
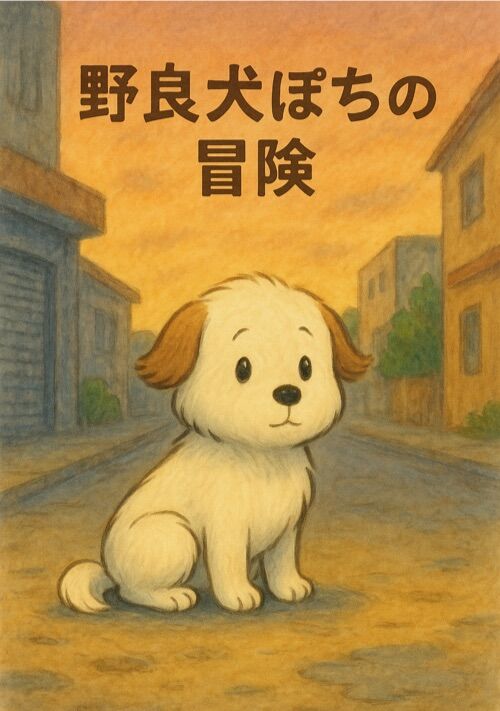
野良犬ぽちの冒険
KAORUwithAI
児童書・童話
――ぼくの名前、まだおぼえてる?
ぽちは、むかし だれかに かわいがられていた犬。
だけど、ひっこしの日に うっかり わすれられてしまって、
気がついたら、ひとりぼっちの「のらいぬ」に なっていた。
やさしい人もいれば、こわい人もいる。
あめの日も、さむい夜も、ぽちは がんばって生きていく。
それでも、ぽちは 思っている。
──また だれかが「ぽち」ってよんでくれる日が、くるんじゃないかって。
すこし さみしくて、すこし あたたかい、
のらいぬ・ぽちの ぼうけんが はじまります。

独占欲強めの最強な不良さん、溺愛は盲目なほど。
猫菜こん
児童書・童話
小さな頃から、巻き込まれで絡まれ体質の私。
中学生になって、もう巻き込まれないようにひっそり暮らそう!
そう意気込んでいたのに……。
「可愛すぎる。もっと抱きしめさせてくれ。」
私、最強の不良さんに見初められちゃったみたいです。
巻き込まれ体質の不憫な中学生
ふわふわしているけど、しっかりした芯の持ち主
咲城和凜(さきしろかりん)
×
圧倒的な力とセンスを持つ、負け知らずの最強不良
和凜以外に容赦がない
天狼絆那(てんろうきずな)
些細な事だったのに、どうしてか私にくっつくイケメンさん。
彼曰く、私に一目惚れしたらしく……?
「おい、俺の和凜に何しやがる。」
「お前が無事なら、もうそれでいい……っ。」
「この世に存在している言葉だけじゃ表せないくらい、愛している。」
王道で溺愛、甘すぎる恋物語。
最強不良さんの溺愛は、独占的で盲目的。

あだ名が242個ある男(実はこれ実話なんですよ25)
tomoharu
児童書・童話
え?こんな話絶対ありえない!作り話でしょと思うような話からあるある話まで幅広い範囲で物語を考えました!ぜひ読んでみてください!数年後には大ヒット間違いなし!!
作品情報【伝説の物語(都道府県問題)】【伝説の話題(あだ名とコミュニケーションアプリ)】【マーライオン】【愛学両道】【やりすぎヒーロー伝説&ドリームストーリー】【トモレオ突破椿】など
・【やりすぎヒーロー伝説&ドリームストーリー】とは、その話はさすがに言いすぎでしょと言われているほぼ実話ストーリーです。
小さい頃から今まで主人公である【紘】はどのような体験をしたのかがわかります。ぜひよんでくださいね!
・【トモレオ突破椿】は、公務員試験合格なおかつ様々な問題を解決させる話です。
頭の悪かった人でも公務員になれることを証明させる話でもあるので、ぜひ読んでみてください!
特別記念として実話を元に作った【呪われし◯◯シリーズ】も公開します!
トランプ男と呼ばれている切札勝が、トランプゲームに例えて次々と問題を解決していく【トランプ男】シリーズも大人気!
人気者になるために、ウソばかりついて周りの人を誘導し、すべて自分のものにしようとするウソヒコをガチヒコが止める【嘘つきは、嘘治の始まり】というホラーサスペンスミステリー小説

隣のじいさん
kudamonokozou
児童書・童話
小学生の頃僕は祐介と友達だった。空き家だった隣にいつの間にか変なじいさんが住みついた。
祐介はじいさんと仲良しになる。
ところが、そのじいさんが色々な騒動を起こす。
でも祐介はじいさんを信頼しており、ある日遠い所へ二人で飛んで行ってしまった。

「いっすん坊」てなんなんだ
こいちろう
児童書・童話
ヨシキは中学一年生。毎年お盆は瀬戸内海の小さな島に帰省する。去年は帰れなかったから二年ぶりだ。石段を上った崖の上にお寺があって、書院の裏は狭い瀬戸を見下ろす絶壁だ。その崖にあった小さなセミ穴にいとこのユキちゃんと一緒に吸い込まれた。長い長い穴の底。そこにいたのがいっすん坊だ。ずっとこの島の歴史と、生きてきた全ての人の過去を記録しているという。ユキちゃんは神様だと信じているが、どうもうさんくさいやつだ。するといっすん坊が、「それなら、おまえの振り返りたい過去を三つだけ、再現してみせてやろう」という。
自分の過去の振り返りから、両親への愛を再認識するヨシキ・・・

不幸でしあわせな子どもたち 「しあわせのふうせん」
山口かずなり
絵本
小説 不幸でしあわせな子どもたち
スピンオフ作品
・
ウルが友だちのメロウからもらったのは、
緑色のふうせん
だけどウルにとっては、いらないもの
いらないものは、誰かにとっては、
ほしいもの。
だけど、気づいて
ふうせんの正体に‥。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















