1 / 4
1F原発復旧3号機カバー酔夢譚 【21】~【30】
しおりを挟む
【21】いわきの夏2011
【22】無骨伝3
【23】緑人間とコンクリート人間と泥んこ人間
【24】帰省直後のがん死
【25】若社長の急死
【26】遮へいスーツと被ばく隠し
【27】靴と怪我
【28】警報無視という違反
【29】お漏らし
【30】首根っこ掴まれるゼネコン派遣社員
【21】いわきの夏2011
立葵がてっぺんまで咲くころ梅雨は明けて7月下旬の酷暑がやってくるが、30℃超えの酷暑の期間は一週間だろう。酷暑も収まりだしたころがお盆だ。
いわき市は浜通りであり東北のハワイなどと呼ばれ過ごしやすい気候である。冬はマイナス2度くらいにはなるが八王子レベル。夏は海風と偏西風が渦巻いて北からの風が流れてくることが多い。
福島県外の人はいわきと言えば常磐線いわき駅を指す。地元ではいわき駅の辺りを平と呼ぶ。いわきとはいわき市のことで、南は茨城と接して勿来の関で知られる常磐線勿来駅、北は久ノ浜町の常磐線の末継駅まで直線距離約50km。広野双葉郡広野町と接する。広野町にはJヴィレッジがある。避難区域の楢葉町もJヴィレッジに掛かっている。その先は避難区域だ。西は郡山との中間まで。県内では会津、中通り、浜通りと南北に分けるが、いわき市は浜通りの中心でもある。西の直線距離も40kmある。
観光では、“吹く風を勿来の関と思へども、道もせに散る山桜かな“で有名な勿来の関文学館、平安時代の白水阿弥陀堂、水族館のある小名浜、夏井川渓谷、スパリゾートハワイの湯本温泉とそこにある石炭化石館、沢登りのマニアックな背戸峨廊渓谷などがある。
ただ、県外から観光目的でツアーするにはスケール感の何かが足りない。首都圏や全国からの観光名所と言えばスパリゾートハワイだろう。しかし原発事故で湯本温泉街の営業はストップしている。
常磐線いわき駅周辺には標高605mの赤井嶽があり、閼伽井嶽薬師がある。首都圏にあればハイキングにはうってつけである。
また夏井川には鮭が遡上し支流の好間川が流れる団地付近にも鮭の産卵場がある。そこはアユ釣りもできて、東京からは車と徒歩で行ける最も近い釣り場でもある。冬は白鳥の飛来があり騒がしい。
しかし過酷事故以後は山も川も温泉もセシウム飛散が原因により、どこも人の通わぬ場所になっている。スパリゾートハワイもいままでは東京から毎日バス数台、千葉からも横浜からもやってくるがストップした。
鹿山建設事務所にも関西以西からくる社員がいるが彼らの中には、着任の挨拶で、いわき駅を降りたら市民は全面マスクを着けて歩いているのかと思っていた、と言う者もいる。
「常磐線から降り立ったとき、この格好でいいのかと不安だった」と。
過酷事故以後にいわき平のホテルには報道陣やタレントが宿泊していた。予約もなかなか取れない。ニュース報道記者、レポーター、ボランティアのタレントたち。ゼネコンや大手メーカー企業の宿泊も定宿としてホテルを使っていた。
いわき駅周辺の繁華街は除染や原発作業員のバブル期だった。
最もバブルだったのは浜通りの6号国道に沿ったコンビニだ。除染や原発作業員で全国一の売り上げを達成していた。弁当は天井まで積み重なった。
その日は9時から27度を記録し、午後はおそらく30℃は超えるだろうと思われた。
瓢タンが駅前のロータリーを歩いていると突然声を掛けられた。
「すいませんが、原発関係の方ですか?」
「まあそうですが」
「ちょっとアイスコーヒー飲んでいきませんか?」
きょうも酷暑かなと思いつつ歩いている瓢タンは気安く返事をした。
「目の前のラトブの珈琲館でいいかな?」
ちょうどアイスコーヒー飲もうと思っていた矢先だった。
その女性はフリー記者でいわきに取材しにきていた。
「原発の仕事ってたいへんなんですね、いろんな下請け組織があって、給料もかなり違うって新聞で・・」
「そうなんですよ、復旧で数千人の人をかき集めているから。職人とは別の世界の反社関係と思われるような全身タトーとかも入ってくるし。」
「そういう構造で安全なんでしょうか?無関係の外人記者が入構証偽造して入ったとかありましたが?原発ってセキュリティの最先端ではないのですか?」
「セキュリティの最先端と言っても、いまはメルトスルーしちゃった後ですから、守るべきものがないでしょう。セキュリティを突破するって言っても、得る物は被ばくだけですから。セキュリティを突破する動機が見当たらない。逆にいまの時期は、被ばくのための人集めかもしれません。審査を厳しくやってたら被ばく要員は集まりませんよ。」
実際に現場では、ほぼどんな者でも手足が動けばよかった。高線量瓦礫を運べればよかった。重機運転の免許なくても誘導の立ち仕事でだけでも人は欲しかった。重機運転は放射線防護されているが誘導は遮蔽スーツだけだ。
「被ばくジプシーってこと?」
「いやあれは事故前の通常運転の原発保守作業員のこと。今はとにかく被ばく作業員集め。」
「危険手当はほんとうに出てるんですか?ピンハネが横行しているとかないんですか?」
野党の中には危険手当が支払え、の活動があるが現実には奥が深い。東電から支払われる日当と危険手当。ゼネコンや日立東芝三菱のような大手企業のような月給保証制度と下請けの日当制の違いがある。そして福島第一の現場では政府や規制委員会や外部団体などの要望などや、東電の工事計画の変更や、元請けの計画変更や、そんなのが重なって変更が多い。そのたびに工事がストップする。
月給制では途中で作業がストップした場合、危険手当は日当なのでストップするが月給は支払われる。
日当制では作業ストップした日から日当も危険手当もストップする。だから下請けは危険手当をプールしておいて作業員の日当はそこから或る程度補償する。さらに下請けを経由する度に会社経費を差し引かれる。
「そういうことで、税込み月30万円弱で四苦八苦する者もいれば、残業代も含めて百万円稼ぐ作業員もいる。」
女性記者自身がフリーで、月給制ではないので日当制の作業員の立場や実情が理解ができたようだ。
「東電や政府は危険手当を直接作業員に支払うことはできないでしょうか?」
「作業員への個別な危険手当という名目ではないんですよ。ゼネコンや日立東芝三菱など元請けが請け負った工事の全体に掛かっているから、元請けとしては下請けに作業員の合計で日々の計算で支払うけど、いろんな理由で作業ストップとかが多いので、下請け会社が作業員にそのまま支払らうわけではなく、作業ストップの時でも日当を支払うために積み立てている場合もある。ただし中にはそのまま全額2万円を作業員に払っている下請けもあるし、元請けでも大小さまざまあって、上場以外の中小企業では5000円だけ下請けに支払っている企業もある。」
瓢タンはそんな世の中のありきたりのピンハネ状況を立て板に水を流すように説明したのだった。
珈琲館のコーヒーは美味かった。
【22】無骨伝3
酷暑で現場では作業員の熱中症が何件も発生した。ゼネコン社員はさすがに肉体労働ではないので熱中症はでないが体調は勝れないようになっていった。というか作業員はゼネコンが建設したプレハブ宿舎で、低家賃月3000円に住んでいるがゼネコン職員はホテル住まいである。そこで毎日いわき平の夜の街へ繰り出すクラブ活動は止まらない。
夏場の原発復旧作業は熱中症防止のため昼間2時以降5時までは禁止になった。そこでみんな1時間早めのサマータイムとなった。宿舎では4時に起きて4時半出発、6時半に構内休憩所に着く。作業前ミーティング、防護服に着替え、8時半に現場、9時半に終了。10時前後に休憩所に戻って作業後ミーティング。11時には帰りの帰途につく。昼飯は宿舎だ。
時間をそれ以上早めると朝食抜きになってしまい、逆に熱中症になりやすい。
復旧作業での私病による死者も数件でている。
マスコミの関心が高まれば世論の注目を集める。したがって政府の目も厳しくなる。そうなると電力会社への政府要求も増してくる。それは末端作業員の安全健康のためと言いながら、電力会社の下につく大手元請け企業へのいろんな手笠足枷となって、さらにそれが下請けへと弱いものへしわ寄せが行く。
熱中症予防の最大の効果は睡眠時間と朝の食事である。それは作業員個人管理となる。現場で管理できることは作業時間を小刻みにしてエアコンの効いた車の中に退避する数を多くすることだが、実際にはそんなことしていると当日予定の作業が終わらないので退避回数は少なくなり、現場での監視役がいるわけではないので作業員任せ、つまり現場も個人管理となり、末端にしわ寄せが行くことになる。
管理を細かくすると作業計画書の内容が細かくなるし、書類の数も量も多くなる。予定していない作業はしてはいけない。となるとゼネコンの業務は図書作成だけでも煩雑なものになる。
電力会社「○×の計画書類ですが、ちょっと矛盾しているところがあるので見直しお願いします。」
電力会社から指摘を受けると再提出~打合せとなる。書類などは、説明なしで書面だけで終わらせようとすればどこかに説明不足や表現不足が見つかる。机上で粗さがし探しをやっていても現実の作業は進まない。ゼネコン社員は電力会社を電力さんと敬称付けることが多い。発注元なので普通の現場では、お客様は神様である、復旧作業では、駄々っ子である。復旧は全国から注目されており、政府や規制委員会からの指摘で方針をころころ変えるからである。
元請け「見直しって、作業はもう明日から作業ですよ。」
電力「じゃあ早朝の作業前に再度打合せしましょうか。」
元請け「早朝?・・・ああ、いいですよ、まだその時間酔っぱらってますが」
電力「・・・それでは来なくていいです」電話は切れた。
この工事監督は深夜というか2時過ぎまで飲んでいる。打ち合わせのために酒を断って出勤するという感覚が無い。仕事をするためにはまず酒が必要である。
9時頃からいわき平の歓楽街に繰り出し、深夜12時頃まで飲んで、店を変えて二次会、そして最後に中国飯店でラーメンたべて2時に締める。飲むほどに仕事が捗るらしい。なので早朝はまだアルコールが抜けない。電力の事務所内でアルコールが検出されればルール違反となる。
打ち合わせは無くなったが、こういう場合、免震棟での作業前確認の際に電力から急遽変更指示がでたりする。
もうひとりのゼネコン社員も監督を見習って強者である。彼が提出した資料に訂正箇所があり電力会社から強く批判されたが電力会社社員のその言い方が上から目線だから嫌いだという。
電力会社「じゃあいまからお話ししますか」
ゼネコン社員「いまから?・・・行けませんね。」
電力会社「どうしたんですか、なぜ来られないのですか?」
ゼネコン社員「体調が思わしくないです」
電力会社「体調?」
ゼネコン社員「はい、そうです。」
原発では老齢の作業員の相次ぐ私病突然死があり、その対策として作業員の健康安全優先。ということで、体調管理の徹底を方針にしている。健康管理最優先である。
電力会社「来ることができないくらい悪いですか」
ゼネコン社員「はい、悪いです、ではまた」
彼は受話器を置いてから呟いた。
“あいつと話していると体の具合がわるくなってくるんだよ・・・”と。
【23】緑人間とコンクリート人間と泥んこ人間
原子炉建屋周辺の道路、路盤上の瓦礫撤去~鉄板敷作業は延々と続くように感じた。600トンクレーンなど大型重機が走るたびに分厚い鉄板が歪むのである。そして敷き直しする。
Rw/Bの屋上からは撤去した瓦礫が降りてくる。瓦礫を片付けるたびに粉塵が飛散しないように緑の飛散防止剤を撒いて粉塵を固着する。
緑の飛散防止剤をホッパーという機械をつかって遠隔操作で撒き散らす。オペフロの上は人間が立てないので遠隔操作で撒く。しかし、道路上では人間がバケツで撒いたほうが早い。バケツで撒けば自分もその緑の飛散防止剤を被ることになる。
道路には飛散防止剤を被って白のタイベックスーツが緑色になった緑人間が歩き回る。現場を移動する乗用車も緑。瓦礫が緑。怪しげな世界になっていった。
モルタル散布で地面を固める作業も続いて、そのため白タイベックスーツは灰色になる。上から下まで灰色だ。
土木工事では関東ローム層の赤土を被って全身土色になる。
昼休み前になれば、一斉に現場から帰ってくる。すると汚染検査が間に合わないから免震棟の復路入口は緑人間、灰色人間、土色人間の行列ができた。誰もが一目散に免震棟休憩所に戻ってくる。
サーベイ要員やサーベイエリアにも限度があって汚染検査まで30分かかる。検査棟入り口は検査待ちの行列ができる。屋外では全面マスクは外せない。検査棟建屋に入ってから外す。屋外で全面マスクそのままの緑と灰色と土色の人間が列を進んでゆく。
昼食はやく食べたい、の思いを全面マスクの中で噛み殺してじっと待つのだった。
瓢タンが現場測定から帰ってきて全面マスクを外すと隣にはゼネコンのヤッシーこと林田安全社員がいた。彼は瓢タンと同じ派遣社員である。
瓢タンはタイベックスーツを脱ぎながら、全面マスクを外した隣の男に言った。
瓢タン「なんだヤッシーか。おまえタイベック緑じゃないか。シュレックか、ハルクか。」
ヤッシー「飛散防止剤を重機ホッパーで撒いてるけど、撒ききれないところはバケツで撒くんだよ。手作業だよ。」
瓢タン「重機の遠隔操作じゃないんかい?」
ヤッシー「遠隔操作なんて報道の見出しだけだよ。現場はそんなもんじゃないよ。人間がバケツで散布するんだよ!」
【24】帰省直後のがん致死
タービンとは原子炉で沸かした蒸気により発電する装置であり、原子炉建屋に隣接する。その建屋と原子炉建屋のの下屋と呼ばれる屋上に架台をつくってそれが原子炉建屋を取り囲む際の東側の架台となる。原子炉の燃料をクレーンで釣り上げるためのドームを支える架台である。
タービン建屋は原子炉隣の台地のようなイメージであり、そのため作業員はそこを203高地と呼んでいた。鬼瓦の親方の土方の命名だった。遮蔽スーツを着てもそこにいることができるのは3分だった。そこでウルトラマン作業とも呼んでいた。
203高地にゆくためには単管パイプで組み立てた階段をのぼらなければいけないが、14kgの遮蔽スーツを着て一気に登りきるには40~50過ぎの年代にはきつかった。
北海道からきた50代の作業員が単管梯子の途中まで登って、うづくまった。14kgを背負って階段を登るには体力が不足していた。一度息が切れると回復が難しいみたいで、作業をせずに降りる元気しか残っていないみたいだった。
その後、その作業員は北海道へ帰って、まもなく肺がんで亡くなったが、これは私病といって持病によるものだろう。原発作業に来る前から癌だったと思われる。なぜなら放射線による晩発性の癌はすぐには現れない。
放射線被ばくの影響は確定的、確率的と二分される。確定的なものは直後に症状がでるから確定的と言う。
確率的な影響で比較的短期間で症状が出るのは白血病だ。そのため厚労省も白血病は5mSvという低線量被ばく歴を妥当性の必要条件としている。放射線の影響か、影響なしか、どちらも証明は難しい。証明ができるとしたら、遺伝子解析によってその癌がいつ発生したか突き止められる頃だろう。原発作業の時期に癌がスタートしたと証明できれば因果関係は科学的に証明できる。
白血病以外の症状では癌があるが細胞が癌と言われるまでには相応の年数がかかる。原発にやってきて誰もがAB教育と言う放射線被ばく防護のための新規入所教育を受けるが、そこでは確定的影響にはそれぞれ症状に応じて閾値があるが、確率的影響で例えば晩発生の致死性癌などには閾値が無く被ばく線量0mSvから直線的に放射線影響の確率があると教える、これをLNT仮説という。1Sv5%で比例計算した致死癌確率はそのままでは評価できず、個々の日常の生活リスクと比較して評価することになる。
比較リスクは児童ではほぼ0であり、年齢とともに比較リスクが高まり、生涯では致死癌26%である。特に児童の親は子供のリスクは0を願って、できるかぎり子供をリスクから守っている。
労災では50mSvを超えると晩発性癌の因果について妥当性のひとつの目安としている。50mSv以下であっても因果関係を否定できないならば、疑わしきは排除しない、ことが科学的態度と言える。
放射線作業従事者は5年間100mSv(致死性癌確率0.5%)、70歳での生涯1000mSv(致死性癌確率5%)は、日常の致死性癌確率26%とそれ例外の死亡率、作業場の死亡率確率合計に比べれば許容範囲としている。統計は広島長崎原爆を元に致死癌だけのデータである。それ以外は検証できていない。
た放射線作業従事者ではない18歳未満(一般公衆)の場合は、もともとの死亡確率はほぼ0に近いので、年間1mSvを超えることがないように、放射線施設の事業所境界の線量率を年間1mSvで規制している。事業所境界から離れれば更に低くなる。1mSvの致死癌確率は0.005%で、比較するべき日常の児童の10年後の致死癌確率0.1%に対して10%未満なので許容されると政府は考える。
原発作業にやってきて被ばく基準を守って作業して、すぐ帰って、すぐに癌になって死亡するということは考えにくい。
原発の復旧作業には全国からいろんな派遣会社を経由して、さまざまな日雇い労務者も入ってくる。そういう人たちの中には以前からの日々の自己管理不足もある。
人口動態では日本の年間死亡数は約120万人前後であり100人に1人がなくなっているが、職業上の年間死亡数は平均約1000人に1人という統計がある。
復旧現場で作業するのは平均年齢が60歳前後なので死亡率は更に高いはず。人口4千万人に対して日常で約2.5%の年間死亡率であり、生涯致死癌率26%である。
原発復旧作業では4千人が従事しており60歳以上が500人いるとして2.5%は12.5人だから、年間数人が私病で死亡しても確率的にはおかしくない。
メディアに発表されているのは原発作業中の死者であって地元に帰ってからの統計は調査していないが、放射線労災認定については富岡労基署の記録を調べればわかるように情報公開されている。
【25】若社長の急死
珈琲館でアイスコーヒーを一緒にしたフリーライターから瓢タンに連絡があったのはお10月だった。いわきでは過ごしやすい気候である。
「原発の作業員ルポルタージュの本を読みました。」
労働者の実態に興味があるらしい。原発の復旧作業ではいろんな労働者の実態がよくわかるのではないか、というのが彼女の興味だ。
・・・
作業員を集める具体的な方法はゼネコンの下請け先による。一次下請けのY工業、T工業など鳶職や雑工といった作業者集団がある。そこへ正社員として就職するか二次下請け、三次下請けからの採用となる。一次下請けの正社員では月給制であり、二次、三次となると日当制となる。
T工業とY工業では賃金体系は異なる。ゼネコンからは危険手当が一人当たり最大2万円。構内の勤務エリアはそのエリアの空間線量率によって5千円、1万5千円、2万円と異なる。あるいは当人の被ばく線量によって変える場合もある。
また一方は一日1万円の危険手当がつくが一方は5千円しかつかない。しかし一方は基本賃金が20万円で、一方は30万円。というふうに賃金体系も異なる。
多重下請けになると危険手当1000円、日当1万円とかもある。そういう作業員が、まともな手当をもらっている作業員の話をきくと、その途端に自分が下請け構造の下層にいることを嘆く。いろんな事情があろうが、同じ仕事で賃金がおおきく異なると仕事のやる気がなくなる。
ゼネコン職員は全員危険手当の基準は同等だ。東電は危険手当を総請負金額に上乗せして元請けゼネコンに支払うが、現場作業員への支払いを東電が約束しているわけではない。
労働基準監督署から支払い手当の指導をうけているが、一次下請け、二次下請け、三次下請けは概ね2万円に会社経費を引けば1万円~5千円だろう。
元請けの中にも大手だけでなく、中小企業もある。中小企業の元請けの中には危険手当は支払いませんと言う強者もいる。労基署がその理由を聞くと「お金目当てで仕事をしている作業員なんて集めてもろくなことありません。」と答えた。会社としては個々の危険手当をきちっと2万円東電からもらっている。
実は同じ会社内のいわき事務所内で火力発電現場もあり、そこでは危険手当などない。原発復旧社員だけ2万円付けると、火力現場の社員もみな原発復旧へ行きたくなる。それでは会社の統制がとれない、という理由だった。
ただし中には2万円そのまま手渡す一次下請け企業もある。光電技術はそのひとつだった。
光電技術の二代目若社長は社員の作業現場を確認するために短期間だが1F復旧現場に足を運んでいた。短期間と言うのは年末までのこと。
そして免震棟の休憩所に来て、いつも口癖のように言う。
「うちは危険手当はみんなにそのまま2万円払っているからまったく儲かりません。そもそも一般の現場は請負ですので会社経費も諸経費も資材費もいただいてますが、ここは人件費だけですので、会社経費倒れですよ。ほんとに文字通り復旧作業に協力しているだけ。請負ではなく作業だけだから儲けはないです。本音を言うと撤退したいのです。」
そう言いながら若社長は白いスーツに外車を乗って颯爽としていた。
あとから偶然ネットで知ったが、お別れ会が開かれていたが、その呼びかけ人が有名コーヒーチェーンから参議院になった政治家で、参加者は芸能タレントの神田うのなどがいた。かっこいい若社長だったが社交もかっこよかったようだ。。
だった(過去形)というのは2011年末に東京に帰った途端に急死したのだった。
若くて元気なのに不思議な急死だった。短期間の現場視察なので被ばく線量は数Svくだいだろう。労災申請する基準以下である。
普通40歳前後の日常の年間死亡率は0.1%に近い。だから同級生には見つからなくても同窓生など調べてみれば意外な人が若くして急死していることがある。
その後も不思議な死は瓢タンの周りで起こって、鹿山建設の中で鉄腕レースを趣味にしている中年ランナーが急死した。え?あの元気な人が?と思うような人が急死することが世の中には意外と身の回りにある。
【26】遮蔽スーツと被ばく隠し
3号使用済み燃料を取り出すためには原子炉建屋を覆うドームが必要で、そのドームを支えるための建屋を覆う鉄骨カバーが必要となる。夏を過ぎて原子炉建屋カバーを設置するための地上のエリア平均線量は1mSvに低下したがさらに路盤整備で0.5mSvを目標にしている。
一時間で1mSv被ばくすると作業者がどんどん規定限度に達して現場から去らねばならない。そこで放射線遮蔽スーツを着用して最低でも40%は放射線カットしたい。その場合被ばくは1時間0.6mSvである。
環境を一時間0.5mSvまで低下させれば、作業者の被ばくは一時間0.3mSvになる。
30分で0.15mSv、ひと月10日で1.5mSv、年間18mSv、これが一年を通して作業続けるための上限である。日当で生活する作業員は0.1mSv/h以上の高線量エリアの作業やそれ以下の低線量エリアの作業を入れ替えながら毎日計算しながら一年を凌いで次の一年に食いつないでいかなければいけない。
遮蔽スーツには2つの型式があり、ひとつはワンピースタイプ。もうひとつは頸部スカーフとベストと腰スカートのセパレートタイプだった。しかし使い始めが夏だったのでセパレートタイプのスカート部分は外してベスト(胸腹のチョッキ部分)だけ着用するケースが多かった。
放射線管理上では被ばく線量を正しく反映させなければいけないから、セパレートな遮蔽スーツは作業員個々に付けたり外したりできないように縫い付けることにした。革製品用の手縫い針とストレッチャーを使って手縫いした。そしてベストとスカートは縫製され一体型となった。
首は頸椎の被ばく保護で大事なところだとかいうことで頸部スカーフとベストの組み合わせで作業する者もあった。頸椎には骨髄があって造血機能があるから首を守らないといけない、と鳶職の親方の鬼瓦のような土方が瓢タンに言った。
「俺は調べて知ってるんだ。頸椎を守る鉛入りスカーフがないと骨髄の被ばくをして、白血病になるんだ。」
203高地の名付け親方が物知り顔に言った。
しかし遮へいスーツを使用した場合の被ばく計算には頸椎の要素はなかった。むしろ造血機能は骨盤のほうが多い。
スカーフもスカートもあった方がいい。しかし不均等被ばくという計算をする際には首の遮へいは計算ファクターには主として入らない。
そこで瓢タンは言った。
「首も鉛で遮蔽したほうがいいですが、それより骨盤を守るスカートだけは必須です」
どっちも着けるとなると作業員は面倒くさがった。結局どっちか選ぶなら骨盤を守るスカートだということを理解してもらった。
白血病は罹患まで足の速い症状だが、最初の年の夏にはそこまでの事象発生はなかった。厚労省では最低5mSv以上の被ばくと1年以上の経過で労災の条件に入る。そして白血病にも種類があり、骨髄性白血病又はリンパ性白血病であること。となっている。
身体の被ばくを防ぐために遮へいスーツを着用するが、その場合被ばく線量を正しく計算してシステムに反映する必要がある。
単にAPD数値だけ下げたいなら、5センチ四方の鉛板をAPDに張り付ければよい。
しかしその方法は放射線被ばくとそれによる身体影響の統計が合わなくなるという点で違法であって、実際に100mSv被ばくしているのに50mSVと記録されるようになってしまうと疫学統計に生かされないばかりではなく、法定限度の5年で100mSvを守ることもできない。
瓢タンとしては法令に準拠して作業者本人の実際の被ばく結果が正しくになるように放管として指導するばかりだ。
APDを5センチ四方の鉛板で覆うという安易な遮へい方法は誰でも考えるところだが、鹿山建設ではない他の元請け作業では、実際にそれをやった作業員がいて、違法行為という大きな事件となるのだった。
さらにその後、APDをどこかに隠して置くという離れ業をやってのける作業者がいることも発覚したのだった。
それらを監視するために出口管理の放管が目視で検査できるようにタイベックスーツの胸部分を透明ビニール窓を付けるように改善されていったのだった。
【27】靴
作業員のクレームは自分の足の大きさに合った靴がないことだが、電力会社は靴は揃ってます、と回答する。靴を用意する電力会社も大変で、数、大きさ、そして靴の形状種類。形状種類は短靴、長靴、中靴の3種類あるがいずれも形式はレインシューズで、つま先が安全用鋼板入りのどた靴である。作業者の不満は数ではなく、自分に合った靴があるかどうかだ。ぶかぶかの靴では復旧現場のようなでこぼこの路面はつまずいて転んで怪我をしやすい。
つま先に安全鋼板を仕込んであり、24cm25cm26cm27cm28cm29cm~とあるが紐もマジックベルトもついていない、見かけはコックシューズとか防止レインシューズとかで、安全ドタ靴だった。 24cm25cm26cmは使用中で27cm28cm29cmが靴箱に余っている状態だとすると、電力会社としては、余っている靴があるから、靴は足りています、という考え方をする。したがって作業員は自分に合わない27cm28cm29cmから選ぶしかない。自分に合わないのでつまづいたりすることが多くなる。
元請け企業ごとに一般とび職用の靴を用意することもできるが、毎日汚染検査をして管理しなくてはいけない。だからなかなか対応できる企業はいない。東電支給の靴は電力会社が汚染検査管理してくれる。だから仕方なくドタ靴を使う。長くつは比較的脚になじむが夏は暑くて履いていられない。冬は逆に長くつでなければ足指が凍るほど冷たい。
自分に合わない靴だけが残っていてそれを使わざるを得ない現場の実情について、電力会社は作業の目的で現場に出たことないからその辺が良くわからない。
転んでねん挫したとか怪我したとかの軽傷事故が毎月のように発生した。「自分の身は自分で守る。これを徹底してください」 電力会社の安全指針は変わらない。 靴底に汚染が残ってそこから放射能が染み込んで軍足に滲みて、足裏表皮が汚染する場合もある。これをもらい汚染という。電力会社の汚染管理と言っても毎日やるわけではないからだ。
足裏の汚染は作業後に身体サーベイで判明する。処置は除染、つまり洗浄すればよい。問題点は作業員が作業を終えてあとは帰るばかりのときに、汚染が見つかると30分も手間をとってしまう。その結果原発からJヴィレッジ行の帰りの目的時間のバスに乗り遅れる。日常の行動サイクルが変則になるということで作業者もできるだけ汚染はしたくない。
本来は靴の中が汚染しているかどうか毎日測定検査しなければいけないが、電力会社でも、さすがにそこまでのことは対応できないので一週間に一度くらいで精一杯だ。 靴に針のように穴が開いているかどうかも気になるが、靴を水中に沈めて発泡検査も行っている。そのような穴から汚染が染み込むのならその時点でその靴を廃棄する。 それ以前に、靴の中が汚染しているかどうか、ガンマ線では測れない。外のガンマ線が中まで通過する。ベータ線は通過しないからベータ線を測れば良いが靴の中に入れるセンサーなどは開発していない。
そこでスミヤ測定法といって靴の中を濾紙で拭き取ってみてから濾紙に付いた汚染(ベータ線)を測る方法を採用するがそれだけ余計な手間がかかる。
「自分に合うサイズの靴がないなら、電力の係員にリクエストして、出してくれるまで待てばいい」
瓢タンは作業員にそう教える。しかし作業員は暇人ではない。電力の係員が現場に居ないことの方が多い。だんだんリクエストなど面倒になってくる。そして自分に合わないぶかぶか靴で作業して、鉄板の段差に躓いて転ぶ。そして怪我の統計ではつまずき転倒がダントツで多いが、そんなことが実情だった。
【28】警報無視という違反
作業員はタービン建屋下屋を203高地とか、そこの作業をウルトラマン作業とか言っていたが、原子炉建屋の剝き出しのオペフロ上の放射線量はもっと凄い。測定値2.0Sv/hなどの測定値が出たりするとタービン建屋下屋屋上の100mSv/hの数値が可愛く見えてきた。
昨日やってきてまだ二日目の鳶職が3人、原子炉建屋の南側仮設梯子を登って最上段のオペフロ近くの仮設単管パイプの金具を締めに行った。作業終えてから、まだひとつ締めていない箇所に気がついた。そのときAPD警報がキュイーンとプレアラームが鳴動した。ルールでは被ばくを避けるために直ちに作業を終えてその場を仕舞って免震棟休憩所に戻らなければいけない。しかし本人としては、あと一本締めるのは1分もかからないということで引き返して作業を終えた。すると今度はビービービーという最大警報が連続鳴動した。その音は免震等で遠隔監視している監視員にも聞こえた。ちょうど監視員はとび職の親方で鬼瓦の赤ら顔の土方だった。
「おい、おまえ最大警報なってるぞ。すぐに戻ってこい」遠隔監視のマイクから叫んだ。
「は~い、ちょっと工具忘れたんで取ってきま~す」
「バカ、戻れといってるんだよ」
「でも工具が」
「そんなのどうでもいいんだよ!バカ」
そういっているうちに5分もたってしまった。原発復旧にきてまだ二日目であり、本人も焦っており、右往左往して手間取った。
戻ってきた時には作業員のAPDは2.5mSvを示していた。怪我をしたわけではないが、2.0mSVを2割以上も超えると警報無視、つまり故意のルール無視とみなされ、事故事象扱いとなり顛末書対策報告書を電力会社に対して書かなければいけない。
ほんとうに故意の警報無視であれば本人は田舎に帰って一般の工事作業に従事するところだが、今回は遠隔監視でも指導していたし、本人の故意ではなく、右往左往するのは初心者の常、ということで現場に残ることになった。
作業者を帰すことは元請企業の命令ひとつでできるが、その際に十分な納得を得られないといけない。もし本人が納得しない場合には地元に帰ってからメディアに原発現場のことをチクル可能性もないわけではない。
電力会社とそこに従事する作業者全体、元請下請け共に原発内のことは機密情報として公言してはいけない。不本意に解雇された作業者の場合はそんな約束事を無視することもありえるのだった。だから福島原発の復旧現場解雇でも次の現場をあてがうなどして作業員の面倒を見るようにするのが常套手段だ。
【29】お漏らし
3号機現場周りにはトイレはない。というか1Fの構内作業現場にはトイレはまだない。トイレは免震棟や厚生棟と呼ばれる休憩所建物の中にある。
放射性物質の飛び散った1F現場ではズボンを脱ぐことはできない。白いカバーオールと綿手、ゴム手二重、軍足靴下二重、それに防毒用の全面マスク、足、手とマスクとカバーオールは空気が入らないようにガムテープで密封する。そんな状態では野グソもおしっこもできやしない。
Jヴィレッジで着替えをして構外の仮設プレハブ休憩所で一旦休憩し、そこを出発点として再度免震棟で着替えをして現場へ行く段取りの作業で、瓢タンの面の前で起こった。
夏のある暑い日、トイレがすぐ近くにないのでおしっこの我慢も限界というものがある。作業員の大黒は構外休憩所に戻ってきて、タイベックスーツを脱いだとたんにその顔の表情が恍惚状態に変わった。床をみたらおしっこが流れていた。
1Fの現場に出るとトイレはない。トイレするにはまず車で免震棟に戻り白カバーオールと全面マスクと綿手、ゴム手、軍足、要はパンツ一枚になって、汚染検査を通ってから休憩室に入り、休憩室のトイレを使わなければいけない。
ところが夏になれば熱中症予防のために沢山の水分を取ることを義務つけられているので、現場でおしっこをしたくなる。そこで免震棟や所定休憩所までたどり着いてからおもらしする者も出てくる。汚染検査受ける手前でタイベックスーツを脱ぐがその時点でタイムアウトしたのだった。
事務所としては、あらかじめ危険予知して、介護用おむつを、依頼した。しかしJV事務所では最初の夏に在庫をたくさん抱えた。
購入したがみんな見てくれや恰好を気にしておむつを使わないので在庫が事務所のスペースを圧迫してしまい、在庫処分のために瓢タンも祖母に配ったりして在庫減らしを手伝った。
その後、山の中の重機廃棄置き場の現場で放射線管理していると、別の作業員が言った。
「瓢タンさん、ちょっと向こう見ててください」
白いタイベックスーツはチャックのつなぎだからやろうと思えばオシッコは思えば可能だ。しかし汚染しないように、ゴム手袋を新品に代えてから行う。大事なところが汚染したら、報道機関に発表されて、恥ずかしい思いをする。
【30】首根っこ掴まれるゼネコン社員
太平洋に面した原発は海の方から4M(メートル)盤、10M盤、高台(33M)と三段階の敷地がある。Mは海水面からの高さで、4M盤には非常用電源のオイル用タンクやタービン建屋からの復水タンクなどが設置してある。10M盤には原子炉建屋。高台には免震棟など事務所設備。
10M盤といわれる地上道路に3号機入口の大物搬入口がある。扉は爆風で吹き飛ばされている。海から風が吹くと大物搬入口前の線量率は急上昇する。まだヨウ素が存在していたのかセシウム粉塵の仕業か。
そんな頃3号JVの大手ゼネコン職員の中には人材会社雇用でJVの名刺を持たせた派遣社員がいる。JV正社員職員の代わりに被ばくをするようなものだった。作業員の作業監視のために立っているだけで一日2mSV被ばくするのだ。
派遣JV職員の大黒は監視のため立ち仕事(免震等との連絡係)を端折って、いつも待避所に避難していた。そうしないと一ヶ月に20mSV二ヶ月に40mSvの被ばくしてしまう。そうなると2ヶ月で現場を去らなければいけないので、毎日の1万円の手当てがそれで終わってしまう。本来は2万円だが半分は派遣元の経費だ。
残業100時間で20万円、手当20日間で20万円。計40万円。それに毎月の月給が30万円。併せて70万円。こんな現場は他にはない。なんとかしかしてもっと長期間継続したい。そのためには被ばくを低減すればいい。現場の待避所と言う線量率の低いところに閉じこもっていればいい。
それを下請けの作業員にみつかった。作業員は休憩所でいきなり切れて、JV派遣員の首を捕まえて言った。
「こら、なんでいつも逃げるんだ。ふざけんなよ。俺たちが現場で被ばくしてるのにおまえは逃げてばっかりじゃねえか!」
作業員も被ばくを避けたい。みんなそれが本心だ。そしてみんなそれぞれ自分の工夫をしてなんとか被ばく線量を下げている。
線量率の高いほうへ向かず反対側へ向く、下着ポケットのAPDを手で覆う。線量率の高い場所から離れる。APDの被ばく線量数値を下げたい者は、みんなこまめに工夫をして作業している。
【22】無骨伝3
【23】緑人間とコンクリート人間と泥んこ人間
【24】帰省直後のがん死
【25】若社長の急死
【26】遮へいスーツと被ばく隠し
【27】靴と怪我
【28】警報無視という違反
【29】お漏らし
【30】首根っこ掴まれるゼネコン派遣社員
【21】いわきの夏2011
立葵がてっぺんまで咲くころ梅雨は明けて7月下旬の酷暑がやってくるが、30℃超えの酷暑の期間は一週間だろう。酷暑も収まりだしたころがお盆だ。
いわき市は浜通りであり東北のハワイなどと呼ばれ過ごしやすい気候である。冬はマイナス2度くらいにはなるが八王子レベル。夏は海風と偏西風が渦巻いて北からの風が流れてくることが多い。
福島県外の人はいわきと言えば常磐線いわき駅を指す。地元ではいわき駅の辺りを平と呼ぶ。いわきとはいわき市のことで、南は茨城と接して勿来の関で知られる常磐線勿来駅、北は久ノ浜町の常磐線の末継駅まで直線距離約50km。広野双葉郡広野町と接する。広野町にはJヴィレッジがある。避難区域の楢葉町もJヴィレッジに掛かっている。その先は避難区域だ。西は郡山との中間まで。県内では会津、中通り、浜通りと南北に分けるが、いわき市は浜通りの中心でもある。西の直線距離も40kmある。
観光では、“吹く風を勿来の関と思へども、道もせに散る山桜かな“で有名な勿来の関文学館、平安時代の白水阿弥陀堂、水族館のある小名浜、夏井川渓谷、スパリゾートハワイの湯本温泉とそこにある石炭化石館、沢登りのマニアックな背戸峨廊渓谷などがある。
ただ、県外から観光目的でツアーするにはスケール感の何かが足りない。首都圏や全国からの観光名所と言えばスパリゾートハワイだろう。しかし原発事故で湯本温泉街の営業はストップしている。
常磐線いわき駅周辺には標高605mの赤井嶽があり、閼伽井嶽薬師がある。首都圏にあればハイキングにはうってつけである。
また夏井川には鮭が遡上し支流の好間川が流れる団地付近にも鮭の産卵場がある。そこはアユ釣りもできて、東京からは車と徒歩で行ける最も近い釣り場でもある。冬は白鳥の飛来があり騒がしい。
しかし過酷事故以後は山も川も温泉もセシウム飛散が原因により、どこも人の通わぬ場所になっている。スパリゾートハワイもいままでは東京から毎日バス数台、千葉からも横浜からもやってくるがストップした。
鹿山建設事務所にも関西以西からくる社員がいるが彼らの中には、着任の挨拶で、いわき駅を降りたら市民は全面マスクを着けて歩いているのかと思っていた、と言う者もいる。
「常磐線から降り立ったとき、この格好でいいのかと不安だった」と。
過酷事故以後にいわき平のホテルには報道陣やタレントが宿泊していた。予約もなかなか取れない。ニュース報道記者、レポーター、ボランティアのタレントたち。ゼネコンや大手メーカー企業の宿泊も定宿としてホテルを使っていた。
いわき駅周辺の繁華街は除染や原発作業員のバブル期だった。
最もバブルだったのは浜通りの6号国道に沿ったコンビニだ。除染や原発作業員で全国一の売り上げを達成していた。弁当は天井まで積み重なった。
その日は9時から27度を記録し、午後はおそらく30℃は超えるだろうと思われた。
瓢タンが駅前のロータリーを歩いていると突然声を掛けられた。
「すいませんが、原発関係の方ですか?」
「まあそうですが」
「ちょっとアイスコーヒー飲んでいきませんか?」
きょうも酷暑かなと思いつつ歩いている瓢タンは気安く返事をした。
「目の前のラトブの珈琲館でいいかな?」
ちょうどアイスコーヒー飲もうと思っていた矢先だった。
その女性はフリー記者でいわきに取材しにきていた。
「原発の仕事ってたいへんなんですね、いろんな下請け組織があって、給料もかなり違うって新聞で・・」
「そうなんですよ、復旧で数千人の人をかき集めているから。職人とは別の世界の反社関係と思われるような全身タトーとかも入ってくるし。」
「そういう構造で安全なんでしょうか?無関係の外人記者が入構証偽造して入ったとかありましたが?原発ってセキュリティの最先端ではないのですか?」
「セキュリティの最先端と言っても、いまはメルトスルーしちゃった後ですから、守るべきものがないでしょう。セキュリティを突破するって言っても、得る物は被ばくだけですから。セキュリティを突破する動機が見当たらない。逆にいまの時期は、被ばくのための人集めかもしれません。審査を厳しくやってたら被ばく要員は集まりませんよ。」
実際に現場では、ほぼどんな者でも手足が動けばよかった。高線量瓦礫を運べればよかった。重機運転の免許なくても誘導の立ち仕事でだけでも人は欲しかった。重機運転は放射線防護されているが誘導は遮蔽スーツだけだ。
「被ばくジプシーってこと?」
「いやあれは事故前の通常運転の原発保守作業員のこと。今はとにかく被ばく作業員集め。」
「危険手当はほんとうに出てるんですか?ピンハネが横行しているとかないんですか?」
野党の中には危険手当が支払え、の活動があるが現実には奥が深い。東電から支払われる日当と危険手当。ゼネコンや日立東芝三菱のような大手企業のような月給保証制度と下請けの日当制の違いがある。そして福島第一の現場では政府や規制委員会や外部団体などの要望などや、東電の工事計画の変更や、元請けの計画変更や、そんなのが重なって変更が多い。そのたびに工事がストップする。
月給制では途中で作業がストップした場合、危険手当は日当なのでストップするが月給は支払われる。
日当制では作業ストップした日から日当も危険手当もストップする。だから下請けは危険手当をプールしておいて作業員の日当はそこから或る程度補償する。さらに下請けを経由する度に会社経費を差し引かれる。
「そういうことで、税込み月30万円弱で四苦八苦する者もいれば、残業代も含めて百万円稼ぐ作業員もいる。」
女性記者自身がフリーで、月給制ではないので日当制の作業員の立場や実情が理解ができたようだ。
「東電や政府は危険手当を直接作業員に支払うことはできないでしょうか?」
「作業員への個別な危険手当という名目ではないんですよ。ゼネコンや日立東芝三菱など元請けが請け負った工事の全体に掛かっているから、元請けとしては下請けに作業員の合計で日々の計算で支払うけど、いろんな理由で作業ストップとかが多いので、下請け会社が作業員にそのまま支払らうわけではなく、作業ストップの時でも日当を支払うために積み立てている場合もある。ただし中にはそのまま全額2万円を作業員に払っている下請けもあるし、元請けでも大小さまざまあって、上場以外の中小企業では5000円だけ下請けに支払っている企業もある。」
瓢タンはそんな世の中のありきたりのピンハネ状況を立て板に水を流すように説明したのだった。
珈琲館のコーヒーは美味かった。
【22】無骨伝3
酷暑で現場では作業員の熱中症が何件も発生した。ゼネコン社員はさすがに肉体労働ではないので熱中症はでないが体調は勝れないようになっていった。というか作業員はゼネコンが建設したプレハブ宿舎で、低家賃月3000円に住んでいるがゼネコン職員はホテル住まいである。そこで毎日いわき平の夜の街へ繰り出すクラブ活動は止まらない。
夏場の原発復旧作業は熱中症防止のため昼間2時以降5時までは禁止になった。そこでみんな1時間早めのサマータイムとなった。宿舎では4時に起きて4時半出発、6時半に構内休憩所に着く。作業前ミーティング、防護服に着替え、8時半に現場、9時半に終了。10時前後に休憩所に戻って作業後ミーティング。11時には帰りの帰途につく。昼飯は宿舎だ。
時間をそれ以上早めると朝食抜きになってしまい、逆に熱中症になりやすい。
復旧作業での私病による死者も数件でている。
マスコミの関心が高まれば世論の注目を集める。したがって政府の目も厳しくなる。そうなると電力会社への政府要求も増してくる。それは末端作業員の安全健康のためと言いながら、電力会社の下につく大手元請け企業へのいろんな手笠足枷となって、さらにそれが下請けへと弱いものへしわ寄せが行く。
熱中症予防の最大の効果は睡眠時間と朝の食事である。それは作業員個人管理となる。現場で管理できることは作業時間を小刻みにしてエアコンの効いた車の中に退避する数を多くすることだが、実際にはそんなことしていると当日予定の作業が終わらないので退避回数は少なくなり、現場での監視役がいるわけではないので作業員任せ、つまり現場も個人管理となり、末端にしわ寄せが行くことになる。
管理を細かくすると作業計画書の内容が細かくなるし、書類の数も量も多くなる。予定していない作業はしてはいけない。となるとゼネコンの業務は図書作成だけでも煩雑なものになる。
電力会社「○×の計画書類ですが、ちょっと矛盾しているところがあるので見直しお願いします。」
電力会社から指摘を受けると再提出~打合せとなる。書類などは、説明なしで書面だけで終わらせようとすればどこかに説明不足や表現不足が見つかる。机上で粗さがし探しをやっていても現実の作業は進まない。ゼネコン社員は電力会社を電力さんと敬称付けることが多い。発注元なので普通の現場では、お客様は神様である、復旧作業では、駄々っ子である。復旧は全国から注目されており、政府や規制委員会からの指摘で方針をころころ変えるからである。
元請け「見直しって、作業はもう明日から作業ですよ。」
電力「じゃあ早朝の作業前に再度打合せしましょうか。」
元請け「早朝?・・・ああ、いいですよ、まだその時間酔っぱらってますが」
電力「・・・それでは来なくていいです」電話は切れた。
この工事監督は深夜というか2時過ぎまで飲んでいる。打ち合わせのために酒を断って出勤するという感覚が無い。仕事をするためにはまず酒が必要である。
9時頃からいわき平の歓楽街に繰り出し、深夜12時頃まで飲んで、店を変えて二次会、そして最後に中国飯店でラーメンたべて2時に締める。飲むほどに仕事が捗るらしい。なので早朝はまだアルコールが抜けない。電力の事務所内でアルコールが検出されればルール違反となる。
打ち合わせは無くなったが、こういう場合、免震棟での作業前確認の際に電力から急遽変更指示がでたりする。
もうひとりのゼネコン社員も監督を見習って強者である。彼が提出した資料に訂正箇所があり電力会社から強く批判されたが電力会社社員のその言い方が上から目線だから嫌いだという。
電力会社「じゃあいまからお話ししますか」
ゼネコン社員「いまから?・・・行けませんね。」
電力会社「どうしたんですか、なぜ来られないのですか?」
ゼネコン社員「体調が思わしくないです」
電力会社「体調?」
ゼネコン社員「はい、そうです。」
原発では老齢の作業員の相次ぐ私病突然死があり、その対策として作業員の健康安全優先。ということで、体調管理の徹底を方針にしている。健康管理最優先である。
電力会社「来ることができないくらい悪いですか」
ゼネコン社員「はい、悪いです、ではまた」
彼は受話器を置いてから呟いた。
“あいつと話していると体の具合がわるくなってくるんだよ・・・”と。
【23】緑人間とコンクリート人間と泥んこ人間
原子炉建屋周辺の道路、路盤上の瓦礫撤去~鉄板敷作業は延々と続くように感じた。600トンクレーンなど大型重機が走るたびに分厚い鉄板が歪むのである。そして敷き直しする。
Rw/Bの屋上からは撤去した瓦礫が降りてくる。瓦礫を片付けるたびに粉塵が飛散しないように緑の飛散防止剤を撒いて粉塵を固着する。
緑の飛散防止剤をホッパーという機械をつかって遠隔操作で撒き散らす。オペフロの上は人間が立てないので遠隔操作で撒く。しかし、道路上では人間がバケツで撒いたほうが早い。バケツで撒けば自分もその緑の飛散防止剤を被ることになる。
道路には飛散防止剤を被って白のタイベックスーツが緑色になった緑人間が歩き回る。現場を移動する乗用車も緑。瓦礫が緑。怪しげな世界になっていった。
モルタル散布で地面を固める作業も続いて、そのため白タイベックスーツは灰色になる。上から下まで灰色だ。
土木工事では関東ローム層の赤土を被って全身土色になる。
昼休み前になれば、一斉に現場から帰ってくる。すると汚染検査が間に合わないから免震棟の復路入口は緑人間、灰色人間、土色人間の行列ができた。誰もが一目散に免震棟休憩所に戻ってくる。
サーベイ要員やサーベイエリアにも限度があって汚染検査まで30分かかる。検査棟入り口は検査待ちの行列ができる。屋外では全面マスクは外せない。検査棟建屋に入ってから外す。屋外で全面マスクそのままの緑と灰色と土色の人間が列を進んでゆく。
昼食はやく食べたい、の思いを全面マスクの中で噛み殺してじっと待つのだった。
瓢タンが現場測定から帰ってきて全面マスクを外すと隣にはゼネコンのヤッシーこと林田安全社員がいた。彼は瓢タンと同じ派遣社員である。
瓢タンはタイベックスーツを脱ぎながら、全面マスクを外した隣の男に言った。
瓢タン「なんだヤッシーか。おまえタイベック緑じゃないか。シュレックか、ハルクか。」
ヤッシー「飛散防止剤を重機ホッパーで撒いてるけど、撒ききれないところはバケツで撒くんだよ。手作業だよ。」
瓢タン「重機の遠隔操作じゃないんかい?」
ヤッシー「遠隔操作なんて報道の見出しだけだよ。現場はそんなもんじゃないよ。人間がバケツで散布するんだよ!」
【24】帰省直後のがん致死
タービンとは原子炉で沸かした蒸気により発電する装置であり、原子炉建屋に隣接する。その建屋と原子炉建屋のの下屋と呼ばれる屋上に架台をつくってそれが原子炉建屋を取り囲む際の東側の架台となる。原子炉の燃料をクレーンで釣り上げるためのドームを支える架台である。
タービン建屋は原子炉隣の台地のようなイメージであり、そのため作業員はそこを203高地と呼んでいた。鬼瓦の親方の土方の命名だった。遮蔽スーツを着てもそこにいることができるのは3分だった。そこでウルトラマン作業とも呼んでいた。
203高地にゆくためには単管パイプで組み立てた階段をのぼらなければいけないが、14kgの遮蔽スーツを着て一気に登りきるには40~50過ぎの年代にはきつかった。
北海道からきた50代の作業員が単管梯子の途中まで登って、うづくまった。14kgを背負って階段を登るには体力が不足していた。一度息が切れると回復が難しいみたいで、作業をせずに降りる元気しか残っていないみたいだった。
その後、その作業員は北海道へ帰って、まもなく肺がんで亡くなったが、これは私病といって持病によるものだろう。原発作業に来る前から癌だったと思われる。なぜなら放射線による晩発性の癌はすぐには現れない。
放射線被ばくの影響は確定的、確率的と二分される。確定的なものは直後に症状がでるから確定的と言う。
確率的な影響で比較的短期間で症状が出るのは白血病だ。そのため厚労省も白血病は5mSvという低線量被ばく歴を妥当性の必要条件としている。放射線の影響か、影響なしか、どちらも証明は難しい。証明ができるとしたら、遺伝子解析によってその癌がいつ発生したか突き止められる頃だろう。原発作業の時期に癌がスタートしたと証明できれば因果関係は科学的に証明できる。
白血病以外の症状では癌があるが細胞が癌と言われるまでには相応の年数がかかる。原発にやってきて誰もがAB教育と言う放射線被ばく防護のための新規入所教育を受けるが、そこでは確定的影響にはそれぞれ症状に応じて閾値があるが、確率的影響で例えば晩発生の致死性癌などには閾値が無く被ばく線量0mSvから直線的に放射線影響の確率があると教える、これをLNT仮説という。1Sv5%で比例計算した致死癌確率はそのままでは評価できず、個々の日常の生活リスクと比較して評価することになる。
比較リスクは児童ではほぼ0であり、年齢とともに比較リスクが高まり、生涯では致死癌26%である。特に児童の親は子供のリスクは0を願って、できるかぎり子供をリスクから守っている。
労災では50mSvを超えると晩発性癌の因果について妥当性のひとつの目安としている。50mSv以下であっても因果関係を否定できないならば、疑わしきは排除しない、ことが科学的態度と言える。
放射線作業従事者は5年間100mSv(致死性癌確率0.5%)、70歳での生涯1000mSv(致死性癌確率5%)は、日常の致死性癌確率26%とそれ例外の死亡率、作業場の死亡率確率合計に比べれば許容範囲としている。統計は広島長崎原爆を元に致死癌だけのデータである。それ以外は検証できていない。
た放射線作業従事者ではない18歳未満(一般公衆)の場合は、もともとの死亡確率はほぼ0に近いので、年間1mSvを超えることがないように、放射線施設の事業所境界の線量率を年間1mSvで規制している。事業所境界から離れれば更に低くなる。1mSvの致死癌確率は0.005%で、比較するべき日常の児童の10年後の致死癌確率0.1%に対して10%未満なので許容されると政府は考える。
原発作業にやってきて被ばく基準を守って作業して、すぐ帰って、すぐに癌になって死亡するということは考えにくい。
原発の復旧作業には全国からいろんな派遣会社を経由して、さまざまな日雇い労務者も入ってくる。そういう人たちの中には以前からの日々の自己管理不足もある。
人口動態では日本の年間死亡数は約120万人前後であり100人に1人がなくなっているが、職業上の年間死亡数は平均約1000人に1人という統計がある。
復旧現場で作業するのは平均年齢が60歳前後なので死亡率は更に高いはず。人口4千万人に対して日常で約2.5%の年間死亡率であり、生涯致死癌率26%である。
原発復旧作業では4千人が従事しており60歳以上が500人いるとして2.5%は12.5人だから、年間数人が私病で死亡しても確率的にはおかしくない。
メディアに発表されているのは原発作業中の死者であって地元に帰ってからの統計は調査していないが、放射線労災認定については富岡労基署の記録を調べればわかるように情報公開されている。
【25】若社長の急死
珈琲館でアイスコーヒーを一緒にしたフリーライターから瓢タンに連絡があったのはお10月だった。いわきでは過ごしやすい気候である。
「原発の作業員ルポルタージュの本を読みました。」
労働者の実態に興味があるらしい。原発の復旧作業ではいろんな労働者の実態がよくわかるのではないか、というのが彼女の興味だ。
・・・
作業員を集める具体的な方法はゼネコンの下請け先による。一次下請けのY工業、T工業など鳶職や雑工といった作業者集団がある。そこへ正社員として就職するか二次下請け、三次下請けからの採用となる。一次下請けの正社員では月給制であり、二次、三次となると日当制となる。
T工業とY工業では賃金体系は異なる。ゼネコンからは危険手当が一人当たり最大2万円。構内の勤務エリアはそのエリアの空間線量率によって5千円、1万5千円、2万円と異なる。あるいは当人の被ばく線量によって変える場合もある。
また一方は一日1万円の危険手当がつくが一方は5千円しかつかない。しかし一方は基本賃金が20万円で、一方は30万円。というふうに賃金体系も異なる。
多重下請けになると危険手当1000円、日当1万円とかもある。そういう作業員が、まともな手当をもらっている作業員の話をきくと、その途端に自分が下請け構造の下層にいることを嘆く。いろんな事情があろうが、同じ仕事で賃金がおおきく異なると仕事のやる気がなくなる。
ゼネコン職員は全員危険手当の基準は同等だ。東電は危険手当を総請負金額に上乗せして元請けゼネコンに支払うが、現場作業員への支払いを東電が約束しているわけではない。
労働基準監督署から支払い手当の指導をうけているが、一次下請け、二次下請け、三次下請けは概ね2万円に会社経費を引けば1万円~5千円だろう。
元請けの中にも大手だけでなく、中小企業もある。中小企業の元請けの中には危険手当は支払いませんと言う強者もいる。労基署がその理由を聞くと「お金目当てで仕事をしている作業員なんて集めてもろくなことありません。」と答えた。会社としては個々の危険手当をきちっと2万円東電からもらっている。
実は同じ会社内のいわき事務所内で火力発電現場もあり、そこでは危険手当などない。原発復旧社員だけ2万円付けると、火力現場の社員もみな原発復旧へ行きたくなる。それでは会社の統制がとれない、という理由だった。
ただし中には2万円そのまま手渡す一次下請け企業もある。光電技術はそのひとつだった。
光電技術の二代目若社長は社員の作業現場を確認するために短期間だが1F復旧現場に足を運んでいた。短期間と言うのは年末までのこと。
そして免震棟の休憩所に来て、いつも口癖のように言う。
「うちは危険手当はみんなにそのまま2万円払っているからまったく儲かりません。そもそも一般の現場は請負ですので会社経費も諸経費も資材費もいただいてますが、ここは人件費だけですので、会社経費倒れですよ。ほんとに文字通り復旧作業に協力しているだけ。請負ではなく作業だけだから儲けはないです。本音を言うと撤退したいのです。」
そう言いながら若社長は白いスーツに外車を乗って颯爽としていた。
あとから偶然ネットで知ったが、お別れ会が開かれていたが、その呼びかけ人が有名コーヒーチェーンから参議院になった政治家で、参加者は芸能タレントの神田うのなどがいた。かっこいい若社長だったが社交もかっこよかったようだ。。
だった(過去形)というのは2011年末に東京に帰った途端に急死したのだった。
若くて元気なのに不思議な急死だった。短期間の現場視察なので被ばく線量は数Svくだいだろう。労災申請する基準以下である。
普通40歳前後の日常の年間死亡率は0.1%に近い。だから同級生には見つからなくても同窓生など調べてみれば意外な人が若くして急死していることがある。
その後も不思議な死は瓢タンの周りで起こって、鹿山建設の中で鉄腕レースを趣味にしている中年ランナーが急死した。え?あの元気な人が?と思うような人が急死することが世の中には意外と身の回りにある。
【26】遮蔽スーツと被ばく隠し
3号使用済み燃料を取り出すためには原子炉建屋を覆うドームが必要で、そのドームを支えるための建屋を覆う鉄骨カバーが必要となる。夏を過ぎて原子炉建屋カバーを設置するための地上のエリア平均線量は1mSvに低下したがさらに路盤整備で0.5mSvを目標にしている。
一時間で1mSv被ばくすると作業者がどんどん規定限度に達して現場から去らねばならない。そこで放射線遮蔽スーツを着用して最低でも40%は放射線カットしたい。その場合被ばくは1時間0.6mSvである。
環境を一時間0.5mSvまで低下させれば、作業者の被ばくは一時間0.3mSvになる。
30分で0.15mSv、ひと月10日で1.5mSv、年間18mSv、これが一年を通して作業続けるための上限である。日当で生活する作業員は0.1mSv/h以上の高線量エリアの作業やそれ以下の低線量エリアの作業を入れ替えながら毎日計算しながら一年を凌いで次の一年に食いつないでいかなければいけない。
遮蔽スーツには2つの型式があり、ひとつはワンピースタイプ。もうひとつは頸部スカーフとベストと腰スカートのセパレートタイプだった。しかし使い始めが夏だったのでセパレートタイプのスカート部分は外してベスト(胸腹のチョッキ部分)だけ着用するケースが多かった。
放射線管理上では被ばく線量を正しく反映させなければいけないから、セパレートな遮蔽スーツは作業員個々に付けたり外したりできないように縫い付けることにした。革製品用の手縫い針とストレッチャーを使って手縫いした。そしてベストとスカートは縫製され一体型となった。
首は頸椎の被ばく保護で大事なところだとかいうことで頸部スカーフとベストの組み合わせで作業する者もあった。頸椎には骨髄があって造血機能があるから首を守らないといけない、と鳶職の親方の鬼瓦のような土方が瓢タンに言った。
「俺は調べて知ってるんだ。頸椎を守る鉛入りスカーフがないと骨髄の被ばくをして、白血病になるんだ。」
203高地の名付け親方が物知り顔に言った。
しかし遮へいスーツを使用した場合の被ばく計算には頸椎の要素はなかった。むしろ造血機能は骨盤のほうが多い。
スカーフもスカートもあった方がいい。しかし不均等被ばくという計算をする際には首の遮へいは計算ファクターには主として入らない。
そこで瓢タンは言った。
「首も鉛で遮蔽したほうがいいですが、それより骨盤を守るスカートだけは必須です」
どっちも着けるとなると作業員は面倒くさがった。結局どっちか選ぶなら骨盤を守るスカートだということを理解してもらった。
白血病は罹患まで足の速い症状だが、最初の年の夏にはそこまでの事象発生はなかった。厚労省では最低5mSv以上の被ばくと1年以上の経過で労災の条件に入る。そして白血病にも種類があり、骨髄性白血病又はリンパ性白血病であること。となっている。
身体の被ばくを防ぐために遮へいスーツを着用するが、その場合被ばく線量を正しく計算してシステムに反映する必要がある。
単にAPD数値だけ下げたいなら、5センチ四方の鉛板をAPDに張り付ければよい。
しかしその方法は放射線被ばくとそれによる身体影響の統計が合わなくなるという点で違法であって、実際に100mSv被ばくしているのに50mSVと記録されるようになってしまうと疫学統計に生かされないばかりではなく、法定限度の5年で100mSvを守ることもできない。
瓢タンとしては法令に準拠して作業者本人の実際の被ばく結果が正しくになるように放管として指導するばかりだ。
APDを5センチ四方の鉛板で覆うという安易な遮へい方法は誰でも考えるところだが、鹿山建設ではない他の元請け作業では、実際にそれをやった作業員がいて、違法行為という大きな事件となるのだった。
さらにその後、APDをどこかに隠して置くという離れ業をやってのける作業者がいることも発覚したのだった。
それらを監視するために出口管理の放管が目視で検査できるようにタイベックスーツの胸部分を透明ビニール窓を付けるように改善されていったのだった。
【27】靴
作業員のクレームは自分の足の大きさに合った靴がないことだが、電力会社は靴は揃ってます、と回答する。靴を用意する電力会社も大変で、数、大きさ、そして靴の形状種類。形状種類は短靴、長靴、中靴の3種類あるがいずれも形式はレインシューズで、つま先が安全用鋼板入りのどた靴である。作業者の不満は数ではなく、自分に合った靴があるかどうかだ。ぶかぶかの靴では復旧現場のようなでこぼこの路面はつまずいて転んで怪我をしやすい。
つま先に安全鋼板を仕込んであり、24cm25cm26cm27cm28cm29cm~とあるが紐もマジックベルトもついていない、見かけはコックシューズとか防止レインシューズとかで、安全ドタ靴だった。 24cm25cm26cmは使用中で27cm28cm29cmが靴箱に余っている状態だとすると、電力会社としては、余っている靴があるから、靴は足りています、という考え方をする。したがって作業員は自分に合わない27cm28cm29cmから選ぶしかない。自分に合わないのでつまづいたりすることが多くなる。
元請け企業ごとに一般とび職用の靴を用意することもできるが、毎日汚染検査をして管理しなくてはいけない。だからなかなか対応できる企業はいない。東電支給の靴は電力会社が汚染検査管理してくれる。だから仕方なくドタ靴を使う。長くつは比較的脚になじむが夏は暑くて履いていられない。冬は逆に長くつでなければ足指が凍るほど冷たい。
自分に合わない靴だけが残っていてそれを使わざるを得ない現場の実情について、電力会社は作業の目的で現場に出たことないからその辺が良くわからない。
転んでねん挫したとか怪我したとかの軽傷事故が毎月のように発生した。「自分の身は自分で守る。これを徹底してください」 電力会社の安全指針は変わらない。 靴底に汚染が残ってそこから放射能が染み込んで軍足に滲みて、足裏表皮が汚染する場合もある。これをもらい汚染という。電力会社の汚染管理と言っても毎日やるわけではないからだ。
足裏の汚染は作業後に身体サーベイで判明する。処置は除染、つまり洗浄すればよい。問題点は作業員が作業を終えてあとは帰るばかりのときに、汚染が見つかると30分も手間をとってしまう。その結果原発からJヴィレッジ行の帰りの目的時間のバスに乗り遅れる。日常の行動サイクルが変則になるということで作業者もできるだけ汚染はしたくない。
本来は靴の中が汚染しているかどうか毎日測定検査しなければいけないが、電力会社でも、さすがにそこまでのことは対応できないので一週間に一度くらいで精一杯だ。 靴に針のように穴が開いているかどうかも気になるが、靴を水中に沈めて発泡検査も行っている。そのような穴から汚染が染み込むのならその時点でその靴を廃棄する。 それ以前に、靴の中が汚染しているかどうか、ガンマ線では測れない。外のガンマ線が中まで通過する。ベータ線は通過しないからベータ線を測れば良いが靴の中に入れるセンサーなどは開発していない。
そこでスミヤ測定法といって靴の中を濾紙で拭き取ってみてから濾紙に付いた汚染(ベータ線)を測る方法を採用するがそれだけ余計な手間がかかる。
「自分に合うサイズの靴がないなら、電力の係員にリクエストして、出してくれるまで待てばいい」
瓢タンは作業員にそう教える。しかし作業員は暇人ではない。電力の係員が現場に居ないことの方が多い。だんだんリクエストなど面倒になってくる。そして自分に合わないぶかぶか靴で作業して、鉄板の段差に躓いて転ぶ。そして怪我の統計ではつまずき転倒がダントツで多いが、そんなことが実情だった。
【28】警報無視という違反
作業員はタービン建屋下屋を203高地とか、そこの作業をウルトラマン作業とか言っていたが、原子炉建屋の剝き出しのオペフロ上の放射線量はもっと凄い。測定値2.0Sv/hなどの測定値が出たりするとタービン建屋下屋屋上の100mSv/hの数値が可愛く見えてきた。
昨日やってきてまだ二日目の鳶職が3人、原子炉建屋の南側仮設梯子を登って最上段のオペフロ近くの仮設単管パイプの金具を締めに行った。作業終えてから、まだひとつ締めていない箇所に気がついた。そのときAPD警報がキュイーンとプレアラームが鳴動した。ルールでは被ばくを避けるために直ちに作業を終えてその場を仕舞って免震棟休憩所に戻らなければいけない。しかし本人としては、あと一本締めるのは1分もかからないということで引き返して作業を終えた。すると今度はビービービーという最大警報が連続鳴動した。その音は免震等で遠隔監視している監視員にも聞こえた。ちょうど監視員はとび職の親方で鬼瓦の赤ら顔の土方だった。
「おい、おまえ最大警報なってるぞ。すぐに戻ってこい」遠隔監視のマイクから叫んだ。
「は~い、ちょっと工具忘れたんで取ってきま~す」
「バカ、戻れといってるんだよ」
「でも工具が」
「そんなのどうでもいいんだよ!バカ」
そういっているうちに5分もたってしまった。原発復旧にきてまだ二日目であり、本人も焦っており、右往左往して手間取った。
戻ってきた時には作業員のAPDは2.5mSvを示していた。怪我をしたわけではないが、2.0mSVを2割以上も超えると警報無視、つまり故意のルール無視とみなされ、事故事象扱いとなり顛末書対策報告書を電力会社に対して書かなければいけない。
ほんとうに故意の警報無視であれば本人は田舎に帰って一般の工事作業に従事するところだが、今回は遠隔監視でも指導していたし、本人の故意ではなく、右往左往するのは初心者の常、ということで現場に残ることになった。
作業者を帰すことは元請企業の命令ひとつでできるが、その際に十分な納得を得られないといけない。もし本人が納得しない場合には地元に帰ってからメディアに原発現場のことをチクル可能性もないわけではない。
電力会社とそこに従事する作業者全体、元請下請け共に原発内のことは機密情報として公言してはいけない。不本意に解雇された作業者の場合はそんな約束事を無視することもありえるのだった。だから福島原発の復旧現場解雇でも次の現場をあてがうなどして作業員の面倒を見るようにするのが常套手段だ。
【29】お漏らし
3号機現場周りにはトイレはない。というか1Fの構内作業現場にはトイレはまだない。トイレは免震棟や厚生棟と呼ばれる休憩所建物の中にある。
放射性物質の飛び散った1F現場ではズボンを脱ぐことはできない。白いカバーオールと綿手、ゴム手二重、軍足靴下二重、それに防毒用の全面マスク、足、手とマスクとカバーオールは空気が入らないようにガムテープで密封する。そんな状態では野グソもおしっこもできやしない。
Jヴィレッジで着替えをして構外の仮設プレハブ休憩所で一旦休憩し、そこを出発点として再度免震棟で着替えをして現場へ行く段取りの作業で、瓢タンの面の前で起こった。
夏のある暑い日、トイレがすぐ近くにないのでおしっこの我慢も限界というものがある。作業員の大黒は構外休憩所に戻ってきて、タイベックスーツを脱いだとたんにその顔の表情が恍惚状態に変わった。床をみたらおしっこが流れていた。
1Fの現場に出るとトイレはない。トイレするにはまず車で免震棟に戻り白カバーオールと全面マスクと綿手、ゴム手、軍足、要はパンツ一枚になって、汚染検査を通ってから休憩室に入り、休憩室のトイレを使わなければいけない。
ところが夏になれば熱中症予防のために沢山の水分を取ることを義務つけられているので、現場でおしっこをしたくなる。そこで免震棟や所定休憩所までたどり着いてからおもらしする者も出てくる。汚染検査受ける手前でタイベックスーツを脱ぐがその時点でタイムアウトしたのだった。
事務所としては、あらかじめ危険予知して、介護用おむつを、依頼した。しかしJV事務所では最初の夏に在庫をたくさん抱えた。
購入したがみんな見てくれや恰好を気にしておむつを使わないので在庫が事務所のスペースを圧迫してしまい、在庫処分のために瓢タンも祖母に配ったりして在庫減らしを手伝った。
その後、山の中の重機廃棄置き場の現場で放射線管理していると、別の作業員が言った。
「瓢タンさん、ちょっと向こう見ててください」
白いタイベックスーツはチャックのつなぎだからやろうと思えばオシッコは思えば可能だ。しかし汚染しないように、ゴム手袋を新品に代えてから行う。大事なところが汚染したら、報道機関に発表されて、恥ずかしい思いをする。
【30】首根っこ掴まれるゼネコン社員
太平洋に面した原発は海の方から4M(メートル)盤、10M盤、高台(33M)と三段階の敷地がある。Mは海水面からの高さで、4M盤には非常用電源のオイル用タンクやタービン建屋からの復水タンクなどが設置してある。10M盤には原子炉建屋。高台には免震棟など事務所設備。
10M盤といわれる地上道路に3号機入口の大物搬入口がある。扉は爆風で吹き飛ばされている。海から風が吹くと大物搬入口前の線量率は急上昇する。まだヨウ素が存在していたのかセシウム粉塵の仕業か。
そんな頃3号JVの大手ゼネコン職員の中には人材会社雇用でJVの名刺を持たせた派遣社員がいる。JV正社員職員の代わりに被ばくをするようなものだった。作業員の作業監視のために立っているだけで一日2mSV被ばくするのだ。
派遣JV職員の大黒は監視のため立ち仕事(免震等との連絡係)を端折って、いつも待避所に避難していた。そうしないと一ヶ月に20mSV二ヶ月に40mSvの被ばくしてしまう。そうなると2ヶ月で現場を去らなければいけないので、毎日の1万円の手当てがそれで終わってしまう。本来は2万円だが半分は派遣元の経費だ。
残業100時間で20万円、手当20日間で20万円。計40万円。それに毎月の月給が30万円。併せて70万円。こんな現場は他にはない。なんとかしかしてもっと長期間継続したい。そのためには被ばくを低減すればいい。現場の待避所と言う線量率の低いところに閉じこもっていればいい。
それを下請けの作業員にみつかった。作業員は休憩所でいきなり切れて、JV派遣員の首を捕まえて言った。
「こら、なんでいつも逃げるんだ。ふざけんなよ。俺たちが現場で被ばくしてるのにおまえは逃げてばっかりじゃねえか!」
作業員も被ばくを避けたい。みんなそれが本心だ。そしてみんなそれぞれ自分の工夫をしてなんとか被ばく線量を下げている。
線量率の高いほうへ向かず反対側へ向く、下着ポケットのAPDを手で覆う。線量率の高い場所から離れる。APDの被ばく線量数値を下げたい者は、みんなこまめに工夫をして作業している。
0
あなたにおすすめの小説

島猫たちのエピソード2025
BIRD
エッセイ・ノンフィクション
「Cat nursery Larimar 」は、ひとりでは生きられない仔猫を預かり、保護者&お世話ボランティア達が協力して育てて里親の元へ送り出す「仔猫の保育所」です。
石垣島は野良猫がとても多い島。
2021年2月22日に設立した保護団体【Cat nursery Larimar(通称ラリマー)】は、自宅では出来ない保護活動を、施設にスペースを借りて頑張るボランティアの集まりです。
「保護して下さい」と言うだけなら、誰にでも出来ます。
でもそれは丸投げで、猫のために何かした内には入りません。
もっと踏み込んで、その猫の医療費やゴハン代などを負担出来る人、譲渡会を手伝える人からの依頼のみ受け付けています。
本作は、ラリマーの保護活動や、石垣島の猫ボランティアについて書いた作品です。
スコア収益は、保護猫たちのゴハンやオヤツの購入に使っています。
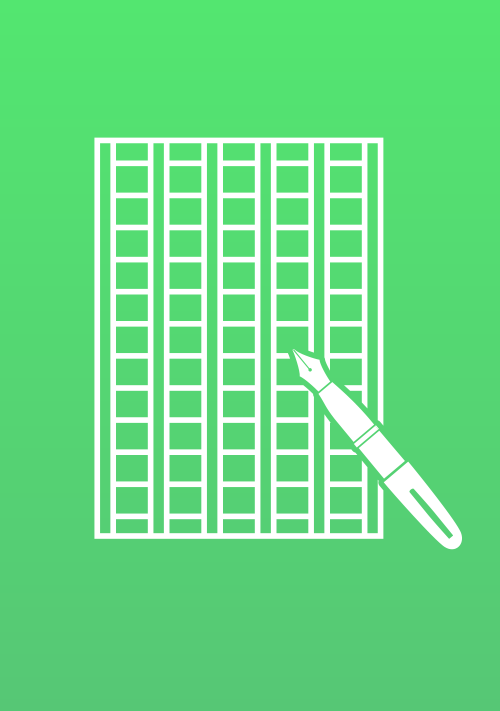
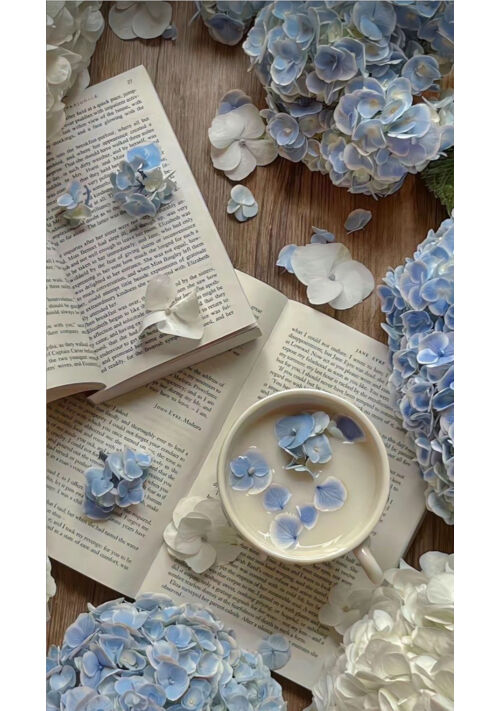
月弥総合病院
御月様(旧名 僕君☽☽︎)
キャラ文芸
月弥総合病院。極度の病院嫌いや完治が難しい疾患、診察、検査などの医療行為を拒否したり中々治療が進められない子を治療していく。
また、ここは凄腕の医師達が集まる病院。特にその中の計5人が圧倒的に遥か上回る実力を持ち、「白鳥」と呼ばれている。
(小児科のストーリー)医療に全然詳しく無いのでそれっぽく書いてます...!!
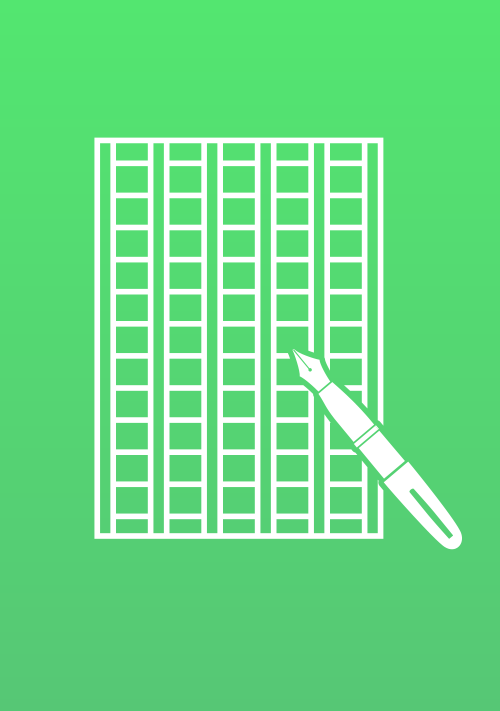

同じアパートに住む年上未亡人美女は甘すぎる。
ピコサイクス
青春
大学生の翔太は、一人暮らしを始めたばかり。
真下の階に住むのは、落ち着いた色気と優しさを併せ持つ大人の女性・水無瀬紗夜。
引っ越しの挨拶で出会った瞬間、翔太は心を奪われてしまう。
偶然にもアルバイト先のスーパーで再会した彼女は、翔太をすぐに採用し、温かく仕事を教えてくれる存在だった。
ある日の仕事帰り、ふたりで過ごす時間が増えていき――そして気づけば紗夜の部屋でご飯をご馳走になるほど親密に。
優しくて穏やかで――その色気に触れるたび、翔太の心は揺れていく。
大人の女性と大学生、甘くちょっぴり刺激的な同居生活(?)がはじまる。
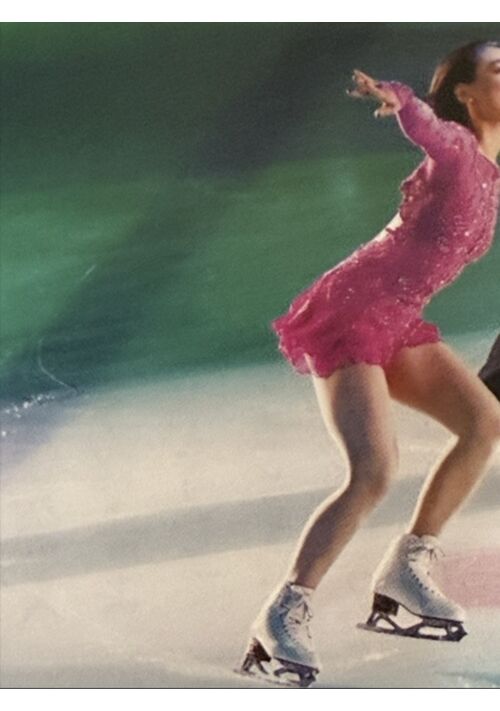
あるフィギュアスケーターの性事情
蔵屋
恋愛
この小説はフィクションです。
しかし、そのようなことが現実にあったかもしれません。
何故ならどんな人間も、悪魔や邪神や悪神に憑依された偽善者なのですから。
この物語は浅岡結衣(16才)とそのコーチ(25才)の恋の物語。
そのコーチの名前は高木文哉(25才)という。
この物語はフィクションです。
実在の人物、団体等とは、一切関係がありません。

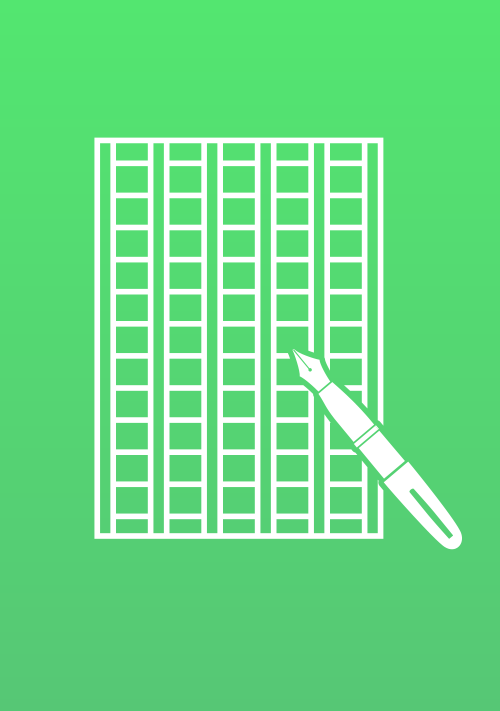
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















