4 / 4
1F原発復旧3号機カバー酔夢譚 エピローグ
しおりを挟む
1F原発復旧酔夢譚
【エピローグ】(1)なんちゃって重機
3号原子炉建屋オペフロの竜骨のような折れ曲がった鉄骨残骸を遠隔操作クレーンでひとつづつ切り取っては地上に降ろしていた。
ある朝、現場リーダ、下請け作業員が朝礼のために免震棟休憩所の打ち合わせ室に集まったとき、いきなり青成さんが、監督に変わって円卓の真ん中でしゃべりだした。
「きょうは作業中止です。大型クレーンのジブが折れました。今後の方策を決めてから改めて支持します。」
そう言って、みんなを連れて遠隔操作の画面を確認しに行った。すると確かに、まだ作業する以前に、あらかじめ倒してくの字になっているクレーンマストの真ん中が折れつつあった。
みんなで見ていると更に折れ曲がっていって、亀裂が見えた。
「きょう鉄骨吊り上げる前で、まだなにもしないうちに折れて良かったなあ。」
「もし瓦礫残骸を吊ってお降ろすときに折れたら、あと始末も大変だぞ、大事故になったかもしれない」
取り合えず、電力会社は労基署に報告し、突然の大型クレーン事故ということで厚労省の判断を仰ぐことになった。
作業員は地上の整備作業だけして昼前に原発を離れて宿舎に帰った。
すると昼過ぎに、クレーンのジブをそのままにしてはいけないから片付けろと電力会社からJVに指示があった。
作業にはルールがある。8時間に追加できる残業は2時間だ。そして被ばく線量の上限は2mSvである。
昼間で作業していたから、もう一度現場に集めても許される作業時間は4時間くらいしかない。
被ばく線量は0.5mSv被ばくしているから残り1.5mSvしかない。
それらの条件に見合う作業員を集めて現場に夕方に集合したのは6時過ぎだった。
「いまからやって時間オーバーしたらどうなるんですか」
職長はJV監督に詰め寄った。
厚労省指示だから問題にはならない、というのが電力会社の答えだった。
実は大型クレーンは電力会社の持ち物で、JVはそれを使用している。折れ曲がったクレーンが報道などで移されると、電力会社の管理はどうなっているんだと言って報道陣が騒ぎだす。それで夕方暗いうちから片づけ始めて朝までにきれいに片づけようということだった。
大型クレーンのマストが自然に切断するなんて前代未聞だ。吊り上げ中だったら大事故になっている。マストのせん断破壊や脆弱性をメンテナンスで見つけることはできないのか?
ハインリッヒの法則では隠れた29の軽微な不安全があり、300のヒヤリハットが隠されている。
【エピローグ】(2)ホワイトアウトなんちゃって汚染
瓢タンが防護服と全面マスクを装備して3号原子炉建屋前の道路で放射線測定をしていると、突然ゴ~ンという鐘の響きに似た音とともに目の前が真っ白になった。ホワイトアウトと同様前方の視界がまったく効かない。
しかしすぐにまたいつもの世界が広がった。
前方を見ると大型クレーンで原子炉オペフロから破壊された燃料取り出しクレーン鉄骨を吊り降ろしてきたところである。
その鉄骨には粉塵が夥しく積もっていた。遠隔操作でも鉄骨に粉塵が積もっていることがはっきりわかった。
それを作業員が現場に行って放棄で履いて除染するのは内部被ばくが避けられないだろうから放射線管理違反になる。現場の遠隔重機のユンボで鉄骨を叩いたら粉塵が落下するのではないか?そのあとに作業員がマニュアルで放棄で掃いたらいいのではないか、あるいはそのまま高線量瓦礫置き場に捨てておこうというのが協議した結果である。
現場重機でガツーンと一発叩いたら、辺り一面がホワイトアウトで真っ白になった。
現場は10M盤と呼ばれ海抜約10mのエリアだ。そこから大量の放射性粉塵が飛散した。飛散したダストは距離の拡散で空気中で見えなくなったが、まだらプルームとなって高台と呼ばれる30Mの高さへ移動した。
プルームはまだらに漂いながら移動する。
高台には免震棟休憩所がある。ちょうど鹿山建設の社員3人が休憩を終えて出口で帰りの構内シャトルバスを待っていた所だった。
シャトルバスに乗って、入退管理棟へ行き、そこで最終の管理区域出口の放射線検査をする。
すると3人とも汚染が発覚した。
「え?だって作業終えて免震棟検査所で汚染ない事を確認して、バスに乗っただけだよ」
3人は異口同音にいきさつを説明した。
「じゃ、バスの中で汚染したのか?」
実は鹿山建設の他に同じ場所でバスを待っていた電力会社の社員も2人汚染した。
「う~~ん、これはちょっと困った」検査員はそう言った。
「とりあえず、原因はこれから究明するとして、汚染しているのは衣服ですからユニホームを脱いで、電力支給のジャージに着替えて帰ってください」
原因はバスでもない。なぜなら他の乗客は汚染していない。
すると鹿山建設3人と電力2人が立っていた場所に問題があるのではないか。
そう言えば、夏の真っ盛りで、熱中症予防のために山から水を引いてミストを噴霧していた。
ちょうど固まって立っていた5人が、ミストの放射能によって汚染したのか?いやミストは山から汚染していないことを確認して給水している。
じゃ、配管に汚染が溜まってそれがたまたま5人に降りかかったか?
5人は衣服汚染であり、衣服を交換したことで除染ができたことになり、大きな問題にはならなかった。
なぜ?は最後まで疑問のままだったがミスト噴霧が中止になったことで報道陣も幕引きになった。
しかし瓢タンは知っていた、あの高線量粉塵のホワイトアウトを体験したのは瓢タンだけだった。そのプルームが風に飛ばされて、まだらに移動して、5人に降りかかったのだ。と。ゴーンの瞬間に飛散して移動したと思われる時間と5人がバス待ちで立っていた時間が一致していた。
1F原発復旧酔夢譚【エピローグ】(3)放射線
原発事故から10年経って放射線被ばくの労災認定は白血病や甲状腺癌など10人になり、係争中が9件ある。そのうち一人は肺がんで死亡した。
放射線労災申請の認定は科学的証明によるものではない。被ばく線量基準と個々人の日常のリスクとの比較判断に依る。
逆に因果関係として放射線と無関係であることの科学的証明もない。
労災以外でも瓢タンの事務所では同じ放射線管理の同僚が10年後に癌を発症してその後死亡したが労災申請はしていない。
現場のエレベータ点検保守会社では入れ替わり3人が作業にやってきたが、その3人ともが癌を発症したがこれも労災申請はしていない。
東日本大震災から10年。震災による死者は二万人を超えたが、原発事故に依る避難者のうち震災後の原発避難関連死者数が止まらず2000人を超えた。
福島県児童甲状腺癌の罹患率は他県と変わらないそうだが、その手術数は異常な数に達して、当時は児童だったが、10年を経て多数の若者が手術したことによる不利益を被っている。原発事故がなければこのようなこともなかったことは万人が認める事実であろう。逆に原発事故が災害による事故であるなら災害により不利益を被った被害者はまず救出や支援を受けなければいけないが、実際には直接原因が放射線なのか、検査方法にあるのか診断にあるのか、専門家たちの机上の議論が終わらない。
今回の問題として甲状腺内部被ばくを実測しておらず、わからないという根本問題がある。従って原発稼働の必須条件として、地元自治体は避難者全員がWBCでセシウムとヨウ素の内部被ばく測定ができる設備を準備することが必要である。
ALPS処理水の放流は当初は費用比較でに現実的な予算として選択された方法だが、中国の反対に依る水産禁輸により、実害予算は予想をはるかに超えてしまった。世界で反対している国は中国であり、中国に同調する共産圏、イスラムや発展途上国である。
中国はすでに大気放出は賛成しており、今後の実害を計算するなら再度処理水解決の選択肢から大気放流やその他の選択肢を見直してみることも可能だろう。
それよりもまず大元のデブリ汚染水を止めることが優先される。それとも永遠に処理水放流を続けるのだろうか。
水素爆発直後にもっとも危険だった原子炉建屋の使用済み燃料はオペフロの貯蔵プールが破壊されなかったことは幸運だった。そもそも当時ヘリコプターで散水したときに世界からは使用済み燃料が原子炉の上にあること自体がクレージーと非難された。
10年経て核分裂崩壊熱は空冷でも可能なくらいに冷えたと思われるが、莫大な核分裂放射性物質を燃料棒に貯めているのでいち早く地上の共有プールに保管しなければいけない。
3号は鹿山建設JVによって7年余りに渡る地道な作業により使用済み燃料取り出しのドーム建設が完成して、その後メーカーT社により使用済み燃料は地上に移されたが、1号、2号はまだその途上である。
過酷事故を想定せずに使用済み燃料を原子炉上に保管すると言う当時の安易な設計構造が現実に事故が起こってみると最も困難な事態に直面した。
避難区域については帰還困難を解除されたが、野や山は除染しきれていない。大人は帰還するが子供の帰還率は低い。広島長崎の原爆では飛散した放射能の量は少なかったので10年で市街の復興されたが、原発事故では街の復興はまだまだ先の話である。
事故後すぐに汚染土壌を避難区域の中間貯蔵に移したが、その際に期間を定めて、時期が来れば他県に移すことになった。しかし他県での受け入れは当該地域の市民に反対されている。汚染除去された除去土壌の基準値を新たに定めて、基準以下だから他県に移すことが法令上可能になったが、市民の安心の同意は得られていない。
放射線、放射能がなければ原発復旧は10年で終わっている。終わりが見えないのはひとえに放射線、放射能が原因であり、現場での扱いの困難さが原発事故復旧の諸問題の根源とも言える。
その現場での放射線、放射能管理は学者の机上理論では解決ができない。あくまで現場作業管理の問題である。
【エピローグ】(1)なんちゃって重機
3号原子炉建屋オペフロの竜骨のような折れ曲がった鉄骨残骸を遠隔操作クレーンでひとつづつ切り取っては地上に降ろしていた。
ある朝、現場リーダ、下請け作業員が朝礼のために免震棟休憩所の打ち合わせ室に集まったとき、いきなり青成さんが、監督に変わって円卓の真ん中でしゃべりだした。
「きょうは作業中止です。大型クレーンのジブが折れました。今後の方策を決めてから改めて支持します。」
そう言って、みんなを連れて遠隔操作の画面を確認しに行った。すると確かに、まだ作業する以前に、あらかじめ倒してくの字になっているクレーンマストの真ん中が折れつつあった。
みんなで見ていると更に折れ曲がっていって、亀裂が見えた。
「きょう鉄骨吊り上げる前で、まだなにもしないうちに折れて良かったなあ。」
「もし瓦礫残骸を吊ってお降ろすときに折れたら、あと始末も大変だぞ、大事故になったかもしれない」
取り合えず、電力会社は労基署に報告し、突然の大型クレーン事故ということで厚労省の判断を仰ぐことになった。
作業員は地上の整備作業だけして昼前に原発を離れて宿舎に帰った。
すると昼過ぎに、クレーンのジブをそのままにしてはいけないから片付けろと電力会社からJVに指示があった。
作業にはルールがある。8時間に追加できる残業は2時間だ。そして被ばく線量の上限は2mSvである。
昼間で作業していたから、もう一度現場に集めても許される作業時間は4時間くらいしかない。
被ばく線量は0.5mSv被ばくしているから残り1.5mSvしかない。
それらの条件に見合う作業員を集めて現場に夕方に集合したのは6時過ぎだった。
「いまからやって時間オーバーしたらどうなるんですか」
職長はJV監督に詰め寄った。
厚労省指示だから問題にはならない、というのが電力会社の答えだった。
実は大型クレーンは電力会社の持ち物で、JVはそれを使用している。折れ曲がったクレーンが報道などで移されると、電力会社の管理はどうなっているんだと言って報道陣が騒ぎだす。それで夕方暗いうちから片づけ始めて朝までにきれいに片づけようということだった。
大型クレーンのマストが自然に切断するなんて前代未聞だ。吊り上げ中だったら大事故になっている。マストのせん断破壊や脆弱性をメンテナンスで見つけることはできないのか?
ハインリッヒの法則では隠れた29の軽微な不安全があり、300のヒヤリハットが隠されている。
【エピローグ】(2)ホワイトアウトなんちゃって汚染
瓢タンが防護服と全面マスクを装備して3号原子炉建屋前の道路で放射線測定をしていると、突然ゴ~ンという鐘の響きに似た音とともに目の前が真っ白になった。ホワイトアウトと同様前方の視界がまったく効かない。
しかしすぐにまたいつもの世界が広がった。
前方を見ると大型クレーンで原子炉オペフロから破壊された燃料取り出しクレーン鉄骨を吊り降ろしてきたところである。
その鉄骨には粉塵が夥しく積もっていた。遠隔操作でも鉄骨に粉塵が積もっていることがはっきりわかった。
それを作業員が現場に行って放棄で履いて除染するのは内部被ばくが避けられないだろうから放射線管理違反になる。現場の遠隔重機のユンボで鉄骨を叩いたら粉塵が落下するのではないか?そのあとに作業員がマニュアルで放棄で掃いたらいいのではないか、あるいはそのまま高線量瓦礫置き場に捨てておこうというのが協議した結果である。
現場重機でガツーンと一発叩いたら、辺り一面がホワイトアウトで真っ白になった。
現場は10M盤と呼ばれ海抜約10mのエリアだ。そこから大量の放射性粉塵が飛散した。飛散したダストは距離の拡散で空気中で見えなくなったが、まだらプルームとなって高台と呼ばれる30Mの高さへ移動した。
プルームはまだらに漂いながら移動する。
高台には免震棟休憩所がある。ちょうど鹿山建設の社員3人が休憩を終えて出口で帰りの構内シャトルバスを待っていた所だった。
シャトルバスに乗って、入退管理棟へ行き、そこで最終の管理区域出口の放射線検査をする。
すると3人とも汚染が発覚した。
「え?だって作業終えて免震棟検査所で汚染ない事を確認して、バスに乗っただけだよ」
3人は異口同音にいきさつを説明した。
「じゃ、バスの中で汚染したのか?」
実は鹿山建設の他に同じ場所でバスを待っていた電力会社の社員も2人汚染した。
「う~~ん、これはちょっと困った」検査員はそう言った。
「とりあえず、原因はこれから究明するとして、汚染しているのは衣服ですからユニホームを脱いで、電力支給のジャージに着替えて帰ってください」
原因はバスでもない。なぜなら他の乗客は汚染していない。
すると鹿山建設3人と電力2人が立っていた場所に問題があるのではないか。
そう言えば、夏の真っ盛りで、熱中症予防のために山から水を引いてミストを噴霧していた。
ちょうど固まって立っていた5人が、ミストの放射能によって汚染したのか?いやミストは山から汚染していないことを確認して給水している。
じゃ、配管に汚染が溜まってそれがたまたま5人に降りかかったか?
5人は衣服汚染であり、衣服を交換したことで除染ができたことになり、大きな問題にはならなかった。
なぜ?は最後まで疑問のままだったがミスト噴霧が中止になったことで報道陣も幕引きになった。
しかし瓢タンは知っていた、あの高線量粉塵のホワイトアウトを体験したのは瓢タンだけだった。そのプルームが風に飛ばされて、まだらに移動して、5人に降りかかったのだ。と。ゴーンの瞬間に飛散して移動したと思われる時間と5人がバス待ちで立っていた時間が一致していた。
1F原発復旧酔夢譚【エピローグ】(3)放射線
原発事故から10年経って放射線被ばくの労災認定は白血病や甲状腺癌など10人になり、係争中が9件ある。そのうち一人は肺がんで死亡した。
放射線労災申請の認定は科学的証明によるものではない。被ばく線量基準と個々人の日常のリスクとの比較判断に依る。
逆に因果関係として放射線と無関係であることの科学的証明もない。
労災以外でも瓢タンの事務所では同じ放射線管理の同僚が10年後に癌を発症してその後死亡したが労災申請はしていない。
現場のエレベータ点検保守会社では入れ替わり3人が作業にやってきたが、その3人ともが癌を発症したがこれも労災申請はしていない。
東日本大震災から10年。震災による死者は二万人を超えたが、原発事故に依る避難者のうち震災後の原発避難関連死者数が止まらず2000人を超えた。
福島県児童甲状腺癌の罹患率は他県と変わらないそうだが、その手術数は異常な数に達して、当時は児童だったが、10年を経て多数の若者が手術したことによる不利益を被っている。原発事故がなければこのようなこともなかったことは万人が認める事実であろう。逆に原発事故が災害による事故であるなら災害により不利益を被った被害者はまず救出や支援を受けなければいけないが、実際には直接原因が放射線なのか、検査方法にあるのか診断にあるのか、専門家たちの机上の議論が終わらない。
今回の問題として甲状腺内部被ばくを実測しておらず、わからないという根本問題がある。従って原発稼働の必須条件として、地元自治体は避難者全員がWBCでセシウムとヨウ素の内部被ばく測定ができる設備を準備することが必要である。
ALPS処理水の放流は当初は費用比較でに現実的な予算として選択された方法だが、中国の反対に依る水産禁輸により、実害予算は予想をはるかに超えてしまった。世界で反対している国は中国であり、中国に同調する共産圏、イスラムや発展途上国である。
中国はすでに大気放出は賛成しており、今後の実害を計算するなら再度処理水解決の選択肢から大気放流やその他の選択肢を見直してみることも可能だろう。
それよりもまず大元のデブリ汚染水を止めることが優先される。それとも永遠に処理水放流を続けるのだろうか。
水素爆発直後にもっとも危険だった原子炉建屋の使用済み燃料はオペフロの貯蔵プールが破壊されなかったことは幸運だった。そもそも当時ヘリコプターで散水したときに世界からは使用済み燃料が原子炉の上にあること自体がクレージーと非難された。
10年経て核分裂崩壊熱は空冷でも可能なくらいに冷えたと思われるが、莫大な核分裂放射性物質を燃料棒に貯めているのでいち早く地上の共有プールに保管しなければいけない。
3号は鹿山建設JVによって7年余りに渡る地道な作業により使用済み燃料取り出しのドーム建設が完成して、その後メーカーT社により使用済み燃料は地上に移されたが、1号、2号はまだその途上である。
過酷事故を想定せずに使用済み燃料を原子炉上に保管すると言う当時の安易な設計構造が現実に事故が起こってみると最も困難な事態に直面した。
避難区域については帰還困難を解除されたが、野や山は除染しきれていない。大人は帰還するが子供の帰還率は低い。広島長崎の原爆では飛散した放射能の量は少なかったので10年で市街の復興されたが、原発事故では街の復興はまだまだ先の話である。
事故後すぐに汚染土壌を避難区域の中間貯蔵に移したが、その際に期間を定めて、時期が来れば他県に移すことになった。しかし他県での受け入れは当該地域の市民に反対されている。汚染除去された除去土壌の基準値を新たに定めて、基準以下だから他県に移すことが法令上可能になったが、市民の安心の同意は得られていない。
放射線、放射能がなければ原発復旧は10年で終わっている。終わりが見えないのはひとえに放射線、放射能が原因であり、現場での扱いの困難さが原発事故復旧の諸問題の根源とも言える。
その現場での放射線、放射能管理は学者の机上理論では解決ができない。あくまで現場作業管理の問題である。
0
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説

島猫たちのエピソード2025
BIRD
エッセイ・ノンフィクション
「Cat nursery Larimar 」は、ひとりでは生きられない仔猫を預かり、保護者&お世話ボランティア達が協力して育てて里親の元へ送り出す「仔猫の保育所」です。
石垣島は野良猫がとても多い島。
2021年2月22日に設立した保護団体【Cat nursery Larimar(通称ラリマー)】は、自宅では出来ない保護活動を、施設にスペースを借りて頑張るボランティアの集まりです。
「保護して下さい」と言うだけなら、誰にでも出来ます。
でもそれは丸投げで、猫のために何かした内には入りません。
もっと踏み込んで、その猫の医療費やゴハン代などを負担出来る人、譲渡会を手伝える人からの依頼のみ受け付けています。
本作は、ラリマーの保護活動や、石垣島の猫ボランティアについて書いた作品です。
スコア収益は、保護猫たちのゴハンやオヤツの購入に使っています。
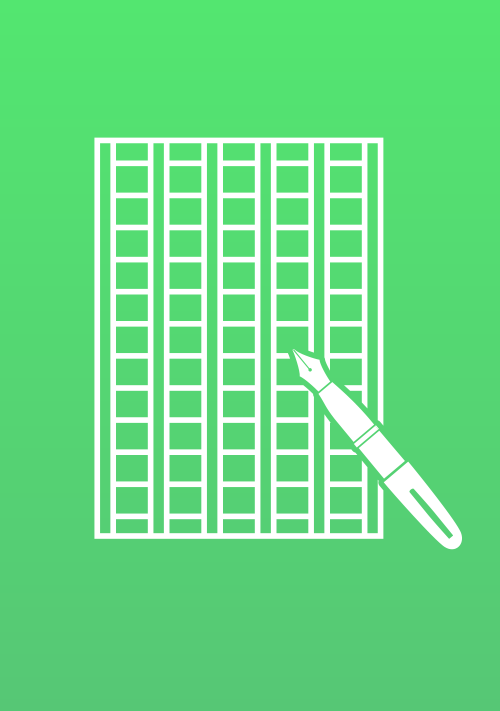
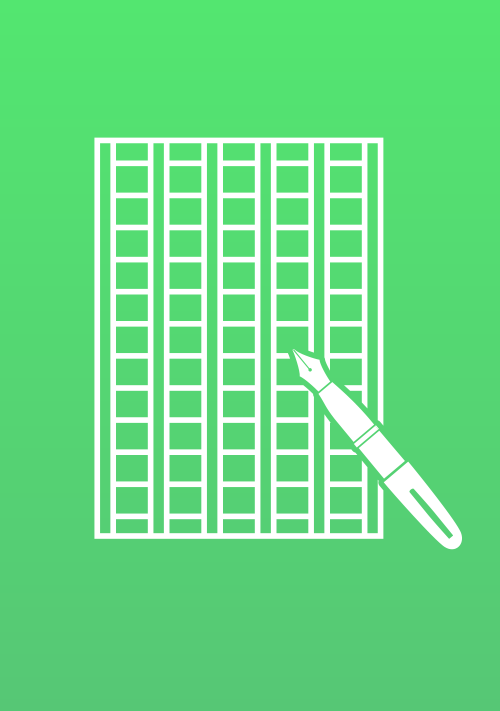
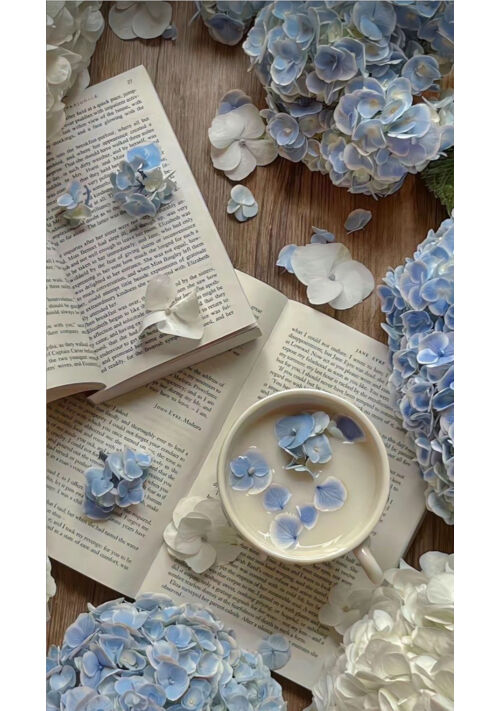
月弥総合病院
御月様(旧名 僕君☽☽︎)
キャラ文芸
月弥総合病院。極度の病院嫌いや完治が難しい疾患、診察、検査などの医療行為を拒否したり中々治療が進められない子を治療していく。
また、ここは凄腕の医師達が集まる病院。特にその中の計5人が圧倒的に遥か上回る実力を持ち、「白鳥」と呼ばれている。
(小児科のストーリー)医療に全然詳しく無いのでそれっぽく書いてます...!!

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。


同じアパートに住む年上未亡人美女は甘すぎる。
ピコサイクス
青春
大学生の翔太は、一人暮らしを始めたばかり。
真下の階に住むのは、落ち着いた色気と優しさを併せ持つ大人の女性・水無瀬紗夜。
引っ越しの挨拶で出会った瞬間、翔太は心を奪われてしまう。
偶然にもアルバイト先のスーパーで再会した彼女は、翔太をすぐに採用し、温かく仕事を教えてくれる存在だった。
ある日の仕事帰り、ふたりで過ごす時間が増えていき――そして気づけば紗夜の部屋でご飯をご馳走になるほど親密に。
優しくて穏やかで――その色気に触れるたび、翔太の心は揺れていく。
大人の女性と大学生、甘くちょっぴり刺激的な同居生活(?)がはじまる。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















