36 / 43
本編
35
しおりを挟む
「お姉さま……私、なにかしましたか?」
「ええ。すてきな言葉を、私に贈ってくれたわ」
「言葉……」
魔法使いにとって、言葉は大切なものだ。言霊を用いて魔法を使う彼らは、言葉は力を持つと知っているからだ。
言葉を用いずとも魔法を扱える魔女も、生まれながらにして魔女だったわけではない。膨大な魔力をもって生まれ、魔法使いとして知識をつけて魔力を高めれば魔女になる。レアケにとって言葉は大切なものだからこそ、アニカやアウネーテ、そしてエスガの偽りのない言葉は胸に響いた。
「お姉さまによろこんでもらえて、うれしいです!」
アニカはすべてを理解したわけではないだろうが、レアケがよろこんでいることを純粋によろこんでくれる。その偽りのない笑顔にレアケもつられてほほ笑んだ。
「お姉さま、あの……色々な都合で、私がエスガお兄さまとお姉さまより先にフィヨルに入ることになってしまって」
「ここはあなたの家でもあるのだから、問題ないじゃない」
アニカは前フィヨル侯爵の子女であり、現フィヨル侯爵の妹、まごうことなきフィヨル侯爵家の一員だ。レアケはエスガと共にフィヨル侯爵領に入ったものの、まだフィヨル侯爵の婚約者という立場であり、フィヨル侯爵家の一員ではない。元々貴族とは縁遠い生まれの上、早々に家族と離別しているため、一家という概念にこだわりがない。アニカが気にするようなことは、一切気にしていなかった。
「内装など、ひとまず私の方でお願いしたのですが……お姉さまの好みで変えてくださいね」
「私の?」
「はい、お姉さまはフィヨル侯爵夫人になる方ですから!」
よほどレアケがエスガと夫婦になることがうれしいのか、アニカは目を輝かせている。レアケに好感を抱いているからというのもあるだろうが、なによりいままで苦労をかけていた兄がようやく肩の荷を降ろし、想い人と結ばれることをよろこんでいるのだろう。
「……あなたって、いい子ね」
「え?」
「いえ……アニカが選んでくれた内装、とても気に入ったわ。あなたとは好みが合うみたい」
華美さはなく、質素で落ち着いた内装だ。アニカの感性はエスガが侍女として働いている間、修道院で生活していたことが影響をあたえたのかもしれない。元々森に引きこもって質素な暮らしをし、レイフら王族のきらびやかな装いを嫌悪していたレアケとは好みにぴったりとあうようだ。
「わあ、うれしいですお姉さま! 私がここにいる間、仲良くしてくださいね!」
「ええ。仲良くしてね、アニカ。……えっ、まって。ここにいる間って?」
アニカが笑顔であったため、うっかりその言葉を聞き流しそうになった、レアケだが数秒経って驚き、問いかける。
「いつかは、私も嫁ぐ予定ですから」
「ああ……そういうことね」
アニカはすでに結婚していてもおかしくない年齢だ。フィヨル侯爵家の血筋として嫁ぎ、血のつながりを結んでいく。
「……エスガはなんて言っているの?」
「私が望む相手なら、構わないと」
エスガは大切な妹を嫁に出すことは渋りそうなものだが、彼自身が望む相手と結婚しようとしているからか反対もできないのだろう。
「望む相手がいるのね」
「はい。もう何年もアプローチしているのですが、相手にされなくて……けれど、成人してからは少し見込みが見えてきました!」
アニカはその相手を長く想い続けているようで、意外にも恋には積極的だ。
(歳が離れている相手かしら)
成人してから見込みが見えてきたということは、成人するまでは相手にできないような相手ということだ。歳が離れた大人であれば、未成年の少女を相手になどできないだろう。
「……そう。私も、アニカが望むのであればいいと思うわ」
アニカが未成年である間はまったく相手にしなかった、なかなかできた男だとレアケは感心した。紅茶を一口口に含んで香り楽しみ、それを飲み込もうとしたところ。
「お姉さまに、お母さまと呼ばれる日がきてしまうのかもしれませんね」
「……っ」
レアケはアニカの言葉で口にした紅茶を吹きそうになった。なんとかこらえて飲み込んだものの、そのまま咳きこんでしまう。そんなレアケの背をアウネーテが慌ててさすった。
(まさか、相手はエルフレズ!?)
アニカの兄、エスガに嫁ぐレアケをお姉さまと呼ぶ彼女が、レアケにお母さまと呼ばれることになる。すなわち、レアケ・ラーセンの父、エルフレズ・ラーセンに嫁ぐということだ。
「お姉さま、大丈夫ですか?」
「っ、……ええ、問題ないわ……」
レアケにとっては予想外の相手だった。歳が離れていると推理してはいたものの、さすがに父と娘ほどに歳が離れているとは思っていなかったようだ。
「……本当に、エルフレズがいいの?」
「はい」
相手がエルフレズであることを否定することもなく、アニカは笑顔でうなずいた。
「彼は……」
エルフレズはけっして、善意でエスガとアニカを助けたわけではない。彼の計画のため、利用するために兄妹を助けたはずだ。そのことを言いかけたレアケだが、すんでのところで言葉を飲み込む。レアケはエルフレズのすべてを理解しているわけではないのだから、それはただの憶測でしかない。それに、エルフレズを想うアニカに彼を貶めるような言葉を言うべきではない。
「エルフレズさまがお兄さまと私を助けてくれたのは、善意ではなかったのかもしれません」
アニカは笑顔のまま、レアケが飲み込んだ言葉を自ら口にした。それはすでにエスガが伝えていたのかもしれないし、もしかしたら本人から直接聞いたものなのかもしれない。
「私はあの方の深謀のすべてを理解することはできません。ですが、どのような理由であったとしても……私があの方に助けられたことは変わりませんから」
母を亡くし、貧しくその日を生きて、冬の寒さに命を奪われそうになっていたアニカをエルフレズは助けた。それが彼女の兄エスガを利用するためだとしても、エスガは仕事を手にし、アニカは雨風しのげる寝床を得られた。アニカはエルフレズにとても感謝し、いつからか恋心を抱くようになった。
他人にどのように言われても、アニカにとってはそれがすべてなのだろう。物事は他人の言葉で揺らぐことがあっても、結局は受け取る側がどう感じるのかがすべてだ。
「お母さまと呼ぶかどうかはわからないけれど……がんばってね、アニカ」
「はいっ」
頬を赤く染め、満面の笑みで答えるアニカは心からエルフレズを想っているのだろう。レアケはそれをほほ笑ましく思いつつも、仮に二人が結ばれてもアニカをお母さまと呼ぶことはないだろうとぼんやりと考えていた。
なにせエルフレズとはいままで関わりがなく、エスガとの結婚のために養女となっただけで、そのことに恩は感じつつも父親だとは一切思えない。どちらかといえば、エスガの父親のような存在に思えるくらいだ。
(年の差が……いえ、それは私が言えることじゃあないわね……)
魔女であるレアケは容姿が二十歳ほどにしか見えないが、実年齢は二十をはるかに上回る。レアケとエスガの年の差を考えれば、アニカとエルフレズの年齢差などかわいいものだ。
「うっ、痛い……」
レアケはエスガとの歳の差がまったく気にならないわけではない。しかし、歳の差はどうあがいてもけっして変えられないものだ。
(いまは同じくらいに見えるけれど……)
レアケが魔女であることが幸いなのか、それとも不幸なのか、年の差があれどもいまの二人は同じ年ごろに見える。しかしそれは短い間だけのこと。
「お姉さま?」
「……き、気にしないで。自虐しただけだから」
レアケは紅茶を一気に飲み干し、一つため息をついた。
(……なんだか、無性にエスガに会いたい)
先ほど別れたばかり、まだ一時間も経っていないうちに、レアケはエスガが恋しくなった。
「ええ。すてきな言葉を、私に贈ってくれたわ」
「言葉……」
魔法使いにとって、言葉は大切なものだ。言霊を用いて魔法を使う彼らは、言葉は力を持つと知っているからだ。
言葉を用いずとも魔法を扱える魔女も、生まれながらにして魔女だったわけではない。膨大な魔力をもって生まれ、魔法使いとして知識をつけて魔力を高めれば魔女になる。レアケにとって言葉は大切なものだからこそ、アニカやアウネーテ、そしてエスガの偽りのない言葉は胸に響いた。
「お姉さまによろこんでもらえて、うれしいです!」
アニカはすべてを理解したわけではないだろうが、レアケがよろこんでいることを純粋によろこんでくれる。その偽りのない笑顔にレアケもつられてほほ笑んだ。
「お姉さま、あの……色々な都合で、私がエスガお兄さまとお姉さまより先にフィヨルに入ることになってしまって」
「ここはあなたの家でもあるのだから、問題ないじゃない」
アニカは前フィヨル侯爵の子女であり、現フィヨル侯爵の妹、まごうことなきフィヨル侯爵家の一員だ。レアケはエスガと共にフィヨル侯爵領に入ったものの、まだフィヨル侯爵の婚約者という立場であり、フィヨル侯爵家の一員ではない。元々貴族とは縁遠い生まれの上、早々に家族と離別しているため、一家という概念にこだわりがない。アニカが気にするようなことは、一切気にしていなかった。
「内装など、ひとまず私の方でお願いしたのですが……お姉さまの好みで変えてくださいね」
「私の?」
「はい、お姉さまはフィヨル侯爵夫人になる方ですから!」
よほどレアケがエスガと夫婦になることがうれしいのか、アニカは目を輝かせている。レアケに好感を抱いているからというのもあるだろうが、なによりいままで苦労をかけていた兄がようやく肩の荷を降ろし、想い人と結ばれることをよろこんでいるのだろう。
「……あなたって、いい子ね」
「え?」
「いえ……アニカが選んでくれた内装、とても気に入ったわ。あなたとは好みが合うみたい」
華美さはなく、質素で落ち着いた内装だ。アニカの感性はエスガが侍女として働いている間、修道院で生活していたことが影響をあたえたのかもしれない。元々森に引きこもって質素な暮らしをし、レイフら王族のきらびやかな装いを嫌悪していたレアケとは好みにぴったりとあうようだ。
「わあ、うれしいですお姉さま! 私がここにいる間、仲良くしてくださいね!」
「ええ。仲良くしてね、アニカ。……えっ、まって。ここにいる間って?」
アニカが笑顔であったため、うっかりその言葉を聞き流しそうになった、レアケだが数秒経って驚き、問いかける。
「いつかは、私も嫁ぐ予定ですから」
「ああ……そういうことね」
アニカはすでに結婚していてもおかしくない年齢だ。フィヨル侯爵家の血筋として嫁ぎ、血のつながりを結んでいく。
「……エスガはなんて言っているの?」
「私が望む相手なら、構わないと」
エスガは大切な妹を嫁に出すことは渋りそうなものだが、彼自身が望む相手と結婚しようとしているからか反対もできないのだろう。
「望む相手がいるのね」
「はい。もう何年もアプローチしているのですが、相手にされなくて……けれど、成人してからは少し見込みが見えてきました!」
アニカはその相手を長く想い続けているようで、意外にも恋には積極的だ。
(歳が離れている相手かしら)
成人してから見込みが見えてきたということは、成人するまでは相手にできないような相手ということだ。歳が離れた大人であれば、未成年の少女を相手になどできないだろう。
「……そう。私も、アニカが望むのであればいいと思うわ」
アニカが未成年である間はまったく相手にしなかった、なかなかできた男だとレアケは感心した。紅茶を一口口に含んで香り楽しみ、それを飲み込もうとしたところ。
「お姉さまに、お母さまと呼ばれる日がきてしまうのかもしれませんね」
「……っ」
レアケはアニカの言葉で口にした紅茶を吹きそうになった。なんとかこらえて飲み込んだものの、そのまま咳きこんでしまう。そんなレアケの背をアウネーテが慌ててさすった。
(まさか、相手はエルフレズ!?)
アニカの兄、エスガに嫁ぐレアケをお姉さまと呼ぶ彼女が、レアケにお母さまと呼ばれることになる。すなわち、レアケ・ラーセンの父、エルフレズ・ラーセンに嫁ぐということだ。
「お姉さま、大丈夫ですか?」
「っ、……ええ、問題ないわ……」
レアケにとっては予想外の相手だった。歳が離れていると推理してはいたものの、さすがに父と娘ほどに歳が離れているとは思っていなかったようだ。
「……本当に、エルフレズがいいの?」
「はい」
相手がエルフレズであることを否定することもなく、アニカは笑顔でうなずいた。
「彼は……」
エルフレズはけっして、善意でエスガとアニカを助けたわけではない。彼の計画のため、利用するために兄妹を助けたはずだ。そのことを言いかけたレアケだが、すんでのところで言葉を飲み込む。レアケはエルフレズのすべてを理解しているわけではないのだから、それはただの憶測でしかない。それに、エルフレズを想うアニカに彼を貶めるような言葉を言うべきではない。
「エルフレズさまがお兄さまと私を助けてくれたのは、善意ではなかったのかもしれません」
アニカは笑顔のまま、レアケが飲み込んだ言葉を自ら口にした。それはすでにエスガが伝えていたのかもしれないし、もしかしたら本人から直接聞いたものなのかもしれない。
「私はあの方の深謀のすべてを理解することはできません。ですが、どのような理由であったとしても……私があの方に助けられたことは変わりませんから」
母を亡くし、貧しくその日を生きて、冬の寒さに命を奪われそうになっていたアニカをエルフレズは助けた。それが彼女の兄エスガを利用するためだとしても、エスガは仕事を手にし、アニカは雨風しのげる寝床を得られた。アニカはエルフレズにとても感謝し、いつからか恋心を抱くようになった。
他人にどのように言われても、アニカにとってはそれがすべてなのだろう。物事は他人の言葉で揺らぐことがあっても、結局は受け取る側がどう感じるのかがすべてだ。
「お母さまと呼ぶかどうかはわからないけれど……がんばってね、アニカ」
「はいっ」
頬を赤く染め、満面の笑みで答えるアニカは心からエルフレズを想っているのだろう。レアケはそれをほほ笑ましく思いつつも、仮に二人が結ばれてもアニカをお母さまと呼ぶことはないだろうとぼんやりと考えていた。
なにせエルフレズとはいままで関わりがなく、エスガとの結婚のために養女となっただけで、そのことに恩は感じつつも父親だとは一切思えない。どちらかといえば、エスガの父親のような存在に思えるくらいだ。
(年の差が……いえ、それは私が言えることじゃあないわね……)
魔女であるレアケは容姿が二十歳ほどにしか見えないが、実年齢は二十をはるかに上回る。レアケとエスガの年の差を考えれば、アニカとエルフレズの年齢差などかわいいものだ。
「うっ、痛い……」
レアケはエスガとの歳の差がまったく気にならないわけではない。しかし、歳の差はどうあがいてもけっして変えられないものだ。
(いまは同じくらいに見えるけれど……)
レアケが魔女であることが幸いなのか、それとも不幸なのか、年の差があれどもいまの二人は同じ年ごろに見える。しかしそれは短い間だけのこと。
「お姉さま?」
「……き、気にしないで。自虐しただけだから」
レアケは紅茶を一気に飲み干し、一つため息をついた。
(……なんだか、無性にエスガに会いたい)
先ほど別れたばかり、まだ一時間も経っていないうちに、レアケはエスガが恋しくなった。
10
あなたにおすすめの小説


「がっかりです」——その一言で終わる夫婦が、王宮にはある
柴田はつみ
恋愛
妃の席を踏みにじったのは令嬢——けれど妃の心を折ったのは、夫のたった一言だった
王太子妃リディアの唯一の安らぎは、王太子アーヴィンと交わす午後の茶会。だが新しく王宮に出入りする伯爵令嬢ミレーユは、妃の席に先に座り、殿下を私的に呼び、距離感のない振る舞いを重ねる。
リディアは王宮の礼節としてその場で正す——正しいはずだった。けれど夫は「リディア、そこまで言わなくても……」と、妃を止めた。
「わかりました。あなたには、がっかりです」
微笑んで去ったその日から、夫婦の茶会は終わる。沈黙の王宮で、言葉を失った王太子は、初めて“追う”ことを選ぶが——遅すぎた。

五年後、元夫の後悔が遅すぎる。~娘が「パパ」と呼びそうで困ってます~
放浪人
恋愛
「君との婚姻は無効だ。実家へ帰るがいい」
大聖堂の冷たい石畳の上で、辺境伯ロルフから突然「婚姻は最初から無かった」と宣告された子爵家次女のエリシア。実家にも見放され、身重の体で王都の旧市街へ追放された彼女は、絶望のどん底で愛娘クララを出産する。
生き抜くために針と糸を握ったエリシアは、持ち前の技術で不思議な力を持つ「祝布(しゅくふ)」を織り上げる職人として立ち上がる。施しではなく「仕事」として正当な対価を払い、決して土足で踏み込んでこない救恤院の監督官リュシアンの温かい優しさに触れエリシアは少しずつ人間らしい心と笑顔を取り戻していった。
しかし五年後。辺境を襲った疫病を救うための緊急要請を通じ、エリシアは冷酷だった元夫ロルフと再会してしまう。しかも隣にいる娘の青い瞳は彼と瓜二つだった。
「すまない。私は父としての責任を果たす」
かつての合理主義の塊だった元夫は、自らの過ちを深く悔い、家の権益を捨ててでも母子を守る「強固な盾」になろうとする。娘のクララもまた、危機から救ってくれた彼を「パパ」と呼び始めてしまい……。
だが、どんなに後悔されても、どんなに身を挺して守られても、一度完全に壊された関係が元に戻ることは絶対にない。エリシアが真の伴侶として選ぶのは、凍えた心を溶かし、温かい日常を共に歩んでくれたリュシアンただ一人だった。
これは、全てを奪われた一人の女性が母として力強く成長し誰にも脅かされることのない「本物の家族」と「静かで確かな幸福」を自分の手で選び取るまでの物語。

契約妻に「愛さない」と言い放った冷酷騎士、一分後に彼女の健気さが性癖に刺さって理性が崩壊した件
水月
恋愛
冷酷騎士様の「愛さない」は一分も持たなかった件の旦那様視点短編となります。
「君を愛するつもりはない」
結婚初夜、帝国最強の冷酷騎士ヴォルフラム・ツヴァルト公爵はそう言い放った。
出来損ないと蔑まれ、姉の代わりの生贄として政略結婚に差し出されたリーリア・ミラベルにとって、それはむしろ救いだった。
愛を期待されないのなら、失望させることもない。
契約妻として静かに役目を果たそうとしたリーリアは、緩んだ軍服のボタンを自らの銀髪と微弱な強化魔法で直す。
ただ「役に立ちたい」という一心だった。
――その瞬間。
冷酷騎士の情緒が崩壊した。
「君は、自分の価値を分かっていない」
開始一分で愛さない宣言は撤回。
無自覚に自己評価が低い妻に、激重独占欲を発症した最強騎士が爆誕する。

私が王子との結婚式の日に、妹に毒を盛られ、公衆の面前で辱められた。でも今、私は時を戻し、運命を変えに来た。
MayonakaTsuki
恋愛
王子との結婚式の日、私は最も信頼していた人物――自分の妹――に裏切られた。毒を盛られ、公開の場で辱められ、未来の王に拒絶され、私の人生は血と侮辱の中でそこで終わったかのように思えた。しかし、死が私を迎えたとき、不可能なことが起きた――私は同じ回廊で、祭壇の前で目を覚まし、あらゆる涙、嘘、そして一撃の記憶をそのまま覚えていた。今、二度目のチャンスを得た私は、ただ一つの使命を持つ――真実を突き止め、奪われたものを取り戻し、私を破滅させた者たちにその代償を払わせる。もはや、何も以前のままではない。何も許されない。

巨乳令嬢は男装して騎士団に入隊するけど、何故か騎士団長に目をつけられた
狭山雪菜
恋愛
ラクマ王国は昔から貴族以上の18歳から20歳までの子息に騎士団に短期入団する事を義務付けている
いつしか時の流れが次第に短期入団を終わらせれば、成人とみなされる事に変わっていった
そんなことで、我がサハラ男爵家も例外ではなく長男のマルキ・サハラも騎士団に入団する日が近づきみんな浮き立っていた
しかし、入団前日になり置き手紙ひとつ残し姿を消した長男に男爵家当主は苦悩の末、苦肉の策を家族に伝え他言無用で使用人にも箝口令を敷いた
当日入団したのは、男装した年子の妹、ハルキ・サハラだった
この作品は「小説家になろう」にも掲載しております。

贖罪の花嫁はいつわりの婚姻に溺れる
マチバリ
恋愛
貴族令嬢エステルは姉の婚約者を誘惑したという冤罪で修道院に行くことになっていたが、突然ある男の花嫁になり子供を産めと命令されてしまう。夫となる男は稀有な魔力と尊い血統を持ちながらも辺境の屋敷で孤独に暮らす魔法使いアンデリック。
数奇な運命で結婚する事になった二人が呪いをとくように幸せになる物語。
書籍化作業にあたり本編を非公開にしました。
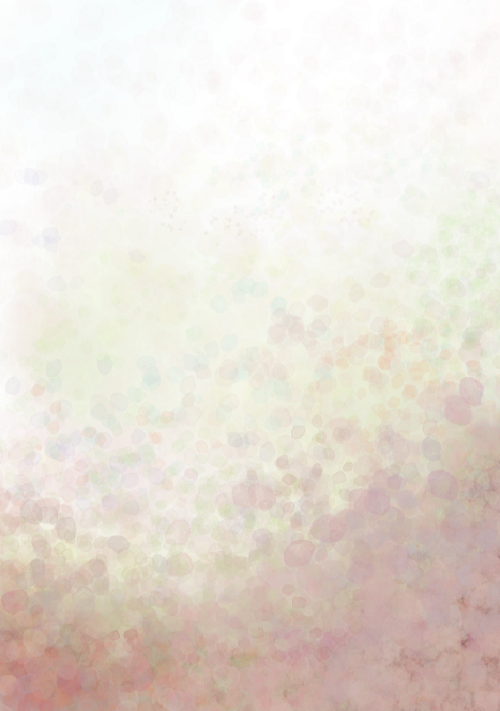
「今とっても幸せですの。ごめんあそばせ♡」 捨てられ者同士、溺れちゃうほど愛し合ってますのでお構いなく!
若松だんご
恋愛
「キサマとはやっていけない。婚約破棄だ。俺が愛してるのは、このマリアルナだ!」
婚約者である王子が開いたパーティ会場で。妹、マリアルナを伴って現れた王子。てっきり結婚の日取りなどを発表するのかと思っていたリューリアは、突然の婚約破棄、妹への婚約変更に驚き戸惑う。
「姉から妹への婚約変更。外聞も悪い。お前も噂に晒されて辛かろう。修道院で余生を過ごせ」
リューリアを慰めたり、憤慨することもない父。マリアルナが王子妃になることを手放しで喜んだ母。
二人は、これまでのリューリアの人生を振り回しただけでなく、これからの未来も勝手に決めて命じる。
四つ違いの妹。母によく似たかわいらしい妹が生まれ、母は姉であ、リューリアの育児を放棄した。
そんなリューリアを不憫に思ったのか、ただの厄介払いだったのか。田舎で暮らしていた祖母の元に預けられて育った。
両親から離れたことは寂しかったけれど、祖母は大切にしてくれたし、祖母の家のお隣、幼なじみのシオンと仲良く遊んで、それなりに楽しい幼少期だったのだけど。
「第二王子と結婚せよ」
十年前、またも家族の都合に振り回され、故郷となった町を離れ、祖母ともシオンとも別れ、未来の王子妃として厳しい教育を受けることになった。
好きになれそうにない相手だったけれど、未来の夫となる王子のために、王子に代わって政務をこなしていた。王子が遊び呆けていても、「男の人はそういうものだ」と文句すら言わせてもらえなかった。
そして、20歳のこの日。またも周囲の都合によって振り回され、周囲の都合によって未来まで決定されてしまった。
冗談じゃないわ。どれだけ人を振り回したら気が済むのよ、この人たち。
腹が立つけれど、どうしたらいいのかわからずに、従う道しか選べなかったリューリア。
せめて。せめて修道女として生きるなら、故郷で生きたい。
自分を大事にしてくれた祖母もいない、思い出だけが残る町。けど、そこで幼なじみのシオンに再会する。
シオンは、結婚していたけれど、奥さんが「真実の愛を見つけた」とかで、行方をくらましていて、最近ようやく離婚が成立したのだという。
真実の愛って、そんなゴロゴロ転がってるものなのかしら。そして、誰かを不幸に、悲しませないと得られないものなのかしら。
というか。真実もニセモノも、愛に真贋なんてあるのかしら。
捨てられた者同士。傷ついたもの同士。
いっしょにいて、いっしょに楽しんで。昔を思い出して。
傷を舐めあってるんじゃない。今を楽しみ、愛を、想いを育んでいるの。だって、わたしも彼も、幼い頃から相手が好きだったってこと、思い出したんだもの。
だから。
わたしたちの見つけた「真実の愛(笑)」、邪魔をしないでくださいな♡
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















