8 / 18
叔母の家
しおりを挟む
城の裏門から出たところに馬車が用意してあった。
キリウスとレーナが直々に見送りに出てきたことにレオナードは驚き、恐縮した。
「レオナードが無事に帰ってこれますように」
と、レーナがレオナードの左手を取って、その腕に紫と黒の組紐で編んだ腕輪のようなものを結んだ。
「これはお守りなの。必ず着けていて。きっとあなたを守るから」
自分の腕に触れた女王の手の温かさに、レオナードは優しい笑みを浮かべた。
「恐れ入ります、女王陛下。叔母のことが済んだらすぐに戻ってまいりますので」
「ええ。気をつけてね」
レオナードは女王と国王の後ろに控えたフランが何か言いたそうな顔で自分を見ているのに気がついたが、声をかけることなく馬車に乗り込んだ。
イスラトルの町に着いたのは夕刻だった。
城の馬車は薄暗い町道を抜けて、一軒の古い屋敷の前で止まった。
馬車から降りたレオナードは昔と変わらぬ佇まいを見せる叔母の屋敷を暗澹とした思いで眺めた。
屋敷に入る門の前で、ふと、隣の屋敷を見ると昔、仲のよかった少女が住む家には灯りは灯らず、人の住んでいる気配がしない。
自分が訪れなくなった間に隣の家には何かあったのだろうか、とレオナードは訝しながら叔母の家の小道を歩き、屋敷の扉を叩いた。
「まあ!レオナードじゃないの。ずいぶん久しぶりだわね!元気だった?まあまあまあ!こんなに大きくなって」
もうじき30になろうという男を捕まえて大きくなったというのも妙な話だ、とレオナードは苦笑しながら首にしがみついてくる叔母の身体を引き剥がした。
「この辺りに妖物が出たと聞いて、叔母上が無事かどうかを確認に来ただけです。どうやらご無事のようなので、私は明日城に戻ります」
「まあ、レオナードったら、もっとゆっくりしていってもいいんじゃない?本当に顔を見るのは久しぶりなのだし。ああ、それに、妖物ね。まだ退治されていないんでしょう?警護団の方が言ってたわ。私、怖いわ。家に一人だし。レオナードがいてくれたらとっても心強いのだけど。ああ、それから、今お城で国王様の侍従をしているのでしょう?すごいわ!ねえ、国王様ってどんな方?噂通りの美丈夫なの?」
まくしたてるような叔母の口撃にたじたじとなったレオナードは、だから叔母は苦手なのだと心の中で溜息を吐いた。
「・・・しかし、叔母上・・・私はあまりゆっくりしてもいられないので・・・」
「あら、そういえば、夕食は?まだなのでしょう?ああ、来ることがわかっていたらご馳走を作っていたのに。今夜は簡単な食事しかないけど、食べるでしょう?」
食べるでしょう?と質問形式だけれど、実は叔母の『でしょう?』は強制だと分かっているレオナードは素直に
「いただきます」と答えた。
断るほうが面倒なことになるのが目に見えているのだ。
それにしても、見ないうちに・・・
レオナードは叔母の丸々と太った後ろ姿を半眼になって眺めた。
レーナ様もフランも抱き上げると羽根のように軽かった。女性とはそういうものだと思っていたが・・・
叔母が倒れても抱き上げるのは自分には無理だと思いながら叔母の後について家の中に入った。
簡単な食事しかない、と叔母は言ったはずだが、とレオナードは食卓に並べられている余裕で4人前はありそうなパンや野菜スープや盛られた肉の塊をみて首を傾げた。
自分の聞き間違いか、それとも・・・
「叔母上、誰か客人でもあるのですか?」
「え?何を言ってるの?おかしな子ね」そう言いながら、叔母は自分の皿に肉を積み上げていく。
なるほど、4人分だと思ったのは、ほぼ叔母の分だったのか。と、レオナードは納得して無言で自分の皿に肉を取り分けた。
「あら、それだけでいいの?もっと食べないと。そんなに細くてお城の仕事が務まるの?」
太った侍従などみっともなくて、自分の美意識に反する、と言いたい気持ちを彼は抑えた。
「叔母上はいくつになってもご健啖のようで羨ましいです」
「あらそう?ところで、レオナード、結婚はいつするの?お相手はいるの?」
レオナードは口に入れた肉を丸飲みしそうになって咽せながら、涙目で叔母を見た。
どうして、話がそう飛躍する。まるでついていけない。
「もう、いい年じゃないの。早く身を固めてお父様を安心させなさいよ。私だって、あなたがいつまでも独身だと心配だわ。ね、お城にいい子はいないの?」
矢継ぎ早な叔母の言葉に放心状態になったレオナードの頭にフランの顔が浮かんだ。
あり得ない。
自分の思考を自分で否定しながら、レオナードは自己嫌悪に陥った。
あり得ない。
今までなら女王のレーナの顔が浮かんだはずだ。
なぜ、フランの顔が浮かぶ。
私は女王に生涯の愛を捧げるのではなかったのか。
フランが頭に浮かぶ理由がわからない。
フランはただの侍従仲間で・・・世話のかかる女性で・・・
「どうしたの?レオナード?」
食事の手を止めて固まっているレオナードを困惑の顔で見ながら、叔母はまた話題を変えた。
「そう言えば、お隣のエルレーンと仲が良かったわね、レオナード」
「!」
そうだった、少女の名はエルレーンだった。
昔、いっしょに遊んだ。
「叔母上、隣はどうしたんですか。人が住んでるようには思えませんでしたが」
叔母はレオナードの言葉を聞くと、ふっくらとした顔に影を落として、
「実はね」と、沈んだ声で話し始めた。
キリウスとレーナが直々に見送りに出てきたことにレオナードは驚き、恐縮した。
「レオナードが無事に帰ってこれますように」
と、レーナがレオナードの左手を取って、その腕に紫と黒の組紐で編んだ腕輪のようなものを結んだ。
「これはお守りなの。必ず着けていて。きっとあなたを守るから」
自分の腕に触れた女王の手の温かさに、レオナードは優しい笑みを浮かべた。
「恐れ入ります、女王陛下。叔母のことが済んだらすぐに戻ってまいりますので」
「ええ。気をつけてね」
レオナードは女王と国王の後ろに控えたフランが何か言いたそうな顔で自分を見ているのに気がついたが、声をかけることなく馬車に乗り込んだ。
イスラトルの町に着いたのは夕刻だった。
城の馬車は薄暗い町道を抜けて、一軒の古い屋敷の前で止まった。
馬車から降りたレオナードは昔と変わらぬ佇まいを見せる叔母の屋敷を暗澹とした思いで眺めた。
屋敷に入る門の前で、ふと、隣の屋敷を見ると昔、仲のよかった少女が住む家には灯りは灯らず、人の住んでいる気配がしない。
自分が訪れなくなった間に隣の家には何かあったのだろうか、とレオナードは訝しながら叔母の家の小道を歩き、屋敷の扉を叩いた。
「まあ!レオナードじゃないの。ずいぶん久しぶりだわね!元気だった?まあまあまあ!こんなに大きくなって」
もうじき30になろうという男を捕まえて大きくなったというのも妙な話だ、とレオナードは苦笑しながら首にしがみついてくる叔母の身体を引き剥がした。
「この辺りに妖物が出たと聞いて、叔母上が無事かどうかを確認に来ただけです。どうやらご無事のようなので、私は明日城に戻ります」
「まあ、レオナードったら、もっとゆっくりしていってもいいんじゃない?本当に顔を見るのは久しぶりなのだし。ああ、それに、妖物ね。まだ退治されていないんでしょう?警護団の方が言ってたわ。私、怖いわ。家に一人だし。レオナードがいてくれたらとっても心強いのだけど。ああ、それから、今お城で国王様の侍従をしているのでしょう?すごいわ!ねえ、国王様ってどんな方?噂通りの美丈夫なの?」
まくしたてるような叔母の口撃にたじたじとなったレオナードは、だから叔母は苦手なのだと心の中で溜息を吐いた。
「・・・しかし、叔母上・・・私はあまりゆっくりしてもいられないので・・・」
「あら、そういえば、夕食は?まだなのでしょう?ああ、来ることがわかっていたらご馳走を作っていたのに。今夜は簡単な食事しかないけど、食べるでしょう?」
食べるでしょう?と質問形式だけれど、実は叔母の『でしょう?』は強制だと分かっているレオナードは素直に
「いただきます」と答えた。
断るほうが面倒なことになるのが目に見えているのだ。
それにしても、見ないうちに・・・
レオナードは叔母の丸々と太った後ろ姿を半眼になって眺めた。
レーナ様もフランも抱き上げると羽根のように軽かった。女性とはそういうものだと思っていたが・・・
叔母が倒れても抱き上げるのは自分には無理だと思いながら叔母の後について家の中に入った。
簡単な食事しかない、と叔母は言ったはずだが、とレオナードは食卓に並べられている余裕で4人前はありそうなパンや野菜スープや盛られた肉の塊をみて首を傾げた。
自分の聞き間違いか、それとも・・・
「叔母上、誰か客人でもあるのですか?」
「え?何を言ってるの?おかしな子ね」そう言いながら、叔母は自分の皿に肉を積み上げていく。
なるほど、4人分だと思ったのは、ほぼ叔母の分だったのか。と、レオナードは納得して無言で自分の皿に肉を取り分けた。
「あら、それだけでいいの?もっと食べないと。そんなに細くてお城の仕事が務まるの?」
太った侍従などみっともなくて、自分の美意識に反する、と言いたい気持ちを彼は抑えた。
「叔母上はいくつになってもご健啖のようで羨ましいです」
「あらそう?ところで、レオナード、結婚はいつするの?お相手はいるの?」
レオナードは口に入れた肉を丸飲みしそうになって咽せながら、涙目で叔母を見た。
どうして、話がそう飛躍する。まるでついていけない。
「もう、いい年じゃないの。早く身を固めてお父様を安心させなさいよ。私だって、あなたがいつまでも独身だと心配だわ。ね、お城にいい子はいないの?」
矢継ぎ早な叔母の言葉に放心状態になったレオナードの頭にフランの顔が浮かんだ。
あり得ない。
自分の思考を自分で否定しながら、レオナードは自己嫌悪に陥った。
あり得ない。
今までなら女王のレーナの顔が浮かんだはずだ。
なぜ、フランの顔が浮かぶ。
私は女王に生涯の愛を捧げるのではなかったのか。
フランが頭に浮かぶ理由がわからない。
フランはただの侍従仲間で・・・世話のかかる女性で・・・
「どうしたの?レオナード?」
食事の手を止めて固まっているレオナードを困惑の顔で見ながら、叔母はまた話題を変えた。
「そう言えば、お隣のエルレーンと仲が良かったわね、レオナード」
「!」
そうだった、少女の名はエルレーンだった。
昔、いっしょに遊んだ。
「叔母上、隣はどうしたんですか。人が住んでるようには思えませんでしたが」
叔母はレオナードの言葉を聞くと、ふっくらとした顔に影を落として、
「実はね」と、沈んだ声で話し始めた。
0
あなたにおすすめの小説


【完結】6人目の娘として生まれました。目立たない伯爵令嬢なのに、なぜかイケメン公爵が離れない
朝日みらい
恋愛
エリーナは、伯爵家の6人目の娘として生まれましたが、幸せではありませんでした。彼女は両親からも兄姉からも無視されていました。それに才能も兄姉と比べると特に特別なところがなかったのです。そんな孤独な彼女の前に現れたのが、公爵家のヴィクトールでした。彼女のそばに支えて励ましてくれるのです。エリーナはヴィクトールに何かとほめられながら、自分の力を信じて幸せをつかむ物語です。

【完結】番としか子供が産まれない世界で
さくらもち
恋愛
番との間にしか子供が産まれない世界に産まれたニーナ。
何故か親から要らない子扱いされる不遇な子供時代に番と言う概念すら知らないまま育った。
そんなニーナが番に出会うまで
4話完結
出会えたところで話は終わってます。

美男美女の同僚のおまけとして異世界召喚された私、ゴミ無能扱いされ王城から叩き出されるも、才能を見出してくれた隣国の王子様とスローライフ
さら
恋愛
会社では地味で目立たない、ただの事務員だった私。
ある日突然、美男美女の同僚二人のおまけとして、異世界に召喚されてしまった。
けれど、測定された“能力値”は最低。
「無能」「お荷物」「役立たず」と王たちに笑われ、王城を追い出されて――私は一人、行くあてもなく途方に暮れていた。
そんな私を拾ってくれたのは、隣国の第二王子・レオン。
優しく、誠実で、誰よりも人の心を見てくれる人だった。
彼に導かれ、私は“癒しの力”を持つことを知る。
人の心を穏やかにし、傷を癒す――それは“無能”と呼ばれた私だけが持っていた奇跡だった。
やがて、王子と共に過ごす穏やかな日々の中で芽生える、恋の予感。
不器用だけど優しい彼の言葉に、心が少しずつ満たされていく。

神様の手違いで、おまけの転生?!お詫びにチートと無口な騎士団長もらっちゃいました?!
カヨワイさつき
恋愛
最初は、日本人で受験の日に何かにぶつかり死亡。次は、何かの討伐中に、死亡。次に目覚めたら、見知らぬ聖女のそばに、ポツンとおまけの召喚?あまりにも、不細工な為にその場から追い出されてしまった。
前世の記憶はあるものの、どれをとっても短命、不幸な出来事ばかりだった。
全てはドジで少し変なナルシストの神様の手違いだっ。おまけの転生?お詫びにチートと無口で不器用な騎士団長もらっちゃいました。今度こそ、幸せになるかもしれません?!

虚弱体質?の脇役令嬢に転生したので、食事療法を始めました
たくわん
恋愛
「跡継ぎを産めない貴女とは結婚できない」婚約者である公爵嫡男アレクシスから、冷酷に告げられた婚約破棄。その場で新しい婚約者まで紹介される屈辱。病弱な侯爵令嬢セラフィーナは、社交界の哀れみと嘲笑の的となった。
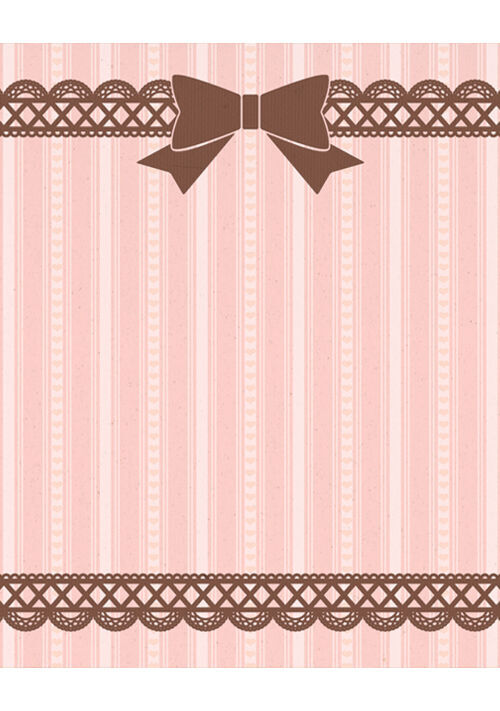
第12回ネット小説大賞コミック部門入賞・コミカライズ企画進行「婚約破棄ですか? それなら昨日成立しましたよ、ご存知ありませんでしたか?」完結
まほりろ
恋愛
第12回ネット小説大賞コミック部門入賞・コミカライズ企画進行中。
コミカライズ化がスタートしましたらこちらの作品は非公開にします。
「アリシア・フィルタ貴様との婚約を破棄する!」
イエーガー公爵家の令息レイモンド様が言い放った。レイモンド様の腕には男爵家の令嬢ミランダ様がいた。ミランダ様はピンクのふわふわした髪に赤い大きな瞳、小柄な体躯で庇護欲をそそる美少女。
対する私は銀色の髪に紫の瞳、表情が表に出にくく能面姫と呼ばれています。
レイモンド様がミランダ様に惹かれても仕方ありませんね……ですが。
「貴様は俺が心優しく美しいミランダに好意を抱いたことに嫉妬し、ミランダの教科書を破いたり、階段から突き落とすなどの狼藉を……」
「あの、ちょっとよろしいですか?」
「なんだ!」
レイモンド様が眉間にしわを寄せ私を睨む。
「婚約破棄ですか? 婚約破棄なら昨日成立しましたが、ご存知ありませんでしたか?」
私の言葉にレイモンド様とミランダ様は顔を見合わせ絶句した。
全31話、約43,000文字、完結済み。
他サイトにもアップしています。
小説家になろう、日間ランキング異世界恋愛2位!総合2位!
pixivウィークリーランキング2位に入った作品です。
アルファポリス、恋愛2位、総合2位、HOTランキング2位に入った作品です。
2021/10/23アルファポリス完結ランキング4位に入ってました。ありがとうございます。
「Copyright(C)2021-九十九沢まほろ」

最弱白竜ですが、なぜか学園最強の銀竜に番認定されました
斉藤めめめ
恋愛
竜の血を引く者だけが貴族になれるこの世界で、白竜は最も格の低い竜の証。
白竜の男爵令嬢リーゼロッテは、特待生として国内最高峰の王立竜騎学園に入学する。待っていたのは上位貴族からの蔑みと、学園を支配する四人の御曹司「四竜」。
その筆頭、銀竜公爵家の嫡男ルシアンに初日から啖呵を切ったリーゼは、いじめと嫉妬の嵐に巻き込まれていく。
それでも彼女は媚びない、逃げない、折れない。
やがてルシアンはリーゼから目が離せなくなり――
白竜の少女が、学園と王国の運命を変える。
身分差×竜×学園ラブファンタジー、開幕。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















