132 / 165
第14章︰ルカソワレーヴェ
第125話
しおりを挟む
「ねぇヴェラ。氷山で取れた水晶を持って帰ってきたけど、こんなに沢山どうするの?」
宿屋で部屋を借り、水晶の入った袋をテーブルの上に置いた。
ララとタクトの2人とは1度別れ、翌朝広場で合流して再び水晶を探しに行く事になった。
「これを使って魔法の練習をしようと思ってな。」
「え…。」
「…今、あからさまに嫌がったな?」
「い、いやぁ?そんな事ない…よ…?」
「なら問題ないな。始めよう。」
「うぅ…。」
以前は魔法を扱う事が出来なかったが、ルナと出会った頃からいつの間にか使えるようになっていた。しかし、魔法に慣れていないせいか、あまり得意ではない。元はステラという事もあり、魔力の量は多いが加減が難しい。まさに、宝の持ち腐れ状態だった。
彼女の説明を聞きながら、吸血鬼が薬を作る時などに使われる合成魔法“アルキミア”の練習が始まった。
「ちょっと…。水晶玉を作れって言ったのに、なんで水晶が粉々になるのよ…。」
「ご、ごめん…。」
あれからいくつの水晶を粉に変えただろうか。何度やっても上手くいかず、床に水晶の粉が溜まる一方だった。
「力が強過ぎるのも問題ね。抑制する為の装飾品が必要かしら…。」
「え!そんなものも作れるの?」
「昔作った事があるわ。色々試してみたけど、1番効果があったのは首輪ね。」
「く、首輪はちょっと…。」
「なら自力で制御しなさい。」
「………はい。」
それからしばらく魔法の練習は続いたが、全ての水晶を粉々に砕く結果となってしまった。
「おはようございますルシュ様。」
「ああ。おはようタクト。」
「ルカくん大丈夫…?なんだか疲れてるみたいだけど…。」
「だ、大丈夫!そんな事ないよ!」
「時間が惜しい。早く頂上へ向かおう。」
昨日同様、氷山の頂上付近で水晶の採掘を始めた。採掘と休憩を繰り返し、昇ったばかりだった太陽は僕達の真上にまで到達していた。
「あのー…ルシュ様。昨日の水晶はどうしたんですか?」
「あーあれか?あれはルカが、粉々に砕いた。」
「えっ。まさか…素手でですか…?」
「そんなわけあるか。魔法に失敗したから、そうなっただけだ。」
「なるほど…そうなんですね。」
タクトはその話を聞いて、苦笑いを浮かべた。
「ちょ、ちょっとヴェラ!そんな事タクトに言わなくてもいいじゃん…!」
「この方が、お前ももっと頑張るんじゃないかと思ってな。」
「え?それってどういう…」
「ルカくんの気持ちわかるなぁ…。初めの頃は、私も全然魔法を使えなかったから…。」
「ララはすごいよね。頑張って勉強して、上級吸血鬼になっちゃうんだもん。」
「凄くなんてないよ。みんなに支えてもらって、やっとここまでこれたって感じかな…。」
「そういえば、他のみんなはどうなの?レミリアとアレクには会ったから、2人は上級吸血鬼になったって知ってるけど…。」
「ユイちゃんも上級吸血鬼になったよ。ユノちゃんは上級クラスのままだけど、ツーくんとユーくんはさらに昇級して、幹部になっちゃったの。」
「え?幹部って事は…レジデンスにいるの?」
「ううん。レジデンス以外にも幹部専用の建物はあるから、そっちに配属になったよ。確か…イリスシティアの南の方じゃなかったかな?」
「そっか。やっぱりツヴェルとユーリはすごいや…。」
「そろそろお喋りはやめて、手を動かさないか?また日が暮れては困るからな。」
「そ、そうだね。わかった…!」
作業を再開して目の前にある岩を砕いていると、少し離れた所で作業していたララが大きな声を上げた。
「ルシュ様!これじゃないですか…!?」
彼女の手には他の水晶と比べ、明らかに輝きの違う大きな水晶が握られていた。
「確かめたいから、それを持ってこっちに来てくれ。」
「は、はい…!」
ヴェラに呼ばれたララは、小走りで僕の横を通り過ぎて行った。しかし、すれ違った瞬間、彼女の手に握られていた水晶が地面に転がり落ちた。
「ララ!?」
その場に倒れた彼女を慌てて抱き起こすと、口の端から血を流して気絶していた。
「ララ…!」
「おい!ララは素手でこれに触ったのか!?」
「ううん!ちゃんと手袋をしてるよ!?」
側にやってきたヴェラが地面に膝をつき、彼女の身体に触れて様子を伺い始めた。タクトは彼女の後ろに立ち、その様子をただ呆然と眺めている。
「原因は水晶しか考えられない…。手袋をしていたはずなのに何故…」
「そんな事よりララはこのままで大丈夫なの!?早く下山して、治療した方がいいんじゃ…!」
「その前に応急処置が必要だ。だが…今は薬の手持ちがない…。失った血を何とか補う方法は…」
「お、俺、いつも自分が飲んでいる薬なら持ってます!これで血の生成を増やせば…」
「今の状態のララにそれは無理だ。副作用に耐えられない。」
「なら僕が血を分けるよ!」
「え…でもそれじゃあルカが…」
「それしかないか…頼んだぞルカ。」
「うん!」
「容態が安定したら急いで下山する。タクトは荷物をまとめて、準備を整えてくれ。」
「わかりました…!」
「…ん。」
「ララ…!」
「タック…?あれ?私…」
「ルシュ様!ララが目を覚ましました!」
ララを家に運び込み、日が沈んで外が暗くなり始めた頃、彼女はようやく目を覚ました。
「もう大丈夫そうだな。大事を取って明日1日休むといい。」
「よかった…これで一安心だね。」
「ありがとうございますルシュ様…。」
「礼ならルカに言うべきだ。あいつの血がなかったら、お前をここまて連れて来る事すら出来なかったからな。」
「え?ルカくんが…血を分けてくれたって事?…ルカくんは、大丈夫なの?」
「た、大した事ないよ!元々量は多いし、余ってたから…。」
「ありがとうルカ。俺はあの場にいただけで…何も出来なかった…。ララが助かったのは、君のおかげだよ。本当にありがとう。」
「タクト…。」
「ララの看病はお前に任せる。私達は宿屋に戻るぞ。」
「う、うん。」
宿屋に戻って来ると、身につけたブレスレットに視線を向けた。中央に埋め込まれた宝石は、ララに血を分けた時は紫色だったがもう既に赤色へと変化していた。本来ならば紫色を保ち続けなければならないのだが、いくら血を消費してもすぐに増えてしまい、赤色の状態のまま放っておく事が多くなっていた。
「お前の血の多さは羨ましい限りだな。」
「僕は多過ぎて困ってるんだけど…。」
「あるものは使えばいい。増やすのは大変だか、減らすのは簡単だ。」
「ところで…ララが倒れた原因って、結局なんだったの?」
「おそらく、耀水晶の属性の力が強過ぎて、手袋をしただけでは防ぎきれなかったんだろう。」
「吸血鬼の命を奪いかねない水晶が、どうして氷山にあったんだろうなぁ…。」
「そんな事は私にもわからない。今日は何かと疲れる1日だったな。早めに休むとしよう。」
「そうだね。」
ベッドに向かって歩き出すと、彼女は僕の前に立ちはだかり、水晶の入った袋を突き出した。
「…お前は元気だろう?せっかく血が余っているのだから、魔法の練習をしなさい。」
「えぇ!?こんな時まで練習しなきゃいけないの!?」
「魔法というものは、何度も反復して行う事で身につくものだ。水晶なら沢山ある。遠慮する必要はないぞ?」
「遠慮してるつもりはないよ!はぁ…。これもルナの理想の為に、通らなくちゃいけない道か…まだまだ先が遠いなぁ。」
色々あったものの、何とか目的の耀水晶を手に入れた僕達は翌朝の出発に向けて、それぞれのタイミングで休息を取る事にした。
「あ、おはようタクト!」
翌朝、ララの様子が気になった僕は出発前に彼女の家を訪ねた。玄関で出迎えてくれたタクトが家の中に僕を招き入れ、彼の案内でリビングに通された。
「その…体調は大丈夫?」
「全然平気!ヴェラに、お前は元気だろ?って言われて魔法の練習をさせられたくらいだよ…。」
「あはは。…ルカが羨ましいよ。ルシュ様に手をかけて貰えるほどの才能があるんだから。」
「これは僕の才能じゃないよ。ルナに才能があったから、僕もたまたまそうなっただけで…。」
「…ルナが生きてるかもしれないって、ルカは信じてるんだよね?」
「うん。」
「何か、そう思う根拠はあるの?」
「根拠って言える程じゃないけど…ルナが死んだ事を知ってるのはヴェラ1人だけなんだ。僕がルナの話をしようとすると、妙に強く否定したり、無理矢理話題を変えようとしてる気がして…。疑いたくは無いけど、ヴェラの話にはどこか違和感があるような気がするんだ。」
「ルシュ様が、嘘をついてるって事…?」
「僕はそう思ってる。」
「…俺も、ルナが生きてるって信じてみるよ。そう思いたいだけかもしれないけど、何もせずに諦めるよりはマシかなって思ったんだ。」
「…ありがとうタクト。」
「ううん。ルカを見てたら自然とそういう気持ちになれたんだ。…ごめんルカ。この間は君に、傷付けるような事を言ってしまって…。」
「気にしてないよ!タクトがルナの事を大切に思ってくれてるの、わかってるから。」
「ありがとう…。あ、そうだ…ララにも会っていく?さっき起きた所だから、まだ部屋にいると思うよ。」
「じゃあそうするね!」
その場に彼を残し、階段を上って彼女の部屋へ向かった。
「あ、ルカくん…いらっしゃい!ごめんねこんな格好で…」
彼女は寝間着姿に上着を羽織り、ベッドの上で身体を起こした。
「そのままでいいのに…!今日は安静にっていう話だったもんね。」
「えっと…今日出発するんだよね?もう少しゆっくりすればいいのに…。」
「僕もそうしたい所だけど…レジデンスに行かない事には、何も始められないからね。出来るだけ急ぎたいんだ。」
「そっか…。あの…ルカくん。実はお願いしたい事があるんだけど…。」
「何?」
彼女はベッドの脇にある机の引き出しから、1枚の封筒を取り出した。
「これを、フランくんに渡して欲しいの。」
「え、でも…。こういうのは、直接渡した方がいいんじゃ…」
「私もそうしたいんだけど、全然会えそうにないから…。それと、何度かレジデンス宛に手紙を出した事があったんだけど、何の返事もなくて届いてるかどうかも心配で…。ルカくんになら信頼して預けられるから、お願いしたいの。」
「僕がレジデンスに行けるのは…まだまだ先だと思うけど…。」
「それでもいいの!お願い出来ないかな…?」
彼女の必死な訴えを、僕は断る事が出来なかった。
彼等に別れの挨拶を済ませ、ヴェラと合流し、次なる水晶を求めてコルトを後にした。
宿屋で部屋を借り、水晶の入った袋をテーブルの上に置いた。
ララとタクトの2人とは1度別れ、翌朝広場で合流して再び水晶を探しに行く事になった。
「これを使って魔法の練習をしようと思ってな。」
「え…。」
「…今、あからさまに嫌がったな?」
「い、いやぁ?そんな事ない…よ…?」
「なら問題ないな。始めよう。」
「うぅ…。」
以前は魔法を扱う事が出来なかったが、ルナと出会った頃からいつの間にか使えるようになっていた。しかし、魔法に慣れていないせいか、あまり得意ではない。元はステラという事もあり、魔力の量は多いが加減が難しい。まさに、宝の持ち腐れ状態だった。
彼女の説明を聞きながら、吸血鬼が薬を作る時などに使われる合成魔法“アルキミア”の練習が始まった。
「ちょっと…。水晶玉を作れって言ったのに、なんで水晶が粉々になるのよ…。」
「ご、ごめん…。」
あれからいくつの水晶を粉に変えただろうか。何度やっても上手くいかず、床に水晶の粉が溜まる一方だった。
「力が強過ぎるのも問題ね。抑制する為の装飾品が必要かしら…。」
「え!そんなものも作れるの?」
「昔作った事があるわ。色々試してみたけど、1番効果があったのは首輪ね。」
「く、首輪はちょっと…。」
「なら自力で制御しなさい。」
「………はい。」
それからしばらく魔法の練習は続いたが、全ての水晶を粉々に砕く結果となってしまった。
「おはようございますルシュ様。」
「ああ。おはようタクト。」
「ルカくん大丈夫…?なんだか疲れてるみたいだけど…。」
「だ、大丈夫!そんな事ないよ!」
「時間が惜しい。早く頂上へ向かおう。」
昨日同様、氷山の頂上付近で水晶の採掘を始めた。採掘と休憩を繰り返し、昇ったばかりだった太陽は僕達の真上にまで到達していた。
「あのー…ルシュ様。昨日の水晶はどうしたんですか?」
「あーあれか?あれはルカが、粉々に砕いた。」
「えっ。まさか…素手でですか…?」
「そんなわけあるか。魔法に失敗したから、そうなっただけだ。」
「なるほど…そうなんですね。」
タクトはその話を聞いて、苦笑いを浮かべた。
「ちょ、ちょっとヴェラ!そんな事タクトに言わなくてもいいじゃん…!」
「この方が、お前ももっと頑張るんじゃないかと思ってな。」
「え?それってどういう…」
「ルカくんの気持ちわかるなぁ…。初めの頃は、私も全然魔法を使えなかったから…。」
「ララはすごいよね。頑張って勉強して、上級吸血鬼になっちゃうんだもん。」
「凄くなんてないよ。みんなに支えてもらって、やっとここまでこれたって感じかな…。」
「そういえば、他のみんなはどうなの?レミリアとアレクには会ったから、2人は上級吸血鬼になったって知ってるけど…。」
「ユイちゃんも上級吸血鬼になったよ。ユノちゃんは上級クラスのままだけど、ツーくんとユーくんはさらに昇級して、幹部になっちゃったの。」
「え?幹部って事は…レジデンスにいるの?」
「ううん。レジデンス以外にも幹部専用の建物はあるから、そっちに配属になったよ。確か…イリスシティアの南の方じゃなかったかな?」
「そっか。やっぱりツヴェルとユーリはすごいや…。」
「そろそろお喋りはやめて、手を動かさないか?また日が暮れては困るからな。」
「そ、そうだね。わかった…!」
作業を再開して目の前にある岩を砕いていると、少し離れた所で作業していたララが大きな声を上げた。
「ルシュ様!これじゃないですか…!?」
彼女の手には他の水晶と比べ、明らかに輝きの違う大きな水晶が握られていた。
「確かめたいから、それを持ってこっちに来てくれ。」
「は、はい…!」
ヴェラに呼ばれたララは、小走りで僕の横を通り過ぎて行った。しかし、すれ違った瞬間、彼女の手に握られていた水晶が地面に転がり落ちた。
「ララ!?」
その場に倒れた彼女を慌てて抱き起こすと、口の端から血を流して気絶していた。
「ララ…!」
「おい!ララは素手でこれに触ったのか!?」
「ううん!ちゃんと手袋をしてるよ!?」
側にやってきたヴェラが地面に膝をつき、彼女の身体に触れて様子を伺い始めた。タクトは彼女の後ろに立ち、その様子をただ呆然と眺めている。
「原因は水晶しか考えられない…。手袋をしていたはずなのに何故…」
「そんな事よりララはこのままで大丈夫なの!?早く下山して、治療した方がいいんじゃ…!」
「その前に応急処置が必要だ。だが…今は薬の手持ちがない…。失った血を何とか補う方法は…」
「お、俺、いつも自分が飲んでいる薬なら持ってます!これで血の生成を増やせば…」
「今の状態のララにそれは無理だ。副作用に耐えられない。」
「なら僕が血を分けるよ!」
「え…でもそれじゃあルカが…」
「それしかないか…頼んだぞルカ。」
「うん!」
「容態が安定したら急いで下山する。タクトは荷物をまとめて、準備を整えてくれ。」
「わかりました…!」
「…ん。」
「ララ…!」
「タック…?あれ?私…」
「ルシュ様!ララが目を覚ましました!」
ララを家に運び込み、日が沈んで外が暗くなり始めた頃、彼女はようやく目を覚ました。
「もう大丈夫そうだな。大事を取って明日1日休むといい。」
「よかった…これで一安心だね。」
「ありがとうございますルシュ様…。」
「礼ならルカに言うべきだ。あいつの血がなかったら、お前をここまて連れて来る事すら出来なかったからな。」
「え?ルカくんが…血を分けてくれたって事?…ルカくんは、大丈夫なの?」
「た、大した事ないよ!元々量は多いし、余ってたから…。」
「ありがとうルカ。俺はあの場にいただけで…何も出来なかった…。ララが助かったのは、君のおかげだよ。本当にありがとう。」
「タクト…。」
「ララの看病はお前に任せる。私達は宿屋に戻るぞ。」
「う、うん。」
宿屋に戻って来ると、身につけたブレスレットに視線を向けた。中央に埋め込まれた宝石は、ララに血を分けた時は紫色だったがもう既に赤色へと変化していた。本来ならば紫色を保ち続けなければならないのだが、いくら血を消費してもすぐに増えてしまい、赤色の状態のまま放っておく事が多くなっていた。
「お前の血の多さは羨ましい限りだな。」
「僕は多過ぎて困ってるんだけど…。」
「あるものは使えばいい。増やすのは大変だか、減らすのは簡単だ。」
「ところで…ララが倒れた原因って、結局なんだったの?」
「おそらく、耀水晶の属性の力が強過ぎて、手袋をしただけでは防ぎきれなかったんだろう。」
「吸血鬼の命を奪いかねない水晶が、どうして氷山にあったんだろうなぁ…。」
「そんな事は私にもわからない。今日は何かと疲れる1日だったな。早めに休むとしよう。」
「そうだね。」
ベッドに向かって歩き出すと、彼女は僕の前に立ちはだかり、水晶の入った袋を突き出した。
「…お前は元気だろう?せっかく血が余っているのだから、魔法の練習をしなさい。」
「えぇ!?こんな時まで練習しなきゃいけないの!?」
「魔法というものは、何度も反復して行う事で身につくものだ。水晶なら沢山ある。遠慮する必要はないぞ?」
「遠慮してるつもりはないよ!はぁ…。これもルナの理想の為に、通らなくちゃいけない道か…まだまだ先が遠いなぁ。」
色々あったものの、何とか目的の耀水晶を手に入れた僕達は翌朝の出発に向けて、それぞれのタイミングで休息を取る事にした。
「あ、おはようタクト!」
翌朝、ララの様子が気になった僕は出発前に彼女の家を訪ねた。玄関で出迎えてくれたタクトが家の中に僕を招き入れ、彼の案内でリビングに通された。
「その…体調は大丈夫?」
「全然平気!ヴェラに、お前は元気だろ?って言われて魔法の練習をさせられたくらいだよ…。」
「あはは。…ルカが羨ましいよ。ルシュ様に手をかけて貰えるほどの才能があるんだから。」
「これは僕の才能じゃないよ。ルナに才能があったから、僕もたまたまそうなっただけで…。」
「…ルナが生きてるかもしれないって、ルカは信じてるんだよね?」
「うん。」
「何か、そう思う根拠はあるの?」
「根拠って言える程じゃないけど…ルナが死んだ事を知ってるのはヴェラ1人だけなんだ。僕がルナの話をしようとすると、妙に強く否定したり、無理矢理話題を変えようとしてる気がして…。疑いたくは無いけど、ヴェラの話にはどこか違和感があるような気がするんだ。」
「ルシュ様が、嘘をついてるって事…?」
「僕はそう思ってる。」
「…俺も、ルナが生きてるって信じてみるよ。そう思いたいだけかもしれないけど、何もせずに諦めるよりはマシかなって思ったんだ。」
「…ありがとうタクト。」
「ううん。ルカを見てたら自然とそういう気持ちになれたんだ。…ごめんルカ。この間は君に、傷付けるような事を言ってしまって…。」
「気にしてないよ!タクトがルナの事を大切に思ってくれてるの、わかってるから。」
「ありがとう…。あ、そうだ…ララにも会っていく?さっき起きた所だから、まだ部屋にいると思うよ。」
「じゃあそうするね!」
その場に彼を残し、階段を上って彼女の部屋へ向かった。
「あ、ルカくん…いらっしゃい!ごめんねこんな格好で…」
彼女は寝間着姿に上着を羽織り、ベッドの上で身体を起こした。
「そのままでいいのに…!今日は安静にっていう話だったもんね。」
「えっと…今日出発するんだよね?もう少しゆっくりすればいいのに…。」
「僕もそうしたい所だけど…レジデンスに行かない事には、何も始められないからね。出来るだけ急ぎたいんだ。」
「そっか…。あの…ルカくん。実はお願いしたい事があるんだけど…。」
「何?」
彼女はベッドの脇にある机の引き出しから、1枚の封筒を取り出した。
「これを、フランくんに渡して欲しいの。」
「え、でも…。こういうのは、直接渡した方がいいんじゃ…」
「私もそうしたいんだけど、全然会えそうにないから…。それと、何度かレジデンス宛に手紙を出した事があったんだけど、何の返事もなくて届いてるかどうかも心配で…。ルカくんになら信頼して預けられるから、お願いしたいの。」
「僕がレジデンスに行けるのは…まだまだ先だと思うけど…。」
「それでもいいの!お願い出来ないかな…?」
彼女の必死な訴えを、僕は断る事が出来なかった。
彼等に別れの挨拶を済ませ、ヴェラと合流し、次なる水晶を求めてコルトを後にした。
0
あなたにおすすめの小説

【魔女ローゼマリー伝説】~5歳で存在を忘れられた元王女の私だけど、自称美少女天才魔女として世界を救うために冒険したいと思います!~
ハムえっぐ
ファンタジー
かつて魔族が降臨し、7人の英雄によって平和がもたらされた大陸。その一国、ベルガー王国で物語は始まる。
王国の第一王女ローゼマリーは、5歳の誕生日の夜、幸せな時間のさなかに王宮を襲撃され、目の前で両親である国王夫妻を「漆黒の剣を持つ謎の黒髪の女」に殺害される。母が最後の力で放った転移魔法と「魔女ディルを頼れ」という遺言によりローゼマリーは辛くも死地を脱した。
15歳になったローゼは師ディルと別れ、両親の仇である黒髪の女を探し出すため、そして悪政により荒廃しつつある祖国の現状を確かめるため旅立つ。
国境の街ビオレールで冒険者として活動を始めたローゼは、運命的な出会いを果たす。因縁の仇と同じ黒髪と漆黒の剣を持つ少年傭兵リョウ。自由奔放で可愛いが、何か秘密を抱えていそうなエルフの美少女ベレニス。クセの強い仲間たちと共にローゼの新たな人生が動き出す。
これは王女の身分を失った最強天才魔女ローゼが、復讐の誓いを胸に仲間たちとの絆を育みながら、王国の闇や自らの運命に立ち向かう物語。友情、復讐、恋愛、魔法、剣戟、謀略が織りなす、ダークファンタジー英雄譚が、今、幕を開ける。

剣ぺろ伝説〜悪役貴族に転生してしまったが別にどうでもいい〜
みっちゃん
ファンタジー
俺こと「天城剣介」は22歳の日に交通事故で死んでしまった。
…しかし目を覚ますと、俺は知らない女性に抱っこされていた!
「元気に育ってねぇクロウ」
(…クロウ…ってまさか!?)
そうここは自分がやっていた恋愛RPGゲーム
「ラグナロク•オリジン」と言う学園と世界を舞台にした超大型シナリオゲームだ
そんな世界に転生して真っ先に気がついたのは"クロウ"と言う名前、そう彼こそ主人公の攻略対象の女性を付け狙う、ゲーム史上最も嫌われている悪役貴族、それが
「クロウ•チューリア」だ
ありとあらゆる人々のヘイトを貯める行動をして最後には全てに裏切られてザマァをされ、辺境に捨てられて惨めな日々を送る羽目になる、そう言う運命なのだが、彼は思う
運命を変えて仕舞えば物語は大きく変わる
"バタフライ効果"と言う事を思い出し彼は誓う
「ザマァされた後にのんびりスローライフを送ろう!」と!
その為に彼がまず行うのはこのゲーム唯一の「バグ技」…"剣ぺろ"だ
剣ぺろと言う「バグ技」は
"剣を舐めるとステータスのどれかが1上がるバグ"だ
この物語は
剣ぺろバグを使い優雅なスローライフを目指そうと奮闘する悪役貴族の物語
(自分は学園編のみ登場してそこからは全く登場しない、ならそれ以降はのんびりと暮らせば良いんだ!)
しかしこれがフラグになる事を彼はまだ知らない

SSSレア・スライムに転生した魚屋さん ~戦うつもりはないけど、どんどん強くなる~
草笛あたる(乱暴)
ファンタジー
転生したらスライムの突然変異だった。
レアらしくて、成長が異常に早いよ。
せっかくだから、自分の特技を活かして、日本の魚屋技術を異世界に広めたいな。
出刃包丁がない世界だったので、スライムの体内で作ったら、名刀に仕上がっちゃった。

【完結】異世界で魔道具チートでのんびり商売生活
シマセイ
ファンタジー
大学生・誠也は工事現場の穴に落ちて異世界へ。 物体に魔力を付与できるチートスキルを見つけ、 能力を隠しつつ魔道具を作って商業ギルドで商売開始。 のんびりスローライフを目指す毎日が幕を開ける!
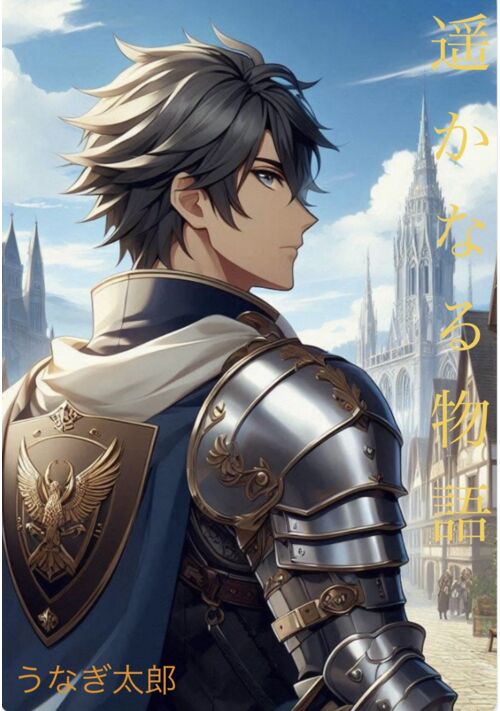
遥かなる物語
うなぎ太郎
ファンタジー
スラーレン帝国の首都、エラルトはこの世界最大の都市。この街に貴族の令息や令嬢達が通う学園、スラーレン中央学園があった。
この学園にある一人の男子生徒がいた。彼の名は、シャルル・ベルタン。ノア・ベルタン伯爵の息子だ。
彼と友人達はこの学園で、様々なことを学び、成長していく。
だが彼が帝国の歴史を変える英雄になろうとは、誰も想像もしていなかったのであった…彼は日々動き続ける世界で何を失い、何を手に入れるのか?
ーーーーーーーー
序盤はほのぼのとした学園小説にしようと思います。中盤以降は戦闘や魔法、政争がメインで異世界ファンタジー的要素も強いです。
※作者独自の世界観です。
※甘々ご都合主義では無いですが、一応ハッピーエンドです。

転生貴族の領地経営〜現代日本の知識で異世界を豊かにする
初
ファンタジー
ローラシア王国の北のエルラント辺境伯家には天才的な少年、リーゼンしかしその少年は現代日本から転生してきた転生者だった。
リーゼンが洗礼をしたさい、圧倒的な量の加護やスキルが与えられた。その力を見込んだ父の辺境伯は12歳のリーゼンを辺境伯家の領地の北を治める代官とした。
これはそんなリーゼンが異世界の領地を経営し、豊かにしていく物語である。

転生してモブだったから安心してたら最恐王太子に溺愛されました。
琥珀
恋愛
ある日突然小説の世界に転生した事に気づいた主人公、スレイ。
ただのモブだと安心しきって人生を満喫しようとしたら…最恐の王太子が離してくれません!!
スレイの兄は重度のシスコンで、スレイに執着するルルドは兄の友人でもあり、王太子でもある。
ヒロインを取り合う筈の物語が何故かモブの私がヒロインポジに!?
氷の様に無表情で周囲に怖がられている王太子ルルドと親しくなってきた時、小説の物語の中である事件が起こる事を思い出す。ルルドの為に必死にフラグを折りに行く主人公スレイ。
このお話は目立ちたくないモブがヒロインになるまでの物語ーーーー。

ハズレ職業の料理人で始まった俺のVR冒険記、気づけば最強アタッカーに!ついでに、女の子とVチューバー始めました
グミ食べたい
ファンタジー
現実に疲れた俺が辿り着いたのは、自由度抜群のVRMMORPG『アナザーワールド・オンライン』。
選んだ職業は“料理人”。
だがそれは、戦闘とは無縁の完全な負け組職業だった。
地味な日々の中、レベル上げ中にネームドモンスター「猛き猪」が出現。
勝てないと判断したアタッカーはログアウトし、残されたのは三人だけ。
熊型獣人のタンク、ヒーラー、そして非戦闘職の俺。
絶体絶命の状況で包丁を構えた瞬間――料理スキルが覚醒し、常識外のダメージを叩き出す!
そこから始まる、料理人の大逆転。
ギルド設立、仲間との出会い、意外な秘密、そしてVチューバーとしての活動。
リアルでは無職、ゲームでは負け組。
そんな男が奇跡を起こしていくVRMMO物語。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















