3 / 43
一部
第3話:転生特典は『無敵』で!
しおりを挟む
その日、日本の首都圏の片隅に位置する埼玉県川口市。無数の人々が暮らし、それぞれの人生を営むこの街の、ありふれたアパートの一室は、まるで世界の喧騒から切り離されたかのように、時が止まったかのような静寂に包まれていた。
季節は六月。長く続いた陰鬱な雨がようやく止み、梅雨の中休みが訪れた、束の間の晴れ間だった。しかし、その晴れ間は穏やかなものではない。分厚い灰色の雲の隙間から突き刺すように差し込む太陽の光は、まるで真夏を先取りしたかのような獰猛さでアスファルトをじりじりと炙り、逃げ場のない熱波を地上へと送りつけていた。部屋の窓は開け放たれているものの、流れ込んでくるのは熱を含んだ湿った風ばかりで、室内の空気は澱のように重く、息苦しいほどの熱気が満ちていた。
この劣悪な環境の中心に、佐藤健太(さとうけんた)、21歳はいた。三流大学に籍を置きながらも、その実、休学中の無為な日々を送る彼は、パンツ一丁という、人類の叡智が長い歴史の果てに到達した最も効率的かつ原始的な避暑スタイルを実践し、もはや彼の身体の一部と化した万年床の上で、意識の混濁した惰眠を貪っていた。エアコンを起動させようにも、その旧式のリモコンは部屋の混沌とした雑然さの中に完全に姿をくらまし、探す気力すら湧いてこない。
「……ん……ぅ……」
喉の奥が焼け付くような渇きを覚え、健太の意識は浅い眠りのぬるま湯から、ゆっくりと、しかし確実に浮上を始めた。重い瞼をこじ開けると、ぼやけた視界に、見慣れた天井の染みが映る。開けっ放しの窓からは、生ぬるい風が吹き込み、汗ばんだ肌を不快に撫でていく。その風は、様々な音の断片を運んできた。近所の公園で甲高い声を上げて遊ぶ子供たちのはしゃぎ声。どこかの家庭から漏れ聞こえてくる、昼のワイドショーと思しきタレントたちの空々しい笑い声。そして、気の早い一匹の蝉が、まるで己の短い命を削り尽くすかのように、ジリジリと空気を震わせる鋭い鳴き声を、健太の鼓膜にぼんやりと届けていた。
健太のアパートの、人が一人立てばそれで満員となるような小さなベランダには、実家から帰省した際に母親が「部屋に緑がないと心が荒むから」という一方的な善意で無理やり置いていった観葉植物の鉢植えがあった。その艶のある濃緑の葉が、風を受けるたびに「さわさわ」と乾いた音を立てて微かに揺れている。健太はその音を聞くともなしに聞きながら、億劫そうに上半身を起こした。軋む身体が、運動不足を如実に物語っている。
部屋の中は、彼の人生そのものを完璧に体現したかのように、凄まじい混沌に満ちていた。読み終えられ、あるいは読むのを途中で放棄された漫画雑誌が、ジェンガさながらの危ういバランスでタワーを形成し、いつ崩れてもおかしくない威圧感を放っている。床には、飲み干されたペットボトルや、カフェインで彼の覚醒を無理やり支えたエナジードリンクの空き缶が、まるで地雷原のように散らばっていた。そして、昨日食べたのであろうコンビニ弁当のプラスチック容器からは、微かに、しかし確実に不穏な酸っぱい匂いが漂い始めており、小さな羽虫がその周りを飛び交っている。
壁には、彼が心の底から愛してやまないアニメの美少女キャラクターのポスターが数枚、画鋲で無造作に留められていた。そのキャラクターたちは、それぞれに理想化された完璧な笑顔で、この惨状をただ静かに見つめている。パソコンモニターの周囲には、同じキャラクターたちの精巧なフィギュアが、まるで祭壇の守護神であるかのように誇らしげに並べられていた。現実の彼には決して向けられることのない、絶対的な肯定の視線がそこにはあった。
西に傾きかけた太陽が、古びたカーテンの隙間から、一本の鋭い光の筋となって室内へと差し込んでいた。その光は、空気中に舞う無数の埃を、まるでスポットライトのようにキラキラと照らし出し、その一筋だけが、幻想的な銀河のように見えた。その非現実的なほどに美しい光景と、足の踏み場もない部屋の惨状との圧倒的なギャップに、健太は自嘲めいた乾いた笑みを漏らした。
「……水…飲も…」
声に出した言葉は、誰に届くでもなく、澱んだ空気の中に虚しく溶けていく。重い足取りで冷蔵庫に向かい、ドアを開ける。ブーンという低いモーター音と共に、生ぬるい庫内の光が彼の顔を照らした。そこにあったのは、ほとんど空になった二リットルの麦茶パックと、いつ買ったのか記憶もおぼろげで賞味期限が極めて怪しい卵が数個、そして隅の方で忘れ去られたチューブのわさびだけだった。健太は小さく舌打ちし、仕方なくキッチンの水道の蛇口をひねる。ごぼごぼという音と共に吐き出された、カルキ臭い常温の水道水。それを両手で受け、一気に呷る。渇ききった喉を液体が通り過ぎていく感覚は、この堕落しきった生活の中で健太が感じられる、数少ない「生きている実感」の一つだった。
健太のこれまでの人生は、「可もなく不可もない」という言葉ですら上等に思えるほど、驚くほどに平凡で、退屈なものだった。地方のそこそこの進学校に入ったものの、周囲の熱意についていけず、特に打ち込めるものも見つからないまま、ただ惰性で日々を過ごした。将来の夢も、明確な目標もない。だから、皆が行くからというだけの理由で、偏差値に見合った三流大学に進学した。しかし、期待していたキャンパスライフは、パンデミックの影響でオンライン授業が中心となり、希薄な人間関係とモニター越しの虚しい講義に、彼は早々に嫌気が差してしまった。そして、大学に入って一年も経たないうちに休学届を提出し、現在に至る。
今の彼の生活を支えているのは、週に三日、深夜に入るコンビニエンスストアのアルバイトだけだ。そこで稼いだ最低限の金で食いつなぎながら、空いた時間のほとんど全てを、アニメ鑑賞とソーシャルゲームに費やしている。画面の中では、彼は世界を救う伝説の勇者にも、強大な魔王を従える孤高の賢者にもなれた。現実ではろくに話したこともないような、可憐な美少女たちに囲まれ、かけがえのない仲間たちと熱い絆で結ばれ、壮大な冒険を繰り広げる。しかし、ログアウトボタンを押せば、そこにあるのは、この六畳一間の薄汚い部屋と、何一つ成し遂げていない、空っぽで無力な自分だけだ。その落差が、彼をさらに仮想世界へと没入させていた。
「……はぁ。なんか面白いこと、起きねーかなぁ……」
その呟きは、彼の心の底からの切実な願いだった。誰かに聞かせるつもりなど毛頭ない、純粋な独り言。彼は椅子に腰かけると、慣れた手つきでパソコンの電源を入れた。ファンが唸りを上げ、モニターが光を放つ。目的は一つ。昨日から鳴り物入りでサービスが始まったばかりの、最新型フルダイブVRMMORPG――『エリュシオン・オンライン』だ。
仮想空間でありながら、視覚や聴覚だけでなく、触覚、味覚、嗅覚といった五感の全てを完全に再現するという、まさに夢のようなゲーム。その革新的な技術は世界中で話題となり、健太もまた、その宣伝映像に心を奪われた一人だった。コンビニの深夜バイトで稼いだ給料のほとんどを、このゲームをプレイするためだけの専用ヘッドギアにつぎ込んだのだ。借金こそしなかったが、貯金は完全に底をついた。
「これさえあれば、俺の人生も少しはマシになる…はずだ」
後悔はなかった。むしろ、この投資こそが、停滞した自分の人生を動かす唯一の起爆剤だと信じていた。ヘッドギアを手に取り、ゆっくりと頭に装着する。フィット感を確かめ、起動スイッチを入れると、視界が穏やかな暗闇に包まれ、心地よい電子音が鼓膜を優しく震わせた。
『―――ようこそ、エリュシオンへ。あなたの魂を、新たな世界へと導きます―――』
無機質でありながら、どこか荘厳さを感じさせるシステム音声と共に、健太の意識は現実の肉体から引き剥がされ、仮想のデータへとダイブしていく感覚に襲われた。これから始まる未知の冒険に、彼の心臓は期待で大きく高鳴った。異世界、圧倒的なチート能力、そして美少女たちとのハーレム。彼の抑圧された欲望のすべてが、そこには詰まっているはずだった。現実の自分ではない、理想の自分になれる場所が、すぐそこにある。
その時だった。
外の空が、一瞬、ありえないほど強く輝いた。まるで、空全体が巨大な閃光弾になったかのように。先ほどまでやかましく鳴いていた蝉の声が、まるでスイッチを切られたかのように、ぴたりと止んだ。
健太の意識は、まだ仮想空間と現実の狭間を、曖昧に漂っていた。そのため、彼はまるで幽体離脱でもしたかのように、神の視点にも似た奇妙な感覚で、自分の部屋の窓の外が、真昼の太陽さえ霞んでしまうほどの純白の光に包まれたのを、はっきりと認識していた。
「え?」
それが、佐藤健太という人間の、最後の言葉だった。
次の瞬間、天から落ちてきた一本の雷が、まるで神が気まぐれに下界を指さしたかのように、日本国埼玉県川口市にある彼のアパートの、彼の部屋だけを、恐ろしいほど正確に、ピンポイントで貫いた。
轟音は、なかった。爆発も、衝撃もなかった。
ただ、全ての物質が、部屋も、家具も、彼が愛したフィギュアも、そして彼自身も、圧倒的な光の奔流に飲み込まれ、原子レベルにまで分解されて消滅していく。彼の存在は、彼の退屈な日常は、彼の俗っぽくも純粋な欲望は、コンマ一秒にも満たない、認識すらできないほどの短い時間の中で、この世界から完全に、一片の痕跡も残さずに消え去った。
***
健太が次に目を覚ました時、彼は、何もない場所にいた。
上も、下も、右も、左も、全ての方向が等しく、どこまでも続く純白の世界。床があるのか、それとも宙に浮いているのかさえ分からない。空気の流れはなく、音もなく、匂いもない。完全な無の世界。自分の身体を見下ろせば、見慣れた手足が存在している。だが、試しにその手で頬に触れてみても、何の感触もなかった。五感そのものが、この空間の物理法則から除外されているかのようだった。
「……どこだ、ここ…?ゲームの、中…か?」
声は出せた。しかし、その声が空気を震わせる感覚はなく、自分の頭蓋骨の中で直接響いているような、ひどく奇妙な感覚だった。混乱し、途方に暮れて、その場で意味もなくくるくると回り始めた彼の背後から、不意に、気の抜けたような、それでいてどこか丁寧な声がした。
「あー、どうも。佐藤健太さん、で、お間違いないでしょうか?」
健太は、文字通り心臓が喉から飛び出すかと思うほど驚いて、勢いよく振り返った。
そこに立っていたのは、一人の男だった。着古されてくたびれた印象のグレーのスーツに、少し曲がったネクタイ。寝癖のついたボサボサの髪に、目の下にはまるで墨で描いたかのような深い隈が刻まれている。手には使い古された革の鞄を提げており、その姿は、連日の徹夜明けで重要な営業先に向かう途中といった風情の、しがないサラリーマンにしか見えなかった。
ただ一つ、決定的に常識外れな点を挙げるならば、彼の背中からは、純白の、それはもう見事なまでに巨大な天使の翼が、本人の疲れた雰囲気とは不釣り合いに、申し訳なさそうに生えていた。
「……あんた、誰だ?その格好…コスプレ…?」
混乱の極みにあった健太が絞り出したのは、そんな間の抜けた質問だった。
「いえ、コスプレではございません。わたくし、こういう者でして」
男は疲れた顔で薄く笑うと、スーツの内ポケットから、年季の入った名刺入れを取り出し、慣れた手つきで一枚の名刺を健太に差し出した。健太は反射的にそれを受け取る。そこには、神々しい金色の箔押し文字で、こう書かれていた。
【天界管理局 対人部 第三課 担当:神(カミ)】
「……かみ?」
健太は、名刺と男の顔を交互に見比べながら、呆然と呟いた。
「はい、神です。一応、このあたりの次元を管理監督させていただいております」
男――神は、深々と、それはもう完璧な角度で頭を下げた。その完璧な四十五度の角度は、長年の営業活動で体に染み付いたものに違いなかった。そして、彼は顔を上げると、さらに深く、今度は土下座でもせんばかりの勢いで再び頭を下げた。
「この度は、まことに、まことに、申し訳ございませんでしたッ!」
「は? え? なにが?」
「わたくしの、完全なる、100パーセントの不手際によりまして、佐藤健太様を、本来の寿命よりおよそ60年ほど早く、死なせてしまいました!」
神は、顔を上げないまま絶叫した。健太は、ぽかんと口を開けて、その常軌を逸した光景をただ眺めていた。
死んだ? 俺が? この、うだつの上がらないサラリーマンみたいな神様の、せいで?
「いやいやいや、意味わかんないんだけど。俺、VRゲームやってて、そしたら光が…」
「ええ、全て存じております。あの時、わたくし、長引く業務の疲れから少々くしゃみをしてしまいまして…」
「くしゃみ?」
「はい。そのくしゃみの拍子にですね、天界の気象コントロールシステムに、ほんの、ほんの僅かですが神力が漏れ出してしまいまして…。それがですね、不運にも雷という形に変換され、これまた不運にも佐藤様のいらっしゃる座標にピンポイントで…その…大変申し訳ない結果を招いてしまった次第でございます…」
神は、非常に言いにくそうに、言葉を濁しながら説明した。
つまり、要約すると、神のくしゃみが原因で発生した雷に直撃されて俺は死んだ、と。
あまりにも馬鹿馬鹿しく、理不尽極まりない死因に、健太は怒る気力さえ一瞬で失せてしまった。その場にへなへなとうずくまり、両手で頭を抱える。
「マジかよ……俺の人生、神のくしゃみエンドかよ……。せめてトラックに轢かれるとか、通り魔に刺されるとか、もうちょい異世界転生の王道っぽい死に方させてくれよ……」
「面目次第もございません……。穴があったら入りたい、とはまさにこのことで…」
しばらくの間、健太はうなだれていたが、やがてゆっくりと顔を上げた。彼の目には、先ほどまでの諦観に満ちた光ではなく、これまで見せたことのない、ギラギラとした鋭い光が宿っていた。それは絶望の色ではなかった。むしろ、この突拍子もない、ありえない状況を、最大限に利用してやろうという、実にしたたかで計算高い光だった。
「…まあ、いいや。死んじまったもんは仕方ねえ」
「お、おお…!なんと、お心の広い…!仏、いや神の目から見ても、貴方様は仏のようです…!」
「で? タダで死んだまんま、ってことはないよな?」
健太は、下卑た笑みを隠そうともせず、にやりと口角を吊り上げて神を見上げた。
「なんか、あるんだろ? お詫び、的なやつが。迷惑料? 慰謝料?」
その露骨な要求に、神は一瞬たじろいだが、すぐに心底安堵したように大きく息をついた。話の通じる相手で良かった、と顔に書いてある。
「は、はい!もちろんでございます!本来であれば、記憶を消去の上、速やかに輪廻の輪にお戻りいただくという流れになるのですが、今回は完全にこちらの過失ですので、特別措置を取らせていただきます」
神は、ぱん、と軽快に手を叩いた。すると、何もない純白の空間に、巨大なプレゼンテーション用のスクリーンのようなものが突如として現れた。
「佐藤様には、二つのオプションがございます。一つは、現在の記憶を持ったまま、現在の地球の別の赤ん坊として、裕福な家庭などを選んで生まれ変わる。もう一つは――」
スクリーンに、鬱蒼とした森、雄大に空を舞うドラゴン、尖った耳を持つ美しいエルフ、屈強なドワーフといった、健太がゲームやアニメでさんざん見てきたファンタジーの世界の映像が次々と映し出された。
「全く別の世界、いわゆる『異世界』に、現在の肉体と記憶を維持したまま転生する、というものです。もちろん、こちらをお選びいただいた場合、お詫びの印としまして、何か一つ、お好きな『特典(チート能力)』を授与させていただきますが…いかがいたしましょう?」
健太の心が、沸騰した。
異世界。チート能力。
それは、彼が薄汚い六畳一間で、万年床の上で、来る日も来る日も夢想し、渇望していたもの、そのものだった。
「異世界! 絶対に異世界でお願いします!」
彼は、神の言葉が終わるか終わらないかのうちに、食い気味に絶叫した。
「承知いたしました。では、特典の方ですが、どのような能力をご希望で…」
「よっしゃー!」
神の問いかけを遮り、健太はここぞとばかりにまくし立て始めた。彼の欲望が、堰を切ったように溢れ出す。
「まず、絶対死なないやつ!不老不死で!病気にも一切ならないし、どんな猛毒を飲んでも平気なやつ!」
「は、はあ…不死性と状態異常無効、ですね…」
「あと、最強の魔法!指パッチン一発で山とか大陸とか吹き飛ばせるレベルの超攻撃魔法!」
「あ、あの、世界のバランスというものがございますので、あまり大規模なものは…」
「それから、どんな攻撃も全く効かない無敵の身体!ドラゴンのブレスを浴びても『あー、ちょっとあったかいな』くらいで済むやつ!」
「ええと、それは物理・魔法ダメージ完全無効という解釈でよろしいでしょうか…」
「当たり前だ!もちろん、女にモテモテになるカリスマ性も必須だよな!ただ道を歩いてるだけで、エルフとか獣人とか王女様とか、あらゆる種族の美少女が寄ってきてハーレムを形成できるくらいのやつ!」
「そ、それは因果律への干渉があまりにも大きすぎます!個人の感情に直接作用するような権限はわたくしには…!」
神は、健太の留まることを知らない欲望の奔流を前に、額から滝のような脂汗を流し、その顔色はどんどん青ざめて土気色になっていく。
「お客様!お客様!少々お待ちください!ご要望が多すぎて、天界の『ご予算』を大幅に、というか天文学的にオーバーしてしまいます!そんな前例はございません!」
「うるせえ!俺はあんたのくしゃみで死んだんだぞ!こっちは被害者だ!これくらい要求するのは当然の権利だろ!」
「そ、それはそうなのですが、しかし、これを認めてしまうとわたくしの査定に響きまして…!始末書どころでは済まない事態に…!」
人と神の、実に低レベルな押し問答は、しばらくの間、無音の空間に虚しく響き続けた。
最終的に、完全に理詰めで追い込まれ、頭を抱えてその場にうずくまった神が、震える声で一つの妥協案を提示した。
「……分かりました。もう、分かりましたから…。でしたら、お客様のご要望の根幹を成す部分、これら全てを、一つの能力に集約する形で付与させていただく、というのはいかがでしょうか…?」
「一つに?」
「はい。いわば、『概念的な無敵』とでも申しましょうか…」
神は、どこからともなく一枚の企画書のような羊皮紙を取り出し、咳払いをしてから、必死の形相で説明を始めた。
「佐藤健太様の存在そのものを、この宇宙における絶対的な『確定事象』として定義し直します。これにより、いかなる物理的、魔法的、精神的、因果的な干渉も、佐藤様に到達する前に『なかったこと』になります。攻撃されれば、その攻撃という事象自体が無に還る。毒を飲んでも、毒が毒としての性質をその場で失う。老化という時間の流れによる事象も、死という生命活動の停止という結果も、佐藤様には一切適用されません。つまり――」
神は、ごくりと喉を鳴らし、最後の切り札を提示するように言った。
「――何があっても、絶対に死なないし、傷つかないし、弱らない。『無敵』です。これならば、先ほどのご要望のほとんどをカバーできるかと存じますが…」
健太は、最初、口を半開きにしてその壮大な説明を聞いていたが、やがてその意味を完全に理解し、その顔に満面の、最高の笑みを浮かべた。
「…それだ! 最高じゃねえか! それで頼む!」
「……はぁ。承知、いたしました…」
神は、何かとんでもなく取り返しのつかないことをしてしまった、という後悔に満ちた顔で、深すぎるため息をついた。
***
「では、これより、特典能力『絶対不干渉(パーフェクト・ワールド)』を、佐藤様の魂にインストールいたします」
神が疲労困憊の様子で指を鳴らすと、健太の身体が淡い金色の光に包まれた。温かいような、冷たいような、これまで感じたことのない不思議な感覚が全身を駆け巡る。脳内に、人間には到底理解不能な膨大な量の情報が激流のように流れ込み、魂そのものが、より高次の存在へと強制的に書き換えられていくような、全能感にも似た圧倒的な感覚に支配された。
数秒後、光が収まると、身体が以前よりも遥かに軽く、そして何よりも「確かなもの」になった気がした。世界の全てが不確定な中で、自分だけが絶対的な存在であるかのような、奇妙な安定感があった。
「さて、と。転生先のワールドですが…いくつか候補はございますが、どこかご希望は?」
「んー、やっぱ王道の剣と魔法の世界だよな。エルフとかドワーフとか獣人とか、そういうのが普通にいる感じの」
「さようでございますか。でしたら、こちらの『アースガルド』という世界がよろしいかと。ちょうど今、魔王が率いる魔王軍と、人間諸国を中心とした人間連合が大規模な戦争を繰り広げておりまして、非常にこう…ファンタジー分が濃厚でございます」
「戦争? なんかめんどくさそうだな」
「まあ、今の佐藤様でしたら、戦争など蚊に刺されたようなものでしょう。あるいは、蚊に刺されるという事象すら、貴方様には干渉できないかもしれませんが」
神は、もはや全てを諦めたかのように、どこか投げやりな口調で言った。その言葉に、健太は自分の手を見つめ、にやにやと込み上げてくる笑みを抑えることができない。
(無敵か……。マジかよ……。ってことは、もう汗水たらしてバイトしなくてもいいし、誰かに頭を下げる必要もねえ。レベル上げとか面倒な修行も一切なしで、いきなり最強の状態でスタートってことだよな?)
彼の頭の中は、これから始まる輝かしくも怠惰な異世界ライフの妄想で、すっかり満たされていた。絶世の美女であるエルフの王女、元気で快活な獣人の少女、クールで凛々しい女騎士。そんな、アニメやゲームでしか見たことのないような美少女たちを、その圧倒的な無敵さで危機から救い、守り、その結果として惚れさせて、大きな屋敷で毎日パーティー三昧の日々を送る。働かずに、ただただ楽しく、己の欲望のままに生きていく。それこそが、彼が求めていた究極の人生だった。
「よっしゃー! やってやるぜ! 俺は、この無敵の力で、異世界に俺だけのハーレムを築いて、ウハウハのスローライフを送ってやるんだ!」
健太は、天界の神を前にして、なんの恥じらいもなく拳を天に突き上げ、高らかに宣言した。
その、あまりにも俗っぽく、志の低い野望に、神は心底呆れ果てたという顔で、もはや何も言うまい、とばかりに力なく首を振った。
「……そうですか。では、お気をつけて。健太様の新たな人生に、幸多からんことを。心から、お祈り申し上げます」
神が、最後の力を振り絞るように、再び指を鳴らす。健太の足元に、眩い光を放つ複雑な幾何学模様の巨大な魔法陣が展開された。強い光が、彼の身体を下から優しく包み込んでいく。
「うおっ、まぶしっ!」
健太は、人間として、最後の呼吸をした。その息は、空調もろくに効いていない川口市の安アパートの、あの埃っぽい生ぬるい空気の味がした。
身体が、足元から光の粒子となってゆっくりと崩れていく。意識が遠のいていく中で、彼は最後に、疲れ果てた神が「まあ、あの世界も、そろそろ大きなテコ入れが必要だったしな…ある意味、彼のような規格外の『バグ』を投入するのも、一興、か…」という、非常に意味深な呟きを聞いたような気がした。
***
最初に感じたのは、ひんやりとした、湿った土の匂いだった。それは、都会のアスファルトと排気ガスの匂いしか知らなかった彼の鼻腔を、優しくくすぐった。
次に、頬を撫でる、心地よく涼やかな風。じめっとした熱気ではなく、木々の葉が含んだ水分を運んでくるような、清涼な風だった。
そして耳に届いたのは、名前も知らない鳥たちの穏やかなさえずりと、絶え間なく聞こえる清らかな水のせせらぎ。
健太がゆっくりと目を開けると、そこには、思わず息を呑むほどに美しい光景が広がっていた。
見上げる空は、日本のそれとは比べ物にならないほどに、吸い込まれそうなほどに澄み切った青色で、絵の具で描いたような白い雲が、ゆったりとした速度で流れていく。周囲は、これまで写真や映像でしか見たことのないような、幹の太い巨木が生い茂る、深い深い森の中だった。木々の隙間から差し込む太陽の光――木漏れ日が、地面にびっしりと生えたビロードのような柔らかな苔の上で、きらきらと無数の光の斑点を踊らせている。
健太が寝転がっていたのは、澄み切った泉のほとりだった。その泉の水は、信じられないほどに透明で、水底で揺れる水草や、そこに転がる小石の一つ一つまで、はっきりと見ることができた。その神秘的な泉から流れ出す小川が、彼の耳に心地よいせせらぎの音を届けていたのだ。
「……すげえ……」
思わず、心の底から感嘆の声が漏れた。
空気そのものが、生まれ育った世界の汚れたそれとは全く違う。深く、深く息を吸い込むと、肺が新鮮な緑の色に染まっていくような、生命力に満ち溢れた感覚があった。
彼はゆっくりと立ち上がり、自分の身体を見下ろした。服装は、転生前の情けないパンツ一丁ではなく、簡素だが丈夫そうな麻のシャツとズボン、そして革製の編み上げ靴に変わっていた。泉の水面に、自分の顔を映してみる。見慣れた、少し眠たそうな、特にこれといった特徴のない平凡な自分の顔がそこにあった。だが、その瞳には、今までになかった輝きが宿っているように見えた。
「ここが……ここが、俺の、新しい世界か…!」
健太は、両腕を大きく広げ、天に向かって、ありったけの声で叫んだ。その歓喜の声は、静かな森の木々にこだまし、近くの枝で羽を休めていた鳥たちを驚かせて、一斉に空へと飛び立たせた。
絶望も、悲しみも、将来への不安も、ここにはない。あるのは、無限に広がる可能性と、何でもできるという絶対的な確信だけだ。
遥か西の地で、滅びゆく王国の最後の希望を背負った一人の王女が、たった一人で絶望的な救いを求める旅を始めたことなど、今の彼が知る由もなかった。
無敵の力と最低の野望を胸に抱いた男の、お気楽で、身勝手な異世界ライフは、今、まさに最高の形でその幕を開けたのである。
季節は六月。長く続いた陰鬱な雨がようやく止み、梅雨の中休みが訪れた、束の間の晴れ間だった。しかし、その晴れ間は穏やかなものではない。分厚い灰色の雲の隙間から突き刺すように差し込む太陽の光は、まるで真夏を先取りしたかのような獰猛さでアスファルトをじりじりと炙り、逃げ場のない熱波を地上へと送りつけていた。部屋の窓は開け放たれているものの、流れ込んでくるのは熱を含んだ湿った風ばかりで、室内の空気は澱のように重く、息苦しいほどの熱気が満ちていた。
この劣悪な環境の中心に、佐藤健太(さとうけんた)、21歳はいた。三流大学に籍を置きながらも、その実、休学中の無為な日々を送る彼は、パンツ一丁という、人類の叡智が長い歴史の果てに到達した最も効率的かつ原始的な避暑スタイルを実践し、もはや彼の身体の一部と化した万年床の上で、意識の混濁した惰眠を貪っていた。エアコンを起動させようにも、その旧式のリモコンは部屋の混沌とした雑然さの中に完全に姿をくらまし、探す気力すら湧いてこない。
「……ん……ぅ……」
喉の奥が焼け付くような渇きを覚え、健太の意識は浅い眠りのぬるま湯から、ゆっくりと、しかし確実に浮上を始めた。重い瞼をこじ開けると、ぼやけた視界に、見慣れた天井の染みが映る。開けっ放しの窓からは、生ぬるい風が吹き込み、汗ばんだ肌を不快に撫でていく。その風は、様々な音の断片を運んできた。近所の公園で甲高い声を上げて遊ぶ子供たちのはしゃぎ声。どこかの家庭から漏れ聞こえてくる、昼のワイドショーと思しきタレントたちの空々しい笑い声。そして、気の早い一匹の蝉が、まるで己の短い命を削り尽くすかのように、ジリジリと空気を震わせる鋭い鳴き声を、健太の鼓膜にぼんやりと届けていた。
健太のアパートの、人が一人立てばそれで満員となるような小さなベランダには、実家から帰省した際に母親が「部屋に緑がないと心が荒むから」という一方的な善意で無理やり置いていった観葉植物の鉢植えがあった。その艶のある濃緑の葉が、風を受けるたびに「さわさわ」と乾いた音を立てて微かに揺れている。健太はその音を聞くともなしに聞きながら、億劫そうに上半身を起こした。軋む身体が、運動不足を如実に物語っている。
部屋の中は、彼の人生そのものを完璧に体現したかのように、凄まじい混沌に満ちていた。読み終えられ、あるいは読むのを途中で放棄された漫画雑誌が、ジェンガさながらの危ういバランスでタワーを形成し、いつ崩れてもおかしくない威圧感を放っている。床には、飲み干されたペットボトルや、カフェインで彼の覚醒を無理やり支えたエナジードリンクの空き缶が、まるで地雷原のように散らばっていた。そして、昨日食べたのであろうコンビニ弁当のプラスチック容器からは、微かに、しかし確実に不穏な酸っぱい匂いが漂い始めており、小さな羽虫がその周りを飛び交っている。
壁には、彼が心の底から愛してやまないアニメの美少女キャラクターのポスターが数枚、画鋲で無造作に留められていた。そのキャラクターたちは、それぞれに理想化された完璧な笑顔で、この惨状をただ静かに見つめている。パソコンモニターの周囲には、同じキャラクターたちの精巧なフィギュアが、まるで祭壇の守護神であるかのように誇らしげに並べられていた。現実の彼には決して向けられることのない、絶対的な肯定の視線がそこにはあった。
西に傾きかけた太陽が、古びたカーテンの隙間から、一本の鋭い光の筋となって室内へと差し込んでいた。その光は、空気中に舞う無数の埃を、まるでスポットライトのようにキラキラと照らし出し、その一筋だけが、幻想的な銀河のように見えた。その非現実的なほどに美しい光景と、足の踏み場もない部屋の惨状との圧倒的なギャップに、健太は自嘲めいた乾いた笑みを漏らした。
「……水…飲も…」
声に出した言葉は、誰に届くでもなく、澱んだ空気の中に虚しく溶けていく。重い足取りで冷蔵庫に向かい、ドアを開ける。ブーンという低いモーター音と共に、生ぬるい庫内の光が彼の顔を照らした。そこにあったのは、ほとんど空になった二リットルの麦茶パックと、いつ買ったのか記憶もおぼろげで賞味期限が極めて怪しい卵が数個、そして隅の方で忘れ去られたチューブのわさびだけだった。健太は小さく舌打ちし、仕方なくキッチンの水道の蛇口をひねる。ごぼごぼという音と共に吐き出された、カルキ臭い常温の水道水。それを両手で受け、一気に呷る。渇ききった喉を液体が通り過ぎていく感覚は、この堕落しきった生活の中で健太が感じられる、数少ない「生きている実感」の一つだった。
健太のこれまでの人生は、「可もなく不可もない」という言葉ですら上等に思えるほど、驚くほどに平凡で、退屈なものだった。地方のそこそこの進学校に入ったものの、周囲の熱意についていけず、特に打ち込めるものも見つからないまま、ただ惰性で日々を過ごした。将来の夢も、明確な目標もない。だから、皆が行くからというだけの理由で、偏差値に見合った三流大学に進学した。しかし、期待していたキャンパスライフは、パンデミックの影響でオンライン授業が中心となり、希薄な人間関係とモニター越しの虚しい講義に、彼は早々に嫌気が差してしまった。そして、大学に入って一年も経たないうちに休学届を提出し、現在に至る。
今の彼の生活を支えているのは、週に三日、深夜に入るコンビニエンスストアのアルバイトだけだ。そこで稼いだ最低限の金で食いつなぎながら、空いた時間のほとんど全てを、アニメ鑑賞とソーシャルゲームに費やしている。画面の中では、彼は世界を救う伝説の勇者にも、強大な魔王を従える孤高の賢者にもなれた。現実ではろくに話したこともないような、可憐な美少女たちに囲まれ、かけがえのない仲間たちと熱い絆で結ばれ、壮大な冒険を繰り広げる。しかし、ログアウトボタンを押せば、そこにあるのは、この六畳一間の薄汚い部屋と、何一つ成し遂げていない、空っぽで無力な自分だけだ。その落差が、彼をさらに仮想世界へと没入させていた。
「……はぁ。なんか面白いこと、起きねーかなぁ……」
その呟きは、彼の心の底からの切実な願いだった。誰かに聞かせるつもりなど毛頭ない、純粋な独り言。彼は椅子に腰かけると、慣れた手つきでパソコンの電源を入れた。ファンが唸りを上げ、モニターが光を放つ。目的は一つ。昨日から鳴り物入りでサービスが始まったばかりの、最新型フルダイブVRMMORPG――『エリュシオン・オンライン』だ。
仮想空間でありながら、視覚や聴覚だけでなく、触覚、味覚、嗅覚といった五感の全てを完全に再現するという、まさに夢のようなゲーム。その革新的な技術は世界中で話題となり、健太もまた、その宣伝映像に心を奪われた一人だった。コンビニの深夜バイトで稼いだ給料のほとんどを、このゲームをプレイするためだけの専用ヘッドギアにつぎ込んだのだ。借金こそしなかったが、貯金は完全に底をついた。
「これさえあれば、俺の人生も少しはマシになる…はずだ」
後悔はなかった。むしろ、この投資こそが、停滞した自分の人生を動かす唯一の起爆剤だと信じていた。ヘッドギアを手に取り、ゆっくりと頭に装着する。フィット感を確かめ、起動スイッチを入れると、視界が穏やかな暗闇に包まれ、心地よい電子音が鼓膜を優しく震わせた。
『―――ようこそ、エリュシオンへ。あなたの魂を、新たな世界へと導きます―――』
無機質でありながら、どこか荘厳さを感じさせるシステム音声と共に、健太の意識は現実の肉体から引き剥がされ、仮想のデータへとダイブしていく感覚に襲われた。これから始まる未知の冒険に、彼の心臓は期待で大きく高鳴った。異世界、圧倒的なチート能力、そして美少女たちとのハーレム。彼の抑圧された欲望のすべてが、そこには詰まっているはずだった。現実の自分ではない、理想の自分になれる場所が、すぐそこにある。
その時だった。
外の空が、一瞬、ありえないほど強く輝いた。まるで、空全体が巨大な閃光弾になったかのように。先ほどまでやかましく鳴いていた蝉の声が、まるでスイッチを切られたかのように、ぴたりと止んだ。
健太の意識は、まだ仮想空間と現実の狭間を、曖昧に漂っていた。そのため、彼はまるで幽体離脱でもしたかのように、神の視点にも似た奇妙な感覚で、自分の部屋の窓の外が、真昼の太陽さえ霞んでしまうほどの純白の光に包まれたのを、はっきりと認識していた。
「え?」
それが、佐藤健太という人間の、最後の言葉だった。
次の瞬間、天から落ちてきた一本の雷が、まるで神が気まぐれに下界を指さしたかのように、日本国埼玉県川口市にある彼のアパートの、彼の部屋だけを、恐ろしいほど正確に、ピンポイントで貫いた。
轟音は、なかった。爆発も、衝撃もなかった。
ただ、全ての物質が、部屋も、家具も、彼が愛したフィギュアも、そして彼自身も、圧倒的な光の奔流に飲み込まれ、原子レベルにまで分解されて消滅していく。彼の存在は、彼の退屈な日常は、彼の俗っぽくも純粋な欲望は、コンマ一秒にも満たない、認識すらできないほどの短い時間の中で、この世界から完全に、一片の痕跡も残さずに消え去った。
***
健太が次に目を覚ました時、彼は、何もない場所にいた。
上も、下も、右も、左も、全ての方向が等しく、どこまでも続く純白の世界。床があるのか、それとも宙に浮いているのかさえ分からない。空気の流れはなく、音もなく、匂いもない。完全な無の世界。自分の身体を見下ろせば、見慣れた手足が存在している。だが、試しにその手で頬に触れてみても、何の感触もなかった。五感そのものが、この空間の物理法則から除外されているかのようだった。
「……どこだ、ここ…?ゲームの、中…か?」
声は出せた。しかし、その声が空気を震わせる感覚はなく、自分の頭蓋骨の中で直接響いているような、ひどく奇妙な感覚だった。混乱し、途方に暮れて、その場で意味もなくくるくると回り始めた彼の背後から、不意に、気の抜けたような、それでいてどこか丁寧な声がした。
「あー、どうも。佐藤健太さん、で、お間違いないでしょうか?」
健太は、文字通り心臓が喉から飛び出すかと思うほど驚いて、勢いよく振り返った。
そこに立っていたのは、一人の男だった。着古されてくたびれた印象のグレーのスーツに、少し曲がったネクタイ。寝癖のついたボサボサの髪に、目の下にはまるで墨で描いたかのような深い隈が刻まれている。手には使い古された革の鞄を提げており、その姿は、連日の徹夜明けで重要な営業先に向かう途中といった風情の、しがないサラリーマンにしか見えなかった。
ただ一つ、決定的に常識外れな点を挙げるならば、彼の背中からは、純白の、それはもう見事なまでに巨大な天使の翼が、本人の疲れた雰囲気とは不釣り合いに、申し訳なさそうに生えていた。
「……あんた、誰だ?その格好…コスプレ…?」
混乱の極みにあった健太が絞り出したのは、そんな間の抜けた質問だった。
「いえ、コスプレではございません。わたくし、こういう者でして」
男は疲れた顔で薄く笑うと、スーツの内ポケットから、年季の入った名刺入れを取り出し、慣れた手つきで一枚の名刺を健太に差し出した。健太は反射的にそれを受け取る。そこには、神々しい金色の箔押し文字で、こう書かれていた。
【天界管理局 対人部 第三課 担当:神(カミ)】
「……かみ?」
健太は、名刺と男の顔を交互に見比べながら、呆然と呟いた。
「はい、神です。一応、このあたりの次元を管理監督させていただいております」
男――神は、深々と、それはもう完璧な角度で頭を下げた。その完璧な四十五度の角度は、長年の営業活動で体に染み付いたものに違いなかった。そして、彼は顔を上げると、さらに深く、今度は土下座でもせんばかりの勢いで再び頭を下げた。
「この度は、まことに、まことに、申し訳ございませんでしたッ!」
「は? え? なにが?」
「わたくしの、完全なる、100パーセントの不手際によりまして、佐藤健太様を、本来の寿命よりおよそ60年ほど早く、死なせてしまいました!」
神は、顔を上げないまま絶叫した。健太は、ぽかんと口を開けて、その常軌を逸した光景をただ眺めていた。
死んだ? 俺が? この、うだつの上がらないサラリーマンみたいな神様の、せいで?
「いやいやいや、意味わかんないんだけど。俺、VRゲームやってて、そしたら光が…」
「ええ、全て存じております。あの時、わたくし、長引く業務の疲れから少々くしゃみをしてしまいまして…」
「くしゃみ?」
「はい。そのくしゃみの拍子にですね、天界の気象コントロールシステムに、ほんの、ほんの僅かですが神力が漏れ出してしまいまして…。それがですね、不運にも雷という形に変換され、これまた不運にも佐藤様のいらっしゃる座標にピンポイントで…その…大変申し訳ない結果を招いてしまった次第でございます…」
神は、非常に言いにくそうに、言葉を濁しながら説明した。
つまり、要約すると、神のくしゃみが原因で発生した雷に直撃されて俺は死んだ、と。
あまりにも馬鹿馬鹿しく、理不尽極まりない死因に、健太は怒る気力さえ一瞬で失せてしまった。その場にへなへなとうずくまり、両手で頭を抱える。
「マジかよ……俺の人生、神のくしゃみエンドかよ……。せめてトラックに轢かれるとか、通り魔に刺されるとか、もうちょい異世界転生の王道っぽい死に方させてくれよ……」
「面目次第もございません……。穴があったら入りたい、とはまさにこのことで…」
しばらくの間、健太はうなだれていたが、やがてゆっくりと顔を上げた。彼の目には、先ほどまでの諦観に満ちた光ではなく、これまで見せたことのない、ギラギラとした鋭い光が宿っていた。それは絶望の色ではなかった。むしろ、この突拍子もない、ありえない状況を、最大限に利用してやろうという、実にしたたかで計算高い光だった。
「…まあ、いいや。死んじまったもんは仕方ねえ」
「お、おお…!なんと、お心の広い…!仏、いや神の目から見ても、貴方様は仏のようです…!」
「で? タダで死んだまんま、ってことはないよな?」
健太は、下卑た笑みを隠そうともせず、にやりと口角を吊り上げて神を見上げた。
「なんか、あるんだろ? お詫び、的なやつが。迷惑料? 慰謝料?」
その露骨な要求に、神は一瞬たじろいだが、すぐに心底安堵したように大きく息をついた。話の通じる相手で良かった、と顔に書いてある。
「は、はい!もちろんでございます!本来であれば、記憶を消去の上、速やかに輪廻の輪にお戻りいただくという流れになるのですが、今回は完全にこちらの過失ですので、特別措置を取らせていただきます」
神は、ぱん、と軽快に手を叩いた。すると、何もない純白の空間に、巨大なプレゼンテーション用のスクリーンのようなものが突如として現れた。
「佐藤様には、二つのオプションがございます。一つは、現在の記憶を持ったまま、現在の地球の別の赤ん坊として、裕福な家庭などを選んで生まれ変わる。もう一つは――」
スクリーンに、鬱蒼とした森、雄大に空を舞うドラゴン、尖った耳を持つ美しいエルフ、屈強なドワーフといった、健太がゲームやアニメでさんざん見てきたファンタジーの世界の映像が次々と映し出された。
「全く別の世界、いわゆる『異世界』に、現在の肉体と記憶を維持したまま転生する、というものです。もちろん、こちらをお選びいただいた場合、お詫びの印としまして、何か一つ、お好きな『特典(チート能力)』を授与させていただきますが…いかがいたしましょう?」
健太の心が、沸騰した。
異世界。チート能力。
それは、彼が薄汚い六畳一間で、万年床の上で、来る日も来る日も夢想し、渇望していたもの、そのものだった。
「異世界! 絶対に異世界でお願いします!」
彼は、神の言葉が終わるか終わらないかのうちに、食い気味に絶叫した。
「承知いたしました。では、特典の方ですが、どのような能力をご希望で…」
「よっしゃー!」
神の問いかけを遮り、健太はここぞとばかりにまくし立て始めた。彼の欲望が、堰を切ったように溢れ出す。
「まず、絶対死なないやつ!不老不死で!病気にも一切ならないし、どんな猛毒を飲んでも平気なやつ!」
「は、はあ…不死性と状態異常無効、ですね…」
「あと、最強の魔法!指パッチン一発で山とか大陸とか吹き飛ばせるレベルの超攻撃魔法!」
「あ、あの、世界のバランスというものがございますので、あまり大規模なものは…」
「それから、どんな攻撃も全く効かない無敵の身体!ドラゴンのブレスを浴びても『あー、ちょっとあったかいな』くらいで済むやつ!」
「ええと、それは物理・魔法ダメージ完全無効という解釈でよろしいでしょうか…」
「当たり前だ!もちろん、女にモテモテになるカリスマ性も必須だよな!ただ道を歩いてるだけで、エルフとか獣人とか王女様とか、あらゆる種族の美少女が寄ってきてハーレムを形成できるくらいのやつ!」
「そ、それは因果律への干渉があまりにも大きすぎます!個人の感情に直接作用するような権限はわたくしには…!」
神は、健太の留まることを知らない欲望の奔流を前に、額から滝のような脂汗を流し、その顔色はどんどん青ざめて土気色になっていく。
「お客様!お客様!少々お待ちください!ご要望が多すぎて、天界の『ご予算』を大幅に、というか天文学的にオーバーしてしまいます!そんな前例はございません!」
「うるせえ!俺はあんたのくしゃみで死んだんだぞ!こっちは被害者だ!これくらい要求するのは当然の権利だろ!」
「そ、それはそうなのですが、しかし、これを認めてしまうとわたくしの査定に響きまして…!始末書どころでは済まない事態に…!」
人と神の、実に低レベルな押し問答は、しばらくの間、無音の空間に虚しく響き続けた。
最終的に、完全に理詰めで追い込まれ、頭を抱えてその場にうずくまった神が、震える声で一つの妥協案を提示した。
「……分かりました。もう、分かりましたから…。でしたら、お客様のご要望の根幹を成す部分、これら全てを、一つの能力に集約する形で付与させていただく、というのはいかがでしょうか…?」
「一つに?」
「はい。いわば、『概念的な無敵』とでも申しましょうか…」
神は、どこからともなく一枚の企画書のような羊皮紙を取り出し、咳払いをしてから、必死の形相で説明を始めた。
「佐藤健太様の存在そのものを、この宇宙における絶対的な『確定事象』として定義し直します。これにより、いかなる物理的、魔法的、精神的、因果的な干渉も、佐藤様に到達する前に『なかったこと』になります。攻撃されれば、その攻撃という事象自体が無に還る。毒を飲んでも、毒が毒としての性質をその場で失う。老化という時間の流れによる事象も、死という生命活動の停止という結果も、佐藤様には一切適用されません。つまり――」
神は、ごくりと喉を鳴らし、最後の切り札を提示するように言った。
「――何があっても、絶対に死なないし、傷つかないし、弱らない。『無敵』です。これならば、先ほどのご要望のほとんどをカバーできるかと存じますが…」
健太は、最初、口を半開きにしてその壮大な説明を聞いていたが、やがてその意味を完全に理解し、その顔に満面の、最高の笑みを浮かべた。
「…それだ! 最高じゃねえか! それで頼む!」
「……はぁ。承知、いたしました…」
神は、何かとんでもなく取り返しのつかないことをしてしまった、という後悔に満ちた顔で、深すぎるため息をついた。
***
「では、これより、特典能力『絶対不干渉(パーフェクト・ワールド)』を、佐藤様の魂にインストールいたします」
神が疲労困憊の様子で指を鳴らすと、健太の身体が淡い金色の光に包まれた。温かいような、冷たいような、これまで感じたことのない不思議な感覚が全身を駆け巡る。脳内に、人間には到底理解不能な膨大な量の情報が激流のように流れ込み、魂そのものが、より高次の存在へと強制的に書き換えられていくような、全能感にも似た圧倒的な感覚に支配された。
数秒後、光が収まると、身体が以前よりも遥かに軽く、そして何よりも「確かなもの」になった気がした。世界の全てが不確定な中で、自分だけが絶対的な存在であるかのような、奇妙な安定感があった。
「さて、と。転生先のワールドですが…いくつか候補はございますが、どこかご希望は?」
「んー、やっぱ王道の剣と魔法の世界だよな。エルフとかドワーフとか獣人とか、そういうのが普通にいる感じの」
「さようでございますか。でしたら、こちらの『アースガルド』という世界がよろしいかと。ちょうど今、魔王が率いる魔王軍と、人間諸国を中心とした人間連合が大規模な戦争を繰り広げておりまして、非常にこう…ファンタジー分が濃厚でございます」
「戦争? なんかめんどくさそうだな」
「まあ、今の佐藤様でしたら、戦争など蚊に刺されたようなものでしょう。あるいは、蚊に刺されるという事象すら、貴方様には干渉できないかもしれませんが」
神は、もはや全てを諦めたかのように、どこか投げやりな口調で言った。その言葉に、健太は自分の手を見つめ、にやにやと込み上げてくる笑みを抑えることができない。
(無敵か……。マジかよ……。ってことは、もう汗水たらしてバイトしなくてもいいし、誰かに頭を下げる必要もねえ。レベル上げとか面倒な修行も一切なしで、いきなり最強の状態でスタートってことだよな?)
彼の頭の中は、これから始まる輝かしくも怠惰な異世界ライフの妄想で、すっかり満たされていた。絶世の美女であるエルフの王女、元気で快活な獣人の少女、クールで凛々しい女騎士。そんな、アニメやゲームでしか見たことのないような美少女たちを、その圧倒的な無敵さで危機から救い、守り、その結果として惚れさせて、大きな屋敷で毎日パーティー三昧の日々を送る。働かずに、ただただ楽しく、己の欲望のままに生きていく。それこそが、彼が求めていた究極の人生だった。
「よっしゃー! やってやるぜ! 俺は、この無敵の力で、異世界に俺だけのハーレムを築いて、ウハウハのスローライフを送ってやるんだ!」
健太は、天界の神を前にして、なんの恥じらいもなく拳を天に突き上げ、高らかに宣言した。
その、あまりにも俗っぽく、志の低い野望に、神は心底呆れ果てたという顔で、もはや何も言うまい、とばかりに力なく首を振った。
「……そうですか。では、お気をつけて。健太様の新たな人生に、幸多からんことを。心から、お祈り申し上げます」
神が、最後の力を振り絞るように、再び指を鳴らす。健太の足元に、眩い光を放つ複雑な幾何学模様の巨大な魔法陣が展開された。強い光が、彼の身体を下から優しく包み込んでいく。
「うおっ、まぶしっ!」
健太は、人間として、最後の呼吸をした。その息は、空調もろくに効いていない川口市の安アパートの、あの埃っぽい生ぬるい空気の味がした。
身体が、足元から光の粒子となってゆっくりと崩れていく。意識が遠のいていく中で、彼は最後に、疲れ果てた神が「まあ、あの世界も、そろそろ大きなテコ入れが必要だったしな…ある意味、彼のような規格外の『バグ』を投入するのも、一興、か…」という、非常に意味深な呟きを聞いたような気がした。
***
最初に感じたのは、ひんやりとした、湿った土の匂いだった。それは、都会のアスファルトと排気ガスの匂いしか知らなかった彼の鼻腔を、優しくくすぐった。
次に、頬を撫でる、心地よく涼やかな風。じめっとした熱気ではなく、木々の葉が含んだ水分を運んでくるような、清涼な風だった。
そして耳に届いたのは、名前も知らない鳥たちの穏やかなさえずりと、絶え間なく聞こえる清らかな水のせせらぎ。
健太がゆっくりと目を開けると、そこには、思わず息を呑むほどに美しい光景が広がっていた。
見上げる空は、日本のそれとは比べ物にならないほどに、吸い込まれそうなほどに澄み切った青色で、絵の具で描いたような白い雲が、ゆったりとした速度で流れていく。周囲は、これまで写真や映像でしか見たことのないような、幹の太い巨木が生い茂る、深い深い森の中だった。木々の隙間から差し込む太陽の光――木漏れ日が、地面にびっしりと生えたビロードのような柔らかな苔の上で、きらきらと無数の光の斑点を踊らせている。
健太が寝転がっていたのは、澄み切った泉のほとりだった。その泉の水は、信じられないほどに透明で、水底で揺れる水草や、そこに転がる小石の一つ一つまで、はっきりと見ることができた。その神秘的な泉から流れ出す小川が、彼の耳に心地よいせせらぎの音を届けていたのだ。
「……すげえ……」
思わず、心の底から感嘆の声が漏れた。
空気そのものが、生まれ育った世界の汚れたそれとは全く違う。深く、深く息を吸い込むと、肺が新鮮な緑の色に染まっていくような、生命力に満ち溢れた感覚があった。
彼はゆっくりと立ち上がり、自分の身体を見下ろした。服装は、転生前の情けないパンツ一丁ではなく、簡素だが丈夫そうな麻のシャツとズボン、そして革製の編み上げ靴に変わっていた。泉の水面に、自分の顔を映してみる。見慣れた、少し眠たそうな、特にこれといった特徴のない平凡な自分の顔がそこにあった。だが、その瞳には、今までになかった輝きが宿っているように見えた。
「ここが……ここが、俺の、新しい世界か…!」
健太は、両腕を大きく広げ、天に向かって、ありったけの声で叫んだ。その歓喜の声は、静かな森の木々にこだまし、近くの枝で羽を休めていた鳥たちを驚かせて、一斉に空へと飛び立たせた。
絶望も、悲しみも、将来への不安も、ここにはない。あるのは、無限に広がる可能性と、何でもできるという絶対的な確信だけだ。
遥か西の地で、滅びゆく王国の最後の希望を背負った一人の王女が、たった一人で絶望的な救いを求める旅を始めたことなど、今の彼が知る由もなかった。
無敵の力と最低の野望を胸に抱いた男の、お気楽で、身勝手な異世界ライフは、今、まさに最高の形でその幕を開けたのである。
20
あなたにおすすめの小説

40歳のおじさん 旅行に行ったら異世界でした どうやら私はスキル習得が早いようです
カムイイムカ(神威異夢華)
ファンタジー
部長に傷つけられ続けた私
とうとうキレてしまいました
なんで旅行ということで大型連休を取ったのですが
飛行機に乗って寝て起きたら異世界でした……
スキルが簡単に得られるようなので頑張っていきます

備蓄スキルで異世界転移もナンノソノ
ちかず
ファンタジー
久しぶりの早帰りの金曜日の夜(但し、矢作基準)ラッキーの連続に浮かれた矢作の行った先は。
見た事のない空き地に1人。異世界だと気づかない矢作のした事は?
異世界アニメも見た事のない矢作が、自分のスキルに気づく日はいつ来るのだろうか。スキル【備蓄】で異世界に騒動を起こすもちょっぴりズレた矢作はそれに気づかずマイペースに頑張るお話。
鈍感な主人公が降り注ぐ困難もナンノソノとクリアしながら仲間を増やして居場所を作るまで。

異世界に移住することになったので、異世界のルールについて学ぶことになりました!
心太黒蜜きな粉味
ファンタジー
※完結しました。感想をいただけると、今後の励みになります。よろしくお願いします。
これは、今まで暮らしていた世界とはかなり異なる世界に移住することになった僕の話である。
ようやく再就職できた会社をクビになった僕は、不気味な影に取り憑かれ、異世界へと運ばれる。
気がつくと、空を飛んで、口から火を吐いていた!
これは?ドラゴン?
僕はドラゴンだったのか?!
自分がドラゴンの先祖返りであると知った僕は、超絶美少女の王様に「もうヒトではないからな!異世界に移住するしかない!」と告げられる。
しかも、この世界では衣食住が保障されていて、お金や結婚、戦争も無いというのだ。なんて良い世界なんだ!と思ったのに、大いなる呪いがあるって?
この世界のちょっと特殊なルールを学びながら、僕は呪いを解くため7つの国を巡ることになる。
※派手なバトルやグロい表現はありません。
※25話から1話2000文字程度で基本毎日更新しています。
※なろうでも公開しています。

最低のEランクと追放されたけど、実はEXランクの無限増殖で最強でした。
みこみこP
ファンタジー
高校2年の夏。
高木華音【男】は夏休みに入る前日のホームルーム中にクラスメイトと共に異世界にある帝国【ゼロムス】に魔王討伐の為に集団転移させれた。
地球人が異世界転移すると必ずDランクからAランクの固有スキルという世界に1人しか持てないレアスキルを授かるのだが、華音だけはEランク・【ムゲン】という存在しない最低ランクの固有スキルを授かったと、帝国により死の森へ捨てられる。
しかし、華音の授かった固有スキルはEXランクの無限増殖という最強のスキルだったが、本人は弱いと思い込み、死の森を生き抜く為に無双する。

スティールスキルが進化したら魔物の天敵になりました
東束末木
ファンタジー
第18回ファンタジー小説大賞 奨励賞、いただきました!!
スティールスキル。
皆さん、どんなイメージを持ってますか?
使うのが敵であっても主人公であっても、あまりいい印象は持たれない……そんなスキル。
でもこの物語のスティールスキルはちょっと違います。
スティールスキルが一人の少年の人生を救い、やがて世界を変えてゆく。
楽しくも心温まるそんなスティールの物語をお楽しみください。
それでは「スティールスキルが進化したら魔物の天敵になりました」、開幕です。
2025/12/7
一話あたりの文字数が多くなってしまったため、第31話から1回2~3千文字となるよう分割掲載となっています。
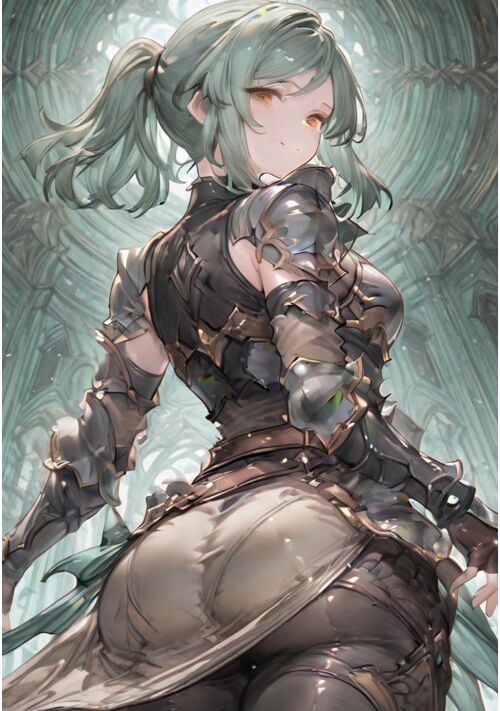
【完結】うだつが上がらない底辺冒険者だったオッサンは命を燃やして強くなる
邪代夜叉(ヤシロヤシャ)
ファンタジー
まだ遅くない。
オッサンにだって、未来がある。
底辺から這い上がる冒険譚?!
辺鄙の小さな村に生まれた少年トーマは、幼い頃にゴブリン退治で村に訪れていた冒険者に憧れ、いつか自らも偉大な冒険者となることを誓い、十五歳で村を飛び出した。
しかし現実は厳しかった。
十数年の時は流れてオッサンとなり、その間、大きな成果を残せず“とんまのトーマ”と不名誉なあだ名を陰で囁かれ、やがて採取や配達といった雑用依頼ばかりこなす、うだつの上がらない底辺冒険者生活を続けていた。
そんなある日、荷車の護衛の依頼を受けたトーマは――

Sランクパーティを引退したおっさんは故郷でスローライフがしたい。~王都に残した仲間が事あるごとに呼び出してくる~
味のないお茶
ファンタジー
Sランクパーティのリーダーだったベルフォードは、冒険者歴二十年のベテランだった。
しかし、加齢による衰えを感じていた彼は後人に愛弟子のエリックを指名し一年間見守っていた。
彼のリーダー能力に安心したベルフォードは、冒険者家業の引退を決意する。
故郷に帰ってゆっくりと日々を過しながら、剣術道場を開いて結婚相手を探そう。
そう考えていたベルフォードだったが、周りは彼をほっておいてはくれなかった。
これはスローライフがしたい凄腕のおっさんと、彼を慕う人達が織り成す物語。

最初から最強ぼっちの俺は英雄になります
総長ヒューガ
ファンタジー
いつも通りに一人ぼっちでゲームをしていた、そして疲れて寝ていたら、人々の驚きの声が聞こえた、目を開けてみるとそこにはゲームの世界だった、これから待ち受ける敵にも勝たないといけない、予想外の敵にも勝たないといけないぼっちはゲーム内の英雄になれるのか!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















