21 / 43
五部
第19話:帰郷、そして涙
しおりを挟む水の王国アクアフォールは、歓喜に沸いていた。
帝国軍という、抗いようのない絶対的な脅威が、たった一人の男によって、一夜にして退けられた。
その奇跡のような報せは、瞬く間に都中を駆け巡り、人々を熱狂の渦に巻き込んだ。
その夜、王宮で開かれた祝賀の宴は、これ以上ないほどに、華やかで、そして、心からの感謝に満ちていた。
大理石の床は磨き上げられ、天井の水晶のシャンデリアは、数千の蝋燭の光を乱反射させ、広間全体を、昼間のように明るく照らしている。
楽団が奏でる、勝利を祝う、高らかなファンファーレ。
テーブルには、湖で獲れた新鮮な魚介類を使った、色とりどりの豪華な料理が、所狭しと並べられていた。
人々は、笑っていた。心の底から、安堵し、明日への希望を語り合っていた。
その笑顔の一つ一つが、フィーナの胸を、温かく、しかし、同時に、ちくりと刺した。
彼女は、宴の喧騒から少し離れた、テラスに続く回廊の柱に、一人、もたれかかっていた。
手にした、上質なワインが入った銀の杯には、ほとんど口をつけていない。
彼女の視線の先では、仲間たちが、それぞれのやり方で、この祝宴を楽しんでいた。
健太は、もはや主役であることさえ忘れ、ビュッフェ台に並んだローストビーフの塊に、子供のように目を輝かせながら、一心不乱にかぶりついている。
彼の隣では、ゴルドが、ドワーフの国から特別に取り寄せられたという、燃えるように強い蒸留酒の樽を、王国の将軍たちと、楽しげに飲み比べていた。
少し離れた場所では、ルミナが、人混みを避けるように、窓辺に佇んでいる。
彼女は、宴の騒がしさは苦手なようだったが、その翡翠色の瞳には、穏やかな光が宿っていた。
そして、セシルは。
彼女は、何人かの侍女たちに囲まれ、最初は戸惑っていたものの、彼女たちの屈託のない優しさに触れ、少しずつ、その表情を和らげ、おずおずと、微笑みを浮かべていた。
フランスの、あの息詰まるような日々が、まるで、遠い昔の悪夢だったかのように。
その、平和な光景。
守られた、人々の笑顔。
それを見つめながら、フィーナは、自らの決意を、改めて、固めていた。
帝国という、大きな脅威は去った。だが、自分の戦いは、まだ、何も終わっていない。
彼女は、杯を置くと、仲間たちが集まる輪の中へと、静かに歩み寄った。
「―――皆さん。少し、よろしいでしょうか」
フィーナの、凛とした声に、仲間たちは、一斉に彼女の方を向いた。
彼女は、深々と、頭を下げた。
「これまでの、皆さんのご助力に、心から、感謝いたします。あなた方がいなければ、私は、とうに、命を落としていたでしょう」
「おいおい、姫様、水臭えじゃねえか」
ゴルドが、顔を赤らめながら言う。
「ですが」
フィーナは、顔を上げた。その瞳には、揺るぎない、強い意志の光が宿っていた。
「私は、行かなければならない場所があります」
彼女は、続けた。
「私の故郷、クライロード王国の、跡地へ」
その言葉に、仲間たちの表情が、わずかに、緊張した。
そこが、どのような場所か、彼らは、ヴァレリアから、そして、フィーナ自身の口から、断片的に聞いて知っていた。
魔族に滅ぼされ、今は、不毛の地となっている、悲劇の場所。
「…どうして、今、その場所に?」
ルミナが、静かに問う。
「私の旅は、そこから始まったからです。そして、私の罪もまた、そこにあります。私は、もう一度、あの場所で、自分の目で、現実を見つめ直さなければならない。そうでなければ、私は、本当の意味で、前に進むことができないのです」
彼女は、付け加えた。
「これは、私の、個人的な問題です。皆さんを、これ以上、危険な場所に、巻き込むわけには…」
「―――馬鹿言うなよ」
彼女の言葉を遮ったのは、口の周りをソースでべとべとにしたままの、健太だった。
「何が、個人的な問題だよ。フィーナちゃんの旅は、もう、俺たちの旅でもあるんだぜ?」
彼は、にっと笑った。
「それに、まだ、勇者探しも終わってねえだろ? だったら、パーティーが、バラバラに行動する理由が、ねえじゃんか」
その、あまりにも単純明快な言葉に、ゴルドが、豪快に笑いながら、同意した。
「へっ、その通りだぜ、朴念仁! 姫様が、どこへ行こうと、俺たちは、あんたの剣であり、盾だ! 今さら、水臭いこと、言ってんじゃねえ!」
「…仕方のない人たちですね」
ルミナも、やれやれ、といった風に、小さく微笑んだ。
「フィーナの望みが、そうなのですから。私に、異論はありません」
「わ、私も…! 私も、行きます!」
セシルが、勇気を振り絞って、言った。
「フィーナ様が、どこへ行くのでも、私は、そばにいたいですから…!」
フィーナの瞳から、熱いものが、込み上げてきた。
自分は、もう、一人ではないのだ。
***
アクアフォールの民に、英雄として盛大に見送られ、一行は、再び、旅路についた。
目指すは、北。
フィーナの故郷、クライロード王国。
船で湖を渡り、再び、街道を歩く。
季節は、夏から、初秋へと、その衣を、ゆっくりと着替え始めていた。
あれほど、容赦なく照りつけていた太陽の光は、少しだけ、その勢いを和らげ、空は、どこまでも高く、そして、青く澄み渡っている。
風が、変わっていた。
肌にまとわりつくような熱風ではなく、どこか、涼やかで、乾いた風が、頬を撫でていく。
その風は、街道沿いの木々の葉を揺らし、その葉は、緑色の中に、わずかに、黄色や赤色を、滲ませ始めていた。
道中、フィーナは、仲間たちに、かつての、クライロード王国のことを、何度も、話して聞かせた。
「…私の国の麦畑は、この時期になると、地平線の果てまで、黄金色の絨毯のようになるのです。風が吹くと、それが、大きな波となって、さわさわと、音を立てる…。その光景が、私は、大好きでした」
「城下町には、いつも、活気がありました。腕のいい職人たちが、たくさんいて…。特に、年に一度の収穫祭は、国中の人々が集まり、歌い、踊り、夜通し、お祝いをするのです…」
彼女が語る、その一つ一つの言葉には、故郷への、深い、深い、愛情が、滲んでいた。
仲間たちは、誰も、口を挟むことなく、ただ、静かに、彼女の思い出話に、耳を傾けていた。
彼女が、どれほどのものを、失ってしまったのか。
その痛みを、自分たちのことのように、感じ取っていたからだ。
故郷が、近づくにつれて。
フィーナの呼吸が、少しずつ、浅く、そして、速くなっていくのを、健太は、隣で、感じていた。
彼女は、期待しているのだ。
もしかしたら、少しは、復興しているのではないか、と。
誰かが、生き残っていてくれるのではないか、と。
そして、それと同時に、恐れているのだ。
何もかもが、自分の記憶の中の、あの日のまま、絶望的な姿で、残っていることを。
その、期待と恐怖の狭間で、彼女の心は、激しく、揺れ動いていた。
そして、一行は、ついに、クライロード王国の、国境だった場所へと、たどり着いた。
フィーナが、かつて、黄金色の絨毯のようだと語った、広大な麦畑。
そこにあったのは、ただ、枯れた雑草が、どこまでも、荒涼と広がるだけの、不毛の大地だった。
***
馬車が、ゆっくりと、止まった。
誰も、何も、言えなかった。
目の前に広がる光景が、あまりにも、雄弁に、全てを物語っていたからだ。
風が、ヒュー、と、乾いた音を立てて、荒れ地を吹き抜けていく。
その風が運んでくるのは、もはや、土の匂いですらない。
長い間、生命が活動することをやめてしまった、打ち捨てられた場所だけが放つ、独特の、カビと、塵と、そして、かすかな、死の匂いだった。
遠くに見える、王都の、残骸。
焼け落ちた建物が、まるで、巨大な墓標のように、黒い、不気味なシルエットとなって、灰色の空を、突き刺している。
そして、その中心部には、巨大なクレーターの縁が、大地に刻まれた、永遠に癒えることのない、巨大な傷跡のように、横たわっていた。
「……あ……」
フィーナの、か細い声が、漏れた。
彼女は、まるで、夢遊病者のように、ふらり、と、馬車から降りた。
そして、一歩、また一歩と、その、灰色の世界へと、足を踏み入れていく。
仲間たちが、心配そうに、彼女の後を追った。
完全な、沈黙。
鳥の声も、虫の音も、水のせせらぎも、かつて、ここにあったはずの、全ての生命の音が、完全に、消え失せていた。聞こえるのは、風が、廃墟の隙間を吹き抜ける、うめき声のような音だけだ。
フィーナは、歩いた。
かつての、城下町の、メインストリートだった場所を。
ここは、パン屋があった場所だ。
いつも、焼きたての、香ばしい匂いがしていた。
あそこは、彼女が、よく本を買いに行った、本屋。
優しい、白髪の店主がいた。
ここは、子供たちが、いつも、楽しそうに走り回っていた、噴水広場。
今は、噴水の見る影もなく、ただ、ひび割れた、石の残骸が、転がっているだけだ。
彼女の脳裏に、幸せだった頃の記憶が、鮮やかに、蘇る。
人々の、屈託のない笑顔。
活気のある、話し声。
子供たちの、甲高い、はしゃぎ声。
その、鮮やかな記憶と、目の前に広がる、色のない、音のない、死の世界との、あまりにも、残酷な、ギャップ。
彼女は、ついに、その場に、膝から、崩れ落ちた。
「…うそ…うそよ…こんなの…こんなの、嘘よ…!」
彼女は、地面の灰を、かきむしった。
「どうして…どうして、誰も、いないの…? 少しは…少しくらい、元に戻っていると…誰か、生き残っていてくれると、思ったのに…!」
彼女の肩が、小さく、震え始めた。
それは、これまで、彼女が、気丈に、決して見せようとしなかった、弱さだった。
王女としての、責任感でも、使命感でもない。
ただ、全てを失ってしまった、一人の、無力な少女の、魂の、慟哭だった。
「…う…うわあああああああああああああああん!」
ルミナも、ゴルドも、セシルも、かける言葉を、見つけられなかった。
彼らもまた、それぞれの形で、大切なものを失ってきた。
だからこそ、分かるのだ。
こういう時、どんな、慰めの言葉も、虚しく、そして、残酷でさえあることを。
彼らは、ただ、悲痛な面持ちで、泣きじゃくる、フィーナの、小さな背中を、見つめていた。
その時、健太が、動いた。
彼は、三人の横を、黙って通り過ぎると、フィーナの隣に、静かに、腰を下ろした。
彼は、何も、言わなかった。
気の利いた、慰めの言葉など、彼は、知らない。
ただ、彼は、自分が着ていた、黒いコートを脱ぐと、震える、フィーナの、その小さな肩に、そっと、かけてやった。
コートに残る、彼の、かすかな温もり。
フィーナは、驚いて、顔を上げた。
その、涙でぐしゃぐしゃになった顔を、健太は、ただ、静かに、見つめていた。
そして、しばらくして、ぽつり、と、呟いた。
「…泣きたい時はさ、気の済むまで、泣けばいいんじゃねえの」
その声は、いつもと同じように、どこか、気の抜けた、呑気な響きを持っていた。
「俺たち、もう、どこにも行かねえから。君が、泣き止むまで、ずっと、ここにいるからさ」
その、あまりにも、不器用で、飾り気のない、しかし、何よりも、誠実な、優しさ。
その言葉が、フィーナの心の中で、最後の、砦となっていた、なけなしの理性の壁を、完全に、打ち砕いた。
「…う…うわああああああ……ケンタさ…ん……!」
フィーナは、健太の胸に、顔をうずめると、今度こそ、声を上げて、わんわんと、まるで、子供のように、泣いた。
それは、故郷を失った、絶望の涙だった。
それは、自らの罪を、改めて、自覚した、後悔の涙だった。
そして、それは、この、地獄のような世界で、自分は、もう、一人ではないのだと、知ることができた、安堵の涙でも、あった。
健太は、そんな彼女の、小さな背中を、ただ、黙って、優しく、撫でていた。
空が、ゆっくりと、夕焼けに、染まり始めていた。
それは、鎮魂の炎のように、どこまでも、赤く、そして、静かに、滅びてしまった、この都を、優しく、照らし出していく。
その、夕焼け独特の、全てを、赦すかのような、穏やかな光の中で。
一行は、ただ、静かに、そこにいた。
泣き疲れて、健太の腕の中で、眠ってしまった、一人の少女の、穏やかな寝息と、仲間たちの、静かな呼吸の音だけが、風の音に、混じり合っていた。
やがて、フィーナが、落ち着いた頃。
ルミナが、不意に、何かに気づいた。
「…待ってください。この、空気…」
彼女は、鼻を、くんくんと、ひくつかせた。
「これは…ただの、死の匂いではない。微かに、ですが、非常に、強力な、魔力の残滓が、この土地に、染みついている…! それも、ただの魔族のものではない。もっと、上位の…!」
彼女の視線の先、巨大なクレーターの、その中心部。
夕日の最後の光が、そこに落ちていた、何か、黒い、金属片のようなものを、鈍く、反射させていた。
それは、禍々しい、見たこともない紋章が刻まれた、巨大な鎧の、破片だった。
そして、その破片からは、今もなお、この地の、全ての生命を、拒絶するかのような、邪悪で、冷たいオーラが、放たれていた。
それは、一行が、これから、対峙することになる、新たな、そして、遥かに強大な敵の存在を、明確に示唆するものだった。
絶望の底で、彼らは、新たな、戦いの、始まりを、予感していた。
0
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

40歳のおじさん 旅行に行ったら異世界でした どうやら私はスキル習得が早いようです
カムイイムカ(神威異夢華)
ファンタジー
部長に傷つけられ続けた私
とうとうキレてしまいました
なんで旅行ということで大型連休を取ったのですが
飛行機に乗って寝て起きたら異世界でした……
スキルが簡単に得られるようなので頑張っていきます

最低のEランクと追放されたけど、実はEXランクの無限増殖で最強でした。
みこみこP
ファンタジー
高校2年の夏。
高木華音【男】は夏休みに入る前日のホームルーム中にクラスメイトと共に異世界にある帝国【ゼロムス】に魔王討伐の為に集団転移させれた。
地球人が異世界転移すると必ずDランクからAランクの固有スキルという世界に1人しか持てないレアスキルを授かるのだが、華音だけはEランク・【ムゲン】という存在しない最低ランクの固有スキルを授かったと、帝国により死の森へ捨てられる。
しかし、華音の授かった固有スキルはEXランクの無限増殖という最強のスキルだったが、本人は弱いと思い込み、死の森を生き抜く為に無双する。

備蓄スキルで異世界転移もナンノソノ
ちかず
ファンタジー
久しぶりの早帰りの金曜日の夜(但し、矢作基準)ラッキーの連続に浮かれた矢作の行った先は。
見た事のない空き地に1人。異世界だと気づかない矢作のした事は?
異世界アニメも見た事のない矢作が、自分のスキルに気づく日はいつ来るのだろうか。スキル【備蓄】で異世界に騒動を起こすもちょっぴりズレた矢作はそれに気づかずマイペースに頑張るお話。
鈍感な主人公が降り注ぐ困難もナンノソノとクリアしながら仲間を増やして居場所を作るまで。

異世界に移住することになったので、異世界のルールについて学ぶことになりました!
心太黒蜜きな粉味
ファンタジー
※完結しました。感想をいただけると、今後の励みになります。よろしくお願いします。
これは、今まで暮らしていた世界とはかなり異なる世界に移住することになった僕の話である。
ようやく再就職できた会社をクビになった僕は、不気味な影に取り憑かれ、異世界へと運ばれる。
気がつくと、空を飛んで、口から火を吐いていた!
これは?ドラゴン?
僕はドラゴンだったのか?!
自分がドラゴンの先祖返りであると知った僕は、超絶美少女の王様に「もうヒトではないからな!異世界に移住するしかない!」と告げられる。
しかも、この世界では衣食住が保障されていて、お金や結婚、戦争も無いというのだ。なんて良い世界なんだ!と思ったのに、大いなる呪いがあるって?
この世界のちょっと特殊なルールを学びながら、僕は呪いを解くため7つの国を巡ることになる。
※派手なバトルやグロい表現はありません。
※25話から1話2000文字程度で基本毎日更新しています。
※なろうでも公開しています。

【完結】幼馴染にフラれて異世界ハーレム風呂で優しく癒されてますが、好感度アップに未練タラタラなのが役立ってるとは気付かず、世界を救いました。
三矢さくら
ファンタジー
【本編完結】⭐︎気分どん底スタート、あとはアガるだけの異世界純情ハーレム&バトルファンタジー⭐︎
長年思い続けた幼馴染にフラれたショックで目の前が全部真っ白になったと思ったら、これ異世界召喚ですか!?
しかも、フラれたばかりのダダ凹みなのに、まさかのハーレム展開。まったくそんな気分じゃないのに、それが『シキタリ』と言われては断りにくい。毎日混浴ですか。そうですか。赤面しますよ。
ただ、召喚されたお城は、落城寸前の風前の灯火。伝説の『マレビト』として召喚された俺、百海勇吾(18)は、城主代行を任されて、城に襲い掛かる謎のバケモノたちに立ち向かうことに。
といっても、発現するらしいチートは使えないし、お城に唯一いた呪術師の第4王女様は召喚の呪術の影響で、眠りっ放し。
とにかく、俺を取り囲んでる女子たちと、お城の皆さんの気持ちをまとめて闘うしかない!
フラれたばかりで、そんな気分じゃないんだけどなぁ!

最初から最強ぼっちの俺は英雄になります
総長ヒューガ
ファンタジー
いつも通りに一人ぼっちでゲームをしていた、そして疲れて寝ていたら、人々の驚きの声が聞こえた、目を開けてみるとそこにはゲームの世界だった、これから待ち受ける敵にも勝たないといけない、予想外の敵にも勝たないといけないぼっちはゲーム内の英雄になれるのか!
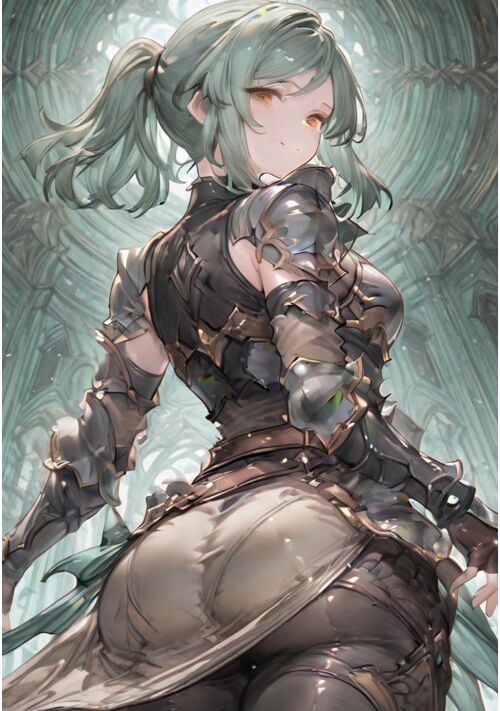
【完結】うだつが上がらない底辺冒険者だったオッサンは命を燃やして強くなる
邪代夜叉(ヤシロヤシャ)
ファンタジー
まだ遅くない。
オッサンにだって、未来がある。
底辺から這い上がる冒険譚?!
辺鄙の小さな村に生まれた少年トーマは、幼い頃にゴブリン退治で村に訪れていた冒険者に憧れ、いつか自らも偉大な冒険者となることを誓い、十五歳で村を飛び出した。
しかし現実は厳しかった。
十数年の時は流れてオッサンとなり、その間、大きな成果を残せず“とんまのトーマ”と不名誉なあだ名を陰で囁かれ、やがて採取や配達といった雑用依頼ばかりこなす、うだつの上がらない底辺冒険者生活を続けていた。
そんなある日、荷車の護衛の依頼を受けたトーマは――
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















