7 / 35
第7話:それぞれの夏を目指す理由
しおりを挟む
職員室前の廊下は、外の陽射しとは裏腹に、ひんやりとした空気が漂っていた。
風祭球児は、壁にもたれて腕を組み、ぼんやりと窓の外を見ていた。グラウンドでは、他の部活の掛け声が賑やかに響いている。
「……俺が行って意味あるのか?」
ぽつりと呟いた声に、横に立つ千紗が振り返る。
「あるよ。風祭くんは、今や野球部の一員なんだから」
球児は少し視線を外しながらも、「……そうかね」とだけ返す。
隣で三島は、汗ばむ手のひらをズボンで拭いていた。
■
職員室のドアの前。
木の扉の向こうからは、校長の低くしわがれた声がかすかに漏れていた。
その前で、三島大地はまっすぐ立っていた。
とはいえ、その内心は、嵐のように揺れていた。
左手は、制服のポケットの中でぎゅっと拳を握っている。
手のひらにはうっすら汗がにじみ、心臓はさっきからずっと落ち着いてくれなかった。
(言えよ……言うって決めただろ。何のためにここまで来たんだ)
何度も頭の中で繰り返す。だが、声にならない。
ただ、“情けない自分”の記憶が、次々と甦る。
──一年前。
3年の先輩たちが引退し、自分が主将に任命された日。
監督は「お前しかいない」と笑ったけど、内心では“なり手が他にいなかっただけ”とわかっていた。
実力も、統率力も、技術も中の下。
声だけは大きいから目立つけど、正直、キャプテンに向いていると思ったことなんて、一度もない。
(風祭が来たときも、内心ホッとしてた。やっと、本物の“野球選手”が来てくれたって)
でも、球児は距離を取っていて、コーチみたいに冷静で。
自分が三振して泣いたときも、何も言わず、黙っていた。
あの沈黙が、何より堪えた。
(でも……逃げたくなかった)
たとえ誰かに頼られているだけでも、期待されてなくても、
自分は「桜が丘の主将」でいるって、あの日決めた。
練習終わりにこっそり素振りを続けてきたのも、
みんなの背中に、自分が立ってるって思いたかったからだ。
「よし……言うぞ」
深く、深く息を吸い込んだ。
(チームのためにやります、って……それだけ伝えればいい)
言葉が上手くなくてもいい。誰かみたいに理路整然と話せなくても。
“伝えること”が、今の自分にできるすべてなんだ。
コン、コン。
ノックの音が、静かな廊下に響いた。
三島は、震えそうになる膝に力を入れて、一歩、扉の向こうへ足を踏み出した。
たとえ拙くてもいい──この夏を、みんなで“前に進む夏”にするために。
■
「じゃあ、行くぞ」
こくりと千紗がうなずき、三島が扉をノックする。
「失礼します!」
重たいドアがゆっくりと開き、職員室の中の冷気が一気に流れ出てきた。
校長席の奥、書類の山の向こうに、長谷川校長は座っていた。
年季の入った眼鏡を押し上げると、無表情で三人を見渡す。
「……なんだね?」
三島が一歩前に出て、深く頭を下げた。
「僕たち、今年の夏の大会にエントリーさせてください。正式な許可と、部費の追加もお願いに来ました!」
校長は静かにペンを置き、書類を数枚めくってから口を開いた。
「桜が丘野球部……ここ十年、初戦敗退ばかりの記録しかないが?」
「……それは、はい、事実です」
三島の声が少し震える。
「でも、それでも僕たちは、今、必死に変わろうとしてます! 逃げずに、本気で野球に向き合いたいんです!」
校長は机に肘をついたまま、興味なさげにため息をつく。
「本気、ねえ。じゃあ聞くが──何のために“夏”を目指すのかね? 結果が見えてる勝負に、意味があると?」
静まりかえった室内で、千紗が小さく吸い込み、震える声で言葉を繋いだ。
「……意味、あると思います」
校長の視線が千紗に向く。
「意味は……結果じゃないんです。私たちは、きっと……“野球を好きでい続けたい”だけなんです。勝ち負けじゃなくて、ちゃんと、向き合いたいんです」
彼女の目には、うっすらと涙が浮かんでいた。
「この夏を逃したら……きっと、誰かが諦めてしまう。その姿を、私はもう見たくないんです……」
風祭は横で、何も言わずに聞いていた。心の奥に、何かが少しだけ熱くなるのを感じた。
しばらくの沈黙ののち、校長は椅子を少し軋ませて背もたれに体を預けた。
「……分かった。今年の夏だけ、特別に許可しよう。ただし──“本気”を証明できるなら、だ」
三島と千紗は、同時に頭を深く下げる。
「ありがとうございますっ!」
■
夕暮れの職員室に、静寂が戻っていた。
壁の時計が午後五時を回り、窓の外では部活動の声が遠くに聞こえる。
長谷川校長は眼鏡を外し、そっと机の上に置いた。
「まったく……今どきの生徒は、熱すぎるのも困りものだな」
苦笑いしながら、先ほど受け取った書類の束を見つめる。
桜が丘高校野球部──夏の大会エントリー申請書。その紙の端には、震えた文字で記された三島主将の署名があった。
「本気でやりたい」
「負けてもいいから挑みたい」
「今しかできないことだから」
あの子たちが並んで訴えた言葉が、耳に残っていた。
ふと、目線が棚の奥にある古びたボールに向いた。色褪せた縫い目。皮が少し剥げた硬式球。
あれは、まだ彼が“先生”でも“校長”でもなく、ただの野球少年だった頃、最後の夏に握ったボールだった。
──県大会三回戦。0対1で敗退。最後の打席は空振り三振。
あの悔しさを、ずっと「時間が解決する」と言い聞かせてきた。
でも、本当は忘れてなどいなかった。
「……あのとき、誰かが“行け”って背中を押してくれたら、もう一球、バットを振れてたかもしれんな」
誰に聞かせるわけでもなく、呟いた声が静かに職員室に響いた。
長谷川は静かに椅子から立ち上がり、申請書の最終ページに目を通す。
そこには、空欄のままの「エースナンバー」の欄。
「ふむ。まだ“背番号1”が決まっていないか……まあ、それも悪くない」
ペンを取り出すと、赤いインクで書類の承認欄に印を押した。
「たまには……負けると分かっていても挑むのも、いいもんだな」
小さく笑い、机に再び眼鏡を戻す。
遠くで聞こえるキャッチボールの音に、昔の夏が少しだけ重なった。
あのボールの音は、いつの時代も、誰かの“はじまり”の音なのかもしれない。
古びた硬式ボールを手に取ると、ひんやりとした感触が掌に残った。
長谷川校長は、ふっと息をつきながら椅子に腰を下ろし、遠い記憶を探るように窓の外を見つめた。
──昭和五十年、夏。
彼は、桜南高校の三番打者だった。
守備はサード。打率は並だったが、選球眼と粘りでチームに貢献するタイプの選手だった。
あの年、初めて三回戦まで進んだ。
相手は、強豪・青葉学園。エースは甲子園常連の速球派で、プロからも注目されていた。
「お前たちは雑草だ。だが、雑草には雑草の強さがある」
そう口癖のように言っていたのは、当時の監督、志村先生だった。
背中を丸めた小柄な男で、無駄話もせず、いつも黙ってグラウンドを歩いていた。
ただ、その目だけは、いつも“本気”を探していた。
その試合。
長谷川は、九回裏ツーアウト、ランナー二塁という場面で打席に立った。
点差は1点。
ベンチに戻る前、志村先生は一言だけこう言った。
「楽しめ」
それだけだった。
──結果は、三球三振。
バットは振った。だが、心が追いつかなかった。
あのとき、もう少し誰かに“背中を押してもらえたら”と思った。
振り遅れた最後のストレートが、今でも夢に出ることがある。
「志村先生……あんたなら、今のこの子たちに、なんて言うだろうな」
硬球を手のひらで転がしながら、長谷川は独り言のように呟いた。
「“楽しめ”か……。だとしたら、俺はまだその答えに届いてないかもしれん」
外では夕焼けがグラウンドを染め、部活動の掛け声が風に乗って聞こえてくる。
窓の向こう、野球部のバックネットには、ボロボロの横断幕がまだ残っていた。
“挑戦は、終わらせなければ終わらない”
あれは志村先生が去った翌年、教え子たちが勝手に作ったものだ。
「……結局、まだ俺も、挑戦の途中なのかもな」
長谷川はボールを棚に戻すと、ペンを取り、次の書類に目を落とした。
そこには、「桜が丘高校野球部、夏季大会エントリー届」と書かれていた。
今度こそ、“挑む”背中に印をつける番だ。
■
職員室を出ると、午後の光が目に眩しかった。
三島は息を吐き、くしゃくしゃになった書類を胸元でぎゅっと抱えた。
職員室の空気は重く、張りつめていた。
夏の大会エントリーを直談判する場面で、千紗は思わず声を震わせ、涙ぐんでしまった。
必死に言葉を紡ぎながらも、こみあげてくる感情は止められなかった。
「……私たちは、ちゃんと向き合いたいんです」
そう言った瞬間、机の下で両手に握りしめていたハンカチが、きゅっと湿った。
校長の許可が下りたあと、三人は無言で職員室を出た。
廊下を曲がったところで、千紗はそっと一人、立ち止まる。
グッと目を閉じ、ポケットからそのハンカチを取り出す。
淡い水色の、少しほつれた縁取り。古びた刺繍で「S.N.」と書かれていた。
それは兄・修司が中学三年の夏、最後の大会で使っていたものだった。
──「これ、貸してやるよ。試合の時、手ぇ汗かくだろ?」
そう言って渡されたその日、兄はユニフォームの背中が泥だらけになるまでグラウンドを走り、
最後の打席で三振し、ベンチで人目を忍んで泣いていた。
夜、部屋でこっそり千紗に言ったのだ。
「悔しくて泣くのも、嬉しくて泣くのも、野球の中にあるんだよ。たぶん、野球って、そういうもんなんだ」
だから千紗は、その言葉をずっと胸にしまっていた。
そしてハンカチを、今でもカバンの中に入れていた。
職員室では情けないほどに涙が出てしまったけれど──
「……泣いて、よかったかも」
千紗はふと、笑ってそう呟いた。
ポケットにハンカチを戻し、もう一度背筋を伸ばす。
先を歩く球児の背中を見つめる。どこか影を抱えながらも、真っ直ぐな背中。
「風祭くんも……悔しくて泣いたこと、あるのかな」
彼のことを少しずつ知っていくうちに、千紗の中で、ただの転校生ではなくなっていた。
重い荷物を背負って、それでも“何か”に向かおうとしている、その姿が。
ハンカチの中に詰まっていた想いが、今、少しだけ形を変えて、千紗の胸の奥に届いた気がした。
「はあ……言えた。マジで、緊張した……」
「よく頑張ったよ、三島くん。私、泣いちゃってごめん……」
「いや、あの涙のおかげで校長ちょっと引いてた」
三人で笑いあいながら歩き出す。その背中には、ほんの少しだけ自信が宿っていた。
ただ──
球児はふと、ポケットの中から一枚の控え書類を取り出す。
部員名、学年、背番号、ポジション欄。
「ピッチャー」の枠だけが、空白のままだ。
「……俺が投げる理由、まだ見つかってない」
ぽつりと漏らした言葉に、千紗は何も言わなかった。ただ、彼の隣を、同じ歩幅で静かに歩いていた。
真夏の予感を孕んだ風が、ほんの少しだけ優しかった。
■
職員室での校長との直談判が終わった後。
午後の校舎から、夕焼け色がじんわりと滲んでいく。
風祭球児は一人、昇降口の階段に腰を下ろしていた。
手にしていたのは、校長の許可を得て返された「夏季大会エントリー名簿」の控え用紙。
そこには、部員の名前と学年、そしてポジション欄が並んでいた。
──「1 投手」──その枠だけが、ぽっかりと空白だった。
球児はじっと、その欄を見つめる。
ペンを持つ右手が、用紙の上をゆっくり滑る。けれど、文字は書かれない。
「……まだ、投げていいのか、俺には分かんねぇよ」
呟いた声は、誰にも届かない。
まるで自分に言い聞かせるように、球児は目を伏せた。
その夜、自室の机。
風呂上がりの濡れた髪を無造作にタオルで拭きながら、球児はふと机の引き出しを開ける。
中から取り出したのは、くたびれた黒表紙のノート。
中学時代からずっと使っている、いわば“野球記録帳”だった。
「フォーム、スイング軌道、リリース位置、投球間隔、バント処理……」
びっしりと書かれた手書きの分析メモ。その隙間を縫うように、今のチームメンバーの特徴も追加されていた。
三島のグリップの高さ。
捕手の配球意図のクセ。
部員ひとりひとりの投球対応や守備範囲。
読み返すうちに、自分がいつの間にか“他人のためにノートを使い始めていた”ことに気づく。
それは、少しだけ──怖いことでもあった。
ペンを取る。
ノートの新しいページを開いて、球児は静かに一行を書き足す。
「まだ、迷ってる。でも、誰かのために投げるって感覚は──ちょっと悪くない」
書き終えたその言葉を、何度か読み返し、ふっと笑った。
「……やっぱ、俺は“投げる”のが好きなんだな」
遠くから、夜風がカーテンを揺らす。
その音が、どこかグラウンドの風の音に似ていた。
風祭球児は、壁にもたれて腕を組み、ぼんやりと窓の外を見ていた。グラウンドでは、他の部活の掛け声が賑やかに響いている。
「……俺が行って意味あるのか?」
ぽつりと呟いた声に、横に立つ千紗が振り返る。
「あるよ。風祭くんは、今や野球部の一員なんだから」
球児は少し視線を外しながらも、「……そうかね」とだけ返す。
隣で三島は、汗ばむ手のひらをズボンで拭いていた。
■
職員室のドアの前。
木の扉の向こうからは、校長の低くしわがれた声がかすかに漏れていた。
その前で、三島大地はまっすぐ立っていた。
とはいえ、その内心は、嵐のように揺れていた。
左手は、制服のポケットの中でぎゅっと拳を握っている。
手のひらにはうっすら汗がにじみ、心臓はさっきからずっと落ち着いてくれなかった。
(言えよ……言うって決めただろ。何のためにここまで来たんだ)
何度も頭の中で繰り返す。だが、声にならない。
ただ、“情けない自分”の記憶が、次々と甦る。
──一年前。
3年の先輩たちが引退し、自分が主将に任命された日。
監督は「お前しかいない」と笑ったけど、内心では“なり手が他にいなかっただけ”とわかっていた。
実力も、統率力も、技術も中の下。
声だけは大きいから目立つけど、正直、キャプテンに向いていると思ったことなんて、一度もない。
(風祭が来たときも、内心ホッとしてた。やっと、本物の“野球選手”が来てくれたって)
でも、球児は距離を取っていて、コーチみたいに冷静で。
自分が三振して泣いたときも、何も言わず、黙っていた。
あの沈黙が、何より堪えた。
(でも……逃げたくなかった)
たとえ誰かに頼られているだけでも、期待されてなくても、
自分は「桜が丘の主将」でいるって、あの日決めた。
練習終わりにこっそり素振りを続けてきたのも、
みんなの背中に、自分が立ってるって思いたかったからだ。
「よし……言うぞ」
深く、深く息を吸い込んだ。
(チームのためにやります、って……それだけ伝えればいい)
言葉が上手くなくてもいい。誰かみたいに理路整然と話せなくても。
“伝えること”が、今の自分にできるすべてなんだ。
コン、コン。
ノックの音が、静かな廊下に響いた。
三島は、震えそうになる膝に力を入れて、一歩、扉の向こうへ足を踏み出した。
たとえ拙くてもいい──この夏を、みんなで“前に進む夏”にするために。
■
「じゃあ、行くぞ」
こくりと千紗がうなずき、三島が扉をノックする。
「失礼します!」
重たいドアがゆっくりと開き、職員室の中の冷気が一気に流れ出てきた。
校長席の奥、書類の山の向こうに、長谷川校長は座っていた。
年季の入った眼鏡を押し上げると、無表情で三人を見渡す。
「……なんだね?」
三島が一歩前に出て、深く頭を下げた。
「僕たち、今年の夏の大会にエントリーさせてください。正式な許可と、部費の追加もお願いに来ました!」
校長は静かにペンを置き、書類を数枚めくってから口を開いた。
「桜が丘野球部……ここ十年、初戦敗退ばかりの記録しかないが?」
「……それは、はい、事実です」
三島の声が少し震える。
「でも、それでも僕たちは、今、必死に変わろうとしてます! 逃げずに、本気で野球に向き合いたいんです!」
校長は机に肘をついたまま、興味なさげにため息をつく。
「本気、ねえ。じゃあ聞くが──何のために“夏”を目指すのかね? 結果が見えてる勝負に、意味があると?」
静まりかえった室内で、千紗が小さく吸い込み、震える声で言葉を繋いだ。
「……意味、あると思います」
校長の視線が千紗に向く。
「意味は……結果じゃないんです。私たちは、きっと……“野球を好きでい続けたい”だけなんです。勝ち負けじゃなくて、ちゃんと、向き合いたいんです」
彼女の目には、うっすらと涙が浮かんでいた。
「この夏を逃したら……きっと、誰かが諦めてしまう。その姿を、私はもう見たくないんです……」
風祭は横で、何も言わずに聞いていた。心の奥に、何かが少しだけ熱くなるのを感じた。
しばらくの沈黙ののち、校長は椅子を少し軋ませて背もたれに体を預けた。
「……分かった。今年の夏だけ、特別に許可しよう。ただし──“本気”を証明できるなら、だ」
三島と千紗は、同時に頭を深く下げる。
「ありがとうございますっ!」
■
夕暮れの職員室に、静寂が戻っていた。
壁の時計が午後五時を回り、窓の外では部活動の声が遠くに聞こえる。
長谷川校長は眼鏡を外し、そっと机の上に置いた。
「まったく……今どきの生徒は、熱すぎるのも困りものだな」
苦笑いしながら、先ほど受け取った書類の束を見つめる。
桜が丘高校野球部──夏の大会エントリー申請書。その紙の端には、震えた文字で記された三島主将の署名があった。
「本気でやりたい」
「負けてもいいから挑みたい」
「今しかできないことだから」
あの子たちが並んで訴えた言葉が、耳に残っていた。
ふと、目線が棚の奥にある古びたボールに向いた。色褪せた縫い目。皮が少し剥げた硬式球。
あれは、まだ彼が“先生”でも“校長”でもなく、ただの野球少年だった頃、最後の夏に握ったボールだった。
──県大会三回戦。0対1で敗退。最後の打席は空振り三振。
あの悔しさを、ずっと「時間が解決する」と言い聞かせてきた。
でも、本当は忘れてなどいなかった。
「……あのとき、誰かが“行け”って背中を押してくれたら、もう一球、バットを振れてたかもしれんな」
誰に聞かせるわけでもなく、呟いた声が静かに職員室に響いた。
長谷川は静かに椅子から立ち上がり、申請書の最終ページに目を通す。
そこには、空欄のままの「エースナンバー」の欄。
「ふむ。まだ“背番号1”が決まっていないか……まあ、それも悪くない」
ペンを取り出すと、赤いインクで書類の承認欄に印を押した。
「たまには……負けると分かっていても挑むのも、いいもんだな」
小さく笑い、机に再び眼鏡を戻す。
遠くで聞こえるキャッチボールの音に、昔の夏が少しだけ重なった。
あのボールの音は、いつの時代も、誰かの“はじまり”の音なのかもしれない。
古びた硬式ボールを手に取ると、ひんやりとした感触が掌に残った。
長谷川校長は、ふっと息をつきながら椅子に腰を下ろし、遠い記憶を探るように窓の外を見つめた。
──昭和五十年、夏。
彼は、桜南高校の三番打者だった。
守備はサード。打率は並だったが、選球眼と粘りでチームに貢献するタイプの選手だった。
あの年、初めて三回戦まで進んだ。
相手は、強豪・青葉学園。エースは甲子園常連の速球派で、プロからも注目されていた。
「お前たちは雑草だ。だが、雑草には雑草の強さがある」
そう口癖のように言っていたのは、当時の監督、志村先生だった。
背中を丸めた小柄な男で、無駄話もせず、いつも黙ってグラウンドを歩いていた。
ただ、その目だけは、いつも“本気”を探していた。
その試合。
長谷川は、九回裏ツーアウト、ランナー二塁という場面で打席に立った。
点差は1点。
ベンチに戻る前、志村先生は一言だけこう言った。
「楽しめ」
それだけだった。
──結果は、三球三振。
バットは振った。だが、心が追いつかなかった。
あのとき、もう少し誰かに“背中を押してもらえたら”と思った。
振り遅れた最後のストレートが、今でも夢に出ることがある。
「志村先生……あんたなら、今のこの子たちに、なんて言うだろうな」
硬球を手のひらで転がしながら、長谷川は独り言のように呟いた。
「“楽しめ”か……。だとしたら、俺はまだその答えに届いてないかもしれん」
外では夕焼けがグラウンドを染め、部活動の掛け声が風に乗って聞こえてくる。
窓の向こう、野球部のバックネットには、ボロボロの横断幕がまだ残っていた。
“挑戦は、終わらせなければ終わらない”
あれは志村先生が去った翌年、教え子たちが勝手に作ったものだ。
「……結局、まだ俺も、挑戦の途中なのかもな」
長谷川はボールを棚に戻すと、ペンを取り、次の書類に目を落とした。
そこには、「桜が丘高校野球部、夏季大会エントリー届」と書かれていた。
今度こそ、“挑む”背中に印をつける番だ。
■
職員室を出ると、午後の光が目に眩しかった。
三島は息を吐き、くしゃくしゃになった書類を胸元でぎゅっと抱えた。
職員室の空気は重く、張りつめていた。
夏の大会エントリーを直談判する場面で、千紗は思わず声を震わせ、涙ぐんでしまった。
必死に言葉を紡ぎながらも、こみあげてくる感情は止められなかった。
「……私たちは、ちゃんと向き合いたいんです」
そう言った瞬間、机の下で両手に握りしめていたハンカチが、きゅっと湿った。
校長の許可が下りたあと、三人は無言で職員室を出た。
廊下を曲がったところで、千紗はそっと一人、立ち止まる。
グッと目を閉じ、ポケットからそのハンカチを取り出す。
淡い水色の、少しほつれた縁取り。古びた刺繍で「S.N.」と書かれていた。
それは兄・修司が中学三年の夏、最後の大会で使っていたものだった。
──「これ、貸してやるよ。試合の時、手ぇ汗かくだろ?」
そう言って渡されたその日、兄はユニフォームの背中が泥だらけになるまでグラウンドを走り、
最後の打席で三振し、ベンチで人目を忍んで泣いていた。
夜、部屋でこっそり千紗に言ったのだ。
「悔しくて泣くのも、嬉しくて泣くのも、野球の中にあるんだよ。たぶん、野球って、そういうもんなんだ」
だから千紗は、その言葉をずっと胸にしまっていた。
そしてハンカチを、今でもカバンの中に入れていた。
職員室では情けないほどに涙が出てしまったけれど──
「……泣いて、よかったかも」
千紗はふと、笑ってそう呟いた。
ポケットにハンカチを戻し、もう一度背筋を伸ばす。
先を歩く球児の背中を見つめる。どこか影を抱えながらも、真っ直ぐな背中。
「風祭くんも……悔しくて泣いたこと、あるのかな」
彼のことを少しずつ知っていくうちに、千紗の中で、ただの転校生ではなくなっていた。
重い荷物を背負って、それでも“何か”に向かおうとしている、その姿が。
ハンカチの中に詰まっていた想いが、今、少しだけ形を変えて、千紗の胸の奥に届いた気がした。
「はあ……言えた。マジで、緊張した……」
「よく頑張ったよ、三島くん。私、泣いちゃってごめん……」
「いや、あの涙のおかげで校長ちょっと引いてた」
三人で笑いあいながら歩き出す。その背中には、ほんの少しだけ自信が宿っていた。
ただ──
球児はふと、ポケットの中から一枚の控え書類を取り出す。
部員名、学年、背番号、ポジション欄。
「ピッチャー」の枠だけが、空白のままだ。
「……俺が投げる理由、まだ見つかってない」
ぽつりと漏らした言葉に、千紗は何も言わなかった。ただ、彼の隣を、同じ歩幅で静かに歩いていた。
真夏の予感を孕んだ風が、ほんの少しだけ優しかった。
■
職員室での校長との直談判が終わった後。
午後の校舎から、夕焼け色がじんわりと滲んでいく。
風祭球児は一人、昇降口の階段に腰を下ろしていた。
手にしていたのは、校長の許可を得て返された「夏季大会エントリー名簿」の控え用紙。
そこには、部員の名前と学年、そしてポジション欄が並んでいた。
──「1 投手」──その枠だけが、ぽっかりと空白だった。
球児はじっと、その欄を見つめる。
ペンを持つ右手が、用紙の上をゆっくり滑る。けれど、文字は書かれない。
「……まだ、投げていいのか、俺には分かんねぇよ」
呟いた声は、誰にも届かない。
まるで自分に言い聞かせるように、球児は目を伏せた。
その夜、自室の机。
風呂上がりの濡れた髪を無造作にタオルで拭きながら、球児はふと机の引き出しを開ける。
中から取り出したのは、くたびれた黒表紙のノート。
中学時代からずっと使っている、いわば“野球記録帳”だった。
「フォーム、スイング軌道、リリース位置、投球間隔、バント処理……」
びっしりと書かれた手書きの分析メモ。その隙間を縫うように、今のチームメンバーの特徴も追加されていた。
三島のグリップの高さ。
捕手の配球意図のクセ。
部員ひとりひとりの投球対応や守備範囲。
読み返すうちに、自分がいつの間にか“他人のためにノートを使い始めていた”ことに気づく。
それは、少しだけ──怖いことでもあった。
ペンを取る。
ノートの新しいページを開いて、球児は静かに一行を書き足す。
「まだ、迷ってる。でも、誰かのために投げるって感覚は──ちょっと悪くない」
書き終えたその言葉を、何度か読み返し、ふっと笑った。
「……やっぱ、俺は“投げる”のが好きなんだな」
遠くから、夜風がカーテンを揺らす。
その音が、どこかグラウンドの風の音に似ていた。
1
あなたにおすすめの小説

【完結】イケメンが邪魔して本命に告白できません
竹柏凪紗
青春
高校の入学式、芸能コースに通うアイドルでイケメンの如月風磨が普通科で目立たない最上碧衣の教室にやってきた。女子たちがキャーキャー騒ぐなか、風磨は碧衣の肩を抱き寄せ「お前、今日から俺の女な」と宣言する。その真意とウソつきたちによって複雑になっていく2人の結末とは──

美味しいコーヒーの愉しみ方 Acidity and Bitterness
碧井夢夏
ライト文芸
<第五回ライト文芸大賞 最終選考・奨励賞>
住宅街とオフィスビルが共存するとある下町にある定食屋「まなべ」。
看板娘の利津(りつ)は毎日忙しくお店を手伝っている。
最近隣にできたコーヒーショップ「The Coffee Stand Natsu」。
どうやら、店長は有名なクリエイティブ・ディレクターで、脱サラして始めたお店らしく……?
神の舌を持つ定食屋の娘×クリエイティブ界の神と呼ばれた男 2人の出会いはやがて下町を変えていく――?
定食屋とコーヒーショップ、時々美容室、を中心に繰り広げられる出会いと挫折の物語。
過激表現はありませんが、重めの過去が出ることがあります。
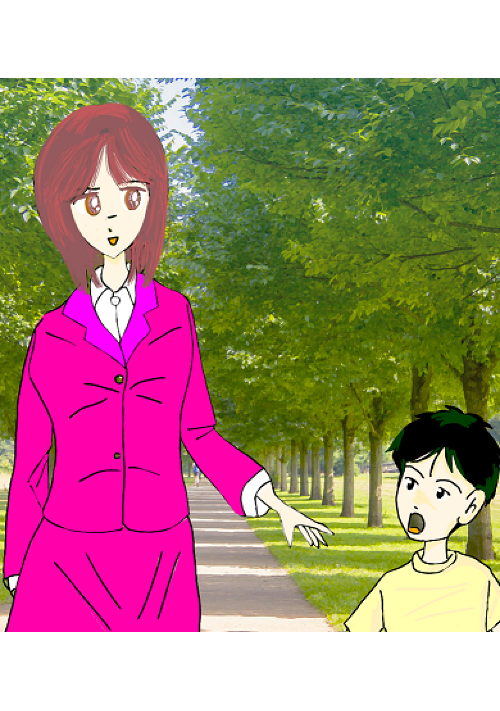
初恋の先生と結婚する為に幼稚園児からやり直すことになった俺
NOV
恋愛
俺の名前は『五十鈴 隆』 四十九歳の独身だ。
俺は最近、リストラにあい、それが理由で新たな職も探すことなく引きこもり生活が続いていた。
そんなある日、家に客が来る。
その客は喪服を着ている女性で俺の小・中学校時代の大先輩の鎌田志保さんだった。
志保さんは若い頃、幼稚園の先生をしていたんだが……
その志保さんは今から『幼稚園の先生時代』の先輩だった人の『告別式』に行くということだった。
しかし告別式に行く前にその亡くなった先輩がもしかすると俺の知っている先生かもしれないと思い俺に確認しに来たそうだ。
でも亡くなった先生の名前は『山本香織』……俺は名前を聞いても覚えていなかった。
しかし志保さんが帰り際に先輩の旧姓を言った途端、俺の身体に衝撃が走る。
旧姓「常谷香織」……
常谷……つ、つ、つねちゃん!! あの『つねちゃん』が……
亡くなった先輩、その人こそ俺が大好きだった人、一番お世話になった人、『常谷香織』先生だったのだ。
その時から俺の頭のでは『つねちゃん』との思い出が次から次へと甦ってくる。
そして俺は気付いたんだ。『つねちゃん』は俺の初恋の人なんだと……
それに気付くと同時に俺は卒園してから一度も『つねちゃん』に会っていなかったことを後悔する。
何で俺はあれだけ好きだった『つねちゃん』に会わなかったんだ!?
もし会っていたら……ずっと付き合いが続いていたら……俺がもっと大事にしていれば……俺が『つねちゃん』と結婚していたら……俺が『つねちゃん』を幸せにしてあげたかった……
あくる日、最近、頻繁に起こる頭痛に悩まされていた俺に今までで一番の激痛が起こった!!
あまりの激痛に布団に潜り込み目を閉じていたが少しずつ痛みが和らいできたので俺はゆっくり目を開けたのだが……
目を開けた瞬間、どこか懐かしい光景が目の前に現れる。
何で部屋にいるはずの俺が駅のプラットホームにいるんだ!?
母さんが俺よりも身長が高いうえに若く見えるぞ。
俺の手ってこんなにも小さかったか?
そ、それに……な、なぜ俺の目の前に……あ、あの、つねちゃんがいるんだ!?
これは夢なのか? それとも……

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

天才天然天使様こと『三天美女』の汐崎真凜に勝手に婚姻届を出され、いつの間にか天使の旦那になったのだが...。【動画投稿】
田中又雄
恋愛
18の誕生日を迎えたその翌日のこと。
俺は分籍届を出すべく役所に来ていた...のだが。
「えっと...結論から申し上げますと...こちらの手続きは不要ですね」「...え?どういうことですか?」「昨日、婚姻届を出されているので親御様とは別の戸籍が作られていますので...」「...はい?」
そうやら俺は知らないうちに結婚していたようだった。
「あの...相手の人の名前は?」
「...汐崎真凛様...という方ですね」
その名前には心当たりがあった。
天才的な頭脳、マイペースで天然な性格、天使のような見た目から『三天美女』なんて呼ばれているうちの高校のアイドル的存在。
こうして俺は天使との-1日婚がスタートしたのだった。

【完結】年収三百万円台のアラサー社畜と総資産三億円以上の仮想通貨「億り人」JKが湾岸タワーマンションで同棲したら
瀬々良木 清
ライト文芸
主人公・宮本剛は、都内で働くごく普通の営業系サラリーマン。いわゆる社畜。
タワーマンションの聖地・豊洲にあるオフィスへ通勤しながらも、自分の給料では絶対に買えない高級マンションたちを見上げながら、夢のない毎日を送っていた。
しかしある日、会社の近所で苦しそうにうずくまる女子高生・常磐理瀬と出会う。理瀬は女子高生ながら仮想通貨への投資で『億り人』となった天才少女だった。
剛の何百倍もの資産を持ち、しかし心はまだ未完成な女子高生である理瀬と、日に日に心が枯れてゆくと感じるアラサー社畜剛が織りなす、ちぐはぐなラブコメディ。

17歳男子高生と32歳主婦の境界線
MisakiNonagase
恋愛
32歳主婦のカレンはインスタグラムで20歳大学生の晴人と知り合う。親密な関係となった3度目のデートのときに、晴人が実は17歳の高校2年生だと知る。
カレンと晴人はその後、どうなる?

一億円の花嫁
藤谷 郁
恋愛
奈々子は家族の中の落ちこぼれ。
父親がすすめる縁談を断り切れず、望まぬ結婚をすることになった。
もうすぐ自由が無くなる。せめて最後に、思いきり贅沢な時間を過ごそう。
「きっと、素晴らしい旅になる」
ずっと憧れていた高級ホテルに到着し、わくわくする奈々子だが……
幸か不幸か!?
思いもよらぬ、運命の出会いが待っていた。
※エブリスタさまにも掲載
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















