1 / 56
第一話:霊 瑞香
妖怪三人組
しおりを挟む
一
麻布十番は一本松の三叉路、江戸初期には『首吊塚』とも呼ばれていた。
なぜ首吊塚と呼ばれるようになったかには諸説あるが、その一つに、関ヶ原の合戦で送られてきた首を家康が検分して埋めたからとも言われているが、しかし。
本当は何があったのか、太郎にそれとなく聞いてみても、彼は口を薄く開けて笑うだけで言う気はさらさら無いようで、その目はまったく笑っていなかった。
麻布とは室町時代からあった町で、民家のほとんどは茅葺が主流、荷を引くものといえば牛車、その牛車で米俵を運んでいるのどかなところであった。
明暦の大火以降に街が整備され武家屋敷が建つようになった頃から懐かしい田舎町風景は一部のみぞとなり、おハイソな街へと変貌を遂げてしまったのである。現在ではその頃の面影はないに等しい。
そんなところに夜中の十二時を過ぎてから闇に紛れるようにひっそりと現れるこぢんまりとした一軒の古い民家があった。
背の高い建物の影になる位置に、夜闇に紛れ込み、瞬きを一つしているうちに、ちょっと他に気を取られているうちに、六畳一間程度しかないそれはそれは小さな茅葺屋根の民家がふうっと闇夜の中に現れるのである。
しかし、この民家に居座っているものは人ではない。
そうこうしているうちに影の内から垂れる水のようにつぅっと民家の前に姿を現したのは、お洒落な長羽織を着た細身の男。腰には刀がぶらさがっている。
仲間内では『メロンソーダ侍』通称『侍(ざむらい)』と呼ばれている。侍風ではあるが生前は侍ではない。大店の長男坊として生まれたのに大して働かずに遊び放題に遊んで家族はもちろん方方に迷惑ばかりかけていた放蕩息子であった。
「よっこらせ」と掛け声をかけながら建て付けの悪い引き戸を雑に開け憎めない笑顔を覗かせた。
「やいや、今日も寒いなあ。これは昭子さんのせいだよ。あれがいるから寒さが増すんだ。まったくしょうもねえ。太郎、あれだ、いつものをちょいとくんな」
「おや侍さん、今日は来るのがずいぶんと早いじゃないか。それに外はそんなに寒いのかい? 寒いのは体にこたえるからやだねえ。いつものアレだね。ちょっと待っておくれな」
しゃがれた声で返事をよこしたのはこの民家の主人、タロ太郎だ。『タロ』が苗字で『太郎』が名前だというんだからふざけている。本人はいつぞやの頃からかこの名前一本で通していて、今ではもう自分の本当の名がなんなのか、本人ですら首を傾げる始末であった。
戸を引いて家の中に入ってみるとすぐに小上がりになっていて、履物を脱いで部屋の中へと上がるシステムになっていた。
部屋の中は狭くて薄暗い。真ん中には不自然に大きなこたつが一つだけ置かれていてあとは何もない。こたつ布団には猫の柄が描かれていた。その奥が台所となっていた。
太郎はその台所にいて侍の飲み物を入れるグラスを用意していた。
侍は慣れた様子でこたつに入り込み、こたつ布団を肩まで引っ張った。
太郎はそんな様子を見て左の唇だけ上げて鼻でふんと一つ笑う。
小馬鹿にしているように見えるその笑いは彼の癖であった。
そんな太郎は長めの金髪に筋の通った鼻、切れ長の目、ぴんと背筋の伸びた立ち姿に流行りのデニムの着物がよく似合っていた。どういうわけか足元はスニーカーという不自然さには首を傾げるところである。しかし本人は全く気にしていない。
「それで、今日は誰の話を聞きたいんだい、たまちゃん」
鈴の音のような耳心地の良い声が侍が座った隣から聞こえた。そのまた隣には「たまこ」と呼ばれた年の頃は十才前後のおかっぱ頭の少女が分厚いノートを広げて鉛筆を持って待ち構えていた。
太郎と侍が話しているうちにどこからともなく二人は現れて、気付いたときにはこたつに入っていたのだ。部屋の中もいくばくか明るくなっている。
「昭子(しょうこ)さん。今日は侍さんの話を聞かせてくれる約束をした日ですよ。侍さんがどうしてここにいるようになったのか、教えてくれる日。いっつも話の途中ではぐらかすから最後まで聞けてないもん」
昭子と呼ばれたのは、先ほどの鈴の音の声の主で、紅色の振袖の打掛にお垂髪(おすべらかし)のよく似合う妖艶な雰囲気に嗅いだことのない甘い香の香りをふわりと漂わせた二十に差し掛かろうかという頃合いの女子(おなご)だ。
肌はこの世に新しく舞い落ちる輝ききった雪のごとく真っ白でとても冷たい。身体をくねらせ太郎にいつものように「あたしにはお酒をちょうだいね」と台所の奥に置いてある酒の瓶を指さした。
「はいはい。いつものですね。ちょいとお待ちを」
ちょこんと頭を下げた太郎は、侍の前にいつものメロンソーダを、昭子には日本酒を、たまこにはオレンジジュースをてきぱきと出した。
各々飲み物を手に取り一口飲むと、頼んでもいないのにおでんの皿がそれぞれの前に置かれる。
麻布十番は一本松の三叉路、江戸初期には『首吊塚』とも呼ばれていた。
なぜ首吊塚と呼ばれるようになったかには諸説あるが、その一つに、関ヶ原の合戦で送られてきた首を家康が検分して埋めたからとも言われているが、しかし。
本当は何があったのか、太郎にそれとなく聞いてみても、彼は口を薄く開けて笑うだけで言う気はさらさら無いようで、その目はまったく笑っていなかった。
麻布とは室町時代からあった町で、民家のほとんどは茅葺が主流、荷を引くものといえば牛車、その牛車で米俵を運んでいるのどかなところであった。
明暦の大火以降に街が整備され武家屋敷が建つようになった頃から懐かしい田舎町風景は一部のみぞとなり、おハイソな街へと変貌を遂げてしまったのである。現在ではその頃の面影はないに等しい。
そんなところに夜中の十二時を過ぎてから闇に紛れるようにひっそりと現れるこぢんまりとした一軒の古い民家があった。
背の高い建物の影になる位置に、夜闇に紛れ込み、瞬きを一つしているうちに、ちょっと他に気を取られているうちに、六畳一間程度しかないそれはそれは小さな茅葺屋根の民家がふうっと闇夜の中に現れるのである。
しかし、この民家に居座っているものは人ではない。
そうこうしているうちに影の内から垂れる水のようにつぅっと民家の前に姿を現したのは、お洒落な長羽織を着た細身の男。腰には刀がぶらさがっている。
仲間内では『メロンソーダ侍』通称『侍(ざむらい)』と呼ばれている。侍風ではあるが生前は侍ではない。大店の長男坊として生まれたのに大して働かずに遊び放題に遊んで家族はもちろん方方に迷惑ばかりかけていた放蕩息子であった。
「よっこらせ」と掛け声をかけながら建て付けの悪い引き戸を雑に開け憎めない笑顔を覗かせた。
「やいや、今日も寒いなあ。これは昭子さんのせいだよ。あれがいるから寒さが増すんだ。まったくしょうもねえ。太郎、あれだ、いつものをちょいとくんな」
「おや侍さん、今日は来るのがずいぶんと早いじゃないか。それに外はそんなに寒いのかい? 寒いのは体にこたえるからやだねえ。いつものアレだね。ちょっと待っておくれな」
しゃがれた声で返事をよこしたのはこの民家の主人、タロ太郎だ。『タロ』が苗字で『太郎』が名前だというんだからふざけている。本人はいつぞやの頃からかこの名前一本で通していて、今ではもう自分の本当の名がなんなのか、本人ですら首を傾げる始末であった。
戸を引いて家の中に入ってみるとすぐに小上がりになっていて、履物を脱いで部屋の中へと上がるシステムになっていた。
部屋の中は狭くて薄暗い。真ん中には不自然に大きなこたつが一つだけ置かれていてあとは何もない。こたつ布団には猫の柄が描かれていた。その奥が台所となっていた。
太郎はその台所にいて侍の飲み物を入れるグラスを用意していた。
侍は慣れた様子でこたつに入り込み、こたつ布団を肩まで引っ張った。
太郎はそんな様子を見て左の唇だけ上げて鼻でふんと一つ笑う。
小馬鹿にしているように見えるその笑いは彼の癖であった。
そんな太郎は長めの金髪に筋の通った鼻、切れ長の目、ぴんと背筋の伸びた立ち姿に流行りのデニムの着物がよく似合っていた。どういうわけか足元はスニーカーという不自然さには首を傾げるところである。しかし本人は全く気にしていない。
「それで、今日は誰の話を聞きたいんだい、たまちゃん」
鈴の音のような耳心地の良い声が侍が座った隣から聞こえた。そのまた隣には「たまこ」と呼ばれた年の頃は十才前後のおかっぱ頭の少女が分厚いノートを広げて鉛筆を持って待ち構えていた。
太郎と侍が話しているうちにどこからともなく二人は現れて、気付いたときにはこたつに入っていたのだ。部屋の中もいくばくか明るくなっている。
「昭子(しょうこ)さん。今日は侍さんの話を聞かせてくれる約束をした日ですよ。侍さんがどうしてここにいるようになったのか、教えてくれる日。いっつも話の途中ではぐらかすから最後まで聞けてないもん」
昭子と呼ばれたのは、先ほどの鈴の音の声の主で、紅色の振袖の打掛にお垂髪(おすべらかし)のよく似合う妖艶な雰囲気に嗅いだことのない甘い香の香りをふわりと漂わせた二十に差し掛かろうかという頃合いの女子(おなご)だ。
肌はこの世に新しく舞い落ちる輝ききった雪のごとく真っ白でとても冷たい。身体をくねらせ太郎にいつものように「あたしにはお酒をちょうだいね」と台所の奥に置いてある酒の瓶を指さした。
「はいはい。いつものですね。ちょいとお待ちを」
ちょこんと頭を下げた太郎は、侍の前にいつものメロンソーダを、昭子には日本酒を、たまこにはオレンジジュースをてきぱきと出した。
各々飲み物を手に取り一口飲むと、頼んでもいないのにおでんの皿がそれぞれの前に置かれる。
0
あなたにおすすめの小説

17歳男子高生と32歳主婦の境界線
MisakiNonagase
恋愛
32歳主婦のカレンはインスタグラムで20歳大学生の晴人と知り合う。親密な関係となった3度目のデートのときに、晴人が実は17歳の高校2年生だと知る。
カレンと晴人はその後、どうなる?
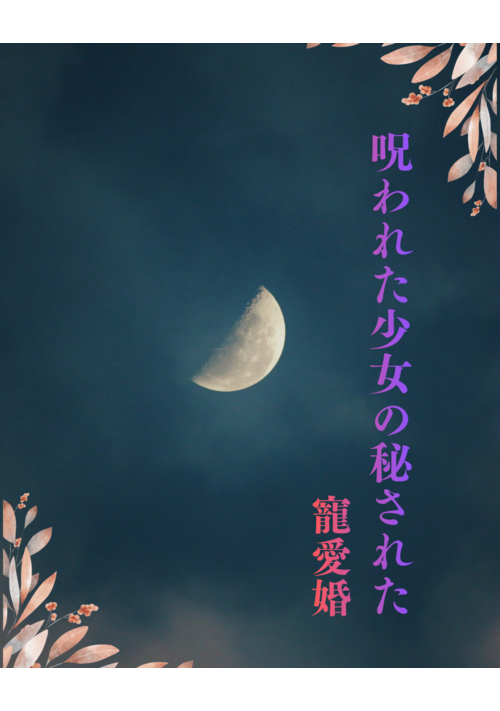
呪われた少女の秘された寵愛婚―盈月―
くろのあずさ
キャラ文芸
異常存在(マレビト)と呼ばれる人にあらざる者たちが境界が曖昧な世界。甚大な被害を被る人々の平和と安寧を守るため、軍は組織されたのだと噂されていた。
「無駄とはなんだ。お前があまりにも妻としての自覚が足らないから、思い出させてやっているのだろう」
「それは……しょうがありません」
だって私は――
「どんな姿でも関係ない。私の妻はお前だけだ」
相応しくない。私は彼のそばにいるべきではないのに――。
「私も……あなた様の、旦那様のそばにいたいです」
この身で願ってもかまわないの?
呪われた少女の孤独は秘された寵愛婚の中で溶かされる
2025.12.6
盈月(えいげつ)……新月から満月に向かって次第に円くなっていく間の月

熟女愛好家ユウスケの青春(熟女漁り)
MisakiNonagase
恋愛
高校まで勉強一筋で大学デビューをしたユウスケは家庭教師の教え子の母親と不倫交際するが、彼にとって彼女とが初の男女交際。そこでユウスケは自分が熟女好きだと自覚する。それからユウスケは戦略と実戦を重ねて、清潔感と聞き上手を武器にたくさんの熟女と付き合うことになるストーリーです。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

後宮の胡蝶 ~皇帝陛下の秘密の妃~
菱沼あゆ
キャラ文芸
突然の譲位により、若き皇帝となった苑楊は封印されているはずの宮殿で女官らしき娘、洋蘭と出会う。
洋蘭はこの宮殿の牢に住む老人の世話をしているのだと言う。
天女のごとき外見と豊富な知識を持つ洋蘭に心惹かれはじめる苑楊だったが。
洋蘭はまったく思い通りにならないうえに、なにかが怪しい女だった――。
中華後宮ラブコメディ。

裏切りの代償
中岡 始
キャラ文芸
かつて夫と共に立ち上げたベンチャー企業「ネクサスラボ」。奏は結婚を機に経営の第一線を退き、専業主婦として家庭を支えてきた。しかし、平穏だった生活は夫・尚紀の裏切りによって一変する。彼の部下であり不倫相手の優美が、会社を混乱に陥れつつあったのだ。
尚紀の冷たい態度と優美の挑発に苦しむ中、奏は再び経営者としての力を取り戻す決意をする。裏切りの証拠を集め、かつての仲間や信頼できる協力者たちと連携しながら、会社を立て直すための計画を進める奏。だが、それは尚紀と優美の野望を徹底的に打ち砕く覚悟でもあった。
取締役会での対決、揺れる社内外の信頼、そして壊れた夫婦の絆の果てに待つのは――。
自分の誇りと未来を取り戻すため、すべてを賭けて挑む奏の闘い。復讐の果てに見える新たな希望と、繊細な人間ドラマが交錯する物語がここに。

滝川家の人びと
卯花月影
歴史・時代
勝利のために走るのではない。
生きるために走る者は、
傷を負いながらも、歩みを止めない。
戦国という時代の只中で、
彼らは何を失い、
走り続けたのか。
滝川一益と、その郎党。
これは、勝者の物語ではない。
生き延びた者たちの記録である。

私の守護霊さん
Masa&G
キャラ文芸
大学生活を送る彩音には、誰にも言えない秘密がある。
彼女のそばには、他人には姿の見えない“守護霊さん”がずっと寄り添っていた。
これは——二人で過ごした最後の一年を描く、かけがえのない物語。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















