41 / 56
第三話:霊 たまこ
鼻で使う昭子と使われる侍の図
しおりを挟む
「さて、今日の夜まであたしらは何をするってんだい? こんな昼日中に出てるのは今日がぼた餅の日だからで、あたしらはこれを食ったらいつもはすぐに影の内に戻るけど、今日はなんだかそんな気分にはなれないねえ。どうする太郎」
昭子は口の周りについた餡ををべろりと長い舌で舐めとった。
「どうするって俺は帰って一眠りできますぜ。餅も食ったことですし、昼間からここにいる理由もないですしね、端から食ったら帰るつもりでした」
そんなことを言いながら太郎はこんぶ茶のおかわりを三人分持ってきた。
昭子はそれを一気に飲み干した。
「相変わらずだねえ」
昭子が太郎に「おまえは冷たい。あたしの数千倍冷たいじゃないか」と言葉を投げる。「そんなこと言われても、ここにいてもやることないでしょ」と至って太郎は自分のペースを崩さない。
昭子は、特大のため息をこれ見よがしにつくと、
「侍はあたしと一緒にここに残るかい?」
こんぶ茶をすすりながら侍の方に向き直る。
「いますよ。まだこのぼた餅を食いきっとらんですし、食後の運動にちょいと街をふらつこうと思ってたんでね」
侍が箱の中に残っているぼた餅を覗き込む。
「まったくどいつもこいつも」
ぼた餅に頬が緩んでいる侍を一瞥し、じゃ、あたしはごろんと横になって昼寝でもする。と言うと、座布団を半分に折って枕を作る。無造作に投げると、森の中に転がっている丸太のようにごろんと横になった。
太郎が茶化そうと口を開いたが侍に首を振られて制された。
ここで茶化したら太郎は昭子の怒りを買い、影に帰れなくなる。
開いた口をゆっくりと閉じ、抜き足差し足で太郎は音もなく影の中に消えて行ったのであった。
「侍、こんぶ茶のおかわり淹れとくれな」
寝っ転がったまま侍に指図する。
へいへいと侍は仕方なく自分の湯呑みも持って台所に立つ。
「そういや俺のことは根ほり葉ほり聞いてくるのに、昭子さんのことはなんにも聞いてませんでしたよね。昭子さんのこと知ってるんですか?」
「あんたらが言ってないなら知らないはずだよ。あたしはなんにも言ってないからね」
「じゃ今日あたり聞いてくるんですかねえ」
「どうだかねえ。ま、聞かれりゃ答えるさ。自分からほいほい馬鹿みたいには言わないけどね。とは言っても、女ってもんは口に出して言わなくても通じ合える部分があるんだよ」
ふふっと肩で笑う。そして大欠伸をした。
「今日がその日かと思うとなんだか寂しくなりますね」
「そうさねえ。今まではあたしら三人プラス1の存在になってたからねえ」
「自分から進んで手伝いもするし、時間も知らせてくれるし何かと役に立ってましたしね」
「ようくあたしらを観察してたっけねえ。もう仲間になったとばかり思ってたけど、やはりあの子は行くべきところに逝かないといけないんだねえ」
「あいつの居場所はここじゃないってことですか」
「上であの子のことを首を長くして待ってる奴らがいるんだろうよ。あ、侍、ちょっと熱めので淹れといておくれな。一眠りするから」
侍は火からおろそうとしていたやかんを今一度火に戻す。
熱めのを淹れておけば、うたた寝から目覚めても少し温いくらいで飲めるという魂胆だ。
「でも昭子さん、そんなこといっつも言ってますけどね、温い状態で飲める内に起きたことなんて一度もないっての覚えてます?」
肩まですっぽりとこたつに潜り込んですでに寝息をたてている昭子にもんくを言うが、それはもう聞こえていなかった。
「まったく。どうせ冷えるんだからだったら熱くしないで適温で淹れて飲めばよかったぜ。俺は本当にお人好しだ。昭子さんの言う通りに熱めで淹れるんだからまたく世話ねえわな」
自分に言ったもんくに自分でおかしくて一人笑いをしつつ、やかんを火からおろす。
昭子の湯呑みと自分の湯呑みにこんぶ茶を淹れて、「さすがに熱いな」と声を漏らした。
昭子は口の周りについた餡ををべろりと長い舌で舐めとった。
「どうするって俺は帰って一眠りできますぜ。餅も食ったことですし、昼間からここにいる理由もないですしね、端から食ったら帰るつもりでした」
そんなことを言いながら太郎はこんぶ茶のおかわりを三人分持ってきた。
昭子はそれを一気に飲み干した。
「相変わらずだねえ」
昭子が太郎に「おまえは冷たい。あたしの数千倍冷たいじゃないか」と言葉を投げる。「そんなこと言われても、ここにいてもやることないでしょ」と至って太郎は自分のペースを崩さない。
昭子は、特大のため息をこれ見よがしにつくと、
「侍はあたしと一緒にここに残るかい?」
こんぶ茶をすすりながら侍の方に向き直る。
「いますよ。まだこのぼた餅を食いきっとらんですし、食後の運動にちょいと街をふらつこうと思ってたんでね」
侍が箱の中に残っているぼた餅を覗き込む。
「まったくどいつもこいつも」
ぼた餅に頬が緩んでいる侍を一瞥し、じゃ、あたしはごろんと横になって昼寝でもする。と言うと、座布団を半分に折って枕を作る。無造作に投げると、森の中に転がっている丸太のようにごろんと横になった。
太郎が茶化そうと口を開いたが侍に首を振られて制された。
ここで茶化したら太郎は昭子の怒りを買い、影に帰れなくなる。
開いた口をゆっくりと閉じ、抜き足差し足で太郎は音もなく影の中に消えて行ったのであった。
「侍、こんぶ茶のおかわり淹れとくれな」
寝っ転がったまま侍に指図する。
へいへいと侍は仕方なく自分の湯呑みも持って台所に立つ。
「そういや俺のことは根ほり葉ほり聞いてくるのに、昭子さんのことはなんにも聞いてませんでしたよね。昭子さんのこと知ってるんですか?」
「あんたらが言ってないなら知らないはずだよ。あたしはなんにも言ってないからね」
「じゃ今日あたり聞いてくるんですかねえ」
「どうだかねえ。ま、聞かれりゃ答えるさ。自分からほいほい馬鹿みたいには言わないけどね。とは言っても、女ってもんは口に出して言わなくても通じ合える部分があるんだよ」
ふふっと肩で笑う。そして大欠伸をした。
「今日がその日かと思うとなんだか寂しくなりますね」
「そうさねえ。今まではあたしら三人プラス1の存在になってたからねえ」
「自分から進んで手伝いもするし、時間も知らせてくれるし何かと役に立ってましたしね」
「ようくあたしらを観察してたっけねえ。もう仲間になったとばかり思ってたけど、やはりあの子は行くべきところに逝かないといけないんだねえ」
「あいつの居場所はここじゃないってことですか」
「上であの子のことを首を長くして待ってる奴らがいるんだろうよ。あ、侍、ちょっと熱めので淹れといておくれな。一眠りするから」
侍は火からおろそうとしていたやかんを今一度火に戻す。
熱めのを淹れておけば、うたた寝から目覚めても少し温いくらいで飲めるという魂胆だ。
「でも昭子さん、そんなこといっつも言ってますけどね、温い状態で飲める内に起きたことなんて一度もないっての覚えてます?」
肩まですっぽりとこたつに潜り込んですでに寝息をたてている昭子にもんくを言うが、それはもう聞こえていなかった。
「まったく。どうせ冷えるんだからだったら熱くしないで適温で淹れて飲めばよかったぜ。俺は本当にお人好しだ。昭子さんの言う通りに熱めで淹れるんだからまたく世話ねえわな」
自分に言ったもんくに自分でおかしくて一人笑いをしつつ、やかんを火からおろす。
昭子の湯呑みと自分の湯呑みにこんぶ茶を淹れて、「さすがに熱いな」と声を漏らした。
0
あなたにおすすめの小説

17歳男子高生と32歳主婦の境界線
MisakiNonagase
恋愛
32歳主婦のカレンはインスタグラムで20歳大学生の晴人と知り合う。親密な関係となった3度目のデートのときに、晴人が実は17歳の高校2年生だと知る。
カレンと晴人はその後、どうなる?
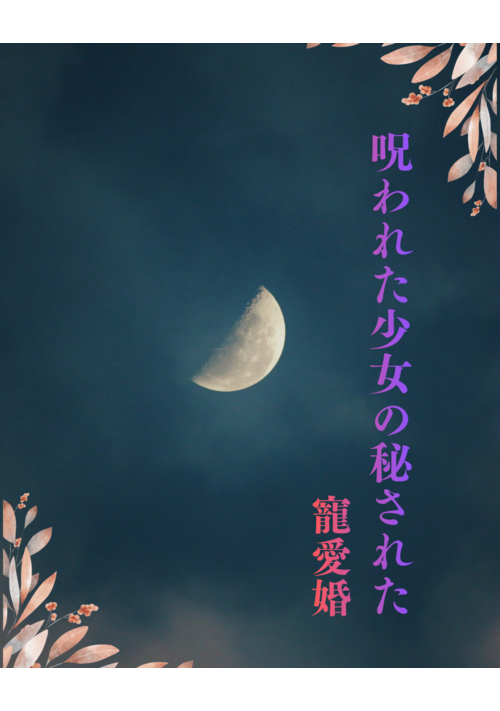
呪われた少女の秘された寵愛婚―盈月―
くろのあずさ
キャラ文芸
異常存在(マレビト)と呼ばれる人にあらざる者たちが境界が曖昧な世界。甚大な被害を被る人々の平和と安寧を守るため、軍は組織されたのだと噂されていた。
「無駄とはなんだ。お前があまりにも妻としての自覚が足らないから、思い出させてやっているのだろう」
「それは……しょうがありません」
だって私は――
「どんな姿でも関係ない。私の妻はお前だけだ」
相応しくない。私は彼のそばにいるべきではないのに――。
「私も……あなた様の、旦那様のそばにいたいです」
この身で願ってもかまわないの?
呪われた少女の孤独は秘された寵愛婚の中で溶かされる
2025.12.6
盈月(えいげつ)……新月から満月に向かって次第に円くなっていく間の月

熟女愛好家ユウスケの青春(熟女漁り)
MisakiNonagase
恋愛
高校まで勉強一筋で大学デビューをしたユウスケは家庭教師の教え子の母親と不倫交際するが、彼にとって彼女とが初の男女交際。そこでユウスケは自分が熟女好きだと自覚する。それからユウスケは戦略と実戦を重ねて、清潔感と聞き上手を武器にたくさんの熟女と付き合うことになるストーリーです。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

後宮の胡蝶 ~皇帝陛下の秘密の妃~
菱沼あゆ
キャラ文芸
突然の譲位により、若き皇帝となった苑楊は封印されているはずの宮殿で女官らしき娘、洋蘭と出会う。
洋蘭はこの宮殿の牢に住む老人の世話をしているのだと言う。
天女のごとき外見と豊富な知識を持つ洋蘭に心惹かれはじめる苑楊だったが。
洋蘭はまったく思い通りにならないうえに、なにかが怪しい女だった――。
中華後宮ラブコメディ。

裏切りの代償
中岡 始
キャラ文芸
かつて夫と共に立ち上げたベンチャー企業「ネクサスラボ」。奏は結婚を機に経営の第一線を退き、専業主婦として家庭を支えてきた。しかし、平穏だった生活は夫・尚紀の裏切りによって一変する。彼の部下であり不倫相手の優美が、会社を混乱に陥れつつあったのだ。
尚紀の冷たい態度と優美の挑発に苦しむ中、奏は再び経営者としての力を取り戻す決意をする。裏切りの証拠を集め、かつての仲間や信頼できる協力者たちと連携しながら、会社を立て直すための計画を進める奏。だが、それは尚紀と優美の野望を徹底的に打ち砕く覚悟でもあった。
取締役会での対決、揺れる社内外の信頼、そして壊れた夫婦の絆の果てに待つのは――。
自分の誇りと未来を取り戻すため、すべてを賭けて挑む奏の闘い。復讐の果てに見える新たな希望と、繊細な人間ドラマが交錯する物語がここに。

滝川家の人びと
卯花月影
歴史・時代
勝利のために走るのではない。
生きるために走る者は、
傷を負いながらも、歩みを止めない。
戦国という時代の只中で、
彼らは何を失い、
走り続けたのか。
滝川一益と、その郎党。
これは、勝者の物語ではない。
生き延びた者たちの記録である。

私の守護霊さん
Masa&G
キャラ文芸
大学生活を送る彩音には、誰にも言えない秘密がある。
彼女のそばには、他人には姿の見えない“守護霊さん”がずっと寄り添っていた。
これは——二人で過ごした最後の一年を描く、かけがえのない物語。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















