40 / 56
第三話:霊 たまこ
ぼた餅とこんぶ茶
しおりを挟む
二
昭子と太郎は己の体を肩まですっぽりとこたつに押し込んでいるのに、寒い寒いとほざいていた。
そもそも寒さなんて感じやしないのに、人の世の雰囲気に便乗してこの世を楽しんでいるのだ。その証拠に、顔には楽しくて仕方がないという文字がくっきりと浮かび上がっている。
こたつの上には湯呑みが二つ。
小皿が三枚重ねられている。
湯呑みの中はこんぶ茶だ。珍しいことに昭子も酒ではなく、太郎同様に渋いこんぶ茶を飲んでいた。
昭子が太郎に「煎餅を買って来い」と命令しているが、太郎はこたつから出るのがいやで、「そろそろ侍さんが来る頃だから待っててくださいよ」と、のらりくらりと昭子の命令をかわしていた。
侍は煎餅なんか持ってこないだろうが。と横になりながらもんくを言う昭子の顔には笑みが浮かんでいる。
持ってくるかもしれないじゃないですか。と言い返す太郎も可笑しそうに肩を揺らしていた。
そんな人間を真似した掛け合いをしばらく続けていると、家の戸が悪い音を立てながら開いた。
「おう、外はだいぶ冷え込んできたよ。あー、さみいさみい」
こちらも手を擦り合わせて「いやはや外は寒い。今年はどうにも天気がおかしいんじゃないかねえ」などと知ったかぶりをみせた侍がいそいそと入ってきた。
ああ、そうだよ。今年はおかしい。去年の方がまだましだったさ。年々天気がおかしくなっていくねえ。この調子じゃ来年もおかしくなりそうだ。まったくどうなることやら。と昭子も天気に詳しくないので適当に口を合わせている。
あーさぶさぶと何度も言いつつ空いている席についた侍は、こたつの上にいいにおいのする紙の箱を置いた。
昭子と太郎がそのにおいにつられてむくりと体を起こす。二人の嗅覚はすこぶるいいのだ。
「ああ、このにおい。ぼた餅だね」
昭子が更に鼻を近づけた。
「侍さんもこんぶ茶でいいですか」
太郎が茶を淹れに席を立つ。
「あんこにこんぶ茶かい? 渋めの茶のほうが合いそうなものを」
渋い顔をした侍に、「あんた、あたしが飲んでるものが見えないのかい?」と昭子が自分の湯呑みを持ち上げてみせた。
「ああ、こんぶ茶は昭子さんの趣味か。さすがだな。俺も丁度こんぶ茶が飲みたかったとこだよ。太郎、俺もそうしてもらおうかな」
侍はすかさず昭子を褒めると台所に向かった太郎の背に、俺もこんぶ茶で頼むよ。と声をかける。太郎は返事こそしなかったものの、その背中は笑っていた。
侍が自分が贔屓にしている饅頭屋で月一だけ作るぼた餅を買ってくるのは三人の間ではもう長いこと習慣化されていた。
なぜ月一なのかと聞くと「知らん。ぼた餅の日は一日と決まってるそうだよ」とこういった具合である。
侍本人のみならず、昭子も太郎もこのぼた餅を楽しみにしているのだ。
侍が贔屓にしている店に顔を出すときのみ、この家は昼日中から現れる。
その店の売り子の女子が侍はたいそうお気に入りのようで、何かと機会を見つけちゃあくだらない世間話をして顔を溶けた餅のようにドロロに綻ばせているのだ。
食える分だけ一つ二つ買えばいいものを、見栄をはってたくさん買って来るものだから、昭子と太郎にもその分け前が入ってくる。
一人でたくさん買って持ってたって食べきれるものじゃない。旨いものは気心知れた仲間と食べた方が何倍も旨くなるのを三人は知っているのだ。
侍が小皿にぼた餅を丁寧に乗せて二人の前に置く。昭子が満面の笑みを顔に浮かべて揉み手をする。太郎が侍の湯呑みを置いた。
「お、いいにおいのこんぶ茶だね」
こんぶ茶の香りを思い切り吸い込み、侍が目を細める。
「よし、食べるとしようや」と太郎もこたつに入り手を合わせた。
三人は、ぼた餅を素手で掴み、口にほうばる。指についた餡を舐めたり吸ったりして取る。こういうところがまだ人慣れしていないところでもあった。食べるための道具を使うのが面倒くさいのだ。
素手で掴んで口に放り込んだほうが早い。三人は食い物については待つと言うことが苦手であった。
うん、この粒餡がなんともいえない。柔らかくてコシもあって旨い。
そうだね、餅に適度なコシがあっていいねえ。つきたてはこれだから旨いんだよ。
中に入っている青紫蘇がいい塩梅に味を締めてますね。一つ一つの大きさもあって食べ応えもある。
等々、侍、昭子、太郎はいかにもらしいことを言い合いながら、一つ、二つとぼた餅が腹の中に収まっていく。
三つ目のぼた餅を各々腹に収め、こんぶ茶を啜って口内の甘ったるさを落ち着けると、
「そういや、今日がその日じゃなかったかい?」
ああ、今日も餅が旨かったねぇ。という一言に添えて何気なしに言った侍の言葉に二人の動きが止まる。
「そうだねえ」
「そうだ。今日がその日だ」
のんびりと相槌を打った昭子とは逆に太郎はきっぱりと言い切った。
「今日だ」
太郎が繰り返す。
三人は心なしか寂しそうな顔をしている。
昭子は湯呑みを両手で掴み、残りのこんぶ茶に目を落とし、太郎は腕組みをして眉間にシワを拵えている。侍は爪楊枝を探し始めた。
昭子が重くなった空気を切った。
昭子と太郎は己の体を肩まですっぽりとこたつに押し込んでいるのに、寒い寒いとほざいていた。
そもそも寒さなんて感じやしないのに、人の世の雰囲気に便乗してこの世を楽しんでいるのだ。その証拠に、顔には楽しくて仕方がないという文字がくっきりと浮かび上がっている。
こたつの上には湯呑みが二つ。
小皿が三枚重ねられている。
湯呑みの中はこんぶ茶だ。珍しいことに昭子も酒ではなく、太郎同様に渋いこんぶ茶を飲んでいた。
昭子が太郎に「煎餅を買って来い」と命令しているが、太郎はこたつから出るのがいやで、「そろそろ侍さんが来る頃だから待っててくださいよ」と、のらりくらりと昭子の命令をかわしていた。
侍は煎餅なんか持ってこないだろうが。と横になりながらもんくを言う昭子の顔には笑みが浮かんでいる。
持ってくるかもしれないじゃないですか。と言い返す太郎も可笑しそうに肩を揺らしていた。
そんな人間を真似した掛け合いをしばらく続けていると、家の戸が悪い音を立てながら開いた。
「おう、外はだいぶ冷え込んできたよ。あー、さみいさみい」
こちらも手を擦り合わせて「いやはや外は寒い。今年はどうにも天気がおかしいんじゃないかねえ」などと知ったかぶりをみせた侍がいそいそと入ってきた。
ああ、そうだよ。今年はおかしい。去年の方がまだましだったさ。年々天気がおかしくなっていくねえ。この調子じゃ来年もおかしくなりそうだ。まったくどうなることやら。と昭子も天気に詳しくないので適当に口を合わせている。
あーさぶさぶと何度も言いつつ空いている席についた侍は、こたつの上にいいにおいのする紙の箱を置いた。
昭子と太郎がそのにおいにつられてむくりと体を起こす。二人の嗅覚はすこぶるいいのだ。
「ああ、このにおい。ぼた餅だね」
昭子が更に鼻を近づけた。
「侍さんもこんぶ茶でいいですか」
太郎が茶を淹れに席を立つ。
「あんこにこんぶ茶かい? 渋めの茶のほうが合いそうなものを」
渋い顔をした侍に、「あんた、あたしが飲んでるものが見えないのかい?」と昭子が自分の湯呑みを持ち上げてみせた。
「ああ、こんぶ茶は昭子さんの趣味か。さすがだな。俺も丁度こんぶ茶が飲みたかったとこだよ。太郎、俺もそうしてもらおうかな」
侍はすかさず昭子を褒めると台所に向かった太郎の背に、俺もこんぶ茶で頼むよ。と声をかける。太郎は返事こそしなかったものの、その背中は笑っていた。
侍が自分が贔屓にしている饅頭屋で月一だけ作るぼた餅を買ってくるのは三人の間ではもう長いこと習慣化されていた。
なぜ月一なのかと聞くと「知らん。ぼた餅の日は一日と決まってるそうだよ」とこういった具合である。
侍本人のみならず、昭子も太郎もこのぼた餅を楽しみにしているのだ。
侍が贔屓にしている店に顔を出すときのみ、この家は昼日中から現れる。
その店の売り子の女子が侍はたいそうお気に入りのようで、何かと機会を見つけちゃあくだらない世間話をして顔を溶けた餅のようにドロロに綻ばせているのだ。
食える分だけ一つ二つ買えばいいものを、見栄をはってたくさん買って来るものだから、昭子と太郎にもその分け前が入ってくる。
一人でたくさん買って持ってたって食べきれるものじゃない。旨いものは気心知れた仲間と食べた方が何倍も旨くなるのを三人は知っているのだ。
侍が小皿にぼた餅を丁寧に乗せて二人の前に置く。昭子が満面の笑みを顔に浮かべて揉み手をする。太郎が侍の湯呑みを置いた。
「お、いいにおいのこんぶ茶だね」
こんぶ茶の香りを思い切り吸い込み、侍が目を細める。
「よし、食べるとしようや」と太郎もこたつに入り手を合わせた。
三人は、ぼた餅を素手で掴み、口にほうばる。指についた餡を舐めたり吸ったりして取る。こういうところがまだ人慣れしていないところでもあった。食べるための道具を使うのが面倒くさいのだ。
素手で掴んで口に放り込んだほうが早い。三人は食い物については待つと言うことが苦手であった。
うん、この粒餡がなんともいえない。柔らかくてコシもあって旨い。
そうだね、餅に適度なコシがあっていいねえ。つきたてはこれだから旨いんだよ。
中に入っている青紫蘇がいい塩梅に味を締めてますね。一つ一つの大きさもあって食べ応えもある。
等々、侍、昭子、太郎はいかにもらしいことを言い合いながら、一つ、二つとぼた餅が腹の中に収まっていく。
三つ目のぼた餅を各々腹に収め、こんぶ茶を啜って口内の甘ったるさを落ち着けると、
「そういや、今日がその日じゃなかったかい?」
ああ、今日も餅が旨かったねぇ。という一言に添えて何気なしに言った侍の言葉に二人の動きが止まる。
「そうだねえ」
「そうだ。今日がその日だ」
のんびりと相槌を打った昭子とは逆に太郎はきっぱりと言い切った。
「今日だ」
太郎が繰り返す。
三人は心なしか寂しそうな顔をしている。
昭子は湯呑みを両手で掴み、残りのこんぶ茶に目を落とし、太郎は腕組みをして眉間にシワを拵えている。侍は爪楊枝を探し始めた。
昭子が重くなった空気を切った。
0
あなたにおすすめの小説

17歳男子高生と32歳主婦の境界線
MisakiNonagase
恋愛
32歳主婦のカレンはインスタグラムで20歳大学生の晴人と知り合う。親密な関係となった3度目のデートのときに、晴人が実は17歳の高校2年生だと知る。
カレンと晴人はその後、どうなる?
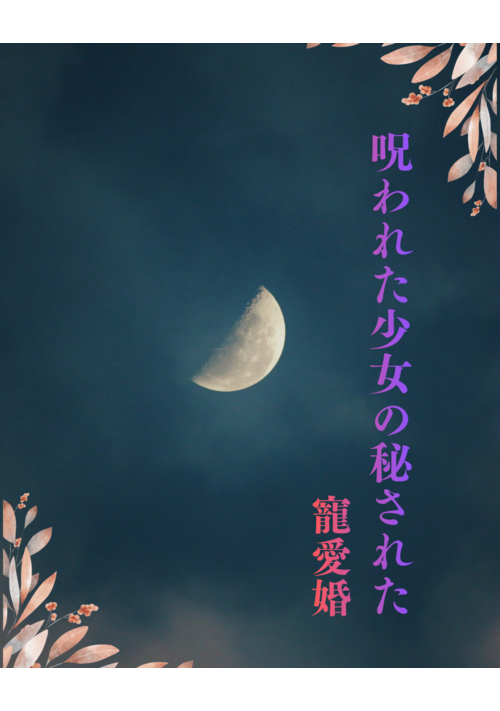
呪われた少女の秘された寵愛婚―盈月―
くろのあずさ
キャラ文芸
異常存在(マレビト)と呼ばれる人にあらざる者たちが境界が曖昧な世界。甚大な被害を被る人々の平和と安寧を守るため、軍は組織されたのだと噂されていた。
「無駄とはなんだ。お前があまりにも妻としての自覚が足らないから、思い出させてやっているのだろう」
「それは……しょうがありません」
だって私は――
「どんな姿でも関係ない。私の妻はお前だけだ」
相応しくない。私は彼のそばにいるべきではないのに――。
「私も……あなた様の、旦那様のそばにいたいです」
この身で願ってもかまわないの?
呪われた少女の孤独は秘された寵愛婚の中で溶かされる
2025.12.6
盈月(えいげつ)……新月から満月に向かって次第に円くなっていく間の月

熟女愛好家ユウスケの青春(熟女漁り)
MisakiNonagase
恋愛
高校まで勉強一筋で大学デビューをしたユウスケは家庭教師の教え子の母親と不倫交際するが、彼にとって彼女とが初の男女交際。そこでユウスケは自分が熟女好きだと自覚する。それからユウスケは戦略と実戦を重ねて、清潔感と聞き上手を武器にたくさんの熟女と付き合うことになるストーリーです。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

後宮の胡蝶 ~皇帝陛下の秘密の妃~
菱沼あゆ
キャラ文芸
突然の譲位により、若き皇帝となった苑楊は封印されているはずの宮殿で女官らしき娘、洋蘭と出会う。
洋蘭はこの宮殿の牢に住む老人の世話をしているのだと言う。
天女のごとき外見と豊富な知識を持つ洋蘭に心惹かれはじめる苑楊だったが。
洋蘭はまったく思い通りにならないうえに、なにかが怪しい女だった――。
中華後宮ラブコメディ。

裏切りの代償
中岡 始
キャラ文芸
かつて夫と共に立ち上げたベンチャー企業「ネクサスラボ」。奏は結婚を機に経営の第一線を退き、専業主婦として家庭を支えてきた。しかし、平穏だった生活は夫・尚紀の裏切りによって一変する。彼の部下であり不倫相手の優美が、会社を混乱に陥れつつあったのだ。
尚紀の冷たい態度と優美の挑発に苦しむ中、奏は再び経営者としての力を取り戻す決意をする。裏切りの証拠を集め、かつての仲間や信頼できる協力者たちと連携しながら、会社を立て直すための計画を進める奏。だが、それは尚紀と優美の野望を徹底的に打ち砕く覚悟でもあった。
取締役会での対決、揺れる社内外の信頼、そして壊れた夫婦の絆の果てに待つのは――。
自分の誇りと未来を取り戻すため、すべてを賭けて挑む奏の闘い。復讐の果てに見える新たな希望と、繊細な人間ドラマが交錯する物語がここに。

滝川家の人びと
卯花月影
歴史・時代
勝利のために走るのではない。
生きるために走る者は、
傷を負いながらも、歩みを止めない。
戦国という時代の只中で、
彼らは何を失い、
走り続けたのか。
滝川一益と、その郎党。
これは、勝者の物語ではない。
生き延びた者たちの記録である。

私の守護霊さん
Masa&G
キャラ文芸
大学生活を送る彩音には、誰にも言えない秘密がある。
彼女のそばには、他人には姿の見えない“守護霊さん”がずっと寄り添っていた。
これは——二人で過ごした最後の一年を描く、かけがえのない物語。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















