14 / 26
災厄の魔王~戯れ~
集うもの
しおりを挟む
そしてストレイト皇国、聖王の都・ヒュンベリオン。その重臣たちが集まる場において、聖王の片腕でもあるヴェルスレムは不眠不休の態で聖王捜索の軍事面で陣頭指揮をとっていた。
作戦会議室の巨大な木の机の上に、領地内の巨大な地図が置かれ、その上にチェスの駒のような部隊配置を表す黒い駒が光を帯びて浮いている。
「国境警備と治安維持及び兵の巡回はガウェイが滞りなく行ってくれたおかげで敵の封じ込めには成功しておるようじゃ」
宰相であるツキュールが長く白い髭をなでつつ現状を確認すれば、ヴェルスレムはそれに続く形で声を上げる。
「今、エルフの君・シュレルスと閃光の騎士・ファルタが森の中をくまなく探してくれている。獣人一匹、この国から出しはしない。聖王陛下を攫ったこと後悔させなければな。」
ツキュールは鬼気迫る様なヴェルスレムの態度に少し眉を寄せた。彼は今、獣人を一匹と言ったのだ。
(…何もなければ良いが。)
ヴェルスレムの金色の髪は連日の激務にくすんだ色をしており、彼の薄紅色の瞳は不眠の為かいつもより赤い。
だがそんな彼等の元に思わぬところから情報がもたらされた。
「邪魔するぜぃ」という野太い声とドォンッという衝撃共に開け放たれた扉に意識を向ければ、そこには大柄の男が部屋に不作法にも入ってくるところだった。男は鎖帷子と鉄製の鎧を着て、毛皮を肩からかけている。
「レッタンダム、どうした」
ヴェルスレムはそんな作法を気にするでもなく入ってきた男に問いただす。
そう、部屋にやってきた彼は「海賊殺し・レッタンダム」。
逞しく、人の体よりも巨大な斧を振るう男で。賊退治の手腕にかけては、その情報収集に始まってヴェルスレムやガウェイすら凌ぐ力を発揮した。それもかつてレッタンダムの故郷の漁村が海賊に襲われ滅ぼされた怒りに由来する。その怒りが彼を海賊殺しの異名を持つまでにさせ、その彼の肉体は漁師としての仕事と復讐の中で鍛えられたのだった。
そしてレッタンダムは宰相ツキュールの左隣まで来ると、机上の地図の上のある一点を指し示し太い笑みを浮かべる。
「ヴェルの旦那。情報を掴んだ、俺はこれは結構臭いと思ってる」
ヴェルスレムは暫し、レッタンダムの茶色の瞳を見ていた。
彼がさしているのは以前は地下コロッセオがあった場所で、今は入口を塞がれて酒場になっている筈の場所だった。
「理由を聞こう」
ヴェルスレムの薄紅の瞳がスゥッと真剣味を帯びると、レッタンダムは悪童のように笑った。
「そうこなくっちゃな」
そしてレッタンダムは、昨日、その酒場から現れた〝数十人の獣人の奴隷″の噂を披露した。
曰く、何人もの城下の人々が見た、明らかに聖都の者でない奴隷の首輪を着けた獣人たち。
というのも聖都は聖王シュレイザードの意向によって奴隷売買は禁止されており、奴隷だとしたらそれは他の領地で奴隷になった者の筈なのだ。奴隷即ち聖都の住人ではないのである。
そして更に今は魔物が活発化し、周辺から逃げてきた多くの人々はいるが…それにしては奴隷たちの〝身なりが良かった″のだという。まるでつい最近、奴隷に落とされたかのように…
「陛下がご不在の隙に奴隷商が入り込んだやもしれぬ」とツキュールは唸り、レッタンダムは獣人のコミュニティーは強いから、もしも獣人を数十人単位で捕らえられれば聖王を攫った盗賊王ジュレガンの行方も掴めるかもしれないと締めくくった。
それに暫し、ヴェルスレムは考え込んでいるようであったが、彼が再び顔を上げた時には強い意志の力があった。
「…わかった、レッタンダム。お前は引き続き賊の情報収集にあたってくれ。
ツキュール様もガウェイの代わりに騎士の全体の采配をお任せします。」
その言葉にツキュールは思わず尋ねていた。
「ヴェルスレム殿はどうされる?」
その言葉に、ヴェルスレムは微笑み、そしてその部屋にあつらえていた銀製の窓を開け放った。
折しも時間帯は明け方である。太陽の光を受けて豊かに輝く彼の金髪は…風に流れるように銀色に、そして薄紅の瞳は蒼と緑のオッドアイへと緩やかに変化する。
…それは彼のかつての過去世・ランスロット卿の姿だった。
そしてランスロット卿は嫣然と、見るものを惹き付けるような笑みを浮かべた。
「…俺はそこに探りに入る」と。
◆◆◆
俺は闇の中で立っていた。
浮かんでいるのか足は空を蹴るのに怖くはなかった。
頭のどこかで夢だと分かるからかもしれない。
すると闇の中にポツンと映像が映し出される。
その映像の中には二人の人が映っていた。
夜なのだろう薄墨を流したような夜のとばりの中で寝台に寝入っている一人は金髪の青年…あれはアーサー王だ。そしてもう一人は銀髪の騎士・ランスロット卿。
アーサー王が眠っている寝台の側でランスロット卿が佇んで彼を見ている。
ジッとそれは真剣にまるで精緻な美術品でも見るように見詰めている…こっちの息が止まりそうなぐらい彼の燃えるような心すら伝わる様な姿だと思った。するとランスロット卿はそっと屈んでアーサー王の閉じられた瞼に口付けを落とす。
瞼への口付けは憧憬…ランスロット卿は、アーサー王を…
瞬間、映像は掻き消えて、また俺は闇の中に放り出されたと思うと声が聞こえた。
アーサー王の声。凛として、それでいて耳に優しい声。
『悪かった…そなたを巻き込んだ。』
どういうことだろう、酷く良くできた夢だと思う。俺は夢を見ているのだろう?そうとしか思えなかった。
『…すまない、巻き込んですまない…』
また声がする、段々と遠くなっていく悲しげな声が。
待ってくれ、とそう問う間もなく、だんだんと意識が浮上していった。
すると視界に飛び込んできたのは、見慣れない天蓋とさし込む光…一瞬、自分がどこにいるのかわからなくて目を瞬かせていると、
「目が覚めたか」
天蓋の紗幕から顔を出すようにガウェイが寝ている俺を見下ろしていた。彼の紅の髪が朝陽に照らされて朱金に染まる。俺はこの色大好きだと考えつつ、まだ覚醒しきっていない頭で頷くと、ガウェイは微笑して屈み、チュッと鼻梁にからかう様に目覚めのキスをくれた。
こんな風に騎士に起こされるのは美姫が似合うのに俺なんかで申し訳ない。
そう思ってガウェイに微笑み「おはよう」と言えば、彼も快活に笑い「おはよう」と返してくれた。
見ればガウェイはもう紅の長衣に鎧。腰にはガラティーンをさして一部の隙も無い。
俺は彼の姿に少し見惚れる…見慣れているのに、こういう時、本当に騎士というのは罪作りだ。
「食堂に行けば、連れにも会えるだろう」
「ガウェイは?」
一緒に来ないのだろうかと思い尋ねると彼は僅かに微笑んだ、
「約束だからな。お前は今日、獣人を此処に連れてくる。此処なら安全だ、俺の副官にも出る前に言っておく。
…けど俺は彼等の集落も守らなきゃならないんだろ?数日とお前は言った…それだけ事態が切迫しているなら早く動いた方が良い。場所だけ教えてくれ…時間が惜しいから俺は直ぐに発つ。」
言いながらガウェイは一旦、ベッドの端に座って俺を覗き込んでくる、透明度の高い琥珀を覗いているようなガウェイの瞳は綺麗だと思った…真剣だから尚更かもしれない。
それに合わせるように俺は上半身を起こして指先で彼の額に軽く触れて魔法を使ってガウェイに直接獣人の集落の場所を送った…言葉を脳内に直接響かせる伝達魔法の応用だ。
暫くするとガウェイはフッと詰めいていた息を吐き出す。
「わかった、此処か…獣人には見つからないよう遠くから守る。」
「そうして貰うと助かります」
獣人を部下に持っているからか彼らに対して理解が深いガウェイに感謝した。
言わなくても適切に動いてくれる安心感はやはりガウェイの有能さを俺に改めて教えてくれた。
「何もなければ良いんですけど…頼みます」
そう言えばガウェイは破顔して、そのまま顔を近づけてきたと思ったら今度は唇に口付けられた。
「っどうして」
キスをするんですか、と問えばガウェイは少し微笑みながらも真剣な声で俺に囁く、
「帰ったら…お前を隷属の首輪から解放してみせる…俺が帰るまで勝手に出ていくなよ」
そして頬を優しく撫ぜられて、ガウェイは出立した。
俺はこの時、知らなかった…俺のこの約束によって彼をたった一人、敵の只中に放り出すことになろうとは思いもよらなかったのだ。
◆◆◆
場所を変えて紅大理石の広い回廊をガウェイは歩いていた。
向かう先はこの〝紅玉の離宮″の最上階。
朝になれば開かれる最上階の巨大な紅水晶の門扉は、この離宮にある門扉の中では正門に次いで大きい。
そこから吹きこむ風はこの宮殿が山に在ることを思い出させてくれる…また精緻な象嵌が施された荘厳な造りの〝紅玉の離宮″が本来は王族のためのものであることも。
本当ならば一家臣に与えられるような宮ではないのである…最上階からは地平線から登る朝陽をうけて輝く湖面も一望できた。その風光明媚な景色を見やり、ガウェイは紅水晶の門扉へ歩き続ける。
風を受けて揺れる紅の長衣を、腰にさしたガラティーンの柄が少しだけ押さえてくれる。
彼の紅の髪は、風に遊ばれるまま流れている。
そして、ガウェイはカツンと最上階に造られたバルコニーまで歩を進め、清冽な山の空気を一杯に吸い、ニッと見るものを惹き付けるような笑みを彼は浮かべると急速に魔力を高め、声なき声を響かせた。
(疾くこよー…)
あるいはガウェイと同様の魔力を持った者には聞こえたかもしれない…この魔力をこめた呼びかけを。
朱金の魔方陣がガウェイの足元に展開されて、今度は山から吹く風とは違う、下から吹き上げるような強風にガウェイの髪と長衣がはためく。
(契約に従い、我にその力を示せ)
20メートルはあろうかという巨大な魔方陣は眩い光を放つと同時に魔剣・ガラティーンも紅の光を辺りに散らす。その巨大な魔法陣はガウェイが振るう力そのものであった。
(汝は炎そのもの、古き盟約の名のもとに来たれ。)
大気が咆哮を上げたような音が轟いた。いやそれは果たして音だったのだろうか、圧倒的な力が収束する。
やがて空中に炎が舞ったかと思うと、其処には…炎の毛皮を轟々と燃え上がらせる狼が空に浮いていたのである。
そして炎に祝福された騎士は炎をまとった狼の頭をひと撫でして快活に笑う。
「久しぶりだな、ちょっと頼まれてくれよ」
そして狼はガウェイの頬を慕わしげにぺろりと舐めた。
まるで意志があるかのように獣の金色の瞳には理知の輝きがあった。
◆
昨日と同じ食堂に行けばレガンとフルレトは二日酔いになりながらも獣人の騎士と話をしていた。
「あっ来たぞ、お前らの連れだろ、ほら」その人は獣の耳を動かしながら気さくに声をかけてくれたので黙礼する。レガンとフルレトは俺を見るとあからさまにホッとしたようだった。
そして二人でその人に感謝の言葉を述べると俺を囲んで口々に目が覚めて俺がいなくて心配したと言ってくれた。酔い潰れて俺をぼっちにしたのは二人だけども、心配させたことには変わりはないからゴメンと謝りながら、俺は一晩で二人がある程度、此処に慣れたみたいで良かったなと思った。
多分それは獣人の騎士がいたことが大きかったのだろう。
そしてビュッフェ形式でご飯を食べた。
朝から貝の味噌汁とか、パンとか卵とか美味しくてぺろりと食べてしまった。
素朴だが新鮮な食材で作られている、朝から凝ったものは別に食べたくないから丁度いいと思う。
そして食事の後は三人で最初に案内されて、俺が泊まった北の宮に集まり作戦会議をすることにした。
昨日は71人の獣人を助け全員を荷馬車や馬を使って集落へ送った。
途中まで彼らを送ったレガンが彼らの安全は保障したし、集落は武装した若者が守りを固めている。
昨日今日で再び連れ戻されること等ないだろう。
そして最強のカードとしてガウェイが遠くから彼らを警護してくれている。
ガウェイが本気を出せば数十人の奴隷商人なんぞ相手になろう筈もない…そう奴隷商人ならばの話である。
そして俺達はお金の確認を始めた。
レガンの手持ちは305000から167000減って138000リラが残り。
獣人が平均で5000リラ。攫われた獣人は残り142人。今日でまた71人が売られる…単純計算で355000リラ。
俺の手持ちはメーター振り切っているので…数える気も無い。
だって数えてもまた領地経営での利潤が自動的に俺のお財布へと入ってくるから本当に必要がないのだ。
だが二人は難しい顔をしている。
昨日の奴隷オークションの場でも思ったけれど彼等の俺に頼らない姿勢は、とても好感が持てる。
だから俺は笑って言った。
「家族を取り戻すんだろう?お金が足らない分は俺が補填するから、全員を取り戻そう」と。
レガンは暫く黙ったのちに「…必ず返す」と言ってくれて、真剣な彼の金色の瞳が俺を映していた。
それに俺は仕方がないなと苦笑を零す。
「でもそれは盗賊業でだろ?そんなお金は貰えないからさ、後で俺の話を聞いてくれよ?」
「ああ?」
よく分かっていないのだろう。当然だ、だって俺の中でも考えは曖昧なのだから。
全てはこの奴隷オークションが終わってからだと決意を新たに俺はレガンとフルレトに向かって笑う…二人はきっと予想もしないのだろうと思いながら。
そしてフルレトは思い出したように口を開く、
「昨日と同じ流れで皆を連れ出して大丈夫だと思うか?」
どういうことだと視線で問うレガンにフルレトは僅かに躊躇うものの言葉を続ける。
「大勢の獣人を連れ出しているのを見られている…二日目もスムーズに行くだろうか」
レガンもそれは考えていたのだろう、黙り込む。沈黙が落ちた室内に俺は指をたて、一寸良いかと提案してみた。
「それなんだが…ガウェイは自分の離宮を解放して、部下はもちろん、食べていけない貧民も養ってる。
一度、彼の元に身を寄せた方が良いと思うんだ」
俺の発言にレガンは幾分考え込んだようだった。
きっと彼の中で今までの苦難の生活と此処での安らかな獣人の姿が秤となっているのだろう。
すんなりと信じるには彼らは辛い目に遭いすぎたのだ…だから俺は黙った。
俺が更に何かを言って説得するというのは道理が違う。決めるのは結局は自らなのだ。
彼ら自身の選択に、俺が口出して良いことでもないと思う。
そしてどれぐらいの時間が経ったのか、レガンは一つ頷いて、「此処に身を寄せよう」と言った。
随分と長く考え込んでいたわりに短い言葉は、逆に彼がした決断の重さを俺に感じさせた。
彼らは自分たちだけで生きてきたのだ。
何年も何年も、獣人だけの世界で生き、死んでいたのだ。
そこから人に頼るということが、どれほど勇気のいることか俺は本当の意味では分かっていないだろう。
…だが察することは出来るから。レガンの手を取り、俺はただ有難うとだけ伝えた。
その手は温かくて、俺達と何の変りも無いのだと…思えて、顔を合わせて二人で笑った。
それは長い長い獣人の虐げられた歴史の中での転換となるのだが…この時はまだ知る由も無い。
◆
そして、その頃のガウェイは僅かな時間で獣人の集落が見下ろせる崖まで到着していた。
この聖都は聖王の力の元、聖王旗下の将軍は国境へと飛ぶことが出来るようになっている。
ガウェイも軍部最高顧問という役職上、国境までの距離を一瞬にして移動出来るのだった。
そして到着して早々、ガウェイは念には念をと集落の周囲をまわり土地勘を得ながら結界石を置いて、何かあれば直ぐに結界を作動できるような状態で準備した。
まさか自分が居ながら結界を作動させなければならない程のことが起こるとは思っていないが…念には念をだ。
森が深く、木々の間から差しこむ光や新鮮な空気が久しく仕事に忙殺されていたガウェイを癒す。
聖王シュレイザードが攫われてから、外敵に備え不眠不休の態で城下の治安の回復や、兵の統率を行い。民に顔を知られている立場を利用してわざと〝普段通り″に過ごしていたのだ。一日半だけ城から離れる事にはなるが、ガウェイにはあわよくば獣人から聖王を攫った盗賊ジュ・レガンの情報を後で聞けるかもしれないという思惑もあった。
匂いに敏感な獣人たちの目をかいくぐって作業をする。
獣人の見張りに出会いそうになれば気配を消して、木々の後ろに隠れてやり過ごす。
「…見つかったら絶対に袋叩きだろこれ。」
別に悪いことをしている訳ではないが、ガウェイの行動は怪しすぎる。
ただ会わないなら会わない方が良い…彼らの心の平安の為にもその方が良いだろう。
ガウェイは坦々と準備をしていったのだった。
◆
太陽の光に照り返しを放つ黒石畳で隙間なく舗装された聖都の道には、都に夢を抱く商人たちが行きかう。
また老若男女であふれる辻馬車の乗合所や伝説の騎士たちの彫刻がほどこされた噴水広場など人は行きかい、さんざめく光の中で笑い、日々を生活していた…聖王の不在も知らずに。
そしてそんな人々が行きかう主要街道沿い。この聖都においても格式高い〝ホテル・テイコク″は。
外国の賓客も迎えることが出来るホテルとして聖都に置いて特別な位置を占めていた。また聖王・シュレイザード自らこのホテル名を付けたことからも、その重用のされかたが分かるというものである。
〝テイコク″は階層にして7階、周囲の街並みを睥睨する白亜の大理石の造りである。その広い敷地内には温泉施設や馬場も存在し、磨き上げられたガラス扉と最上級のスタッフが客を出迎える。
そしてこの日、“テイコク”の最上階は…ある人々によって貸し切られていた。
最高級のホテルであるがゆえにセキュリティーは民間でありながらトップクラスの此処は…拠点となりえたからである。
それを物語るように甲冑を着た騎士や、逆に〝騎士が商人に身を扮したような″者など…皆が一様に真剣な顔で何事かを確認し、話していたかと思うと外へと出て再び帰ったりと出入りが激しい。そして最も人の出入りが多いテイコクのスイートルームの部屋は両開きの重厚な造りで開け放たれていた。
その部屋に入ると目を引くのはシャンデリアの付けられた豪奢な部屋でも。中央に置かれた石造りのテーブルでもなく、そのテーブルの横に佇む白銀の髪の美丈夫だ。
その青年からは女ならば例え遊びとわかっていても惹かれてしまうであろう魅力が溢れていた。白地に銀の刺繍が細かく施された服も彼の魅力を引き出している。流れるような癖のない銀髪は短めに切りそろえられ、蒼と緑のヘテロクロミアの瞳。清冽なそれでいて強い意志の力を感じさせる理知溢れる瞳は…彼がただ姿が良いお人形ではないと語っている。
青年はテーブルの上に広げられている地図の上を浮かび、人員を表すチェスのような黒石に視線を走らせながら、側に控えている男たちに次々と指示を出してゆく。
「包囲は?」
「万事滞りなく、オークションが行われる時間帯には蟻の子一匹出入りできません」
「遅滞なく進めろ、レッタンダムとの連携はとれるようにしておけ。」
そう青年に指示された平民服姿の男は見事に〝騎士の礼″をして部屋を後にする。
その後も、森の探索をしているエルフの君の定時連絡を受け、宰相ツキュールへ伝令を飛ばしと彼は働き続けたが、やがて銀髪の男は一段落した頃合いで自ら顔を上げて地図上の駒に視線を向ける。
すると一つの駒が男の視線一つでスゥッと空中で音もなく動き、ある宿屋の地図の上で止まった…そこは地下にコロッセオがあるレッタンダムの情報がもたらされた酒場であった…時間が来たのだ。
奴隷オークションは前日とは時間をずらし開催される。
今日は前日よりも数時間早く…まさか奴隷売買が行われないであろう時間帯に売買を行うのだと、〝海賊殺し″レッタンダムから情報は下りてきていた。
青年は腰にさしていた剣に手をあて…一度、深く呼吸をした。
「私は直接、奴隷商の元に潜りこみ奴隷オークションの獣人たちを全て買い取ろう…」
そして彼はサファイアの埋め込まれた貴族の仮面をかぶる、その仮面から覗く瞳は見事なオッドアイだ。
「あと近衛騎士の精鋭十人も紛れ込ませる…聖王陛下の行方を掴むためだ、金に糸目はつけるな。」
そして青年…ヴェルスレムは白地のマントを翻し、部屋を出ていったのだった…彼の後ろからは貴族の連れに扮した近衛騎士たちが付き従う。
〝ホテル・テイコク″から現れたこの集団を町の人々は貴族の忍びと勘違いして道を開けていった。いつの時代も権力者は住民にはどこか親しみずらいものだ。だが、もしもこの時、この集団は彼らが敬愛する騎士ヴェルスレムであったと住民が看破したとしたら、きっと町は少しの混乱したのかもしれない。
何しろ城下には余り気軽に降りては来ないが、彼もガウェイ同様、人々から非常に人気が高いからだ…お近づきになりたい者は妙齢の女性を中心に多かった。
作戦会議室の巨大な木の机の上に、領地内の巨大な地図が置かれ、その上にチェスの駒のような部隊配置を表す黒い駒が光を帯びて浮いている。
「国境警備と治安維持及び兵の巡回はガウェイが滞りなく行ってくれたおかげで敵の封じ込めには成功しておるようじゃ」
宰相であるツキュールが長く白い髭をなでつつ現状を確認すれば、ヴェルスレムはそれに続く形で声を上げる。
「今、エルフの君・シュレルスと閃光の騎士・ファルタが森の中をくまなく探してくれている。獣人一匹、この国から出しはしない。聖王陛下を攫ったこと後悔させなければな。」
ツキュールは鬼気迫る様なヴェルスレムの態度に少し眉を寄せた。彼は今、獣人を一匹と言ったのだ。
(…何もなければ良いが。)
ヴェルスレムの金色の髪は連日の激務にくすんだ色をしており、彼の薄紅色の瞳は不眠の為かいつもより赤い。
だがそんな彼等の元に思わぬところから情報がもたらされた。
「邪魔するぜぃ」という野太い声とドォンッという衝撃共に開け放たれた扉に意識を向ければ、そこには大柄の男が部屋に不作法にも入ってくるところだった。男は鎖帷子と鉄製の鎧を着て、毛皮を肩からかけている。
「レッタンダム、どうした」
ヴェルスレムはそんな作法を気にするでもなく入ってきた男に問いただす。
そう、部屋にやってきた彼は「海賊殺し・レッタンダム」。
逞しく、人の体よりも巨大な斧を振るう男で。賊退治の手腕にかけては、その情報収集に始まってヴェルスレムやガウェイすら凌ぐ力を発揮した。それもかつてレッタンダムの故郷の漁村が海賊に襲われ滅ぼされた怒りに由来する。その怒りが彼を海賊殺しの異名を持つまでにさせ、その彼の肉体は漁師としての仕事と復讐の中で鍛えられたのだった。
そしてレッタンダムは宰相ツキュールの左隣まで来ると、机上の地図の上のある一点を指し示し太い笑みを浮かべる。
「ヴェルの旦那。情報を掴んだ、俺はこれは結構臭いと思ってる」
ヴェルスレムは暫し、レッタンダムの茶色の瞳を見ていた。
彼がさしているのは以前は地下コロッセオがあった場所で、今は入口を塞がれて酒場になっている筈の場所だった。
「理由を聞こう」
ヴェルスレムの薄紅の瞳がスゥッと真剣味を帯びると、レッタンダムは悪童のように笑った。
「そうこなくっちゃな」
そしてレッタンダムは、昨日、その酒場から現れた〝数十人の獣人の奴隷″の噂を披露した。
曰く、何人もの城下の人々が見た、明らかに聖都の者でない奴隷の首輪を着けた獣人たち。
というのも聖都は聖王シュレイザードの意向によって奴隷売買は禁止されており、奴隷だとしたらそれは他の領地で奴隷になった者の筈なのだ。奴隷即ち聖都の住人ではないのである。
そして更に今は魔物が活発化し、周辺から逃げてきた多くの人々はいるが…それにしては奴隷たちの〝身なりが良かった″のだという。まるでつい最近、奴隷に落とされたかのように…
「陛下がご不在の隙に奴隷商が入り込んだやもしれぬ」とツキュールは唸り、レッタンダムは獣人のコミュニティーは強いから、もしも獣人を数十人単位で捕らえられれば聖王を攫った盗賊王ジュレガンの行方も掴めるかもしれないと締めくくった。
それに暫し、ヴェルスレムは考え込んでいるようであったが、彼が再び顔を上げた時には強い意志の力があった。
「…わかった、レッタンダム。お前は引き続き賊の情報収集にあたってくれ。
ツキュール様もガウェイの代わりに騎士の全体の采配をお任せします。」
その言葉にツキュールは思わず尋ねていた。
「ヴェルスレム殿はどうされる?」
その言葉に、ヴェルスレムは微笑み、そしてその部屋にあつらえていた銀製の窓を開け放った。
折しも時間帯は明け方である。太陽の光を受けて豊かに輝く彼の金髪は…風に流れるように銀色に、そして薄紅の瞳は蒼と緑のオッドアイへと緩やかに変化する。
…それは彼のかつての過去世・ランスロット卿の姿だった。
そしてランスロット卿は嫣然と、見るものを惹き付けるような笑みを浮かべた。
「…俺はそこに探りに入る」と。
◆◆◆
俺は闇の中で立っていた。
浮かんでいるのか足は空を蹴るのに怖くはなかった。
頭のどこかで夢だと分かるからかもしれない。
すると闇の中にポツンと映像が映し出される。
その映像の中には二人の人が映っていた。
夜なのだろう薄墨を流したような夜のとばりの中で寝台に寝入っている一人は金髪の青年…あれはアーサー王だ。そしてもう一人は銀髪の騎士・ランスロット卿。
アーサー王が眠っている寝台の側でランスロット卿が佇んで彼を見ている。
ジッとそれは真剣にまるで精緻な美術品でも見るように見詰めている…こっちの息が止まりそうなぐらい彼の燃えるような心すら伝わる様な姿だと思った。するとランスロット卿はそっと屈んでアーサー王の閉じられた瞼に口付けを落とす。
瞼への口付けは憧憬…ランスロット卿は、アーサー王を…
瞬間、映像は掻き消えて、また俺は闇の中に放り出されたと思うと声が聞こえた。
アーサー王の声。凛として、それでいて耳に優しい声。
『悪かった…そなたを巻き込んだ。』
どういうことだろう、酷く良くできた夢だと思う。俺は夢を見ているのだろう?そうとしか思えなかった。
『…すまない、巻き込んですまない…』
また声がする、段々と遠くなっていく悲しげな声が。
待ってくれ、とそう問う間もなく、だんだんと意識が浮上していった。
すると視界に飛び込んできたのは、見慣れない天蓋とさし込む光…一瞬、自分がどこにいるのかわからなくて目を瞬かせていると、
「目が覚めたか」
天蓋の紗幕から顔を出すようにガウェイが寝ている俺を見下ろしていた。彼の紅の髪が朝陽に照らされて朱金に染まる。俺はこの色大好きだと考えつつ、まだ覚醒しきっていない頭で頷くと、ガウェイは微笑して屈み、チュッと鼻梁にからかう様に目覚めのキスをくれた。
こんな風に騎士に起こされるのは美姫が似合うのに俺なんかで申し訳ない。
そう思ってガウェイに微笑み「おはよう」と言えば、彼も快活に笑い「おはよう」と返してくれた。
見ればガウェイはもう紅の長衣に鎧。腰にはガラティーンをさして一部の隙も無い。
俺は彼の姿に少し見惚れる…見慣れているのに、こういう時、本当に騎士というのは罪作りだ。
「食堂に行けば、連れにも会えるだろう」
「ガウェイは?」
一緒に来ないのだろうかと思い尋ねると彼は僅かに微笑んだ、
「約束だからな。お前は今日、獣人を此処に連れてくる。此処なら安全だ、俺の副官にも出る前に言っておく。
…けど俺は彼等の集落も守らなきゃならないんだろ?数日とお前は言った…それだけ事態が切迫しているなら早く動いた方が良い。場所だけ教えてくれ…時間が惜しいから俺は直ぐに発つ。」
言いながらガウェイは一旦、ベッドの端に座って俺を覗き込んでくる、透明度の高い琥珀を覗いているようなガウェイの瞳は綺麗だと思った…真剣だから尚更かもしれない。
それに合わせるように俺は上半身を起こして指先で彼の額に軽く触れて魔法を使ってガウェイに直接獣人の集落の場所を送った…言葉を脳内に直接響かせる伝達魔法の応用だ。
暫くするとガウェイはフッと詰めいていた息を吐き出す。
「わかった、此処か…獣人には見つからないよう遠くから守る。」
「そうして貰うと助かります」
獣人を部下に持っているからか彼らに対して理解が深いガウェイに感謝した。
言わなくても適切に動いてくれる安心感はやはりガウェイの有能さを俺に改めて教えてくれた。
「何もなければ良いんですけど…頼みます」
そう言えばガウェイは破顔して、そのまま顔を近づけてきたと思ったら今度は唇に口付けられた。
「っどうして」
キスをするんですか、と問えばガウェイは少し微笑みながらも真剣な声で俺に囁く、
「帰ったら…お前を隷属の首輪から解放してみせる…俺が帰るまで勝手に出ていくなよ」
そして頬を優しく撫ぜられて、ガウェイは出立した。
俺はこの時、知らなかった…俺のこの約束によって彼をたった一人、敵の只中に放り出すことになろうとは思いもよらなかったのだ。
◆◆◆
場所を変えて紅大理石の広い回廊をガウェイは歩いていた。
向かう先はこの〝紅玉の離宮″の最上階。
朝になれば開かれる最上階の巨大な紅水晶の門扉は、この離宮にある門扉の中では正門に次いで大きい。
そこから吹きこむ風はこの宮殿が山に在ることを思い出させてくれる…また精緻な象嵌が施された荘厳な造りの〝紅玉の離宮″が本来は王族のためのものであることも。
本当ならば一家臣に与えられるような宮ではないのである…最上階からは地平線から登る朝陽をうけて輝く湖面も一望できた。その風光明媚な景色を見やり、ガウェイは紅水晶の門扉へ歩き続ける。
風を受けて揺れる紅の長衣を、腰にさしたガラティーンの柄が少しだけ押さえてくれる。
彼の紅の髪は、風に遊ばれるまま流れている。
そして、ガウェイはカツンと最上階に造られたバルコニーまで歩を進め、清冽な山の空気を一杯に吸い、ニッと見るものを惹き付けるような笑みを彼は浮かべると急速に魔力を高め、声なき声を響かせた。
(疾くこよー…)
あるいはガウェイと同様の魔力を持った者には聞こえたかもしれない…この魔力をこめた呼びかけを。
朱金の魔方陣がガウェイの足元に展開されて、今度は山から吹く風とは違う、下から吹き上げるような強風にガウェイの髪と長衣がはためく。
(契約に従い、我にその力を示せ)
20メートルはあろうかという巨大な魔方陣は眩い光を放つと同時に魔剣・ガラティーンも紅の光を辺りに散らす。その巨大な魔法陣はガウェイが振るう力そのものであった。
(汝は炎そのもの、古き盟約の名のもとに来たれ。)
大気が咆哮を上げたような音が轟いた。いやそれは果たして音だったのだろうか、圧倒的な力が収束する。
やがて空中に炎が舞ったかと思うと、其処には…炎の毛皮を轟々と燃え上がらせる狼が空に浮いていたのである。
そして炎に祝福された騎士は炎をまとった狼の頭をひと撫でして快活に笑う。
「久しぶりだな、ちょっと頼まれてくれよ」
そして狼はガウェイの頬を慕わしげにぺろりと舐めた。
まるで意志があるかのように獣の金色の瞳には理知の輝きがあった。
◆
昨日と同じ食堂に行けばレガンとフルレトは二日酔いになりながらも獣人の騎士と話をしていた。
「あっ来たぞ、お前らの連れだろ、ほら」その人は獣の耳を動かしながら気さくに声をかけてくれたので黙礼する。レガンとフルレトは俺を見るとあからさまにホッとしたようだった。
そして二人でその人に感謝の言葉を述べると俺を囲んで口々に目が覚めて俺がいなくて心配したと言ってくれた。酔い潰れて俺をぼっちにしたのは二人だけども、心配させたことには変わりはないからゴメンと謝りながら、俺は一晩で二人がある程度、此処に慣れたみたいで良かったなと思った。
多分それは獣人の騎士がいたことが大きかったのだろう。
そしてビュッフェ形式でご飯を食べた。
朝から貝の味噌汁とか、パンとか卵とか美味しくてぺろりと食べてしまった。
素朴だが新鮮な食材で作られている、朝から凝ったものは別に食べたくないから丁度いいと思う。
そして食事の後は三人で最初に案内されて、俺が泊まった北の宮に集まり作戦会議をすることにした。
昨日は71人の獣人を助け全員を荷馬車や馬を使って集落へ送った。
途中まで彼らを送ったレガンが彼らの安全は保障したし、集落は武装した若者が守りを固めている。
昨日今日で再び連れ戻されること等ないだろう。
そして最強のカードとしてガウェイが遠くから彼らを警護してくれている。
ガウェイが本気を出せば数十人の奴隷商人なんぞ相手になろう筈もない…そう奴隷商人ならばの話である。
そして俺達はお金の確認を始めた。
レガンの手持ちは305000から167000減って138000リラが残り。
獣人が平均で5000リラ。攫われた獣人は残り142人。今日でまた71人が売られる…単純計算で355000リラ。
俺の手持ちはメーター振り切っているので…数える気も無い。
だって数えてもまた領地経営での利潤が自動的に俺のお財布へと入ってくるから本当に必要がないのだ。
だが二人は難しい顔をしている。
昨日の奴隷オークションの場でも思ったけれど彼等の俺に頼らない姿勢は、とても好感が持てる。
だから俺は笑って言った。
「家族を取り戻すんだろう?お金が足らない分は俺が補填するから、全員を取り戻そう」と。
レガンは暫く黙ったのちに「…必ず返す」と言ってくれて、真剣な彼の金色の瞳が俺を映していた。
それに俺は仕方がないなと苦笑を零す。
「でもそれは盗賊業でだろ?そんなお金は貰えないからさ、後で俺の話を聞いてくれよ?」
「ああ?」
よく分かっていないのだろう。当然だ、だって俺の中でも考えは曖昧なのだから。
全てはこの奴隷オークションが終わってからだと決意を新たに俺はレガンとフルレトに向かって笑う…二人はきっと予想もしないのだろうと思いながら。
そしてフルレトは思い出したように口を開く、
「昨日と同じ流れで皆を連れ出して大丈夫だと思うか?」
どういうことだと視線で問うレガンにフルレトは僅かに躊躇うものの言葉を続ける。
「大勢の獣人を連れ出しているのを見られている…二日目もスムーズに行くだろうか」
レガンもそれは考えていたのだろう、黙り込む。沈黙が落ちた室内に俺は指をたて、一寸良いかと提案してみた。
「それなんだが…ガウェイは自分の離宮を解放して、部下はもちろん、食べていけない貧民も養ってる。
一度、彼の元に身を寄せた方が良いと思うんだ」
俺の発言にレガンは幾分考え込んだようだった。
きっと彼の中で今までの苦難の生活と此処での安らかな獣人の姿が秤となっているのだろう。
すんなりと信じるには彼らは辛い目に遭いすぎたのだ…だから俺は黙った。
俺が更に何かを言って説得するというのは道理が違う。決めるのは結局は自らなのだ。
彼ら自身の選択に、俺が口出して良いことでもないと思う。
そしてどれぐらいの時間が経ったのか、レガンは一つ頷いて、「此処に身を寄せよう」と言った。
随分と長く考え込んでいたわりに短い言葉は、逆に彼がした決断の重さを俺に感じさせた。
彼らは自分たちだけで生きてきたのだ。
何年も何年も、獣人だけの世界で生き、死んでいたのだ。
そこから人に頼るということが、どれほど勇気のいることか俺は本当の意味では分かっていないだろう。
…だが察することは出来るから。レガンの手を取り、俺はただ有難うとだけ伝えた。
その手は温かくて、俺達と何の変りも無いのだと…思えて、顔を合わせて二人で笑った。
それは長い長い獣人の虐げられた歴史の中での転換となるのだが…この時はまだ知る由も無い。
◆
そして、その頃のガウェイは僅かな時間で獣人の集落が見下ろせる崖まで到着していた。
この聖都は聖王の力の元、聖王旗下の将軍は国境へと飛ぶことが出来るようになっている。
ガウェイも軍部最高顧問という役職上、国境までの距離を一瞬にして移動出来るのだった。
そして到着して早々、ガウェイは念には念をと集落の周囲をまわり土地勘を得ながら結界石を置いて、何かあれば直ぐに結界を作動できるような状態で準備した。
まさか自分が居ながら結界を作動させなければならない程のことが起こるとは思っていないが…念には念をだ。
森が深く、木々の間から差しこむ光や新鮮な空気が久しく仕事に忙殺されていたガウェイを癒す。
聖王シュレイザードが攫われてから、外敵に備え不眠不休の態で城下の治安の回復や、兵の統率を行い。民に顔を知られている立場を利用してわざと〝普段通り″に過ごしていたのだ。一日半だけ城から離れる事にはなるが、ガウェイにはあわよくば獣人から聖王を攫った盗賊ジュ・レガンの情報を後で聞けるかもしれないという思惑もあった。
匂いに敏感な獣人たちの目をかいくぐって作業をする。
獣人の見張りに出会いそうになれば気配を消して、木々の後ろに隠れてやり過ごす。
「…見つかったら絶対に袋叩きだろこれ。」
別に悪いことをしている訳ではないが、ガウェイの行動は怪しすぎる。
ただ会わないなら会わない方が良い…彼らの心の平安の為にもその方が良いだろう。
ガウェイは坦々と準備をしていったのだった。
◆
太陽の光に照り返しを放つ黒石畳で隙間なく舗装された聖都の道には、都に夢を抱く商人たちが行きかう。
また老若男女であふれる辻馬車の乗合所や伝説の騎士たちの彫刻がほどこされた噴水広場など人は行きかい、さんざめく光の中で笑い、日々を生活していた…聖王の不在も知らずに。
そしてそんな人々が行きかう主要街道沿い。この聖都においても格式高い〝ホテル・テイコク″は。
外国の賓客も迎えることが出来るホテルとして聖都に置いて特別な位置を占めていた。また聖王・シュレイザード自らこのホテル名を付けたことからも、その重用のされかたが分かるというものである。
〝テイコク″は階層にして7階、周囲の街並みを睥睨する白亜の大理石の造りである。その広い敷地内には温泉施設や馬場も存在し、磨き上げられたガラス扉と最上級のスタッフが客を出迎える。
そしてこの日、“テイコク”の最上階は…ある人々によって貸し切られていた。
最高級のホテルであるがゆえにセキュリティーは民間でありながらトップクラスの此処は…拠点となりえたからである。
それを物語るように甲冑を着た騎士や、逆に〝騎士が商人に身を扮したような″者など…皆が一様に真剣な顔で何事かを確認し、話していたかと思うと外へと出て再び帰ったりと出入りが激しい。そして最も人の出入りが多いテイコクのスイートルームの部屋は両開きの重厚な造りで開け放たれていた。
その部屋に入ると目を引くのはシャンデリアの付けられた豪奢な部屋でも。中央に置かれた石造りのテーブルでもなく、そのテーブルの横に佇む白銀の髪の美丈夫だ。
その青年からは女ならば例え遊びとわかっていても惹かれてしまうであろう魅力が溢れていた。白地に銀の刺繍が細かく施された服も彼の魅力を引き出している。流れるような癖のない銀髪は短めに切りそろえられ、蒼と緑のヘテロクロミアの瞳。清冽なそれでいて強い意志の力を感じさせる理知溢れる瞳は…彼がただ姿が良いお人形ではないと語っている。
青年はテーブルの上に広げられている地図の上を浮かび、人員を表すチェスのような黒石に視線を走らせながら、側に控えている男たちに次々と指示を出してゆく。
「包囲は?」
「万事滞りなく、オークションが行われる時間帯には蟻の子一匹出入りできません」
「遅滞なく進めろ、レッタンダムとの連携はとれるようにしておけ。」
そう青年に指示された平民服姿の男は見事に〝騎士の礼″をして部屋を後にする。
その後も、森の探索をしているエルフの君の定時連絡を受け、宰相ツキュールへ伝令を飛ばしと彼は働き続けたが、やがて銀髪の男は一段落した頃合いで自ら顔を上げて地図上の駒に視線を向ける。
すると一つの駒が男の視線一つでスゥッと空中で音もなく動き、ある宿屋の地図の上で止まった…そこは地下にコロッセオがあるレッタンダムの情報がもたらされた酒場であった…時間が来たのだ。
奴隷オークションは前日とは時間をずらし開催される。
今日は前日よりも数時間早く…まさか奴隷売買が行われないであろう時間帯に売買を行うのだと、〝海賊殺し″レッタンダムから情報は下りてきていた。
青年は腰にさしていた剣に手をあて…一度、深く呼吸をした。
「私は直接、奴隷商の元に潜りこみ奴隷オークションの獣人たちを全て買い取ろう…」
そして彼はサファイアの埋め込まれた貴族の仮面をかぶる、その仮面から覗く瞳は見事なオッドアイだ。
「あと近衛騎士の精鋭十人も紛れ込ませる…聖王陛下の行方を掴むためだ、金に糸目はつけるな。」
そして青年…ヴェルスレムは白地のマントを翻し、部屋を出ていったのだった…彼の後ろからは貴族の連れに扮した近衛騎士たちが付き従う。
〝ホテル・テイコク″から現れたこの集団を町の人々は貴族の忍びと勘違いして道を開けていった。いつの時代も権力者は住民にはどこか親しみずらいものだ。だが、もしもこの時、この集団は彼らが敬愛する騎士ヴェルスレムであったと住民が看破したとしたら、きっと町は少しの混乱したのかもしれない。
何しろ城下には余り気軽に降りては来ないが、彼もガウェイ同様、人々から非常に人気が高いからだ…お近づきになりたい者は妙齢の女性を中心に多かった。
0
あなたにおすすめの小説

人族は一人で生きられないらしい――獣人公爵に拾われ、溺愛されて家族になりました
よっちゃん
BL
人族がほとんど存在しない世界に、
前世の記憶を持ったまま転生した少年・レオン。
獣人が支配する貴族社会。
魔力こそが価値とされ、
「弱い人族」は守られるべき存在として扱われる世界で、
レオンは常識の違いに戸惑いながらも必死に生きようとする。
そんな彼を拾ったのは、
辺境を治める獣人公爵アルト。
寡黙で冷静、しかし一度守ると決めたものは決して手放さない男だった。
溺愛され、守られ、育てられる日々。
だが、レオンはただ守られるだけの存在で終わることを選ばない。
学院での出会い。
貴族社会に潜む差別と陰謀。
そして「番」という、深く重い絆。
レオンは学び、考え、
自分にしかできない魔法理論を武器に、
少しずつ“並び立つ覚悟”を身につけていく。
獣人と人族。
価値観も、立場も、すべてが違う二人が、
それでも選び合い、家族になるまでの物語。
溺愛×成長×異世界BL。
読後に残るのは、
「ここに居場所があっていい」と思える、あたたかな幸福。

黒とオメガの騎士の子育て〜この子確かに俺とお前にそっくりだけど、産んだ覚えないんですけど!?〜
せるせ
BL
王都の騎士団に所属するオメガのセルジュは、ある日なぜか北の若き辺境伯クロードの城で目が覚めた。
しかも隣で泣いているのは、クロードと同じ目を持つ自分にそっくりな赤ん坊で……?
「お前が産んだ、俺の子供だ」
いや、そんなこと言われても、産んだ記憶もあんなことやこんなことをした記憶も無いんですけど!?
クロードとは元々険悪な仲だったはずなのに、一体どうしてこんなことに?
一途な黒髪アルファの年下辺境伯×金髪オメガの年上騎士
※一応オメガバース設定をお借りしています
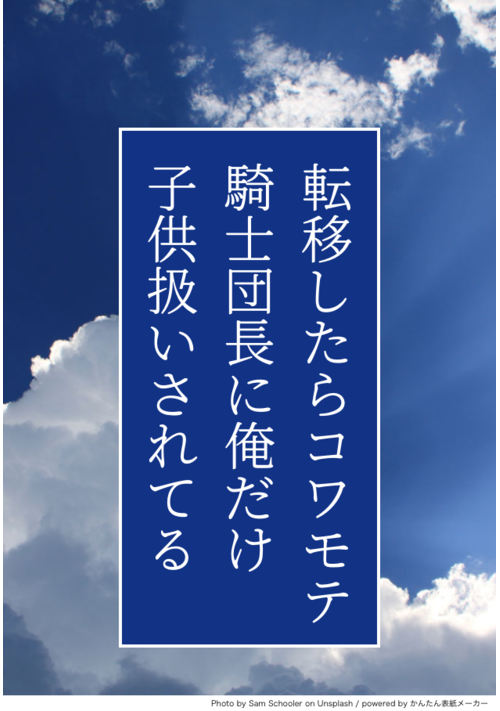
転移したらなぜかコワモテ騎士団長に俺だけ子供扱いされてる
塩チーズ
BL
平々凡々が似合うちょっと中性的で童顔なだけの成人男性。転移して拾ってもらった家の息子がコワモテ騎士団長だった!
特に何も無く平凡な日常を過ごすが、騎士団長の妙な噂を耳にしてある悩みが出来てしまう。

【完結】気が付いたらマッチョなblゲーの主人公になっていた件
白井のわ
BL
雄っぱいが大好きな俺は、気が付いたら大好きなblゲーの主人公になっていた。
最初から好感度MAXのマッチョな攻略対象達に迫られて正直心臓がもちそうもない。
いつも俺を第一に考えてくれる幼なじみ、優しいイケオジの先生、憧れの先輩、皆とのイチャイチャハーレムエンドを目指す俺の学園生活が今始まる。

【Amazonベストセラー入りしました】僕の処刑はいつですか?欲しがり義弟に王位を追われ身代わりの花嫁になったら溺愛王が待っていました。
美咲アリス
BL
「国王陛下!僕は偽者の花嫁です!どうぞ、どうぞ僕を、処刑してください!!」「とりあえず、落ち着こうか?(笑)」意地悪な義母の策略で義弟の代わりに辺境国へ嫁いだオメガ王子のフウル。正直な性格のせいで嘘をつくことができずに命を捨てる覚悟で夫となる国王に真実を告げる。だが美貌の国王リオ・ナバはなぜかにっこりと微笑んだ。そしてフウルを甘々にもてなしてくれる。「きっとこれは処刑前の罠?」不幸生活が身についたフウルはビクビクしながら城で暮らすが、実は国王にはある考えがあって⋯⋯?(Amazonベストセラー入りしました。1位。1/24,2024)

公爵家の末っ子に転生しました〜出来損ないなので潔く退場しようとしたらうっかり溺愛されてしまった件について〜
上総啓
BL
公爵家の末っ子に転生したシルビオ。
体が弱く生まれて早々ぶっ倒れ、家族は見事に過保護ルートへと突き進んでしまった。
両親はめちゃくちゃ溺愛してくるし、超強い兄様はブラコンに育ち弟絶対守るマンに……。
せっかくファンタジーの世界に転生したんだから魔法も使えたり?と思ったら、我が家に代々伝わる上位氷魔法が俺にだけ使えない?
しかも俺に使える魔法は氷魔法じゃなく『神聖魔法』?というか『神聖魔法』を操れるのは神に選ばれた愛し子だけ……?
どうせ余命幾ばくもない出来損ないなら仕方ない、お荷物の僕はさっさと今世からも退場しよう……と思ってたのに?
偶然騎士たちを神聖魔法で救って、何故か天使と呼ばれて崇められたり。終いには帝国最強の狂血皇子に溺愛されて囲われちゃったり……いやいやちょっと待て。魔王様、主神様、まさかアンタらも?
……ってあれ、なんかめちゃくちゃ囲われてない??
―――
病弱ならどうせすぐ死ぬかー。ならちょっとばかし遊んでもいいよね?と自由にやってたら無駄に最強な奴らに溺愛されちゃってた受けの話。
※別名義で連載していた作品になります。
(名義を統合しこちらに移動することになりました)

やっと退場できるはずだったβの悪役令息。ワンナイトしたらΩになりました。
毒島醜女
BL
目が覚めると、妻であるヒロインを虐げた挙句に彼女の運命の番である皇帝に断罪される最低最低なモラハラDV常習犯の悪役夫、イライ・ロザリンドに転生した。
そんな最期は絶対に避けたいイライはヒーローとヒロインの仲を結ばせつつ、ヒロインと円満に別れる為に策を練った。
彼の努力は実り、主人公たちは結ばれ、イライはお役御免となった。
「これでやっと安心して退場できる」
これまでの自分の努力を労うように酒場で飲んでいたイライは、いい薫りを漂わせる男と意気投合し、彼と一夜を共にしてしまう。
目が覚めると罪悪感に襲われ、すぐさま宿を去っていく。
「これじゃあ原作のイライと変わらないじゃん!」
その後体調不良を訴え、医師に診てもらうととんでもない事を言われたのだった。
「あなた……Ωになっていますよ」
「へ?」
そしてワンナイトをした男がまさかの国の英雄で、まさかまさか求愛し公開プロポーズまでして来て――
オメガバースの世界で運命に導かれる、強引な俺様α×頑張り屋な元悪役令息の元βのΩのラブストーリー。

獣のような男が入浴しているところに落っこちた結果
ひづき
BL
異界に落ちたら、獣のような男が入浴しているところだった。
そのまま美味しく頂かれて、流されるまま愛でられる。
2023/04/06 後日談追加
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















