23 / 26
番外編
The Wedding of Sir Gawain and Dame RagnelleⅠ
しおりを挟む
これは古の昔のお話。
或る時、キャメロット城のアーサー王のもとに、若い女が駆け込んできました。
女は身分ある者らしく絹のドレスを哀れにも乱れさせて、切羽詰ったように髪も乱しておりました。
「陛下、アーサー王。どうぞ善良なる民に慈悲をおかけになり、お助け下さいませっ」
そう言ったきり泣き伏した女性に円卓の騎士たちは手をかし支えると、玉座にましますアーサー王に次第を話するよう促しました。
ガウェイン卿といえばアーサー王の側に控えながらも他の騎士たちが女性に願いを奏上するよう勧めるのを、心に引っかかって見ておりました。
アーサー王は慈悲深いのでございます。
とても、とても。
それこそ妖精王に愛され、大陸を統治せしめたほどに慈悲深く強い王なのです。
故に本来なら統治者として美徳であるべきそれによって、大勢の民の悩みをアーサーが王として独り抱え、民の苦しみを払うために心血を注いでしまうことをガウェイン卿は長い間で知っていました。
だからこそガウェイン卿はアーサー王を傍らで支えたいと想っておりますが、民の願いは王しか抱えられぬものであり、ガウェイン卿には抱えることは出来ないものなのでございます。
それはまるで独り玉座に在るアーサーに降りかかる呪いのようだともガウェイン卿は思います。
そんなことを考えている間にも、女は哀れに泣きながらも懸命に事の次第を陛下に奏上なさいます。
そんな婦人の涙を誘う姿にすらガウェイン卿は心は動かされませんでした。
それよりその婦人の涙を受け止めるアーサー王の姿を横から盗み見れば、王はガウェイン卿が思った通り、女性を気遣わしげに見ております。
そんなアーサー王を騎士として誇りに思う反面、ガウェイン卿はアーサー王の心を抱きしめてしまいたいと暴力的な気持ちに切なくなるのでございます。
「あれは夕焼けが血のように染まった日のことでございました。」
そう口火を切った彼女の話は俄かには信じられないことではございました。
曰く、悪の騎士が彼女の夫である領主を捕虜にし、土地を奪ってしまったということです。
領主であるからには剣を扱うこともございましたでしょう、また領主を守り侍る騎士もいたでしょうに土地を奪われたというのです。
「そなたの夫君は無事なのか」とアーサー王が尋ねますと夫人は泣き伏しながらも頷き返します。
故にアーサー王は決意を秘めた瞳で凛と宣言なさいました。
「城に赴き、その騎士から話を聞こう。
事がつまびらかになり、そなたの夫に正義があるのならば私は助力は惜しまない。」
慈悲をお見せになり、更に夫人をキャメロット城で守ると宣言なさったのでございます。
***
此処で夫人の領地へ向かう手勢を選ぶためにアーサー王は動き始めました。
その領地へ行って、この件に関わった領主や騎士の話を聞かなければ、現状を把握することも、ましてや助ける事もままなりません。
アーサー王が下働きに剣と甲冑の研磨をお命じになられたところでアーサーの部屋を訪うものがございました。
木製のドアが開かれ現れたのは、甲冑を纏ったキャメロットが誇る凛々しい円卓の騎士達です。
順に円卓騎士の筆頭・ランスロット卿。
リオネス王子・トリスタン卿。
そして炎の騎士・ガウェイン卿でした。
「どうしたんだ、皆そろって怖い顔をしている」
微笑むアーサー王ですが本当は騎士たちが揃って此処に来た理由は分かっています。
「アーサー、三人で話し合いました。私達が行きますので貴方はキャメロットで報告をお待ちください。」とランスロット卿。
「俺の案内で半日も馬を駆ければ到着する、お前が出向くことではない」とトリスタン卿。
「安全なところに居てくれた方が俺たちは安心なんだ」とガウェイン卿。
三者三様にアーサー王を説得にかかります。
なにせこの王様といったら常々騎士たちの目をかいくぐって一人で城下に下りてしまわれるものですから彼等の説得も力が入るのでございます。
騎士として唯一の主に怪我の一つもさせたくはないのです。
けれど民の為ということが関わるとアーサー王は頑なです。
「私が行った方がその場で判断が出来るであろう」
淡く溶けるように微笑む姿は人を惹き付けてやまない抗いがたい魅力が溢れております。
騎士達は王のこの微笑みに弱いのですけれど負けるわけには参りません、なにしろ大切な王を守るためのことです。
「危険かどうか分かりません、どうか初めは円卓の騎士たちにお任せください」とランスロット卿、尤もなことでことでございます。
けれど王は一歩、騎士達の前に立ち、こう口を開きました。
「私は王であり、騎士だ。
騎士として、王としてお前たちの前で誇れる私でありたい。
卑怯者に誰が付いて来てくれるであろうか…危険であるなら、その場に私はいたいのだ」と。
王子であらせられた時から知っている騎士は口をつぐみ、そして溜息を零しますと彼等は微笑みました。
「王の意志のままに、俺たちの命は王のもの。王の願いを叶えましょう」
そしてガウェイン卿がアーサー王に忠誠の口付けを手の甲へと送りました。
出発は暁と共に、そしてアーサー王は出発なさったのでございます。
◆
城は山を二つ越えた崖の上に聳え立っておりました。堅牢なそれはとても騎士一人に攻め落とせそうなほど無防備ではございません。
というよりも崖を自然の要塞とし敵の攻撃を跳ねつける堅牢な砦でございました。
アーサーはランスロット、ガウェイン、トリスタンを側に侍り王の格好をしてまずは城下町へ入ろうとなさいました。
するとバタバタという羽ばたきとともに、一羽の鴉が一行の前に入り込んで一行を見下ろす木の上に羽根をおろしたのでございます。
神聖な古代を思わせる威厳を備えた鴉。
その鴉は会釈をすることもなく、ひとときもとどまることなく、しかし、貴人淑女のような威厳を保ちながら、樹の上に止まると、それっきり、そこで動かなくなりました。
その鴉の振る舞いが、あまりに厳めしく品位あるものだったのでガウェイン卿が前に進み出て尋ねます。
「そなたは、トサカこそ刈り込まれていたとしても、臆病者には見えはしない。
夜の岸辺からさすらってきた、恐るべき不吉な古代の鴉よ、
夜の支配する冥土の岸辺で何と呼ばれているのか、そなたの御名を唱えよ。」
鴉はそして言った、「Nevermore」と。
鳥がかくも明瞭に言葉を喋ったのを聞いて、一行はひどく驚きました、その答えが、意味も脈絡もなかったとしても。
その鴉は、豊かな繁りをみせる幹に独り止まったまま、喋ったのはその一言だけ。
その一言で、彼の魂を吐き出してしまったかのようでした。彼はそれ以上、彼は何も喋らず、羽毛一本も動かしませんでした。
一体、この不吉な古代の鳥は…この気味が悪い、不恰好な、ぞっとするような、やつれた、不吉な古代の鳥は、
「Never more」と呻くことで、何を伝えようとしているのかガウェイン卿は考えます。
そして腰にさしていた炎の魔剣を引き抜きますと火が炙られるように鞘から零れました。
「魔性のものよ! 鳥にしろ悪魔にしろ、預言者に違いない。
頭上を覆う天に誓って、我々が共に崇める神に誓って俺に語るがいい!
その言葉が、我々の別れの合図だ! 鳥よ、悪魔め!」
そして更にガウェイン卿は果敢にも叫びます。
「出て行け! 夜の支配する冥土の岸辺へ!
羽一枚も残すんじゃない、貴様の話した嘘を思い出させるようなものは何一つ!
俺の心から貴様の嘴を抜いていけ!」
ついに振りかぶる剣から放たれた炎は樹に止まった鴉に直撃し火が燃え盛りました。
そしてその炎の中、鴉はそして言ったのでございます、「Never more」と。
鴉は、飛び回ることもなく、今もなおそこに止まり。
一行の視界の上、幹に止まって身を焼かれながら今もなお、そこに止まっているのです。
鴉の眼は、夢見る悪魔の眼のようで、緋の光が鴉の体を燃やし、
焔の中ゆらめくその影から、抜け出すことはないだろうと不意にガウェイン卿は理解しました――
…Never more、もう二度と!
それはこれからの彼を暗示していたのでございます。
或る時、キャメロット城のアーサー王のもとに、若い女が駆け込んできました。
女は身分ある者らしく絹のドレスを哀れにも乱れさせて、切羽詰ったように髪も乱しておりました。
「陛下、アーサー王。どうぞ善良なる民に慈悲をおかけになり、お助け下さいませっ」
そう言ったきり泣き伏した女性に円卓の騎士たちは手をかし支えると、玉座にましますアーサー王に次第を話するよう促しました。
ガウェイン卿といえばアーサー王の側に控えながらも他の騎士たちが女性に願いを奏上するよう勧めるのを、心に引っかかって見ておりました。
アーサー王は慈悲深いのでございます。
とても、とても。
それこそ妖精王に愛され、大陸を統治せしめたほどに慈悲深く強い王なのです。
故に本来なら統治者として美徳であるべきそれによって、大勢の民の悩みをアーサーが王として独り抱え、民の苦しみを払うために心血を注いでしまうことをガウェイン卿は長い間で知っていました。
だからこそガウェイン卿はアーサー王を傍らで支えたいと想っておりますが、民の願いは王しか抱えられぬものであり、ガウェイン卿には抱えることは出来ないものなのでございます。
それはまるで独り玉座に在るアーサーに降りかかる呪いのようだともガウェイン卿は思います。
そんなことを考えている間にも、女は哀れに泣きながらも懸命に事の次第を陛下に奏上なさいます。
そんな婦人の涙を誘う姿にすらガウェイン卿は心は動かされませんでした。
それよりその婦人の涙を受け止めるアーサー王の姿を横から盗み見れば、王はガウェイン卿が思った通り、女性を気遣わしげに見ております。
そんなアーサー王を騎士として誇りに思う反面、ガウェイン卿はアーサー王の心を抱きしめてしまいたいと暴力的な気持ちに切なくなるのでございます。
「あれは夕焼けが血のように染まった日のことでございました。」
そう口火を切った彼女の話は俄かには信じられないことではございました。
曰く、悪の騎士が彼女の夫である領主を捕虜にし、土地を奪ってしまったということです。
領主であるからには剣を扱うこともございましたでしょう、また領主を守り侍る騎士もいたでしょうに土地を奪われたというのです。
「そなたの夫君は無事なのか」とアーサー王が尋ねますと夫人は泣き伏しながらも頷き返します。
故にアーサー王は決意を秘めた瞳で凛と宣言なさいました。
「城に赴き、その騎士から話を聞こう。
事がつまびらかになり、そなたの夫に正義があるのならば私は助力は惜しまない。」
慈悲をお見せになり、更に夫人をキャメロット城で守ると宣言なさったのでございます。
***
此処で夫人の領地へ向かう手勢を選ぶためにアーサー王は動き始めました。
その領地へ行って、この件に関わった領主や騎士の話を聞かなければ、現状を把握することも、ましてや助ける事もままなりません。
アーサー王が下働きに剣と甲冑の研磨をお命じになられたところでアーサーの部屋を訪うものがございました。
木製のドアが開かれ現れたのは、甲冑を纏ったキャメロットが誇る凛々しい円卓の騎士達です。
順に円卓騎士の筆頭・ランスロット卿。
リオネス王子・トリスタン卿。
そして炎の騎士・ガウェイン卿でした。
「どうしたんだ、皆そろって怖い顔をしている」
微笑むアーサー王ですが本当は騎士たちが揃って此処に来た理由は分かっています。
「アーサー、三人で話し合いました。私達が行きますので貴方はキャメロットで報告をお待ちください。」とランスロット卿。
「俺の案内で半日も馬を駆ければ到着する、お前が出向くことではない」とトリスタン卿。
「安全なところに居てくれた方が俺たちは安心なんだ」とガウェイン卿。
三者三様にアーサー王を説得にかかります。
なにせこの王様といったら常々騎士たちの目をかいくぐって一人で城下に下りてしまわれるものですから彼等の説得も力が入るのでございます。
騎士として唯一の主に怪我の一つもさせたくはないのです。
けれど民の為ということが関わるとアーサー王は頑なです。
「私が行った方がその場で判断が出来るであろう」
淡く溶けるように微笑む姿は人を惹き付けてやまない抗いがたい魅力が溢れております。
騎士達は王のこの微笑みに弱いのですけれど負けるわけには参りません、なにしろ大切な王を守るためのことです。
「危険かどうか分かりません、どうか初めは円卓の騎士たちにお任せください」とランスロット卿、尤もなことでことでございます。
けれど王は一歩、騎士達の前に立ち、こう口を開きました。
「私は王であり、騎士だ。
騎士として、王としてお前たちの前で誇れる私でありたい。
卑怯者に誰が付いて来てくれるであろうか…危険であるなら、その場に私はいたいのだ」と。
王子であらせられた時から知っている騎士は口をつぐみ、そして溜息を零しますと彼等は微笑みました。
「王の意志のままに、俺たちの命は王のもの。王の願いを叶えましょう」
そしてガウェイン卿がアーサー王に忠誠の口付けを手の甲へと送りました。
出発は暁と共に、そしてアーサー王は出発なさったのでございます。
◆
城は山を二つ越えた崖の上に聳え立っておりました。堅牢なそれはとても騎士一人に攻め落とせそうなほど無防備ではございません。
というよりも崖を自然の要塞とし敵の攻撃を跳ねつける堅牢な砦でございました。
アーサーはランスロット、ガウェイン、トリスタンを側に侍り王の格好をしてまずは城下町へ入ろうとなさいました。
するとバタバタという羽ばたきとともに、一羽の鴉が一行の前に入り込んで一行を見下ろす木の上に羽根をおろしたのでございます。
神聖な古代を思わせる威厳を備えた鴉。
その鴉は会釈をすることもなく、ひとときもとどまることなく、しかし、貴人淑女のような威厳を保ちながら、樹の上に止まると、それっきり、そこで動かなくなりました。
その鴉の振る舞いが、あまりに厳めしく品位あるものだったのでガウェイン卿が前に進み出て尋ねます。
「そなたは、トサカこそ刈り込まれていたとしても、臆病者には見えはしない。
夜の岸辺からさすらってきた、恐るべき不吉な古代の鴉よ、
夜の支配する冥土の岸辺で何と呼ばれているのか、そなたの御名を唱えよ。」
鴉はそして言った、「Nevermore」と。
鳥がかくも明瞭に言葉を喋ったのを聞いて、一行はひどく驚きました、その答えが、意味も脈絡もなかったとしても。
その鴉は、豊かな繁りをみせる幹に独り止まったまま、喋ったのはその一言だけ。
その一言で、彼の魂を吐き出してしまったかのようでした。彼はそれ以上、彼は何も喋らず、羽毛一本も動かしませんでした。
一体、この不吉な古代の鳥は…この気味が悪い、不恰好な、ぞっとするような、やつれた、不吉な古代の鳥は、
「Never more」と呻くことで、何を伝えようとしているのかガウェイン卿は考えます。
そして腰にさしていた炎の魔剣を引き抜きますと火が炙られるように鞘から零れました。
「魔性のものよ! 鳥にしろ悪魔にしろ、預言者に違いない。
頭上を覆う天に誓って、我々が共に崇める神に誓って俺に語るがいい!
その言葉が、我々の別れの合図だ! 鳥よ、悪魔め!」
そして更にガウェイン卿は果敢にも叫びます。
「出て行け! 夜の支配する冥土の岸辺へ!
羽一枚も残すんじゃない、貴様の話した嘘を思い出させるようなものは何一つ!
俺の心から貴様の嘴を抜いていけ!」
ついに振りかぶる剣から放たれた炎は樹に止まった鴉に直撃し火が燃え盛りました。
そしてその炎の中、鴉はそして言ったのでございます、「Never more」と。
鴉は、飛び回ることもなく、今もなおそこに止まり。
一行の視界の上、幹に止まって身を焼かれながら今もなお、そこに止まっているのです。
鴉の眼は、夢見る悪魔の眼のようで、緋の光が鴉の体を燃やし、
焔の中ゆらめくその影から、抜け出すことはないだろうと不意にガウェイン卿は理解しました――
…Never more、もう二度と!
それはこれからの彼を暗示していたのでございます。
0
あなたにおすすめの小説

人族は一人で生きられないらしい――獣人公爵に拾われ、溺愛されて家族になりました
よっちゃん
BL
人族がほとんど存在しない世界に、
前世の記憶を持ったまま転生した少年・レオン。
獣人が支配する貴族社会。
魔力こそが価値とされ、
「弱い人族」は守られるべき存在として扱われる世界で、
レオンは常識の違いに戸惑いながらも必死に生きようとする。
そんな彼を拾ったのは、
辺境を治める獣人公爵アルト。
寡黙で冷静、しかし一度守ると決めたものは決して手放さない男だった。
溺愛され、守られ、育てられる日々。
だが、レオンはただ守られるだけの存在で終わることを選ばない。
学院での出会い。
貴族社会に潜む差別と陰謀。
そして「番」という、深く重い絆。
レオンは学び、考え、
自分にしかできない魔法理論を武器に、
少しずつ“並び立つ覚悟”を身につけていく。
獣人と人族。
価値観も、立場も、すべてが違う二人が、
それでも選び合い、家族になるまでの物語。
溺愛×成長×異世界BL。
読後に残るのは、
「ここに居場所があっていい」と思える、あたたかな幸福。

黒とオメガの騎士の子育て〜この子確かに俺とお前にそっくりだけど、産んだ覚えないんですけど!?〜
せるせ
BL
王都の騎士団に所属するオメガのセルジュは、ある日なぜか北の若き辺境伯クロードの城で目が覚めた。
しかも隣で泣いているのは、クロードと同じ目を持つ自分にそっくりな赤ん坊で……?
「お前が産んだ、俺の子供だ」
いや、そんなこと言われても、産んだ記憶もあんなことやこんなことをした記憶も無いんですけど!?
クロードとは元々険悪な仲だったはずなのに、一体どうしてこんなことに?
一途な黒髪アルファの年下辺境伯×金髪オメガの年上騎士
※一応オメガバース設定をお借りしています
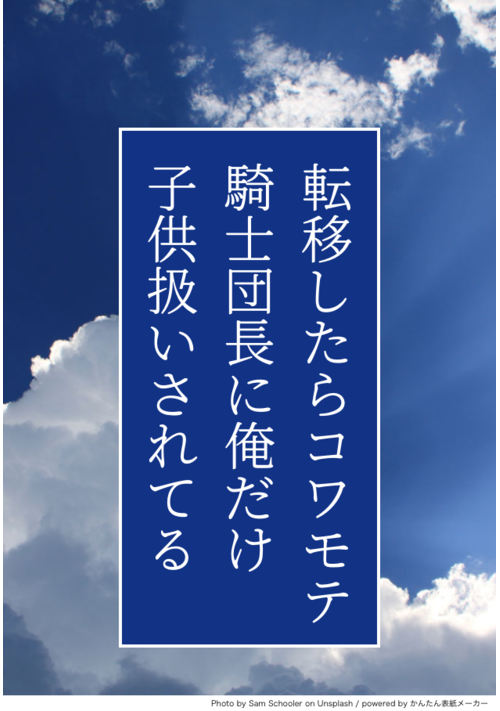
転移したらなぜかコワモテ騎士団長に俺だけ子供扱いされてる
塩チーズ
BL
平々凡々が似合うちょっと中性的で童顔なだけの成人男性。転移して拾ってもらった家の息子がコワモテ騎士団長だった!
特に何も無く平凡な日常を過ごすが、騎士団長の妙な噂を耳にしてある悩みが出来てしまう。

【完結】気が付いたらマッチョなblゲーの主人公になっていた件
白井のわ
BL
雄っぱいが大好きな俺は、気が付いたら大好きなblゲーの主人公になっていた。
最初から好感度MAXのマッチョな攻略対象達に迫られて正直心臓がもちそうもない。
いつも俺を第一に考えてくれる幼なじみ、優しいイケオジの先生、憧れの先輩、皆とのイチャイチャハーレムエンドを目指す俺の学園生活が今始まる。

【Amazonベストセラー入りしました】僕の処刑はいつですか?欲しがり義弟に王位を追われ身代わりの花嫁になったら溺愛王が待っていました。
美咲アリス
BL
「国王陛下!僕は偽者の花嫁です!どうぞ、どうぞ僕を、処刑してください!!」「とりあえず、落ち着こうか?(笑)」意地悪な義母の策略で義弟の代わりに辺境国へ嫁いだオメガ王子のフウル。正直な性格のせいで嘘をつくことができずに命を捨てる覚悟で夫となる国王に真実を告げる。だが美貌の国王リオ・ナバはなぜかにっこりと微笑んだ。そしてフウルを甘々にもてなしてくれる。「きっとこれは処刑前の罠?」不幸生活が身についたフウルはビクビクしながら城で暮らすが、実は国王にはある考えがあって⋯⋯?(Amazonベストセラー入りしました。1位。1/24,2024)

公爵家の末っ子に転生しました〜出来損ないなので潔く退場しようとしたらうっかり溺愛されてしまった件について〜
上総啓
BL
公爵家の末っ子に転生したシルビオ。
体が弱く生まれて早々ぶっ倒れ、家族は見事に過保護ルートへと突き進んでしまった。
両親はめちゃくちゃ溺愛してくるし、超強い兄様はブラコンに育ち弟絶対守るマンに……。
せっかくファンタジーの世界に転生したんだから魔法も使えたり?と思ったら、我が家に代々伝わる上位氷魔法が俺にだけ使えない?
しかも俺に使える魔法は氷魔法じゃなく『神聖魔法』?というか『神聖魔法』を操れるのは神に選ばれた愛し子だけ……?
どうせ余命幾ばくもない出来損ないなら仕方ない、お荷物の僕はさっさと今世からも退場しよう……と思ってたのに?
偶然騎士たちを神聖魔法で救って、何故か天使と呼ばれて崇められたり。終いには帝国最強の狂血皇子に溺愛されて囲われちゃったり……いやいやちょっと待て。魔王様、主神様、まさかアンタらも?
……ってあれ、なんかめちゃくちゃ囲われてない??
―――
病弱ならどうせすぐ死ぬかー。ならちょっとばかし遊んでもいいよね?と自由にやってたら無駄に最強な奴らに溺愛されちゃってた受けの話。
※別名義で連載していた作品になります。
(名義を統合しこちらに移動することになりました)

やっと退場できるはずだったβの悪役令息。ワンナイトしたらΩになりました。
毒島醜女
BL
目が覚めると、妻であるヒロインを虐げた挙句に彼女の運命の番である皇帝に断罪される最低最低なモラハラDV常習犯の悪役夫、イライ・ロザリンドに転生した。
そんな最期は絶対に避けたいイライはヒーローとヒロインの仲を結ばせつつ、ヒロインと円満に別れる為に策を練った。
彼の努力は実り、主人公たちは結ばれ、イライはお役御免となった。
「これでやっと安心して退場できる」
これまでの自分の努力を労うように酒場で飲んでいたイライは、いい薫りを漂わせる男と意気投合し、彼と一夜を共にしてしまう。
目が覚めると罪悪感に襲われ、すぐさま宿を去っていく。
「これじゃあ原作のイライと変わらないじゃん!」
その後体調不良を訴え、医師に診てもらうととんでもない事を言われたのだった。
「あなた……Ωになっていますよ」
「へ?」
そしてワンナイトをした男がまさかの国の英雄で、まさかまさか求愛し公開プロポーズまでして来て――
オメガバースの世界で運命に導かれる、強引な俺様α×頑張り屋な元悪役令息の元βのΩのラブストーリー。

男子高校生だった俺は異世界で幼児になり 訳あり筋肉ムキムキ集団に保護されました。
カヨワイさつき
ファンタジー
高校3年生の神野千明(かみの ちあき)。
今年のメインイベントは受験、
あとはたのしみにしている北海道への修学旅行。
だがそんな彼は飛行機が苦手だった。
電車バスはもちろん、ひどい乗り物酔いをするのだった。今回も飛行機で乗り物酔いをおこしトイレにこもっていたら、いつのまにか気を失った?そして、ちがう場所にいた?!
あれ?身の危険?!でも、夢の中だよな?
急死に一生?と思ったら、筋肉ムキムキのワイルドなイケメンに拾われたチアキ。
さらに、何かがおかしいと思ったら3歳児になっていた?!
変なレアスキルや神具、
八百万(やおよろず)の神の加護。
レアチート盛りだくさん?!
半ばあたりシリアス
後半ざまぁ。
訳あり幼児と訳あり集団たちとの物語。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
北海道、アイヌ語、かっこ良さげな名前
お腹がすいた時に食べたい食べ物など
思いついた名前とかをもじり、
なんとか、名前決めてます。
***
お名前使用してもいいよ💕っていう
心優しい方、教えて下さい🥺
悪役には使わないようにします、たぶん。
ちょっとオネェだったり、
アレ…だったりする程度です😁
すでに、使用オッケーしてくださった心優しい
皆様ありがとうございます😘
読んでくださる方や応援してくださる全てに
めっちゃ感謝を込めて💕
ありがとうございます💞
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















