58 / 96
招かれざる
しおりを挟む
◆◆◆◆◆
御一新前の下屋敷を、現在の本宅とすることが多い大名華族だが、田中子爵家も御多分に洩れず。
本駒込は元大名、官の役人の屋敷が立ち並ぶ地域となっていた。
田中家においては、昨年、跡取りである光留が不在のうちに大きな改築を施していた。
それは、成人した光留の住まいを両親と別にするものであり、子爵家において跡取りの結婚を念頭においたものだというのは、誰もが知ることだった。
母屋と庭を挟み、並ぶ形で建てられた離れ様式だが、二間程度の こぢんまりとしたものではなく、母屋同等の物を揃えた立派な離れとなっていた。
しかし、未だ夫人不在の光留なのだから、食事や風呂などは、母屋で済ませる為、自室と使用人部屋以外は、使わない。
子爵家の下女は、放置するとクモの巣が張りかねない部屋を毎日掃除するのに、半日費やす有り様だった。
そんなことだから、乳母の宵は「早く、早く」と花嫁御寮の御出を願う。
しかし、当の光留は まっしぐらに1人の女を追いかけ回すものだから、最近 宵の口癖は「諦めが肝心」という、悟りにも似たものになっていた。
家のことを取り仕切る宵は、光留の跡継ぎを待ち望む代表格であり、生母である子爵夫人よりも熱心に縁組のことを考えていた。夫人に至っては、元々物静かな人であり、口を挟むこともない。
久我侯爵家の令嬢である夫人は、津多子という。鹿鳴館で光留が連れていた宮津子の叔母にあたり、姿形は光留よりも宮津子に似ている。
栗毛の髪を上品に巻き上げ、粋な縦縞をよく着こなす。座っているだけで お姫様といった風情だ。
そんな津多子に、夫人付きの女中である奈緒が声をかけた。
「奥方様、先程、お勝手口で宵さんが騒いでおられたのですが、不思議なことでお相手が外の者のようでした」
「……外の者? 誰です?」
「日暮れに御用聞きでもありませんし、成り行きを見てくるようにと、人をやりましたが……」
「そう……、貴女は若いのに気が利くわね。あら、アキさん、おいでなさい」
奈緒の後をついてきたのだろう、1匹の三毛猫がニャーと、甘えた声で膝にすり寄る。以前、光留が黒田から譲り受けた猫のアキだ。
大切に飼われているらしく、ビロードの紐に小さな鈴を通されたものを首に掛けられ、声と同じく可愛らしく鳴らす。
「奈緒が、よく面倒をみるから随分、懐いているわね……そうだわ、私も何か探してこようかしら」
「奥方様、私が」
「いいのよ、お勝手に行く口実ができたわ」
津多子は、アキを抱き上げると敷居を跨いだ。長い廊下を二折れ、三折れ、滑るように進むと、明らかに普段とは異なることがわかった。突き当たりには 2人の女中が、お勝手を覗き、ヒソヒソと声を潜めているのが見てとれた。耳に入るのは宵の声だ。
覗く手間が省けたと、壁に寄りかかり耳を澄ます。そんな子爵夫人に気付いた女中が、慌てて頭を下げるが津多子は、人差し指を唇に寄せ無言で、知らぬ顔を強要してみせた。
その時「お引き取りください!」と、強く放たれたのは、宵の一際大きな声であり、それだけで招かざる客のようだと、津多子は察した。続く言葉は、宵ではなかった。
「光留様にお取りつぎ下さい」と、切羽詰まる女の声は、必死に追いすがるといった具合に甲高く響く。
「あら……また、あの子ったら」
多津子は、ねぇ?と 猫のアキに小首を傾げてみせる。光留に会わせろと、屋敷にやってくる女は初めてではない。
最近では3月程前にも、何処ぞの半玉がやって来た。面倒をみるなど、軽口を叩いたのかと思ったが、そのような事実はなく、ただ座敷で話し込んだだけだという。
宵が 宥めすかし、置屋の女将に引き渡したのは言うまでもない。
あの時は、迂闊に名乗ってしまったと後悔していたようだったが、今回もその類いだろうと多津子は、お勝手に背を向けた――
「晃子が参ったと一言お伝え下さい!」
「どちらの晃子さんでしょうか!? 草履も履かずにやって来るような方を、当家の若様に会わせる訳には参りません!」
捲し立てる宵の言葉に、多津子の肩がピクリと上がった。「アキ……アキコさん?」と、腕に抱く猫に視線を落とす。
「……ッ!! それは……」
グッと言葉を呑み込んだような女の声は、か細く震え、黙り込んでしまったようだ。これ幸いとばかりに、強い非難を放つのは宵だ。
「ほら!お家を名乗られないのは、訳があられるのでしょう!? そのような成りで、こんな時刻に押し掛けるとは、余程のこととお見受けします。そのような人を若様に会わせる訳にはいきません!お引き取りを!」
無論、宵は 目の前の尋常ではない女が、何処の誰か察しているだろう。明らかに可笑しい状況において、子爵家が巻き込まれることを回避するには関わらないのが得策だ。
鬼のような剣幕の宵に、産まれて此の方、非難などされた経験がないであろう令嬢は、居たたまれないはずだ、目通り叶わず引き返すことになるだろう。
多津子は、ふぅ……と息を漏らすと「騒がしいこと……」と、踵を返した。宵の声は、徐々に小さく遠ざかり――消えた。
―――――
離れは、静かなものだ。
主である光留が、母屋で食事などを済ませる為、詰める使用人はおらず、宵と2人で住んでいるようなものだった。
このような事情で今、忍び寄る人影が誰なのか?正体に疑問を抱くこともない光留は、寝転がったまま、振り向きもしない。
「何です?宵さん。泥棒みたいに足音を忍ばせて、僕を驚かそうとしても そうはいきませんからね」
「別の意味で驚くことになっていますよ」
宵とは 似ても似つかない、おっとりとした声音に、光留は飛び起きた。
「おたあ様!! 」
「猫のアキさんをお返しに……そして、人間のアキさんがお見えのようよ?」
「……まさか、どこのアキさんです?」
「あらあら、宵と同じ事を言うのね」
怪訝な顔で見上げてくる息子に、クスリ……と笑い、続けた。
「何でも、晃子と名乗る女が、お勝手口で貴方に逢わせて欲しいと言っているようですが、宵が鬼の剣幕で追い返そうとしていました」
「どういうことです!? 今も!? 」
「さぁ……」
「御前、失礼!! 」
光留は、転がるように多津子の目の前を横切り、渡り廊下を駆けた。意味がわからないが、離れへ寄り付かない――、否、光留に寄り付かない母が、わざわざ知らせたということはアキさんは、晃子で間違いないだろう。
明日は、上野駅
大きな賭けの前に 何が起きたのか、数人の女中を突飛ばし、光留は お勝手口に飛び出した。
御一新前の下屋敷を、現在の本宅とすることが多い大名華族だが、田中子爵家も御多分に洩れず。
本駒込は元大名、官の役人の屋敷が立ち並ぶ地域となっていた。
田中家においては、昨年、跡取りである光留が不在のうちに大きな改築を施していた。
それは、成人した光留の住まいを両親と別にするものであり、子爵家において跡取りの結婚を念頭においたものだというのは、誰もが知ることだった。
母屋と庭を挟み、並ぶ形で建てられた離れ様式だが、二間程度の こぢんまりとしたものではなく、母屋同等の物を揃えた立派な離れとなっていた。
しかし、未だ夫人不在の光留なのだから、食事や風呂などは、母屋で済ませる為、自室と使用人部屋以外は、使わない。
子爵家の下女は、放置するとクモの巣が張りかねない部屋を毎日掃除するのに、半日費やす有り様だった。
そんなことだから、乳母の宵は「早く、早く」と花嫁御寮の御出を願う。
しかし、当の光留は まっしぐらに1人の女を追いかけ回すものだから、最近 宵の口癖は「諦めが肝心」という、悟りにも似たものになっていた。
家のことを取り仕切る宵は、光留の跡継ぎを待ち望む代表格であり、生母である子爵夫人よりも熱心に縁組のことを考えていた。夫人に至っては、元々物静かな人であり、口を挟むこともない。
久我侯爵家の令嬢である夫人は、津多子という。鹿鳴館で光留が連れていた宮津子の叔母にあたり、姿形は光留よりも宮津子に似ている。
栗毛の髪を上品に巻き上げ、粋な縦縞をよく着こなす。座っているだけで お姫様といった風情だ。
そんな津多子に、夫人付きの女中である奈緒が声をかけた。
「奥方様、先程、お勝手口で宵さんが騒いでおられたのですが、不思議なことでお相手が外の者のようでした」
「……外の者? 誰です?」
「日暮れに御用聞きでもありませんし、成り行きを見てくるようにと、人をやりましたが……」
「そう……、貴女は若いのに気が利くわね。あら、アキさん、おいでなさい」
奈緒の後をついてきたのだろう、1匹の三毛猫がニャーと、甘えた声で膝にすり寄る。以前、光留が黒田から譲り受けた猫のアキだ。
大切に飼われているらしく、ビロードの紐に小さな鈴を通されたものを首に掛けられ、声と同じく可愛らしく鳴らす。
「奈緒が、よく面倒をみるから随分、懐いているわね……そうだわ、私も何か探してこようかしら」
「奥方様、私が」
「いいのよ、お勝手に行く口実ができたわ」
津多子は、アキを抱き上げると敷居を跨いだ。長い廊下を二折れ、三折れ、滑るように進むと、明らかに普段とは異なることがわかった。突き当たりには 2人の女中が、お勝手を覗き、ヒソヒソと声を潜めているのが見てとれた。耳に入るのは宵の声だ。
覗く手間が省けたと、壁に寄りかかり耳を澄ます。そんな子爵夫人に気付いた女中が、慌てて頭を下げるが津多子は、人差し指を唇に寄せ無言で、知らぬ顔を強要してみせた。
その時「お引き取りください!」と、強く放たれたのは、宵の一際大きな声であり、それだけで招かざる客のようだと、津多子は察した。続く言葉は、宵ではなかった。
「光留様にお取りつぎ下さい」と、切羽詰まる女の声は、必死に追いすがるといった具合に甲高く響く。
「あら……また、あの子ったら」
多津子は、ねぇ?と 猫のアキに小首を傾げてみせる。光留に会わせろと、屋敷にやってくる女は初めてではない。
最近では3月程前にも、何処ぞの半玉がやって来た。面倒をみるなど、軽口を叩いたのかと思ったが、そのような事実はなく、ただ座敷で話し込んだだけだという。
宵が 宥めすかし、置屋の女将に引き渡したのは言うまでもない。
あの時は、迂闊に名乗ってしまったと後悔していたようだったが、今回もその類いだろうと多津子は、お勝手に背を向けた――
「晃子が参ったと一言お伝え下さい!」
「どちらの晃子さんでしょうか!? 草履も履かずにやって来るような方を、当家の若様に会わせる訳には参りません!」
捲し立てる宵の言葉に、多津子の肩がピクリと上がった。「アキ……アキコさん?」と、腕に抱く猫に視線を落とす。
「……ッ!! それは……」
グッと言葉を呑み込んだような女の声は、か細く震え、黙り込んでしまったようだ。これ幸いとばかりに、強い非難を放つのは宵だ。
「ほら!お家を名乗られないのは、訳があられるのでしょう!? そのような成りで、こんな時刻に押し掛けるとは、余程のこととお見受けします。そのような人を若様に会わせる訳にはいきません!お引き取りを!」
無論、宵は 目の前の尋常ではない女が、何処の誰か察しているだろう。明らかに可笑しい状況において、子爵家が巻き込まれることを回避するには関わらないのが得策だ。
鬼のような剣幕の宵に、産まれて此の方、非難などされた経験がないであろう令嬢は、居たたまれないはずだ、目通り叶わず引き返すことになるだろう。
多津子は、ふぅ……と息を漏らすと「騒がしいこと……」と、踵を返した。宵の声は、徐々に小さく遠ざかり――消えた。
―――――
離れは、静かなものだ。
主である光留が、母屋で食事などを済ませる為、詰める使用人はおらず、宵と2人で住んでいるようなものだった。
このような事情で今、忍び寄る人影が誰なのか?正体に疑問を抱くこともない光留は、寝転がったまま、振り向きもしない。
「何です?宵さん。泥棒みたいに足音を忍ばせて、僕を驚かそうとしても そうはいきませんからね」
「別の意味で驚くことになっていますよ」
宵とは 似ても似つかない、おっとりとした声音に、光留は飛び起きた。
「おたあ様!! 」
「猫のアキさんをお返しに……そして、人間のアキさんがお見えのようよ?」
「……まさか、どこのアキさんです?」
「あらあら、宵と同じ事を言うのね」
怪訝な顔で見上げてくる息子に、クスリ……と笑い、続けた。
「何でも、晃子と名乗る女が、お勝手口で貴方に逢わせて欲しいと言っているようですが、宵が鬼の剣幕で追い返そうとしていました」
「どういうことです!? 今も!? 」
「さぁ……」
「御前、失礼!! 」
光留は、転がるように多津子の目の前を横切り、渡り廊下を駆けた。意味がわからないが、離れへ寄り付かない――、否、光留に寄り付かない母が、わざわざ知らせたということはアキさんは、晃子で間違いないだろう。
明日は、上野駅
大きな賭けの前に 何が起きたのか、数人の女中を突飛ばし、光留は お勝手口に飛び出した。
0
あなたにおすすめの小説

エリート警察官の溺愛は甘く切ない
日下奈緒
恋愛
親が警察官の紗良は、30歳にもなって独身なんてと親に責められる。
両親の勧めで、警察官とお見合いする事になったのだが、それは跡継ぎを産んで欲しいという、政略結婚で⁉

不器用な大富豪社長は、闇オクで買った花嫁を寵愛する
獅月@体調不良
恋愛
「 御前を幸せにする為に、俺は買ったんだ 」
〜 闇オク花嫁 〜
毒親である母親の為だけに生きてきた彼女は、
借金を得た母の言葉を聞き、
闇オークションへ売られる事になった。
どんな形にしろ借金は返済出来るし、
母の今後の生活面も確保出来る。
そう、彼女自身が生きていなくとも…。
生きる希望を無くし、
闇オークションに出品された彼女は
100億で落札された。
人食を好む大富豪か、
それとも肉体を求めてか…。
どちらにしろ、借金返済に、
安堵した彼女だが…。
いざ、落札した大富豪に引き渡されると、
その容姿端麗の美しい男は、
タワマンの最上階から5階部分、全てが自宅であり、
毎日30万のお小遣いですら渡し、
一流シェフによる三食デザート付きの食事、
なにより、彼のいない時間は好きにしていいという自由時間を言い渡した。
何一つ手を出して来ない男に疑問と不満を抱く日々……だが……?
表紙 ニジジャーニーから作成
エブリスタ同時公開

魔法師団長の家政婦辞めたら溺愛されました
iru
恋愛
小説家になろうですでに完結済みの作品です。よければお気に入りブックマークなどお願いします。
両親と旅をしている途中、魔物に襲われているところを、魔法師団に助けられたティナ。
両親は亡くなってしまったが、両親が命をかけて守ってくれた自分の命を無駄にせず強く生きていこうと決めた。
しかし、肉親も家もないティナが途方に暮れていると、魔物から助けてくれ、怪我の入院まで面倒を見てくれた魔法師団の団長レオニスから彼の家政婦として住み込みで働かないと誘われた。
魔物から助けられた時から、ひどく憧れていたレオニスの誘いを、ティナはありがたく受ける事にした。
自分はただの家政婦だと強く言い聞かせて、日に日に膨らむ恋心を抑え込むティナだった。
一方、レオニスもティナにどんどん惹かれていっていた。
初めはなくなった妹のようで放っては置けないと家政婦として雇ったが、その健気な様子に強く惹かれていった。
恋人になりたいが、年上で雇い主。
もしティナも同じ気持ちでないなら仕事まで奪ってしまうのではないか。
そんな思いで一歩踏み出せないレオニスだった。
そんな中ある噂から、ティナはレオニスの家政婦を辞めて家を出る決意をする。
レオニスは思いを伝えてティナを引き止めることができるのか?
両片思いのすれ違いのお話です。
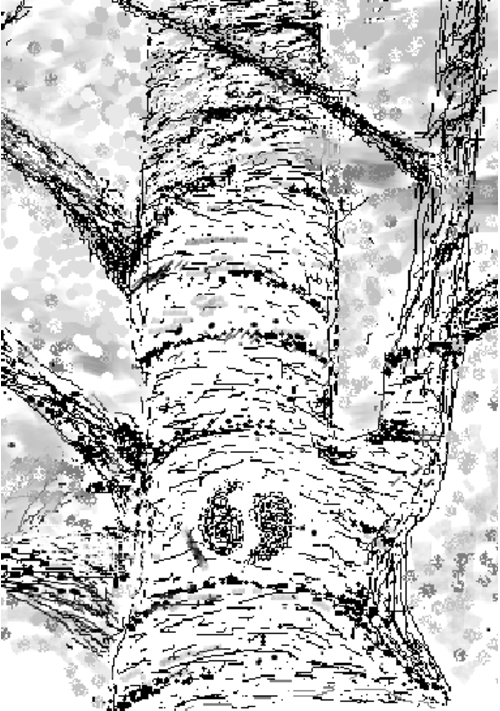
Pomegranate I
Uta Katagi
恋愛
婚約者の彼が突然この世を去った。絶望のどん底にいた詩に届いた彼からの謎のメッセージ。クラウド上に残されたファイルのパスワードと貸金庫の暗証番号のミステリーを解いた後に、詩が手に入れたものは?世代を超えて永遠の愛を誓った彼が遺したこの世界の驚愕の真理とは?詩は本当に彼と再会できるのか?
古代から伝承されたこの世界の秘密が遂に解き明かされる。最新の量子力学という現代科学の視点で古代ミステリーを暴いた長編ラブロマンス。これはもはや、ファンタジーの域を越えた究極の愛の物語。恋愛に憧れ愛の本質に悩み戸惑う人々に真実の愛とは何かを伝える作者渾身の超大作。
*本作品は「小説家になろう」にも掲載しています。

訳あり冷徹社長はただの優男でした
あさの紅茶
恋愛
独身喪女の私に、突然お姉ちゃんが子供(2歳)を押し付けてきた
いや、待て
育児放棄にも程があるでしょう
音信不通の姉
泣き出す子供
父親は誰だよ
怒り心頭の中、なしくずし的に子育てをすることになった私、橋本美咲(23歳)
これはもう、人生詰んだと思った
**********
この作品は他のサイトにも掲載しています

本日は桜・恋日和 ーツアーコンダクター 紫都の慕情の旅
光月海愛(こうつきみあ)
恋愛
旅は好きですか?
派遣添乗員(ツアーコンダクター)の桑崎紫都32歳。
もう、仕事がらみの恋愛はしないと思っていたのに…ーー
切ない過去を持つ男女四人の二泊三日の恋慕情。

【完結・おまけ追加】期間限定の妻は夫にとろっとろに蕩けさせられて大変困惑しております
紬あおい
恋愛
病弱な妹リリスの代わりに嫁いだミルゼは、夫のラディアスと期間限定の夫婦となる。
二年後にはリリスと交代しなければならない。
そんなミルゼを閨で蕩かすラディアス。
普段も優しい良き夫に困惑を隠せないミルゼだった…

王太子妃専属侍女の結婚事情
蒼あかり
恋愛
伯爵家の令嬢シンシアは、ラドフォード王国 王太子妃の専属侍女だ。
未だ婚約者のいない彼女のために、王太子と王太子妃の命で見合いをすることに。
相手は王太子の側近セドリック。
ところが、幼い見た目とは裏腹に令嬢らしからぬはっきりとした物言いのキツイ性格のシンシアは、それが元でお見合いをこじらせてしまうことに。
そんな二人の行く末は......。
☆恋愛色は薄めです。
☆完結、予約投稿済み。
新年一作目は頑張ってハッピーエンドにしてみました。
ふたりの喧嘩のような言い合いを楽しんでいただければと思います。
そこまで激しくはないですが、そういうのが苦手な方はご遠慮ください。
よろしくお願いいたします。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















