89 / 96
宴
しおりを挟む
朝帰りをするのも久方ぶりだと、前を走る近衛の俥を、欠伸を噛みしめながら眺めた。
昨晩は、仮装でもしているのか女物に、身を飾りたてた男が出て来て、驚いたが話してみると気風が良く、直ぐに打ち解けた。
玉三郎ねぇさんと呼ばれる男は、旅芸人だったが体調を崩し、この地に根を張ったと云う経歴の持ち主らしい。が、酒の席でのお涙頂戴は、アテにならない。
ただ、分かったのは清浦が、迷っていた祝いの品に、芋の茎を勧めたという変わり者だということと、夜は店、朝は下駄屋で小銭を稼ぐ生活を送っているということだ。
文字通り朝から晩まで働き詰めのワケは、この店にあるという。明らかに、客入りが悪い。
「お客、いないのですか?」
近衛が、ズバッと斬り込んだ。気を悪くしないか、とも思ったが玉三郎は、よくぞ聞いてくれたと語りだす。
太客がいない店に、売れっ子芸者を派遣する置屋もなく、来たとしても、おひねりも渡せない。
最近では、芸者も下の下、引退した婆さんのような者を派遣されると、一通り嘆いて見せると、忌々しげに唇を尖らせ
「柳橋だし、客の入りも良い。儲けないわけがない!とか、言っちゃって参っちまうよ!嘘さ、大嘘!あんちきしょー!」
つまり、騙されて買ってしまい、朝も働かないと、やってられないと云うことだ。
「成る程ねぇ。でも、芸者なんて飽きてる連中だ。ねぇさんの芸を見せてくれないかい?」
何気ない一言だったが、これが意外と良かった。客がいないのなら、皆も混ざればいいと下働きまで座敷に招き入れ、酒がなくなると、適当に誰かが取りに行くという、あり得ない状態だったが「昔は、人の家にお邪魔して勝手に台所を漁ったものさ」と、笑う清浦は懐かしそうに眼を細めた。
そんな上役をどう見たのか、近衛はパッと明るい表情を作ると、何処から持ち出してきたのか、朱色の盃を差し出した。
「さあ、清浦さん!光留さんのお祝いです。無礼講といきましょう!」
この提案に、異を唱える者などいない。わっ!と、歓声があがると、上も下もなく盃の回し合いになった。
店の者も含めて、太鼓を鳴らし、歌を唄う。
陽気な清浦と玉三郎ねぇさんが、手を取り合って鹿鳴館の紳士淑女と、円舞の真似事をするのに、近衛が「お上手です!」などと、声をかけ、四つん這いで光留の元へ寄ってくる姿は、とても近衛家の者とは思えない、かなり酔っているのだろう。
「清浦さん、大層 喜んでらっしゃいましたよ。貴方のご婚約。最近、お疲れがみえましたが、吹き飛んだようで」
次官としての職務と、山縣の密命をこなすのに難儀しているのだろう。
弱音を吐かないのは清浦らしいと思うが、頬が熱を持ち、頭がぼんやりとすることから、気の利いた励ましの言葉を伝えることは出来ず、ただ 乾いた笑いを漏らすのが精一杯だった。
なので、婚約祝いの座敷が、どんな風に閉められたのか分からない。
その前に寝てしまったからだ。うっすらと瞼を上げると、暗くて周りが窺えない。
背越しに人肌の温もりがし、白粉の香りが鼻をくすぐったことに一瞬、晃子に顔向けが出来ない事態かと、冷っとしたが薄暗い中、こんもりと山を築く影は、ひとつ、ふたつではない。
昨晩、騒いでいた者達がゴロゴロと雑魚寝をしているのだろう。
と、なると背中にピタリと張り付いているのは、真冬の寒さに震える女中が潜り込んできたと思われた。
―― ああ、駄目だ。眠気が襲ってきた。
皆は、まだ寝静まっている。もう一眠りと光留は瞼を綴じた。
◆◆◆◆◆
ガタリと、木戸が鳴る音がし奈緒は、顔を上げた。まだ、使用人達も寝静まる刻限だ。火急の用向きで、他家の使用人でも来たのか?と、手に持つ薪を かまどに投げ入れると立ち上がる。
「誰?」
警戒心を露にし、かけた言葉に返ってきたのは「誰、じゃありませんよ。僕です」という、聞きなれた声――。
「お帰りなさいませ」
「寒い、湯はあります?」
「いえ、今、火を起こしているところです」
「ああ、かまど番ですか」
光留は、台所に上がり込むと六畳ほどの部屋へ入り込んだ。使用人が当番で詰める一間だ。夜間訪れる者の対応を兼ね、かまどに火を起こす者が 前日の夜から寝泊まりする。
津多子の女中でも、この番は回ってくることで、奈緒が火を起こしているようだ。
「何だ、もう布団を上げているんですか」
「かまど番の時間ですので」
「一眠りさせて貰おうと思ったのに」
「お部屋へ」
「部屋で寝たら、朝食に間に合わない」
光留は、吐き捨てると寝転がった。
今日は、日曜で官庁は休みだ。起床が遅れれば、離れで食事をすれば良いのだが、どうしても同席しないといけないと考えているのだろう。奈緒は、自身が羽織る綿入れを光留に掛けた。
「ご報告ですか?」
「ええ、それより座布団とかないですか?枕代わり」
「下働きが座布団なんて……」
「ああ、朝から小言なんて真っ平です。膝」
「え?」
「膝を貸しなさいって。ホラ、頭を持ち上げているのは、結構ツライから早く」
言っていることは本気なのだろう。ブルブルと震えるブロンドの下に、崩した膝を滑り込ませた。
「電話で報告はしていますが、自分の口から伝えるべきことですからね。僕の婚約が決まったのですから。大変、気を揉ませたでしょうし」
「全くです。しかし、白粉の匂いが ぷんぷんするのは如何なことか」
「とんだ鉄砲女郎で、しがみついてきて難儀しました。玉三郎という名でしたが、聞きたいですか?」
「聞きません。晃子様がお知りになったら、どう思われるか」
瞼を綴じる光留には、その言葉が苛立ちを含んでいるように聞こえた。
「きっと笑ってくれますよ。それより、奈緒が側室候補だと耳に入ったのが、僕としてはキツイ。誰が、若奥様の耳に入れたのか……知っています?」
「……こんなことをなさるから、誤解をされるんですよ!」
奈緒は、膝を思いっきりずらした。
畳に打ち付けられた頭は、ゴッと鈍い音をたて「痛ッ!! 」と言う、小さな悲鳴が かまどから爆ぜる杉の葉と共に、辺りに響いた。
昨晩は、仮装でもしているのか女物に、身を飾りたてた男が出て来て、驚いたが話してみると気風が良く、直ぐに打ち解けた。
玉三郎ねぇさんと呼ばれる男は、旅芸人だったが体調を崩し、この地に根を張ったと云う経歴の持ち主らしい。が、酒の席でのお涙頂戴は、アテにならない。
ただ、分かったのは清浦が、迷っていた祝いの品に、芋の茎を勧めたという変わり者だということと、夜は店、朝は下駄屋で小銭を稼ぐ生活を送っているということだ。
文字通り朝から晩まで働き詰めのワケは、この店にあるという。明らかに、客入りが悪い。
「お客、いないのですか?」
近衛が、ズバッと斬り込んだ。気を悪くしないか、とも思ったが玉三郎は、よくぞ聞いてくれたと語りだす。
太客がいない店に、売れっ子芸者を派遣する置屋もなく、来たとしても、おひねりも渡せない。
最近では、芸者も下の下、引退した婆さんのような者を派遣されると、一通り嘆いて見せると、忌々しげに唇を尖らせ
「柳橋だし、客の入りも良い。儲けないわけがない!とか、言っちゃって参っちまうよ!嘘さ、大嘘!あんちきしょー!」
つまり、騙されて買ってしまい、朝も働かないと、やってられないと云うことだ。
「成る程ねぇ。でも、芸者なんて飽きてる連中だ。ねぇさんの芸を見せてくれないかい?」
何気ない一言だったが、これが意外と良かった。客がいないのなら、皆も混ざればいいと下働きまで座敷に招き入れ、酒がなくなると、適当に誰かが取りに行くという、あり得ない状態だったが「昔は、人の家にお邪魔して勝手に台所を漁ったものさ」と、笑う清浦は懐かしそうに眼を細めた。
そんな上役をどう見たのか、近衛はパッと明るい表情を作ると、何処から持ち出してきたのか、朱色の盃を差し出した。
「さあ、清浦さん!光留さんのお祝いです。無礼講といきましょう!」
この提案に、異を唱える者などいない。わっ!と、歓声があがると、上も下もなく盃の回し合いになった。
店の者も含めて、太鼓を鳴らし、歌を唄う。
陽気な清浦と玉三郎ねぇさんが、手を取り合って鹿鳴館の紳士淑女と、円舞の真似事をするのに、近衛が「お上手です!」などと、声をかけ、四つん這いで光留の元へ寄ってくる姿は、とても近衛家の者とは思えない、かなり酔っているのだろう。
「清浦さん、大層 喜んでらっしゃいましたよ。貴方のご婚約。最近、お疲れがみえましたが、吹き飛んだようで」
次官としての職務と、山縣の密命をこなすのに難儀しているのだろう。
弱音を吐かないのは清浦らしいと思うが、頬が熱を持ち、頭がぼんやりとすることから、気の利いた励ましの言葉を伝えることは出来ず、ただ 乾いた笑いを漏らすのが精一杯だった。
なので、婚約祝いの座敷が、どんな風に閉められたのか分からない。
その前に寝てしまったからだ。うっすらと瞼を上げると、暗くて周りが窺えない。
背越しに人肌の温もりがし、白粉の香りが鼻をくすぐったことに一瞬、晃子に顔向けが出来ない事態かと、冷っとしたが薄暗い中、こんもりと山を築く影は、ひとつ、ふたつではない。
昨晩、騒いでいた者達がゴロゴロと雑魚寝をしているのだろう。
と、なると背中にピタリと張り付いているのは、真冬の寒さに震える女中が潜り込んできたと思われた。
―― ああ、駄目だ。眠気が襲ってきた。
皆は、まだ寝静まっている。もう一眠りと光留は瞼を綴じた。
◆◆◆◆◆
ガタリと、木戸が鳴る音がし奈緒は、顔を上げた。まだ、使用人達も寝静まる刻限だ。火急の用向きで、他家の使用人でも来たのか?と、手に持つ薪を かまどに投げ入れると立ち上がる。
「誰?」
警戒心を露にし、かけた言葉に返ってきたのは「誰、じゃありませんよ。僕です」という、聞きなれた声――。
「お帰りなさいませ」
「寒い、湯はあります?」
「いえ、今、火を起こしているところです」
「ああ、かまど番ですか」
光留は、台所に上がり込むと六畳ほどの部屋へ入り込んだ。使用人が当番で詰める一間だ。夜間訪れる者の対応を兼ね、かまどに火を起こす者が 前日の夜から寝泊まりする。
津多子の女中でも、この番は回ってくることで、奈緒が火を起こしているようだ。
「何だ、もう布団を上げているんですか」
「かまど番の時間ですので」
「一眠りさせて貰おうと思ったのに」
「お部屋へ」
「部屋で寝たら、朝食に間に合わない」
光留は、吐き捨てると寝転がった。
今日は、日曜で官庁は休みだ。起床が遅れれば、離れで食事をすれば良いのだが、どうしても同席しないといけないと考えているのだろう。奈緒は、自身が羽織る綿入れを光留に掛けた。
「ご報告ですか?」
「ええ、それより座布団とかないですか?枕代わり」
「下働きが座布団なんて……」
「ああ、朝から小言なんて真っ平です。膝」
「え?」
「膝を貸しなさいって。ホラ、頭を持ち上げているのは、結構ツライから早く」
言っていることは本気なのだろう。ブルブルと震えるブロンドの下に、崩した膝を滑り込ませた。
「電話で報告はしていますが、自分の口から伝えるべきことですからね。僕の婚約が決まったのですから。大変、気を揉ませたでしょうし」
「全くです。しかし、白粉の匂いが ぷんぷんするのは如何なことか」
「とんだ鉄砲女郎で、しがみついてきて難儀しました。玉三郎という名でしたが、聞きたいですか?」
「聞きません。晃子様がお知りになったら、どう思われるか」
瞼を綴じる光留には、その言葉が苛立ちを含んでいるように聞こえた。
「きっと笑ってくれますよ。それより、奈緒が側室候補だと耳に入ったのが、僕としてはキツイ。誰が、若奥様の耳に入れたのか……知っています?」
「……こんなことをなさるから、誤解をされるんですよ!」
奈緒は、膝を思いっきりずらした。
畳に打ち付けられた頭は、ゴッと鈍い音をたて「痛ッ!! 」と言う、小さな悲鳴が かまどから爆ぜる杉の葉と共に、辺りに響いた。
0
あなたにおすすめの小説

エリート警察官の溺愛は甘く切ない
日下奈緒
恋愛
親が警察官の紗良は、30歳にもなって独身なんてと親に責められる。
両親の勧めで、警察官とお見合いする事になったのだが、それは跡継ぎを産んで欲しいという、政略結婚で⁉

不器用な大富豪社長は、闇オクで買った花嫁を寵愛する
獅月@体調不良
恋愛
「 御前を幸せにする為に、俺は買ったんだ 」
〜 闇オク花嫁 〜
毒親である母親の為だけに生きてきた彼女は、
借金を得た母の言葉を聞き、
闇オークションへ売られる事になった。
どんな形にしろ借金は返済出来るし、
母の今後の生活面も確保出来る。
そう、彼女自身が生きていなくとも…。
生きる希望を無くし、
闇オークションに出品された彼女は
100億で落札された。
人食を好む大富豪か、
それとも肉体を求めてか…。
どちらにしろ、借金返済に、
安堵した彼女だが…。
いざ、落札した大富豪に引き渡されると、
その容姿端麗の美しい男は、
タワマンの最上階から5階部分、全てが自宅であり、
毎日30万のお小遣いですら渡し、
一流シェフによる三食デザート付きの食事、
なにより、彼のいない時間は好きにしていいという自由時間を言い渡した。
何一つ手を出して来ない男に疑問と不満を抱く日々……だが……?
表紙 ニジジャーニーから作成
エブリスタ同時公開

魔法師団長の家政婦辞めたら溺愛されました
iru
恋愛
小説家になろうですでに完結済みの作品です。よければお気に入りブックマークなどお願いします。
両親と旅をしている途中、魔物に襲われているところを、魔法師団に助けられたティナ。
両親は亡くなってしまったが、両親が命をかけて守ってくれた自分の命を無駄にせず強く生きていこうと決めた。
しかし、肉親も家もないティナが途方に暮れていると、魔物から助けてくれ、怪我の入院まで面倒を見てくれた魔法師団の団長レオニスから彼の家政婦として住み込みで働かないと誘われた。
魔物から助けられた時から、ひどく憧れていたレオニスの誘いを、ティナはありがたく受ける事にした。
自分はただの家政婦だと強く言い聞かせて、日に日に膨らむ恋心を抑え込むティナだった。
一方、レオニスもティナにどんどん惹かれていっていた。
初めはなくなった妹のようで放っては置けないと家政婦として雇ったが、その健気な様子に強く惹かれていった。
恋人になりたいが、年上で雇い主。
もしティナも同じ気持ちでないなら仕事まで奪ってしまうのではないか。
そんな思いで一歩踏み出せないレオニスだった。
そんな中ある噂から、ティナはレオニスの家政婦を辞めて家を出る決意をする。
レオニスは思いを伝えてティナを引き止めることができるのか?
両片思いのすれ違いのお話です。
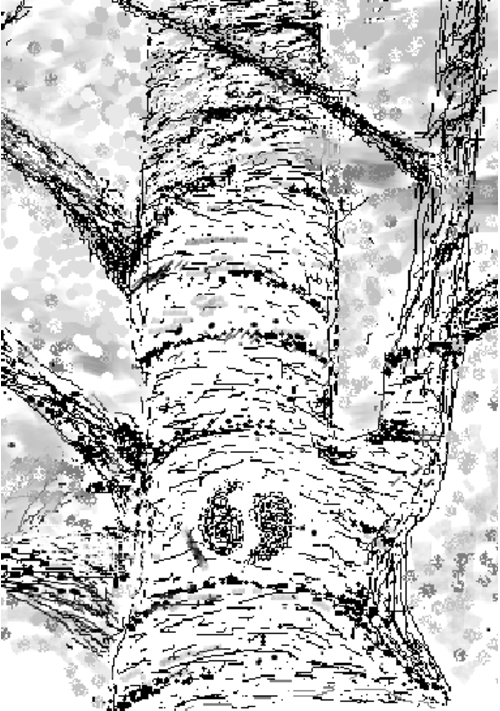
Pomegranate I
Uta Katagi
恋愛
婚約者の彼が突然この世を去った。絶望のどん底にいた詩に届いた彼からの謎のメッセージ。クラウド上に残されたファイルのパスワードと貸金庫の暗証番号のミステリーを解いた後に、詩が手に入れたものは?世代を超えて永遠の愛を誓った彼が遺したこの世界の驚愕の真理とは?詩は本当に彼と再会できるのか?
古代から伝承されたこの世界の秘密が遂に解き明かされる。最新の量子力学という現代科学の視点で古代ミステリーを暴いた長編ラブロマンス。これはもはや、ファンタジーの域を越えた究極の愛の物語。恋愛に憧れ愛の本質に悩み戸惑う人々に真実の愛とは何かを伝える作者渾身の超大作。
*本作品は「小説家になろう」にも掲載しています。

訳あり冷徹社長はただの優男でした
あさの紅茶
恋愛
独身喪女の私に、突然お姉ちゃんが子供(2歳)を押し付けてきた
いや、待て
育児放棄にも程があるでしょう
音信不通の姉
泣き出す子供
父親は誰だよ
怒り心頭の中、なしくずし的に子育てをすることになった私、橋本美咲(23歳)
これはもう、人生詰んだと思った
**********
この作品は他のサイトにも掲載しています

本日は桜・恋日和 ーツアーコンダクター 紫都の慕情の旅
光月海愛(こうつきみあ)
恋愛
旅は好きですか?
派遣添乗員(ツアーコンダクター)の桑崎紫都32歳。
もう、仕事がらみの恋愛はしないと思っていたのに…ーー
切ない過去を持つ男女四人の二泊三日の恋慕情。

【完結・おまけ追加】期間限定の妻は夫にとろっとろに蕩けさせられて大変困惑しております
紬あおい
恋愛
病弱な妹リリスの代わりに嫁いだミルゼは、夫のラディアスと期間限定の夫婦となる。
二年後にはリリスと交代しなければならない。
そんなミルゼを閨で蕩かすラディアス。
普段も優しい良き夫に困惑を隠せないミルゼだった…

王太子妃専属侍女の結婚事情
蒼あかり
恋愛
伯爵家の令嬢シンシアは、ラドフォード王国 王太子妃の専属侍女だ。
未だ婚約者のいない彼女のために、王太子と王太子妃の命で見合いをすることに。
相手は王太子の側近セドリック。
ところが、幼い見た目とは裏腹に令嬢らしからぬはっきりとした物言いのキツイ性格のシンシアは、それが元でお見合いをこじらせてしまうことに。
そんな二人の行く末は......。
☆恋愛色は薄めです。
☆完結、予約投稿済み。
新年一作目は頑張ってハッピーエンドにしてみました。
ふたりの喧嘩のような言い合いを楽しんでいただければと思います。
そこまで激しくはないですが、そういうのが苦手な方はご遠慮ください。
よろしくお願いいたします。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















