あなたにおすすめの小説
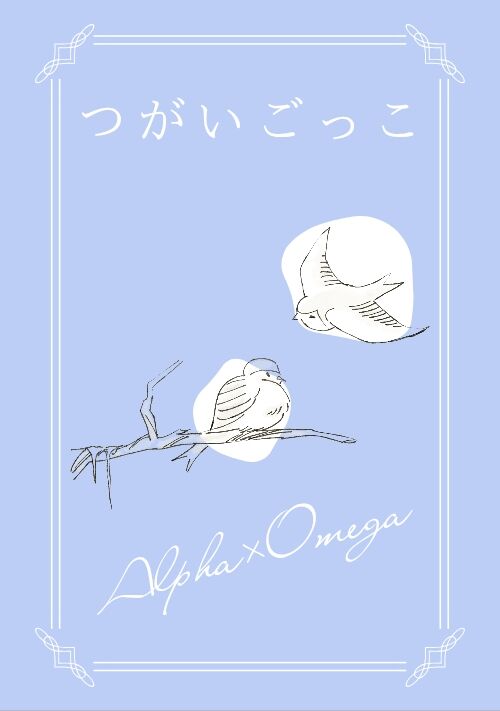
つがいごっこ~4歳のときに番ったらしいアルファと30歳で再会しまして~
深山恐竜
BL
俺は4歳のときにうなじを噛まれて番を得た。
子どもがたくさんいる遊び場で、気が付いたらそうなっていたとか。
相手は誰かわからない。
うなじに残る小さな歯型と、顔も知らない番。
しかし、そのおかげで、番がいないオメガに制限をかけられる社会で俺は自由に生きていた。
そんなある日、俺は番と再会する。
彼には俺の首筋を噛んだという記憶がなかった。
そのせいで、自由を謳歌していた俺とは反対に、彼は苦しんできたらしい。
彼はオメガのフェロモンも感じられず、しかし親にオメガと番うように強制されたことで、すっかりオメガを怖がるようになっていた。
「でも、あなただけは平気なんです。なんででしょう」
首を傾げる彼に、俺は提案する。
「なぁ、俺と番ごっこをしないか?」
偽物の番となった本物の番が繰り広げるラブストーリー。

番を拒み続けるΩと、執着を隠しきれないαが同じ学園で再会したら逃げ場がなくなった話 ――優等生αの過保護な束縛は恋か支配か
雪兎
BL
第二性が存在する世界。
Ωであることを隠し、平穏な学園生活を送ろうと決めていた転校生・湊。
しかし入学初日、彼の前に現れたのは――
幼い頃に「番になろう」と言ってきた幼馴染のα・蓮だった。
成績優秀、容姿端麗、生徒から絶大な信頼を集める完璧なα。
だが湊だけが知っている。
彼が異常なほど執着深いことを。
「大丈夫、全部管理してあげる」
「君が困らないようにしてるだけだよ」
座席、時間割、交友関係、体調管理。
いつの間にか整えられていく環境。
逃げ場のない距離。
番を拒みたいΩと、手放す気のないα。
これは保護か、それとも束縛か。
閉じた学園の中で、二人の関係は静かに歪み始める――。

伝説のS級おじさん、俺の「匂い」がないと発狂して国を滅ぼすらしいい
マンスーン
BL
ギルドの事務職員・三上薫は、ある日、ギルドロビーで発作を起こしかけていた英雄ガルド・ベルンシュタインから抱きしめられ、首筋を猛烈に吸引。「見つけた……俺の酸素……!」と叫び、離れなくなってしまう。
最強おじさん(変態)×ギルドの事務職員(平凡)
世界観が現代日本、異世界ごちゃ混ぜ設定になっております。


処刑エンドの悪役公爵、隠居したいのに溺愛されてます
ひなた翠
BL
目が覚めたら、やり込んだBLゲームの悪役公爵になっていた。
しかも手には鞭。目の前には涙を浮かべた美少年。
——このままじゃ、王太子に処刑される。
前世は冴えない社畜サラリーマン。今世は冷徹な美貌を持つ高位貴族のアルファ。
中身と外見の落差に戸惑う暇もなく、エリオットは処刑回避のための「隠居計画」を立てる。
囚われのオメガ・レオンを王太子カイルに引き渡し、爵位も領地も全部手放して、ひっそり消える——はずだった。
ところが動くほど状況は悪化していく。
レオンを自由にしようとすれば「傍にいたい」と縋りつかれ、
カイルに会えば「お前の匂いは甘い」と迫られ、
隠居を申し出れば「逃げるな」と退路を塞がれる。
しかもなぜか、子供の頃から飲んでいた「ビタミン剤」を忘れるたび、身体がおかしくなる。
周囲のアルファたちの視線が絡みつき、カイルの目の色が変わり——
自分でも知らなかった秘密が暴かれたとき、逃げ場はもう、どこにもなかった。
誰にも愛されなかった男が、異世界で「本当の自分」を知り、運命の番と出会う——
ギャップ萌え×じれったさ×匂いフェチ全開の、オメガバース転生BL。

鎖に繋がれた騎士は、敵国で皇帝の愛に囚われる
結衣可
BL
戦場で捕らえられた若き騎士エリアスは、牢に繋がれながらも誇りを折らず、帝国の皇帝オルフェンの瞳を惹きつける。
冷酷と畏怖で人を遠ざけてきた皇帝は、彼を望み、夜ごと逢瀬を重ねていく。
憎しみと抗いのはずが、いつしか芽生える心の揺らぎ。
誇り高き騎士が囚われたのは、冷徹な皇帝の愛。
鎖に繋がれた誇りと、独占欲に満ちた溺愛の行方は――。

冤罪で堕とされた最強騎士、狂信的な男たちに包囲される
マンスーン
BL
王国最強の聖騎士団長から一転、冤罪で生存率0%の懲罰部隊へと叩き落とされたレオン。
泥にまみれてもなお気高く、圧倒的な強さを振るう彼に、狂った執着を抱く男たちが集結する。

だって、君は210日のポラリス
大庭和香
BL
モテ属性過多男 × モブ要素しかない俺
モテ属性過多の理央は、地味で凡庸な俺を平然と「恋人」と呼ぶ。大学の履修登録も丸かぶりで、いつも一緒。
一方、平凡な小市民の俺は、旅行先で両親が事故死したという連絡を受け、
突然人生の岐路に立たされた。
――立春から210日、夏休みの終わる頃。
それでも理央は、変わらず俺のそばにいてくれて――
📌別サイトで読み切りの形で投稿した作品を、連載形式に切り替えて投稿しています。
エピローグまで公開いたしました。14,000字程度になりました。読み切りの形のときより短くなりました……1000文字ぐらい書き足したのになぁ。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















