14 / 17
第三章:明日を落としても
第十四話:罪悪感
しおりを挟む
終業式
空調が効いているとは言え、体育館の中は生徒で溢れかえっていて、どうにも暑さは拭えない。しかも夏休みを前に生徒は皆、浮足立っている。校長の挨拶が始まった頃には、あちこちから退屈そうにスマホを弄る音が聞こえ始めていた。
半井ゼンジも欠伸を噛み殺しながら、空調のルーバーが動く様をぼんやりと眺めていた。
にわかに生徒のざわめきに不穏が入り混じり始める。教師の何名かが急ぎ足で、体育館を出入りしていた。
不穏は急速度で伝播して、あっという間に体育館を覆い尽くして行った。
「嘘でしょ」
「えっえっ……」
殆ど言葉にならない声が所々から聞こえる。学年主任が校長になにやら耳打ちをした所で、ゼンジは様子のおかしさに気づいた。見渡すとスマホを見ていた生徒のほぼ全員が、凍りついたように固まっている。校長の声が大きくなってマイクがキィーンという音を立てた。
「全校生徒は、速やかに担任の指示に従い教室へ戻るように。既に知っている者もいるかと思うが、慌てず、担任からの説明があるまで待機をして欲しい」
何が起きた?
トントンと肩を叩かれて振り返ると、最後尾にいたはずのアラタが顔面蒼白でスマホを差し出していた。
(東京都……市のマンションで、都内の高校に通う蓮波綾さん16歳が刃物で刺され死亡。「娘を殺した」と通報の母親、蓮波由紀恵容疑者42歳を殺人容疑で逮捕。)
……何だこれ。
酷く、喉が乾く。
「キャア!!」
ガタンッという音と共に、女生徒の悲鳴が聞こえる。白昼夢でも見ているような、スローモーションの世界。全ての感覚が遠くて、ビニールにでも包まれているような息苦しさを感じる。なんなんだ、この感覚は。ぼんやりと音のする方へ目をやると、佐伯遥が気を失って倒れていた。
教室に戻ってから、担任が来て事件の詳細を説明するまで、誰一人として口を開く者はいなかった。事件の詳細と言っても、ニュースと変わらない程度の概要しか分からない。警察関係者が校舎を出入りする様子が、教室の窓から聞こえてきていた。
蓮波綾が、母親に殺された。
「……詳しい事情などは、まだ不明なんだがな。蓮波と交流のあった生徒に、警察の方が話を聞きたいそうだ」
担任もまさかの出来事で余裕がないのだろう。ずっと、ゼンジの顔を見ながら話している。他の生徒たちは俯いたまま、この世の終わりのような顔をして押し黙っていた。
つい昨日まで面白半分に噂していた人物が、ある日突然、この世から居なくなる。
皆、言い訳探しに必死で担任の話などそっちのけの様子だった。
「半井」
名前を呼び終わらないうちに立ち上がったゼンジは、鞄を抱えると「先に職員室へ行ってます」それだけ言って、教室を後にした。
シン……と静まり返った廊下を、蝉の声だけがジーワジーワとしがみつくようにして鳴き喚いていた。
◆
職員室に顔を出すと、学年主任から生活指導室で待っていて欲しいと伝えられた。警察関係者は佐伯遥と一緒に話を聞きたいそうだ、と言われる。
佐伯って倒れていたけど……話出来るのか。
半井ゼンジは、相変わらず白昼夢を見ているような奇妙な感覚の中で、ぼんやりとズレた事を考えていた。
「おい大丈夫か、半井。気分悪いんじゃないのか。顔、真っ青だぞ」
という学年主任の声は、一つもゼンジの耳に届いていなかった。
生活指導室のドアが、酷く重たく感じる。
蓮波綾が殺されたのは、昨日の夜。という話だった。
あの時、蓮波を選んでいれば間に合った。
全身から血が抜けるような眩暈を覚えて、生まれてから一番重いドアを開く。中に入ると奥の席でぼーっと一点を見つめたまま、瞬きすらしようとしない遥の姿が目に入った。
喉の奥にどうしようもない罪悪感がへばりついて、言葉が出ない。何を言っても言い訳にしかならない。俺は、取り返しのつかない事をしてしまった。俺は、とんでもない過ちを犯した。
いつまでも入り口で突っ立ったまま動かないゼンジに気づいた遥が、力のない眼差しを向けた。血の気のない唇を微かに動かしながら、掠れた声で伝える。
「半井君のせいじゃない……」
「――……ごめん」
「……私一人でも、行けば良かった……」
「……行けないだろ。男の俺が一緒じゃなきゃ……あんなの、行ける訳が……」
遥の顔が悲しみで歪んで、その頬を涙が伝う。ゼンジも、心臓が押し潰されるような感覚に、自分がもう何を言っているのかさえ分からなくなっていた。遠くで聞こえる嗚咽が自分のものだと気づくのでさえやっとだ。
そのうち遥の様子がおかしくなってきた。口を開いてもヒューッと音を立てるばかりで、呼吸が上手に出来ていないようだった。苦しそうに顔を歪めている。
「……ちゃん……」
「ちょっと、先生呼んでくる」
「……綾ちゃん。最後まで……望月君の事、気にしてた」
「――……うん」
「……家族って言ってた……望月君の事――……私、平気なフリして、バカみたいに……嫉妬…嫉妬なんかしたから、あんな事に……」
ヒューッっという呼吸音が大きくなる。入った時から血の気のなかった遥の顔色が、青いを通り越してあっという間に白くなる。ゼンジは堪らず近づくと、その冷え切った手を握りしめた。
「大丈夫、大丈夫だから」
「ごめっごめんね!綾ちゃん……うぅ……綾ちゃあん」
警察関係者がやってくるまで、遥はゼンジの腕にすがりついて号泣していた。ゼンジも声を殺しながら静かに泣き続けていた。
結局、遥の事情聴取は後日という事になった。家族が迎えに来て、これから病院へ行くと言う。連絡先の交換をして、ゼンジだけが残って聴取を受けた。直近の、遥とのやり取りを中心に話す。
途中、何度も聞き返されるが、その度にゼンジは「え?」という表情をしていた。聞いていなかったり、同じ話を繰り返していたり、質問とはかけ離れた話を始めたり。同席していた担任が刑事と顔を見合わせ、彼も後日に……と相談し始めていた。
部屋に入ってきた時の遥と一緒だった。一点を見つめたまま瞬きすらしようとしないゼンジは、思い詰めた表情で何度目になるか分からない同じ台詞を繰り返していた。
「――……俺が佐伯さんの言う通り、一緒に蓮波の家に行っていれば、助けられたんです」
刑事が、やるせないといった表情で精一杯の言葉をかける。
「君のせいじゃないよ。昨日の夜、福祉関係者も電話をかけてたんだ。繋がらなかったそうだ。今日の午前中に、緊急で訪問する予定だったと言っていたよ」
制服のズボンに、止まる事なく涙が零れ落ちてゆく。
何を言っても、今は納得出来ないだろうな。
そう思いながら刑事は、申し訳無さそうな顔をして続けた。
「逮捕された母親がね。望月って生徒の名前を出してるんだよ……綾さんの日記が、見つかってね。その中にも出てくるんだ。君の名前と一緒に」
「――……望月の家には行ったんですか」
「ここへ来る前に、連絡はしたよ。家の人は出ていったから関係ないの、一点張りでね。退学届も、本人が書いて提出したものと確認されてるし……望月君の事は、その……君が詳しいとしか言わないんだよ」
「……でしょうね」
ゼンジは、視線を動かして再び瞬きを始めるとポツリポツリと話しだした。
綾にタオルを渡した、あの日からの出来事を。
◆
港区にある、とある総合病院の個室。
頭を包帯でぐるぐる巻きにされ、右目に眼帯をした望月リクがスースーと寝息を立てていた。出勤途中にオーナーから呼び出された瀬能ゴウは、猛烈に酷い二日酔いのような気分で、眠っているリクの姿を見つめていた。
最近のリクは笑うようになった、とスタッフから聞いた矢先の事件だった。
別に神様を信じてるワケじゃないけど、とゴウは思う。
あまりにも惨いんじゃないの。
蓮波綾が亡くなった事は、出勤途中の電車内で知った。
受け止めきれる訳ないじゃない。
大人にだって、無理なのに。
店長の話では、本当に一瞬の出来事だったらしい。悲鳴を上げて気を失ったリクに驚いて、救急車を呼ぼうと目を離した、ほんの数分の間にそれは起きた。
リクは何を思ったのか、デスクの引き出しにあったドライバーで、右目を突いてしまった。
救急車が来るまでうわ言のように、蓮波綾の名前を呼び続け、頭が痛いと訴えていたと言う。
集中治療室に入ったのが、10時前。幸い失明は免れたものの……予後に関する担当医師の見解は、厳しいものだった。精神病院の紹介状を書くのでなるべく早い入院を、と勧められる。
「素人で、どうにか出来るレベルではないと思います。もっと強い希死念慮がこれから出てくる可能性が高いですね」
「すみません、希死念慮ってなんですか?元々強い頭痛持ちだったと、本人は言っていたようなんですが」
「瀬能さん。望月さんの脳に異常は見当たりませんでした。精神的なものと見ています。自殺未遂ですよ、彼がしたのは。専門家によるケアが必要です」
医師との面談を終えたゴウは、休憩室でオーナーに連絡を取った。そういう子は今までにもいた。入院が必要なら、させたら良いじゃないか。と、えらくアッサリした返事が返ってきた。
ゴウは、保険証ってどうなってんだろ……と思った。しかし、その手の事を聞いてしまうと不機嫌になる人でもある。「ありがとうございます」感謝の意を述べるに留めて電話を切った。
時計を見ると14時を回っていた。自販機でお茶を買ったゴウは、飯山ハルキが到着するのを病室で待った。
飯山ハルキが汗を拭きながら、病室に姿を現したのは15時前だった。リクの姿を見て、いたたまれない表情を見せる。当然、綾が亡くなった事は知っていた。
ゴウとリクが繋がっていたのは、知らなかったが。
怪我の経緯をゴウから聞いたハルキは、眠っているリクの手を握ると自分の額に当てて呟いた。
「桐生。置き去りにして……本当に、ごめんな」
疲れ切って澱んだ空気が、病室内を漂う。元気なのは、外の天気くらいのものだった。憎たらしいほどに晴れている。ハルキは、冷えたミネラルウォーターを一気に飲み干すとゴウに尋ねた。
「――……桐生とは、いつから繋がりがあったの?」
「家で餃子やった日」
「急にレジ締め云々言い出して出てったの。あれ、そうだったんだ」
「そう、ごめん」
大きなため息をつきながら、ゴウがパイプ椅子に腰掛ける。髪をかきあげたその横顔には、後悔と疲労の色が強く滲み出ていた。ハルキも疲れた顔はしていたが、ゴウの肩へ優しく手を置いた。
「ハルキに相談してからにすれば良かったって、後悔してる」
「俺に相談しても、変わらなかったよ」
「ナカライ君との繋がりを……僕たちだけでも持っておくべきだったよね。それは、ハルキの役割だったじゃん?僕が何も言わなかったからさ、連絡とか取ってないでしょ」
「まあそうだけど……何が正解とか分からないよ、こればっかりは。だから自分を責めたらダメだよ、ゴウちゃん」
鎮痛剤がよく効いているのかス――ッと寝息を立てるリクの肩が、大きく動く。
「――……リク君にとっての蓮波さんって、どんな存在だったんだろうね」
ゴウが、窓から遠くを眺めながら呟いた。ハルキはどこかぼんやりとしながらも、かつてきちんと生徒と向き合う努力をしていた頃の教師の面持ちで答えた。
「桐生と蓮波は、双子みたいな関係だったんじゃないかな。何となくだけどさ。今思えばだけど纏ってるものが、とてもよく似てた」
「ハルキは悲しい?」
「――……さっきから、ずっと実感が湧かないんだよね。何回もニュース見てんのに。こういうのって、後から来るんだよな」
ゴウはハルキの手をギュッと握ると切ない表情はそのままに、頬杖をついた。
「僕がずっと一緒にいるから。だから大丈夫だよ。あのさ、リク君から止められてたんだけど……彼にも必要だと思う。一緒にいる人」
分かってる、というようにハルキがゴウの手を握り返した。
「蓮波が俺に言った最後の言葉ってさ。『望月君を止めるのは、半井君。』だったんだよ」
これ以上、たらればを話していても仕方がない。リクはよく眠っていて起きる気配がなかった。二人は顔を見合わせると立ち上がり、ゼンジと連絡を取るために病室から離れて外にある喫煙所へと向かって行った。
眠っていたリクの左目が開いたのは、二人が出ていった直後だった。
◆
洗いたてのシーツの匂いに包まれながら、半井ゼンジは目を覚ました。
一瞬、自分がどこにいるのか分からなくて、混乱する。生活指導室で蓮波綾と望月リクについて、刑事に話をしていた筈なのに。途中で気分が悪くなり、担任から保健室に連れて来られた事をゼンジは忘れてしまっていた。
引きずり込まれるようにして、すぐに眠ってしまったらしい。家の人には連絡しておくから、と担任が言っていたのは夢ではなかったのか。
スマホを見ると家族から、メッセージが入ってる。
(無理そうだったら、車で迎えに行く。)
ゼンジは(大丈夫)と返すと、まだ靄がかかっている頭を目覚めさせるように、こめかみを揉んだ。起き上がって靴を履く。
「冷たい水、飲む?」
声をかけてきたのは、保健師の下田だった。泣きはらしたのか目が赤い。ゼンジは頷いたが、さっきスマホで確認した時間は15時を回っていた。事件の事があって、全校生徒はとっくに帰宅させられている。
「ありがとうございます。先生、帰らなくて大丈夫なんですか。もし俺のせいだったら、すいません」
その長身をカーテンから覗かせたゼンジが頭を下げる。下田は悲しげに笑うと首を振った。そして小さい冷蔵庫からミネラルウォーターを取り出すと、ゼンジに渡した。
「このまま、蓮波さんのお通夜に行くから」
お通夜……もう本当に蓮波はこの世にいないんだな、という実感がこみ上げてくる。冷たいミネラルウォーターを口につけながらゼンジは、現実に戻ってきた感覚を味わっていた。
白昼夢みたいな変な感覚は消えたけれど……実感は湧いても、感情が麻痺してこれっぽっちも伴ってくれない。
何だか疲れたな。すごく疲れた。
「……蓮波さん、そこのベッドの常連さんでね」
下田の声で我に返る。彼女は、ゼンジの寝ていた隣のベッドへ目をやっていた。その目は虚ろで涙が浮かんでいた。
「私、何も分かってなかった。無責任にカウンセリング行けとか。そんな話しかしなくて。彼女がお母さんとの間に何を抱えてたのか、聞こうともしなかった」
「蓮波は、望月の居場所を作りたいと言ってました。そのために、やらなきゃいけない事があるって。それが母親との対話……だったのかな」
「福祉関係者の人と話をしたの。お母さんね。全部、蓮波さんが悪いと思い込んでたフシがあったって。こんな事になってから、あれもそうだった、これもそうだったって……思い当たることしかないの。もう、本当に自分が嫌になる……」
下田の目から、涙がポロポロと零れ落ちる。ゼンジはふらつく身体を何とか保って俯いたまま、誰へともなく呟いた。
「蓮波ってヤツを知っていて、罪悪感を感じない人なんているんですかね。俺、いないと思いますよ」
下田の小さい嗚咽を聞きながら立ち上がる。ベッドに置かれていたスマホが動いているのに気づいたゼンジは、通話ボタンを押して耳に当てた。声の主は飯山ハルキだった。蓮波のお通夜の事だろうか。
「はい」
「今、望月君が入院してる病院にいるんだけどね」
「……入院?具合悪いんですか、アイツ」
ゼンジの顔がサッと曇った。当然、望月だって蓮波の件は知っているだろうと思うけど。でも俺は今、アイツがどんな生活を送ってるのか知らない。本当に病気か事故で入院している可能性だって十分にある。
雑音と共に電話の声が、賑やかな感じの声色に変わった。
「あ、ナカライ君?僕、瀬能って言います。飯山のパートナーで」
「――……はあ」
「いきなりだから、ワケ分からないよね。あのね、僕の知り合いの所で預かってたの。リク君。新橋のお店だったんだけど」
新橋。退学届にあった消印の場所。
案外、近い場所にいたんだなとゼンジは驚きを隠せずにいた。夏休みを使って、しらみつぶしに調べるしかないと思っていたのに。知り合いに聞けば辿りつける場所にいた。
切れていた糸が、再び繋がったような気がする。
ぬか喜びが漏れ出てしまったのだろうか。瀬能が気まずそうに続けた。
「蓮波さんの件を知った、リク君ね。ドライバーで目を突いちゃって」
「えっ?!」
「失明はギリしなくて済んだんだけど……発作的に死のうとしたみたいで。入院を勧められたの。手続きとかお金は、気にしなくていいんだけど。一緒にいてくれる人が必要だなって、ハルキと話して」
「――……望月に、俺には言うなって言われてたんじゃないですか?」
「まあね。でもさ、男の強がりみたいなのってあるじゃん。本音では、ずっとナカライ君に会いたかったと思うよ。港区の総合病院なんだけどさ。僕らまだいるから、今から来てほしいんだ。彼を一人にしたくないんだよね」
声が飯山に変わる。
「蓮波と最後に話した時ね。彼女、言ってたんだよ。『望月君を止めるのは、半井君。』って」
「……すぐ行きます。もう二度と離れたくない」
気がつくと、ゼンジは駅に向かって走りだしていた。
◆
望月リクは誰もいなくなった病室で、苦い表情を浮かべながらこめかみを押さえていた。
目の奥が焼かれているように痛む。鎮痛剤、全然効いてないじゃないか。別に目を潰そうとか死のうなんて意図はなかった。ただ、目の奥が痛くて堪らなかった。我慢出来ないほどに痛かったから、ドライバーで目を突いた。
そうすれば、頭痛が止まると思ったから。
それを精神病院へ入院とか、大袈裟にもほどがある。そんな事になったら、兄貴が絶対に嗅ぎつけてきて……嗅ぎつけてきて、俺に何をするんだ?
とっくに、俺は捨てられてるだろ。
止んでいた声が再び脳内をこだまして、耐え難い痛みが襲いかかる。リクは、うるさい!と怒鳴りつけたくなる気持ちを必死で押さえた。目立つ頭の包帯を外してパジャマを脱ぐと、簡易クローゼットの中を漁った。
瀬能ゴウが来てたって事は……ビンゴ。着替えやら下着が置いてある。病院に来る途中で買ったのか。どれも新品で、まだタグがついていた。なんか、こういうのは気にする人なんだよな……雑な性格してるクセして。
リクはゴウの妙な所を評価しながら、素早く着替えるとこっそり病室を後にした。
こんな時、自分の小柄さは得だと思う。隣の四人部屋に入ると散歩用なのだろう、帽子が掛けてあるのが目に入った。他の患者にばれないよう仕切りカーテンの隙間から入って拝借すると、目深に被った。老人はベッドでぐっすりと寝息を立てている。ついでにブルゾンの膨らみを確認して、ポケットに入っていた財布も拝借する。
そうして病室を出たリクは、ナースステーションの前を堂々と通り過ぎていった。エレベーターで一階のロビーまで降りてゆく。
気配を消すのが得意なのは、皮肉にも虐待の賜物であった。
人の波をどんどん潜り抜け、病院から遠ざかる。人気のない通りまで来て、周囲に人がいないのを確認するとそのまま走りだした。
けれども、声が追いかけてくる。
お前のせいで、蓮波が死んじゃった。
うるさい、うるさい!
リクは自分の中で執拗に鳴り響く、不快な声の主がようやく誰だか理解した。
これは、俺の声じゃない。
兄貴……桐生カイの声だ。
お前は、父さんと本当によく似てるよ。愛されてるって勘違いしたんだろ?
蓮波は、お前を選ばなかったね。
要らない人間が出来るのは、消える事だけだよ。ねえ、母さん。
もう止めてくれ!!
鋭い痛みが、目の奥を貫いてゆく。発作的に悲鳴をあげそうになる口で、指を思い切り噛んだ。咬み傷が深すぎて血が垂れ始めている。何をやってるんだ、俺は。リクは指をギュッと握りしめると、そのまま走り続けた。
兄の声から逃れるように。
◆
「――……え?」
乗車するはずだった特別快速が発車してしまった。半井ゼンジは、電話の奥の瀬能ゴウの声を酷く遠くに感じながら、立ち尽くしていた。
「本当にごめん。目を離した隙にリク君、病院から抜け出しちゃったんだよ。まさか動ける状態だったとは思わなくて。ああもう!こんなの言い訳にしかならないよね。知り合いにも探してもらうよう頼んである。だけど……」
「だけど、なんなんですか?」
ゴウは、華僑グループが慈善事業をやっている訳では無い事を、誰よりも知っている。望月リクが信誠会に戻れば、もう後がない。オーナーは、リクを二度と許さないだろうし、信誠会はすぐにでも、リクを海外へと売り飛ばしてしまうだろう。
「もう二度と戻ってこない可能性もあるの。それだけは覚悟してほしい」
反対車線から特急が通り過ぎて、突風が吹き付けてゆく。プァーー!という叫びのような音に、思わず耳を塞いでしまった。スマホがホームへ無様に転がり落ちてゆく。
夏の遅い夕焼け。その焼け付くような眩しさに、ゼンジは目を開けている事も出来なかった。
また糸が切れてしまう……もう二度と繋がらないかもしれない。
助けてくれ、蓮波。
ゼンジは無意識のうちに祈っていた。
空調が効いているとは言え、体育館の中は生徒で溢れかえっていて、どうにも暑さは拭えない。しかも夏休みを前に生徒は皆、浮足立っている。校長の挨拶が始まった頃には、あちこちから退屈そうにスマホを弄る音が聞こえ始めていた。
半井ゼンジも欠伸を噛み殺しながら、空調のルーバーが動く様をぼんやりと眺めていた。
にわかに生徒のざわめきに不穏が入り混じり始める。教師の何名かが急ぎ足で、体育館を出入りしていた。
不穏は急速度で伝播して、あっという間に体育館を覆い尽くして行った。
「嘘でしょ」
「えっえっ……」
殆ど言葉にならない声が所々から聞こえる。学年主任が校長になにやら耳打ちをした所で、ゼンジは様子のおかしさに気づいた。見渡すとスマホを見ていた生徒のほぼ全員が、凍りついたように固まっている。校長の声が大きくなってマイクがキィーンという音を立てた。
「全校生徒は、速やかに担任の指示に従い教室へ戻るように。既に知っている者もいるかと思うが、慌てず、担任からの説明があるまで待機をして欲しい」
何が起きた?
トントンと肩を叩かれて振り返ると、最後尾にいたはずのアラタが顔面蒼白でスマホを差し出していた。
(東京都……市のマンションで、都内の高校に通う蓮波綾さん16歳が刃物で刺され死亡。「娘を殺した」と通報の母親、蓮波由紀恵容疑者42歳を殺人容疑で逮捕。)
……何だこれ。
酷く、喉が乾く。
「キャア!!」
ガタンッという音と共に、女生徒の悲鳴が聞こえる。白昼夢でも見ているような、スローモーションの世界。全ての感覚が遠くて、ビニールにでも包まれているような息苦しさを感じる。なんなんだ、この感覚は。ぼんやりと音のする方へ目をやると、佐伯遥が気を失って倒れていた。
教室に戻ってから、担任が来て事件の詳細を説明するまで、誰一人として口を開く者はいなかった。事件の詳細と言っても、ニュースと変わらない程度の概要しか分からない。警察関係者が校舎を出入りする様子が、教室の窓から聞こえてきていた。
蓮波綾が、母親に殺された。
「……詳しい事情などは、まだ不明なんだがな。蓮波と交流のあった生徒に、警察の方が話を聞きたいそうだ」
担任もまさかの出来事で余裕がないのだろう。ずっと、ゼンジの顔を見ながら話している。他の生徒たちは俯いたまま、この世の終わりのような顔をして押し黙っていた。
つい昨日まで面白半分に噂していた人物が、ある日突然、この世から居なくなる。
皆、言い訳探しに必死で担任の話などそっちのけの様子だった。
「半井」
名前を呼び終わらないうちに立ち上がったゼンジは、鞄を抱えると「先に職員室へ行ってます」それだけ言って、教室を後にした。
シン……と静まり返った廊下を、蝉の声だけがジーワジーワとしがみつくようにして鳴き喚いていた。
◆
職員室に顔を出すと、学年主任から生活指導室で待っていて欲しいと伝えられた。警察関係者は佐伯遥と一緒に話を聞きたいそうだ、と言われる。
佐伯って倒れていたけど……話出来るのか。
半井ゼンジは、相変わらず白昼夢を見ているような奇妙な感覚の中で、ぼんやりとズレた事を考えていた。
「おい大丈夫か、半井。気分悪いんじゃないのか。顔、真っ青だぞ」
という学年主任の声は、一つもゼンジの耳に届いていなかった。
生活指導室のドアが、酷く重たく感じる。
蓮波綾が殺されたのは、昨日の夜。という話だった。
あの時、蓮波を選んでいれば間に合った。
全身から血が抜けるような眩暈を覚えて、生まれてから一番重いドアを開く。中に入ると奥の席でぼーっと一点を見つめたまま、瞬きすらしようとしない遥の姿が目に入った。
喉の奥にどうしようもない罪悪感がへばりついて、言葉が出ない。何を言っても言い訳にしかならない。俺は、取り返しのつかない事をしてしまった。俺は、とんでもない過ちを犯した。
いつまでも入り口で突っ立ったまま動かないゼンジに気づいた遥が、力のない眼差しを向けた。血の気のない唇を微かに動かしながら、掠れた声で伝える。
「半井君のせいじゃない……」
「――……ごめん」
「……私一人でも、行けば良かった……」
「……行けないだろ。男の俺が一緒じゃなきゃ……あんなの、行ける訳が……」
遥の顔が悲しみで歪んで、その頬を涙が伝う。ゼンジも、心臓が押し潰されるような感覚に、自分がもう何を言っているのかさえ分からなくなっていた。遠くで聞こえる嗚咽が自分のものだと気づくのでさえやっとだ。
そのうち遥の様子がおかしくなってきた。口を開いてもヒューッと音を立てるばかりで、呼吸が上手に出来ていないようだった。苦しそうに顔を歪めている。
「……ちゃん……」
「ちょっと、先生呼んでくる」
「……綾ちゃん。最後まで……望月君の事、気にしてた」
「――……うん」
「……家族って言ってた……望月君の事――……私、平気なフリして、バカみたいに……嫉妬…嫉妬なんかしたから、あんな事に……」
ヒューッっという呼吸音が大きくなる。入った時から血の気のなかった遥の顔色が、青いを通り越してあっという間に白くなる。ゼンジは堪らず近づくと、その冷え切った手を握りしめた。
「大丈夫、大丈夫だから」
「ごめっごめんね!綾ちゃん……うぅ……綾ちゃあん」
警察関係者がやってくるまで、遥はゼンジの腕にすがりついて号泣していた。ゼンジも声を殺しながら静かに泣き続けていた。
結局、遥の事情聴取は後日という事になった。家族が迎えに来て、これから病院へ行くと言う。連絡先の交換をして、ゼンジだけが残って聴取を受けた。直近の、遥とのやり取りを中心に話す。
途中、何度も聞き返されるが、その度にゼンジは「え?」という表情をしていた。聞いていなかったり、同じ話を繰り返していたり、質問とはかけ離れた話を始めたり。同席していた担任が刑事と顔を見合わせ、彼も後日に……と相談し始めていた。
部屋に入ってきた時の遥と一緒だった。一点を見つめたまま瞬きすらしようとしないゼンジは、思い詰めた表情で何度目になるか分からない同じ台詞を繰り返していた。
「――……俺が佐伯さんの言う通り、一緒に蓮波の家に行っていれば、助けられたんです」
刑事が、やるせないといった表情で精一杯の言葉をかける。
「君のせいじゃないよ。昨日の夜、福祉関係者も電話をかけてたんだ。繋がらなかったそうだ。今日の午前中に、緊急で訪問する予定だったと言っていたよ」
制服のズボンに、止まる事なく涙が零れ落ちてゆく。
何を言っても、今は納得出来ないだろうな。
そう思いながら刑事は、申し訳無さそうな顔をして続けた。
「逮捕された母親がね。望月って生徒の名前を出してるんだよ……綾さんの日記が、見つかってね。その中にも出てくるんだ。君の名前と一緒に」
「――……望月の家には行ったんですか」
「ここへ来る前に、連絡はしたよ。家の人は出ていったから関係ないの、一点張りでね。退学届も、本人が書いて提出したものと確認されてるし……望月君の事は、その……君が詳しいとしか言わないんだよ」
「……でしょうね」
ゼンジは、視線を動かして再び瞬きを始めるとポツリポツリと話しだした。
綾にタオルを渡した、あの日からの出来事を。
◆
港区にある、とある総合病院の個室。
頭を包帯でぐるぐる巻きにされ、右目に眼帯をした望月リクがスースーと寝息を立てていた。出勤途中にオーナーから呼び出された瀬能ゴウは、猛烈に酷い二日酔いのような気分で、眠っているリクの姿を見つめていた。
最近のリクは笑うようになった、とスタッフから聞いた矢先の事件だった。
別に神様を信じてるワケじゃないけど、とゴウは思う。
あまりにも惨いんじゃないの。
蓮波綾が亡くなった事は、出勤途中の電車内で知った。
受け止めきれる訳ないじゃない。
大人にだって、無理なのに。
店長の話では、本当に一瞬の出来事だったらしい。悲鳴を上げて気を失ったリクに驚いて、救急車を呼ぼうと目を離した、ほんの数分の間にそれは起きた。
リクは何を思ったのか、デスクの引き出しにあったドライバーで、右目を突いてしまった。
救急車が来るまでうわ言のように、蓮波綾の名前を呼び続け、頭が痛いと訴えていたと言う。
集中治療室に入ったのが、10時前。幸い失明は免れたものの……予後に関する担当医師の見解は、厳しいものだった。精神病院の紹介状を書くのでなるべく早い入院を、と勧められる。
「素人で、どうにか出来るレベルではないと思います。もっと強い希死念慮がこれから出てくる可能性が高いですね」
「すみません、希死念慮ってなんですか?元々強い頭痛持ちだったと、本人は言っていたようなんですが」
「瀬能さん。望月さんの脳に異常は見当たりませんでした。精神的なものと見ています。自殺未遂ですよ、彼がしたのは。専門家によるケアが必要です」
医師との面談を終えたゴウは、休憩室でオーナーに連絡を取った。そういう子は今までにもいた。入院が必要なら、させたら良いじゃないか。と、えらくアッサリした返事が返ってきた。
ゴウは、保険証ってどうなってんだろ……と思った。しかし、その手の事を聞いてしまうと不機嫌になる人でもある。「ありがとうございます」感謝の意を述べるに留めて電話を切った。
時計を見ると14時を回っていた。自販機でお茶を買ったゴウは、飯山ハルキが到着するのを病室で待った。
飯山ハルキが汗を拭きながら、病室に姿を現したのは15時前だった。リクの姿を見て、いたたまれない表情を見せる。当然、綾が亡くなった事は知っていた。
ゴウとリクが繋がっていたのは、知らなかったが。
怪我の経緯をゴウから聞いたハルキは、眠っているリクの手を握ると自分の額に当てて呟いた。
「桐生。置き去りにして……本当に、ごめんな」
疲れ切って澱んだ空気が、病室内を漂う。元気なのは、外の天気くらいのものだった。憎たらしいほどに晴れている。ハルキは、冷えたミネラルウォーターを一気に飲み干すとゴウに尋ねた。
「――……桐生とは、いつから繋がりがあったの?」
「家で餃子やった日」
「急にレジ締め云々言い出して出てったの。あれ、そうだったんだ」
「そう、ごめん」
大きなため息をつきながら、ゴウがパイプ椅子に腰掛ける。髪をかきあげたその横顔には、後悔と疲労の色が強く滲み出ていた。ハルキも疲れた顔はしていたが、ゴウの肩へ優しく手を置いた。
「ハルキに相談してからにすれば良かったって、後悔してる」
「俺に相談しても、変わらなかったよ」
「ナカライ君との繋がりを……僕たちだけでも持っておくべきだったよね。それは、ハルキの役割だったじゃん?僕が何も言わなかったからさ、連絡とか取ってないでしょ」
「まあそうだけど……何が正解とか分からないよ、こればっかりは。だから自分を責めたらダメだよ、ゴウちゃん」
鎮痛剤がよく効いているのかス――ッと寝息を立てるリクの肩が、大きく動く。
「――……リク君にとっての蓮波さんって、どんな存在だったんだろうね」
ゴウが、窓から遠くを眺めながら呟いた。ハルキはどこかぼんやりとしながらも、かつてきちんと生徒と向き合う努力をしていた頃の教師の面持ちで答えた。
「桐生と蓮波は、双子みたいな関係だったんじゃないかな。何となくだけどさ。今思えばだけど纏ってるものが、とてもよく似てた」
「ハルキは悲しい?」
「――……さっきから、ずっと実感が湧かないんだよね。何回もニュース見てんのに。こういうのって、後から来るんだよな」
ゴウはハルキの手をギュッと握ると切ない表情はそのままに、頬杖をついた。
「僕がずっと一緒にいるから。だから大丈夫だよ。あのさ、リク君から止められてたんだけど……彼にも必要だと思う。一緒にいる人」
分かってる、というようにハルキがゴウの手を握り返した。
「蓮波が俺に言った最後の言葉ってさ。『望月君を止めるのは、半井君。』だったんだよ」
これ以上、たらればを話していても仕方がない。リクはよく眠っていて起きる気配がなかった。二人は顔を見合わせると立ち上がり、ゼンジと連絡を取るために病室から離れて外にある喫煙所へと向かって行った。
眠っていたリクの左目が開いたのは、二人が出ていった直後だった。
◆
洗いたてのシーツの匂いに包まれながら、半井ゼンジは目を覚ました。
一瞬、自分がどこにいるのか分からなくて、混乱する。生活指導室で蓮波綾と望月リクについて、刑事に話をしていた筈なのに。途中で気分が悪くなり、担任から保健室に連れて来られた事をゼンジは忘れてしまっていた。
引きずり込まれるようにして、すぐに眠ってしまったらしい。家の人には連絡しておくから、と担任が言っていたのは夢ではなかったのか。
スマホを見ると家族から、メッセージが入ってる。
(無理そうだったら、車で迎えに行く。)
ゼンジは(大丈夫)と返すと、まだ靄がかかっている頭を目覚めさせるように、こめかみを揉んだ。起き上がって靴を履く。
「冷たい水、飲む?」
声をかけてきたのは、保健師の下田だった。泣きはらしたのか目が赤い。ゼンジは頷いたが、さっきスマホで確認した時間は15時を回っていた。事件の事があって、全校生徒はとっくに帰宅させられている。
「ありがとうございます。先生、帰らなくて大丈夫なんですか。もし俺のせいだったら、すいません」
その長身をカーテンから覗かせたゼンジが頭を下げる。下田は悲しげに笑うと首を振った。そして小さい冷蔵庫からミネラルウォーターを取り出すと、ゼンジに渡した。
「このまま、蓮波さんのお通夜に行くから」
お通夜……もう本当に蓮波はこの世にいないんだな、という実感がこみ上げてくる。冷たいミネラルウォーターを口につけながらゼンジは、現実に戻ってきた感覚を味わっていた。
白昼夢みたいな変な感覚は消えたけれど……実感は湧いても、感情が麻痺してこれっぽっちも伴ってくれない。
何だか疲れたな。すごく疲れた。
「……蓮波さん、そこのベッドの常連さんでね」
下田の声で我に返る。彼女は、ゼンジの寝ていた隣のベッドへ目をやっていた。その目は虚ろで涙が浮かんでいた。
「私、何も分かってなかった。無責任にカウンセリング行けとか。そんな話しかしなくて。彼女がお母さんとの間に何を抱えてたのか、聞こうともしなかった」
「蓮波は、望月の居場所を作りたいと言ってました。そのために、やらなきゃいけない事があるって。それが母親との対話……だったのかな」
「福祉関係者の人と話をしたの。お母さんね。全部、蓮波さんが悪いと思い込んでたフシがあったって。こんな事になってから、あれもそうだった、これもそうだったって……思い当たることしかないの。もう、本当に自分が嫌になる……」
下田の目から、涙がポロポロと零れ落ちる。ゼンジはふらつく身体を何とか保って俯いたまま、誰へともなく呟いた。
「蓮波ってヤツを知っていて、罪悪感を感じない人なんているんですかね。俺、いないと思いますよ」
下田の小さい嗚咽を聞きながら立ち上がる。ベッドに置かれていたスマホが動いているのに気づいたゼンジは、通話ボタンを押して耳に当てた。声の主は飯山ハルキだった。蓮波のお通夜の事だろうか。
「はい」
「今、望月君が入院してる病院にいるんだけどね」
「……入院?具合悪いんですか、アイツ」
ゼンジの顔がサッと曇った。当然、望月だって蓮波の件は知っているだろうと思うけど。でも俺は今、アイツがどんな生活を送ってるのか知らない。本当に病気か事故で入院している可能性だって十分にある。
雑音と共に電話の声が、賑やかな感じの声色に変わった。
「あ、ナカライ君?僕、瀬能って言います。飯山のパートナーで」
「――……はあ」
「いきなりだから、ワケ分からないよね。あのね、僕の知り合いの所で預かってたの。リク君。新橋のお店だったんだけど」
新橋。退学届にあった消印の場所。
案外、近い場所にいたんだなとゼンジは驚きを隠せずにいた。夏休みを使って、しらみつぶしに調べるしかないと思っていたのに。知り合いに聞けば辿りつける場所にいた。
切れていた糸が、再び繋がったような気がする。
ぬか喜びが漏れ出てしまったのだろうか。瀬能が気まずそうに続けた。
「蓮波さんの件を知った、リク君ね。ドライバーで目を突いちゃって」
「えっ?!」
「失明はギリしなくて済んだんだけど……発作的に死のうとしたみたいで。入院を勧められたの。手続きとかお金は、気にしなくていいんだけど。一緒にいてくれる人が必要だなって、ハルキと話して」
「――……望月に、俺には言うなって言われてたんじゃないですか?」
「まあね。でもさ、男の強がりみたいなのってあるじゃん。本音では、ずっとナカライ君に会いたかったと思うよ。港区の総合病院なんだけどさ。僕らまだいるから、今から来てほしいんだ。彼を一人にしたくないんだよね」
声が飯山に変わる。
「蓮波と最後に話した時ね。彼女、言ってたんだよ。『望月君を止めるのは、半井君。』って」
「……すぐ行きます。もう二度と離れたくない」
気がつくと、ゼンジは駅に向かって走りだしていた。
◆
望月リクは誰もいなくなった病室で、苦い表情を浮かべながらこめかみを押さえていた。
目の奥が焼かれているように痛む。鎮痛剤、全然効いてないじゃないか。別に目を潰そうとか死のうなんて意図はなかった。ただ、目の奥が痛くて堪らなかった。我慢出来ないほどに痛かったから、ドライバーで目を突いた。
そうすれば、頭痛が止まると思ったから。
それを精神病院へ入院とか、大袈裟にもほどがある。そんな事になったら、兄貴が絶対に嗅ぎつけてきて……嗅ぎつけてきて、俺に何をするんだ?
とっくに、俺は捨てられてるだろ。
止んでいた声が再び脳内をこだまして、耐え難い痛みが襲いかかる。リクは、うるさい!と怒鳴りつけたくなる気持ちを必死で押さえた。目立つ頭の包帯を外してパジャマを脱ぐと、簡易クローゼットの中を漁った。
瀬能ゴウが来てたって事は……ビンゴ。着替えやら下着が置いてある。病院に来る途中で買ったのか。どれも新品で、まだタグがついていた。なんか、こういうのは気にする人なんだよな……雑な性格してるクセして。
リクはゴウの妙な所を評価しながら、素早く着替えるとこっそり病室を後にした。
こんな時、自分の小柄さは得だと思う。隣の四人部屋に入ると散歩用なのだろう、帽子が掛けてあるのが目に入った。他の患者にばれないよう仕切りカーテンの隙間から入って拝借すると、目深に被った。老人はベッドでぐっすりと寝息を立てている。ついでにブルゾンの膨らみを確認して、ポケットに入っていた財布も拝借する。
そうして病室を出たリクは、ナースステーションの前を堂々と通り過ぎていった。エレベーターで一階のロビーまで降りてゆく。
気配を消すのが得意なのは、皮肉にも虐待の賜物であった。
人の波をどんどん潜り抜け、病院から遠ざかる。人気のない通りまで来て、周囲に人がいないのを確認するとそのまま走りだした。
けれども、声が追いかけてくる。
お前のせいで、蓮波が死んじゃった。
うるさい、うるさい!
リクは自分の中で執拗に鳴り響く、不快な声の主がようやく誰だか理解した。
これは、俺の声じゃない。
兄貴……桐生カイの声だ。
お前は、父さんと本当によく似てるよ。愛されてるって勘違いしたんだろ?
蓮波は、お前を選ばなかったね。
要らない人間が出来るのは、消える事だけだよ。ねえ、母さん。
もう止めてくれ!!
鋭い痛みが、目の奥を貫いてゆく。発作的に悲鳴をあげそうになる口で、指を思い切り噛んだ。咬み傷が深すぎて血が垂れ始めている。何をやってるんだ、俺は。リクは指をギュッと握りしめると、そのまま走り続けた。
兄の声から逃れるように。
◆
「――……え?」
乗車するはずだった特別快速が発車してしまった。半井ゼンジは、電話の奥の瀬能ゴウの声を酷く遠くに感じながら、立ち尽くしていた。
「本当にごめん。目を離した隙にリク君、病院から抜け出しちゃったんだよ。まさか動ける状態だったとは思わなくて。ああもう!こんなの言い訳にしかならないよね。知り合いにも探してもらうよう頼んである。だけど……」
「だけど、なんなんですか?」
ゴウは、華僑グループが慈善事業をやっている訳では無い事を、誰よりも知っている。望月リクが信誠会に戻れば、もう後がない。オーナーは、リクを二度と許さないだろうし、信誠会はすぐにでも、リクを海外へと売り飛ばしてしまうだろう。
「もう二度と戻ってこない可能性もあるの。それだけは覚悟してほしい」
反対車線から特急が通り過ぎて、突風が吹き付けてゆく。プァーー!という叫びのような音に、思わず耳を塞いでしまった。スマホがホームへ無様に転がり落ちてゆく。
夏の遅い夕焼け。その焼け付くような眩しさに、ゼンジは目を開けている事も出来なかった。
また糸が切れてしまう……もう二度と繋がらないかもしれない。
助けてくれ、蓮波。
ゼンジは無意識のうちに祈っていた。
0
あなたにおすすめの小説
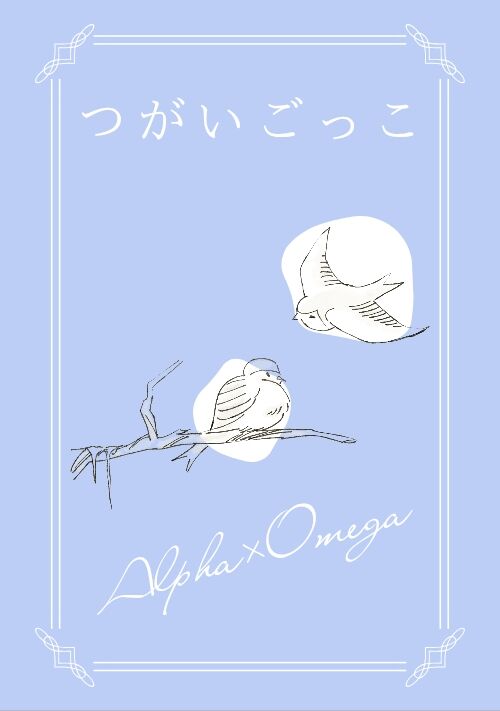
つがいごっこ~4歳のときに番ったらしいアルファと30歳で再会しまして~
深山恐竜
BL
俺は4歳のときにうなじを噛まれて番を得た。
子どもがたくさんいる遊び場で、気が付いたらそうなっていたとか。
相手は誰かわからない。
うなじに残る小さな歯型と、顔も知らない番。
しかし、そのおかげで、番がいないオメガに制限をかけられる社会で俺は自由に生きていた。
そんなある日、俺は番と再会する。
彼には俺の首筋を噛んだという記憶がなかった。
そのせいで、自由を謳歌していた俺とは反対に、彼は苦しんできたらしい。
彼はオメガのフェロモンも感じられず、しかし親にオメガと番うように強制されたことで、すっかりオメガを怖がるようになっていた。
「でも、あなただけは平気なんです。なんででしょう」
首を傾げる彼に、俺は提案する。
「なぁ、俺と番ごっこをしないか?」
偽物の番となった本物の番が繰り広げるラブストーリー。

番を拒み続けるΩと、執着を隠しきれないαが同じ学園で再会したら逃げ場がなくなった話 ――優等生αの過保護な束縛は恋か支配か
雪兎
BL
第二性が存在する世界。
Ωであることを隠し、平穏な学園生活を送ろうと決めていた転校生・湊。
しかし入学初日、彼の前に現れたのは――
幼い頃に「番になろう」と言ってきた幼馴染のα・蓮だった。
成績優秀、容姿端麗、生徒から絶大な信頼を集める完璧なα。
だが湊だけが知っている。
彼が異常なほど執着深いことを。
「大丈夫、全部管理してあげる」
「君が困らないようにしてるだけだよ」
座席、時間割、交友関係、体調管理。
いつの間にか整えられていく環境。
逃げ場のない距離。
番を拒みたいΩと、手放す気のないα。
これは保護か、それとも束縛か。
閉じた学園の中で、二人の関係は静かに歪み始める――。

伝説のS級おじさん、俺の「匂い」がないと発狂して国を滅ぼすらしいい
マンスーン
BL
ギルドの事務職員・三上薫は、ある日、ギルドロビーで発作を起こしかけていた英雄ガルド・ベルンシュタインから抱きしめられ、首筋を猛烈に吸引。「見つけた……俺の酸素……!」と叫び、離れなくなってしまう。
最強おじさん(変態)×ギルドの事務職員(平凡)
世界観が現代日本、異世界ごちゃ混ぜ設定になっております。


処刑エンドの悪役公爵、隠居したいのに溺愛されてます
ひなた翠
BL
目が覚めたら、やり込んだBLゲームの悪役公爵になっていた。
しかも手には鞭。目の前には涙を浮かべた美少年。
——このままじゃ、王太子に処刑される。
前世は冴えない社畜サラリーマン。今世は冷徹な美貌を持つ高位貴族のアルファ。
中身と外見の落差に戸惑う暇もなく、エリオットは処刑回避のための「隠居計画」を立てる。
囚われのオメガ・レオンを王太子カイルに引き渡し、爵位も領地も全部手放して、ひっそり消える——はずだった。
ところが動くほど状況は悪化していく。
レオンを自由にしようとすれば「傍にいたい」と縋りつかれ、
カイルに会えば「お前の匂いは甘い」と迫られ、
隠居を申し出れば「逃げるな」と退路を塞がれる。
しかもなぜか、子供の頃から飲んでいた「ビタミン剤」を忘れるたび、身体がおかしくなる。
周囲のアルファたちの視線が絡みつき、カイルの目の色が変わり——
自分でも知らなかった秘密が暴かれたとき、逃げ場はもう、どこにもなかった。
誰にも愛されなかった男が、異世界で「本当の自分」を知り、運命の番と出会う——
ギャップ萌え×じれったさ×匂いフェチ全開の、オメガバース転生BL。

冤罪で堕とされた最強騎士、狂信的な男たちに包囲される
マンスーン
BL
王国最強の聖騎士団長から一転、冤罪で生存率0%の懲罰部隊へと叩き落とされたレオン。
泥にまみれてもなお気高く、圧倒的な強さを振るう彼に、狂った執着を抱く男たちが集結する。

鎖に繋がれた騎士は、敵国で皇帝の愛に囚われる
結衣可
BL
戦場で捕らえられた若き騎士エリアスは、牢に繋がれながらも誇りを折らず、帝国の皇帝オルフェンの瞳を惹きつける。
冷酷と畏怖で人を遠ざけてきた皇帝は、彼を望み、夜ごと逢瀬を重ねていく。
憎しみと抗いのはずが、いつしか芽生える心の揺らぎ。
誇り高き騎士が囚われたのは、冷徹な皇帝の愛。
鎖に繋がれた誇りと、独占欲に満ちた溺愛の行方は――。

だって、君は210日のポラリス
大庭和香
BL
モテ属性過多男 × モブ要素しかない俺
モテ属性過多の理央は、地味で凡庸な俺を平然と「恋人」と呼ぶ。大学の履修登録も丸かぶりで、いつも一緒。
一方、平凡な小市民の俺は、旅行先で両親が事故死したという連絡を受け、
突然人生の岐路に立たされた。
――立春から210日、夏休みの終わる頃。
それでも理央は、変わらず俺のそばにいてくれて――
📌別サイトで読み切りの形で投稿した作品を、連載形式に切り替えて投稿しています。
エピローグまで公開いたしました。14,000字程度になりました。読み切りの形のときより短くなりました……1000文字ぐらい書き足したのになぁ。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















