11 / 27
相槌を打たなかったキミへ【4‐3】
しおりを挟む
***
「都井さん、何飲みますか? 何でもご馳走しろってオーナーに言われてるんで選び放題ですよ!」
「え、……あー、俺お酒とかあんま詳しくないんだけど……」
「そうなんですねー! まぁオレも成人したばっかりでそんなに詳しくないんで、ちょっと先輩に聞いて見繕ってきます! あ! 食べられないものとかありますか?」
「………………辛いもの……」
「りょうかいでーす!」
そう言って苗加の後輩は席を離れる。
正直、この場所に一人残されるのは心細かったが、通されたテーブルが奥まった場所にあっただけまだ助かった。
と、いうより、俺が今座っている席は他の席とは違い半個室のようにカーテンで仕切られている。同じような席が後二か所設けられていたが、それ以外は店内を見渡せるほど風通しの良さそうな配置になっている。
あの席に通されていたら、居た堪れなくて胃が痛くなっていたな、と思うと、苗加と江草さんの配慮に感謝した。
中々帰ってこない苗加の後輩を待つことに飽き、手持無沙汰になった俺は、何気なしに店内を見渡した。
営業開始時間が十九時と聞いていたため、その時間に合わせてきたが、店内にはそこそこの人数の客がいた。
勿論、というか予想通り、男性客は一人もおらず、俺のことが目に入った客の女の子は一瞬不思議そうな顔をした。しかし、すぐに担当ホストの方に笑顔を向け、俺のことはそれほど気にしていない様だった。
よく考えれば、高いお金を払ってホストに会いにきているのだ。俺のことを見ている時間すら惜しいだろう。
変に他人に介入してこない空気に少しだけ居心地の良さを感じてしまい、乾いた笑いが漏れた。
「すみませーん! 遅くなりました!」
ようやく戻ってきた後輩の手にはビール瓶が握られていた。
「え、ビール……?」
「あ、はい! お酒詳しくないってことだったんで、最初は飲み慣れた物の方がいいかと思って! ……もしかしてビール苦手でした……?」
「いや、むしろ助かる。あんまり高いお酒持ってこられてもどうしようかと思った」
「あーよかった!」
心底安堵した表情で後輩はグラスにビールを注ぎ始めた。それを俺の前に置く。
「そうだ! 忘れてた! これ、オレの名刺です!」
「あ、あぁ……」
ホストクラブでホストから名刺を貰うなんて、夢にも思わなかった。
「結城ナナト?」
「はい! よろしくおねがいします!」
ナナトはヒロムに重なるような無邪気な顔で笑った。
まだあどけなさが残るような子が、本当にホストクラブでやっていけるのかと、兄弟程度の年の差のはずなのに心配になってくる。
っていっても、苗加もどうにかなってるんだから大丈夫か……
俺は注いでもらったビールに口をつける。そう言えば久しぶりにお酒を飲んだな、と考えると、最近は友人たちと飲み会にも行っていないことに気が付いた。ここ数年はずっと一人で仕事をこなす日々を繰り返していた。誰かと騒がしい場所でお酒を飲むなんて久しぶりで、なんだか心地よかった。
「ごめんなさい。ヒロムさんに都井さんが来たことは伝えてあるんですけど、丁度姫様が来ちゃって、そっちの相手をしなくちゃいけないみたいで……。多分すぐに引き上げてこっちに来ると思うんですけど」
お酒を飲んだことによる心地よさと非現実空間に浸っていた俺は、申し訳なさそうにしているナナトの顔を見て我に返った。
「あ、違う、違う。退屈してたわけじゃなくて、お酒飲んだの久しぶりだな、ってぼんやり考えてただけだから」
「あ、そうなんですね、良かった! オレ、まだこういう仕事始めて日が浅いし、元々お喋りな方でも無かったから、ちゃんと楽しませられてるかいつも不安で……」
なんでそんな子がホストを始めたのか気になった。
「じゃあなんでホストに……?」
「実は、実家が……その、あまり裕福じゃなくて……少しでも生活の足しになればと思って……」
夜の世界で働く人の事情は人それぞれ。
軽々しく立ち入ってしまったことに後悔すると同時に、親と折り合いが悪い自分と無意識に比べてしまい気分が落ちる。
「そっか……大変だな……」
「っていうのは嘘なんですけど」
「は?」
「ヒロムさんにこう言えって教えられたんで。ホストになった理由なんてほぼみんな嘘つきますよ? 同情も立派な営業方法なんで!」
開いた口が塞がらない。
純粋そうだと思っていたナナトもしっかりホストだった。
「本当の理由は、派手な世界で派手に活躍してみたかったからです! これマジなやつなんで内緒ですよ?」
「はぁ……」
逆に深刻な理由じゃなくて良かったと思ってしまうくらい脱力した。
「都井さんはどうしてカメラマンになったんですか?」
「俺は……元々叔父がスタジオやってて、それを継いだ感じ……」
「でも、好きじゃないと継ごうとは思わないですよね? 写真撮るの好きだったんですか?」
「まぁ、そこそこ……」
情熱を語るのが恥ずかしくて逃げる。
ナナトは何かを察した顔をすると、話題を別に移した。
「それにしても、ヒロムさん遅いですね~」
「いや、俺的には別に来てもらわなくてもいいんだけど」
客が来ているなら売り上げに繋がらない俺より、客に時間を使った方が有意義だと思う。
「え? ヒロムさんの接客ですよ? 勿体無いですよ!」
「勿体無いって……」
「オレだって間近でヒロムさんの接客見て勉強できるって楽しみにしてるのに、そんなこと言わないでくださいよ~」
ナナトの情けない声と表情に思わず噴き出す。
「ちょっとオレ、偵察してきます!」
「え、そこまでしなくても……」
立ち上がろうとするナナトを引き留め、席に座らせ、短く息を吐く。
「忙しいのに、邪魔したくないんだよ」
「都井さん……」
ナナトが残念そうな顔で俺を見たが、すぐに驚いたような顔に変わる。
「オーナー!」
「え?」
ナナトの視線の先に目を向けると江草さんが穏やかな笑顔で立っていた。
「こんばんは」
「あ、こんばんは! お誘いありがとうございます」
まさか江草さんも来てくれるとは思わず、声が上ずる。
江草さんは俺たちのテーブルの上を一瞥すると、勢いよく立ちあがったナナトに声を掛けた。
「ナナト、フードはどうした?」
「あ、あー! 忘れてました……」
そういえば、苦手な食べ物を聞かれたのにテーブルの上にはビールしか無かった。
「すぐに持ってきます!」
「ほら、慌てると危ない……、今日は永野さんが来る日だからお願いして何か作ってもらってきて」
「そうか! 永野さんの日か! 分かりました!」
慌てると危ない、と注意されたのにも関わらず、ナナトは慌てて店の奥に消えていった。
「あの、永野さんっていうのは……?」
「あぁ、私が経営しているホストクラブのシェフをしてくれている方でね。色んなホテルの料理長を務めていたくらい腕がいいんだよ」
「シェフ……」
ホストクラブにシェフがいることを初めて知った俺は驚きと共に思わず声が漏れた。
「そんなことで驚いて貰えるなんて、招待した甲斐があるよ」
気持ちの良い声で笑われてしまい恥ずかしくなる。
「さ、遠慮しないでどんどん飲んで! って言っても今はビールしか無いのか……。ナナトが戻ってきたらシャンパン持ってこさせるよ」
「いえ、そんなお気遣いなく……」
ビールの値段はたかが知れていると想像つくが、シャンパンの値段は、想像もつかない。もし高価なものを振舞われてしまったら頭が上がらなくなってしまう。
「都井くんは謙虚だね。でも相手からの好意を仕事に繋げることも重要だと思わない?」
「え……?」
そう、囁いた江草さんは俺の隣に腰を下ろした。
知り合いと言うには近い位置で。
「その点、ヒロムは素直で可愛いよ」
まるで、惚気を聞かされているような気分になったが、江草さんの俺を見つめる瞳はどこか鋭い。
捕って食べられてしまいそうな雰囲気に息を飲む。
何か、言葉に出来ない違和感を感じると、江草さんの顔はいつもの柔和なものに戻った。
ホッとしたのもつかの間、突然割って入った声に飛び上がりそうになる。
「心広くん!」
「ヒロム……?」
焦ったような顔をして現れた苗加は、まるでそうするのが当たり前かのように、すぐに江草さんの隣にぴったりと付いて座った。
今まで見た中で一番”ホストみたいな”恰好をした苗加の首には細いチェーンのネックレスが光っていた。
「オーナー、客席に入る時は声をかけてください」
「そうは言っても、ヒロムは接客中だったじゃないか」
「でも……」
「そんなに、私が都井くんと話すのが嫌だった?」
「それは、……はい……」
「本当に可愛いなぁヒロムは」
事情を知っている俺の前だからなのか、それともこれが通常運転なのかは分からないが、とにかく空気甘い。いくら一度見ているとはいえ正直きつい。
前回神社で二人に会った時のモヤモヤ感が再び蘇ってくる。
目の前でこれを繰り広げられている状態では、どんなに美味しい料理を食べたとしてもまずく感じるだろう。
そのくらい、二人の間の空気は”遠慮がない”。
「そういえば、都井くんの名前はミヒロっていうんだね?」
「え、あ、はい。心が広いって書いて心広です」
急に話を振られ、言わなくて良いことまで喋ってしまった。
どうせ苗加が知っているのだから、江草さんにばれるのも時間の問題かと思い、無理矢理諦めた。
「心広くんか……良い名前だね」
「……ありがとうございます」
俺が江草さんと話している間、苗加は一度も俺のことを見ようとはしなかった。
あまりにも不自然な視線の逸らし方に首を捻り、一つの結論に思い当たる。
…………もしかして嫉妬されてる……?
江草さんが俺にばかり構うから、苗加は良い気がしないんじゃないか、そう考えたら苗加の行動の意味も理解できる。
人の恋愛ごとに巻き込まれるなんてごめんだ、と背中に冷たい汗が流れる。
「あ! 俺! トイレ行ってきます!」
大きい声でトイレ宣言してしまった恥ずかしさよりも早くここを立ち去りたい一心で立ち上がる。
「じゃあおれが案内して……」
「いや、いい! なんとなく分かる!」
付いてこようとする苗加をその場に残し、俺は足早にテーブルを離れた。
「都井さん、何飲みますか? 何でもご馳走しろってオーナーに言われてるんで選び放題ですよ!」
「え、……あー、俺お酒とかあんま詳しくないんだけど……」
「そうなんですねー! まぁオレも成人したばっかりでそんなに詳しくないんで、ちょっと先輩に聞いて見繕ってきます! あ! 食べられないものとかありますか?」
「………………辛いもの……」
「りょうかいでーす!」
そう言って苗加の後輩は席を離れる。
正直、この場所に一人残されるのは心細かったが、通されたテーブルが奥まった場所にあっただけまだ助かった。
と、いうより、俺が今座っている席は他の席とは違い半個室のようにカーテンで仕切られている。同じような席が後二か所設けられていたが、それ以外は店内を見渡せるほど風通しの良さそうな配置になっている。
あの席に通されていたら、居た堪れなくて胃が痛くなっていたな、と思うと、苗加と江草さんの配慮に感謝した。
中々帰ってこない苗加の後輩を待つことに飽き、手持無沙汰になった俺は、何気なしに店内を見渡した。
営業開始時間が十九時と聞いていたため、その時間に合わせてきたが、店内にはそこそこの人数の客がいた。
勿論、というか予想通り、男性客は一人もおらず、俺のことが目に入った客の女の子は一瞬不思議そうな顔をした。しかし、すぐに担当ホストの方に笑顔を向け、俺のことはそれほど気にしていない様だった。
よく考えれば、高いお金を払ってホストに会いにきているのだ。俺のことを見ている時間すら惜しいだろう。
変に他人に介入してこない空気に少しだけ居心地の良さを感じてしまい、乾いた笑いが漏れた。
「すみませーん! 遅くなりました!」
ようやく戻ってきた後輩の手にはビール瓶が握られていた。
「え、ビール……?」
「あ、はい! お酒詳しくないってことだったんで、最初は飲み慣れた物の方がいいかと思って! ……もしかしてビール苦手でした……?」
「いや、むしろ助かる。あんまり高いお酒持ってこられてもどうしようかと思った」
「あーよかった!」
心底安堵した表情で後輩はグラスにビールを注ぎ始めた。それを俺の前に置く。
「そうだ! 忘れてた! これ、オレの名刺です!」
「あ、あぁ……」
ホストクラブでホストから名刺を貰うなんて、夢にも思わなかった。
「結城ナナト?」
「はい! よろしくおねがいします!」
ナナトはヒロムに重なるような無邪気な顔で笑った。
まだあどけなさが残るような子が、本当にホストクラブでやっていけるのかと、兄弟程度の年の差のはずなのに心配になってくる。
っていっても、苗加もどうにかなってるんだから大丈夫か……
俺は注いでもらったビールに口をつける。そう言えば久しぶりにお酒を飲んだな、と考えると、最近は友人たちと飲み会にも行っていないことに気が付いた。ここ数年はずっと一人で仕事をこなす日々を繰り返していた。誰かと騒がしい場所でお酒を飲むなんて久しぶりで、なんだか心地よかった。
「ごめんなさい。ヒロムさんに都井さんが来たことは伝えてあるんですけど、丁度姫様が来ちゃって、そっちの相手をしなくちゃいけないみたいで……。多分すぐに引き上げてこっちに来ると思うんですけど」
お酒を飲んだことによる心地よさと非現実空間に浸っていた俺は、申し訳なさそうにしているナナトの顔を見て我に返った。
「あ、違う、違う。退屈してたわけじゃなくて、お酒飲んだの久しぶりだな、ってぼんやり考えてただけだから」
「あ、そうなんですね、良かった! オレ、まだこういう仕事始めて日が浅いし、元々お喋りな方でも無かったから、ちゃんと楽しませられてるかいつも不安で……」
なんでそんな子がホストを始めたのか気になった。
「じゃあなんでホストに……?」
「実は、実家が……その、あまり裕福じゃなくて……少しでも生活の足しになればと思って……」
夜の世界で働く人の事情は人それぞれ。
軽々しく立ち入ってしまったことに後悔すると同時に、親と折り合いが悪い自分と無意識に比べてしまい気分が落ちる。
「そっか……大変だな……」
「っていうのは嘘なんですけど」
「は?」
「ヒロムさんにこう言えって教えられたんで。ホストになった理由なんてほぼみんな嘘つきますよ? 同情も立派な営業方法なんで!」
開いた口が塞がらない。
純粋そうだと思っていたナナトもしっかりホストだった。
「本当の理由は、派手な世界で派手に活躍してみたかったからです! これマジなやつなんで内緒ですよ?」
「はぁ……」
逆に深刻な理由じゃなくて良かったと思ってしまうくらい脱力した。
「都井さんはどうしてカメラマンになったんですか?」
「俺は……元々叔父がスタジオやってて、それを継いだ感じ……」
「でも、好きじゃないと継ごうとは思わないですよね? 写真撮るの好きだったんですか?」
「まぁ、そこそこ……」
情熱を語るのが恥ずかしくて逃げる。
ナナトは何かを察した顔をすると、話題を別に移した。
「それにしても、ヒロムさん遅いですね~」
「いや、俺的には別に来てもらわなくてもいいんだけど」
客が来ているなら売り上げに繋がらない俺より、客に時間を使った方が有意義だと思う。
「え? ヒロムさんの接客ですよ? 勿体無いですよ!」
「勿体無いって……」
「オレだって間近でヒロムさんの接客見て勉強できるって楽しみにしてるのに、そんなこと言わないでくださいよ~」
ナナトの情けない声と表情に思わず噴き出す。
「ちょっとオレ、偵察してきます!」
「え、そこまでしなくても……」
立ち上がろうとするナナトを引き留め、席に座らせ、短く息を吐く。
「忙しいのに、邪魔したくないんだよ」
「都井さん……」
ナナトが残念そうな顔で俺を見たが、すぐに驚いたような顔に変わる。
「オーナー!」
「え?」
ナナトの視線の先に目を向けると江草さんが穏やかな笑顔で立っていた。
「こんばんは」
「あ、こんばんは! お誘いありがとうございます」
まさか江草さんも来てくれるとは思わず、声が上ずる。
江草さんは俺たちのテーブルの上を一瞥すると、勢いよく立ちあがったナナトに声を掛けた。
「ナナト、フードはどうした?」
「あ、あー! 忘れてました……」
そういえば、苦手な食べ物を聞かれたのにテーブルの上にはビールしか無かった。
「すぐに持ってきます!」
「ほら、慌てると危ない……、今日は永野さんが来る日だからお願いして何か作ってもらってきて」
「そうか! 永野さんの日か! 分かりました!」
慌てると危ない、と注意されたのにも関わらず、ナナトは慌てて店の奥に消えていった。
「あの、永野さんっていうのは……?」
「あぁ、私が経営しているホストクラブのシェフをしてくれている方でね。色んなホテルの料理長を務めていたくらい腕がいいんだよ」
「シェフ……」
ホストクラブにシェフがいることを初めて知った俺は驚きと共に思わず声が漏れた。
「そんなことで驚いて貰えるなんて、招待した甲斐があるよ」
気持ちの良い声で笑われてしまい恥ずかしくなる。
「さ、遠慮しないでどんどん飲んで! って言っても今はビールしか無いのか……。ナナトが戻ってきたらシャンパン持ってこさせるよ」
「いえ、そんなお気遣いなく……」
ビールの値段はたかが知れていると想像つくが、シャンパンの値段は、想像もつかない。もし高価なものを振舞われてしまったら頭が上がらなくなってしまう。
「都井くんは謙虚だね。でも相手からの好意を仕事に繋げることも重要だと思わない?」
「え……?」
そう、囁いた江草さんは俺の隣に腰を下ろした。
知り合いと言うには近い位置で。
「その点、ヒロムは素直で可愛いよ」
まるで、惚気を聞かされているような気分になったが、江草さんの俺を見つめる瞳はどこか鋭い。
捕って食べられてしまいそうな雰囲気に息を飲む。
何か、言葉に出来ない違和感を感じると、江草さんの顔はいつもの柔和なものに戻った。
ホッとしたのもつかの間、突然割って入った声に飛び上がりそうになる。
「心広くん!」
「ヒロム……?」
焦ったような顔をして現れた苗加は、まるでそうするのが当たり前かのように、すぐに江草さんの隣にぴったりと付いて座った。
今まで見た中で一番”ホストみたいな”恰好をした苗加の首には細いチェーンのネックレスが光っていた。
「オーナー、客席に入る時は声をかけてください」
「そうは言っても、ヒロムは接客中だったじゃないか」
「でも……」
「そんなに、私が都井くんと話すのが嫌だった?」
「それは、……はい……」
「本当に可愛いなぁヒロムは」
事情を知っている俺の前だからなのか、それともこれが通常運転なのかは分からないが、とにかく空気甘い。いくら一度見ているとはいえ正直きつい。
前回神社で二人に会った時のモヤモヤ感が再び蘇ってくる。
目の前でこれを繰り広げられている状態では、どんなに美味しい料理を食べたとしてもまずく感じるだろう。
そのくらい、二人の間の空気は”遠慮がない”。
「そういえば、都井くんの名前はミヒロっていうんだね?」
「え、あ、はい。心が広いって書いて心広です」
急に話を振られ、言わなくて良いことまで喋ってしまった。
どうせ苗加が知っているのだから、江草さんにばれるのも時間の問題かと思い、無理矢理諦めた。
「心広くんか……良い名前だね」
「……ありがとうございます」
俺が江草さんと話している間、苗加は一度も俺のことを見ようとはしなかった。
あまりにも不自然な視線の逸らし方に首を捻り、一つの結論に思い当たる。
…………もしかして嫉妬されてる……?
江草さんが俺にばかり構うから、苗加は良い気がしないんじゃないか、そう考えたら苗加の行動の意味も理解できる。
人の恋愛ごとに巻き込まれるなんてごめんだ、と背中に冷たい汗が流れる。
「あ! 俺! トイレ行ってきます!」
大きい声でトイレ宣言してしまった恥ずかしさよりも早くここを立ち去りたい一心で立ち上がる。
「じゃあおれが案内して……」
「いや、いい! なんとなく分かる!」
付いてこようとする苗加をその場に残し、俺は足早にテーブルを離れた。
1
あなたにおすすめの小説

【完結済】あの日、王子の隣を去った俺は、いまもあなたを想っている
キノア9g
BL
かつて、誰よりも大切だった人と別れた――それが、すべての始まりだった。
今はただ、冒険者として任務をこなす日々。けれどある日、思いがけず「彼」と再び顔を合わせることになる。
魔法と剣が支配するリオセルト大陸。
平和を取り戻しつつあるこの世界で、心に火種を抱えたふたりが、交差する。
過去を捨てたはずの男と、捨てきれなかった男。
すれ違った時間の中に、まだ消えていない想いがある。
――これは、「終わったはずの恋」に、もう一度立ち向かう物語。
切なくも温かい、“再会”から始まるファンタジーBL。
全8話
お題『復縁/元恋人と3年後に再会/主人公は冒険者/身を引いた形』設定担当AI /c

「自由に生きていい」と言われたので冒険者になりましたが、なぜか旦那様が激怒して連れ戻しに来ました。
キノア9g
BL
「君に義務は求めない」=ニート生活推奨!? ポジティブ転生者と、言葉足らずで愛が重い氷の伯爵様の、全力すれ違い新婚ラブコメディ!
あらすじ
「君に求める義務はない。屋敷で自由に過ごしていい」
貧乏男爵家の次男・ルシアン(前世は男子高校生)は、政略結婚した若き天才当主・オルドリンからそう告げられた。
冷徹で無表情な旦那様の言葉を、「俺に興味がないんだな! ラッキー、衣食住保証付きのニート生活だ!」とポジティブに解釈したルシアン。
彼はこっそり屋敷を抜け出し、偽名を使って憧れの冒険者ライフを満喫し始める。
「旦那様は俺に無関心」
そう信じて、半年間ものんきに遊び回っていたルシアンだったが、ある日クエスト中に怪我をしてしまう。
バレたら怒られるかな……とビクビクしていた彼の元に現れたのは、顔面蒼白で息を切らした旦那様で――!?
「君が怪我をしたと聞いて、気が狂いそうだった……!」
怒鳴られるかと思いきや、折れるほど強く抱きしめられて困惑。
えっ、放置してたんじゃなかったの? なんでそんなに必死なの?
実は旦那様は冷徹なのではなく、ルシアンが好きすぎて「嫌われないように」と身を引いていただけの、超・奥手な心配性スパダリだった!
「君を守れるなら、森ごと消し飛ばすが?」
「過保護すぎて冒険になりません!!」
Fランク冒険者ののんきな妻(夫)×国宝級魔法使いの激重旦那様。
すれ違っていた二人が、甘々な「週末冒険者夫婦」になるまでの、勘違いと溺愛のハッピーエンドBL。


異世界にやってきたら氷の宰相様が毎日お手製の弁当を持たせてくれる
七瀬京
BL
異世界に召喚された大学生ルイは、この世界を救う「巫覡」として、力を失った宝珠を癒やす役目を与えられる。
だが、異界の食べ物を受けつけない身体に苦しみ、倒れてしまう。
そんな彼を救ったのは、“氷の宰相”と呼ばれる美貌の男・ルースア。
唯一ルイが食べられるのは、彼の手で作られた料理だけ――。
優しさに触れるたび、ルイの胸に芽生える感情は“感謝”か、それとも“恋”か。
穏やかな日々の中で、ふたりの距離は静かに溶け合っていく。
――心と身体を癒やす、年の差主従ファンタジーBL。
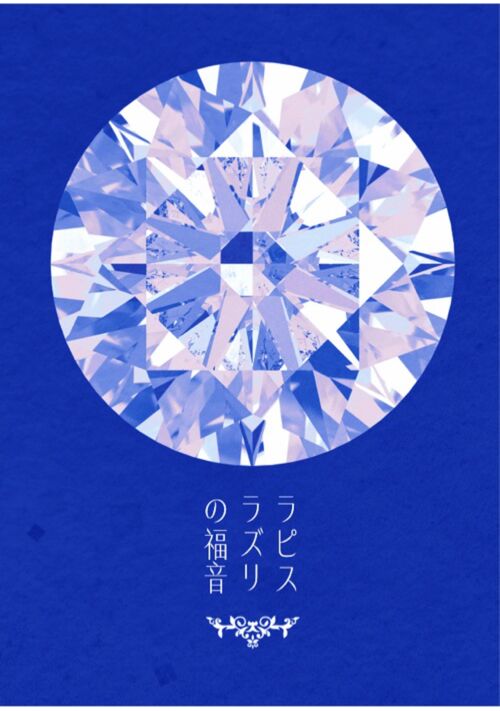
ラピスラズリの福音
東雲
BL
*異世界ファンタジーBL*
特別な世界観も特殊な設定もありません。壮大な何かもありません。
幼馴染みの二人が遠回りをしながら、相思相愛の果てに結ばれるお話です。
金髪碧眼美形攻め×純朴一途筋肉受け
息をするように体の大きい子受けです。
珍しく年齢制限のないお話ですが、いつもの如く己の『好き』と性癖をたんと詰め込みました!

俺の居場所を探して
夜野
BL
小林響也は炎天下の中辿り着き、自宅のドアを開けた瞬間眩しい光に包まれお約束的に異世界にたどり着いてしまう。
そこには怪しい人達と自分と犬猿の仲の弟の姿があった。
そこで弟は聖女、自分は弟の付き人と決められ、、、
このお話しは響也と弟が対立し、こじれて決別してそれぞれお互い的に幸せを探す話しです。
シリアスで暗めなので読み手を選ぶかもしれません。
遅筆なので不定期に投稿します。
初投稿です。

婚約破棄された令息の華麗なる逆転劇 ~偽りの番に捨てられたΩは、氷血公爵に愛される~
なの
BL
希少な治癒能力と、大地に生命を呼び戻す「恵みの魔法」を持つ公爵家のΩ令息、エリアス・フォン・ラティス。
傾きかけた家を救うため、彼は大国アルビオンの第二王子、ジークフリート殿下(α)との「政略的な番契約」を受け入れた。
家のため、領民のため、そして――
少しでも自分を必要としてくれる人がいるのなら、それでいいと信じて。
だが、運命の番だと信じていた相手は、彼の想いを最初から踏みにじっていた。
「Ωの魔力さえ手に入れば、あんな奴はもう要らない」
その冷たい声が、彼の世界を壊した。
すべてを失い、偽りの罪を着せられ追放されたエリアスがたどり着いたのは、隣国ルミナスの地。
そこで出会ったのは、「氷血公爵」と呼ばれる孤高のα、アレクシス・ヴァン・レイヴンだった。
人を寄せつけないほど冷ややかな瞳の奥に、誰よりも深い孤独を抱えた男。
アレクシスは、心に傷を抱えながらも懸命に生きようとするエリアスに惹かれ、次第にその凍てついた心を溶かしていく。
失われた誇りを取り戻すため、そして真実の愛を掴むため。
今、令息の華麗なる逆転劇が始まる。

執着
紅林
BL
聖緋帝国の華族、瀬川凛は引っ込み思案で特に目立つこともない平凡な伯爵家の三男坊。だが、彼の婚約者は違った。帝室の血を引く高貴な公爵家の生まれであり帝国陸軍の将校として目覚しい活躍をしている男だった。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















