2 / 4
2話
しおりを挟む
(和也視点)
俺は記憶を失っているらしい。
たまに、そのことが無性に怖くなる。自分の根っこがちぎれてしまって、どこかに吹き飛ばされるんじゃあないかという恐怖だ。
俺は記憶を取り戻そうと、怪しげな民間療法を含めて必死にいろいろなことをしたが、どれも効果はなかった。記憶を失う前の俺が快活な性格で、美術が好きで、勉強はそこそこ、ということは友達や家族から聞いてわかったが、その情報が俺の記憶を呼び覚ますことはなかった。
ただ、ナポレオンの絵画のキーホルダーなど身の回りに美術に関連したものが多く残っていて、それらを見て絵の名前を言い当てることはできた。
部屋を整理していたら、昔俺が描いたのだという絵がいっぱい出てきた。スケッチブックだけで段ボールひと箱分もあるそれを、俺は一枚一枚ゆっくりと眺めた。
「あれ、これ」
途中、俺はあることに気が付いた。
「諒さん?」
昔の俺は特定の人物——諒さんばかり描いていた。
諒さんは病院に一度お見舞いに来てくれた人だ。中学、高校、大学と同じの同級生なのだと家族から聞いた。
高校生時代のアルバムをめくると、いつも彼が隣にいた。そうであるなら、俺が友達を描いていても不思議ではない。しかし。
「きれいだな」
友達に頼んでデッサンをしたというには、あまりにも、その絵は美しかった。諒さんを美しく描く、という強い意志を持って描いたように見えた。
まつ毛、首の角度、それから髪の毛。
他のデッサンにはない、匂い立つような、魅力のある絵だった。
俺はすとん、と理解した。
「ああ、俺、諒さんのこと好きだったのかも」
それなら、この絵も納得だ。俺は諒さんを描いたスケッチブックを段ボールから出して、毎晩眺めた。
彼への気持ちを思い出せたことがうれしかった。スケッチブックの裏には『竹中教室』と書かれていた。
諒さんはどんな人なんだろうか。
俺はスマホのデータを探した。諒さんの写真はたくさん保存されていた。一番古いものは中学生らしい制服を着た諒さんで、最新の写真は隠し撮りのような諒さんだ。しかし、2人のメッセージはなかった。母親に聞いてみると、毎日電話していたはずだと言われた。しかし、電話番号は登録されていない。
今度諒さんに聞いてみたいと思ったが、何を理由に訪ねていけばいいのかわからない。
母親は親友なんだから、理由なんていらないでしょ、と無責任なことを言うが、諒さんは病院で一度会っただけで、いまの俺からしたら知り合い以下といってもいいくらいだ。
悩む俺に、母親は少女趣味な紙袋にじゃがいもを詰めて、もっていけ、と命令した。
*
諒さんが電話をするためにリビングを出たあと、俺はぼんやりと諒さんの部屋を眺めた。生活感のない部屋で、さっき諒さんが脱ぎ捨てたコートとマフラー、それからダッシュボードの上に置かれた鍵だけが唯一人の住んでいる気配を感じさせた。
鍵にはナポレオン絵画を模したキーホルダーのようなものが付いている。廊下にも絵が飾られていた。諒さんが中学高校と俺と同じ美術部に入っていたというから、彼もやはり絵が好きなんだろうか。
そんなことも、俺は知らない。
母親が言うには、ここに俺は入り浸っていたそうだが、なにを見ても、記憶が戻ることはない。それに、諒さんの対応も不思議だ。
親友だった、とまわりの人間は言うが、諒さんの反応は「知り合い」といったところだろうか。
俺はまわりから聞く「諒さんと俺」と、俺が見た「諒さんと俺」のあまりの違いに戸惑う。
何か、何かあるのだろう。
記憶がなくなる前の俺と、諒さんには、ふたりにしかわからない何かがあったんだ。
そして、それを知るのが怖い。
「俺、諒さんのストーカーだったのかなぁ」
俺の気持ちが一方通行で、諒さんは迷惑に思っていたのかもしれない。
それを思い出してしまうのが怖い。
俺はぐっとコーヒーを飲みほした。苦いその飲み物のことは好きではない。しかし、諒さんが勧めてくるのだから、記憶を無くす前の俺は好きだったのかもしれない。
なにもかも憶測だ。俺は憶測でしか俺がわからない。
ゆっくりと立ち上がった。この部屋にもういてはいけないと思った。
「諒さん、ごめんなさい、帰ります。コーヒーごちそうさまでした」
リビングのドアをあけると、廊下で立ち尽くしている諒さんと目が合った。
「どうしました?」
諒さんはこちらを見て、それから廊下に飾ってある絵を一枚指さした。
「この絵、どう思う?」
「……」
それは、大胆な緑を配色した絵だった。緑と、茶色、あとは白。ガラスの額縁に入れられている。
「木の抽象画ですか?」
俺の答えに、諒さんは苦笑した。
「はずれ」
諒さんは僕の肩を叩いた。
「和也」
初めて名前を呼ばれて、俺はどきりとした。
「バイバイ。気を付けて帰るんだよ」
諒さんは、そう言ってなにか吹っ切れたような笑顔で僕を見送ってくれた。
*
何か、俺は大きな間違いをしたのかもしれない。俺は帰り道、諒さんのことばかり考えていた。
脳裏には諒さんの別れ際の笑顔がこびりついていた。たぶん、これはやはり推測なのだが、おそらく、諒さんはああいう風に笑う人ではないのだと思う。
スケッチブックの中の諒さんは、もっと憂いを帯びた、それでいて慈愛に満ちた笑みを浮かべている。
彼に何かあったのだろうが、それが何なのか、俺にはわからない。
わからないなら、もう諒さんの人生から、俺は退場した方がいいのかもしれない。
俺はふらふらと歩いた。この町の道はもうある程度覚えていた。通った小学校、中学校、高校。俺の記憶のピースが落ちているんではないかと、家族が俺を連れ歩いてくれたからだ。
俺は最初は家に戻るつもりだったのだが、なんとなく、そんな気になれなくて、頭の中の諒さんの笑顔を忘れるためにめちゃくちゃに歩いた。闇雲に、そのうち意識的に歩いて歩いて、俺は俺の面影を探した。
ねえ、本当の俺がここにいたとしたら、あんな笑顔を浮かべる諒さんになんて声をかけた?
もちろん、返答はない。
雪はどんどん大粒になっていく。
白く町が覆われて、まるで俺の頭の中みたいだと思った。何もない、真っ白な頭。
ふと、足が止まった。交差点の雑居ビルの2階の看板に目が留まる。『竹中教室』とあった。あのスケッチブックの裏に書いてあった四文字に、俺は吸い寄せられた。
時刻はすでに21時になろうとしている。それでも、その教室からは蛍光灯の光が漏れていた。2階へ続く階段は薄暗い。
ドアノブにゆっくりと手をかけて、ドアを開けると、そこにはモデルを中心にずらりと生徒が円形に並び、絵を描いていた。狭い教室に、イーゼルとキャンパスと彫刻と絵画と生徒が詰め込まれている。俺はその光景に圧倒されて、そして中心に一心不乱に動く筆の音に飲まれた。生徒は誰一人こちらを振りむかない。誰もがキャンパスの中の世界に没頭していた。
「どうしました?」
声を掛けてきてくれたのは高齢の男性だった。年季の入った前掛けは絵の具で汚れている。この教室の先生だと思った。
「あ、あの、俺」
何か言わなければ、と思ったが、不審すぎる自分の状況にふさわしい説明が出てこない。
「あれ、和也くん」
「え……」
「記憶喪失になったって聞いたけど、もうよくなったのかね?」
老人は低く、生徒たちの集中を乱さないように、小さな声で話した。
「あ……えっと、あの……」
老人は俺の戸惑い、驚いている顔を見ると、ふむ、と顎を一度掻いて、それから俺の背中を押した。
「おいで。君の特等席が空いているよ」
老人は俺を窓辺の席に座らせて、説明した。
「君はここの生徒だったんだよ。ずっとね。そしてここは君の特等席だ。……おかえり、和也くん」
「……」
その席は、驚くほど自分に馴染んだ。
「親は、ここには連れてきてくれませんでした」
俺が言うと、老人は笑った。
「はは、内緒で通っていたんだよ。高校一年生の時かな? 絵を描く暇があるなら勉強しろと言われて辞めたのさ。それでも納得できない君はこっそりバイトをして、それでこっそり通ってくれていた。私と、君と、諒くんだけの秘密さ」
「……俺、悪い奴だったんですね」
「芸術を愛する、素晴らしい青年だ。どうだ、描いてみるかね? 好きなものをモチーフにして」
「でも……」
「教室の中に、好きなものはないかな?」
言われて、思わず教室を見渡す。そして、俺ははたと気が付いた。白いカーテンと、茶色い壁、窓向こうの緑。
喉が渇く。目がぐるぐるして、汗が噴き出た。
「俺、この教室の風景を抽象画にしたことありますか……」
「ああ、何度もね」
俺は顔を覆った。
俺は記憶を失っているらしい。
たまに、そのことが無性に怖くなる。自分の根っこがちぎれてしまって、どこかに吹き飛ばされるんじゃあないかという恐怖だ。
俺は記憶を取り戻そうと、怪しげな民間療法を含めて必死にいろいろなことをしたが、どれも効果はなかった。記憶を失う前の俺が快活な性格で、美術が好きで、勉強はそこそこ、ということは友達や家族から聞いてわかったが、その情報が俺の記憶を呼び覚ますことはなかった。
ただ、ナポレオンの絵画のキーホルダーなど身の回りに美術に関連したものが多く残っていて、それらを見て絵の名前を言い当てることはできた。
部屋を整理していたら、昔俺が描いたのだという絵がいっぱい出てきた。スケッチブックだけで段ボールひと箱分もあるそれを、俺は一枚一枚ゆっくりと眺めた。
「あれ、これ」
途中、俺はあることに気が付いた。
「諒さん?」
昔の俺は特定の人物——諒さんばかり描いていた。
諒さんは病院に一度お見舞いに来てくれた人だ。中学、高校、大学と同じの同級生なのだと家族から聞いた。
高校生時代のアルバムをめくると、いつも彼が隣にいた。そうであるなら、俺が友達を描いていても不思議ではない。しかし。
「きれいだな」
友達に頼んでデッサンをしたというには、あまりにも、その絵は美しかった。諒さんを美しく描く、という強い意志を持って描いたように見えた。
まつ毛、首の角度、それから髪の毛。
他のデッサンにはない、匂い立つような、魅力のある絵だった。
俺はすとん、と理解した。
「ああ、俺、諒さんのこと好きだったのかも」
それなら、この絵も納得だ。俺は諒さんを描いたスケッチブックを段ボールから出して、毎晩眺めた。
彼への気持ちを思い出せたことがうれしかった。スケッチブックの裏には『竹中教室』と書かれていた。
諒さんはどんな人なんだろうか。
俺はスマホのデータを探した。諒さんの写真はたくさん保存されていた。一番古いものは中学生らしい制服を着た諒さんで、最新の写真は隠し撮りのような諒さんだ。しかし、2人のメッセージはなかった。母親に聞いてみると、毎日電話していたはずだと言われた。しかし、電話番号は登録されていない。
今度諒さんに聞いてみたいと思ったが、何を理由に訪ねていけばいいのかわからない。
母親は親友なんだから、理由なんていらないでしょ、と無責任なことを言うが、諒さんは病院で一度会っただけで、いまの俺からしたら知り合い以下といってもいいくらいだ。
悩む俺に、母親は少女趣味な紙袋にじゃがいもを詰めて、もっていけ、と命令した。
*
諒さんが電話をするためにリビングを出たあと、俺はぼんやりと諒さんの部屋を眺めた。生活感のない部屋で、さっき諒さんが脱ぎ捨てたコートとマフラー、それからダッシュボードの上に置かれた鍵だけが唯一人の住んでいる気配を感じさせた。
鍵にはナポレオン絵画を模したキーホルダーのようなものが付いている。廊下にも絵が飾られていた。諒さんが中学高校と俺と同じ美術部に入っていたというから、彼もやはり絵が好きなんだろうか。
そんなことも、俺は知らない。
母親が言うには、ここに俺は入り浸っていたそうだが、なにを見ても、記憶が戻ることはない。それに、諒さんの対応も不思議だ。
親友だった、とまわりの人間は言うが、諒さんの反応は「知り合い」といったところだろうか。
俺はまわりから聞く「諒さんと俺」と、俺が見た「諒さんと俺」のあまりの違いに戸惑う。
何か、何かあるのだろう。
記憶がなくなる前の俺と、諒さんには、ふたりにしかわからない何かがあったんだ。
そして、それを知るのが怖い。
「俺、諒さんのストーカーだったのかなぁ」
俺の気持ちが一方通行で、諒さんは迷惑に思っていたのかもしれない。
それを思い出してしまうのが怖い。
俺はぐっとコーヒーを飲みほした。苦いその飲み物のことは好きではない。しかし、諒さんが勧めてくるのだから、記憶を無くす前の俺は好きだったのかもしれない。
なにもかも憶測だ。俺は憶測でしか俺がわからない。
ゆっくりと立ち上がった。この部屋にもういてはいけないと思った。
「諒さん、ごめんなさい、帰ります。コーヒーごちそうさまでした」
リビングのドアをあけると、廊下で立ち尽くしている諒さんと目が合った。
「どうしました?」
諒さんはこちらを見て、それから廊下に飾ってある絵を一枚指さした。
「この絵、どう思う?」
「……」
それは、大胆な緑を配色した絵だった。緑と、茶色、あとは白。ガラスの額縁に入れられている。
「木の抽象画ですか?」
俺の答えに、諒さんは苦笑した。
「はずれ」
諒さんは僕の肩を叩いた。
「和也」
初めて名前を呼ばれて、俺はどきりとした。
「バイバイ。気を付けて帰るんだよ」
諒さんは、そう言ってなにか吹っ切れたような笑顔で僕を見送ってくれた。
*
何か、俺は大きな間違いをしたのかもしれない。俺は帰り道、諒さんのことばかり考えていた。
脳裏には諒さんの別れ際の笑顔がこびりついていた。たぶん、これはやはり推測なのだが、おそらく、諒さんはああいう風に笑う人ではないのだと思う。
スケッチブックの中の諒さんは、もっと憂いを帯びた、それでいて慈愛に満ちた笑みを浮かべている。
彼に何かあったのだろうが、それが何なのか、俺にはわからない。
わからないなら、もう諒さんの人生から、俺は退場した方がいいのかもしれない。
俺はふらふらと歩いた。この町の道はもうある程度覚えていた。通った小学校、中学校、高校。俺の記憶のピースが落ちているんではないかと、家族が俺を連れ歩いてくれたからだ。
俺は最初は家に戻るつもりだったのだが、なんとなく、そんな気になれなくて、頭の中の諒さんの笑顔を忘れるためにめちゃくちゃに歩いた。闇雲に、そのうち意識的に歩いて歩いて、俺は俺の面影を探した。
ねえ、本当の俺がここにいたとしたら、あんな笑顔を浮かべる諒さんになんて声をかけた?
もちろん、返答はない。
雪はどんどん大粒になっていく。
白く町が覆われて、まるで俺の頭の中みたいだと思った。何もない、真っ白な頭。
ふと、足が止まった。交差点の雑居ビルの2階の看板に目が留まる。『竹中教室』とあった。あのスケッチブックの裏に書いてあった四文字に、俺は吸い寄せられた。
時刻はすでに21時になろうとしている。それでも、その教室からは蛍光灯の光が漏れていた。2階へ続く階段は薄暗い。
ドアノブにゆっくりと手をかけて、ドアを開けると、そこにはモデルを中心にずらりと生徒が円形に並び、絵を描いていた。狭い教室に、イーゼルとキャンパスと彫刻と絵画と生徒が詰め込まれている。俺はその光景に圧倒されて、そして中心に一心不乱に動く筆の音に飲まれた。生徒は誰一人こちらを振りむかない。誰もがキャンパスの中の世界に没頭していた。
「どうしました?」
声を掛けてきてくれたのは高齢の男性だった。年季の入った前掛けは絵の具で汚れている。この教室の先生だと思った。
「あ、あの、俺」
何か言わなければ、と思ったが、不審すぎる自分の状況にふさわしい説明が出てこない。
「あれ、和也くん」
「え……」
「記憶喪失になったって聞いたけど、もうよくなったのかね?」
老人は低く、生徒たちの集中を乱さないように、小さな声で話した。
「あ……えっと、あの……」
老人は俺の戸惑い、驚いている顔を見ると、ふむ、と顎を一度掻いて、それから俺の背中を押した。
「おいで。君の特等席が空いているよ」
老人は俺を窓辺の席に座らせて、説明した。
「君はここの生徒だったんだよ。ずっとね。そしてここは君の特等席だ。……おかえり、和也くん」
「……」
その席は、驚くほど自分に馴染んだ。
「親は、ここには連れてきてくれませんでした」
俺が言うと、老人は笑った。
「はは、内緒で通っていたんだよ。高校一年生の時かな? 絵を描く暇があるなら勉強しろと言われて辞めたのさ。それでも納得できない君はこっそりバイトをして、それでこっそり通ってくれていた。私と、君と、諒くんだけの秘密さ」
「……俺、悪い奴だったんですね」
「芸術を愛する、素晴らしい青年だ。どうだ、描いてみるかね? 好きなものをモチーフにして」
「でも……」
「教室の中に、好きなものはないかな?」
言われて、思わず教室を見渡す。そして、俺ははたと気が付いた。白いカーテンと、茶色い壁、窓向こうの緑。
喉が渇く。目がぐるぐるして、汗が噴き出た。
「俺、この教室の風景を抽象画にしたことありますか……」
「ああ、何度もね」
俺は顔を覆った。
13
あなたにおすすめの小説

酔った俺は、美味しく頂かれてました
雪紫
BL
片思いの相手に、酔ったフリして色々聞き出す筈が、何故かキスされて……?
両片思い(?)の男子大学生達の夜。
2話完結の短編です。
長いので2話にわけました。
他サイトにも掲載しています。

記憶喪失になったら弟の恋人になった
天霧 ロウ
BL
ギウリは種違いの弟であるトラドのことが性的に好きだ。そして酔ったフリの勢いでトラドにキスをしてしまった。とっさにごまかしたものの気まずい雰囲気になり、それ以来、ギウリはトラドを避けるような生活をしていた。
そんなある日、酒を飲んだ帰りに路地裏で老婆から「忘れたい記憶を消せる薬を売るよ」と言われる。半信半疑で買ったギウリは家に帰るとその薬を飲み干し意識を失った。
そして目覚めたときには自分の名前以外なにも覚えていなかった。
見覚えのない場所に戸惑っていれば、トラドが訪れた末に「俺たちは兄弟だけど、恋人なの忘れたのか?」と寂しそうに告げてきたのだった。
トラド×ギウリ
(ファンタジー/弟×兄/魔物×半魔/ブラコン×鈍感/両片思い/溺愛/人外/記憶喪失/カントボーイ/ハッピーエンド/お人好し受/甘々/腹黒攻/美形×地味)
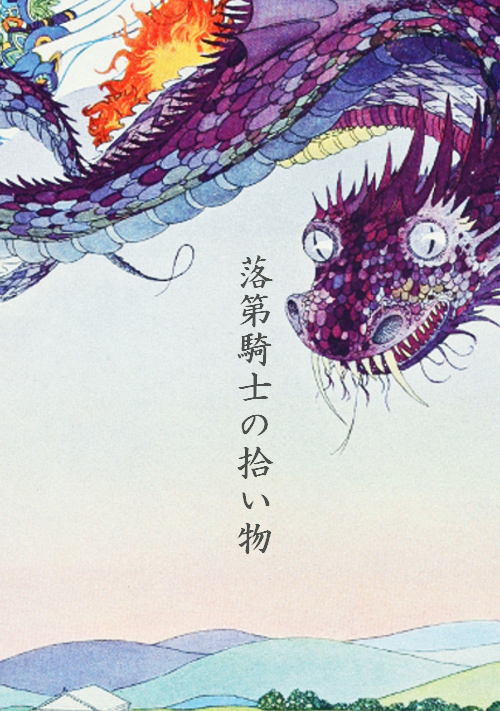
落第騎士の拾い物
深山恐竜
BL
「オメガでございます」
ひと月前、セレガは医者から第三の性別を告知された。将来は勇猛な騎士になることを夢見ていたセレガは、この診断に絶望した。
セレガは絶望の末に”ドラゴンの巣”へ向かう。そこで彼は騎士見習いとして最期の戦いをするつもりであった。しかし、巣にはドラゴンに育てられたという男がいた。男は純粋で、無垢で、彼と交流するうちに、セレガは未来への希望を取り戻す。
ところがある日、発情したセレガは男と関係を持ってしまって……?
オメガバースの設定をお借りしています。
ムーンライトノベルズにも掲載中

記憶の代償
槇村焔
BL
「あんたの乱れた姿がみたい」
ーダウト。
彼はとても、俺に似ている。だから、真実の言葉なんて口にできない。
そうわかっていたのに、俺は彼に抱かれてしまった。
だから、記憶がなくなったのは、その代償かもしれない。
昔書いていた記憶の代償の完結・リメイクバージョンです。
いつか完結させねばと思い、今回執筆しました。
こちらの作品は2020年BLOVEコンテストに応募した作品です

ド天然アルファの執着はちょっとおかしい
のは(山端のは)
BL
一嶌はそれまで、オメガに興味が持てなかった。彼らには托卵の習慣があり、いつでも男を探しているからだ。だが澄也と名乗るオメガに出会い一嶌は恋に落ちた。その瞬間から一嶌の暴走が始まる。
【アルファ→なんかエリート。ベータ→一般人。オメガ→男女問わず子供産む(この世界では産卵)くらいのゆるいオメガバースなので優しい気持ちで読んでください】
※ムーンライトノベルズにも掲載しております

恋の仇花
小貝川リン子
BL
曜介と真尋は幼少期からの幼馴染で、喧嘩も多いが互いに淡い恋心を抱いていた。しかし小学五年生の夏、真尋が担任教師に暴行されたことを切っ掛けに、二人の関係性は決定的に変わってしまう。
互いが互いを思っているのに、二人を隔てる溝は一層深くなり、心の距離さえ遠のいていく。それは高校生になった今でも変わらない。いつかまた、あいつの手を取ることができるのだろうか。
幼少期の回想を挟みつつ、高校時代の青春と葛藤、大人になり結ばれるまでの話が第一部。結ばれて以降の熱々で甘々な日常を第二部で描きます。
曜介(ようすけ):主人公。真尋に冷たい態度を取られているが、ずっと大切に思っている。
真尋(まひろ):ヒロイン。過去のトラウマにより性に関して無節操。様々な相手と肉体関係を持つ。
京太郎(きょうたろう):もう一人の幼馴染。曜介・真尋の親友であり続ける。

魔性の男は純愛がしたい
ふじの
BL
子爵家の私生児であるマクシミリアンは、その美貌と言動から魔性の男と呼ばれていた。しかし本人自体は至って真面目なつもりであり、純愛主義の男である。そんなある日、第三王子殿下のアレクセイから突然呼び出され、とある令嬢からの執拗なアプローチを避けるため、自分と偽装の恋人になって欲しいと言われ─────。
アルファポリス先行公開(のちに改訂版をムーンライトノベルズにも掲載予定)

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















