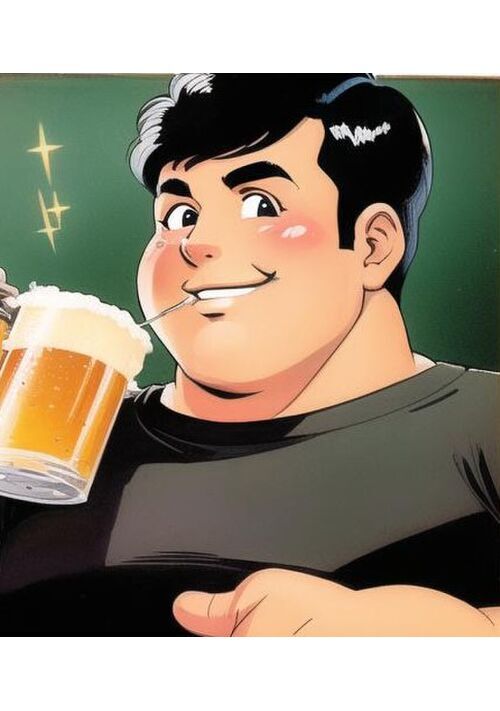92 / 134
第二部
91 リボン
しおりを挟む
記憶喪失少年アーネスト君が来てから早五日。
さすがに夜遅くなる酒場の給仕はザックも許可しなかったから、件の彼は大人しく部屋で先に寝ている。
ぐっすり眠ってその分元気溌剌~って感じで昼間は張り切って動いてるわ。
この日も、肩に着くさらさらの金髪が揺れていて、目には鮮やかだ。
「アーニー、向こうのお客さんにこの料理持っていって!」
「はい!」
「アーニー、そっちのテーブルのお皿下げるのお願いね。私はこっちを片付けるから」
「はい!」
とまあこんな感じで一緒に動いてるわ。
「アーニー、ちょっと休憩にしましょ」
「え、でも……まだお昼の忙しい時間ですし……」
「あなたにちょっと用事があるの」
ホールは奇跡の皿ジェンガを披露して給仕するマルスに少し任せて、私は小さな同僚を一旦店の奥へと連れて行った。
因みに呼び方についてだけど、アーネストって呼び方が正直嫌だった私は、愛称のアーニーって呼ぶようにしたのよね。
その方が呼びやすいし、あのわっるい奴を連想しなくて済むもの。
彼の方も別に嫌がったりしなかったから確定だった。
今ではマルスもザックも私に倣ってアーニー呼びになっている。
王都警備隊の方からは、まだ彼の保護者が現れたって連絡はない。
一週間も経っていないから、もう少し気長に待ってみようってマルスとザックとは言っていた。
だけど、こんな小さい子の捜索願も出されていないなんて、もしかして王都やその近隣の子じゃないのかしら。どこか遠くから連れて来られていたとしたら、仮に捜索願が出ていたとしても王都警備隊の管轄外だから、その地域に問い合わせないとわからない。
けどねえ、日中街で見かける警備隊の方でも先の事件に加えて別にまた吸血事件が起きたってわけで、今は細かく問い合わせている暇はなさそうだった。
それにこっちもただ任せているだけってのも嫌だったから、出来る範囲で調べてはいた。
彼が身に付けていたブカブカの男性服はどう見ても高級な物だったから、きっと良い所の出なんだろうって密かにマルスとは推測を立てて、上流家庭にアーネストって名前の息子のいる家はないかって訊いて回ってみたりもした。まあこっちも今の所進展はなしだけど……。
一番不安だろうアーニーは弱音を一切吐かない。
私が彼くらいの年で同じような立場に置かれたら、どうしたらいいのうわーんって泣き通しだったかもしれないわ。
「ちょっとここで待っててね」
「は、はい」
店の奥の適当な場所に一人残されたアーニーは、戸惑ったように私を見ていた。
私が彼に何の用かって?
うふふそれはね、一生懸命お手伝いはいいんだけど、ここは曲がりなりにも食べ物を扱っている所だし、彼の髪の毛がそのままだとバサバサして衛生上ちょっと……と見兼ねたのよね。それで昨日ある物を買ってきた。
なるべく急いで戻ると、ちゃんと待っていた彼へと後ろを向くように促した。
「え……ええと……」
彼は躊躇を見せた。
あらら緊張しちゃってまあ。
何となく、自分からは良いけど他者から触られるのは駄目なんだろうなって思う。
それでも日本の衛生管理の下で育った私としてはこのままにはできないってわけで、例え嫌われてもいいやと腹を括った。
「ほらほら後ろ向いてってば」
両肩を掴んでぐいぐい押して強制回れ右をさせると、さらりとした髪に指を梳き込んだ。
「え? え? リズお姉さん? あの!?」
「ちょっとじっとして」
アーニーが目を白黒させているのが顔を見なくてもわかった。
硬直して動かないのをいい事に、私はさっさと手を動かす。
「ハイ出来上がり」
「……え?」
肩に掛かっていた髪の毛がなくなって、彼はちょっとビックリしたように振り返った。
頭に手をやって、自身の頭髪が後ろで一括りにされているのがわかって余計に戸惑った顔になる。しかも指先が結んだ部分を触って解けてしまった。
両肩にぱさりと毛先が落ちて元通りだったけど、彼はその手に一本の黒いリボンを握っている。
両端にレースのあしらわれた男の子が付けるには些か可愛過ぎる装飾品だけど、彼なら全然大丈夫って太鼓判を押すわ。
「リズお姉さん、あの、これ……?」
「見ての通り、リボンよ。私の好みで買っちゃったけどアーニーにあげる。仕事中は髪の毛をそれで結んでおくのよ。ほら私だって後ろ髪はきちんと束ねてるでしょ? お皿を運ぶ時に髪の毛が邪魔だろうし、それにね、お客さんのお料理に入ったら大変だもの」
「あ……そっか、そうですよね」
きちんと理由を説明すれば彼は素直に納得してくれた。
「えと、ありがとうございます」
彼はつぶらな金色の瞳でジッと手の中の黒リボンを見つめて、下唇を少し口の中に仕舞うようにしてゆっくりと瞬いた。これはもしや……喜んでる?
唇を元に戻すと今度は口角を押し上げえくぼを作った。
ほくほく顔って言うのかしらねこれは。
どう見ても喜んでいる顔よね。
その証拠に彼は自分で結び直そうとする。
けど普段髪を結ぶ習慣がないためか手古摺っていたから見兼ねて結んであげた。
今度は頭を触られても強張る素振りはなく、大人しくしてくれていた。
結び終えると、やっぱり気になるのか後ろに手をやるから、鏡台の前まで連れて行ってやれば、自分の髪を結んだ像を横目で確認して嬉しそうにはにかんだ。
「うん、よく似合ってるわよ」
思ったままに褒めてあげたら、彼は嬉しそうに頬を染めて振り返る。
「ほ、本当ですか?」
「お世辞言ってどうするのよ。それに一つだけじゃ洗濯したら使えるのなくなっちゃうし、後で別のリボンもあげるわね」
「えっ、いいんですか!?」
「勿論よ。高い物じゃないしね」
「嬉しいです。何かをもらうのは初めてで……」
「初めて……?」
どうして初めてなんてわかるの?
言葉のあやかしら。
私が思わず怪訝な顔をしていれば、彼はハッと我に返って口元を押さえ失言に青くなった。
ああ、この反応って……。
「もしかしてアーニー、あなた……」
記憶がないわけじゃない?
言外に含まれた私の言葉を読み取ったのか、彼は私の手に縋るように飛び付いた。
「ご、ごめんなさい。あの、あの、二人には言わないで下さい。どうしてあの夜に家からあの路地にいたのかは本当にわからないんです。でも、自分がどこの誰かは覚えてます。嘘をついてごめんなさい」
なるほど、自分の素姓はわかっていたのね。だから泣きじゃくるでもなく大人しく成り行きに身を任せていたんだわ。こりゃ一本取られたわね。すっかり騙されてた。
「どうして警備隊に素姓を伝えなかったの?」
怒るでもない私の問いに、アーニーはやや目も顔も伏せると、少しの躊躇の末に告白した。
「……うちに帰りたくないんです」
こんな小さな子供が帰りたくないって口にするなんて、一体どんな家庭なのかしらね。
「それは、どうしても? 落ち着いて考えても考えは変わらないの?」
「……はい」
「まさか、叩かれたりしてた……とか?」
「……」
これには明確な言葉は返らなかったけど、それがまさに答えよね。
まあ誰しも人に言えない事情はあるものよね。私だって他者を責める立場にはない。さすがにこんな小さな子が自らの意思で潜伏希望って点は苦々しい気持ちになったけど。
「わかったわ。二人にはまだ言わないでおく。だけどその必要性を感じたら話すわ。その前にあなたの覚悟が出来たら、きちんとあなたの口から二人にも話すのよ?」
言い含めるように理解の色を見せれば、彼はその身に奇跡が舞い降りたかのような表情になった。
大方、私がむんずと首根っこを掴んで問答無用で警備隊に引き渡すとでも思っていたんじゃないかしらね。
「はい……はい!」
目を潤ませたりもするもんだから、私は苦笑を禁じ得なかった。
「リズお姉さん、本当にありがとうございます。リボンも、ありがとうございました!」
もう一度鏡の中の自分の姿を眺め、今にもえへへっとか笑いそうな感じになっている。
あらら冗談抜きに本気で嬉しそうね。きゃわゆい~。
リボンがそんなに気に入ったのかしら。
……まさか女装癖に目覚めたとか言わないわよね?
もしそうなら責任重大だわ。
だってこのまま大きくなったら将来は間違いなくイケメンでしょ。乙女としてはそんな有望株の芽を摘んじゃうなんて勿体ない事したくないもの。
まあ幸い杞憂そうだったけど、アーニーはこの日からは私のあげたリボンで髪を結んでお手伝いをするようになった。
「――リズお姉さん、えと、今日もお願いしますっ」
でもやっぱり自分じゃ上手く出来なくて、いつもそう言って私に髪を結んでもらってだけどね。
「ふふっはいはい座って?」
私の部屋の椅子にちょこんと乗ってお行儀よくする後頭部に早速手に取った櫛を通す。朝にアーニーの髪を結んであげるのが、私の日課に加わりつつあった。
処刑どころで今日も元気よく働くアーニーを見つめる瞳がある。
その男は昼休憩時に普通にこの店で昼食を食べ終えると、店を出てふと考えるように扉のすぐ外で立ち止まった。店内へと意識を向けるようにやや肩越しに視線を向ける。
「アーネスト……か。しかしそんな馬鹿げた話があるわけがない。だが、似ている……」
彼はまさにそのアーネストの件でザックへと進展がない旨を報告に来ていた。
一つ息をつき、王都警備隊の制服の裾を翻して午後の任務へと去ろうとした矢先、トンと背中に何かが当たった。
「――っとと、あっすみませんお客さん!」
木の扉だった。
店の入口の真ん前で立ち止まっていた彼の方が営業妨害と怒られても仕方がなかったのだが、開けた扉をぶつけてしまった相手の方が慌てたように謝罪してきた。
扉向こうから申し訳なさそうな様子で顔を覗かせているのは一人の少女だ。
店で給仕をしているリズという娘だと思い出し、彼の方も「ああいやこちらこそ悪いね」と潔く謝って場所を譲った。
店先の立て看板を仕舞いにか、少女が外に出てくる。
その時、ちらと彼女の分厚い前髪の隙間からその奥の瞳が垣間見えた。
昼過ぎの明るい陽光が分厚い前髪の向こうへ差し込んだのだ。
菫色の綺麗な瞳だった。
彼が思わずじっと見つめてしまえば、「ええと本当にすみませんでした」と再び瞳を隠した前髪を揺らして頭を下げられてしまった。
「ああ、いや、本当に大丈夫だから気にしないで。ご馳走様、美味しかったよ」
「そうですか! ありがとうございます。ご来店ありがとうございました~!」
調子よく店員の少女に見送られ、今度こそ彼は踵を返し店の前から立ち去っていく。
「……ここにも一人」
やや距離が開き小さな声なら届かない所まで来ると、彼は堪え切れなくなったように密かに呟いた。
髪の色は違うが、あれも本当の彼女の髪色なのかどうか怪しい所だ。
少年といい少女といい、気になる人物に事欠かない店だと、彼はもう一度振り返った。
既に片付けられたのか立て看板はなく、少女の姿もない。
少し様子を見てみる必要がありそうだ、と彼はふっと微かな吐息で嗤った。
さすがに夜遅くなる酒場の給仕はザックも許可しなかったから、件の彼は大人しく部屋で先に寝ている。
ぐっすり眠ってその分元気溌剌~って感じで昼間は張り切って動いてるわ。
この日も、肩に着くさらさらの金髪が揺れていて、目には鮮やかだ。
「アーニー、向こうのお客さんにこの料理持っていって!」
「はい!」
「アーニー、そっちのテーブルのお皿下げるのお願いね。私はこっちを片付けるから」
「はい!」
とまあこんな感じで一緒に動いてるわ。
「アーニー、ちょっと休憩にしましょ」
「え、でも……まだお昼の忙しい時間ですし……」
「あなたにちょっと用事があるの」
ホールは奇跡の皿ジェンガを披露して給仕するマルスに少し任せて、私は小さな同僚を一旦店の奥へと連れて行った。
因みに呼び方についてだけど、アーネストって呼び方が正直嫌だった私は、愛称のアーニーって呼ぶようにしたのよね。
その方が呼びやすいし、あのわっるい奴を連想しなくて済むもの。
彼の方も別に嫌がったりしなかったから確定だった。
今ではマルスもザックも私に倣ってアーニー呼びになっている。
王都警備隊の方からは、まだ彼の保護者が現れたって連絡はない。
一週間も経っていないから、もう少し気長に待ってみようってマルスとザックとは言っていた。
だけど、こんな小さい子の捜索願も出されていないなんて、もしかして王都やその近隣の子じゃないのかしら。どこか遠くから連れて来られていたとしたら、仮に捜索願が出ていたとしても王都警備隊の管轄外だから、その地域に問い合わせないとわからない。
けどねえ、日中街で見かける警備隊の方でも先の事件に加えて別にまた吸血事件が起きたってわけで、今は細かく問い合わせている暇はなさそうだった。
それにこっちもただ任せているだけってのも嫌だったから、出来る範囲で調べてはいた。
彼が身に付けていたブカブカの男性服はどう見ても高級な物だったから、きっと良い所の出なんだろうって密かにマルスとは推測を立てて、上流家庭にアーネストって名前の息子のいる家はないかって訊いて回ってみたりもした。まあこっちも今の所進展はなしだけど……。
一番不安だろうアーニーは弱音を一切吐かない。
私が彼くらいの年で同じような立場に置かれたら、どうしたらいいのうわーんって泣き通しだったかもしれないわ。
「ちょっとここで待っててね」
「は、はい」
店の奥の適当な場所に一人残されたアーニーは、戸惑ったように私を見ていた。
私が彼に何の用かって?
うふふそれはね、一生懸命お手伝いはいいんだけど、ここは曲がりなりにも食べ物を扱っている所だし、彼の髪の毛がそのままだとバサバサして衛生上ちょっと……と見兼ねたのよね。それで昨日ある物を買ってきた。
なるべく急いで戻ると、ちゃんと待っていた彼へと後ろを向くように促した。
「え……ええと……」
彼は躊躇を見せた。
あらら緊張しちゃってまあ。
何となく、自分からは良いけど他者から触られるのは駄目なんだろうなって思う。
それでも日本の衛生管理の下で育った私としてはこのままにはできないってわけで、例え嫌われてもいいやと腹を括った。
「ほらほら後ろ向いてってば」
両肩を掴んでぐいぐい押して強制回れ右をさせると、さらりとした髪に指を梳き込んだ。
「え? え? リズお姉さん? あの!?」
「ちょっとじっとして」
アーニーが目を白黒させているのが顔を見なくてもわかった。
硬直して動かないのをいい事に、私はさっさと手を動かす。
「ハイ出来上がり」
「……え?」
肩に掛かっていた髪の毛がなくなって、彼はちょっとビックリしたように振り返った。
頭に手をやって、自身の頭髪が後ろで一括りにされているのがわかって余計に戸惑った顔になる。しかも指先が結んだ部分を触って解けてしまった。
両肩にぱさりと毛先が落ちて元通りだったけど、彼はその手に一本の黒いリボンを握っている。
両端にレースのあしらわれた男の子が付けるには些か可愛過ぎる装飾品だけど、彼なら全然大丈夫って太鼓判を押すわ。
「リズお姉さん、あの、これ……?」
「見ての通り、リボンよ。私の好みで買っちゃったけどアーニーにあげる。仕事中は髪の毛をそれで結んでおくのよ。ほら私だって後ろ髪はきちんと束ねてるでしょ? お皿を運ぶ時に髪の毛が邪魔だろうし、それにね、お客さんのお料理に入ったら大変だもの」
「あ……そっか、そうですよね」
きちんと理由を説明すれば彼は素直に納得してくれた。
「えと、ありがとうございます」
彼はつぶらな金色の瞳でジッと手の中の黒リボンを見つめて、下唇を少し口の中に仕舞うようにしてゆっくりと瞬いた。これはもしや……喜んでる?
唇を元に戻すと今度は口角を押し上げえくぼを作った。
ほくほく顔って言うのかしらねこれは。
どう見ても喜んでいる顔よね。
その証拠に彼は自分で結び直そうとする。
けど普段髪を結ぶ習慣がないためか手古摺っていたから見兼ねて結んであげた。
今度は頭を触られても強張る素振りはなく、大人しくしてくれていた。
結び終えると、やっぱり気になるのか後ろに手をやるから、鏡台の前まで連れて行ってやれば、自分の髪を結んだ像を横目で確認して嬉しそうにはにかんだ。
「うん、よく似合ってるわよ」
思ったままに褒めてあげたら、彼は嬉しそうに頬を染めて振り返る。
「ほ、本当ですか?」
「お世辞言ってどうするのよ。それに一つだけじゃ洗濯したら使えるのなくなっちゃうし、後で別のリボンもあげるわね」
「えっ、いいんですか!?」
「勿論よ。高い物じゃないしね」
「嬉しいです。何かをもらうのは初めてで……」
「初めて……?」
どうして初めてなんてわかるの?
言葉のあやかしら。
私が思わず怪訝な顔をしていれば、彼はハッと我に返って口元を押さえ失言に青くなった。
ああ、この反応って……。
「もしかしてアーニー、あなた……」
記憶がないわけじゃない?
言外に含まれた私の言葉を読み取ったのか、彼は私の手に縋るように飛び付いた。
「ご、ごめんなさい。あの、あの、二人には言わないで下さい。どうしてあの夜に家からあの路地にいたのかは本当にわからないんです。でも、自分がどこの誰かは覚えてます。嘘をついてごめんなさい」
なるほど、自分の素姓はわかっていたのね。だから泣きじゃくるでもなく大人しく成り行きに身を任せていたんだわ。こりゃ一本取られたわね。すっかり騙されてた。
「どうして警備隊に素姓を伝えなかったの?」
怒るでもない私の問いに、アーニーはやや目も顔も伏せると、少しの躊躇の末に告白した。
「……うちに帰りたくないんです」
こんな小さな子供が帰りたくないって口にするなんて、一体どんな家庭なのかしらね。
「それは、どうしても? 落ち着いて考えても考えは変わらないの?」
「……はい」
「まさか、叩かれたりしてた……とか?」
「……」
これには明確な言葉は返らなかったけど、それがまさに答えよね。
まあ誰しも人に言えない事情はあるものよね。私だって他者を責める立場にはない。さすがにこんな小さな子が自らの意思で潜伏希望って点は苦々しい気持ちになったけど。
「わかったわ。二人にはまだ言わないでおく。だけどその必要性を感じたら話すわ。その前にあなたの覚悟が出来たら、きちんとあなたの口から二人にも話すのよ?」
言い含めるように理解の色を見せれば、彼はその身に奇跡が舞い降りたかのような表情になった。
大方、私がむんずと首根っこを掴んで問答無用で警備隊に引き渡すとでも思っていたんじゃないかしらね。
「はい……はい!」
目を潤ませたりもするもんだから、私は苦笑を禁じ得なかった。
「リズお姉さん、本当にありがとうございます。リボンも、ありがとうございました!」
もう一度鏡の中の自分の姿を眺め、今にもえへへっとか笑いそうな感じになっている。
あらら冗談抜きに本気で嬉しそうね。きゃわゆい~。
リボンがそんなに気に入ったのかしら。
……まさか女装癖に目覚めたとか言わないわよね?
もしそうなら責任重大だわ。
だってこのまま大きくなったら将来は間違いなくイケメンでしょ。乙女としてはそんな有望株の芽を摘んじゃうなんて勿体ない事したくないもの。
まあ幸い杞憂そうだったけど、アーニーはこの日からは私のあげたリボンで髪を結んでお手伝いをするようになった。
「――リズお姉さん、えと、今日もお願いしますっ」
でもやっぱり自分じゃ上手く出来なくて、いつもそう言って私に髪を結んでもらってだけどね。
「ふふっはいはい座って?」
私の部屋の椅子にちょこんと乗ってお行儀よくする後頭部に早速手に取った櫛を通す。朝にアーニーの髪を結んであげるのが、私の日課に加わりつつあった。
処刑どころで今日も元気よく働くアーニーを見つめる瞳がある。
その男は昼休憩時に普通にこの店で昼食を食べ終えると、店を出てふと考えるように扉のすぐ外で立ち止まった。店内へと意識を向けるようにやや肩越しに視線を向ける。
「アーネスト……か。しかしそんな馬鹿げた話があるわけがない。だが、似ている……」
彼はまさにそのアーネストの件でザックへと進展がない旨を報告に来ていた。
一つ息をつき、王都警備隊の制服の裾を翻して午後の任務へと去ろうとした矢先、トンと背中に何かが当たった。
「――っとと、あっすみませんお客さん!」
木の扉だった。
店の入口の真ん前で立ち止まっていた彼の方が営業妨害と怒られても仕方がなかったのだが、開けた扉をぶつけてしまった相手の方が慌てたように謝罪してきた。
扉向こうから申し訳なさそうな様子で顔を覗かせているのは一人の少女だ。
店で給仕をしているリズという娘だと思い出し、彼の方も「ああいやこちらこそ悪いね」と潔く謝って場所を譲った。
店先の立て看板を仕舞いにか、少女が外に出てくる。
その時、ちらと彼女の分厚い前髪の隙間からその奥の瞳が垣間見えた。
昼過ぎの明るい陽光が分厚い前髪の向こうへ差し込んだのだ。
菫色の綺麗な瞳だった。
彼が思わずじっと見つめてしまえば、「ええと本当にすみませんでした」と再び瞳を隠した前髪を揺らして頭を下げられてしまった。
「ああ、いや、本当に大丈夫だから気にしないで。ご馳走様、美味しかったよ」
「そうですか! ありがとうございます。ご来店ありがとうございました~!」
調子よく店員の少女に見送られ、今度こそ彼は踵を返し店の前から立ち去っていく。
「……ここにも一人」
やや距離が開き小さな声なら届かない所まで来ると、彼は堪え切れなくなったように密かに呟いた。
髪の色は違うが、あれも本当の彼女の髪色なのかどうか怪しい所だ。
少年といい少女といい、気になる人物に事欠かない店だと、彼はもう一度振り返った。
既に片付けられたのか立て看板はなく、少女の姿もない。
少し様子を見てみる必要がありそうだ、と彼はふっと微かな吐息で嗤った。
応援ありがとうございます!
0
お気に入りに追加
326
1 / 5
この作品を読んでいる人はこんな作品も読んでいます!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる