41 / 42
赤髪の花婿・15
しおりを挟む
「なにするんですっ」
「なんだよ、まだ乾いてないんじゃん」
「血のにおいと得物だけでって、あなたどれだけ自分の勘で生きてるんですか。あの刃物だって、わたしが調達したものだとしたらどうす――」
月明かりを背にした赤伯の輪郭が覆い被さり、まくし立てていた唇がふさがれる。
柔らかな感触。二人にとってそれは初めてのものだった。
「……それだけじゃない、青明を信じてたから」
その唇は触れるだけで離れていくと、赤伯は青明の手を取る。
「もう寝よう、髪、結ばなくて……いいだろ」
「…………顔、真っ赤じゃないですか」
「なっ……う、うるさい!」
ばつの悪さを誤魔化すように、燭台の灯りを吹き消すと、勢いよく青明を横抱きにする。
そのまま寝台へ運ぶと赤伯は天蓋を落とした。包むように幕のかかった寝台は、まるで二人きりの世界だった。
「あっ、青明! 俺、どうしよう」
「今度はなんですか……」
抱きしめていた青明の両肩を掴むと、赤伯は慌てて起き上がった。
別段青明も気にはしていないのだが、どうにも緊張感に欠けるというか、雰囲気や情緒を作るのが下手というか。
けれど、そんなところも、また――。
「青明から、ちゃんと聞いてない……」
「は?」
「好きって、聞いてない……!」
薄明かりの中でも分かるほどに頬を染めた赤伯は、それでも青明を真っ直ぐに見つめている。
その言葉を期待して、待っているのだろう。そういうところで青明も素直になれればいいのだが、彼の場合、そうもいかないのだ。
「意外と、そういうこと気にされるんですね……」
「なんで」
「いえ、その……もっと、本能的に動かれる方だと」
「んん? それってなんか馬鹿にしてるよな!」
「そんなまさか……」
赤伯は子供っぽく頬を膨らませて迫る。
「……赤伯さま、もう一度ここに、いただけますか?」
青明はそう言いながら、自らの唇を指差した。
その様子が妙に艶っぽくて、思わず生唾を飲み込む。
「お、おう……」
瞼を閉じながらゆっくり唇を近づけると、柔らかな感触を押し付ける。
すると青明の唇が薄く開いて、温かな舌が赤伯の唇をたどった。
「んっ……!」
赤伯は一瞬目を見開いてから、腹の底からわきあがる衝動に任せてその唇に噛みついた。
「はっ……んん……」
たどたどしくも、熱情に溢れる口づけ。濡れた音と吐息だけが寝台に響く。
「ん……赤伯さま」
「どうした?」
まだ湿った黒髪を優しく撫でる。手入れの行き届いた絹糸のような触感が手の平に気持ち良い。
「……お慕い申し上げております」
「なんだよ、まだ乾いてないんじゃん」
「血のにおいと得物だけでって、あなたどれだけ自分の勘で生きてるんですか。あの刃物だって、わたしが調達したものだとしたらどうす――」
月明かりを背にした赤伯の輪郭が覆い被さり、まくし立てていた唇がふさがれる。
柔らかな感触。二人にとってそれは初めてのものだった。
「……それだけじゃない、青明を信じてたから」
その唇は触れるだけで離れていくと、赤伯は青明の手を取る。
「もう寝よう、髪、結ばなくて……いいだろ」
「…………顔、真っ赤じゃないですか」
「なっ……う、うるさい!」
ばつの悪さを誤魔化すように、燭台の灯りを吹き消すと、勢いよく青明を横抱きにする。
そのまま寝台へ運ぶと赤伯は天蓋を落とした。包むように幕のかかった寝台は、まるで二人きりの世界だった。
「あっ、青明! 俺、どうしよう」
「今度はなんですか……」
抱きしめていた青明の両肩を掴むと、赤伯は慌てて起き上がった。
別段青明も気にはしていないのだが、どうにも緊張感に欠けるというか、雰囲気や情緒を作るのが下手というか。
けれど、そんなところも、また――。
「青明から、ちゃんと聞いてない……」
「は?」
「好きって、聞いてない……!」
薄明かりの中でも分かるほどに頬を染めた赤伯は、それでも青明を真っ直ぐに見つめている。
その言葉を期待して、待っているのだろう。そういうところで青明も素直になれればいいのだが、彼の場合、そうもいかないのだ。
「意外と、そういうこと気にされるんですね……」
「なんで」
「いえ、その……もっと、本能的に動かれる方だと」
「んん? それってなんか馬鹿にしてるよな!」
「そんなまさか……」
赤伯は子供っぽく頬を膨らませて迫る。
「……赤伯さま、もう一度ここに、いただけますか?」
青明はそう言いながら、自らの唇を指差した。
その様子が妙に艶っぽくて、思わず生唾を飲み込む。
「お、おう……」
瞼を閉じながらゆっくり唇を近づけると、柔らかな感触を押し付ける。
すると青明の唇が薄く開いて、温かな舌が赤伯の唇をたどった。
「んっ……!」
赤伯は一瞬目を見開いてから、腹の底からわきあがる衝動に任せてその唇に噛みついた。
「はっ……んん……」
たどたどしくも、熱情に溢れる口づけ。濡れた音と吐息だけが寝台に響く。
「ん……赤伯さま」
「どうした?」
まだ湿った黒髪を優しく撫でる。手入れの行き届いた絹糸のような触感が手の平に気持ち良い。
「……お慕い申し上げております」
0
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

生まれ変わったら知ってるモブだった
マロン
BL
僕はとある田舎に小さな領地を持つ貧乏男爵の3男として生まれた。
貧乏だけど一応貴族で本来なら王都の学園へ進学するんだけど、とある理由で進学していない。
毎日領民のお仕事のお手伝いをして平民の困り事を聞いて回るのが僕のしごとだ。
この日も牧場のお手伝いに向かっていたんだ。
その時そばに立っていた大きな樹に雷が落ちた。ビックリして転んで頭を打った。
その瞬間に思い出したんだ。
僕の前世のことを・・・この世界は僕の奥さんが描いてたBL漫画の世界でモーブル・テスカはその中に出てきたモブだったということを。

番を拒み続けるΩと、執着を隠しきれないαが同じ学園で再会したら逃げ場がなくなった話 ――優等生αの過保護な束縛は恋か支配か
雪兎
BL
第二性が存在する世界。
Ωであることを隠し、平穏な学園生活を送ろうと決めていた転校生・湊。
しかし入学初日、彼の前に現れたのは――
幼い頃に「番になろう」と言ってきた幼馴染のα・蓮だった。
成績優秀、容姿端麗、生徒から絶大な信頼を集める完璧なα。
だが湊だけが知っている。
彼が異常なほど執着深いことを。
「大丈夫、全部管理してあげる」
「君が困らないようにしてるだけだよ」
座席、時間割、交友関係、体調管理。
いつの間にか整えられていく環境。
逃げ場のない距離。
番を拒みたいΩと、手放す気のないα。
これは保護か、それとも束縛か。
閉じた学園の中で、二人の関係は静かに歪み始める――。
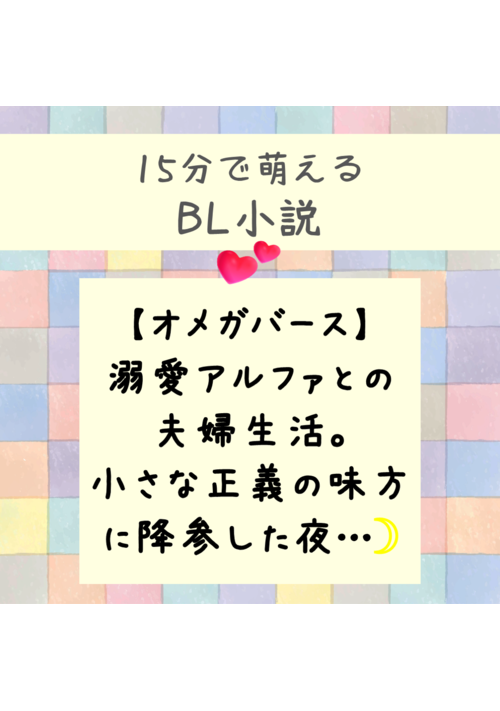

籠中の鳥と陽の差す国〜訳アリ王子の受難〜
むらくも
BL
氷の国アルブレアの第三王子グラキエは、太陽の国ネヴァルストの第五王子ラズリウの婚約者。
長い冬が明け、いよいよ二人はラズリウの祖国へ婚約の報告に向かう事になった。
初めて国外へ出るグラキエのテンションは最高潮。
しかし見知らぬ男に目をつけられ、不覚にも誘拐されてしまう。
そこに婚約者を探し回っていたラズリウが飛び込んできて──
……王への謁見どころじゃないんだが?
君は、必ず守るから。
無防備なおのぼりα王子×婚約者が心配なΩ王子の
ゆるあまオメガバース&ファンタジーBL
※「籠中の鳥と陽色の君〜訳アリ王子の婚約お試し期間〜」の続きのお話です。

その首輪は、弟の牙でしか外せない。
ゆずまめ鯉
BL
養子ゆえに、王位継承権を持たないオメガで長男のレイン(24)は、国家騎士団として秘密裏に働き、ただ義弟たちを守るためだけに生きてきた。
第一継承権を持つアルファで次男のリオール(19)は、そんな兄に「ごく潰し」と陰口を叩く連中を許せなかった。自分を犠牲にしてまで守る価値はないと思っていた。なにかと怪我の多い国家騎士団を辞めさせたかった。
初めて訪れた発情期のとき。約束をすっぽかされたリオールが不審に思い、兄の部屋へ行くと、国家騎士団の同僚──グウェンソード(28)に押し倒されるところを目撃して激高する。
「今すぐ部屋から出ろ!」
独占欲をあらわにしたリオールは、グウェンソードを部屋から追い出し、兄であるレインを欲望のままに抱いた。
翌朝、差し出されたのは特注の首輪──外せるのはリオールのみ。
「俺以外に触らせるな」
そう囁かれたレインは、何年も首輪と弟の執着に縛られ続けてきた。
弟には婚約者がいるのに、こんな関係を続けてもいいのか。
本当にこのままでもいいのか。
ひたすら執着して独占したがる弟と、罪悪感に苛まれる兄。
その首輪は、いつか弟の牙で血に染まるのか──。
どうにかしてレインを落としたいリオールと、弟との関係に悩むレインのオメガバースです。
リオール・グランケット(19)×レイン・グランケット(24)
※この作品は2015年頃に本文を書き、2017年頃にオメガバースに改稿、さらに2026年に手直しした作品になります。読みにくいかもしれません。ご了承ください。
三人称ですが攻めだったり受けだったり視点がよくかわります。攻め視点多めです。

君に望むは僕の弔辞
爺誤
BL
僕は生まれつき身体が弱かった。父の期待に応えられなかった僕は屋敷のなかで打ち捨てられて、早く死んでしまいたいばかりだった。姉の成人で賑わう屋敷のなか、鍵のかけられた部屋で悲しみに押しつぶされかけた僕は、迷い込んだ客人に外に出してもらった。そこで自分の可能性を知り、希望を抱いた……。
全9話
匂わせBL(エ◻︎なし)。死ネタ注意
表紙はあいえだ様!!
小説家になろうにも投稿

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















