あなたにおすすめの小説

鎖に繋がれた騎士は、敵国で皇帝の愛に囚われる
結衣可
BL
戦場で捕らえられた若き騎士エリアスは、牢に繋がれながらも誇りを折らず、帝国の皇帝オルフェンの瞳を惹きつける。
冷酷と畏怖で人を遠ざけてきた皇帝は、彼を望み、夜ごと逢瀬を重ねていく。
憎しみと抗いのはずが、いつしか芽生える心の揺らぎ。
誇り高き騎士が囚われたのは、冷徹な皇帝の愛。
鎖に繋がれた誇りと、独占欲に満ちた溺愛の行方は――。


上司、快楽に沈むまで
赤林檎
BL
完璧な男――それが、営業部課長・**榊(さかき)**の社内での評判だった。
冷静沈着、部下にも厳しい。私生活の噂すら立たないほどの隙のなさ。
だが、その“完璧”が崩れる日がくるとは、誰も想像していなかった。
入社三年目の篠原は、榊の直属の部下。
真面目だが強気で、どこか挑発的な笑みを浮かべる青年。
ある夜、取引先とのトラブル対応で二人だけが残ったオフィスで、
篠原は上司に向かって、いつもの穏やかな口調を崩した。「……そんな顔、部下には見せないんですね」
疲労で僅かに緩んだ榊の表情。
その弱さを見逃さず、篠原はデスク越しに距離を詰める。
「強がらなくていいですよ。俺の前では、もう」
指先が榊のネクタイを掴む。
引き寄せられた瞬間、榊の理性は音を立てて崩れた。
拒むことも、許すこともできないまま、
彼は“部下”の手によって、ひとつずつ乱されていく。
言葉で支配され、触れられるたびに、自分の知らなかった感情と快楽を知る。それは、上司としての誇りを壊すほどに甘く、逃れられないほどに深い。
だが、篠原の視線の奥に宿るのは、ただの欲望ではなかった。
そこには、ずっと榊だけを見つめ続けてきた、静かな執着がある。
「俺、前から思ってたんです。
あなたが誰かに“支配される”ところ、きっと綺麗だろうなって」
支配する側だったはずの男が、
支配されることで初めて“生きている”と感じてしまう――。
上司と部下、立場も理性も、すべてが絡み合うオフィスの夜。
秘密の扉を開けた榊は、もう戻れない。
快楽に溺れるその瞬間まで、彼を待つのは破滅か、それとも救いか。
――これは、ひとりの上司が“愛”という名の支配に沈んでいく物語。

異世界にやってきたら氷の宰相様が毎日お手製の弁当を持たせてくれる
七瀬京
BL
異世界に召喚された大学生ルイは、この世界を救う「巫覡」として、力を失った宝珠を癒やす役目を与えられる。
だが、異界の食べ物を受けつけない身体に苦しみ、倒れてしまう。
そんな彼を救ったのは、“氷の宰相”と呼ばれる美貌の男・ルースア。
唯一ルイが食べられるのは、彼の手で作られた料理だけ――。
優しさに触れるたび、ルイの胸に芽生える感情は“感謝”か、それとも“恋”か。
穏やかな日々の中で、ふたりの距離は静かに溶け合っていく。
――心と身体を癒やす、年の差主従ファンタジーBL。

【完結】社畜の俺が一途な犬系イケメン大学生に告白された話
日向汐
BL
「好きです」
「…手離せよ」
「いやだ、」
じっと見つめてくる眼力に気圧される。
ただでさえ16時間勤務の後なんだ。勘弁してくれ──。
・:* ✧.---------・:* ✧.---------˚✧₊.:・:
純真天然イケメン大学生(21)× 気怠げ社畜お兄さん(26)
閉店間際のスーパーでの出会いから始まる、
一途でほんわか甘いラブストーリー🥐☕️💕
・:* ✧.---------・:* ✧.---------˚✧₊.:・:
📚 **全5話/9月20日(土)完結!** ✨
短期でサクッと読める完結作です♡
ぜひぜひ
ゆるりとお楽しみください☻*
・───────────・
🧸更新のお知らせや、2人の“舞台裏”の小話🫧
❥❥❥ https://x.com/ushio_hinata_2?s=21
・───────────・
応援していただけると励みになります💪( ¨̮ 💪)
なにとぞ、よしなに♡
・───────────・

執着
紅林
BL
聖緋帝国の華族、瀬川凛は引っ込み思案で特に目立つこともない平凡な伯爵家の三男坊。だが、彼の婚約者は違った。帝室の血を引く高貴な公爵家の生まれであり帝国陸軍の将校として目覚しい活躍をしている男だった。
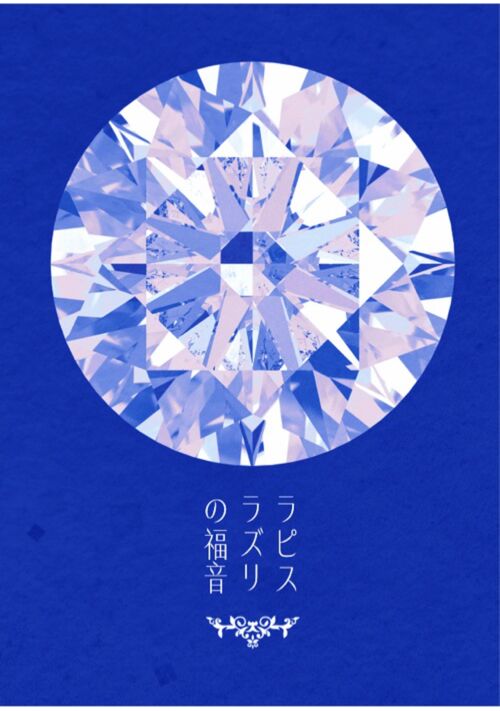
ラピスラズリの福音
東雲
BL
*異世界ファンタジーBL*
特別な世界観も特殊な設定もありません。壮大な何かもありません。
幼馴染みの二人が遠回りをしながら、相思相愛の果てに結ばれるお話です。
金髪碧眼美形攻め×純朴一途筋肉受け
息をするように体の大きい子受けです。
珍しく年齢制限のないお話ですが、いつもの如く己の『好き』と性癖をたんと詰め込みました!

希少なΩだと隠して生きてきた薬師は、視察に来た冷徹なα騎士団長に一瞬で見抜かれ「お前は俺の番だ」と帝都に連れ去られてしまう
水凪しおん
BL
「君は、今日から俺のものだ」
辺境の村で薬師として静かに暮らす青年カイリ。彼には誰にも言えない秘密があった。それは希少なΩ(オメガ)でありながら、その性を偽りβ(ベータ)として生きていること。
ある日、村を訪れたのは『帝国の氷盾』と畏れられる冷徹な騎士団総長、リアム。彼は最上級のα(アルファ)であり、カイリが必死に隠してきたΩの資質をいとも簡単に見抜いてしまう。
「お前のその特異な力を、帝国のために使え」
強引に帝都へ連れ去られ、リアムの屋敷で“偽りの主従関係”を結ぶことになったカイリ。冷たい命令とは裏腹に、リアムが時折見せる不器用な優しさと孤独を秘めた瞳に、カイリの心は次第に揺らいでいく。
しかし、カイリの持つ特別なフェロモンは帝国の覇権を揺るがす甘美な毒。やがて二人は、宮廷を渦巻く巨大な陰謀に巻き込まれていく――。
運命の番(つがい)に抗う不遇のΩと、愛を知らない最強α騎士。
偽りの関係から始まる、甘く切ない身分差ファンタジー・ラブ!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















