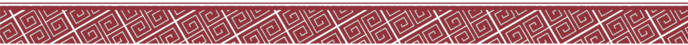38 / 59
31、中枢の浮者
しおりを挟むその朝は、早くから人が集まり、今までで一番寺の中が騒がしい。
日本の神社のような感じとは違うけれど、それでも次々と寺にやってくる人々の顔が、この日が待ち遠しかったといわんばかりにうきうきしている。
いつもの檀家さんのほかにも、各町村の檀家さんたちが、一般客を案内したり、ゴザを敷いたり、場所を譲り合ったりしている。
お寺を慕う人たちがこんなにいたのかと驚かされる。
「美波、ここにいたのですか?」
振り向くと、白い着物に身を包み、クランの花の首飾りと耳飾りをあしらった、本当に花のようなクランがそこにいた。
手には薄い水色の包みを持っている。
「わあ、クラン……! 今日は一段ときれいだよ!」
「ありがとうございます!」
クランの頬が、ぽっと染まる。
すごくかわいい。
これなら、誰だって絶対クランを好きになる。
「朝からすごい人出だね」
「はい、近い村から朝昼晩と分かれて三回奉納を行うのです」
「三回も?」
「はい、ここはなんといってもサイシュエンで最も古く由緒ある寺ですからね。マローからも参拝客が来ますし、各地の寺からも来賓として高僧がお見えになるんですよ」
「そっかあ、すごいなあ……」
「あの、美波……」
クランがおずおずと手元の包みを差し出して、端を解いた。
中には淡い黄色の着物が入っていた。
「これはどうしたの? あ、替えの着物だね?」
「いえ、これは、美波のために設えました」
「え、わたし?」
「美波はいつも地味なものをお好みなので、お嫌かもしれませんが、でも今日は奉納祭ですし、各地から集まった人々は、美波を初めて目にいたします。中央からの浮者は中央からこの地に配された恵みにちがいありませんが、美波もまたこの地に舞い降りた尊い恵みです。ですから、もしお嫌でなければ、今日だけでもどうかこれをお召しになってください」
「……わたしに秘密でこれをつくっていたの?」
いつだったか、部屋を訪ねたとき、クランが慌てていた様子が思い出される。
真新しい絹のうっとりするような手触り。
黄色と緑色の絹糸の丁寧な刺繍。
「嫌なわけないよ! ありがとう! すごくうれしい」
「美波、よかった! マシンとムラークが送ってくれた飾り紐と合うように設えましたの!」
「えーっ、クラン、気が利きすぎだよ!」
部屋に戻って、クランに着つけてもらった。
さらっとして嫌味のない無地に、手縫いの刺繍が衿と袖、裾にあしらわれている。
からし色と深緑色の飾り紐を二本対にして締めると、ぐっと印象が引き締まる。
「クランって、日本にいたらデザイナーになれるよ。それくらいうまくまとまってる」
「デザイナーとはなんでしょうか? でも、褒められたのはわかります」
クランとわたしとが立ち鏡の前に二人並んだ。
「あっ、刺繍の柄、同じなんだね」
「はい、美波とわたしの二人だけのおそろいです」
「わあ、かわいい!」
そうだ!
わたしは、この世界に持ってきた鞄を手に取った。
中のメイクポーチから、口紅を出した。
「クラン、口紅塗ってあげる」
「まあ、それは……浮者の国のものですか?」
「そうよ。ほんとなら若いクランにはもっとグロスっぽいのがよかったけど、これでも塗り方で血色のいい感じに……。こうしてグラデリップにするの。内側だけ塗って、ぼかして。クラン、上下ん~ってして」
「ん~」
「ほらね、かわいい! きれい!」
鏡の中のクランがますます女らしく、華やかになった。
クランが目をぱちぱちしている。
「まあ、なんて素晴らしい発色! とても自然なのに、とても美しいです!」
「お寺のお嬢様だからお化粧はだめなんだろうなと思っていたけど、今日くらい許してもらえるよね? だって、お婿さん候補が来るんでしょ?」
「ハナムンのお化粧よりも薄いのに、とても印象が強く残りますね。すごいです。こんな素晴らしいものを、美波はなぜ今まで使わなかったのですか?」
「だって、メイク落としがないし。クランがお化粧も派手なおしゃれもしてないのに、わたしだけするの変だと思ったから」
「そうだったんですか? 知りませんでした。美波は地味なものがお好みだとばかり……」
「そんなわけないよ~。でも、着飾っても見せたい相手がこの世界では左手だけだから」
「そうでしたね。美波、わたしにも塗らせてください」
今度はクランに塗ってもらった。
ふたりできゃあきゃあと盛り上がっていると、戸口の方から物音がした。
「だれ?」
「す、すみません……、コルグ様がクラン様をお呼びです」
顔を袖で隠したムラークくんだった。
あちゃ~、また刺激の強いものを見せちゃったんだね。
ムラークくんて、本当にいつもタイミングが悪いよね。
クランはムラークくんと一緒にコルグさんのもとへ向かった。
それと入れ替わるかのように、わたしの部屋をゼンジさんが訪ねてきた。
「あれ、クランがこちらにいると聞いてきたんですが」
「あ、今コルグさんに呼ばれていっちゃた」
「わあ、美波浮者、どうしたんですか! 今日は本物の嫁入り前の娘みたいですよ」
「みたいって……」
「冗談です。いつもそういうお召し物をめされていればいいのに。とてもおきれいですよ。いつもよりお顔の色もよさそうですし」
「クランが今日のために作ってくれたの。顔色は、化粧のせいかな」
「そうでしたか。それなら、クランの馬子にも衣裳もそれなりに期待できるかな。からかってやろうと思ってきたのに」
「からかうなんて……」
いらぬ口と思いながらも、つい出てしまった。
「クランは本当にとってもきれいだよ。後悔しないの? ゼンジさん」
ゼンジさんの笑顔がわずかに陰り、視線が下がった。
「クランの頑固は折り紙付きですからね」
「だけど、浮者とうまくいくとは限らないよね? そのときは、ゼンジさんがクランを幸せにしてくれるよね……?」
「僕には無理ですよ」
「どうして」
「僕はただの薬師見習いです。浮者でなかったら、クランの相手はカーツ様でしょう」
「カーツさんとクランがうまくいくと思う? わたしにはそうは思えないよ」
「だめならマシンがいますよ」
「ゼンジさんが僧侶になることはできないの?」
「僕がですか? そんな器でないことは自他ともに周知の上ですよ」
「そこを、クランのためになんとかがんばれないの?」
「無茶いいますねぇ。僕のような興味の偏った偏執的な人間に、僧侶のような格式ばった組織は無理です」
「でも、クランのことが好きなんでしょう?」
ゼンジさんが遠くを見るように目を細めた。
「子どものころ、出会ってすぐのクランは、自分の流の少なさを承知で、とにかく流を増やす訓練に必死でした。とにかく、ひたむきさと頑固さだけは、同世代の子どもたちの中で誰よりも持っていました。無茶も多くて、僕が手当てしてやるなんてこともしょっちゅうで」
「それは好きでやってたんでしょ?」
「はは……、まあそうですね。クランは尊敬するコルグ流者のためになりたいと、初めからいっていました。その当時の僕はまだ薬師になるとは決めていなくて、ただ、人の世話をしたり看病をしたりするのが好きなだけでした。寺に来たときは一応僧侶になるつもりで来ていたんですが、すぐに自分には無理だろうなとも気がついていました。だから、なんというか、クランはまぶしかったですね。誰よりも目的がはっきりしていて、真剣でまっすぐで、僕にはまぶしかった」
ゼンジさんの目には、今もそのころのクランがありありと浮かんでいるようだった。
「ある時、自分が僧侶に向いてない気がすると、クランに打ち明けました。クランは僕にいいました。自分はコルグ流者のために働くと決めているから、お前はわたしがそうなれるように怪我を治してくれと。百万回でも、一千万回でも、治してくれといいました。敵わないなと思いました。だけど、同時にうれしかったんです。クランの怪我を治す役目なら、僕はずっとクランのそばにいられる。子どもは単純ですから、僕はそう思ってしまったんです」
「それで、薬師に……」
「なにがあったって、クランの怪我は僕が治す。それが僕の矜持です」
そんな、そんなの……、もうなにもいえないよ……。
ふたりは想い合っているのに。
こんなに、お互いのことを理解して、大切に思っているのに。
自分の心に決めた道を貫くことはすごく大切だと思うし、それがハナムン人の矜持だっていうこともわかる。
だけど、こんなの、こんなのってないよ……。
ゼンジさんが部屋を後にしてから、わたしは考えていた。
旬さんには余計な手出しはするなと釘を刺されてしまった。
わたしはこの数カ月、クランのためを思って首飾りと耳飾りをつくってきた。
クランの決めたことを応援すると決めてた。
だけど、本当にもうなにもできないの?
待って……。
コルグさんはクランの結婚についてどう考えているんだろう。
コルグさんから、ゼンジと幸せになってほしいっていってもらえれば、クランの気持ちは動くかもしれない。
わたしの足は、コルグさんのいるだろう本堂へ向かっていた。
準備が整い、今にも式が始まりそうなところへ、わたしはずんずん入っていった。
「コルグさん、お忙しいところ恐縮なんですが、少しお話しできませんか? クランのことで……」
「美波浮者」
コルグさんも周りの僧侶たちも、明らかに困っていた。
「申し訳ありません。今日は難しいと存じます。この通り終日奉納祭ですございますから」
「そ、そうですね……」
参拝客や来賓客で埋まる本堂を横目に、わたしは引き下がるしかなかった。
でも、どうしよう。
もし中央からの浮者がクランを気に入ってしまったら。
コルグさんの気持ちがクランに伝わったとしても、その時はもう断われないかもしれない。
ええと、ええと、どうしたらいいんだろう……。
わたしは側にいた僧侶に尋ねた。
「すみません、中央からの浮者はいつごろ来るんですか?」
「浮者ならもうお見えです。今、本堂に向かっている、あの方がそうですよ」
「えっ!」
見ると、本堂の向かう列の中央に、中国風の大きな傘のようなものがあり、そこにいる黄色い着物のの人がどうやら浮者らしいとすぐにわかった。
しかも、その列を迎えに出ているのは、誰あろう、クランだった。
「うそでしょ!」
心の叫びが声に出ていた。
周りの目が一気にわたしに集まってしまった。
僧侶たちがわたしに低い声で囁く。
「美波浮者、どうぞあちらのお席へ」
そ、それどころじゃないよ~!
とはいうものの、今さらこの状況じゃどうにもしようがない。
わたしは案内された席へ座った。
浮者の列がクランを前にして本堂の階段を昇ってくる。
クランの後に続いて、黄色の着物の男性が入ってきた。
頭には、顔半分が見えないような目隠しになっている帽子がある。
わたしは表情を見ようと目を凝らしたけれど、鼻から上が少しも見えない。
ああ、もう……!
でも、下半分の顔からすると、明らかに年寄ではなかった。
むしろ顎がしっかりしていて、鼻すじも通っている。
下半分だけを査定するならイケメンの部類だ。
でも、それだけでは、彼がクランを気に入ったかどうかは判別つかない。
クランも相手の顔をはっきりはまだ見ていないんじゃなかろうか。
その後、従者の挨拶や、コルグさんの挨拶が続き、来賓の紹介や、わたしの紹介も行われた。
気が気じゃなくて、わたしはクランと浮者を交互に見た。
そわそわと落ち着かないわたしの様子に、クランが心配そうにこちらを見ている。
ああもう、こんなことなら、もっと早くにゼンジさんと話しておくべきだったよ……!
そのあと続けて行われた、読経が全然耳に入ってこない。
あれほど楽しみにしていた音楽の奉納も、楽しめない。
マシンくんやカーツさんたちのがんばりに集中したいと思うのに、頭の中ではクランとゼンジさんのことがいっぱいだ。
ああ、もう無理!
演武や流術の奉納にいたっては、後で旬さんに詳しく報告しなきゃいけないと思っていたのに、ほとんど覚えてもいない。
むしろ、早く終わってとさえ思っていた。
ごめんね、本当にごめんね!
わたしはそんなにキャパシティ広くないの……!
「それでは、美波浮者もご退室下さいませ。お部屋でどうぞゆっくりお休みください」
「えっ……!」
突然退室を促されてしまった。
わたしのそわそわしい態度が良くなかったのかと思ったけれど、どうやら中央からの浮者も退席するらしい。
クランが引き続き案内をしている。
わたしは急いでその後を追おうとすると、僧侶たちに止められた。
「美波浮者、お待ちください」
「すみません、わたし、クランに話さなきゃいけないことが」
「この後、クラン様はお庭の案内などをなされますので」
そ、そんなの、聞いてない!
いや、クランがそんなようなことをいってた気もする。
でも、いきなりふたりっきりにさせるの!?
うわあああ、どうしよう!
パニックになりかけていたわたしの後ろに、いつのまにかカーツさんが立っていた。
「美波浮者、どうされたのですか? 終始落ち着かないご様子でしたが」
「え、えと、それは……」
……カ、カーツさんにはいいにくいよ!
「部屋までお送りしましょう」
「いや、大丈夫!」
「いえ、送ります」
押し切られてしまった。
カーツさんの後ろを歩きながら、頭を悩ませていると、カーツさんの背中におでこがぶつかった。
びっくりした、急に止まらないでよ……。
「Nicht angemessen(相応しくない)」
えっ、この声……?
カーツさんの壁のような背中から顔を出した。
庭先に、中央からの浮者とクランがいた。
しかも、浮者の手はクランの首飾りを掬うように触れていて、クランが硬直している。
「Kenne deinen Platz(身の程を知れ)」
なにこの言葉。
ハナムン語じゃない。
なんだろう、ドイツ語みたいなイントネーションみたいだけど。
次の瞬間、浮者の手が高く振り上がった。
クランが首飾りをかばうように身を縮めた。
クランがなぐられる!
なぜかはわからない、でも少なくともわたしにはそう見えた。
「クラン!」
わたしが叫ぶよりも、カーツさんの行動のほうが早かった。
瞬く間に、カーツさんは浮者の手を薙ぎ払い、ふたりの間に割りいっていた。
浮者の帽子が吹き飛んでいた。
帽子から顕わになった髪は短く、金髪だった。
目が青く、彫りが深い。
三十代半ばくらいと思しき西洋人の顔立ちだった。
「Glaubst du, du kannst damit durchkommen?(こんなことして、ただで済むと思うのか?)」
浮者がまるでボクシングのように拳を構えた。
カーツさんも応戦するようにカンフーの構えを取った。
うそでしょ、待ってよ!
パニックになったわたしの口から出てきたのは、すごく間抜けな言葉だった。
「グ、グーテンターク! ダンケシェーン!」
だって、ドイツ語なんて、こんにちはとありがとうくらいしか知らないよ、普通!
でも浮者には効果があった。
驚いたように、こちらを向いたのだ。
通じるかわからなかったけど、通じたらしい。
クランが泣きそうな顔をしている。
カーツさんは相変わらず敵意むき出し。
浮者はじろりとこちらを睨みつけながら近づいてきた。
「Deutsche(ドイツ語)……、話せるのか?」
えっ、日本語話せるの?
だったら初めから日本語で話してよ……。
「ダ……エチ? ドイツ語、話せません。日本語で話できますか?」
「あなたが新しい浮者か? あなたから全く浮を感じない。その肩の手はなんだ? その手のはりぼてから妙に強い浮が出ているぞ」
中央の浮者が旬さんに手を伸ばしてきた。
わたしは慌てて後ろへ下がる。
「わたしはHeinrich Rommel(ハインリヒ・ロンメル)、Deutsches(ドイツ)軍第八歩兵連隊のUnteroffizier(伍長)だ」
「軍……、ドイツの軍人さんなんですか?」
「わたしは一九四四年、Omaha-Strand(オハマ・ビーチ)でAlliierte(連合軍)と交戦中に突如こちらの世界に飛ばされた」
「一九四四年……!?」
信じられない……!
だとしたら、この人は今90歳以上になるはずだ。
浮者って、そんなに長生きなの!?
わたしが言葉を失っていると、ハインリヒがずいと身を寄せてきた。
「あなたの名前はなんだ? 浮のないあなたではここでの暮らしは苦労しただろう。中央に迎えの浮信をいれてやろう」
「わ、わたしは沢渡美波です……。フシンというのは……?」
「遠く離れた相手と意思の通信を行うことをいうのだ。そのようなことも知らされていなかったとは、やはりこの寺があなたをここへ閉じ込めようとしていたのだな」
「えっ? それは違います!」
「なにもわからないところへきて、いろいろ吹き込まれたのだろう。大丈夫だ。イスウエンの大将軍は浮者を手厚く保護してくれる。浮のないあなたでも、ちゃんと浮者として相応しい暮らしができる」
「あの、ですから」
「マローでのことはすでに聞いている。もしかすると、その手のはりぼてがあなたの浮術の源なのか? 怖がらなくて大丈夫だ。わたしの外見は珍しいだろうが、Japan(日本)とDeutschland(ドイツ)は三国同盟の同志ではないか」
三国同盟って、そんな第二次世界大戦のときのことを持ち出されても……。
怖いのは外見のことじゃないし。
それより今は、いろんな衝撃で頭がこんがらかってる。
「ええと、あの、まず、確認なんですけど、ハインリヒさんは、サイシュエンに定住する浮者として、この地にやって来たんですよね?」
「そうだ。この地は中央により強固な管理下に置かれる」
「管理下って……。その、もっと穏やかな関わり合い方をこれから模索していくんですよね?」
「穏やかな関わり合いとはなんだ? あなたは浮者であるにもかかわらず、流者たちに騙されいいように利用されていたのだぞ。運が悪ければもっとひどい蹂躙されていたかもしれない」
「わたしはここでそんな目にあったことは一度もありません」
「なにをいうか。あの女の首飾りがその証拠だろう? あなたはいいように操られているだけだ」
「だから、そんなことないです」
「流者がユーファオーの樹で装飾品をつくるなどあり得ない。ただでさえ印帳と師筆の原材料が少ないのに。おおかたあなたに取り入って、この女があなたにユーファオーの樹を採取させたのであろう。小狡いハナムン人のやりそうなことだ」
ちょっと、待ってよ……!
さすがにそれはないんじゃない?
背中のあたりがぐっと押されるように熱くなった。
でも、ここで物事を荒立てたら、悪くいわれるのはきっとトラントランのみんななんだろう。
肩を上下させて、呼吸を整えた。
「ほかの地域の人たちのことは知りませんけど、トラントランの人たちのことを悪くいうのはやめてください。わたしはこの人たちのお陰で、こうして無事に生きているんです」
「Fraulein(フロイライン)沢渡、あなたはここへきてまだ間もない。知らないことがあまりに多すぎる。ハナムン人を簡単に信用してはいけない」
「信用というのなら、わたしはあなたこそ信用していいのかどうかわかりません。無抵抗の女性に手を挙げようとしていたのですよ!」
「それは、この女が身分不相応の装飾品を付けていたからだ」
「この女じゃない! 彼女の名前はクラン・ファです! その装飾品は友情の証にわたしの一存で贈ったものです。誰になにをいわれたわけでもありません!」
「そうしむけられたんだろう、表面をとりつくろったおべっかや裏工作。それこそがハナムン人の狡猾なやり方なんだ。あなたには浮がない。だから、そうしたハナムン人たちの気配がわからないのだ」
むぐぐ……、どうしたらいいの、この人とまったく話がかみ合わない!
怒りで頭が回らない。
なんていい返せばそうじゃないってわかってもらえるのかが、全然わからない。
「時間をかけて、お互いを理解し合っていければよいのではないでしょうか」
クランが強張った微笑みを浮かべて、そういった。
その立ち姿には、クランの勇気と覚悟が現れていた。
わたしは胸を打たれた。
クランは本気でそう思っているに違いない。
突然ハインリヒが背を向け、クランのそばへつかつかと歩いていった。
そして、なんのためらいもなく、クランの頬に平手を打ち付けた。
わたしもクランも、カーツさんまでもがなにが起こったのかわからないくらいの出来事だった。
悲鳴を上げて、クランが倒れ、カーツさんがそれを抱きとめた。
「Passen Sie uns nicht auf(口を挟むな)ハナムン人風情が」
さすがに堪忍袋も限界だった。
庭に飛び出し、ハインリヒの前に立ちはだかった。
「あなたにクランは渡さない」
ハインリヒは、ふうとオーバーなため息をついた。
「ここまで洗脳されているとなると、あなたは本当のお人よしだ」
「あなたがそれをいう? 第二次世界大戦後、ドイツはどうなった? アドルフ・ヒトラーは?」
ハインリヒの表情がにわかに動いた。
「クランには悪いけど、わたしはこの人を認めない。すぐに荷物をまとめてイスウエンに帰って!」
「美波!」
クランの悲痛な声が響いた。
振り返ると、クランが強く左右に首をふっている。
わたしはクランの真正面に立って、強張って胸の前で固く握られていた拳にそっと手を重ねた。
「わたしクランの決めたことを応援するって決めてた。クランの気持ちも、ゼンジさんの気持ちもよくわかる。本当に心から立派だと思う。だけど、お願いクラン。わたしと旬さんがユーファオーの樹に浮を満たし続けるから。たとえここを離れても、クランが呼んだから必ず来るから。何日寝込んだって、絶対にトラントランに来るから。だから、自分を大切にしてくれる人と一緒になって……!」
クランは強い意志の目をしていた。
わたしもその目から逸らさなかった。
このまま日が暮れるまでだって見つめあっててもよかった。
わたしの意志は変わらない。
突然、糸が切れたみたいだった。
クランがわっと泣き出して、わたしの胸に抱きついた。
よかったー……。
はじめて、クランの頭をよしよしした。
「あなたは騙されている! 」
ハインリヒがわめくように叫んだ。
わたしはクランを抱きながら、肩越しに応えた。
「クランになら騙されたって許すわ。クランにはそれ以上のことをしてもらってる」
「あなたはおかしい! 洗脳されている! 中央に帰って報告する!」
う、それは、まずいような……。
トラントラン全体が中央への反逆分子みたいに報告されたら困る。
「ハインリヒさん、なぜあなたはそんなにハナムンの人を毛嫌いするの? わたしにはわからない。ハナムン人を嫌いなら、どうしてサイシュエンへの定住を受け入れたの? ハナムンのために浮を注力するこの役割を、どうして受けたの?」
いつの間にか、あたりに人だかりができていた。
ハインリヒは口をゆがめて、わたしをにらみつける。
怖っ……!
ただでさえ人と対立することが苦手なのに、相手は元軍人。
迫力がすごすぎる……。
「あなたのような浮のない浮者になにができるというのだ。それとも、その手になにか秘密でもあるのか?」
ハインリヒがまた拳をつくった。
えっ、わたしと戦おうとしてる?
思いもよらなかった方向に、ぎょっと体を固くした。
で、でも大丈夫……。
もしハインリヒがわたしに害意を向けたら旬さんのカウンターが発動する。
「非常に妙だ。わたしが構えているのに、あなたはなにも変わらない。浮が増えることもないし、わたしに警戒を向けることもないし、浮が防御に動くこともない」
いや、気持ちとしてはものすっごく警戒してるし、防御してる気分なんですけど……。
「やはり種はその左手か。それは浮具か? いったいなにを隠している」
うわーん、この人、会話にならないよ。
旬さん、ごめん……!
イスウエンのこととかいろいろ聞きたかったのに、旬さんの言ってた通り、わたしの肩入れが過ぎてしまった。
もう関係の修復はむりかも……。
でも、あそこで黙ってなんていられなかったよ。
「あの、暴力はよしましょう。この左手のことなら、もう少し穏やかな状況でお話ししたいですし。それに今日は奉納祭ですし」
「浮のない浮者ならハナムン人に手玉に取られてもおかしくない。だが、あの妙な手はなんだ? なんの効果があるのだ。ここは攻撃して様子を見るほかあるまいな」
「いや、だから、さっきから、全然話聞いてないですよね!」
やっぱり駄目だ、この人!
そのとき、旬さんがすばやく空に指を走らせた。
「美波、攻撃をよけろ」
「よ、よけろ!?」
「俺のシールドではこいつの攻撃を防げそうにない」
「うそ、なんで?」
「今まで俺は物理的な攻撃と、流の攻撃を想定してシールドとシェルターを作ってきた。だが、俺と美波以外の浮に今日初めて触れてわかった。流と浮は全く別物だ」
「えっ、い、今そんなこと言われても!」
「なんだ、その左手は! やはりなにかの術なんだな!」
動く左手を目にしたハインリヒがわたしに手を伸ばしてきた。
それも、ボクシングのジャブのように素早い拳だ。
わたしはぎゅっと目をつぶるしかできなかった。
ドムッという重低音がしたと同時に、ぶわっと風が舞った。
わたしにはなんの痛みもなく、そっと目を開けると、ハインリヒの拳を受けて膝をつくカーツさんがそこにいた。
カーツさんは両腕でハインリヒのジャブを受け止めていたが、その威力はジャブという代物ではなかった。
カーツさんの体のあちこちに、打撲の跡があった。
たったの一発のジャブで?
ありえない……!
「カーツさん!」
わたしとクランが駆け寄ると、カーツさんはぜいぜいと肩で息をしていた。
「浮者であるわたしに歯向かうとどうなるかわかっただろう」
ハインリヒの目が冷たく光った。
再び拳をつくったハインリヒがこちらを見下ろした。
旬さん、どうにかして!
わたしはもうパニック寸前だった。
「でかしたカーツ」
旬さんがぱっと空に書いた字。
わたしは意味がわからなかった。
次の瞬間、ハインリヒの四方に、突然灰色の壁が現れた。
その壁はほんの息をのむ間に、ハインリヒを閉じ込めた。
あとに残ったのは、工事現場においてあるような簡易トイレのような長方形の箱だった。
「しゅ……旬さん、なにこれ……?」
「監獄の独房みたいなもんかな」
独房の小さな格子窓から、ハインリヒの叫び声が聞こえた。
とりあえずよかったことは、三回のうち、少なくとも一回は中央からの浮者がちゃんと来たことを、周辺の町村にも知ってもらえたことだった。
ただし、グレーボックスの中身をどうするのかという問題は残る。
残り二回の奉納が済んだ後、わたしたちは再び庭にいた。
その場には、コルグさん、クラン、六人の師父が集まっていた。
旬さんに治療してもらったカーツさんもいる。
カーツさんは二回目の奉納にも出る予定だったが、大事をとって休むことになり、出られなくなってしまってとても残念がっていた。
カーツさんの郷里の家族や親類が足をはこんできていたらしいのだ。
「さて、なにがあったのかをもう一度話してくれるか、カーツ」
コルグさんがすっと背筋の伸びた声をかけた。
「はい。一回目の奉納が終わった後、わたしは美波浮者を部屋まで送るために、この庭に面した回廊を歩いていました。
そこで、ハインリヒ浮者が、クラン様の首飾りに触れて、なにかおっしゃっていました。
次にハインリヒ浮者が手を振り上げたので、わたしはとっさに間に入りました。
ハインリヒ浮者と差し向かい、互いに臨戦態勢に入りました。
そのとき、美波浮者がハインリヒ浮者に、なにか大きな声で呼びかけました。
ハインリヒ浮者はすぐに美波浮者の気づき、イスウエンから迎えを寄こしてもらうことと、イスウエンでの保護についてを説明しました。
さらには、美波浮者がわれわれに騙されていると考え、美波浮者を説得しようとしていました。
その話の途中で、クラン様が口を出し、それがお気に召さなかったハインリヒ浮者は、クラン様に平手を振り下ろしました。
それを見た美波浮者がハインリヒ浮者の前に立ちはだかり、クラン様をハインリヒ様には渡さないとおっしゃられました。
そして、ユーファオーの樹には美波浮者と旬浮者が浮を注力する、クラン様が呼べば必ずトラントランへ来る。だから、クラン様には自分を大事にしてくれる相手を選んで欲しいと、そうおっしゃられました。
それを見たハインリヒ浮者はますます激高し、美波浮者に拳を向けました。
その拳をわたしが受けました。
傷は旬浮者のご慈悲によってこのようにもう治っております。
ハインリヒ浮者が第二打撃目を振るおうとしたとき、旬浮者の新しい浮術が発動しました。
その術によって、ハインリヒ浮者この灰色の長箱の中に今も閉じ込められております」
コルグさんがクランを見た。
「なにか不足や蛇足はあるか?」
「いいえ、おおむねカーツのいう通りです」
「美波浮者からはいかがでしょう」
「わたしも同じ認識です」
「では、わたしから美波浮者にいくつかお聞きしたいのですがよろしいでしょうか。まず、ハインリヒ浮者の容貌についてですが、あのように髪も目の色も色あせているのは、病かなにかによるものですか?」
「え? いえいえ! 病ではありません。ハナムンには、ハインリヒさんのように金や茶や赤の髪をした人はいないのですか?」
「ハナムンでは皆黒い髪、黒い目で生まれます。年を取れば等しく髪は白くなります」
「そうなんですね……。えーと、ハインリヒさんは浮者の国ではドイツという国の生まれで、ドイツ以外でも複数の国で青や緑、茶色や紫のような目を持って、明るい髪をした人たちがたくさんいます。それから、肌がハインリヒさんのように色白の人、あるいは浅黒い人、髪と同じくらい黒い人などもたくさんいて、そのように外見が違うことは互いに認め合い尊重されています。あ、自分の意志で髪や目の色を変えておしゃれを楽しむという文化もあります」
「ほう、そのように外見そのものを変える文化が……。とても興味深いですね」
感心したようにうなづいたのはグアンさんとターマンさんだった。
この様子からすると、ハインリヒは浮者の中でもさらにマイノリティな存在だということだ。
ここへ来たばかりのときは、ハナムン語は当然、下町言葉もわからなかったはずだ。
だとすると、ハナムンになれるまでに、すごく苦労したのかもしれない。
「では、美波浮者がハインリヒ浮者に呼び掛けたのは、下町言葉ではなくそのドイツなる国の言葉だったのですね。美波浮者はそのドイツ語も巧みにお話されるのでしょうか?」
「それは、まったく……。あ、でも電子辞書があるので多少は。でも、ハインリヒ浮者は下町言葉が喋れます。ちょっと会話がかみ合わない感じですけど」
「それを聞いて安心しました。見張りに立たせていた者から、ハナムン語が通じないようだと聞いていたので」
「そうですか……」
コルグさんが日本語で灰色の箱に声をかけた。
「ハインリヒ浮者、このような事態になってしまいましたこと、トラントランの長として、心より申し訳なく存じます。どうかお心をお鎮め下さいますようお願い申し上げます」
「……」
答えはない。
それからなんどもコルグさんが声をかけたが、ハインリヒは一言も返さなかった。
「旬さん、まさか……」
「大丈夫だ、中でちゃんと生きてる」
旬さんの字を見てほっとした。
「コルグさん、ハインリヒさんはちゃんと生きてるそうです」
「それならひとまず安心ですが、この後どうしたものでしょう。いつまでもこの箱の中に閉じ込めておくわけにはいかないと存じますが」
「出してイスウエンに返しても問題ないか?」
「問題ないとは言い切れません」
「俺達も、ハインリヒにはいろいろと聞きたいことがある」
「いずれにしろ、顔を見て話した方がいいよね。旬さん、壁の一面をガラスとかにできない?」
「一旦物質化したものを変形させるのは無理だな。なんとか会話できるように話してみてくれ」
そ、そんなこといってもな……。
この人との会話が成り立つかどうか、そこから心配ですよ……。
「ハインリヒさん、美波です。あの、狭い箱の中に閉じ込めてしまってすみません。お体つらくないですか? えと……、暴力はなしでちゃんと話をしたいので、この箱を取り払いたいのですが、もう攻撃はしないって約束してくれませんか?」
「……」
「こんなやり方しかできなくてすみません……」
「Deutschland(ドイツ)はどうなったんだ?」
「え……?」
今、ドイツはどうなったかっていったの?
そうか、戦中にハナムンに呼び寄せられて、その後のドイツのことを知らないんだ。
でも、他の浮者から聞かなかったんだろうか……。
「わたしがこの国に来たのはおよそ一年前です。地球のある人と常に通信ができる状態です。多分、あなたの知りたいことも、知りたくないことも、地球における最も新しい情報をお話しできるのはわたしです。顔を見てお話しませんか?」
「わかった……」
旬さんがなにかを掬い、離すように仕草すると、独房の壁が音もなく消えた。
ハインリヒが疲れたようにそこに立っていた。
「Fraulein沢渡とだけ話したい」
ハインリヒの要望を聞き入れ、わたしたちは客間の一室へ入った。
ろうそくに火がともされ、部屋は夕闇と拮抗するようにほの暗くもとった。
「それでDeutschlandはどうなったんだ?」
わたしが口を開きかけると、旬さんが素早く制した。
「まだいうな。こちらが聞きたいことを先に聞く」
「でも……」
「美波に駆け引きはできない。俺が話す」
「話す?」
次の瞬間、ハインリヒの視線がまるでダーツのように旬さんの左手に刺さった。
ハインリヒとテレパシーで話しているんだと、すぐにわかった。
わたしの耳にはハインリヒの言葉しか聞こえてこない。
「イスウエンでの浮者の暮らしは中世の貴族のようなものだ。わたしの知る母国の貴族的な印象とは違うが、日本の華族や天皇家ならそうなのではという暮らしぶりだ。まあ、わたしには中国と日本の違いもよくわかってはいないのだが……」
「浮者の多くは日本人だ。昔は浮者の数が少なかった。浮者は長生きなんだ。でも、ここ五十年は浮者の数が増えている。それも、俺のように日本以外の国から来たものも多い。大将軍は、日本人だけでなく、外国人の浮者にも同じだけの保護を与えてくれた。さすがに言葉だけは自分で何とかするしかなかったが、それでも日本語さえ覚えれば、やっていける。イスウエンでは」
「浮者には位がある。わたしはただの旗本だ。それは仕方がない。ハナムン語がいまだにあまり喋れないし、浮術も基礎的な身体強化や単純な攻撃力増強ぐらいしか使えないからだ」
「位の上の術者は、いろんな術の研究をしている。身体能力を上げるのが得意な者は、町奉行に所属することが多い。知識や財産にかかわる浮術、物質に浮を与える浮術を得意とする者は、勘定奉行に所属する。寺社奉行はそれ以外の浮術ならなんでもだ。大将軍や将軍の研究に携わるのは、寺社奉行のお偉方が多い。地球に戻る術は、多くの術者が研究している。成功例はない。ただし、あなたとFraulein沢渡のように、地球との交信という術は存在する。あなたの存在は、大老階級の浮術に匹敵する。あなたのつくった監獄もおそらく町奉行の上の階級だ。あれほどの物体を自由に操れる様をわたしは目にしたことがない」
「術を使っていないように見せる方法? ああ、あるだろう。だが、そういう細かな術は浮者というより、流者のほうが得意だろう。実際、トラントランに入る前にムネ町だったか、あそこの守長一族がそれらしい術を使っていた。あの触りはいちいち癇に障る。吹き飛ばしてやろうかと思った」
「留洞か……。わたしにはたいしたことはわからない。それこそ、大老階級でないと。わたしもそうだが、浮者の多くは強い浮の力をまとってこの地に降り、自分の力を自覚するまでにそう時間はかからない。だが、その力が己のどこから来るのかはわからない。だから、突然浮が使えなくなっても、その理由がわからない。ああ、浮が使えなくなる浮者もいる。だからこそ、イスウエンでの浮者の保護が必要なのだ」
「そうか……、やはりそうか……。Berlin(ベルリン)の壁はなくなったんだな……」
「俺の家族の消息がわかるのか? 妻はMalta Rommel(マルタ・ロンメル)、お腹には子どもがいた。名前は男ならWerner(ヴェルナー)、女ならGertrud(ガートルード)だ」
ひと通りの話が終わるころには、外はとっぷりとくれていた。
旬さんが薄暗い部屋の空中に、何かまだ聞きたいことがあるか、と書いた。
「いろいろと話してくれてありがとうございます。ハインリヒさん。わたしから少し個人的な質問をしてもかまわないでしょうか?」
「ああ」
「ハインリヒさんは、これまでハナムンでの暮らしに慣れるために、とても苦労されてきたのではないですか? アジア人のような容姿ばかりの中であなたの姿はとても目立ったろうし、ハナムンでも一部の人しか日本語が使えないから、言葉の交流も困難でしたでしょう。あなたがハナムン人に対して偏った見方をするのは、過去になにかあったからなのですか?」
「ああ……。イスウエンにたどり着くまでは、本当に苦労した。簡単に言葉では言えない……」
そういいながらも、ハインリヒはぽつぽつと過去にあったでことを話してくれた。
戦地から突然最北の地ココウエンのユーファオーの樹のもとに導かれた。近くの町にたどり着いたその日に、敵と間違えてハナムン人を銃殺してしまったこと。なにが起こっているのかわからないまま逃げ、自分の力に目覚めたときにもまた、ハナムン人を浮術により死なせてしまったこと。民に恐れられる一方で、自分を利用しようとすり寄ってきた権力者たち。彼らに乗せられて力を振るい、あがめられる一方で送られる軽蔑の視線。誰を信じればいいのかわからなくなり、そこを離れ、ひとりになった。同じことをなんども繰り返した。恐れられ、利用され、蔑まれ、騙されたことに気づく。ときに丸めこまれ、うわっつらの言葉や態度に翻弄され、また誰を信じばいいのかわからなくなり、その土地を出る。ときには実際追われるようにしてでたこともあったらしい。そんなときは自分の浮の力に任せ、家屋や町村の一角をこなごなに破壊してしまうこともあったという。
ハインリヒの言葉からは感情的なものはそぎ落とされていたが、あったことを聞くだけでも、十分深く心に傷を負ってもおかしくない。
わたしだって、ハナムンに来たばかりのころは、とにかく恐怖だった。
旬さんがいたからなんとかやってこれたものの、ひとりだったらと思うと、気が遠くなる。
わたしは、恵まれていたのだ。
「そんなあなたが、イスウエンを出て、浮の注力のために定住をしようと決めたのはなぜなんですか?」
「好き好んで来るわけない。中央を除くユーファオーの樹は十三本。たまたま外れくじを引いてしまっただけだ。そこそこの浮の量があり、旗本の中でも大した術の使えない浮者。下から数えてその十三人の中にわたしの名前があっただけだ。わたしはこちらで結婚もしていないしな。イスウエンと同じだけの暮らしを保証するとはいわれたが、イスウエンと同じ暮らしなどできるはずがない」
「あのときもいったけれど、サイシュエンのユーファオーの樹は、わたしと旬さんが浮を注力します。あなたが中央にもどったら、あなたは罰せられるんですか?」
「さあどうだろうか。報告してみなければわからない。派遣されたうちの何人かは俺のようになにかしらうまくいかない者もいるだろうから、そいつのかわりにまた別の地に派遣されるだけかもしれない。一応、明日ユーファオーの樹に注力して、それからイスウエンに帰るつもりだ。浮信でもそう伝える」
「あの、トラントランの人たちのことは」
「あなたたちが洗脳されていないということはわかった。わたしと違って、身の危険や精神の疲弊にさらされてもないということも。正直なところ、わたしはひどく神経質になっていた。サイシュエンに入るなり、毎晩のように花嫁候補とかいう娘が部屋に忍んでくる。クラン・ファにはつらく当たってしまったと反省している」
うわ……、そんなのわたしでも絶対やだよ……。
そんなことが立て続けにあったら、人間関係が嫌になって当たり前だ。
でも、別れてもう七十年以上たつのに、奥さんを愛し続けているんだ。
わたしは顔を見てしゃべることはできないけど、毎晩話ができる。
でも、旬さんのいない夜が七十年続くなんて、多分耐えられないと思う。
「あの、ちょっと待っててもらえますか?」
わたしは自分の部屋に戻り、鞄から電子辞書を掴むとすぐに来た道を戻った。
部屋に戻るなり、辞書でドイツ語の辞書を選択する。
それとともに印帳を開いた。
「ハインリヒさん、もう一度、ご家族の名前と自宅の住所とか、覚えていることを教えてもらえますか? 発音だけだと不安なので、ちゃんとアルファベットも教えてください」
「それは?」
「電子辞書といいます」
音声ボタンを押すと、辞書のスピーカーから、ドイツ語でグーテンタークと流れた。
「こ、こんな小さな機械がしゃべった!」
「二〇二一年の地球では、これよりもっと便利な翻訳の道具もあります。これはたまたまわたしがこちらに来るときに鞄に入れていたので、持ってくることができたんです」
ハインリヒの発音を辞書に聞かせて、単語検索をかけた。
その単語を印帳にメモしていく。ハインリヒと、妻、子の名前。父と母、兄の名前。妻の父母、妹の名前。所属していた軍の名前、住んでいた町の名前。出身校の名前。
「これでどうですか? つづりに間違いはないですか?」
印帳を開いて見せると、ハインリヒは息をつきながらわずかに視線を下げた。
「わたしは字が読めない」
「え? ……そうだったんですか」
「母国語だけではなく、下町言葉も読めない。字が苦手なんだ。だから印帳と師筆も使えない」
思わず、目を見開いてハインリヒを見ていた。
そうか、字を読んだり書くのが苦手という学習障害があったはず。
たしか、ディスレクシア。失読症。
ハイウッドスターが公表して知られるようになった障害だ。
ハインリヒはハナムンにおいて、外見や会話によるコミュニケーションに加えて、文字が読めない書けないという三重の苦労をしてきたんだ。
自分に置き換えて、想像もできないくらいの大変さだ。
その苦労を考えると押しつぶされそうな気分になる。
わたしはわざと大きな声を出した。
「わかりました!」
わたしはハインリヒの前に印帳をもう一度広げて見せた。
「これ、ハインリヒさんの名前、これ奥さんのマルタさん、お子さんの名前、お父さんの名前、お母さんの名前です」
全部を指さして確認して見せると、わたしは印帳を胸に抱いた。
「ここにちゃんと書きましたからね。ご家族のことがわかったら、ちゃんとお知らせしますからね」
「ああ……」
ハインリヒさんがわずかに頬を緩めた。
帰り際、ハインリヒさんがぽつんといった。
「久しぶりに、祖国の言葉を聞けてうれしかった」
そ、そんなこといわれたら、もう、こうするしかないじゃん……。
電子手帳を差し出した。
「貸してあげます。明日、一緒にユーファオーの森に行きましょう。それまで、これをハインリヒさんに貸します」
「いいのか? なくしたとうそをいって持ち帰ってしまうかもしれないぞ」
「えっ、そんなことするんですか? じゃあだめです。ちゃんと返してください」
「わかった。明日、森へ行く前までだな」
「はい。あ、使い方を教えますね」
ハインリヒさんが用意された部屋へ案内されて行くのを見送った。
廊下の角を曲がる前に、グーテンタークが聞こえて、ちょっと可笑しかった。
8
あなたにおすすめの小説

愛された側妃と、愛されなかった正妃
編端みどり
恋愛
隣国から嫁いだ正妃は、夫に全く相手にされない。
夫が愛しているのは、美人で妖艶な側妃だけ。
連れて来た使用人はいつの間にか入れ替えられ、味方がいなくなり、全てを諦めていた正妃は、ある日側妃に子が産まれたと知った。自分の子として育てろと無茶振りをした国王と違い、産まれたばかりの赤ん坊は可愛らしかった。
正妃は、子育てを通じて強く逞しくなり、夫を切り捨てると決めた。
※カクヨムさんにも掲載中
※ 『※』があるところは、血の流れるシーンがあります
※センシティブな表現があります。血縁を重視している世界観のためです。このような考え方を肯定するものではありません。不快な表現があればご指摘下さい。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

私が王子との結婚式の日に、妹に毒を盛られ、公衆の面前で辱められた。でも今、私は時を戻し、運命を変えに来た。
MayonakaTsuki
恋愛
王子との結婚式の日、私は最も信頼していた人物――自分の妹――に裏切られた。毒を盛られ、公開の場で辱められ、未来の王に拒絶され、私の人生は血と侮辱の中でそこで終わったかのように思えた。しかし、死が私を迎えたとき、不可能なことが起きた――私は同じ回廊で、祭壇の前で目を覚まし、あらゆる涙、嘘、そして一撃の記憶をそのまま覚えていた。今、二度目のチャンスを得た私は、ただ一つの使命を持つ――真実を突き止め、奪われたものを取り戻し、私を破滅させた者たちにその代償を払わせる。もはや、何も以前のままではない。何も許されない。

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

わたしの下着 母の私をBBA~と呼ぶことのある息子がまさか...
MisakiNonagase
青春
39才の母・真知子は息子が私の下着を持ち出していることに気づいた。
ネットで同様の事象がないか調べると、案外多いようだ。
さて、真知子は息子を問い詰める? それとも気づかないふりを続けてあげるか?

裏切りの代償
中岡 始
キャラ文芸
かつて夫と共に立ち上げたベンチャー企業「ネクサスラボ」。奏は結婚を機に経営の第一線を退き、専業主婦として家庭を支えてきた。しかし、平穏だった生活は夫・尚紀の裏切りによって一変する。彼の部下であり不倫相手の優美が、会社を混乱に陥れつつあったのだ。
尚紀の冷たい態度と優美の挑発に苦しむ中、奏は再び経営者としての力を取り戻す決意をする。裏切りの証拠を集め、かつての仲間や信頼できる協力者たちと連携しながら、会社を立て直すための計画を進める奏。だが、それは尚紀と優美の野望を徹底的に打ち砕く覚悟でもあった。
取締役会での対決、揺れる社内外の信頼、そして壊れた夫婦の絆の果てに待つのは――。
自分の誇りと未来を取り戻すため、すべてを賭けて挑む奏の闘い。復讐の果てに見える新たな希望と、繊細な人間ドラマが交錯する物語がここに。

冤罪で辺境に幽閉された第4王子
satomi
ファンタジー
主人公・アンドリュート=ラルラは冤罪で辺境に幽閉されることになったわけだが…。
「辺境に幽閉とは、辺境で生きている人間を何だと思っているんだ!辺境は不要な人間を送る場所じゃない!」と、辺境伯は怒っているし当然のことだろう。元から辺境で暮している方々は決して不要な方ではないし、‘辺境に幽閉’というのはなんとも辺境に暮らしている方々にしてみれば、喧嘩売ってんの?となる。
辺境伯の娘さんと婚約という話だから辺境伯の主人公へのあたりも結構なものだけど、娘さんは美人だから万事OK。

天才天然天使様こと『三天美女』の汐崎真凜に勝手に婚姻届を出され、いつの間にか天使の旦那になったのだが...。【動画投稿】
田中又雄
恋愛
18の誕生日を迎えたその翌日のこと。
俺は分籍届を出すべく役所に来ていた...のだが。
「えっと...結論から申し上げますと...こちらの手続きは不要ですね」「...え?どういうことですか?」「昨日、婚姻届を出されているので親御様とは別の戸籍が作られていますので...」「...はい?」
そうやら俺は知らないうちに結婚していたようだった。
「あの...相手の人の名前は?」
「...汐崎真凛様...という方ですね」
その名前には心当たりがあった。
天才的な頭脳、マイペースで天然な性格、天使のような見た目から『三天美女』なんて呼ばれているうちの高校のアイドル的存在。
こうして俺は天使との-1日婚がスタートしたのだった。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる