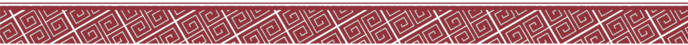40 / 59
33、たくされし赤いつぼみ
しおりを挟む旬さんの意図がよくわからないまま、わたしは次の日改めてハインリヒに聞いた。
「Jemandem eine Extrawurst braten(ソーセージを余分に一本焼いてあげる)つまり、えこひいきしてやるといったんだ」
「いいんですか! わーい!」
「それくらい、Frau美波はわたしに価値のある機会を与えてくれた」
門まで見送りに出てきたのは、昨日星の勉強会に参加してくれた人たちばかりではなかった。
多くの僧侶たちが列をなし、檀家さんたちもがそこにいた。
ハインリヒは来たとき被っていた帽子はもうしていなかった。
「ハインリヒ浮者、星座盤ができたらお送りします」
「ありがとう、ムラーク。楽しみにしている」
「ハインリヒ浮者、もしお近くにいらっしゃることがあれば、ぜひ寺へ寄ってください。我々に稽古をつけてください」
「カーツ、あなたの闘気に敵う者はDeutsche(ドイツ)軍の訓練所にも町奉行にもそういない。あなたは自分の師を信じて精進すればいい」
「では、交流試合をぜひ」
どんだけ戦うのが好きなの……?
ついていけないわたしは、遠巻きにうすい微笑みを浮かべて見ていた。
カーツさんが突然、ハインリヒに差し出した。
石の重しのふたつの腕輪だった。
えっ、それ、贈るの!? いる!? それ、いる!?
「このような些末なものを献上するのも失礼かとも存じましたが、偉大な祝福をいただいたことになにか感謝の形を差し上げたく」
「これは? いまあなたがつけているその腕輪と同じものか?」
「これは、修行のために磨き上げた石です。このように手首足首に巻いて、日ごろの鍛錬としています。わたしのものは泥を固めてものですが、これは石でできています。徐々に重い素材に変えていくことで、より負荷をかけることができるのです」
ハインリヒさんは腕輪の一つを持ち上げた。
そんなのもらっても困るよね……。
カーツさんも、思いが一途なのはわかるけど、もう少し相手のことを考える心遣いがさ……。
「これはすごい!」
ハインリヒが目を輝かせたので、わたしはまさかの二度見をしてしまった。
「このような球体を、石でつくれるとは。それも、このように均一で滑らかな加工。これぞ、Meister(マイスター)の手技だ!」
な……、なぜ?
ハインリヒはカーツさん手製の石加工に感激している。
どうやら、その技術の高さに驚いているらしい。
マイスターってつまり、職人気質……ってこと?
「喜んでいただけて恐悦至極です!」
カーツさんも珍しく頬を染めている。
なんか、よくわからないけど、よかったね。
ほんと、よくわからないけど……。
ハインリヒが馬にまたがった。
馬上の黄色い着物は光を反射して金色に見える。
すがすがしい顔に、金髪と碧眼がきらめいていた。
「Frau美波、Dr大倉、それにトラントランの皆には、いろいろと世話になった」
「ええと、ハインリヒさん、定住のことなんですけど……」
わたしがいいかけると、ハインリヒはクランに視線を向けた。
クランはわずかに肩をこわばらせた。
「いずれにしろ、わたしは一度中央に報告しに戻らねばならない。あなたがたが責を問われることはないだろう。少なくともわたしからはそのような報告をするつもりはない。Frau美波とDr大倉がここにとどまるのであれば、サイシュエンの浮の注力には問題がないしな。それから、クラン・ファ」
クランが小動物のように視線を向けた。
「あなたに対する非礼をわびたい。すまなかった」
ちょっとちょっと、謝るという人が、馬の上から相手を見下ろすの?
わたしのいわんとすることを察して、ハインリヒが気まずそうに乗ったばかりの馬を降りた。
「あなたは、Frau美波がわたしにもう一晩留まるようにといったとき、真っ先にそれに賛同した。昨晩も、わたしの言葉を訳す役割を果たしてくれた。初め、あなたが日本語が話すのは、わたしに対するおべっかだと思っていた。だが、よく考えてみたら、サイシュエンのあらゆる町や村ですりよってきた守長やその娘たちのような付け焼刃ではなく、通訳はわたしの従者よりもはるかに早くてうまい。あなたが時間をかけてお互いを理解しえばいいといったことは、本心からだったと今ならわかる」
それは当然だ。
クランは初めから、トラントランのために、コルグさんの支えになるために、浮者とうまくやっていきたいと願って、日本語を学んでいたのだ。
あたしゃを使っていた下町言葉のころからわたしはそれを知っている。
「だが、すまない。わたしは祖国の妻や家族を裏切ることはできない」
「それはそうです。今更態度を改めたって、クランはもう渡しませんよ」
わたしはここぞとばかりに釘を刺しておいた。
クランがくすっと頬をほころばせた。
「それを聞いて安心いたしました。実は、これをお渡しするかどうか迷っていたのです」
クランが檀家の女性たちに目配せをした。
檀家さんたちがつぎつぎとクランのそばに寄ってきた。
クランが胸元からなにかを取り出し、手を広げると中に三色の布で作られたお守りのようなものだった。
片手に納まるくらいの袋に、金色の紐と、赤い小さな珠がついている。
そういえば、昨晩クランにドイツの国旗やハインリヒの家族の名前についていろいろ聞かれたけど、もしかして、これをつくるためだったの?
「美波浮者から、ハインリヒ浮者の祖国の色をお聞きしました。黒、赤、金の布でこの匂い袋をつくりました。中に入っているのはレンレンという花を乾燥させたもので、浮者の国ではキンモクセイという花に似ているそうです。離れた場所にも匂いが届くことから、ハナムンでは遠くにいる人とのつながりを忘れないために、このような匂い袋を旅発つ人に渡す習慣があります」
受け取ったハインリヒが匂い袋を花に近づけた。
「確かに、osmanthus(オスマントス)の香りだ……。布に、なにか刺繍がしてあるのか?」
「はい、黒地にはハインリヒ浮者のお名前、赤地には奥方様のお名前、金地には、お子様のお名前を刺繍いたしました。ランヤードリングにかわる、祖国とのつながりにしていただければと存じます」
青い目が、読めない刺繍の字を吸い寄せられた。
ハインリヒは、赤い糸、そして、金の糸の上を何度も指でなぞった。
糸のふくらみを愛おしむかのように、なんどもなんども。
その目にキラキラとしたものが浮かんでいる。
その様子をクランがじっと見つめていた。
「ありがとう、クラン・ファ。今は胸がいっぱいで、それ以外の言葉が見つからない……」
クランの顔にようやく安堵の笑みがこぼれた。
すると、ミックさんをはじめ檀家の女性たちがなにやらそわそわと口にした。
「わたしたちも手伝ったんだよ」
「そうさ、みんなで大急ぎでね。でもうまくできているだろう?」
「ドイツ語っていうのは、ハナムンの字と全然違うんだねぇ」
さすがはクラン、さすがは檀家の女性たちだ。すごい!
「まったく、クラン様を殴りつけたと聞いたときは、一体どうしてくれようかと思ったけどねぇ、まあ、こうしてみると案外いい男じゃないのさ」
「ほんとうだねぇ、目なんか空の色と同じできれいだねぇ」
「髪だって、初めは若白髪かと思ったけど、よく見たらちょっと金色がかっていて、ハナムン人みたいに伸ばしたらきっときれいだよ」
お、おばさまパワーもすごい……。
言葉が通じないのをいいことに遠慮がない。
いや、通じていたとしても、このぐいぐい来る感じは変わらないだろうけど……。
クランが苦笑しながら、檀家の者たちも手伝ってくれました、と一言添えるにとどまった。
「ハインリヒ浮者、またいつでもトラントランへお越しください。わたしたちは、いつでもあなたを歓迎いたします」
クランがそういうと、コルグさんと師父たちがそろって頭を下げた。
それにならって、その場にいた全員が頭を下げた。
ハインリヒも丁寧に頭を下げた。
よかったね、ハインリヒ。
ハインリヒたち一行が、道の先に消えていくのを見届けた。
ハインリヒが最後に残して言った言葉。
「Rom wurde nicht an einem Tag gebaut(ローマは1日にしてならず)」
九十歳を超えるハインリヒから、こんな前向きな言葉が聞けたのは、正直驚きだった。
トラントランで過ごした時間が、彼にとっての一歩になったんだ。
でも、浮がないから、わたしはきっとハインリヒほど長生きはしない。
なら、わたしだったら「一期一会」かな。
そのときそのときを大事にするしかないよね。
あっ、そういえば、ハインリヒって考えてみたらすごい年上じゃん!
あんまり失礼だったから心の中では呼び捨てしていたけど、本当なら人生の大先輩に呼び捨てはないよね。
今度からハインリヒさんと呼ぼう。
ふー、危ない危ない。
うっかり心の声が出なくてよかったよ。
「さあて、帰ろ……」
振り返ってみて驚いた。
クランを先頭に、みんながそこに立っていたからだ。
「わあっ! どうしたの?」
「美波!」
突然クランが抱きついてきた。
「わたし、美波となら結婚してもいいです!」
「は、はあ……?」
僧侶たちがそれぞれ顔を背けて目のやり場に困っている。
なんなの、この公開セクハラは……。
「なにいってるの? 自分を大切にしてくれる人を選ぶって約束したでしょ?」
「はい、なにもかも、美波浮者のおかげです!」
クランが落ち着きを取り戻すと、コルグさんが頭を下げた。
え、急になんだろう……。
わたしも習って頭を下げた。
「ハインリヒ浮者とこのように親睦を深められたこと、我々ハナムン人との間に立ってくださったこと、本当に心より感謝申し上げます」
「えっ、いえいえ! わたしはなにも……。わたしがというより、ハインリヒさんの心を開いたのは、ここにいるクランや、カーツさんや、ムラークくん、それにトラントランのみなさんだと思います」
「しかしその機会を我々に与えてくださった」
「ああ、まあ、でもそれは、わたしもみなさんに与えてもらいましたから。トラントランなら、ハインリヒさんにもなにかを与えてくれるんじゃないかと思ったっていうか……。すみません、みなさんのお力をはじめから最後まで頼っていました。わたしひとりではどうにも。こちらこそ、同じ浮者の国のハインリヒさんに優しさを示してくださってありがとうございました。なんだかんだいっても、やっぱり同じ地球にいた人だと思うと、放っておけないというか、自分の身と置き換えて考えてしまうので。皆さんの親切心、寛容さ、それに忍耐に救われました。ありがとうございます」
「そのようなお言葉、恐悦至極、この胸に深く染み入ります」
あれー、もしかして、それをいうために待っていたの?
なんか、すっごく照れるというか、いや、恐れ多いし恥ずかしいんですけど……。
「いや、みなさん顔を上げてください。お願いします」
「この感謝は……」
「いや、もういいですから、ははは……。みなさんも、どうぞいつものように。えっと……、クラン、行こ!」
「はいっ!」
わたしは逃げるようにして戻ってきてしまった。
クランが嬉々としてわたしの腕に絡みついている。
部屋に戻ると、話題はあの匂い袋になった。
「それにしても、たった一日であんな豪華な匂い袋を作るなんて、クランの裁縫の腕前には本当に驚いたよ」
「美波に相談しようと思ったのですが、最後まで本当に渡すかどうか迷っていましたし、それに、仕上がるかどうかもわからなかったので……」
「そうだよね、あの感じで行くと、場合によっては勘違いされてもおかしくないもんね。正しく意図が伝わる贈り物になってよかったよね」
「はい。もともとレンレンは恋人や夫婦間で贈るものなので、本当にどう伝えればいいか悩んでいたのです。友人や家族であれば、クランの香りを入れるのですが、クランを入れたらわたしになってしまいますし……」
「あー、なるほど、それは、わたしを思い出してってなっちゃうね」
「はい。ハインリヒ浮者は字がお読みになれないと聞いていたので、刺繍は絶対いい案だと思っていたのです。でもあまり面積の広いものは刺繍に時間がかかりますし、ランヤードリングのように普段から持ち歩くのにいいものといえば、お守りか匂い袋がいいと思いました。ハインリヒ浮者がおっしゃることには浮者の国の神なる存在は、わたしにはまだよく理解ができなかったので、匂い袋が良いかと」
「そうだったんだね。あんなに目にあわされたのに、ハインリヒさんにそこまで考えてしてくれたんだね。ありがとうね、クラン、あなたって本当に素晴らしい人だよ」
クランはにまっと微笑むと、わたしの肩に頭を乗せてきた。
「ん?」
「美波はわたしのお姉様です」
「ああ……!」
わたしはよしよししてあげた。
ようやくクランに正式に姉認定してもらえたのね。
これなら、頑張った甲斐があったというものだ。
そのとき、戸口でガチャンと陶器の音がした。
あれ、このパターン、またムラークくんか?
「ムラークくん?」
声をかけると、ゼンジさんが顔を伏せ気味で入ってきた。
「えっと、お茶を持ってきたんですけど……」
「あ、ゼンジさんだったの? ありがとう……」
女性のホモソーシャルというか、女同士の友情って、ここではそんなに怪しい感じに見えるの?
修練場ではたがいに健闘を称えたり励まし合ったりしながら肩をたたいたりしているし、子どもたちは大人の僧侶たちが見ていないときは結構わちゃわちゃしていたりする。
これくらいのスキンシップは、僧侶たちと比べても普通だと思うんだけど。
いまいちよくわからない。
一度聞いてみたかったんだよね。
口を開きかけたとき、クランがゼンジさんを見た。
「お茶なんて、気が利くじゃない」
「そうだろ? 僕の読みだと、美波浮者は今夜あたり熱を出すと思ってね。それで神経を鎮めるお茶を持ってきました」
「今夜熱を? そんなことないよ、今は全然そんな感じないですよ?」
ゼンジさんはちょっと気持ち悪い笑みを浮かべた。
「ふふふ、僕の観察で行けば、ここ数日の美波浮者の活動量は、限界値を超えています。おそらく間違いなく、熱を出すでしょう」
なにその予言……。
怖いんだけど……。
クランがぱっとこちらを振り返った。
「美波、ゼンジのいう通りかもしれません。少し休んでください」
「う、うん……。じゃあ、そうしようかな……」
ゼンジさんの淹れてくれたお茶の香りを楽しみつつ、わたしはふたりの様子を見つめた。
「あの、クラン」
「えっと、ゼンジ」
ふたりが同じタイミングで口を開いた。
あ、わたし、いないほうがいい?
「……ちょっと失礼するね、御不浄に……」
「いえ!」
「あの!」
クランとゼンジさんがそろって立ち上がった。
ゼンジさんが、頬を染めている。
「美波浮者、どうか見届け人になってください」
「見届け人……?」
「美波、お願いします。ハナムンでは婚姻には見届け人が必要なんです。普通、周りで一番偉い方にそれをお願いする習わしです」
えっ、なに、今がそれなの……!?
急すぎて、びっくりだよ!
「わ、わかった……」
わたしが改めて席に着くと、ふたりも席についた。
「クラン、僕は立派な薬師になる。なにがあっても、どんなときも、クランが必要とする限り、何百万回でも何千万回でも、君の怪我を治す。ずっと君の側にいる、命の限り」
「ゼンジ、わたしはあなたの妻として、あなたを支え慈しみます。何百万回でも何千万回でも、この命のある限り、あなたを戸口で送り出します」
あとで聞くところによると、戸口で送り出すというのは、ハナムンでは誓いの言葉の常套句なのだそう。
貞淑な妻になります、というような意味合いらしい。
二人がわたしのほうを向いた。
「異論がなければ、見届けました、と」
わたしはうれしくて満面の笑みを浮かべていた。
「見届けました」
クランとゼンジさんが互いの手を取った。
頬を赤らめたクランの可愛らしい姿。
ゼンジさんの喜びに満ちた笑顔。
おめでとう!
見たかったものがようやく見れた気がした。
それなのに、わたしの視界が涙でかすんでくる。
「美波、なぜ泣くのですか?」
「うわーん、うれし涙だよぉ、ふたりが結ばれてよかったよ~!」
いつの間にか、クランに背中をポンポンされていた。
あれー、なんか、あやされてる?
姉はわたしなのに。
……でも、まあいっか。
それから約一か月の準備期間を経て、クランとゼンジさんは結婚のお披露目をお寺で行うことになった。
サイシュエン一の古刹の一人娘の結婚式。大名、領地中の守長らが一同に集まるものだと思っていたら、クランが婿を迎えるのではなく、嫁に出た、つまりはファ家の取り仕切る式ではなく、ゼンジさんの実家クム家が取り仕切る式となったことで、その規模や対外的な影響もはかなり小さくなった。
でも、クランにとっては、本当にクランを思ってくれる人たちにお祝いしてもらえるようになったのだから、これはこれで喜ばしいことだ。
大名や各地の守長らから手紙や贈り物などが寺宛てに届いたが、守長一族が自ら足をはこんだのは近隣の町村にとどまった。
逆に、大名家から誰かしらが来るとなると、クム家では対応できないので困ってしまうのだという。
確かに、一介の薬師見習いの結婚に大名一族が来るなんて、考えたらおかしいので、そうだなと思う。
花嫁衣装を身に着けたクランは本当に美しかった。
ハナムンの結婚の装いは、ふたりともお揃いの、水色、黄色、茶色の着物を着る。
色にはそれぞれ、天、ユーファオーの樹、大地の意味があるらしく、着物にはユーファオーの樹や葉の刺繍が入っている。
二人に多くの恵みが与えられますように、という願いが込められているそうだ。
わたしの贈った首飾りと耳飾りをつけて、クランはゼンジと一緒に本堂の祭壇の前で、コルグさんに経をあげてもらっている。
なんでかわからないけど、さっきから感動で涙が止まらない。
こんなに幸せが溢れる二人の姿、目に焼き付けておきたいのに。
うう、涙よ、止まれ……。
お披露目からさかのぼること約三週間前。
旬さんがふたりのために結婚指輪を作ろうか、といってくれたけど、旬さんが具現化するものはすべて灰色か黒になってしまうのでちょっと考え物だ。でも、ガラスや鏡のような感じできなくはないので実際に作ってもらったら、硬度もガラスみたいにもろかったので、やはり結婚指輪は難しいという結論になった。
「色がお祝っぽくないんだよね……」
「なら、ユーファオーの樹でなにかつくるか。それに俺が祝福を付与すればいいんじゃないか?」
「でも、旬さんの浮を付与すると、なんでも灰色っぽくなっちゃうんだよね。もともと灰色とか黒なら別にいいんだけど」
「じゃあ、灰色の指輪に、ユーファオーの樹の飾りでも付けたらどうだ?」
「うん? うーん……」
旬さんにそういわれたとき、わたしの頭になぜか、ハインリヒさんの匂い袋が思い出された。
あのとき、匂い袋の紐の先についていた赤い珠。
あれはクランのアクセサリーを作ったときに残ったユーファオーの樹の木ビーズだ。
クランにいわれて譲ってあげたものだ。
なぜか急にその赤いビーズが頭に浮かんだ。
赤い珠、赤いピン……。
何度となく頭に浮かんでくるピンのイメージ。
結局わたしにはこれが一体何を意味しているのかが全然分からない。
ピン、ピン、安全ピン……。
ん?
「安全ピン?」
「どうした?」
「えっと……、なんだろう、旬さん、安全ピンって作れる?」
「安全ピンて、あの缶バッジとかについているあれか?」
「缶バッジか、バッジって良くない?」
「そうか? 子どもがつけるものじゃないのか?」
「あれ……そうかな、じゃあ変かな……」
なんか今すごくいい案が浮かんだような気がしたんだけど……。
うーん……。
「別に作る分にはかまわないけど、こうか?」
旬さんが手のひらをぐっと握り、開くと、そこには無数の安全ピンがあった。
どれもマットな灰色をしている。
「わあ、たくさんあるね」
「缶バッジの缶に当たろところを、ユーファオーの樹で作るのか?」
「って思ったんだけど、子どもっぽいっていわれたら、なんかそうとしか思えなくなっちゃったなあ……」
「もう一回ユーファオーの樹に行ってみるか? 俺ももう少しエレベーターの改良ができそうなんだ。ハインリヒの浮に触れたおかげで、浮流への理解もかなり深まったしな」
「あ、そういえば、浮と流は全然違うっていってたよね。具体的にどう違うの?」
「そうだな、美波にも分かりやすい例えでいうと……。テニスボールが売っているの見たことあるか?」
「えーと、確か円柱みたいなプラスチックの筒状の箱に入って売っていたような……」
「うん、それ。流は、そのテニスボールが箱の中でくるくる回転しているイメージ。浮は、そのボールが超高速回転しているイメージだ」
「えっ、超高速回転?」
「そうだ。だからぱっと見同じように見えるんだけど、その中のボールの回転速度とか圧力とかが段違いなんだ。だから、対流術を想定していたシールドとシェルターではハインリヒの攻撃に対応できなかった。あのときカーツがハインリヒの攻撃を受けてくれたから、浮での攻撃や敵意というものがどういうものかがわかって、それで反撃できたんだ」
「そうだったんだあ。カーツさんはその立役者だったんだね。お礼しなきゃなあ。クランのアクセサリーを手伝ってもらったお礼もまだだし」
そんな段違いの攻撃を受けても立っていられたカーツさんて、本当にすごい人なんだ。
頭の中までマッチョって感じで、わたしにはちょっと理解できないことが多いけど、ハインリヒさんとはすごく通じ合っていたし、武人や軍人には、そうでないとわからない世界みたいなのがあるんだろうな……。
多分、わたしには一生わからないや。
「そういや、カーツの様子はどうなんだ? トンビに油揚げをさらわれて」
「ちょっと、トンビも油揚げも、言い方! でも、不思議とカーツさん落ち着いているんだよね。というより、なんかどこかほっとしたような感じ。カーツさんも自分とクランでは合わないかもって思っていたのかも」
「ふーん、まあ、今度顔を合わせたら流の鑑定でもしてやるか」
「もう、なにその上から目線」
「俺は浮者様だからな」
「ハインリヒさんの悪いところだけを見習うのはやめてください」
「でも、美波はサイシュエンのユーファオーの樹に浮を注力するって約束してしまったんだろ? それなら少しはでかい態度を取ったっていいはずだ」
「うん……、ごめんね、勝手に約束しちゃって」
「まあいいさ。エレベーターをもっとうまく使えるようになればいい話だ」
「あ、そういえば、ソーセージはえこひいきっていうドイツのことわざだったみたいだよ。なにがそんなに気になっていたの?」
このあと旬さんは話をそらして、この質問には答えなかった。
そんなに言質が欲しかったのかな。
旬さん、お肉好きだからなあ。
その翌日、わたしたちはユーファオーの森に向かった。
いつものようにローワンさんとカーツさんに付き添いを頼んだ。
ふたりで木に触れると、わたしは例のごとく睡魔に襲われた。
あっという間に時間が経ち、旬さんに肩をたたかれて目が覚めた。
「美波、いい案が浮かんだ。早く帰って試そう」
「ん……、うん」
目をこすりながらうなづいていると、なぜか手になにかを握っていた。
見ると、赤いつぼみのようなものだった。
「なにこれ……」
ローワンさんとカーツさんが確認してくれた。
「これはユーファオー樹のの花のつぼみではないでしょうか?」
「ユーファオーの樹の?」
樹を見上げてよく目を凝らすと、確かに枝のところどころに赤くぷっくりとしたものがついていた。
「へー……、ユーファオーの樹は赤い花が咲くんですね」
「いえ、花は青です」
「え、青?」
「マヌーケルンの夜、一斉に花が開くのですが、花はすべて一晩で消えてしまうのです。それと同時に、この地に浮者が舞い降ります」
「じゃあ、浮者がまたやってくるんですね?」
「それはわかりません。マヌーケルンの夜が訪れたからといって、必ずしも浮者が来るというわけではないのです」
「そうなんですね……。なんか、その感じだと、花が咲いてもわたしには見えそうにありませんね」
相変わらず、不思議な樹なのねぇ……。
そう思いながら視線を上げると、目の前に赤いものが降ってきた。
「あっ、また?」
コロコロと転がってわたしの足元にまた赤いつぼみが転がった。
えっ、大丈夫なの?
今度こそ、樹の病気?
「つ、つぼみが落ちるなんておかしくない? 旬さん!」
「いや違う、樹の意志だ」
「ええっ? でも、花が咲く前につぼみが落ちちゃうなんて……。ハナムンの人の信仰の対象なのに……」
「美波、樹に向かってなにかいってみろ」
「なにかって?」
「わからん」
「わからんって……」
ええと、なんだろう……。
とりあえず、枯れずに元気でいてください。
ハナムンの国を守ってください。
ええと、あと、少しでもいいので浮流が見えるようにしてください……。
そっと樹を見上げると、いつかのように一斉に降ってきた。
前回は枝だったけど、今回は赤いつぼみだった。
雨のようにざああっと落ち、ばらばらとはじけるようにしてあたりに飛び散っていった。
「……わああっ!」
頭をかばうと、ちょうど腕と頭の間にできたくぼみに赤い実がたまった。
ひえ~……、これってわたしのせい?
わたしのせいじゃないよね?
わたしのせいじゃないって、誰かいって……。
「美波浮者、動かないで!」
突然のローワンさんとの声に、わたしは頭をかばった状態のまま、硬直した。
え、まさか、赤毛猿?
また赤毛猿ですか!?
「美波浮者、ゆっくり腕を降ろしてください。つぼみを落とさないように」
「落とさないように?」
いわれたとおりにゆっくり腕を降ろした。
全部を落とさないようにするのはやっぱり無理で、足元にコロコロ転がっていくのが見えた。
「すいません、落ちちゃいます~っ」
「多少は仕方ありません。できるだけ落とさないように」
「はい……」
ようやく腕を前にして、落とさずに済んだつぼみを眼下に見た。
だいたい二十か三十くらいだろうか?
「すみません、結構落ちちゃったみたいです……」
足元を見ると、赤いつぼみが見当たらない。
きょろきょろ見渡しても、あたりにあれだけ落ちて散らばったはずの赤いつぼみが一つもなくなっていた。
ま、まさか、また動物が来ていっせいに取っていったのだろうか?
良く見ると、足元には茶色い物体が無数に転がっていた。
あれ、まさか、枯れたつぼみ?
わたしは腕の中を見た。
不思議と、腕の中にあるつぼみは赤いままだった。
どうなってるの、これ……。
「美波浮者、見てください。あなたが持っているつぼみだけが色を失っていない」
ローワンさんとかーつさんがそれぞれ、枯れたつぼみを手にしていた。
「ど、どういうことですか? わたしのせいですか? 旬さん……」
旬さんがわたしの腕からつぼみのひとつをつまみあげた。
旬さんの手にしたつぼみは色あせずにあざやかな色を保っている。
「樹の意志だ。樹がこれを美波にくれたんだろう」
「え~っ、浮流を見えるようにしてくださいっていったからかなあ……。なにもこんなにたくさんつぼみを落とさなくても……。今年は花が咲かなくなっちゃったんじゃ……うわああ……、どうしよう、わたしが変なことお願いしたせいなの……?」
ローワンさんによると、つぼみが落ちるということは今までになかったそうだ。
カーツさんもユーファオーの森には何度も行で来ているが、この時期つぼみがつくことは知っていたが、つぼみが落ちていることは一度も見たことがないという。
「旬浮者のおっしゃるように、樹の意志ではないでしょうか? 枝が自然に落ちてきたのと同じように」
「でも、このつぼみをどうすればいいんだろう。ユーファオーの樹だから、なにか薬効がありそうですよね?」
「かもしれませんが、わたしには……。帰って薬房の者に聞いてみましょう」
「美波浮者、わたしが持ちましょう」
カーツさんが持っていた布を広げてくれた。
わたしがそこへつぼみを降ろそうとすると、旬さんが素早くわたしの目の前に黒い文字を引いた。
「樹が下ろすなといってる」
「えっ、下ろすな? じゃあ……ど、どうすればいいの?」
「手渡すみたいだぞ」
「手渡す? カーツさんに手渡せばいいの?」
旬さんのいったことを伝えると、ローワンさんとカーツさんは顔を見合わせた。
「しかし、我々が触ったら、つぼみは枯れてしまいます」
「えっと、旬さんがいうには、手放すのはだめで、手渡すのはいいらしいんですけど……」
「しかし、せっかくのユーファオーの樹の恵みです。むやみに無駄にすることになっては……」
旬さんが続けざまに空中に文字を書いた。
「樹は美波の手から、ハナムン人に手渡してほしいらしい。すぐに決められないなら、トラントランに関わる人というように暫定的に決めればいいといっている」
「……旬さん、すごいね。いつの間に樹ともおしゃべりできるようになって……。うらやましいよ……」
「とにかく、美波が決めるもののようだ。それよりも前に手放してしまったもの、美波の意志がないままに他人が触れたものはみんな力を失うそうだ」
「ええと、じゃあ、トラントランに関わる人のために使います! これでいい?」
「多分な」
「えと……、もう布に下ろしてもいいんだよね?」
恐る恐る布につぼみを降ろすと、色はあせずに赤いままその場にとどまった。
いや~……、本当に不思議ばっかりの木で驚くよ……。
ローワンさんとカーツさんも不思議そうに顔を見合わせるばかりだ。
「それで、旬さん、このつぼみにはなんの力があるの?」
「それは俺にもよくわからない」
下手くそな関西弁で思わず突っ込みたくなる答えだった。
寺に戻った後、ひとまずつぼみを持ってコルグさんを訪ねた。
「これがつぼみですか……。これまで浮者がつぼみを持ち帰ったということは、聞いたことがありません。それも、話を聞いた限りには、確かに樹のほうから持ち帰ってほしかったというような印象を受けますね」
「コルグさんも知らないんじゃ、なんの力があるのかわからないですね……」
「しばらく様子を見て、少しずつ調べてみるほかないのではないでしょうか。あるいは、ハインリヒ浮者に手紙を書いてみるとか」
「そっか、そうですね!」
そうじゃん、ハインリヒさんを頼っちゃおう!
仲良くなっておいてよかったよー!
旬さんがさっと指を滑らせた。
「今日ユーファオーの樹の浮を見てきたが、安定していたし、樹も細くなったりというようなことはなかった。近いうちに、エレベーターの改良も兼ねて、しばらくトラントランを空けることになると思うが、構わないか?」
「はい、それはもちろんです。必要な物資や人手がありましたら、おっしゃってください。いつごろを予定されていますか?」
「とりあえずは、クランとゼンジのお披露目が終わってからだ。それまでにそちらでもなにか俺達に要望があれはいってくれ。美波が約束したとおり、サイシュエンのユーファオーの樹のことは、俺達ふたりで約束を守る」
「ありがたく存じます」
コルグさんの部屋を出て、わたしたちは薬房へ向かった。
薬房の長であるムッタさんにつぼみを見せてみた。
数えてみたら、二十一個あったので、ひとまず可能性のありそうなことは調べてみてもいいだろう。
わたしは旬さんにいわれたとおり、つぼみの一つをムッタさんに手渡した。
「初めて見ますし、聞いたことがありませんね。つぼみといっても、非常に硬く、また色もあせていない。匂いは……しませんね」
「ユーファオーの樹のつぼみですし、なにかしらの薬効があるのではと思うのですが、調べてみてもらえますか?」
「このような貴重なものをわたしに預からせていただいてもよいのですか?」
「はい、ユーファオーの樹からハナムン人に手渡してほしいと頼まれたのですが、いったいなんの力があって、どう使って欲しいのかがわからなくて……。すみませんが、お力をお貸しください」
「もったいないお言葉です。できる限り力を尽くしてみましょう」
「ありがとうございます」
「使い方というところで行くと、ターマンのところへも持っていくとよいかもしれません」
「あ、なるほど、そうですね!」
わたしはターマンさんを訪ね、二つ目のつぼみを手渡した。
「ユーファオーの樹のつぼみとは……。だとすれば、なにかしら流術に反応するやもしれませんね。クワンランや、そのほかの楽器の演奏を聞かせてみましょう」
「ありがとうございます。このつぼみの使い方がわかったら、教えてください」
つぼみの残りはあと十九個。
祭壇にでも預けておきたいけど、わたし以外がむやみに触ると枯れてしまうらしい。
部屋に戻って、きちんと管理すべく、化粧箱の一角を開けて、そこへ並べた。
布は畳んでしまう。
カーツさんに後で返さないと。
つぼみのひとつをつまみ上げる。
ユーファオーの樹じゃなかったら、このつぼみこそ、クランの耳飾りにでも使いたいくらいの素材なんだけど。
「この赤がかわいいんだもん」
そのとき、ふっとまた頭に赤いピンのイメージが沸いた。
赤、赤……。
ピン……。
うーん……。
でも、ここまできたら、もう絶対ユーファオーの樹がわたしになにかさせたがっているようにしか思えない。
つぼみを手にしながら、意識がふっと持っていかけるように眠くなった。
わたしは夢を見ていた。
ユーファオーの樹に触れてから見るようになった、あの夢だ。
同じ夢を見ているということはわかる。
多分、ユーファオーの樹がわたしにさせたがっているなにかなのだろうとも思う。
だけど、きっと目覚めたらまたこの夢のことを忘れてしまうな違いない。
赤、ピン、つぼみ。
一体、どうすればいいの?
「美波、大丈夫か?」
旬さんに揺り起こされて、目の前に浮かぶ文字を見つけたとき、やはり私の夢は駆け足に通り過ぎて行ってしまっていた。
「まあ、美波も一応浮者ってことだよ」
「一応って……」
「まったくないようでいても、わずかな浮が美波の中にちゃんとあって、それがユーファオーの樹と反応しあっているんだよ。そんなに焦らなくてもいい。気長に考えていれば、いつかはわかるよ」
「そうだといいけど……」
「それよりも、俺の新しいエレベーターの機能を見たくないか?」
「みたい!」
旬さんの左手が仕草すると、目の前にエレベーターが現れた。
中に入るといつものように、ボタンと到着までの時間を知らせるパネルがある。
ドアの面以外はガラス張りだ。
「一番右上のボタンが、ハインリヒだ。あいつが無事イスウエンに着けば、俺達もイスウエンに行ける」
「そうだね! そうしたら、ハインリヒさん、ビックリしちゃうかも。あ、でも、ムラークくんの星座盤を持って行ってあげればいいよね」
「ムラークも一緒に行けばいい」
「そうだよ! ハインリヒさん、喜ぶよきっと!」
「まあ、このように、誰かが移動中だとわかれば、そいつを追っていろんな町や村にいけるってことはわかった。今までは、人物の浮流ややユーファオーの樹の浮をたよりに、エレベーターの移動をしてきた。だが俺は気づいてしまったんだ」
「なにに?」
「俺はハナムンの地理が全くわからない。地図も一度も目にしたことがない」
「うん」
「美波は地図を見たことがあるが、ほとんどの町や村には行ったことがない」
「うん」
「俺達は当てにならない」
「うん……。それはそうだね」
「だったら、当てになるやつを乗せればいい」
「当てになるやつ?」
「そうだ。目的地にいったことがあるやつにエレベーターに乗ってもらう。そして、そいつの記憶を頼りに、エレベーターを飛ばすんだ」
「記憶を頼りに? そんなことができるの?」
「まだ試してないから本当に可能かはやってみなければわからない。だが、グアンさんやターマンさんの話を聞いて、他社の意識に働きかけるっていうことがうまくできれば、不可能ではない」
「そっか、最終的な目的地に一度で行けなくても、数珠つなぎするように近づいていけば、目的地までたどり着けるね!」
「まあ、実際にやるのはお披露目が終わってからだ。それまでは、そうだな、誰がどこにいったことがあるのかを知りたいな」
「わかった! それなら、任せて! みんなに聞いてまとめてみるよ」
「よし、頼んだぞ」
「だけど、旬さんて本当にすごいね! 記憶を頼りにか……。あっ、ねえ、それってもしかして、わたしの記憶を頼りに、日本に戻るっていうことはできないの?」
「試してみてもいいけど、またハナムンにもどれるとは限らないぞ。いいのか、クランとゼンジのお披露目を見なくても」
「そ、それはだめ! 終わってから試そう」
「そうだな。でも、そんな簡単なことで戻れるくらいなら、イスウエンの浮者たちも地球に戻ってると思うけどな」
「……そ、そうなんだ……」
浮流がわからないわたしには、そのあたりの加減がよくわからない。
けど、持ち上げといて落とされるのはちょっとがっかりしてしまう。
まだ試してもないのに。
「それで、一緒に乗ってもらう人専用の席を用意した」
旬さんがぱっと指を指すと、エレベーターの一角に椅子が現れた。
椅子にはなにやら手足を止めるらしい怪しげなバンドがついている。
さらには頭に取り付けるらしい、なんというか、電気椅子の電極のような帽子みたいなものがある。
「旬さんなんか……、電気椅子みたいなのがでてきたんだけど、まさか、これにその人を縛り付けるの……?」
「相手の記憶に浮術をかけるからな、恐らくはこんな感じになると思う」
「だめだよ、絶対だめでしょ、これは!」
もう、信じらんないよ!
なんでこんな拷問の道具みたいやつなの!
「却下します!」
「なんでだ、まだ一度も試してないのに」
「このビジュアルがもう駄目だよ!」
「ビジュアルって……、そういうけどなあ、俺だっていろいろ考えたり調べたりして作ってるんだぞ」
「だめです、こんな拷問か死刑の道具みたいなの」
「いや、拷問じゃないし、死なない程度にやるし」
「だめ! ぜったいだめ!」
「でも」
「だめなものはだめ! これをどうしても使うっていうなら、旬さんのこと嫌いになる!」
旬さんの手が止まり、しばらく返事がなかった。
「嫌いになったって、美波はどうせ俺を頼らなきゃ生きていけないんだぞ」
そういうこというの?
わたしはむっとして、旬さんの手を振り払うと、椅子に座って見せた。
「じゃあ、旬さんは、わたしがこの椅子にこうやって縛られても平気なの?
記憶に浮術をかけられて、手足を縛られても、抵抗もできずされるがままでも平気なの?」
またしばらく返事がなかった。
「やばい、想像したらなんかエロい」
わたしは初めて旬さんの左手にグーパンチを食らわせていた。
8
あなたにおすすめの小説

愛された側妃と、愛されなかった正妃
編端みどり
恋愛
隣国から嫁いだ正妃は、夫に全く相手にされない。
夫が愛しているのは、美人で妖艶な側妃だけ。
連れて来た使用人はいつの間にか入れ替えられ、味方がいなくなり、全てを諦めていた正妃は、ある日側妃に子が産まれたと知った。自分の子として育てろと無茶振りをした国王と違い、産まれたばかりの赤ん坊は可愛らしかった。
正妃は、子育てを通じて強く逞しくなり、夫を切り捨てると決めた。
※カクヨムさんにも掲載中
※ 『※』があるところは、血の流れるシーンがあります
※センシティブな表現があります。血縁を重視している世界観のためです。このような考え方を肯定するものではありません。不快な表現があればご指摘下さい。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

私が王子との結婚式の日に、妹に毒を盛られ、公衆の面前で辱められた。でも今、私は時を戻し、運命を変えに来た。
MayonakaTsuki
恋愛
王子との結婚式の日、私は最も信頼していた人物――自分の妹――に裏切られた。毒を盛られ、公開の場で辱められ、未来の王に拒絶され、私の人生は血と侮辱の中でそこで終わったかのように思えた。しかし、死が私を迎えたとき、不可能なことが起きた――私は同じ回廊で、祭壇の前で目を覚まし、あらゆる涙、嘘、そして一撃の記憶をそのまま覚えていた。今、二度目のチャンスを得た私は、ただ一つの使命を持つ――真実を突き止め、奪われたものを取り戻し、私を破滅させた者たちにその代償を払わせる。もはや、何も以前のままではない。何も許されない。

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

わたしの下着 母の私をBBA~と呼ぶことのある息子がまさか...
MisakiNonagase
青春
39才の母・真知子は息子が私の下着を持ち出していることに気づいた。
ネットで同様の事象がないか調べると、案外多いようだ。
さて、真知子は息子を問い詰める? それとも気づかないふりを続けてあげるか?

裏切りの代償
中岡 始
キャラ文芸
かつて夫と共に立ち上げたベンチャー企業「ネクサスラボ」。奏は結婚を機に経営の第一線を退き、専業主婦として家庭を支えてきた。しかし、平穏だった生活は夫・尚紀の裏切りによって一変する。彼の部下であり不倫相手の優美が、会社を混乱に陥れつつあったのだ。
尚紀の冷たい態度と優美の挑発に苦しむ中、奏は再び経営者としての力を取り戻す決意をする。裏切りの証拠を集め、かつての仲間や信頼できる協力者たちと連携しながら、会社を立て直すための計画を進める奏。だが、それは尚紀と優美の野望を徹底的に打ち砕く覚悟でもあった。
取締役会での対決、揺れる社内外の信頼、そして壊れた夫婦の絆の果てに待つのは――。
自分の誇りと未来を取り戻すため、すべてを賭けて挑む奏の闘い。復讐の果てに見える新たな希望と、繊細な人間ドラマが交錯する物語がここに。

冤罪で辺境に幽閉された第4王子
satomi
ファンタジー
主人公・アンドリュート=ラルラは冤罪で辺境に幽閉されることになったわけだが…。
「辺境に幽閉とは、辺境で生きている人間を何だと思っているんだ!辺境は不要な人間を送る場所じゃない!」と、辺境伯は怒っているし当然のことだろう。元から辺境で暮している方々は決して不要な方ではないし、‘辺境に幽閉’というのはなんとも辺境に暮らしている方々にしてみれば、喧嘩売ってんの?となる。
辺境伯の娘さんと婚約という話だから辺境伯の主人公へのあたりも結構なものだけど、娘さんは美人だから万事OK。

天才天然天使様こと『三天美女』の汐崎真凜に勝手に婚姻届を出され、いつの間にか天使の旦那になったのだが...。【動画投稿】
田中又雄
恋愛
18の誕生日を迎えたその翌日のこと。
俺は分籍届を出すべく役所に来ていた...のだが。
「えっと...結論から申し上げますと...こちらの手続きは不要ですね」「...え?どういうことですか?」「昨日、婚姻届を出されているので親御様とは別の戸籍が作られていますので...」「...はい?」
そうやら俺は知らないうちに結婚していたようだった。
「あの...相手の人の名前は?」
「...汐崎真凛様...という方ですね」
その名前には心当たりがあった。
天才的な頭脳、マイペースで天然な性格、天使のような見た目から『三天美女』なんて呼ばれているうちの高校のアイドル的存在。
こうして俺は天使との-1日婚がスタートしたのだった。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる