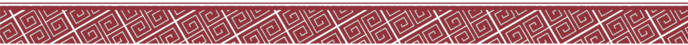41 / 59
34、愛しい友のそのとき
しおりを挟む怒ったせいなのか、ユーファオーの樹の影響なのか、わたしその夕方から発熱して寝込んでしまった。
準備に忙しいはずのクランとゼンジさんが代わる代わる様子を見に来ては、世話を焼いてくれた。
もうろうとしながらも、夢を見てた。
またあの夢だった。
夢の中に、はっきりとつぼみが出てきた。
わたしはそのつぼみを誰かの胸元に差そうとしていた。
水色の着物を着ている誰かの胸元に。
つぼみの下には灰色の尖った針のようなものが出ていた。
ピンだ……。
そう思ったところで、目が覚めた。
「美波、大丈夫か?」
旬さんの手がよじ登って来て、わたしの額に触れた。
「旬さん、わかったよ……。あのつぼみの使い方……」
「そうか、よかったな。まだ熱がある、静かに寝てろ」
「また忘れちゃうとやだから、話しておくね……」
わたしはもうろうとしながらも、夢で見たことを伝えた。
自分の口が喋っているのはわかっていたけれど、途中から意識が遠のいて、なにを話しているのかわからなくなっていた。
その日はもうわたしは目覚めなかった。
そして翌朝、わたしの熱はすっかり引いていて、気分も嘘のようによくなっていた。
「美波、悪かった。エレベーターの椅子は考え直した」
「よかった、旬さんならそういってくれると思った」
「まずは、つぼみでピンをつくろう」
「ピンって?」
「まさか、覚えてないのか?」
旬さんの手が一瞬止まり、しばらくした後、昨日わたしが話したということを空中に書き始めた。
「わたしが、そういったの? ごめん、全然覚えてない……夢を見ていたのかな……」
「はっきりと、確信があるみたいだったぞ」
「そっか……。それなら試してみようか」
わたしは化粧箱の中からつぼみを取り出した。
「これは誰に?」
「これはクランに」
旬さんに手渡した。
旬さんが軽くつぼみを包むと、ゆっくりと指を開いた。
手の中には、つぼみのピンバッジができていた。
「もうひとつ」
「これはゼンジか?」
「うん」
もうひとつも同じようにピンバッジになった。
「もうこれが結婚祝いでいいんじゃないのか?」
「そうかな……」
「じゃあ、とりあえず俺がこのバッジに祝福をしておく。いつまでも健康で互いを思いやって生きて行けるように」
「わたしも。クランとゼンジさんが、いつまでも笑顔でいられますように……」
わたしの手の中に、ふたつのピンバッジがある。
赤いつぼみのピンバッジ。
わたしに頭に度々浮かんできたものは、これだったのだろうか。
頭はすっきりしているけれど、いまいちぴんと来ていなかった。
「あ、箱がいるよね」
「カーツに作らせるか」
「言い方!」
工房を訪ねるとカーツさんはおらず、そこにいた小坊主さんに呼んできてもらった。
ひとまず借りていた布を返した。
「カーツさん、すみません、忙しかったですか?」
「いえ、ひと段落ついたところでしたから」
「お願いがあって。これが入る桐の箱を作ってほしいんですけど」
わたしが手を開いて見せると、カーツさんはわずかに目を見開いた。
「これは先日のつぼみですか? この下の灰色の台座と留め具のようなものはなんでょうか。とても精巧な形をしていますね」
「これは、ピンバッジというもので、こういうふうに使うのを夢で見たんです」
「夢で?」
「はい。クランとゼンジさんのお祝いにするんです」
カーツさんは一瞬の間をおいて、うなづいた。
「わかりました。大きさはこれくらいでいいですか?」
「はい、お願いします。それと……」
はたから見る限りには大丈夫そうな気がしていたけど、さっきの間からすると、やっぱりクランのこと全然気にしていないってわけではないんだね……。
「あの、元気、出してくださいね……」
「はい?」
「クランのこと」
「ああ……」
カーツさんはわずかに目を伏せた後、まっすぐとした目を向けてきた。
「美波浮者のおかげで、クラン様にとって一倍良い婚姻となったと思います。自分の未熟さを知る良い機会でもございました」
「……そっか、じゃあ、気持ちの区切りはついたんですね?」
「はい」
やっぱり、こういうところはきちんと心の整理をつけられるんだ。
それだけでもすごく精神力の高い僧侶としても人としても立派なことだと思う。
「カーツさんにはいままで、わたしやクランのためにいろいろとお世話になってきました。旅の同行から始まって、アクセサリー作りに、ハインリヒさんのときにはの盾になってわたしたちを守ってくれました。その怪我のせいで、演武の奉納をご家族には見てもらえませんでしたが……」
「僧侶として当たり前のことをしたまでです」
「そうかもしれませんが、改めてお礼をいわせてください。ありがとうございます」
「身に余るお言葉、ありがたく存じます」
「それで、カーツさんになにかお礼をしたいんですが……」
「いえ、そのような見返りを求めて行ってきたことではございませんので、お気持ちだけありがたく頂戴いたします」
なんとなくそういう気もしてたんだよね。
「そうですか。カーツさんならそういう気もしていました。一応、旬さんはカーツさんの触りの鑑定をっていってたんだけど。でも、カーツさんには必要なかったですかね。ええと、でも、なにか気が変わったり、わたしたちにできることがあれば声をかけてください」
「変わりました」
「えっ」
「旬浮者の触りの鑑定を受けたく存じます」
「気が変わるの早くないですか」
「すみません、旬浮者には何度も怪我を治療していただいておりましたし、まさか鑑定をしていただけると思わなかったので。それに触りを理解することは、術を高めるうえでとても重要なことですので。夏には階級試験もございます」
そっか……。確か試験は二年に一度だったよね。
じゃあ、今は僧侶のみなさんにとってはとても大事な時期でもあるんだ。
「あ、先にいっておきますが、お礼なので鑑定のお礼の品物などは必要ありませんから。お礼のお礼なんておかしいですもんね」
「お心遣い感謝いたします」
旬さんがカーツさんの触りについて鑑定し、いくつかの質問を受けた。
わたしは翻訳しながら、ときどき自分でも印帳にメモを取る。
カーツさんは、ときどき、おおっと感嘆を上げたり、ふむふむとうなづいたり、とても熱心に話を聞いていた。
やっぱり、トラントランの人たちって、すごくまじめなんだよね。
僧侶のみんなが試験で成果を発揮できるといいなあ。
「旬浮者、美波浮者、素晴らしいご助言の数々、本当にありがとう存じます。今後の鍛錬に生かしていきたいと存じます」
「はい、カーツさんならきっとよい結果につながると信じています。頑張ってください」
わたしたちは工房を後にして、ムラークくんを探した。
「ムラークくんにもお礼をしたいけど、彼もなにもいらないっていいそうだなあ。鑑定はそう何回やってもいいものなの?」
「したところで、触りが変わっていなければ鑑定する意味もない」
回廊を歩いていると、庭を挟んだ向かい側に、ちょうどマシンくんと一緒に荷物を運んでいるムラークくんを見つけた。
「ムラークくん!」
「美波浮者、ご機嫌麗しく。なにか御用ですか?」
「うん、探していたの。少し話せる?」
「では、荷物を運び終えたら、伺います」
「うん、わたしの部屋で待ってるね」
その後、ムラークくんがマシンくんと一緒にやってきた。
「あれ、どうしてマシンくんまで?」
「もし旬浮者と日本語でお話しするようならば、聞き取りの勉強をさせていただきたく」
「あ、そうなんだ。えっと、あんまり日本語は使わないかもしれないけど、じゃあどうぞ」
二人の少年と差し向かって椅子に座った。
「ええとね、ムラークくん、まずはクランのアクセサリーのお手伝いをしてくれて本当にありがとう。後半はほとんどムラークくんがやってくれたよね。しかも、わたしがやるよりもずっときれいに。本当にありがとう」
「いえ、こちらこそ、貴重なユーファオーの樹の加工をさせていただけて、感謝しております」
「ああ……。そっか、ユーファオーの樹の加工をすると、流の扱いが上手になるんだっけ? どう、効果はあった?」
「はい、ここでお見せしてもよろしいでしょうか?」
「あ、ぜひ。わたしはみえないけど、旬さんはちゃんと見てるからね」
ムラークくんは両手を合わせると、集中するように息を整え目を閉じた。
わたしにはいつものようになにも見えない。
ムラークくんの静かな呼吸だけが聞こえている。
「いかがでしたか?」
「旬さんどう?」
「流がかなり安定するようになった。音やリズム、速度もほぼ一定だ」
旬さんの言葉を伝えると、ムラークくんは嬉しそうに笑った。
「ありがとうございます! これで、次の試験は階級が上がるかもしれません」
「そうなんだ、がんばったんだね!」
「美波浮者のおかげです」
「どういたしまして。ところで、その階級試験って、やっぱりみんな受かりたいものだよね?」
「はい、日ごろの成果を試す機会でもありますし、階級が上がればそれだけ使える流術も増えます。マシンのように住職を目指すものは当然ですが、僕はグアン師父のように研究を極めたいので、その目的に近づくということでもあります。なので、やっぱり階級は上がりたいです。故郷への手紙にも修行の成果があったと書きたいです」
そっか、幼くてもひとりひとり目標に向かって、一段階ずつ前進しようと頑張っているんだな。
なにか応援できればいいなと思うんだけど。
そういえば、前にマシンくんに小坊主さんたちの鑑定をお願いされたっけ……。
「ねえムラークくん、以前、わたしのへやにクンくんたちを連れてきたよね?
あの後、マシンくんからは五人の流の触りを鑑定してほしいっていわれたんだけど、ムラークくんはどう思っているの?」
ムラークくんとマシンくんは顔を見合わせた。
「あのときは、すみませんでした。みんな必死なので、僕も断り切れなくて。美波浮者は病み上がりでしたのに」
「そのことは大丈夫だよ。ムラークくんはどうして断り切れなかったの?」
「僕やマシンは家が恵まれていますから、実家に相談してお礼の品を用意してもらえました。でも、クンたちは、もともと家が裕福ではないのでお礼を用意できません。でも、寺の中で一緒に学ぶ僕たちにはそういう貧富は関係ありません。等しく学びの機会と己を磨く時間が与えられ、尊敬する師が指導してくださいます。裕福だからといって流が多いわけでも、術が巧みになるわけでも、精神的に優れているわけでもありません。己の心と向き合い努力を積み重ねることで、僧侶として成長するのです。
それなのに、僕はマシンから旬浮者に触りの鑑定をしてもらったと聞いたとき、単純に、いいな僕も見て欲しいと思ってしまいました。美波浮者と旬浮者のご厚意に甘えて、実家のお金を頼りに、鑑定をお願いしてしまいました。そのときは、自分のことしか頭になくて、鑑定を受けられない友のことを少しも思っていませんでした。
あとで、クラン様がお怒りだったと聞きました。自らの試行錯誤によってそれを見つけるのが修行。楽をしようとするなど、僧侶の風上にも置けないと。クンたちは自分の力で努力を続けているのに、僕は楽をしてしまったんだと思いました。
クンたちが、美波浮者と親しくなりたいといったとき、僕は二つの気持ちのはざまにいました。自分たちの力で己を磨く僧侶としての在り方をクンたちも簡単に手放そうとしていること、それに彼らが気づいていないことに対する危機感。その一方で、美波浮者と旬浮者がクンたちにご温情をかけてくださればいいなと願う期待。
僕自身、先ほど申しあげたとおり、流がうまく使えるようになったり、階級が上がったりすることはとてもうれしいです。でも、いま申し上げたことを踏まえると、単純に喜ぶべきことではないと考えます。僕は自分においても、友においても、僧侶としての本質を忘れるべからずと考えます」
……す、すごい。
わたしはムラークくんに圧倒されていた。
単純に、僕もマシンと同じです、というような返答が帰ってくると思っていたのに、すごく深く考えている。
しかも、この様子ではお礼をしたいといっても、受けてはくれなそうだ。
「ムラークくん、君は深い洞察力があるんだね」
「あ、ありがとうございます」
「それに、マシンくんはとても友達思いだし」
「は、はい」
ふたりの少年がめいめいにうなづいた。
そうだなあ、これは、お礼という形でクンくんたちの鑑定をするっていう方向で何とかまとまらないかなあ。
でも、どうすればいいんだろう。
マシンくんはクンくんたちにも鑑定をして欲しいと思っている。
ムラークくんはクンくんたちに僧侶としての本質を見失ってほしくないと考えている。
わたしはお礼という形をとって鑑定をしてあげたいと思っている。
うーん……。
「うーん……」
うーん……。
だめだ、わたしの頭だけではどうしたらいいのかわからないよ。
こんなときはいつもだったらクランに相談するんだけど、お披露目の準備で忙しいところを邪魔できないし。
二人を見ると、伺うようにわたしを見つめている。
うーん、だめだ、もうお手上げ。
わたしはふたりに降参の笑みを送った。
「ごめんね、もう白状しちゃう」
「え?」
「本当はね、ムラークくんにお礼をしたかったの。アクセサリーを手伝ってくれたことのね。カーツさんにはそのお礼に鑑定をしてあげたの。他にもいろいろとお世話になってるしね。それで、ムラークくんにもって思ったんだけど、鑑定はもうしちゃってるし、今ユーファオーの樹の加工で流の扱いがうまくなったっていうから、これじゃあ、なにもいりませんっていわれちゃうなあと思って。
それで、ムラークくんがクンくんたちの鑑定をして欲しいっていえば、それをお礼にしようって思ったの。でも、ムラークくんが予想以上に深いところまで考えていたから、それもだめかなって」
マシンくんが驚いたようにムラークくんを見た。
まさに「ムラーク、お前が一言いってくれれば」みたいな表情だった。
「それでね、ふたりに相談なんだけど、わたしたち三人はこう考えているよね。マシンくんは旬さんにクンくんたちの鑑定をして欲しい。ムラークくんはクンくんたちに僧侶としての本質を見失ってほしくないと考えている」
マシンくんとムラークくんがうなづく。
「わたしはお礼という形をとって前回受けられなかったみんなの鑑定をしてあげたらいいと思っている。これをなんとか上手に成立させられないかなあ? できれば、コルグさんやみんなに話しても、ちゃんと納得してもらえるような形で。わたしの頭じゃそこまで知恵が回らないの」
二人の少年が、はっと息を吸った。
「考えてみます!」
「はい、考えます!」
「できるだけ早い方がいいよね。試験まであんまり時間がないから」
「はい!」
そして、時間は元のお披露目の日に戻る。
お経が終わった後、わたしから贈り物を渡すことになっている。
ユーファオーの樹のつぼみのピンバッジだ。
「美波浮者と旬浮者から、ふたりの結婚のお祝いの品を下賜いただきます」
その声を合図に、わたしはクランの設えてくれた薄い黄色の着物で前に進み出た。
晴れがましいふたりの前に立って、わたしは泣きはらした顔で微笑んだ。
「結婚おめでとうございます。ハナムンで一番美しく貞淑な花嫁と、花嫁思いのハナムン一果報者の花婿に、永遠の幸せを願ってこれを贈ります」
クランとゼンジの水色の着物の胸元に、それぞれ赤いつぼみのピンバッジをつけた。
互いに深く首を垂れた。
厳かな雰囲気の中、わたしは頭を下げているあいだ鼻水が落ちないようにするので必死だった。
あとでクランに話したら、大笑いされてしまった。
それから広い客間に席を移して、宴会が始まった。
いつもは酒気のない寺が、にぎやかで華やかになった。
檀家さんたちや小坊主さんたちが大忙しで、祝いの御膳やお酒、お祝いの品を運んでいる。
いつも質素な御膳になれていたわたしには、お魚やお肉、卵や甘いお菓子など、目を見張るようなごちそうに目もお腹も驚いてしまった。
連席の僧侶たちも、今日は頬を染めてお酒を楽しんでいる。
周辺の守長たちの様子からすれば、御馳走もお酒も珍しくはないのだろう。
着ているものは当然礼服や普段よりいいものなのだろうが、とてもよいものを身に着けているという印象だ。
キリ家の末席にはマッカリもいた。
一応花嫁より地味な装いだったので、少し安心した。
ハナムンで初めてのお酒を頂いた。
ハナムンのお酒はクランの香りがしてする甘いものと、かなり辛口の蒸留酒があった。
久しぶりのお酒だったので、ペースがわからず、つい甘いお酒を飲みすぎてしまった。
酔い覚ましに席を外して、外の空気を吸うことにした。
心配したクランがゼンジさんについていくようにいってくれたけど、とんでもない。
ムラークくんがいたので、一緒に来てもらうことにした。
「はー、酔っぱらっちゃったなあ。お酒なんて、一年ぶりくらいだよ」
「あちらの東屋で少し休まれますか?」
「うん、そうしようかな……」
庭の離れにある東屋に腰を掛けた。
「ごめんね、ムラークくん。昼間から酔っ払いの面倒見させちゃて……」
「いえ、むしろ息がつけてありがたいくらいです」
ムラークくんでもそういうこというんだ。
あんまりお酒の席の雰囲気が好きじゃないのかな。
「ハナムンでは何歳からお酒が飲めるの?」
「普通は成人の十五歳くらいからですが、修行に身を置く僧侶たちは、師父の許しがなければ飲めません」
「成人が十五かあ、あと一年半くらい?」
「はい、そうです。えっと、クランが前に十七で結婚するっていってたけど、僧侶はこれも当てはまらないんだね?」
「そうですね。ただ、やはり家の状況もあるので、成人したら還俗する者もいますし、結婚のために還俗することもあります。寺の中で唯一結婚を許されるのは住職だけなのです」
ふーん、そうかあ……。
やっぱりお寺はハナムンの中でもそれなりに特殊な場所なんだね。
「ムラークくんはグアンさんみたいな師父を目指しているんだよね。星の研究の。そうすると、家庭を持たない流者としての道を歩むんだね……。すごいね……」
「いえ、僕は、その師父のような流者を目指していますが、いずれは家庭を持ちたいと考えています。祖父も研究者でありながら家族を大切にしていましたから」
「そっか……。ムラークくんのおじいさん、ロマンチストだもんね。ムラークくんは、おじいさんの研究を引き継ぐんだ。うん、偉い」
ん、じゃあ、ムラークくんも十七くらいで僧侶をやめちゃうの?
「ムラークくんはいつ還俗するの?」
「まだはっきりとは決めてませんが……。多分十七前後には……」
「えー……、そうなんだ……。せっかく仲良くなれたのに、そっか、今いるみんなと五年後も一緒にいられるとは限らないんだね……。ムラークくんがいなくなったら、さみしいだろうな……」
またアクセサリーを作りたくなったら、誰に頼めばいいんだろう……。
星の勉強会をやりたいときは?
ムラークくんのまだ幼さの残る輪郭を見て考える。
そうか思ってみると、本当に人との出会いは一期一会だ。
わたしは浮が少ないから多分長生きはしないだろうけど、ハインリヒさんのように長く生きるとしたら、そのときそのときの人との関わり合いは、本当に一生に一度のことなのかもしれない。
一緒にいる時間、与えられた機会、許された立場、どれもこれもが多分、今考えている以上に重要なことなんだ。
わたしがさみしいといったせいか、ムラークくんが返答に困ったような顔をしている。
「あ、ごめんごめん! 引き留めようとか考えていたわけじゃないよ。ただ、えーと、こういうこと。この前、ユーファオーの樹からつぼみを渡されたの。わたしは樹の声が聞こえないけど、旬さんがいうには、ハナムンの人に手渡してほしいんだって。ハインリヒさんがいってたの。自分たちがこの世界に持ち込んだものは、ハナムンの人への恵みなんだって。それで、カーツさんはハインリヒさんのランヤードリングを受け取ることで、武人としての祝福をもらってる。旬さんもみんなの浮の触りを鑑定することで、みんなの恵みになっている。わたしは、そもそも浮がないからあんまり役に立ってないけど、ユーファオーの樹からつぼみを預かったよ。だから、わたしもちゃんと浮者としての役割を果たさなきゃいけないなって、改めて思ったの」
そこまで話して、思考が止まった。
それで、えーと、なにを話そうと思っていたんだっけ……。
あ、そうだ。
「だから、ムラークくんにも、ムラークくんと一緒にいられるうちに、ちゃんと恵みを渡したいなと思ったの! ……といっても、なにがその恵みになるのか、まだよくわかってないんだけど……ははは……」
ムラークくんがぽかんとしたようにこちらを見ている。
あら、これは、酔っ払いの戯言みたいに聞こえているのかな。
そりゃそうか、こんな状態じゃ。
あはは、すいません……。
「でしたらあ、わたしにもお与えくださりますでしょうかあ?」
声の方を振り向くと、マッカリとその後ろに困ったような顔をしているマシンくんだった。
「ご無沙汰しておりますう、美波浮者あ。またこうしてご尊顔をお目にかかれてえ、うれしく存じますう」
マッカリ……。
でも、そうだ。
マッカリとこうして出会って話している、それもなにかの星のめぐりあわせなのだ。
ユーファオーの樹の意志がはっきりとわからない以上、ユーファオーの樹がつぼみを渡したいのは、彼女なのかもしれない。
「マッカリさん、どうぞ。座ってください。ただし、わたしに害意がある者が近づくとシールドとシェルターが反応しますから、御承知の上でなら」
「……ありがとう存じます」
マッカリはわずかに身じろいだが、落ち着いてゆっくりと東屋の腰掛に座った。
「ムラークう、美波浮者にお水か酔い覚ましをお持ちなさいい。なにもせずただ楽しくおしゃべりするだけならばあ、用に足りませんよう」
「は、はい……」
ムラークくんがぺこっと頭を下げて庭を去っていった。
マシンくんはマッカリの少し後ろで立ちんぼしている。
「マシンくん、こっちへ来て座ったら?」
「ですが……」
「マシンん、美波浮者のおっしゃるとおりにい」
「……はい」
どうやら、マシンくんもムラークくんも、やはり守長一族とは身分に大きな差があるらしい。
席を同じくするのにもはばかられるほどに。
「えーと、それで、マッカリさんはなにが欲しいの?」
わたしはシンプルに聞いた。
この人のペースに飲まれると、こっちが訳が分からなくなってくる。
多少言葉遣いや態度が相応しくなくても、酔っぱらっていることを踏まえればそこは丸く収まるだろう。
マシンくんが傍らで驚いたようにわたしとマッカリを見比べていた。
マッカリは少し考えるような素振りをした。
「正直に申しますと、わたしが欲しいのは美波浮者の信頼でございます。ここにいるマシンやムラークをことのほかかわいがってくださっていると聞いております。わたしも、美波浮者とお心を近づけて親しくなりたいと願っております」
驚いたことに、いつもの演技めいた口調がすっかりなくなっていた。
このまえ、素を見せて欲しいといったからなのだろうか。
「マッカリは人の心が読めるんでしょう? わたしが今なにを考えているかわかる?」
驚きを浮かべたのは本人だけでなく、マシンくんもだった。
「……そこまでおわかりでしたか……。そうです、わたしの流術は、人の心の声を聴くことができます」
おお、素直に話してくれた……。
「それだけでなく、一見術を使っていないように見えるよね。なにをしているの?」
「それは……」
作りこまれたマッカリの顔にはじめてゆがみが生じた。
「そんなに怯えなくてもいいよ。あなたは心が読めるのでしょう? わたしがあなたをどうするつもりでもないことがわかるはずだよ」
マッカリがはじめて大きく姿勢を崩し、まるで息も絶え絶えのようにうなだれた。
「も、申し訳ありません……。わたしは確かに心の声を聴くことができます。それを隠して使うこともできます。でも、美波浮者のお心は聞こえません。今聞こえるのは、マシンの驚きと侮蔑、そしてその左手から聞こえる大きな圧力です」
圧力……?
旬さん、そんな圧迫面接みたいなことをしてどうしようというんだろう。
それにわたしの声は聞こえないってどういうこと?
「わたしの声聞こえないの?」
「はい、美波浮者のかすかな浮は、左手の浮に覆われて、わたしの耳まで届かないのです。その左手の浮も、おそらく下町言葉だとは存じますが、音が大きすぎてわたしには圧が強すぎます……」
うーん、話しにくいというより、ちょっともう旬さんを怖がってしまってるね……。
「旬さん、どうしたいの?」
旬さんの指がするすると空をなでた。
「隠して使う方法を知りたい」
わたしはマッカリに目を向けた。
ふと、額に汗がにじんでいるのが見えた。
えっ、これって、大丈夫?
マシンくんを見ると、気の毒そうというか、心配というよりちょっと諦めが入ったような表情をしている。
うーん……、と、とりあえず聞いてみよう。
「術を使っていないように見せる方法、どうやっているの?」
マッカリは焦りと怯えをないまぜにした瞳を投げてきた。
「お許しください……、それは死んでも口にはできないのです……」
続けざまに、マッカリがヒッと悲鳴を上げた。
旬さんがまた圧力をかけたのだろうか。
でも、それを口にすれば命にかかわる。
ターマンさんも術を見せてくれたとき、同じ様なことをいっていた。
そういう意味なのか、はたまた一族から制裁を受けるという意味なのか。
どっちにしろ、死んでほしいとまで思わない。
「そっか、じゃあしょうがないね。え……、なに、これをいえってこと? うーん……」
旬さんが続けざまに文字を並べたので、仕方なくマッカリに伝えた。
「えっと……、あなたがいってもいわなくても、キリ一族が同じ術を使っていることはもうわかっている。信頼が欲しいといって席についたのはあなただ。それにも関わらずなお隠そうとするなら、あなたはそこに座っている意味はない。ただし、その責任はあなただけではなく、あなたをここへ差し向けた一族にもある。責任は等しく取ってもらう。町ごと消えても文句は言えまい」
こんなに脅したたらもう降伏しかないよ。
案の定、見る間に顔から色が消えていく。
マシンくんまでもが蒼白になっている。
そりゃそうだよ、ムネ町ごと消されたら、マシンくんやムラークくんの実家も消えちゃうじゃん。
マシンくんが救いを求めるようにわたしを見た。
「旬さん、町ごとはちょっと……。マシンくんたちの実家もあるしさ」
「そうだったか」
そのとき、庭の向こうから足音がした。
クランとムラークくんだった。
「マッカリ! 性懲りもなくまた! ここでなにをしているの!」
その声に顔を上げたマッカリの表情を見て、クランは驚きのあまり足を止めた。
わたしには見えなかったけれど、クランの強張った顔を見る限り、かなり印象深い顔だったようだ。
「マッカリ……」
マッカリが勢い良く立ち上がると、クランに突進していった。
ぶつかるのかと思ったら、肩が触れ合いそうなところでたちどまり、クランになにかを囁いて、そのまま走って行ってしまった。
クランが驚いたよう目を見開き、その背中を視線で追った。
「クラン、大丈夫?」
「は、はい」
腰掛から立ち上がると、足元がふらついた。
あれれ、やっぱりけっこう酔いがまわってるんだ。
ムラークくんはが持ってきてくれた水と薬を飲んだ。
「美波こそ、大丈夫ですか? 部屋でお休みになられますか?」
「うん、そうさせてもらおうかな。でも、クランこそ、主賓が抜け出してきたらだめじゃない」
「マッカリが部屋を出て行った後、ムラークがこちらへ水を取りに来ていたので、つい気になって」
「そうだったの。とにかくクランは戻って。わたしは部屋で休むから」
「わかりました……。ムラーク美波浮者を部屋までお送りしなさい。誰に引き留められても相手にしてはいけませんよ。マシンはカーツを呼びに行きなさい。カーツに美波の部屋に誰も通さないように見張りをさせます」
こんな良き日に、つまらないいざこざになってしまった。
主役であるクランにこんな心配までさせて。
わたしはムラークくんと部屋に戻った後、マッカリのことを考えた。
旬さんの意図はわかるけれど、あんなに追い詰めるべきじゃなかったと思う。
あれじゃあ、思いつめてなにか危険なことをしでかさないとも限らない。
「ねえ、ムラークくん。マッカリに伝えてくれる? 今日のあなたは、少なくとも前回よりは本当のあなたを見せてくれました。これで終わりだと思わないで。今日が始まりだと思って、対話しましょう。あなたに必要なものをあげられるのはわたしかもしれない。間違えずに伝えられる? それとも手紙にした方がいい?」
「いえ、大丈夫です。逆に手紙に残さない方がいいかもしれません」
「そっか。じゃあ、お願いね」
ムラークくんはこくりとうなづいて部屋を出て行った。
トラントランの子どもたちは、本当に賢い子どもたちだ。
しばらくして、カーツさんがやってきた。
「すみません、クランがちょっと神経質になってしまって。なにもないと思いますけど、よろしくお願いします」
「承知しました。命に代えてもこの戸はわたしがお守りします」
「あはは、大げさだけど、でも頼りにしてますね」
宴会が終わり、宿泊客以外が帰宅すると、寺ではもう夕餉の時間だ。
宴会料理の下げわたしがあるので、今日のお膳はとても豪華だ。
わたしの夕餉を、クランが部屋へ持ってきてくれた。
小坊主さんがもう一つの膳を持ってきて置いていった。
「これから本堂に向かおうと思っていたのに……。膳が二つってことは、クランもここで食べるの?」
「お許しくださいますか?」
「うん、構わないけど、今日はどうしたの?」
「美波とこの寺で過ごすのはこれで最後ですから」
「えっ、どういうこと?」
わたしは目を丸くしてしまった。
逆にクランのほうも驚いていた。
「あの……、わたしは明日クム家に引っ越します」
「え、えっ、聞いてないよ!」
「いっておりませんでしたか? すみません、嫁入りはお披露目が終わった後と決まっているものですから、わたしも忙しくて、うっかりしていたかもしれません」
「そうだったの? ……知らなかったよ……」
そういえば、クランの部屋の荷物をやけに出し入れしているようだったけど、あれは単にお披露目の準備をしていたわけではなく引っ越しの準備もしていたのだ。
突然のクランの引っ越しに、わたしは強いショックを受けていた。
「そんな……。そ、そっか、でも、考えてみたら当たり前だったね……。わたし、クランはずっとお寺にいるものだと勘違いしてた……」
「すみません、わたしもちゃんと伝えるべきでした。でも、ゼンジはこれまで通り毎日通いますし、わたしも炊房の手伝いにちょくちょく参りますから。まったく会えなくなるということではなありません」
「う、うん……」
情けない顔をしていたのだろう。
クランがわたしの肩を抱いて、背中をさすってくれた。
「クランがいなくなるなんて、考えてもみなかったよ。どうしよう、すごく寂しい。わたし、明日からやっていけるかな……」
「クム家での生活になれたら、わたしもできるだけ頻繁にこちらに通うようにいたします。あちらも、わたしと美波のことはよく理解してくれているようですから」
そうだ、クランはもうクラン・ファではなく、クラン・クムなのだ。
これまでのようにわたしの都合だけで振り回していいわけではない。
クム家の嫁として、ゼンジの妻としての役割を負っている。
子どもができたら、その世話だってしなくてはならない。
クランはもう、お寺のお嬢様のクランではないのだ。
頭ではの理解できるのに、心が全く追いつかない。
泣いたりしてクランを困らせちゃいけないとわかっているのに、どうしよう、涙が止まらない。
「美波、やっぱりあなたを残していくのが心配です……」
「ううん、これ、うれし涙だから……」
精一杯強がった。
クランに心残りを持たせちゃいけない。
明日は笑ってクランを送り出してあげなきゃ。
今夜の別れの夕餉は、本来だったらコルグさんや生きていたらお母さんと過ごすものかもしれない。
それをクランはわたしと一緒に過ごすことにしたのだ。
決して母親代わりになどなれないけど、それでもクランのお姉様として、きちんとクランを送り出してあげたい。
「大丈夫、心配いらない。考えてみたら、そうだよね。ゼンジさんは毎日通ってくるからクランの様子もきけるし、クランもゼンジさんから話聞けるんだもんね。わたしもマシンくんとムラークくんと今計画があって忙しいし、ほんと、考えてみたらさみしがってる暇なんてないよ」
「まあ、わたしに内緒でなんの計画ですか?」
「クランは今日のために忙しかったから、相談しなかったんだ。ごめんね。階級試験のことだよ」
「そんな面白そうな計画、わたしも参加したかったです」
「うん、まだ全然詳しいことは決まってないから、もしかしたらまたクランに相談するかも。そのときは、相談に乗って?」
「はい、もちろんです」
お膳にはクランの香りがするあの甘いお酒もあった。
悪酔いしそうで口はつけなかった。
お腹もそんなに空いてなかったけど、クランに心配させまいと、おいしいね、といいながらたくさん箸をつけた。
こんなふうにクランと差し向かって、話をしながら食事をとることはもうないのだろう。
本当に、人と関わり合うことを許される時間は、散って消えていく花のように短いのかもしれない。
わたしは大事な時間をかみしめるように味わった。
その夜になると、旬さんがベッドに突っ伏したわたしの頭をなでてくれた。
「うれし涙でも、そんなふうに泣いてると、明日顔が腫れるぞ」
「うう……、やっばりざみじい……」
「こうなると思った」
「わかってたならなんでいってくれないの」
「いってたら、カーツを応援したのか?」
「……ううん、それはないけど……」
「だろ」
「でも心の準備が……」
「明日のために、今から心を調えないと」
「うん……」
「そんなにさみしがる必要はない」
「……うう、だけど……」
「俺がいる」
……そうだね、旬さんはずっとわたしの側にいてくれるもんね。
わたしは旬さんと手をつなぎ合って眠った。
明日はきっと泣かずに笑顔で送り出そう。
そのときそのときを大切にする。
あのときああしておけばって思わないように。
8
あなたにおすすめの小説

愛された側妃と、愛されなかった正妃
編端みどり
恋愛
隣国から嫁いだ正妃は、夫に全く相手にされない。
夫が愛しているのは、美人で妖艶な側妃だけ。
連れて来た使用人はいつの間にか入れ替えられ、味方がいなくなり、全てを諦めていた正妃は、ある日側妃に子が産まれたと知った。自分の子として育てろと無茶振りをした国王と違い、産まれたばかりの赤ん坊は可愛らしかった。
正妃は、子育てを通じて強く逞しくなり、夫を切り捨てると決めた。
※カクヨムさんにも掲載中
※ 『※』があるところは、血の流れるシーンがあります
※センシティブな表現があります。血縁を重視している世界観のためです。このような考え方を肯定するものではありません。不快な表現があればご指摘下さい。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

私が王子との結婚式の日に、妹に毒を盛られ、公衆の面前で辱められた。でも今、私は時を戻し、運命を変えに来た。
MayonakaTsuki
恋愛
王子との結婚式の日、私は最も信頼していた人物――自分の妹――に裏切られた。毒を盛られ、公開の場で辱められ、未来の王に拒絶され、私の人生は血と侮辱の中でそこで終わったかのように思えた。しかし、死が私を迎えたとき、不可能なことが起きた――私は同じ回廊で、祭壇の前で目を覚まし、あらゆる涙、嘘、そして一撃の記憶をそのまま覚えていた。今、二度目のチャンスを得た私は、ただ一つの使命を持つ――真実を突き止め、奪われたものを取り戻し、私を破滅させた者たちにその代償を払わせる。もはや、何も以前のままではない。何も許されない。

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

わたしの下着 母の私をBBA~と呼ぶことのある息子がまさか...
MisakiNonagase
青春
39才の母・真知子は息子が私の下着を持ち出していることに気づいた。
ネットで同様の事象がないか調べると、案外多いようだ。
さて、真知子は息子を問い詰める? それとも気づかないふりを続けてあげるか?

裏切りの代償
中岡 始
キャラ文芸
かつて夫と共に立ち上げたベンチャー企業「ネクサスラボ」。奏は結婚を機に経営の第一線を退き、専業主婦として家庭を支えてきた。しかし、平穏だった生活は夫・尚紀の裏切りによって一変する。彼の部下であり不倫相手の優美が、会社を混乱に陥れつつあったのだ。
尚紀の冷たい態度と優美の挑発に苦しむ中、奏は再び経営者としての力を取り戻す決意をする。裏切りの証拠を集め、かつての仲間や信頼できる協力者たちと連携しながら、会社を立て直すための計画を進める奏。だが、それは尚紀と優美の野望を徹底的に打ち砕く覚悟でもあった。
取締役会での対決、揺れる社内外の信頼、そして壊れた夫婦の絆の果てに待つのは――。
自分の誇りと未来を取り戻すため、すべてを賭けて挑む奏の闘い。復讐の果てに見える新たな希望と、繊細な人間ドラマが交錯する物語がここに。

冤罪で辺境に幽閉された第4王子
satomi
ファンタジー
主人公・アンドリュート=ラルラは冤罪で辺境に幽閉されることになったわけだが…。
「辺境に幽閉とは、辺境で生きている人間を何だと思っているんだ!辺境は不要な人間を送る場所じゃない!」と、辺境伯は怒っているし当然のことだろう。元から辺境で暮している方々は決して不要な方ではないし、‘辺境に幽閉’というのはなんとも辺境に暮らしている方々にしてみれば、喧嘩売ってんの?となる。
辺境伯の娘さんと婚約という話だから辺境伯の主人公へのあたりも結構なものだけど、娘さんは美人だから万事OK。

天才天然天使様こと『三天美女』の汐崎真凜に勝手に婚姻届を出され、いつの間にか天使の旦那になったのだが...。【動画投稿】
田中又雄
恋愛
18の誕生日を迎えたその翌日のこと。
俺は分籍届を出すべく役所に来ていた...のだが。
「えっと...結論から申し上げますと...こちらの手続きは不要ですね」「...え?どういうことですか?」「昨日、婚姻届を出されているので親御様とは別の戸籍が作られていますので...」「...はい?」
そうやら俺は知らないうちに結婚していたようだった。
「あの...相手の人の名前は?」
「...汐崎真凛様...という方ですね」
その名前には心当たりがあった。
天才的な頭脳、マイペースで天然な性格、天使のような見た目から『三天美女』なんて呼ばれているうちの高校のアイドル的存在。
こうして俺は天使との-1日婚がスタートしたのだった。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる