2 / 2
列車の到着
しおりを挟む
人生楽しいことなんてないと感じているあなた。
人生つらいことや悲しいことばかりだというあなた。
あるいは、我が人生においてつらいことや悲しいことなんて起こり得ない、それは捉え方次第なのだと考えているあなた。
本物のつらいこと、本物の悲しいこと。残念ながらいつの日かそれがあなたの頭上に降り注ぐことは確定している。だって少なくとも、あなたが大切に想っているひとたちがいつかは必ず死ぬという時点で、この先に悲しい出来事が起こることは必然ではないか。
もし「大切なひとなどいない」という人があれば、これだけは憶えておくといい。
大切なひとを一人も思い浮かべられないのであれば、あなたは自分が死ぬそのときに、つらくて悲しくて泣くのだ。いずれにせよ本物の悲しみは必ず訪れる。誰にでも。誰にでもだ。
✳︎
四月の手紙を九月に読んだ。
だが正確に言えば、それは個人的な手紙ではない。ただの電話料金の請求書だった。
でもそれはぼくにとっては紛れもない手紙だった。初めて携帯電話を持った頃、TSUTAYAから届くダイレクトメールがぼくにとっては紛れもないメールであったように。それらは紛れもなくぼくに宛てられた、メールであり手紙であった。少なくともぼくにとっては。
四月の電話料金の請求書を九月に読んだことにはもちろんそれなりの理由があった。第一に電話が止まることによる影響が最小限であったこと。ぼくには今、それほど多くの友だちはいない、ごく控えめに言って。そして第二に、電話料金の支払いなどという瑣末な手続きにさえ気がまわらないような状況であったことがあげられる。ぼくの頭上にはまさに、本物の悲しみが降り注いでいたのだ。
✳︎
「悪いことは重なるものよね」と言う人がある。その発言は主として、一日ないし数日の範囲での悪い出来事について言い表わしているように思う。
ただ、ぼくの場合は少し違う。彼女の言う「悪いこと」は蓄積するのだ。数日なんてものじゃなく、それこそ数年単位で。ぼくの本物のつらさ、本物の悲しみは、その蓄積により肥大化した癌のようなものだ。
昔、たしか『自殺の文学史』というタイトルの本を読んだことがある。そこには「最後の一滴症候群」という症例が記載されていた。
他者から見て決定的な自殺の動機が見えないとき、それは最後の一滴症候群によるものではないかという仮説だ。
グラスから水が溢れるとき、それは必ずしも、勢いよく注がれる水がその勢いを殺さぬまま溢れてしまうわけではない。表面張力が起こるほどなみなみに水が注がれたグラスは、たった一滴の水が滴り落ちただけで溢れてしまうのだ。その最後の一滴こそが最終的な自殺の引き金であり、しかも他者の目にはそうとは映らないのだ。
それは口にした一粒のたこ焼きにたまたまたこが入っていなかったせいかも知れない。誰がたこの入っていないたこ焼きに当たっただけで死を選ぶだろう?
でも、そういうことは実際に起こり得るのだ。ほんとうに。それは誰にだって、ある場合にはいとも簡単に起こり得ることなのだ…。
✳︎
今日、ぼくはここで、能力の許す限り「抽象的」でありたいと願っている。抽象的であることによってのみ獲得される情調があり、抽象的であることによってのみ達成される事物がある。ぼくがここでぼくの本物のつらさや本物の悲しみについて具体的に、細部を克明に書き記すことであなたに得られるものは、ほとんどなに一つないだろう。「これはあなたのケースで、わたしはそうではないわ」とあなたは言うだろう。それは至極まっとうな言い分だ。
フォーマットとしてたくさんの種類の小説がある。時系列に沿って書き上げられたものもあれば、時系列的な順序がめちゃくちゃなものもある。年代記もあれば未来の話もある。もちろん、過去のエピソードが入れ子構造になっているものもあるし、それらが組み合わされたものもある。あげればきりがない。
小説の語り部がその小説自体について物語内で言及することはアンフェアにも思えるが、そんなことはさして重要なことではない。これは前述したどのフォーマットとも少し異なる、いわば抽象的な短編小説である。
✳︎
抽象的であることはときとして素晴らしい。
それが自分にも起こり得ることとして受け入れ易いからだ。しかしもちろん、危険も孕んでいる。
四月の手紙を九月に読んだぼくは、その四月から九月までの間に本物の悲しみに苛まれた。それは蓄積された悲しみであり、同時にぼくをぼくたらしめる特性の否定であった。
ぼくの歴史は無に等しいと思った。しかし、それは生易しい表現にすぎなかった。
実際のところ、ぼくの歴史は無未満なのだ。つまり、無のほうがマシだと言うことだ。
ぼくがこれまで出会った、そして大切なひととして認識してきた彼ら・彼女ら・彼にも彼女にも属さない…あるいは彼であり彼女でもある友人たちにとって、ぼくとの関わりなどないほうがよかった。これがぼくの行き着いた結論である。
ある人にとっては時間の無駄で、またある人にとっては人生を損なわれる結果となった。これは一重に、ぼくが責任を負うべきものだ。
ある友人はぼくに言った。
「おまえにとっては重要じゃないことかも知れないが、俺にとっては絶望に似たことをおまえは平気でやるから、俺は疲れてしまった。
今の問題はおまえのだらしなさ、大人になれないおまえの問題だけだ。このままじゃおまえの周りの人間、一人残らず確実に不幸にするぞ?
誠意っていうのは、その中に『自分』があっちゃいけないんだ。おまえの全ては、自分中心に回りすぎてる」
彼はぼくにとって、一番の親友だった。
「狡さっていうのは俺には通用しないんだよ、本質でしか見てないから。
わかってないのもわかってる、わからないのもわかってる。でも俺にも限界がある。
価値観の違いだと思おうとして俺自身誤魔化してきたけど、あまりにも酷い。
自分が関わっている人をどれだけ巻き込んで引き摺りこんでいるか、これは俺以外の人間に対してのことだが、おまえはわかっていない。わかっていないことも俺はわかってる。今までもそうだった。
でも俺がどれだけ、こちら側に引き戻そうと時間をつかってきたか、おまえにはほんとうにわからないと思う。
おまえがどれだけ、気づかないところで人を裏切っているのかわからないと思う。
その自覚すらきっとないから、新しい逃げ道しか見つけられないよ、きっと」
そして最後に彼は言った。
「当たり前のことを少しずつやるしか無いんだよ、おまえにはもう昼も夜も働いてそのほとんどを何かに返していくしか道は残ってないんだよ。
俺が言いたいことなんて山ほどある。悲しいし悔しいし腹立たしいし、心配もしてる。アホらしい。
こんな感情をよく人に与えたもんだよ、ほんとに」
✳︎
我々はかつて親友同士だった。でも、だからこそ最後に言ってくれたんだろう。
我々はかつて親友同士だった。
もう上手く思い出せないほど昔の話だ。
✳︎
彼の言うとおり、平たく言えばぼくは「屑」だった。しかしそれに気づいていない屑。人の気持ちがわからない、人の気持ちを踏み躙ることを平然とやった。
ぼくはそれに気づくまで、自分でも何をしていたのかわからなかった。ただ生きていた、それだけだ。
気がついたとき、ぼくにはそれを償うすべさえ残されてはいなかった。誰もぼくとは会おうとしなかったし、連絡をしても返してくれる人は一人もいなかった。
ぼくは自分を屑だと蔑むことで、なにも独り自己憐憫に浸っているわけではない。
ただ思うのは、「屑のなかにも貴賤がある」ということだ。
自分を屑だと自覚している人間は少なくはないだろう。それが勘違いで、実際には本人が思うほど屑ではないというケースもある。しかし、明らかに屑であるにもかかわらず、「自分が屑だと自覚していない人間」、これはもうほんとうに屑、屑のなかでも取り立てて屑である。掛け値なしの屑。屑のなかの屑と言って差し支えない。
ぼくの屑度合いとは、まさにこれに当てはまった。
ぼくは自分が屑であるという事実、唾棄すべきろくでなしに過ぎないという事実を認識していなかった。
✳︎
大切なひとたちから一切の連絡が途絶えて久しい。
ぼくにとっての大切なひとたちが死んだとして、ぼくにはその死を知るすべがない。本物の悲しみ…。ぼくはたった一人老いてゆくのだ、そしてたった一人死ぬのだ。ぼくが死ぬそのとき、ぼくはつらくて悲しくて泣くのだろう。ぼくは死ぬことが怖かった。
ぼくがもし大切なひとたちよりも先に死ぬなら、大切なひとが死ぬという本物の悲しみに見舞われることはないだろう。しかしそれでも、ぼくは自分が死ぬとき、おそらくつらくて悲しくて泣くのだろう。
いずれにせよ何人にも本物の悲しみが降り注ぐことは確定している。決まっているんだ、ちゃんと。
✳︎
時々遠くのほうから、列車の走る音、線路の軋みが聞こえる気がした。
その列車にはぼくの大切なひとたちが一人残らず乗っていた。大きな旅列車ではないが向かい合うボックス席はほとんど満席で、誰もがぼくとの再会を楽しみに談笑していた。その中には時空を超えて各々に時間を潰す人たちの姿もあった。デイジーは虚な目をしてぼくに恋焦がれ、アリョーシャは慎ましく両膝を揃えぼくに会った時まず何を口にするかということに思いを巡らせていた。レオポルド・ブルームは長すぎる一日にうんざりしながら車窓からの風景を眺め、かのウンベルト・ペニャローサは胃痛に耐えながら、早くもその人格に崩壊の兆しを見せている最中だった。
ガタンゴトン、ガタンゴトン…。
✳︎
大切なひとの死を知るすべがある例外として、両親、そして田舎の祖母がいた。
四月にその祖母が死んだ。新型ウイルス蔓延の影響で三年間会いに行けなかった。これは紛れもなく本物の悲しみだった。
彼女も、時折その軋みが聞こえるあの列車に乗り込んでいた。ぼくと会えることを楽しみにしてくれている。ぼくはそのことが嬉しかった。ぼくは列車の到着を心待ちにしている。でもぼくを覆う悲しみは消えはしなかった。彼女はもう死んでしまっていて、ぼくはまだ生きている。その死を聞いたあとあてもなく国道沿いを歩いていたぼくを、大型トラックの影たちが何度も何度も轢き殺した。それでもぼくは死ねなかった。
✳︎
五月に入るとぼくは、休みがちになっていた仕事を無断欠勤するようになった。料金未払いで電話が止まるまでは毎日なにかと理由をつけて連絡だけは入れていたが、最終的にはそのまま辞めた。社会的モラルに反する辞め方だったが、もう自分にもそれをどうすることもできなかった。しばらくして会社から解雇通知が届いた。それでぼくは仕事をくびになったことを知った。
五月は転落の季節だった。借金をし、その金をあたかも自分の貯金のように使い果たす。後先考えずにそれを繰り返した。この、生活とも言えないような酷い暮らしは九月まで続くのだが、一人暮らしのアパートの家賃さえ後回しにしていた。他人の金をなににつかったのか、それさえ憶えていない。
とうとう十年来行きつけだったバーに顔を出すことさえなくなってしまった。
そのバーはぼくのかつての一番の親友にとっても行きつけだったので、顔を合わせることを避けるために事前に連絡してから行かねばならなくなっていた。しかも仲が良かった他の常連客が足を運ぶことの多い土日は、彼も顔を出す可能性が高かったので行くことができなかった。彼のほうがぼくより後から常連になったが、連絡を入れねばならないのは必ずいつもぼくだった。あるいは事実である可能性も大いにあるけれど、親愛なるマスターはぼくより彼を優遇しているのではないだろうかという邪推から、徐々に足が遠のいた。そして、これまで仲良くしていた他の常連客たちとの大切な繋がりも途絶えた。
ぼくの孤独感はいよいよ本格的に強まっていった。
✳︎
六月のある雨の日、ぼくは路上で猫がスクーターに撥ねられる場面に居合わせた。
ぼくはその場面を今でもよく思い出す。日常生活を送るなかで「目の前で轢かれた猫を見殺しにしたときと同じだな」と感じる場面が時折ある。
そのスクーターの運転手は猫を撥ねたその瞬間、「クソがっ」と口走ってそのまま走り去った。
ぼくは本心から咄嗟に猫を助けたくて、交通量が多いその通りの歩道でどうしたものかと物怖じしていた。が、後続車が停まりヒールを履いた若い女性が中から現れて、すぐ近くのコンビニへと駆け込んでいった。
彼女は大きなビニール袋を手に戻ってきて、痙攣する猫を抱き抱えると車へと乗り込んで猛スピードで去っていった。
あの女性は猫を病院へ連れて行ったのだと思う。彼女がコンビニへ走り戻るまでのその間、ぼくはビクビクと苦しそうに悶える猫を見つめただ立ち尽くすばかりだった。
あのときとった自分の行動にぼくは失望した。「もし今度同じことが起こったら」と反復して考え続けた。ヒールを履いて走りづらそうに、夢中でコンビニへと駆け込んだあの女性の姿を何度も何度も思い返して、寝覚めの悪い夢を見続けていた。
もちろんぼくは昔から壊れていたと思う、昔のことはよく思い出す。
薄っぺらい正義感のようなものかも知れない。だがこれは、もっとずっと昔、ぼくが比較的まともだった時代から感覚的に存在し続けてきたものだった。ぼくはそれをただ見過ごすことができない。ほとんど反射的に、いわば本能に近い衝動で、ぼくは不器用なりにただアウトプットする。アクションを起こすのだ。場合によっては自己満足でしかないかも知れない。でもそれは自分の考えやら思想やらを敷衍したりアピールしたり押しつけたりする目的からではなくて、頭で考えるよりもまず身体が動いてしまう…といった類のことだった。
それはかつての「ぼくという人間」の、美徳とは言えないまでも本質であることに間違いなかったはずだ。
好むと好まざるとにかかわらず、こういった特定の局面、シチュエーションにおいて必ず自らがとってしまう行動、選びとってしまう結果であり、筋の通った人間性であり、突き詰めて言えばそれが「ぼくという人間」であり、最期まで残り続けるものだと思っていた。
身に余るようなことだけれど、ぼくが死んで、誰かがぼくについてなにかを口にしてくれたとする、「あいつはああいう人間だった。あいつらしいな」。そういう場面で、残るものだと思っていた。
だから、ぼくが猫を助けるべきだったのだ。
あの頃のぼくなら真っ先に猫を助けただろう、そう思える時代がぼくにもあったはずなのだ。
✳︎
七月にぼくはまた一つ歳をとった。そのことを祝ってくれるひとは誰一人としていなかったし、ぼく自身も歳をとることに喜びなど感じ得なかった。
脳内では楽しかったはずの過去の誕生日パーティーの思い出が酷く脚色されて再生された。
「くだらない、あいつの誕生日パーティーの招待状なんか送り返せ!」
「何歳まで生きるつもりだ?」
ぼくは滑稽さが際立つ三角帽子をかぶり、パーティー会場に独り立ち尽くしていた。
どこまでがほんとうに起こったことで、どこからがぼくの勝手な脚色なのかわからなかった。はっきりしていることは、もう誰もぼくのためにパーティーなど開かないということ、さらに言えばもう誰もぼくをパーティーに招待などしないということだった。
ぼくはこの命の続く限り何度でもこの思いを味わうことになるのだと考えると、底知れぬ孤独感に苛まれた。死ぬことは怖かった。でも、生きることを続けることはそれにも増して怖かった。できるだけ楽な死に方を調べもした。ぼくは空想のなかで何度も死に、その度につらくて悲しくて泣いた。その涙は軽くて薄っぺらくて、そのことがぼくの滑稽さをより際立たせていた。七月中ぼくは、一人として参加者がやってくる見込みもないパーティー会場で三角帽子をかぶり、ただ列車の到着を待っていた。
✳︎
世界中のカレンダーは音もなく八月へと切り替わっていた。
七月から八月にかけて、たくさんの人が死んだ。そのなかには著名人も含まれるし、刑が執行された死刑囚も含まれていた。
まだほんの子どもだった頃、ずっとずっと昔から、ぼくにとってそもそも人の死というものがおしなべて悲しいものだった。
例えば、一度の死刑では足りないんじゃないかと思われるような残虐の限りを尽くした死刑囚もいるけれど、そんな連中にだって死んだ意義みたいなものはあると思った。刑が執行されたことで、生きていたときと死んだあとでは、なにかを同じようには語れない、漠然としたーーー人によってはあるいは判然とした、確固たるーーー違いを残していることは少なくとも確かだと思う。
それくらい人の死とは重いというか、ある意味ではこれ以上は望めない極限の境界線であり、不可逆的な、絶対に元には戻せないという絶対性を孕んでいると、ぼくは考えている。
以前のぼくは口が悪くて態度も悪くて、しょっちゅう誰かに対して中指を突き立てて生きていた。「死ね」という言葉を口にすることも多かった。
現実にはあり得ないことだけれど、ぼくが死ねと言った対象の人物が仮にその場で死んだら、ぼくは多分その場で泣いたと思う。人の死を重いと認識している自分があるのに、その自分の内面には双極性の乖離がある(それがぼくの抱える大きな欠陥の一つなのは決定的事実だと思うけれど、それはまた別の話だ)。
人が死ぬということは、生きているこの自分とは、そしてもちろん生きている他の誰とももう永遠に交われない・関われない・その反応を感知できないとか、そういうことだ。完全に違う次元に行ってしまう、フェードアウトしてしまう。絶対に戻ってこない。そのひとがここにいたら…というのはもう幻想であり仮定でしかなくなり、脳みそで想像して補うことしかできないはずだ。究極的な別れだと言ってもいいと思う。
そのなかには肉体の消滅、消滅と言ってしまえば聞こえは悪くないが、どんな死に方をしても、その直前まで生命活動を行なっていた人体が壊れる・腐る…骨にまでなってしまえば綺麗だけれど、否応なくそういう過程(生きている側から見たら汚いこと、あり得ないくらい臭いこと、直視するのが難しいほどに生々しいこと、極限にグロテスクなこと)が必ず含まれているのだ。どんな死にでも。もうその臓器は機能していなくて、臓器が機能していない人体は放っておけば腐るだけで、その亡骸はもう祖母でもなければシドでもナンシーでもない…とも言えるわけだ。対面したそのひとが、死んだ人間のどの部分をもってそのひとと思うか? 魂とでも言うならその魂はもうその肉体には入っていない、じゃあその腐るばかりの肉の塊はそのひとじゃない。そう割り切れる人もなかには大勢いるだろう。大して知らない人の死なら尚更だ。でも死者にとって、生前ただの「期限付きの所有物」「借り物」だったとしても、その死骸はそのひとのーーー生きている者たちがそれぞれそのひととして想像する・思い返す・そのひとそのもののーーー形をとっていて、それが対面した相手に与える印象には大きな衝撃、インパクト、あるいはギャップというか相違、違和感があると思う。そういうのを目の当たりにして初めて、人は「このひとは死んだんだ」と納得できるのかも知れない。報道されたり人づてに聞いたところで、信じられない人だってきっとたくさんいる。棺桶のなかに収まっているそのひとの残骸みたいな死の証拠を、死者の生前を知っている人全員が拝めるわけじゃない。ただそのひとの不在を認識するだけだということが、死という事象全体の大部分を占めるのではないだろうか。
怒りの感情は突発的なものだってよく言うでしょう? なかには根深い執念的な怨みもあるだろうけれど、それだって人の寿命が数百年・数千年続くなら立ち消えてしまうんじゃないだろうか。
死に際に「末代まで呪ってやる」とか口走ろうが、孫の孫まで呪ったってせいぜい二百四十年とかそこいらだものな。そういう尺度で見たら蜜蜂がすぐ死ぬみたいなのと大して変わらないような気さえしてくる、そういう観点からなら人間だって、すぐ死んじゃうんだよ。なんだったら自分の体感している時間なんて、それこそ蜜蜂が体感している時間と変わりないんじゃないかな…とさえ思えてくる。
ぼくが誰かに対して何かしら怒りを覚えて、許せなかったとしても、その相手が死んだら即座に無条件に、その場で許してしまうような気がする。死んだ人間に対しては大抵のことが許せそうな気がする。
考えたくもないけれど、ぼくに妻がいて、彼女が殺されたとする。それをぼくは死んでも許せないだろう。
でも、ぼくがその後も妻のいない世界で生きていくとする。そのうちに怒りより、「あのひとがいない」という悲しみだけが残って、怒りを上回って押し潰して、ついには消してしまうだろう。そう考えると怒りという感情は、突き詰めればぼくという自分のためだけの、やり場がなくなる運命しか辿れない小物なのかも知れないなと、そう思う。何よりも重大なのは「妻が死んでしまった」ことで、もう会えなくて、反応も貰えなくて、ぼくの脳みそで想像することしかできなくて、さみしくて悲しいということに、たえられそうもないことだ。
それでもぼくの、妻に対する愛みたいなものは消えないだろう。ずっと想い続けるはずだから、生きるならあるいはずっと独り身でいるかも知れない。もしぼくが死んだら(現世で会えないのはわかりきっているのだから)、死んだ先でまた会えるかも知れないと考えるだろう。死後にどうなるのかなんてわからないから、一縷の望みを託すように自分で死んでみるかも知れない。でも、それはまた同じことの繰り返しのように思えなくもない。ぼくが死ぬことでぼくの大切なひとたちは、以前のぼくとまったくの同一の感情までは抱かないかも知れないが、それでもやはり、悲しむんじゃないだろうか。そういうことを想像したら、簡単には自殺なんてできないはずなんだ。生きている人から見たら、あまりに身勝手な選択にも思えることなんだ。でも例にあげたぼくの場合は、それよりも死んだ妻と会えるかも知れないという、その想いのほうがきっと強い。その想いを抑えることなんてきっとできない。
もっと単純に、あるいは複雑に、別の理由から。例えばぼくはぼくが許せない。消えてしまいたい(ぼくは「死にたい」と口にしたことはなくて、そういうとき「消えたい」という言葉を独りで口にしていたことを憶えている。抽象的であるほうがまだ救いがあったから直截的な言葉を避けていたんだと思う)。そんなとき、誰かに相談することはできないんだ。迷惑がかかると思ってしまう。勝手にやるべき。ずれた責任感(でも周りに消えたいとアナウンスすることが責任感なんて言えるのか? それは責任感の対極にある行動ではないか?)、誤った責任感を持ってしまって、履き違えて、ちゃんと考えに考え抜いてその責任感を実行してしまうひと。そういうひとが自殺するんじゃないだろうか?
ぼくはそれがとても悲しい。涙が出てくる。例え大して知らない赤の他人のことでも、なぜだか涙が出てくるんだ。
✳︎
そして九月。ぼくは四月の手紙を九月に読んだ。このままじゃいけないということは、嫌というほど自分でもわかっていた。
働きもせず借金を繰り返す毎日。曜日の感覚すらなく、今が何日なのかわからない…かろうじて九月であるということがわかる、それだけが、ぼくにとっての時間感覚のすべてだった。
金木犀の花の香りはぼくに孤独を思い出させた。大好きな香りだが、そこには手で触れられる現実の、実際的な孤独感が否応なくしがみついていた。
社会復帰の時期だな、と、ぼくは思う。いつまでもこんな毎日を刻んでゆくわけにはいかないのだ。この半年余りでぼくがしたことと言えば、過去の記憶を無制限に再生させること、ただ罪悪感に苛まれ日々を無下に送ること、そして完全なる孤独のなかで自分と向き合い、人の死について思いを巡らせること、これだけだ。
どれほどの人を傷つけてきたのだろう、と、ぼくは思う。どれほどたくさんの人たちを損なってきたのだろう。
それを考えるとあまりにも、ぼくの生きた歴史は打算的で、罪深いものだった。
償うすべがあるのなら、まずはぼく自身のこの生活を立て直す必要があった。誰の目から見ても、今のぼくにはその罪を償う資格すら与えられてはいないのだ。屑のままで、独り勝手に命を終えるしか道は残されていないのだ。
✳︎
ぼくは列車の到着を待っていた。
運転士はなにをやっているのだ? なぜこんなにも、到着が遅いのだ?
でも、その空想の列車に運転士がいるのだとすれば、それはぼく自身だった。
みんながーーーぼくの大切なひとたち、全員がーーーぼくとの再会を待ち侘びて乗り込んだ列車が到着するためには、まずはぼくが運転士としてその役割を果たさなければならない。
ガタンゴトン…。聞こえる。
ガタンゴトン…、まだ聞こえている。列車の走る音と、線路の軋みが、まだ確かに。過ぎてゆく毎日と、積み重ねてゆくぼくのやるべきこと。夜も、朝も、その列車は走り続ける。忘れはしない。
ガタンゴトン、ガタンゴトン。
今は閉ざされていても、きっとぼくはそれを切り開くだろう。
ガタンゴトン、ガタンゴトン。
いつか届くまで。出発進行。
ガタンゴトン、ガタンゴトン。
ぼくは成すべきことを成し、列車を終着駅へと走らせる。大丈夫。頑張れ。
人生つらいことや悲しいことばかりだというあなた。
あるいは、我が人生においてつらいことや悲しいことなんて起こり得ない、それは捉え方次第なのだと考えているあなた。
本物のつらいこと、本物の悲しいこと。残念ながらいつの日かそれがあなたの頭上に降り注ぐことは確定している。だって少なくとも、あなたが大切に想っているひとたちがいつかは必ず死ぬという時点で、この先に悲しい出来事が起こることは必然ではないか。
もし「大切なひとなどいない」という人があれば、これだけは憶えておくといい。
大切なひとを一人も思い浮かべられないのであれば、あなたは自分が死ぬそのときに、つらくて悲しくて泣くのだ。いずれにせよ本物の悲しみは必ず訪れる。誰にでも。誰にでもだ。
✳︎
四月の手紙を九月に読んだ。
だが正確に言えば、それは個人的な手紙ではない。ただの電話料金の請求書だった。
でもそれはぼくにとっては紛れもない手紙だった。初めて携帯電話を持った頃、TSUTAYAから届くダイレクトメールがぼくにとっては紛れもないメールであったように。それらは紛れもなくぼくに宛てられた、メールであり手紙であった。少なくともぼくにとっては。
四月の電話料金の請求書を九月に読んだことにはもちろんそれなりの理由があった。第一に電話が止まることによる影響が最小限であったこと。ぼくには今、それほど多くの友だちはいない、ごく控えめに言って。そして第二に、電話料金の支払いなどという瑣末な手続きにさえ気がまわらないような状況であったことがあげられる。ぼくの頭上にはまさに、本物の悲しみが降り注いでいたのだ。
✳︎
「悪いことは重なるものよね」と言う人がある。その発言は主として、一日ないし数日の範囲での悪い出来事について言い表わしているように思う。
ただ、ぼくの場合は少し違う。彼女の言う「悪いこと」は蓄積するのだ。数日なんてものじゃなく、それこそ数年単位で。ぼくの本物のつらさ、本物の悲しみは、その蓄積により肥大化した癌のようなものだ。
昔、たしか『自殺の文学史』というタイトルの本を読んだことがある。そこには「最後の一滴症候群」という症例が記載されていた。
他者から見て決定的な自殺の動機が見えないとき、それは最後の一滴症候群によるものではないかという仮説だ。
グラスから水が溢れるとき、それは必ずしも、勢いよく注がれる水がその勢いを殺さぬまま溢れてしまうわけではない。表面張力が起こるほどなみなみに水が注がれたグラスは、たった一滴の水が滴り落ちただけで溢れてしまうのだ。その最後の一滴こそが最終的な自殺の引き金であり、しかも他者の目にはそうとは映らないのだ。
それは口にした一粒のたこ焼きにたまたまたこが入っていなかったせいかも知れない。誰がたこの入っていないたこ焼きに当たっただけで死を選ぶだろう?
でも、そういうことは実際に起こり得るのだ。ほんとうに。それは誰にだって、ある場合にはいとも簡単に起こり得ることなのだ…。
✳︎
今日、ぼくはここで、能力の許す限り「抽象的」でありたいと願っている。抽象的であることによってのみ獲得される情調があり、抽象的であることによってのみ達成される事物がある。ぼくがここでぼくの本物のつらさや本物の悲しみについて具体的に、細部を克明に書き記すことであなたに得られるものは、ほとんどなに一つないだろう。「これはあなたのケースで、わたしはそうではないわ」とあなたは言うだろう。それは至極まっとうな言い分だ。
フォーマットとしてたくさんの種類の小説がある。時系列に沿って書き上げられたものもあれば、時系列的な順序がめちゃくちゃなものもある。年代記もあれば未来の話もある。もちろん、過去のエピソードが入れ子構造になっているものもあるし、それらが組み合わされたものもある。あげればきりがない。
小説の語り部がその小説自体について物語内で言及することはアンフェアにも思えるが、そんなことはさして重要なことではない。これは前述したどのフォーマットとも少し異なる、いわば抽象的な短編小説である。
✳︎
抽象的であることはときとして素晴らしい。
それが自分にも起こり得ることとして受け入れ易いからだ。しかしもちろん、危険も孕んでいる。
四月の手紙を九月に読んだぼくは、その四月から九月までの間に本物の悲しみに苛まれた。それは蓄積された悲しみであり、同時にぼくをぼくたらしめる特性の否定であった。
ぼくの歴史は無に等しいと思った。しかし、それは生易しい表現にすぎなかった。
実際のところ、ぼくの歴史は無未満なのだ。つまり、無のほうがマシだと言うことだ。
ぼくがこれまで出会った、そして大切なひととして認識してきた彼ら・彼女ら・彼にも彼女にも属さない…あるいは彼であり彼女でもある友人たちにとって、ぼくとの関わりなどないほうがよかった。これがぼくの行き着いた結論である。
ある人にとっては時間の無駄で、またある人にとっては人生を損なわれる結果となった。これは一重に、ぼくが責任を負うべきものだ。
ある友人はぼくに言った。
「おまえにとっては重要じゃないことかも知れないが、俺にとっては絶望に似たことをおまえは平気でやるから、俺は疲れてしまった。
今の問題はおまえのだらしなさ、大人になれないおまえの問題だけだ。このままじゃおまえの周りの人間、一人残らず確実に不幸にするぞ?
誠意っていうのは、その中に『自分』があっちゃいけないんだ。おまえの全ては、自分中心に回りすぎてる」
彼はぼくにとって、一番の親友だった。
「狡さっていうのは俺には通用しないんだよ、本質でしか見てないから。
わかってないのもわかってる、わからないのもわかってる。でも俺にも限界がある。
価値観の違いだと思おうとして俺自身誤魔化してきたけど、あまりにも酷い。
自分が関わっている人をどれだけ巻き込んで引き摺りこんでいるか、これは俺以外の人間に対してのことだが、おまえはわかっていない。わかっていないことも俺はわかってる。今までもそうだった。
でも俺がどれだけ、こちら側に引き戻そうと時間をつかってきたか、おまえにはほんとうにわからないと思う。
おまえがどれだけ、気づかないところで人を裏切っているのかわからないと思う。
その自覚すらきっとないから、新しい逃げ道しか見つけられないよ、きっと」
そして最後に彼は言った。
「当たり前のことを少しずつやるしか無いんだよ、おまえにはもう昼も夜も働いてそのほとんどを何かに返していくしか道は残ってないんだよ。
俺が言いたいことなんて山ほどある。悲しいし悔しいし腹立たしいし、心配もしてる。アホらしい。
こんな感情をよく人に与えたもんだよ、ほんとに」
✳︎
我々はかつて親友同士だった。でも、だからこそ最後に言ってくれたんだろう。
我々はかつて親友同士だった。
もう上手く思い出せないほど昔の話だ。
✳︎
彼の言うとおり、平たく言えばぼくは「屑」だった。しかしそれに気づいていない屑。人の気持ちがわからない、人の気持ちを踏み躙ることを平然とやった。
ぼくはそれに気づくまで、自分でも何をしていたのかわからなかった。ただ生きていた、それだけだ。
気がついたとき、ぼくにはそれを償うすべさえ残されてはいなかった。誰もぼくとは会おうとしなかったし、連絡をしても返してくれる人は一人もいなかった。
ぼくは自分を屑だと蔑むことで、なにも独り自己憐憫に浸っているわけではない。
ただ思うのは、「屑のなかにも貴賤がある」ということだ。
自分を屑だと自覚している人間は少なくはないだろう。それが勘違いで、実際には本人が思うほど屑ではないというケースもある。しかし、明らかに屑であるにもかかわらず、「自分が屑だと自覚していない人間」、これはもうほんとうに屑、屑のなかでも取り立てて屑である。掛け値なしの屑。屑のなかの屑と言って差し支えない。
ぼくの屑度合いとは、まさにこれに当てはまった。
ぼくは自分が屑であるという事実、唾棄すべきろくでなしに過ぎないという事実を認識していなかった。
✳︎
大切なひとたちから一切の連絡が途絶えて久しい。
ぼくにとっての大切なひとたちが死んだとして、ぼくにはその死を知るすべがない。本物の悲しみ…。ぼくはたった一人老いてゆくのだ、そしてたった一人死ぬのだ。ぼくが死ぬそのとき、ぼくはつらくて悲しくて泣くのだろう。ぼくは死ぬことが怖かった。
ぼくがもし大切なひとたちよりも先に死ぬなら、大切なひとが死ぬという本物の悲しみに見舞われることはないだろう。しかしそれでも、ぼくは自分が死ぬとき、おそらくつらくて悲しくて泣くのだろう。
いずれにせよ何人にも本物の悲しみが降り注ぐことは確定している。決まっているんだ、ちゃんと。
✳︎
時々遠くのほうから、列車の走る音、線路の軋みが聞こえる気がした。
その列車にはぼくの大切なひとたちが一人残らず乗っていた。大きな旅列車ではないが向かい合うボックス席はほとんど満席で、誰もがぼくとの再会を楽しみに談笑していた。その中には時空を超えて各々に時間を潰す人たちの姿もあった。デイジーは虚な目をしてぼくに恋焦がれ、アリョーシャは慎ましく両膝を揃えぼくに会った時まず何を口にするかということに思いを巡らせていた。レオポルド・ブルームは長すぎる一日にうんざりしながら車窓からの風景を眺め、かのウンベルト・ペニャローサは胃痛に耐えながら、早くもその人格に崩壊の兆しを見せている最中だった。
ガタンゴトン、ガタンゴトン…。
✳︎
大切なひとの死を知るすべがある例外として、両親、そして田舎の祖母がいた。
四月にその祖母が死んだ。新型ウイルス蔓延の影響で三年間会いに行けなかった。これは紛れもなく本物の悲しみだった。
彼女も、時折その軋みが聞こえるあの列車に乗り込んでいた。ぼくと会えることを楽しみにしてくれている。ぼくはそのことが嬉しかった。ぼくは列車の到着を心待ちにしている。でもぼくを覆う悲しみは消えはしなかった。彼女はもう死んでしまっていて、ぼくはまだ生きている。その死を聞いたあとあてもなく国道沿いを歩いていたぼくを、大型トラックの影たちが何度も何度も轢き殺した。それでもぼくは死ねなかった。
✳︎
五月に入るとぼくは、休みがちになっていた仕事を無断欠勤するようになった。料金未払いで電話が止まるまでは毎日なにかと理由をつけて連絡だけは入れていたが、最終的にはそのまま辞めた。社会的モラルに反する辞め方だったが、もう自分にもそれをどうすることもできなかった。しばらくして会社から解雇通知が届いた。それでぼくは仕事をくびになったことを知った。
五月は転落の季節だった。借金をし、その金をあたかも自分の貯金のように使い果たす。後先考えずにそれを繰り返した。この、生活とも言えないような酷い暮らしは九月まで続くのだが、一人暮らしのアパートの家賃さえ後回しにしていた。他人の金をなににつかったのか、それさえ憶えていない。
とうとう十年来行きつけだったバーに顔を出すことさえなくなってしまった。
そのバーはぼくのかつての一番の親友にとっても行きつけだったので、顔を合わせることを避けるために事前に連絡してから行かねばならなくなっていた。しかも仲が良かった他の常連客が足を運ぶことの多い土日は、彼も顔を出す可能性が高かったので行くことができなかった。彼のほうがぼくより後から常連になったが、連絡を入れねばならないのは必ずいつもぼくだった。あるいは事実である可能性も大いにあるけれど、親愛なるマスターはぼくより彼を優遇しているのではないだろうかという邪推から、徐々に足が遠のいた。そして、これまで仲良くしていた他の常連客たちとの大切な繋がりも途絶えた。
ぼくの孤独感はいよいよ本格的に強まっていった。
✳︎
六月のある雨の日、ぼくは路上で猫がスクーターに撥ねられる場面に居合わせた。
ぼくはその場面を今でもよく思い出す。日常生活を送るなかで「目の前で轢かれた猫を見殺しにしたときと同じだな」と感じる場面が時折ある。
そのスクーターの運転手は猫を撥ねたその瞬間、「クソがっ」と口走ってそのまま走り去った。
ぼくは本心から咄嗟に猫を助けたくて、交通量が多いその通りの歩道でどうしたものかと物怖じしていた。が、後続車が停まりヒールを履いた若い女性が中から現れて、すぐ近くのコンビニへと駆け込んでいった。
彼女は大きなビニール袋を手に戻ってきて、痙攣する猫を抱き抱えると車へと乗り込んで猛スピードで去っていった。
あの女性は猫を病院へ連れて行ったのだと思う。彼女がコンビニへ走り戻るまでのその間、ぼくはビクビクと苦しそうに悶える猫を見つめただ立ち尽くすばかりだった。
あのときとった自分の行動にぼくは失望した。「もし今度同じことが起こったら」と反復して考え続けた。ヒールを履いて走りづらそうに、夢中でコンビニへと駆け込んだあの女性の姿を何度も何度も思い返して、寝覚めの悪い夢を見続けていた。
もちろんぼくは昔から壊れていたと思う、昔のことはよく思い出す。
薄っぺらい正義感のようなものかも知れない。だがこれは、もっとずっと昔、ぼくが比較的まともだった時代から感覚的に存在し続けてきたものだった。ぼくはそれをただ見過ごすことができない。ほとんど反射的に、いわば本能に近い衝動で、ぼくは不器用なりにただアウトプットする。アクションを起こすのだ。場合によっては自己満足でしかないかも知れない。でもそれは自分の考えやら思想やらを敷衍したりアピールしたり押しつけたりする目的からではなくて、頭で考えるよりもまず身体が動いてしまう…といった類のことだった。
それはかつての「ぼくという人間」の、美徳とは言えないまでも本質であることに間違いなかったはずだ。
好むと好まざるとにかかわらず、こういった特定の局面、シチュエーションにおいて必ず自らがとってしまう行動、選びとってしまう結果であり、筋の通った人間性であり、突き詰めて言えばそれが「ぼくという人間」であり、最期まで残り続けるものだと思っていた。
身に余るようなことだけれど、ぼくが死んで、誰かがぼくについてなにかを口にしてくれたとする、「あいつはああいう人間だった。あいつらしいな」。そういう場面で、残るものだと思っていた。
だから、ぼくが猫を助けるべきだったのだ。
あの頃のぼくなら真っ先に猫を助けただろう、そう思える時代がぼくにもあったはずなのだ。
✳︎
七月にぼくはまた一つ歳をとった。そのことを祝ってくれるひとは誰一人としていなかったし、ぼく自身も歳をとることに喜びなど感じ得なかった。
脳内では楽しかったはずの過去の誕生日パーティーの思い出が酷く脚色されて再生された。
「くだらない、あいつの誕生日パーティーの招待状なんか送り返せ!」
「何歳まで生きるつもりだ?」
ぼくは滑稽さが際立つ三角帽子をかぶり、パーティー会場に独り立ち尽くしていた。
どこまでがほんとうに起こったことで、どこからがぼくの勝手な脚色なのかわからなかった。はっきりしていることは、もう誰もぼくのためにパーティーなど開かないということ、さらに言えばもう誰もぼくをパーティーに招待などしないということだった。
ぼくはこの命の続く限り何度でもこの思いを味わうことになるのだと考えると、底知れぬ孤独感に苛まれた。死ぬことは怖かった。でも、生きることを続けることはそれにも増して怖かった。できるだけ楽な死に方を調べもした。ぼくは空想のなかで何度も死に、その度につらくて悲しくて泣いた。その涙は軽くて薄っぺらくて、そのことがぼくの滑稽さをより際立たせていた。七月中ぼくは、一人として参加者がやってくる見込みもないパーティー会場で三角帽子をかぶり、ただ列車の到着を待っていた。
✳︎
世界中のカレンダーは音もなく八月へと切り替わっていた。
七月から八月にかけて、たくさんの人が死んだ。そのなかには著名人も含まれるし、刑が執行された死刑囚も含まれていた。
まだほんの子どもだった頃、ずっとずっと昔から、ぼくにとってそもそも人の死というものがおしなべて悲しいものだった。
例えば、一度の死刑では足りないんじゃないかと思われるような残虐の限りを尽くした死刑囚もいるけれど、そんな連中にだって死んだ意義みたいなものはあると思った。刑が執行されたことで、生きていたときと死んだあとでは、なにかを同じようには語れない、漠然としたーーー人によってはあるいは判然とした、確固たるーーー違いを残していることは少なくとも確かだと思う。
それくらい人の死とは重いというか、ある意味ではこれ以上は望めない極限の境界線であり、不可逆的な、絶対に元には戻せないという絶対性を孕んでいると、ぼくは考えている。
以前のぼくは口が悪くて態度も悪くて、しょっちゅう誰かに対して中指を突き立てて生きていた。「死ね」という言葉を口にすることも多かった。
現実にはあり得ないことだけれど、ぼくが死ねと言った対象の人物が仮にその場で死んだら、ぼくは多分その場で泣いたと思う。人の死を重いと認識している自分があるのに、その自分の内面には双極性の乖離がある(それがぼくの抱える大きな欠陥の一つなのは決定的事実だと思うけれど、それはまた別の話だ)。
人が死ぬということは、生きているこの自分とは、そしてもちろん生きている他の誰とももう永遠に交われない・関われない・その反応を感知できないとか、そういうことだ。完全に違う次元に行ってしまう、フェードアウトしてしまう。絶対に戻ってこない。そのひとがここにいたら…というのはもう幻想であり仮定でしかなくなり、脳みそで想像して補うことしかできないはずだ。究極的な別れだと言ってもいいと思う。
そのなかには肉体の消滅、消滅と言ってしまえば聞こえは悪くないが、どんな死に方をしても、その直前まで生命活動を行なっていた人体が壊れる・腐る…骨にまでなってしまえば綺麗だけれど、否応なくそういう過程(生きている側から見たら汚いこと、あり得ないくらい臭いこと、直視するのが難しいほどに生々しいこと、極限にグロテスクなこと)が必ず含まれているのだ。どんな死にでも。もうその臓器は機能していなくて、臓器が機能していない人体は放っておけば腐るだけで、その亡骸はもう祖母でもなければシドでもナンシーでもない…とも言えるわけだ。対面したそのひとが、死んだ人間のどの部分をもってそのひとと思うか? 魂とでも言うならその魂はもうその肉体には入っていない、じゃあその腐るばかりの肉の塊はそのひとじゃない。そう割り切れる人もなかには大勢いるだろう。大して知らない人の死なら尚更だ。でも死者にとって、生前ただの「期限付きの所有物」「借り物」だったとしても、その死骸はそのひとのーーー生きている者たちがそれぞれそのひととして想像する・思い返す・そのひとそのもののーーー形をとっていて、それが対面した相手に与える印象には大きな衝撃、インパクト、あるいはギャップというか相違、違和感があると思う。そういうのを目の当たりにして初めて、人は「このひとは死んだんだ」と納得できるのかも知れない。報道されたり人づてに聞いたところで、信じられない人だってきっとたくさんいる。棺桶のなかに収まっているそのひとの残骸みたいな死の証拠を、死者の生前を知っている人全員が拝めるわけじゃない。ただそのひとの不在を認識するだけだということが、死という事象全体の大部分を占めるのではないだろうか。
怒りの感情は突発的なものだってよく言うでしょう? なかには根深い執念的な怨みもあるだろうけれど、それだって人の寿命が数百年・数千年続くなら立ち消えてしまうんじゃないだろうか。
死に際に「末代まで呪ってやる」とか口走ろうが、孫の孫まで呪ったってせいぜい二百四十年とかそこいらだものな。そういう尺度で見たら蜜蜂がすぐ死ぬみたいなのと大して変わらないような気さえしてくる、そういう観点からなら人間だって、すぐ死んじゃうんだよ。なんだったら自分の体感している時間なんて、それこそ蜜蜂が体感している時間と変わりないんじゃないかな…とさえ思えてくる。
ぼくが誰かに対して何かしら怒りを覚えて、許せなかったとしても、その相手が死んだら即座に無条件に、その場で許してしまうような気がする。死んだ人間に対しては大抵のことが許せそうな気がする。
考えたくもないけれど、ぼくに妻がいて、彼女が殺されたとする。それをぼくは死んでも許せないだろう。
でも、ぼくがその後も妻のいない世界で生きていくとする。そのうちに怒りより、「あのひとがいない」という悲しみだけが残って、怒りを上回って押し潰して、ついには消してしまうだろう。そう考えると怒りという感情は、突き詰めればぼくという自分のためだけの、やり場がなくなる運命しか辿れない小物なのかも知れないなと、そう思う。何よりも重大なのは「妻が死んでしまった」ことで、もう会えなくて、反応も貰えなくて、ぼくの脳みそで想像することしかできなくて、さみしくて悲しいということに、たえられそうもないことだ。
それでもぼくの、妻に対する愛みたいなものは消えないだろう。ずっと想い続けるはずだから、生きるならあるいはずっと独り身でいるかも知れない。もしぼくが死んだら(現世で会えないのはわかりきっているのだから)、死んだ先でまた会えるかも知れないと考えるだろう。死後にどうなるのかなんてわからないから、一縷の望みを託すように自分で死んでみるかも知れない。でも、それはまた同じことの繰り返しのように思えなくもない。ぼくが死ぬことでぼくの大切なひとたちは、以前のぼくとまったくの同一の感情までは抱かないかも知れないが、それでもやはり、悲しむんじゃないだろうか。そういうことを想像したら、簡単には自殺なんてできないはずなんだ。生きている人から見たら、あまりに身勝手な選択にも思えることなんだ。でも例にあげたぼくの場合は、それよりも死んだ妻と会えるかも知れないという、その想いのほうがきっと強い。その想いを抑えることなんてきっとできない。
もっと単純に、あるいは複雑に、別の理由から。例えばぼくはぼくが許せない。消えてしまいたい(ぼくは「死にたい」と口にしたことはなくて、そういうとき「消えたい」という言葉を独りで口にしていたことを憶えている。抽象的であるほうがまだ救いがあったから直截的な言葉を避けていたんだと思う)。そんなとき、誰かに相談することはできないんだ。迷惑がかかると思ってしまう。勝手にやるべき。ずれた責任感(でも周りに消えたいとアナウンスすることが責任感なんて言えるのか? それは責任感の対極にある行動ではないか?)、誤った責任感を持ってしまって、履き違えて、ちゃんと考えに考え抜いてその責任感を実行してしまうひと。そういうひとが自殺するんじゃないだろうか?
ぼくはそれがとても悲しい。涙が出てくる。例え大して知らない赤の他人のことでも、なぜだか涙が出てくるんだ。
✳︎
そして九月。ぼくは四月の手紙を九月に読んだ。このままじゃいけないということは、嫌というほど自分でもわかっていた。
働きもせず借金を繰り返す毎日。曜日の感覚すらなく、今が何日なのかわからない…かろうじて九月であるということがわかる、それだけが、ぼくにとっての時間感覚のすべてだった。
金木犀の花の香りはぼくに孤独を思い出させた。大好きな香りだが、そこには手で触れられる現実の、実際的な孤独感が否応なくしがみついていた。
社会復帰の時期だな、と、ぼくは思う。いつまでもこんな毎日を刻んでゆくわけにはいかないのだ。この半年余りでぼくがしたことと言えば、過去の記憶を無制限に再生させること、ただ罪悪感に苛まれ日々を無下に送ること、そして完全なる孤独のなかで自分と向き合い、人の死について思いを巡らせること、これだけだ。
どれほどの人を傷つけてきたのだろう、と、ぼくは思う。どれほどたくさんの人たちを損なってきたのだろう。
それを考えるとあまりにも、ぼくの生きた歴史は打算的で、罪深いものだった。
償うすべがあるのなら、まずはぼく自身のこの生活を立て直す必要があった。誰の目から見ても、今のぼくにはその罪を償う資格すら与えられてはいないのだ。屑のままで、独り勝手に命を終えるしか道は残されていないのだ。
✳︎
ぼくは列車の到着を待っていた。
運転士はなにをやっているのだ? なぜこんなにも、到着が遅いのだ?
でも、その空想の列車に運転士がいるのだとすれば、それはぼく自身だった。
みんながーーーぼくの大切なひとたち、全員がーーーぼくとの再会を待ち侘びて乗り込んだ列車が到着するためには、まずはぼくが運転士としてその役割を果たさなければならない。
ガタンゴトン…。聞こえる。
ガタンゴトン…、まだ聞こえている。列車の走る音と、線路の軋みが、まだ確かに。過ぎてゆく毎日と、積み重ねてゆくぼくのやるべきこと。夜も、朝も、その列車は走り続ける。忘れはしない。
ガタンゴトン、ガタンゴトン。
今は閉ざされていても、きっとぼくはそれを切り開くだろう。
ガタンゴトン、ガタンゴトン。
いつか届くまで。出発進行。
ガタンゴトン、ガタンゴトン。
ぼくは成すべきことを成し、列車を終着駅へと走らせる。大丈夫。頑張れ。
20
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説

妻を蔑ろにしていた結果。
下菊みこと
恋愛
愚かな夫が自業自得で後悔するだけ。妻は結果に満足しています。
主人公は愛人を囲っていた。愛人曰く妻は彼女に嫌がらせをしているらしい。そんな性悪な妻が、屋敷の最上階から身投げしようとしていると報告されて急いで妻のもとへ行く。
小説家になろう様でも投稿しています。
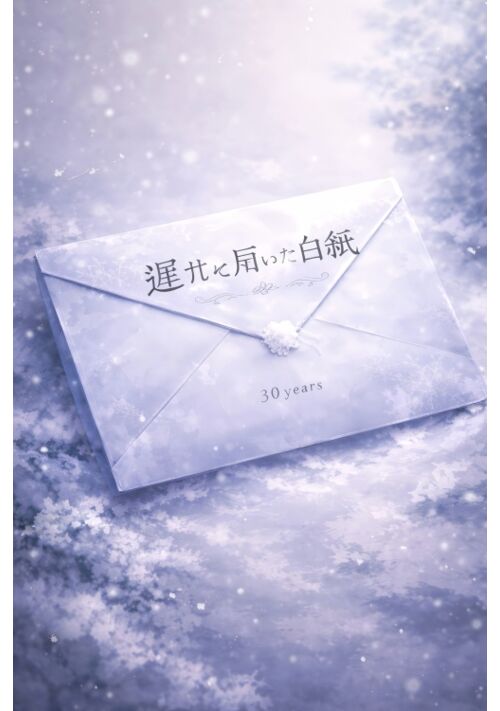
三十年後に届いた白い手紙
RyuChoukan
ファンタジー
三十年前、帝国は一人の少年を裏切り者として処刑した。
彼は最後まで、何も語らなかった。
その罪の真相を知る者は、ただ一人の女性だけだった。
戴冠舞踏会の夜。
公爵令嬢は、一通の白い手紙を手に、皇帝の前に立つ。
それは復讐でも、告発でもない。
三十年間、辺境の郵便局で待ち続けられていた、
「渡されなかった約束」のための手紙だった。
沈黙のまま命を捨てた男と、
三十年、ただ待ち続けた女。
そして、すべてを知った上で扉を開く、次の世代。
これは、
遅れて届いた手紙が、
人生と運命を静かに書き換えていく物語。

冤罪で辺境に幽閉された第4王子
satomi
ファンタジー
主人公・アンドリュート=ラルラは冤罪で辺境に幽閉されることになったわけだが…。
「辺境に幽閉とは、辺境で生きている人間を何だと思っているんだ!辺境は不要な人間を送る場所じゃない!」と、辺境伯は怒っているし当然のことだろう。元から辺境で暮している方々は決して不要な方ではないし、‘辺境に幽閉’というのはなんとも辺境に暮らしている方々にしてみれば、喧嘩売ってんの?となる。
辺境伯の娘さんと婚約という話だから辺境伯の主人公へのあたりも結構なものだけど、娘さんは美人だから万事OK。



友人の結婚式で友人兄嫁がスピーチしてくれたのだけど修羅場だった
海林檎
恋愛
え·····こんな時代錯誤の家まだあったんだ····?
友人の家はまさに嫁は義実家の家政婦と言った風潮の生きた化石でガチで引いた上での修羅場展開になった話を書きます·····(((((´°ω°`*))))))

どうやらお前、死んだらしいぞ? ~変わり者令嬢は父親に報復する~
野菜ばたけ@既刊5冊📚好評発売中!
ファンタジー
「ビクティー・シークランドは、どうやら死んでしまったらしいぞ?」
「はぁ? 殿下、アンタついに頭沸いた?」
私は思わずそう言った。
だって仕方がないじゃない、普通にビックリしたんだから。
***
私、ビクティー・シークランドは少し変わった令嬢だ。
お世辞にも淑女然としているとは言えず、男が好む政治事に興味を持ってる。
だから父からも煙たがられているのは自覚があった。
しかしある日、殺されそうになった事で彼女は決める。
「必ず仕返ししてやろう」って。
そんな令嬢の人望と理性に支えられた大勝負をご覧あれ。
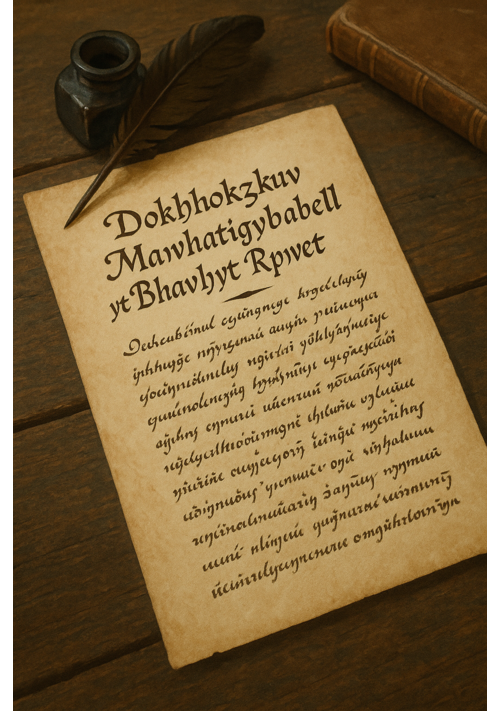
冷遇妃マリアベルの監視報告書
Mag_Mel
ファンタジー
シルフィード王国に敗戦国ソラリから献上されたのは、"太陽の姫"と讃えられた妹ではなく、悪女と噂される姉、マリアベル。
第一王子の四番目の妃として迎えられた彼女は、王宮の片隅に追いやられ、嘲笑と陰湿な仕打ちに晒され続けていた。
そんな折、「王家の影」は第三王子セドリックよりマリアベルの監視業務を命じられる。年若い影が記す報告書には、ただ静かに耐え続け、死を待つかのように振舞うひとりの女の姿があった。
王位継承争いと策謀が渦巻く王宮で、冷遇妃の運命は思わぬ方向へと狂い始める――。
(小説家になろう様にも投稿しています)
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















