5 / 8
第五話 今の想いを言葉に
しおりを挟む
ケーキを一口食べた瞬間、自然と頬がゆるむ。
「……美味しい」
「うむ。甘ったるくなくて何個でも入りそうだ……」
他愛ない感想を交わしながら、ケーキと紅茶を味わう。さっきまで胸にあった緊張が、少しずつ溶けていくのを感じた。――今なら、言えるかもしれない。
私は、カップをそっと置き、もう一度深呼吸をした。
(……よし)
「先ほどの話なんですけど……」
そう切り出すと、アルベルト様もカップを置き、いつもの穏やかな表情を引っ込めて、真剣な眼差しでこちらに向き合ってくれた。
「誤魔化しても仕方がないので、直球で言いますね。アルベルト様は、今は彼女……のことを、どう思っていますか」
周りにはまだ人がいる。声を潜めてはいるが、公爵令嬢、と特定されるような言葉は避け、あえて曖昧に伝えた。
アルベルト様は、私の意図をすぐに察したように小さく頷き、安心させるように微笑む。
「なるほど。理解したよ」
そう言ってから、少しだけ間を置いた。
「つまり君は、少し前まで彼女に恋をしていた僕が、今はどんな気持ちを抱いているのか。それが知りたい、ということだね」
顎に手を当て、言葉を探すような仕草をしてから、アルベルト様ははっきりと続けた。
「まず、はっきり言えることが一つある。僕はもう、彼女に対して恋愛感情は一切抱いていない」
その声音には、迷いも、ためらいもなかった。
「これは本心だ。だから、何も心配しなくていい。僕は今、君のことが百パーセント好きだと、声高らかに言えるぐらいだからな」
あまりにも堂々と言われて、思わず頬が熱くなるのを感じた。
「それから……そうだな。君からすれば“ちょっと前”の話なのだろうが」
アルベルト様は、どこか懐かしむように笑う。
「僕からすれば、彼女に恋心を抱いていたのは、もう三十年以上も前のことだ。さすがにそんな昔の感情は、僕ですらほとんど覚えていないのだよ」
アルベルト様の言葉を聞き終えて、胸の奥に溜まっていたものが、すうっとほどけていくのを感じた。
「……ありがとうございます」
それだけ言うのが精一杯で、視線を落とす。
「正直に話してくれて、嬉しいです。私、今日の歴史学のとき……ちょっとだけ、不安になってしまって」
ティーカップの中に広がる琥珀色の水面を見つめながら、言葉を絞り出す。
「原作のアルベルト様なら、ああいう場面で、きっと彼女の隣に座ったり、声をかけたりするんだろうなって。だから……今のアルベルト様を見ていても、つい、勝手に重ねて考えてしまって……」
「でも、それってだめだなって思ったんです。人の気持ちを、私の想像で決めつけるみたいで……ここはもう物語の世界じゃないのに」
小さく息を吸って、続けた。
「だから、ちゃんと聞こうって。アルベルト様に、直接聞こうと思ったんです」
言い終えた途端、遅れて猛烈な恥ずかしさが込み上げてきた。アルベルト様の目を直視できず、手元のカップを意味もなく見つめる。彼は私の言葉を遮らず、最後まで静かに聞いてくれていた。
「ちゃんと聞いてくれて、ありがとう。うむ……不思議なことだが、本当に以前の僕に引っ張られる部分が、口調以外ほとんどなくてな」
アルベルト様はそう言って、少しだけ肩の力を抜いたように微笑む。
「彼女に関しては、本当に何の未練もないのだよ。まぁ……三十数年も生きれば、以前より落ち着きも出るというものさ」
そして、ふっと表情を和らげて、こちらを見る。
「それよりも――君が、やきもちを焼いてくれたことのほうが、僕は嬉しいのさ」
「……え」
心臓が、跳ねるように音を立てた。
「ほんとだ……私、やきもち、焼いてたんですね」
自分の言葉に、今さら気づいて、頬が熱くなる。
「今、気づいたのかい?」
くすっと楽しそうに笑われる。
「可愛らしいではないか」
「……からかわないでください」
そう言い返しながらも、口元が緩んでしまうのを、どうしても止められなかった。
私は照れたのを隠すように紅茶を一口飲んだ。けれど、そのつもりもお見通しだったのだろう。アルベルト様は、にこにこと楽しそうにこちらを見ている。
「他に、まだ心配事や気になることはないかい?」
「はい、おかげさまで……あ、ひとつだけあります。アルベルト様……」
わざと少し間を置いてから、私は口元を緩めた。
「今、関西弁ですか?」
私がそう尋ねると、アルベルト様は一瞬きょとんとしたあと、大きく笑った。
「いや、もしかしたら九州弁かもしれないよ」
「……それはもう、別人ですね」
思わずそう口にすると、アルベルト様は堪えきれなかったように肩を揺らして笑った。
「ははは、そうかもしれないな」
指先で目尻を軽く押さえながら、楽しそうに息を整える。
「だが、まあ……別人というか、ちょっと人より人生経験が豊富な、ただのアルベルト・レイヴンさ」
その言い方があまりに自然で、肩の力が抜けていて、私は思わず微笑んでしまう。
「なるほど……では私も、ちょっと人より人生経験が豊富なフェリシア・ヒルントですね」
冗談めかしてそう言うと、アルベルト様は一瞬驚いたように目を瞬かせ、それからふっと優しく笑った。
「ふふ。お揃いだな」
そう言いながら、テーブルの上に置かれた私のカップの方へ、ちらりと視線をやる。
「……嬉しく思ってくれるかい?」
「えぇ。お揃い、嬉しいです」
そう答えると、アルベルト様は満足そうに小さく頷いた。
紅茶を一口飲みながら、カップの縁越しに向けられるその穏やかな視線が、なんだか少しだけ照れくさくて、でも――心地よかった。
紅茶を一口飲みながら、他愛ない話から少し踏み込んだ話まで、ゆっくりと言葉を交わしていく。ひとつ話すたび、ひとつ頷き合うたびに、互いの距離がほんの少しずつ近づいていくのが分かった。
ただ一緒にいて、同じ時間を過ごしているだけで心地いい。これからも、アルベルト様とそういう未来を歩んでいけるのだろう、そんな安心感が、胸の奥に静かに広がっていた。
ケーキ屋を出る頃には、空はすっかり夕暮れ色に染まっていた。
名残惜しさはあったけれど、不思議と寂しさはない。また明日も、その次の日も、こうして言葉を交わせるのだから。
「……美味しい」
「うむ。甘ったるくなくて何個でも入りそうだ……」
他愛ない感想を交わしながら、ケーキと紅茶を味わう。さっきまで胸にあった緊張が、少しずつ溶けていくのを感じた。――今なら、言えるかもしれない。
私は、カップをそっと置き、もう一度深呼吸をした。
(……よし)
「先ほどの話なんですけど……」
そう切り出すと、アルベルト様もカップを置き、いつもの穏やかな表情を引っ込めて、真剣な眼差しでこちらに向き合ってくれた。
「誤魔化しても仕方がないので、直球で言いますね。アルベルト様は、今は彼女……のことを、どう思っていますか」
周りにはまだ人がいる。声を潜めてはいるが、公爵令嬢、と特定されるような言葉は避け、あえて曖昧に伝えた。
アルベルト様は、私の意図をすぐに察したように小さく頷き、安心させるように微笑む。
「なるほど。理解したよ」
そう言ってから、少しだけ間を置いた。
「つまり君は、少し前まで彼女に恋をしていた僕が、今はどんな気持ちを抱いているのか。それが知りたい、ということだね」
顎に手を当て、言葉を探すような仕草をしてから、アルベルト様ははっきりと続けた。
「まず、はっきり言えることが一つある。僕はもう、彼女に対して恋愛感情は一切抱いていない」
その声音には、迷いも、ためらいもなかった。
「これは本心だ。だから、何も心配しなくていい。僕は今、君のことが百パーセント好きだと、声高らかに言えるぐらいだからな」
あまりにも堂々と言われて、思わず頬が熱くなるのを感じた。
「それから……そうだな。君からすれば“ちょっと前”の話なのだろうが」
アルベルト様は、どこか懐かしむように笑う。
「僕からすれば、彼女に恋心を抱いていたのは、もう三十年以上も前のことだ。さすがにそんな昔の感情は、僕ですらほとんど覚えていないのだよ」
アルベルト様の言葉を聞き終えて、胸の奥に溜まっていたものが、すうっとほどけていくのを感じた。
「……ありがとうございます」
それだけ言うのが精一杯で、視線を落とす。
「正直に話してくれて、嬉しいです。私、今日の歴史学のとき……ちょっとだけ、不安になってしまって」
ティーカップの中に広がる琥珀色の水面を見つめながら、言葉を絞り出す。
「原作のアルベルト様なら、ああいう場面で、きっと彼女の隣に座ったり、声をかけたりするんだろうなって。だから……今のアルベルト様を見ていても、つい、勝手に重ねて考えてしまって……」
「でも、それってだめだなって思ったんです。人の気持ちを、私の想像で決めつけるみたいで……ここはもう物語の世界じゃないのに」
小さく息を吸って、続けた。
「だから、ちゃんと聞こうって。アルベルト様に、直接聞こうと思ったんです」
言い終えた途端、遅れて猛烈な恥ずかしさが込み上げてきた。アルベルト様の目を直視できず、手元のカップを意味もなく見つめる。彼は私の言葉を遮らず、最後まで静かに聞いてくれていた。
「ちゃんと聞いてくれて、ありがとう。うむ……不思議なことだが、本当に以前の僕に引っ張られる部分が、口調以外ほとんどなくてな」
アルベルト様はそう言って、少しだけ肩の力を抜いたように微笑む。
「彼女に関しては、本当に何の未練もないのだよ。まぁ……三十数年も生きれば、以前より落ち着きも出るというものさ」
そして、ふっと表情を和らげて、こちらを見る。
「それよりも――君が、やきもちを焼いてくれたことのほうが、僕は嬉しいのさ」
「……え」
心臓が、跳ねるように音を立てた。
「ほんとだ……私、やきもち、焼いてたんですね」
自分の言葉に、今さら気づいて、頬が熱くなる。
「今、気づいたのかい?」
くすっと楽しそうに笑われる。
「可愛らしいではないか」
「……からかわないでください」
そう言い返しながらも、口元が緩んでしまうのを、どうしても止められなかった。
私は照れたのを隠すように紅茶を一口飲んだ。けれど、そのつもりもお見通しだったのだろう。アルベルト様は、にこにこと楽しそうにこちらを見ている。
「他に、まだ心配事や気になることはないかい?」
「はい、おかげさまで……あ、ひとつだけあります。アルベルト様……」
わざと少し間を置いてから、私は口元を緩めた。
「今、関西弁ですか?」
私がそう尋ねると、アルベルト様は一瞬きょとんとしたあと、大きく笑った。
「いや、もしかしたら九州弁かもしれないよ」
「……それはもう、別人ですね」
思わずそう口にすると、アルベルト様は堪えきれなかったように肩を揺らして笑った。
「ははは、そうかもしれないな」
指先で目尻を軽く押さえながら、楽しそうに息を整える。
「だが、まあ……別人というか、ちょっと人より人生経験が豊富な、ただのアルベルト・レイヴンさ」
その言い方があまりに自然で、肩の力が抜けていて、私は思わず微笑んでしまう。
「なるほど……では私も、ちょっと人より人生経験が豊富なフェリシア・ヒルントですね」
冗談めかしてそう言うと、アルベルト様は一瞬驚いたように目を瞬かせ、それからふっと優しく笑った。
「ふふ。お揃いだな」
そう言いながら、テーブルの上に置かれた私のカップの方へ、ちらりと視線をやる。
「……嬉しく思ってくれるかい?」
「えぇ。お揃い、嬉しいです」
そう答えると、アルベルト様は満足そうに小さく頷いた。
紅茶を一口飲みながら、カップの縁越しに向けられるその穏やかな視線が、なんだか少しだけ照れくさくて、でも――心地よかった。
紅茶を一口飲みながら、他愛ない話から少し踏み込んだ話まで、ゆっくりと言葉を交わしていく。ひとつ話すたび、ひとつ頷き合うたびに、互いの距離がほんの少しずつ近づいていくのが分かった。
ただ一緒にいて、同じ時間を過ごしているだけで心地いい。これからも、アルベルト様とそういう未来を歩んでいけるのだろう、そんな安心感が、胸の奥に静かに広がっていた。
ケーキ屋を出る頃には、空はすっかり夕暮れ色に染まっていた。
名残惜しさはあったけれど、不思議と寂しさはない。また明日も、その次の日も、こうして言葉を交わせるのだから。
12
あなたにおすすめの小説
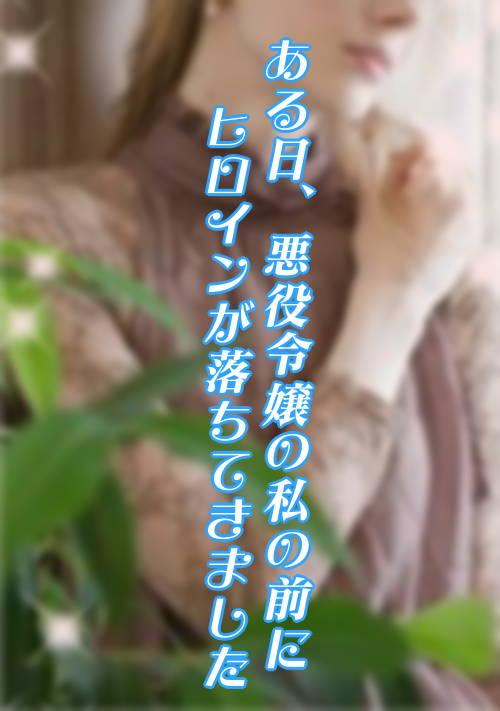
ある日、悪役令嬢の私の前にヒロインが落ちてきました
結城芙由奈@コミカライズ連載中
恋愛
【どうやら私はこの世界では悪役令嬢と呼ばれる存在だったらしい】
以前から自分を取り巻く環境に違和感を覚えていた私はどうしても馴染めることが出来ずにいた。周囲とのぎこちない生活、婚約者として紹介された相手からは逃げ回り、友達もいない学園生活を送っていた私の前に、ある日自称ヒロインを名乗る人物が上から落ちてきて、私のことを悪役令嬢呼ばわりしてきた――。
※短めで終わる予定です
※他サイトでも投稿中

気がついたら自分は悪役令嬢だったのにヒロインざまぁしちゃいました
みゅー
恋愛
『転生したら推しに捨てられる婚約者でした、それでも推しの幸せを祈ります』のスピンオフです。
前世から好きだった乙女ゲームに転生したガーネットは、最推しの脇役キャラに猛アタックしていた。が、実はその最推しが隠しキャラだとヒロインから言われ、しかも自分が最推しに嫌われていて、いつの間にか悪役令嬢の立場にあることに気づく……そんなお話です。
同シリーズで『悪役令嬢はざまぁされるその役を放棄したい』もあります。

溺愛王子の甘すぎる花嫁~悪役令嬢を追放したら、毎日が新婚初夜になりました~
紅葉山参
恋愛
侯爵令嬢リーシャは、婚約者である第一王子ビヨンド様との結婚を心から待ち望んでいた。けれど、その幸福な未来を妬む者もいた。それが、リーシャの控えめな立場を馬鹿にし、王子を我が物にしようと画策した悪役令嬢ユーリーだった。
ある夜会で、ユーリーはビヨンド様の気を引こうと、リーシャを罠にかける。しかし、あなたの王子は、そんなつまらない小細工に騙されるほど愚かではなかった。愛するリーシャを信じ、王子はユーリーを即座に糾弾し、国外追放という厳しい処分を下す。
邪魔者が消え去った後、リーシャとビヨンド様の甘美な新婚生活が始まる。彼は、人前では厳格な王子として振る舞うけれど、私と二人きりになると、とろけるような甘さでリーシャを愛し尽くしてくれるの。
「私の可愛い妻よ、きみなしの人生なんて考えられない」
そう囁くビヨンド様に、私リーシャもまた、心も身体も預けてしまう。これは、障害が取り除かれたことで、むしろ加速度的に深まる、世界一甘くて幸せな夫婦の溺愛物語。新婚の王子妃として、私は彼の、そして王国の「最愛」として、毎日を幸福に満たされて生きていきます。

冷徹宰相様の嫁探し
菱沼あゆ
ファンタジー
あまり裕福でない公爵家の次女、マレーヌは、ある日突然、第一王子エヴァンの正妃となるよう、申し渡される。
その知らせを持って来たのは、若き宰相アルベルトだったが。
マレーヌは思う。
いやいやいやっ。
私が好きなのは、王子様じゃなくてあなたの方なんですけど~っ!?
実家が無害そう、という理由で王子の妃に選ばれたマレーヌと、冷徹宰相の恋物語。
(「小説家になろう」でも公開しています)

66番目の悪魔と悪役令嬢 ~王子からの婚約破棄は契約魔法でブロック~
星森
恋愛
王宮の大広間で、第2王子セディリオは高らかに宣言した。
「イレーネ・ルクレール公爵令嬢との婚約を破棄し、メリィ・アーデン準男爵令嬢と新たに婚約する!」
だがその瞬間、婚約に関する契約魔法が発動し、イレーネと王子は逃げ場のない結界に閉じ込められる。
婚約破棄の理由が正当でないため、修正しなければ結界は解けない──それが、この契約魔法だった。
潔白を主張する王子。
静かに本を開き、お茶を淹れ、生活を始める公爵令嬢。
干し肉しか持たない王子と、予め準備していた備蓄で優雅に過ごす令嬢。
トイレ問題、食事問題、価値観の衝突……密室生活は、王子の未熟さを容赦なく暴いていく。
やがて明らかになるのは、
“聖女になり損ねた令嬢”メリィの虚偽と陰謀。
そして、王子自身の短慮と過ち。
結界から出る方法は3つ。
1. **王子が正当な婚約破棄理由を提示する**
2. **イレーネの提案する苛烈な結婚条件を受け入れて婚約を続行する**
3. **イレーネに婚約破棄させる**
追い詰められた王子は、ついに選択を迫られる。
「……俺が間違っていたことを、公表する」
しかしイレーネの条件は容赦がない。
白い結婚、側室の制限、離婚権の独占、そして──離婚時の臣籍降下。
これは愚かな王子と、冷静すぎる公爵令嬢が、結界の中で互いの人生を叩き直す物語。
契約魔法が解けたとき、2人の関係は“婚約者”のままなのか、それとも……?
⚠️この物語は一部にAIの生成した文章を使用しています。タイトル変えました。

旦那様は、転生後は王子様でした
編端みどり
恋愛
近所でも有名なおしどり夫婦だった私達は、死ぬ時まで一緒でした。生まれ変わっても一緒になろうなんて言ったけど、今世は貴族ですって。しかも、タチの悪い両親に王子の婚約者になれと言われました。なれなかったら替え玉と交換して捨てるって言われましたわ。
まだ12歳ですから、捨てられると生きていけません。泣く泣くお茶会に行ったら、王子様は元夫でした。
時折チートな行動をして暴走する元夫を嗜めながら、自身もチートな事に気が付かない公爵令嬢のドタバタした日常は、周りを巻き込んで大事になっていき……。
え?! わたくし破滅するの?!
しばらく不定期更新です。時間できたら毎日更新しますのでよろしくお願いします。


モブの私がなぜかヒロインを押し退けて王太子殿下に選ばれました
みゅー
恋愛
その国では婚約者候補を集め、その中から王太子殿下が自分の婚約者を選ぶ。
ケイトは自分がそんな乙女ゲームの世界に、転生してしまったことを知った。
だが、ケイトはそのゲームには登場しておらず、気にせずそのままその世界で自分の身の丈にあった普通の生活をするつもりでいた。だが、ある日宮廷から使者が訪れ、婚約者候補となってしまい……
そんなお話です。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















