8 / 8
第八話 何度でもあなたと
しおりを挟む
卒業後、私たちはほどなくして結婚した。アルベルト様はヒルント家に婿入りし、今では立派な後継ぎとして、家業に携わっている。
商会は相変わらず西へ東へと手を広げ、どの土地でも繁盛を見せていた。私は帳簿や契約書を整え、時には現地との交渉にも同行しながら、彼の隣でその歩みを支え続けている。
そんなある日、遠い東の国で――私たちは、見覚えのあり過ぎる穀物と調味料に出会った。
「……フェリシア」
「……はい」
袋の中を覗き込んだまま、二人してしばし沈黙する。次の瞬間、ほとんど同時に顔を上げた。
「これ、米じゃないかい」
「米ですね」
「しかも――」
「味噌、です」
確認するように囁き合ったあと、堪えきれずに噴き出してしまった。周囲の人間が不思議そうな顔をするのも構わず、私たちは声を潜めて、けれど目を輝かせた。
「前世の……」
「前世の、アレだな」
言葉にしただけで、胸の奥が熱くなる。この世界には存在しないと思っていた、あの味。あの記憶。それを、今こうして、隣にいる同じ“前世持ち”と共有している。
「……持ち帰ろう」
「絶対にです」
「おにぎり、食べたいな」
「お味噌汁も作りましょうね」
そう言って笑い合った時、ああ、私たちは本当に、同じ人生を二度歩いているのだと実感した。
それから先の年月は、穏やかに積み重なっていった。
商会はさらに大きくなり、国を越え、海を越えた。それでも私たちは、変わらず同じ食卓を囲んでいた。
愛するアルベルト様や、愛する子供たちと過ごす何気ない時間は、いつの間にか、かけがえのない宝物になっていった。
季節が巡り、髪に白が混じる頃になっても、私たちはずっと隣で過ごした。
歩幅はゆっくりになり、遠くへ出かけることが難しくなっても、子供達や孫達に囲まれ、笑いは絶えず、日々は幸せに満ちていた。
その日も、窓から差し込む柔らかな陽射しの中で、二人は静かに過ごしていた。
少し違うのは、私がベッドに横になり、アルベルト様がその傍らの椅子に座っているということだろうか。
アルベルト様は、私の手を包むように握りしめていた。
その指先にこもる力が、私よりも彼のほうが、ずっと名残惜しんでいることを教えてくれる。
「……充実した人生でしたね」
ふと、そんな言葉がこぼれる。
「うむ。二度目だというのに、ずいぶん贅沢な人生だった」
冗談めかした声に、思わず小さく笑う。
包まれた手には昔よりもシワがふえているのが感じられたが、その指先に触れる温もりはずっと昔から、変わることはなかった。
「ねえ」
「どうしたんだい」
「また……来世で会えたら、いいですね」
ほんの願いのように告げると、隣から穏やかな気配が伝わってくる。
アルベルト様は、私の手を離さぬまま、少し震えた声で呟いた。
「ああ。絶対だ」
「じゃあ、私は曲がり角でパンをくわえて走ってますね」
「ちゃんと『遅刻遅刻~』って言うのだぞ」
二人で笑い合いながら、穏やかな空気は静かに流れていく。
そして――ふいに、しん、と世界が静まった。
「あなたのこと、とても愛していますよ」
「僕もだよ。愛しい人」
気がつけば、部屋はとても静かだった。
周りの音も、景色も、すべてが遠ざかっていく。
けれど、不思議と寂しさはなかった。
胸の奥には、温かなものが確かに残っている。
きっとまた、どこかで。
同じ魂で、同じように。
***
「やばい、遅刻する!!」
パンをくわえた女子高生――こと、私は、朝の通学路を全力で駆け抜けていた。
歯磨きセットはちゃんとカバンに入っているから、一限目が始まる前に磨けばいい。……たぶん、大丈夫。
そう自分に言い聞かせながら、勢いよく角を曲がった、その瞬間。
「わっ!!」
誰かと、ぶつかった。鈍い衝撃と同時に、口に咥えていたパンが宙を舞い、無情にも地面へ落ちる。
「いたたた……」
尻もちをついたまま腰をさすり、私は慌てて顔を上げた。
「ご、ごめんなさい! お怪我はありませんか!?」
視界に入ったのは、近くの“お金持ちが通う”と噂の私立校の制服。
そこに立っていたのは、その制服を着た男子高校生だった。
どこか見覚えのある整った顔。
糸目。
そして、少し伸ばされた漆黒の髪。
「……某通信教育教材で見たやつだ……」
思わず漏れたその一言に、彼は一瞬だけ目を見開いた。そして次の瞬間、堪えきれないというように、じわじわと笑みが広がっていく。嬉しさを隠しきれない、少し潤んだ瞳で。
「『遅刻遅刻~』って言うのは、忘れていたのかい?」
その声を聞くと、心臓が、長い眠りから叩き起こされたかのように、胸の奥で激しく鐘を打った。
気づけば、私たちは互いの存在を確かめるように、自然と手を取り合っていた。
初めて触れたはずの手なのに、驚くほどしっくりと馴染む。
「ねえ、僕たち……多分、たくさん話したいことがあると思うんだけど」
真剣な眼差しでそう言われて、私は思わず息を飲む。
「私も、まったく同じことを思っています」
「正直に言うとね」
彼は少しだけ困ったように笑って続ける。
「今、僕は猛烈に……これから取るべき行動について迷っている」
「……私も、まったく同じことを思っています」
重なる言葉に、彼は小さく目を見開き、それから嬉しそうに目を細めた。
「……今日は、何時まで?」
「……十六時です」
一瞬だけ考えるように視線を逸らしてから、彼は決意したようにうなずいた。
「よし。じゃあ、十六時に君の学校の正門に迎えに行く。絶対、来てくれるか?」
「当たり前です。……絶対に、来てくださいね」
「ああ。約束だ」
名残惜しさを噛みしめるように、私たちはゆっくりと手を離した。
振り返りたい気持ちを必死に抑えて、私は自分の学校へと駆け出す。手のひらに残るぬくもりが、これが夢じゃないと、何度も教えてくれた。
それから十六時まで、私は驚くほど集中して授業を受けた。いつもと様子の違う私に、周りの友人たちは目を丸くしていたが、「勉強に目覚めた!」と、とりあえず誤魔化しておく。
教室からは正門は見えない。本当に、アルベルト様――いや、現世での名前は何だろう――彼は、約束通り来てくれているだろうか。心臓が早鐘のように打ち、手のひらが少し汗ばんでいる。ホームルームが終わると、私は下駄箱へと駆け降りた。
背中を丸めながらローファーを履き替える。あぁ、つい最近変えたばかりの綺麗なローファーで良かった。小さなことでも、今の私には安心材料だ。前髪を整え、制服を軽くはたき、深呼吸をひとつ――でも、胸の鼓動は落ち着くどころか、ますます早まるばかりだった。
校舎の外に出ると、正門の向こうに彼の姿が目に入った。遠くからでも分かる、何十年も隣で見た、あの凛とした立ち姿。私の胸は一気に跳ね上がり、呼吸が詰まりそうになる。
その瞬間、さっきまで整えていた前髪も、制服の乱れも、全く気にならなかった。心の中の高鳴りに身を任せ、私は彼に向かって駆け出す。
駆け寄ってきた私を視界に入れた彼は、心底嬉しそうに微笑んだ。その笑顔に、胸の奥がぎゅっと締めつけられる。
近づいた私たちは、まるでずっとそうしていたかのように自然に手を取り合う。指先が触れた瞬間、言葉にできない感情が体中に広がった。
「……どこで話しましょうか」
今すぐにでも色々と話したい気持ちを抑え、そっと尋ねる。
「そうだね……駅前のクレープ屋でテイクアウトして、公園でゆっくり喋ろう」
彼の穏やかな笑顔に、自然と頷く。胸の高鳴りを押さえつつ、手を握り返す。
繋いだ手から伝わってくる体温は、記憶の中にある彼よりもずっと近く、確かなものだった。アスファルトの上を響く二人の足音。すれ違う自転車や、夕暮れの街灯。彼の隣で見る景色は、やっぱり美しい。全てが特別なもののように感じられた。
私たちは公園のベンチに腰を下ろし、ぽつりぽつりと話し始めた。
「あの時の、学園の中庭の奥で話したことを思い出すな」
「ふふ、同じことを思ってました。はっきりと覚えてますよ」
彼は小さく笑って、クレープを一口頬張る。
「チョコレート、やっぱり好きなんですね」
「君はやっぱりフルーツが好きなんだね。以前との共通点を見つけると、なんだかすごく嬉しくなるよ」
少し間を置いて、私は手元のクレープを握りしめながら呟く。
「口調、変わったんですね」
「さすがにこの世界であの口調だったら浮くからね。君が僕だと気づいてくれるか不安だったけど、気づいてくれて良かった」
「関西弁でも、九州弁でもないですね」
「あはは!よく覚えてたね」
笑い合いながらクレープを頬張る。柔らかな甘さが口の中に広がり、二人の沈黙も心地好く感じられる。
「やっぱり、君がこうやって隣に居ると一番落ち着くな」
「多くの時間を過ごしましたからね」
静かな公園のベンチで、クレープの紙を丁寧にたたみながら、私たちは小さな幸せを噛みしめる。夕暮れの風が、木々を揺らし、遠くで子どもたちの笑い声が聞こえていた。
「ねえ、これからも……ずっと一緒に、こうしていられますか?」
「もちろん。またずっと、一緒に。会いたいときに、いつでも会おう」
その言葉は約束というより、ずっと前から決まっていた事実のようだった。
「……記憶は、全部あるんですか?」
「何一つ忘れてないよ。君は?」
「私も。全部、覚えています」
少し間が空いて、彼はふっと口元を緩めた。
「君のその敬語は、癖なの?」
「い、いえ……つい……」
「じゃあさ」
彼はそう言って、指先で私の手を軽くつつく。
「今世では、敬語なしにしよう」
「……努力、します」
「そこも含めて君らしいけどね」
からかうような声なのに、どこまでも優しい。私は小さく息を吐いて、肩の力を抜いた。
「じゃあ……改めて」
「うん?」
「自己紹介、しよっか。まだお互いの名前も知らないよ私たち」
「あはは!本当だ。じゃあ改めて、僕の名前は――――」
夕暮れのオレンジが藍色に溶ける中、私たちは並んで歩く。これからも、未来も、時間も――すべてを一緒に過ごせるのだと、私は確信していた。
商会は相変わらず西へ東へと手を広げ、どの土地でも繁盛を見せていた。私は帳簿や契約書を整え、時には現地との交渉にも同行しながら、彼の隣でその歩みを支え続けている。
そんなある日、遠い東の国で――私たちは、見覚えのあり過ぎる穀物と調味料に出会った。
「……フェリシア」
「……はい」
袋の中を覗き込んだまま、二人してしばし沈黙する。次の瞬間、ほとんど同時に顔を上げた。
「これ、米じゃないかい」
「米ですね」
「しかも――」
「味噌、です」
確認するように囁き合ったあと、堪えきれずに噴き出してしまった。周囲の人間が不思議そうな顔をするのも構わず、私たちは声を潜めて、けれど目を輝かせた。
「前世の……」
「前世の、アレだな」
言葉にしただけで、胸の奥が熱くなる。この世界には存在しないと思っていた、あの味。あの記憶。それを、今こうして、隣にいる同じ“前世持ち”と共有している。
「……持ち帰ろう」
「絶対にです」
「おにぎり、食べたいな」
「お味噌汁も作りましょうね」
そう言って笑い合った時、ああ、私たちは本当に、同じ人生を二度歩いているのだと実感した。
それから先の年月は、穏やかに積み重なっていった。
商会はさらに大きくなり、国を越え、海を越えた。それでも私たちは、変わらず同じ食卓を囲んでいた。
愛するアルベルト様や、愛する子供たちと過ごす何気ない時間は、いつの間にか、かけがえのない宝物になっていった。
季節が巡り、髪に白が混じる頃になっても、私たちはずっと隣で過ごした。
歩幅はゆっくりになり、遠くへ出かけることが難しくなっても、子供達や孫達に囲まれ、笑いは絶えず、日々は幸せに満ちていた。
その日も、窓から差し込む柔らかな陽射しの中で、二人は静かに過ごしていた。
少し違うのは、私がベッドに横になり、アルベルト様がその傍らの椅子に座っているということだろうか。
アルベルト様は、私の手を包むように握りしめていた。
その指先にこもる力が、私よりも彼のほうが、ずっと名残惜しんでいることを教えてくれる。
「……充実した人生でしたね」
ふと、そんな言葉がこぼれる。
「うむ。二度目だというのに、ずいぶん贅沢な人生だった」
冗談めかした声に、思わず小さく笑う。
包まれた手には昔よりもシワがふえているのが感じられたが、その指先に触れる温もりはずっと昔から、変わることはなかった。
「ねえ」
「どうしたんだい」
「また……来世で会えたら、いいですね」
ほんの願いのように告げると、隣から穏やかな気配が伝わってくる。
アルベルト様は、私の手を離さぬまま、少し震えた声で呟いた。
「ああ。絶対だ」
「じゃあ、私は曲がり角でパンをくわえて走ってますね」
「ちゃんと『遅刻遅刻~』って言うのだぞ」
二人で笑い合いながら、穏やかな空気は静かに流れていく。
そして――ふいに、しん、と世界が静まった。
「あなたのこと、とても愛していますよ」
「僕もだよ。愛しい人」
気がつけば、部屋はとても静かだった。
周りの音も、景色も、すべてが遠ざかっていく。
けれど、不思議と寂しさはなかった。
胸の奥には、温かなものが確かに残っている。
きっとまた、どこかで。
同じ魂で、同じように。
***
「やばい、遅刻する!!」
パンをくわえた女子高生――こと、私は、朝の通学路を全力で駆け抜けていた。
歯磨きセットはちゃんとカバンに入っているから、一限目が始まる前に磨けばいい。……たぶん、大丈夫。
そう自分に言い聞かせながら、勢いよく角を曲がった、その瞬間。
「わっ!!」
誰かと、ぶつかった。鈍い衝撃と同時に、口に咥えていたパンが宙を舞い、無情にも地面へ落ちる。
「いたたた……」
尻もちをついたまま腰をさすり、私は慌てて顔を上げた。
「ご、ごめんなさい! お怪我はありませんか!?」
視界に入ったのは、近くの“お金持ちが通う”と噂の私立校の制服。
そこに立っていたのは、その制服を着た男子高校生だった。
どこか見覚えのある整った顔。
糸目。
そして、少し伸ばされた漆黒の髪。
「……某通信教育教材で見たやつだ……」
思わず漏れたその一言に、彼は一瞬だけ目を見開いた。そして次の瞬間、堪えきれないというように、じわじわと笑みが広がっていく。嬉しさを隠しきれない、少し潤んだ瞳で。
「『遅刻遅刻~』って言うのは、忘れていたのかい?」
その声を聞くと、心臓が、長い眠りから叩き起こされたかのように、胸の奥で激しく鐘を打った。
気づけば、私たちは互いの存在を確かめるように、自然と手を取り合っていた。
初めて触れたはずの手なのに、驚くほどしっくりと馴染む。
「ねえ、僕たち……多分、たくさん話したいことがあると思うんだけど」
真剣な眼差しでそう言われて、私は思わず息を飲む。
「私も、まったく同じことを思っています」
「正直に言うとね」
彼は少しだけ困ったように笑って続ける。
「今、僕は猛烈に……これから取るべき行動について迷っている」
「……私も、まったく同じことを思っています」
重なる言葉に、彼は小さく目を見開き、それから嬉しそうに目を細めた。
「……今日は、何時まで?」
「……十六時です」
一瞬だけ考えるように視線を逸らしてから、彼は決意したようにうなずいた。
「よし。じゃあ、十六時に君の学校の正門に迎えに行く。絶対、来てくれるか?」
「当たり前です。……絶対に、来てくださいね」
「ああ。約束だ」
名残惜しさを噛みしめるように、私たちはゆっくりと手を離した。
振り返りたい気持ちを必死に抑えて、私は自分の学校へと駆け出す。手のひらに残るぬくもりが、これが夢じゃないと、何度も教えてくれた。
それから十六時まで、私は驚くほど集中して授業を受けた。いつもと様子の違う私に、周りの友人たちは目を丸くしていたが、「勉強に目覚めた!」と、とりあえず誤魔化しておく。
教室からは正門は見えない。本当に、アルベルト様――いや、現世での名前は何だろう――彼は、約束通り来てくれているだろうか。心臓が早鐘のように打ち、手のひらが少し汗ばんでいる。ホームルームが終わると、私は下駄箱へと駆け降りた。
背中を丸めながらローファーを履き替える。あぁ、つい最近変えたばかりの綺麗なローファーで良かった。小さなことでも、今の私には安心材料だ。前髪を整え、制服を軽くはたき、深呼吸をひとつ――でも、胸の鼓動は落ち着くどころか、ますます早まるばかりだった。
校舎の外に出ると、正門の向こうに彼の姿が目に入った。遠くからでも分かる、何十年も隣で見た、あの凛とした立ち姿。私の胸は一気に跳ね上がり、呼吸が詰まりそうになる。
その瞬間、さっきまで整えていた前髪も、制服の乱れも、全く気にならなかった。心の中の高鳴りに身を任せ、私は彼に向かって駆け出す。
駆け寄ってきた私を視界に入れた彼は、心底嬉しそうに微笑んだ。その笑顔に、胸の奥がぎゅっと締めつけられる。
近づいた私たちは、まるでずっとそうしていたかのように自然に手を取り合う。指先が触れた瞬間、言葉にできない感情が体中に広がった。
「……どこで話しましょうか」
今すぐにでも色々と話したい気持ちを抑え、そっと尋ねる。
「そうだね……駅前のクレープ屋でテイクアウトして、公園でゆっくり喋ろう」
彼の穏やかな笑顔に、自然と頷く。胸の高鳴りを押さえつつ、手を握り返す。
繋いだ手から伝わってくる体温は、記憶の中にある彼よりもずっと近く、確かなものだった。アスファルトの上を響く二人の足音。すれ違う自転車や、夕暮れの街灯。彼の隣で見る景色は、やっぱり美しい。全てが特別なもののように感じられた。
私たちは公園のベンチに腰を下ろし、ぽつりぽつりと話し始めた。
「あの時の、学園の中庭の奥で話したことを思い出すな」
「ふふ、同じことを思ってました。はっきりと覚えてますよ」
彼は小さく笑って、クレープを一口頬張る。
「チョコレート、やっぱり好きなんですね」
「君はやっぱりフルーツが好きなんだね。以前との共通点を見つけると、なんだかすごく嬉しくなるよ」
少し間を置いて、私は手元のクレープを握りしめながら呟く。
「口調、変わったんですね」
「さすがにこの世界であの口調だったら浮くからね。君が僕だと気づいてくれるか不安だったけど、気づいてくれて良かった」
「関西弁でも、九州弁でもないですね」
「あはは!よく覚えてたね」
笑い合いながらクレープを頬張る。柔らかな甘さが口の中に広がり、二人の沈黙も心地好く感じられる。
「やっぱり、君がこうやって隣に居ると一番落ち着くな」
「多くの時間を過ごしましたからね」
静かな公園のベンチで、クレープの紙を丁寧にたたみながら、私たちは小さな幸せを噛みしめる。夕暮れの風が、木々を揺らし、遠くで子どもたちの笑い声が聞こえていた。
「ねえ、これからも……ずっと一緒に、こうしていられますか?」
「もちろん。またずっと、一緒に。会いたいときに、いつでも会おう」
その言葉は約束というより、ずっと前から決まっていた事実のようだった。
「……記憶は、全部あるんですか?」
「何一つ忘れてないよ。君は?」
「私も。全部、覚えています」
少し間が空いて、彼はふっと口元を緩めた。
「君のその敬語は、癖なの?」
「い、いえ……つい……」
「じゃあさ」
彼はそう言って、指先で私の手を軽くつつく。
「今世では、敬語なしにしよう」
「……努力、します」
「そこも含めて君らしいけどね」
からかうような声なのに、どこまでも優しい。私は小さく息を吐いて、肩の力を抜いた。
「じゃあ……改めて」
「うん?」
「自己紹介、しよっか。まだお互いの名前も知らないよ私たち」
「あはは!本当だ。じゃあ改めて、僕の名前は――――」
夕暮れのオレンジが藍色に溶ける中、私たちは並んで歩く。これからも、未来も、時間も――すべてを一緒に過ごせるのだと、私は確信していた。
42
この作品は感想を受け付けておりません。
あなたにおすすめの小説
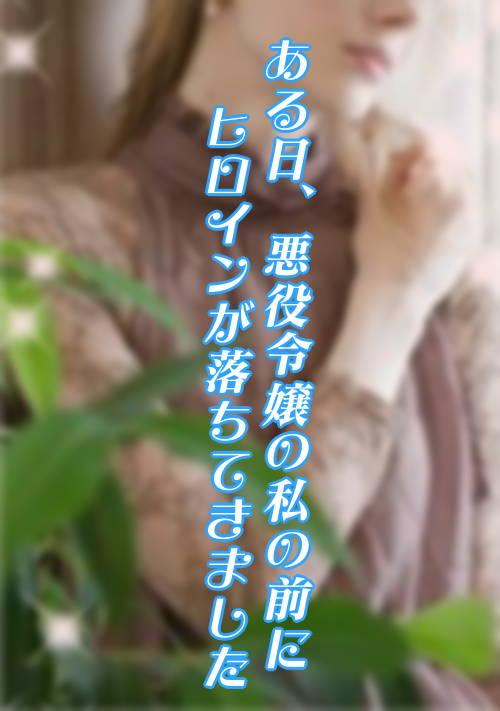
ある日、悪役令嬢の私の前にヒロインが落ちてきました
結城芙由奈@コミカライズ連載中
恋愛
【どうやら私はこの世界では悪役令嬢と呼ばれる存在だったらしい】
以前から自分を取り巻く環境に違和感を覚えていた私はどうしても馴染めることが出来ずにいた。周囲とのぎこちない生活、婚約者として紹介された相手からは逃げ回り、友達もいない学園生活を送っていた私の前に、ある日自称ヒロインを名乗る人物が上から落ちてきて、私のことを悪役令嬢呼ばわりしてきた――。
※短めで終わる予定です
※他サイトでも投稿中

気がついたら自分は悪役令嬢だったのにヒロインざまぁしちゃいました
みゅー
恋愛
『転生したら推しに捨てられる婚約者でした、それでも推しの幸せを祈ります』のスピンオフです。
前世から好きだった乙女ゲームに転生したガーネットは、最推しの脇役キャラに猛アタックしていた。が、実はその最推しが隠しキャラだとヒロインから言われ、しかも自分が最推しに嫌われていて、いつの間にか悪役令嬢の立場にあることに気づく……そんなお話です。
同シリーズで『悪役令嬢はざまぁされるその役を放棄したい』もあります。

溺愛王子の甘すぎる花嫁~悪役令嬢を追放したら、毎日が新婚初夜になりました~
紅葉山参
恋愛
侯爵令嬢リーシャは、婚約者である第一王子ビヨンド様との結婚を心から待ち望んでいた。けれど、その幸福な未来を妬む者もいた。それが、リーシャの控えめな立場を馬鹿にし、王子を我が物にしようと画策した悪役令嬢ユーリーだった。
ある夜会で、ユーリーはビヨンド様の気を引こうと、リーシャを罠にかける。しかし、あなたの王子は、そんなつまらない小細工に騙されるほど愚かではなかった。愛するリーシャを信じ、王子はユーリーを即座に糾弾し、国外追放という厳しい処分を下す。
邪魔者が消え去った後、リーシャとビヨンド様の甘美な新婚生活が始まる。彼は、人前では厳格な王子として振る舞うけれど、私と二人きりになると、とろけるような甘さでリーシャを愛し尽くしてくれるの。
「私の可愛い妻よ、きみなしの人生なんて考えられない」
そう囁くビヨンド様に、私リーシャもまた、心も身体も預けてしまう。これは、障害が取り除かれたことで、むしろ加速度的に深まる、世界一甘くて幸せな夫婦の溺愛物語。新婚の王子妃として、私は彼の、そして王国の「最愛」として、毎日を幸福に満たされて生きていきます。

冷徹宰相様の嫁探し
菱沼あゆ
ファンタジー
あまり裕福でない公爵家の次女、マレーヌは、ある日突然、第一王子エヴァンの正妃となるよう、申し渡される。
その知らせを持って来たのは、若き宰相アルベルトだったが。
マレーヌは思う。
いやいやいやっ。
私が好きなのは、王子様じゃなくてあなたの方なんですけど~っ!?
実家が無害そう、という理由で王子の妃に選ばれたマレーヌと、冷徹宰相の恋物語。
(「小説家になろう」でも公開しています)

66番目の悪魔と悪役令嬢 ~王子からの婚約破棄は契約魔法でブロック~
星森
恋愛
王宮の大広間で、第2王子セディリオは高らかに宣言した。
「イレーネ・ルクレール公爵令嬢との婚約を破棄し、メリィ・アーデン準男爵令嬢と新たに婚約する!」
だがその瞬間、婚約に関する契約魔法が発動し、イレーネと王子は逃げ場のない結界に閉じ込められる。
婚約破棄の理由が正当でないため、修正しなければ結界は解けない──それが、この契約魔法だった。
潔白を主張する王子。
静かに本を開き、お茶を淹れ、生活を始める公爵令嬢。
干し肉しか持たない王子と、予め準備していた備蓄で優雅に過ごす令嬢。
トイレ問題、食事問題、価値観の衝突……密室生活は、王子の未熟さを容赦なく暴いていく。
やがて明らかになるのは、
“聖女になり損ねた令嬢”メリィの虚偽と陰謀。
そして、王子自身の短慮と過ち。
結界から出る方法は3つ。
1. **王子が正当な婚約破棄理由を提示する**
2. **イレーネの提案する苛烈な結婚条件を受け入れて婚約を続行する**
3. **イレーネに婚約破棄させる**
追い詰められた王子は、ついに選択を迫られる。
「……俺が間違っていたことを、公表する」
しかしイレーネの条件は容赦がない。
白い結婚、側室の制限、離婚権の独占、そして──離婚時の臣籍降下。
これは愚かな王子と、冷静すぎる公爵令嬢が、結界の中で互いの人生を叩き直す物語。
契約魔法が解けたとき、2人の関係は“婚約者”のままなのか、それとも……?
⚠️この物語は一部にAIの生成した文章を使用しています。タイトル変えました。

旦那様は、転生後は王子様でした
編端みどり
恋愛
近所でも有名なおしどり夫婦だった私達は、死ぬ時まで一緒でした。生まれ変わっても一緒になろうなんて言ったけど、今世は貴族ですって。しかも、タチの悪い両親に王子の婚約者になれと言われました。なれなかったら替え玉と交換して捨てるって言われましたわ。
まだ12歳ですから、捨てられると生きていけません。泣く泣くお茶会に行ったら、王子様は元夫でした。
時折チートな行動をして暴走する元夫を嗜めながら、自身もチートな事に気が付かない公爵令嬢のドタバタした日常は、周りを巻き込んで大事になっていき……。
え?! わたくし破滅するの?!
しばらく不定期更新です。時間できたら毎日更新しますのでよろしくお願いします。


モブの私がなぜかヒロインを押し退けて王太子殿下に選ばれました
みゅー
恋愛
その国では婚約者候補を集め、その中から王太子殿下が自分の婚約者を選ぶ。
ケイトは自分がそんな乙女ゲームの世界に、転生してしまったことを知った。
だが、ケイトはそのゲームには登場しておらず、気にせずそのままその世界で自分の身の丈にあった普通の生活をするつもりでいた。だが、ある日宮廷から使者が訪れ、婚約者候補となってしまい……
そんなお話です。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















