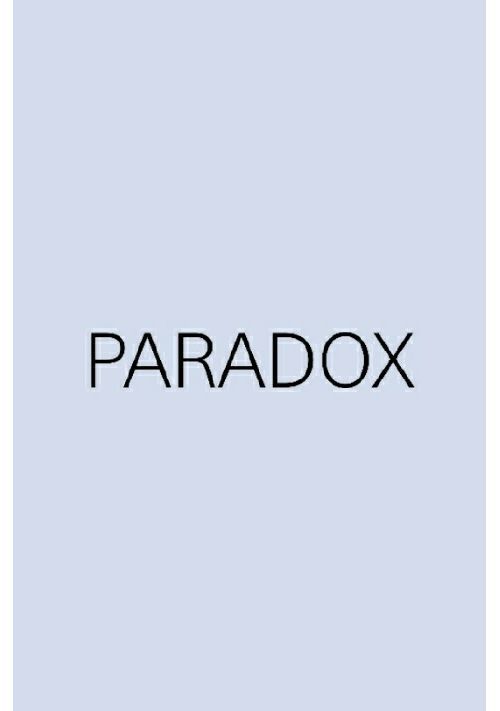1 / 1
聖女が悪役令嬢になるため頑張っていた公爵令嬢を救ったお話。
しおりを挟む
王立学院の中庭、人目につきにくいそこで、金色の縦ロールが目立つ美しい少女が、藍色のセミロングの美少女と話をしている。
人目につきにくい場所ではあるけど、多分目立っているんだろうなぁと、藍色美少女のほうの私は思いながら、泣きながら話す縦ロール美少女、アリエッタ様を慰めていた。
突然呼び出されたと思ったら、泣きながらアリエッタ様がどうしたらいいのかわからないの、と言い出したのだ。
***
「わっ、わたくしっ、頑張ったのよ…?」
アリエッタ様は続ける。
「聖女と、ライト様がご成婚するために…っ、ら、ライト様がっ、私を婚約破棄しやすいようにあなたをいじめたわ…っ」
そう、アリエッタ様がいう聖女は、私のことである。
ライト様は王太子だ。
しかし、いじめとはどれのことを指しているんだろうか。
そして、私と殿下のご成婚って、なんのこっちゃ。
などと思っていると、アリエッタ様が続けた。
「あなたのカテーシーを嘲笑ったり」
聖女たるものもっと美しい礼をするべきよっ!といわれて練習に付き合ってくださったことのことだろうか。
「勉強ができないのをバカにしたり」
バカにするというか、心配口調でしたよね私の赤点に対して。平民上がりだから大変なはずよ!と言いながらその後勉強おしえてくれたじゃないですか。
「ライト様といっしょにいるのを、と、咎めたり…っ」
あなた婚約者なんですからソレは普通だと思います。
アリエッタ様は基本的に人が良い。
なので、よくしてもらった記憶はあれど、私はいじめられた記憶はない。
いじめた方が「やってない」というイジメはよく聞くけど、いじめた方が「いじめた」といっていじめられた方が自覚してない、というイジメは成立するんだろうか。
「ライト様が、あなたの良さに気づくようにあなたの話もしてみたわ…」
「多分それ、殿下はアリエッタ様が一生懸命喋るの可愛いなぁって見てただけで内容はあんまり聞いてないと思います」
「…っ。どうしてあなたたちは惹かれ合わないの?」
「そもそも、なんで私と殿下が結婚するみたいな話になってるんですか?」
まず、そこがよくわからなかったので、ズバリきいてみると、アリエッタ様は「え?」と目をぱちくりとさせた。
「お、お父様が、…聖女が現れたのなら、お前はその席を譲るべきだ、とおっしゃっていて。そのほうが、国のためになると、だからお前は悪役に徹して、聖女と殿下の恋路を応援しろ、と……」
つまり、今アリエッタ様がこの数ヶ月謎の努力をし、今泣いているのはアリエッタ様のクソ親父のせいということだろうか。
実はこっそりアリエッタ様のファンでもある聖女な私は、「ああもうこれ、殿下に告口しよ」と思いながら、「アリエッタ様、申し訳ありません、私、殿下以外に好きな人、いるんです」と告白した。
***
「というわけなんですよ、殿下」
「フォンテール公爵、娘になんてことをさせてるんだ」
生徒会室のど真ん中に座りながら、冷たい空気を出している金髪の美しい青年はがライト殿下。アリエッタ様の現婚約者であり、側から見ているともうアリエッタ様に溺愛としか言いようのない愛を注ぎまくっている人だ。
その後ろに立っている黒髪でオッドアイの青年ーカイド様も、私の話に眉を寄せていた。
「確かに聖女であれば、身分問わず王族との結婚は許されます。ですが、アリエッタ様とのご婚約を破棄してまでソレを成立させる必要性が私には見えないのですが」
「そうなんだよね。自分の娘になんで婚約破棄されるようにいい含めるのか、謎すぎる。……フォンテール公爵とアリエッタの間には何か確執があるのか?」
「どうでしょうか。娘を溺愛しているという噂しか知りませんが」
「まさか、娘を嫁にやりたくないとかいう、そういう話か?」
「それは、貴族らしからぬ考えすぎますので、考えにくいとはおいもいますが…」
殿下とカイド様の話を聞きつつ、この様子ならアリエッタ様に殿下からきちんとお話がいくな、と思って退出に向けて殿下に声をかけた。
「では私はこれで、失礼致します。このあと治癒魔法の訓練がありますので」
聖女というのは、白の魔力と呼ばれる治癒や解呪、浄化、結界などに向いている魔力が秀でている者の中で、特に強い魔力を持つものに与えられる称号だ。
国のために働くことを前提に、訓練と保護を受ける。
癒しの象徴のような存在にもなるので、国民からの人気の高い、職業…職業なのかな、まあ、そういう感じだ。基本は貴族のほうが魔力が強いので、平民から選ばれることは稀ではあるが、私はその稀なタイプ人間だった。
しかし、14歳で全員が受ける魔力検査で引っかかるまで、魔法なんてものは無縁だったので、現時点でのコントロールは下手くそだ。
毎日、放課後訓練が待っていて面倒ではあるのだが、まあ、私が聖女であることで孤児である私を育ててくれた下町のみんなに恩返しができているようなので頑張っている。
一礼してから部屋を出ようとすると、殿下が止める。
「そうだ。言いたくないなら構わないが、ユリア嬢、君の好きな人って誰なんだ?」
尋ねられた言葉に、私はすこし驚いたが、別に隠すようなことでもない。
「あなたの後ろにおりますよ」
私の言葉に、私の想い人、カイド様はピシリと固まった。
あれ、お伝えしたことなかったっけ。
***
「あ、あの、ユリアさん…」
「アリエッタ様。こんな時間まで残っていらしたんですか?」
訓練を終えると、アリエッタ様がおずおずと声をかけてきた。
どうやら図書館で自習をしつつ、私を待っていてくれたようだ。
「すこし、お話しできないかしら」
「ええ、構いませんよ。アリエッタ様の時間が大丈夫なら、学園のカフェに行きますか?」
私の言葉遣いは綺麗ではない。聖女のくせに愛想もないし、むしろ表情筋は死にぎみだ。
顔は、顔の造形は、綺麗だと自覚しているけれども。
それでも、アリエッタ様は自分に対する言動の時は、それを咎めたことはない。
本当に、優しい人なのだ。
「いいえ、できれば人気のない場所がいいのだけれど…」
「ですが、薄暗くなってきてますし、人気のない場所というのは危険です」
「ええ、そう、そうよね…」
困ったようにアリエッタ様は頬に手を添える。
お昼間は泣いていたのでアレだが、アリエッタ様はおっとりとした喋り方をする人だ。
「ああ、そうだわ。もしよかったら、わたくしの部屋にいらっしゃらない?」
「アリエッタ様のお部屋に、ですか?」
「ええ」
私はちょっと迷ったけれど、アリエッタ様のお話しが気になったので、伺うことにした。
お部屋はとても整っていて、なんだかいい匂いがする。
私の部屋にもメイドはついているし、綺麗にしてもらっているけれど、何が違うというのか…。家主の女子力だろうか。
「お座りになって。どうぞリラックスしてくださると嬉しいわ」
そう言って、メイドにお茶を運ばせる。
優しい香りのハーブティーとクッキーが目の前に並び、それを一口飲みながら、私はきいた。
「…あの」
「なあに?」
「その、アリエッタ様的いじめは、その」
「ええ。その話をしたかったのよ」
アリエッタ様も、優雅にお茶を飲むと、小首をかしげて「ごめんなさいね」と言った。
「わたくし、婚約破棄をされなければ、とずっと思っていたのだけれど、なぜそんなに頑なだったのか、わからないの。確かにお父様にはそう言われたけれど、聖女を虐めたことをきっかけにして婚約破棄をされれば、フォンテール家もわたくしも、ただではいられないでしょう?そんなことがスッポリ頭から抜けるほど、私は、…なぜか婚約破棄をしなければ、と思っていたわ」
「アリエッタ様…」
アリエッタ様は悲しげに微笑む。
その顔が壮絶に美しくて、思わず息を呑んだ。
「落ち着いて考えると、どうにも頭にもやがかかったような、不思議な感覚があって。そもそも、わたくしは、ライト様をその…、お、お慕い…しているのに…」
今度はかぁ、と赤くなるアリエッタ様。
殿下、殿下すみません。こんな可愛らしいアリエッタ様を独り占めてしていて申し訳ありません。
私は心の中だけで殿下に謝罪を重ねつつ、アリエッタ様に言った。
「ええと、私を呼ばれたということは、そのもやが黒い魔力を元にしたものかどうかを、内々でしらべてほしい、ということでしょうか?」
黒い魔力というのは、白い魔法の対極にある、呪いなどを得意とする魔力だ。
使い方次第では便利なものなのだが、悪用する人間も多いため人気のない魔力だったりする。
ちなみに、カイド様は、この黒い魔力の適性が高い。
黒い魔力に聖女、聖人という認定があればおそらく選ばれていたであろうほどに。
まあ、それは置いておいて。
「ええ。あなたをいじめていたような、わたくしの願いなど、聞きたくないかもしれないけれど」
「それはないですね」
私は食い気味に返事をする。
「お昼間にもお伝えしましたが、私はアリエッタ様にいじめられたとは一切思っておりません。むしろ、いつも優しくご指導いただいていたと思っております。ですから、感謝こそしていますが、恨むなどは全くありません。むしろ、好きです。アリエッタ様のお力になれるなんて光栄だし嬉しいです」
そこまで一気に言うと、アリエッタ様は目を大きく開いて、それから、「ありがとう」と破顔した。
その顔をみた私が、もう一度心の中で殿下に詫びたのは言うまでもない。
結果、確かにアリエッタ様は黒い魔法で思考を制御されていた。
その魔法をかける手筈をしたのは、アリエッタ様の父親で、その理由まではっきり見えた私は思わず吐きそうになったけど、これをアリエッタ様に伝えるわけにはいかない。
「明日、先に殿下にこのことをお伝えしていいですか?」
その言葉に、アリエッタ様は神妙な顔でひとつ頷いた。
***
「殿下、アリエッタ様の父親を捕まえることってできます?」
「なんだい藪から棒に」
「実は…」
私は昨日会ったことを包み隠さずに殿下に申し上げた。
黒い魔法がだれに、どのような目的で使用されたのか、も。
カイド様は絶句し、殿下は青の魔力(水、氷に特化した魔力)が暴走しかけて机を凍らせかけた(カイド様が止めた)
「つまり?結局真犯人はフォンテール公爵だった、というわけか」
「そういうことになりますね」
アリエッタ様にくすぶる黒い魔力を調べようとしたところ、それをかけた人と公爵の会話が念思として流れ込んできた。
『にしても、本当にいいんですかい?このお嬢さんが婚約破棄になんてなったら、公爵にはデメリットしかないでしょうに』
『いいや?そんなことはないのだよ。この子が、結婚してこの家から出ることがなくなるんだからね』
『?』
『聖女を虐めて婚約破棄になるような娘、たとえ公爵位でも欲しがる家などそうあるまい?そうすれば、この子はずっと、ずぅっとこの家で過ごせるんだ』
『公爵、あんた、この娘を』
『姉上に似ているこの子を手放すなんて、本当は嫌だったんだよ。いやぁ、いいタイミングで聖女が現れたものだ』
この後も会話は続いて、それを踏まえて犯行動機を要約すると。
姉ちゃんにガチ恋して拗らせた弟が、姉ちゃんにクリソツな娘を手込めにして一生家に囲うためだった。
つまり、アリエッタ様の本来があまりに善人だったために成功はしなかったものの、もし成功していたら、アリエッタ様は今頃実の父親にあーんなことやこーんなことをされた上に軟禁されていた、ということになる。
まあ、殿下がバチクソにキレるのは当然だろう。
「このあたりのこと、証拠揃えられるだろうか」
「やってみましょう」
カイド様はそう頭を下げて、それにうん、と殿下は頷いた。
「とりあえず、僕はアリエッタのところに行ってくるよ。全部は話せないけれど、ある程度のことは彼女にも伝えるべきだ。あと、保護する。もう、絶対保護する。嫌がっても困らせても王宮に連れて行く」
「あの殿下」
「なに」
「アリエッタ様は寮に住んでらっしゃいますけれど」
私がそう言うと、「僕は王宮から通ってるから。問題ないよ。王宮住み、いけるいける」と言って出て行った。
いけるいけるって。
まあ、殿下なら悪いようにしないかと思って、カイド様に退出の許可を取ろうとしたら、唐突に頭を撫でられた。
「!?」
「ああ、すまない。…その、君は、大丈夫か?」
「え?え??何がですか???」
「その…、人の悪意なんて、読み取って気持ちのいいものじゃないだろう」
眉を寄せて心配そうにこちらを見るカイド様。
ああ、カイド様。そう言うところなんですよ。私があなたを想ってやまないのは。
いつだって、優しくフォローしてくれる。
努力を、認めてくれる。
聖女になってから、苦しむことを許してくれるのは、カイド様だった。
「カイド様」
「うん?なんだ」
「好きです」
私の言葉にカイド様はガタタッと体勢を崩したが、その表情は、別に嫌がっている様子じゃなかった。
***
そこからの殿下の動きはもう凄まじかった。
まずアリエッタ様に事情をやんわりと説明。
そして、王に申告。
どうやって証拠を集めたのかはわからないけれど、あっという間にフォンテール公爵の思惑とやったことは証明され、しかしそのままの情報を出すとアリエッタ様の評判も傷つくということで、内々にフォンテール公爵は国王の管轄する屋敷に軟禁、表立っては療養ということになり、そしてアリエッタ様のお兄様がフォンテール公爵を継ぎ(アリエッタ様のお兄様は父親の思惑に気づいて動いていたらしい。もしかしたら証拠集めが早かったのはそのせいかも)学校を卒業と同時にアリエッタ様と殿下が結婚することが正式に決定し、その祝いの儀をなぜか私が担当することになり、…もっと謎なんだけど、私とカイド様がくっついた。突然、告白されたのだ。
***
殿下が後押ししてくださったらしいけど、…これに関しては未だにカイド様は命令されたんじゃなかろうか、と勘繰ってしまう。
疑うのは良くないけれど、私たちの展開が急すぎて、なんか、…なんか。
大体、顔は自信あるけどそれ以外には聖女っていう肩書きくらいしか誇れるもののない私(誇るどころか愛想とか考えるとマイナス要素しかなくない?)がカイド様に愛されるなんて、…ちょっと信じられないのだ。
いろいろ怒涛のように決まって、なかなか一息つく暇もなかったけど、ようやく訪れた1人ののんびりした時間。
せっかくのおやすみ時間なのにそんなことばかりぐるぐる考えてしまって、あーあ、とため息をついた時だった。
窓がこつん、と鳴る。
「え、幽霊?」
と反射的に怖がってしまったが、本当に幽霊なら私は強い。
意を決してカーテンを開けると、窓の外の木の上に、カイド様がいた。
「!?」
「あ、ああ、その、すまない。驚かすつもりは…」
カイド様は木の上に座ったまま、おろおろと手をこちらに伸ばすが、私が夜着なことに気がついて「あ、ああああああすまないっ」と伸ばした手を引っ込めて自分の目を覆った。
かわいいな。
「しょ、少々お待ちくださいカイド様」
私はとりあえずカーテンを閉めて部屋に戻りさくっときがえてから、再びカーテンを開けた。
カイド様は目を覆ったまま待っていた。
繰り返すけど、かわいいな、この人。
「ええと、もう大丈夫です。でもどうしたんですか、こんなところまで。下手したら捕まりますよ、女子寮に来るなんて」
「あ、ああ、そうなんだが…その、君に想いを伝えてから、…全然、話ができなかったから」
私は、息が詰まって、でもなんとか絞り出した。
「外へ、参りましょう。私たちはもう婚約しています。女子寮で会うよりは、外で逢引した方が、その…カイド様の評判的に安全です」
提案をすぐに飲んでくれたカイド様と並んで、夜の学園の庭にでる。
月明かりがまっすぐ差し込むそこは、夜であってもそこそこ明るかった。
「ライト様に、叱られたのもあって、会いに来たんだ」
「それ、素直に言いますか普通」
「! す、すまない」
そんな不器用さもかわいいですカイド様。
そうは思いつつ、胸は痛んだ。
会いたいから会いに来てくれたわけではないのだな、と思って。
私は、こんな性格だし、顔には出ないけれど、…傷がつかないわけではないのだ。
「ユリア嬢!」
突然カイド様がハッとしたように私を呼び、手を握った。
「ちがう、何か誤解しているようだが、私は、『我慢して不機嫌になるくらいならさっさと会いにいけ』と叱られたんだ。君に会うこと自体を命じられたわけではない。愛している人に会えないイライラをついライト様にぶつけてしま…、あ」
カイド様の顔が、月明かりの下でもはっきりわかるくらい赤く染まっていく。
「あ、の…、カイド様はいったい、私のどこがお気に召したんですか?」
「1番最初は、顔だな」
「かお、ですか」
素直だなカイド様。
「そのあと、中身に惹かれた。…外見の美しさもそうなんだが、…君は、いつだって人のために動ける人間だったから。…私は、…その…、こんな魔力があるだろう?」
黒の魔力。
カイド様が殿下のお側にいられるようになるためには、たくさんの試練があったのだと、そういえばアリエッタ様が言っていた。
「だから、人から悪意を向けられることも多かった。けれど、君は、真っ直ぐに、私を好きだと言ってくれたから」
「好きって言われたから好きになったんですか?」
「いや、それは違うな。背中を押された、と言うのが正しい。私は、君が好きな人が私だといってくれたあの日よりもっと前から、君に惹かれていたから」
「うれしい、です」
カイド様って、口下手で無口なイメージがあったけれど、案外饒舌なんだな。
そんなことを思っていたら、そっとくちづけられた。
カイド様は「あ」って顔をしている。
台無しです、カイド様。
そう思うも、なんだかおかしくなって、ふふっと笑ってしまった。
「カイド様」
「なんだ」
「好きになってくれてありがとうございます。」
「それは、私のセリフでもあるな」
微笑むカイド様に、今度は私から口付けを返す。
先程よりも深く長いそれは、空に浮かぶ月だけが、見守ってくれていた。
人目につきにくい場所ではあるけど、多分目立っているんだろうなぁと、藍色美少女のほうの私は思いながら、泣きながら話す縦ロール美少女、アリエッタ様を慰めていた。
突然呼び出されたと思ったら、泣きながらアリエッタ様がどうしたらいいのかわからないの、と言い出したのだ。
***
「わっ、わたくしっ、頑張ったのよ…?」
アリエッタ様は続ける。
「聖女と、ライト様がご成婚するために…っ、ら、ライト様がっ、私を婚約破棄しやすいようにあなたをいじめたわ…っ」
そう、アリエッタ様がいう聖女は、私のことである。
ライト様は王太子だ。
しかし、いじめとはどれのことを指しているんだろうか。
そして、私と殿下のご成婚って、なんのこっちゃ。
などと思っていると、アリエッタ様が続けた。
「あなたのカテーシーを嘲笑ったり」
聖女たるものもっと美しい礼をするべきよっ!といわれて練習に付き合ってくださったことのことだろうか。
「勉強ができないのをバカにしたり」
バカにするというか、心配口調でしたよね私の赤点に対して。平民上がりだから大変なはずよ!と言いながらその後勉強おしえてくれたじゃないですか。
「ライト様といっしょにいるのを、と、咎めたり…っ」
あなた婚約者なんですからソレは普通だと思います。
アリエッタ様は基本的に人が良い。
なので、よくしてもらった記憶はあれど、私はいじめられた記憶はない。
いじめた方が「やってない」というイジメはよく聞くけど、いじめた方が「いじめた」といっていじめられた方が自覚してない、というイジメは成立するんだろうか。
「ライト様が、あなたの良さに気づくようにあなたの話もしてみたわ…」
「多分それ、殿下はアリエッタ様が一生懸命喋るの可愛いなぁって見てただけで内容はあんまり聞いてないと思います」
「…っ。どうしてあなたたちは惹かれ合わないの?」
「そもそも、なんで私と殿下が結婚するみたいな話になってるんですか?」
まず、そこがよくわからなかったので、ズバリきいてみると、アリエッタ様は「え?」と目をぱちくりとさせた。
「お、お父様が、…聖女が現れたのなら、お前はその席を譲るべきだ、とおっしゃっていて。そのほうが、国のためになると、だからお前は悪役に徹して、聖女と殿下の恋路を応援しろ、と……」
つまり、今アリエッタ様がこの数ヶ月謎の努力をし、今泣いているのはアリエッタ様のクソ親父のせいということだろうか。
実はこっそりアリエッタ様のファンでもある聖女な私は、「ああもうこれ、殿下に告口しよ」と思いながら、「アリエッタ様、申し訳ありません、私、殿下以外に好きな人、いるんです」と告白した。
***
「というわけなんですよ、殿下」
「フォンテール公爵、娘になんてことをさせてるんだ」
生徒会室のど真ん中に座りながら、冷たい空気を出している金髪の美しい青年はがライト殿下。アリエッタ様の現婚約者であり、側から見ているともうアリエッタ様に溺愛としか言いようのない愛を注ぎまくっている人だ。
その後ろに立っている黒髪でオッドアイの青年ーカイド様も、私の話に眉を寄せていた。
「確かに聖女であれば、身分問わず王族との結婚は許されます。ですが、アリエッタ様とのご婚約を破棄してまでソレを成立させる必要性が私には見えないのですが」
「そうなんだよね。自分の娘になんで婚約破棄されるようにいい含めるのか、謎すぎる。……フォンテール公爵とアリエッタの間には何か確執があるのか?」
「どうでしょうか。娘を溺愛しているという噂しか知りませんが」
「まさか、娘を嫁にやりたくないとかいう、そういう話か?」
「それは、貴族らしからぬ考えすぎますので、考えにくいとはおいもいますが…」
殿下とカイド様の話を聞きつつ、この様子ならアリエッタ様に殿下からきちんとお話がいくな、と思って退出に向けて殿下に声をかけた。
「では私はこれで、失礼致します。このあと治癒魔法の訓練がありますので」
聖女というのは、白の魔力と呼ばれる治癒や解呪、浄化、結界などに向いている魔力が秀でている者の中で、特に強い魔力を持つものに与えられる称号だ。
国のために働くことを前提に、訓練と保護を受ける。
癒しの象徴のような存在にもなるので、国民からの人気の高い、職業…職業なのかな、まあ、そういう感じだ。基本は貴族のほうが魔力が強いので、平民から選ばれることは稀ではあるが、私はその稀なタイプ人間だった。
しかし、14歳で全員が受ける魔力検査で引っかかるまで、魔法なんてものは無縁だったので、現時点でのコントロールは下手くそだ。
毎日、放課後訓練が待っていて面倒ではあるのだが、まあ、私が聖女であることで孤児である私を育ててくれた下町のみんなに恩返しができているようなので頑張っている。
一礼してから部屋を出ようとすると、殿下が止める。
「そうだ。言いたくないなら構わないが、ユリア嬢、君の好きな人って誰なんだ?」
尋ねられた言葉に、私はすこし驚いたが、別に隠すようなことでもない。
「あなたの後ろにおりますよ」
私の言葉に、私の想い人、カイド様はピシリと固まった。
あれ、お伝えしたことなかったっけ。
***
「あ、あの、ユリアさん…」
「アリエッタ様。こんな時間まで残っていらしたんですか?」
訓練を終えると、アリエッタ様がおずおずと声をかけてきた。
どうやら図書館で自習をしつつ、私を待っていてくれたようだ。
「すこし、お話しできないかしら」
「ええ、構いませんよ。アリエッタ様の時間が大丈夫なら、学園のカフェに行きますか?」
私の言葉遣いは綺麗ではない。聖女のくせに愛想もないし、むしろ表情筋は死にぎみだ。
顔は、顔の造形は、綺麗だと自覚しているけれども。
それでも、アリエッタ様は自分に対する言動の時は、それを咎めたことはない。
本当に、優しい人なのだ。
「いいえ、できれば人気のない場所がいいのだけれど…」
「ですが、薄暗くなってきてますし、人気のない場所というのは危険です」
「ええ、そう、そうよね…」
困ったようにアリエッタ様は頬に手を添える。
お昼間は泣いていたのでアレだが、アリエッタ様はおっとりとした喋り方をする人だ。
「ああ、そうだわ。もしよかったら、わたくしの部屋にいらっしゃらない?」
「アリエッタ様のお部屋に、ですか?」
「ええ」
私はちょっと迷ったけれど、アリエッタ様のお話しが気になったので、伺うことにした。
お部屋はとても整っていて、なんだかいい匂いがする。
私の部屋にもメイドはついているし、綺麗にしてもらっているけれど、何が違うというのか…。家主の女子力だろうか。
「お座りになって。どうぞリラックスしてくださると嬉しいわ」
そう言って、メイドにお茶を運ばせる。
優しい香りのハーブティーとクッキーが目の前に並び、それを一口飲みながら、私はきいた。
「…あの」
「なあに?」
「その、アリエッタ様的いじめは、その」
「ええ。その話をしたかったのよ」
アリエッタ様も、優雅にお茶を飲むと、小首をかしげて「ごめんなさいね」と言った。
「わたくし、婚約破棄をされなければ、とずっと思っていたのだけれど、なぜそんなに頑なだったのか、わからないの。確かにお父様にはそう言われたけれど、聖女を虐めたことをきっかけにして婚約破棄をされれば、フォンテール家もわたくしも、ただではいられないでしょう?そんなことがスッポリ頭から抜けるほど、私は、…なぜか婚約破棄をしなければ、と思っていたわ」
「アリエッタ様…」
アリエッタ様は悲しげに微笑む。
その顔が壮絶に美しくて、思わず息を呑んだ。
「落ち着いて考えると、どうにも頭にもやがかかったような、不思議な感覚があって。そもそも、わたくしは、ライト様をその…、お、お慕い…しているのに…」
今度はかぁ、と赤くなるアリエッタ様。
殿下、殿下すみません。こんな可愛らしいアリエッタ様を独り占めてしていて申し訳ありません。
私は心の中だけで殿下に謝罪を重ねつつ、アリエッタ様に言った。
「ええと、私を呼ばれたということは、そのもやが黒い魔力を元にしたものかどうかを、内々でしらべてほしい、ということでしょうか?」
黒い魔力というのは、白い魔法の対極にある、呪いなどを得意とする魔力だ。
使い方次第では便利なものなのだが、悪用する人間も多いため人気のない魔力だったりする。
ちなみに、カイド様は、この黒い魔力の適性が高い。
黒い魔力に聖女、聖人という認定があればおそらく選ばれていたであろうほどに。
まあ、それは置いておいて。
「ええ。あなたをいじめていたような、わたくしの願いなど、聞きたくないかもしれないけれど」
「それはないですね」
私は食い気味に返事をする。
「お昼間にもお伝えしましたが、私はアリエッタ様にいじめられたとは一切思っておりません。むしろ、いつも優しくご指導いただいていたと思っております。ですから、感謝こそしていますが、恨むなどは全くありません。むしろ、好きです。アリエッタ様のお力になれるなんて光栄だし嬉しいです」
そこまで一気に言うと、アリエッタ様は目を大きく開いて、それから、「ありがとう」と破顔した。
その顔をみた私が、もう一度心の中で殿下に詫びたのは言うまでもない。
結果、確かにアリエッタ様は黒い魔法で思考を制御されていた。
その魔法をかける手筈をしたのは、アリエッタ様の父親で、その理由まではっきり見えた私は思わず吐きそうになったけど、これをアリエッタ様に伝えるわけにはいかない。
「明日、先に殿下にこのことをお伝えしていいですか?」
その言葉に、アリエッタ様は神妙な顔でひとつ頷いた。
***
「殿下、アリエッタ様の父親を捕まえることってできます?」
「なんだい藪から棒に」
「実は…」
私は昨日会ったことを包み隠さずに殿下に申し上げた。
黒い魔法がだれに、どのような目的で使用されたのか、も。
カイド様は絶句し、殿下は青の魔力(水、氷に特化した魔力)が暴走しかけて机を凍らせかけた(カイド様が止めた)
「つまり?結局真犯人はフォンテール公爵だった、というわけか」
「そういうことになりますね」
アリエッタ様にくすぶる黒い魔力を調べようとしたところ、それをかけた人と公爵の会話が念思として流れ込んできた。
『にしても、本当にいいんですかい?このお嬢さんが婚約破棄になんてなったら、公爵にはデメリットしかないでしょうに』
『いいや?そんなことはないのだよ。この子が、結婚してこの家から出ることがなくなるんだからね』
『?』
『聖女を虐めて婚約破棄になるような娘、たとえ公爵位でも欲しがる家などそうあるまい?そうすれば、この子はずっと、ずぅっとこの家で過ごせるんだ』
『公爵、あんた、この娘を』
『姉上に似ているこの子を手放すなんて、本当は嫌だったんだよ。いやぁ、いいタイミングで聖女が現れたものだ』
この後も会話は続いて、それを踏まえて犯行動機を要約すると。
姉ちゃんにガチ恋して拗らせた弟が、姉ちゃんにクリソツな娘を手込めにして一生家に囲うためだった。
つまり、アリエッタ様の本来があまりに善人だったために成功はしなかったものの、もし成功していたら、アリエッタ様は今頃実の父親にあーんなことやこーんなことをされた上に軟禁されていた、ということになる。
まあ、殿下がバチクソにキレるのは当然だろう。
「このあたりのこと、証拠揃えられるだろうか」
「やってみましょう」
カイド様はそう頭を下げて、それにうん、と殿下は頷いた。
「とりあえず、僕はアリエッタのところに行ってくるよ。全部は話せないけれど、ある程度のことは彼女にも伝えるべきだ。あと、保護する。もう、絶対保護する。嫌がっても困らせても王宮に連れて行く」
「あの殿下」
「なに」
「アリエッタ様は寮に住んでらっしゃいますけれど」
私がそう言うと、「僕は王宮から通ってるから。問題ないよ。王宮住み、いけるいける」と言って出て行った。
いけるいけるって。
まあ、殿下なら悪いようにしないかと思って、カイド様に退出の許可を取ろうとしたら、唐突に頭を撫でられた。
「!?」
「ああ、すまない。…その、君は、大丈夫か?」
「え?え??何がですか???」
「その…、人の悪意なんて、読み取って気持ちのいいものじゃないだろう」
眉を寄せて心配そうにこちらを見るカイド様。
ああ、カイド様。そう言うところなんですよ。私があなたを想ってやまないのは。
いつだって、優しくフォローしてくれる。
努力を、認めてくれる。
聖女になってから、苦しむことを許してくれるのは、カイド様だった。
「カイド様」
「うん?なんだ」
「好きです」
私の言葉にカイド様はガタタッと体勢を崩したが、その表情は、別に嫌がっている様子じゃなかった。
***
そこからの殿下の動きはもう凄まじかった。
まずアリエッタ様に事情をやんわりと説明。
そして、王に申告。
どうやって証拠を集めたのかはわからないけれど、あっという間にフォンテール公爵の思惑とやったことは証明され、しかしそのままの情報を出すとアリエッタ様の評判も傷つくということで、内々にフォンテール公爵は国王の管轄する屋敷に軟禁、表立っては療養ということになり、そしてアリエッタ様のお兄様がフォンテール公爵を継ぎ(アリエッタ様のお兄様は父親の思惑に気づいて動いていたらしい。もしかしたら証拠集めが早かったのはそのせいかも)学校を卒業と同時にアリエッタ様と殿下が結婚することが正式に決定し、その祝いの儀をなぜか私が担当することになり、…もっと謎なんだけど、私とカイド様がくっついた。突然、告白されたのだ。
***
殿下が後押ししてくださったらしいけど、…これに関しては未だにカイド様は命令されたんじゃなかろうか、と勘繰ってしまう。
疑うのは良くないけれど、私たちの展開が急すぎて、なんか、…なんか。
大体、顔は自信あるけどそれ以外には聖女っていう肩書きくらいしか誇れるもののない私(誇るどころか愛想とか考えるとマイナス要素しかなくない?)がカイド様に愛されるなんて、…ちょっと信じられないのだ。
いろいろ怒涛のように決まって、なかなか一息つく暇もなかったけど、ようやく訪れた1人ののんびりした時間。
せっかくのおやすみ時間なのにそんなことばかりぐるぐる考えてしまって、あーあ、とため息をついた時だった。
窓がこつん、と鳴る。
「え、幽霊?」
と反射的に怖がってしまったが、本当に幽霊なら私は強い。
意を決してカーテンを開けると、窓の外の木の上に、カイド様がいた。
「!?」
「あ、ああ、その、すまない。驚かすつもりは…」
カイド様は木の上に座ったまま、おろおろと手をこちらに伸ばすが、私が夜着なことに気がついて「あ、ああああああすまないっ」と伸ばした手を引っ込めて自分の目を覆った。
かわいいな。
「しょ、少々お待ちくださいカイド様」
私はとりあえずカーテンを閉めて部屋に戻りさくっときがえてから、再びカーテンを開けた。
カイド様は目を覆ったまま待っていた。
繰り返すけど、かわいいな、この人。
「ええと、もう大丈夫です。でもどうしたんですか、こんなところまで。下手したら捕まりますよ、女子寮に来るなんて」
「あ、ああ、そうなんだが…その、君に想いを伝えてから、…全然、話ができなかったから」
私は、息が詰まって、でもなんとか絞り出した。
「外へ、参りましょう。私たちはもう婚約しています。女子寮で会うよりは、外で逢引した方が、その…カイド様の評判的に安全です」
提案をすぐに飲んでくれたカイド様と並んで、夜の学園の庭にでる。
月明かりがまっすぐ差し込むそこは、夜であってもそこそこ明るかった。
「ライト様に、叱られたのもあって、会いに来たんだ」
「それ、素直に言いますか普通」
「! す、すまない」
そんな不器用さもかわいいですカイド様。
そうは思いつつ、胸は痛んだ。
会いたいから会いに来てくれたわけではないのだな、と思って。
私は、こんな性格だし、顔には出ないけれど、…傷がつかないわけではないのだ。
「ユリア嬢!」
突然カイド様がハッとしたように私を呼び、手を握った。
「ちがう、何か誤解しているようだが、私は、『我慢して不機嫌になるくらいならさっさと会いにいけ』と叱られたんだ。君に会うこと自体を命じられたわけではない。愛している人に会えないイライラをついライト様にぶつけてしま…、あ」
カイド様の顔が、月明かりの下でもはっきりわかるくらい赤く染まっていく。
「あ、の…、カイド様はいったい、私のどこがお気に召したんですか?」
「1番最初は、顔だな」
「かお、ですか」
素直だなカイド様。
「そのあと、中身に惹かれた。…外見の美しさもそうなんだが、…君は、いつだって人のために動ける人間だったから。…私は、…その…、こんな魔力があるだろう?」
黒の魔力。
カイド様が殿下のお側にいられるようになるためには、たくさんの試練があったのだと、そういえばアリエッタ様が言っていた。
「だから、人から悪意を向けられることも多かった。けれど、君は、真っ直ぐに、私を好きだと言ってくれたから」
「好きって言われたから好きになったんですか?」
「いや、それは違うな。背中を押された、と言うのが正しい。私は、君が好きな人が私だといってくれたあの日よりもっと前から、君に惹かれていたから」
「うれしい、です」
カイド様って、口下手で無口なイメージがあったけれど、案外饒舌なんだな。
そんなことを思っていたら、そっとくちづけられた。
カイド様は「あ」って顔をしている。
台無しです、カイド様。
そう思うも、なんだかおかしくなって、ふふっと笑ってしまった。
「カイド様」
「なんだ」
「好きになってくれてありがとうございます。」
「それは、私のセリフでもあるな」
微笑むカイド様に、今度は私から口付けを返す。
先程よりも深く長いそれは、空に浮かぶ月だけが、見守ってくれていた。
応援ありがとうございます!
0
お気に入りに追加
2
この作品の感想を投稿する
1 / 4
この作品を読んでいる人はこんな作品も読んでいます!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる