38 / 65
第3巻 理を紡ぐ者たち
第10章 灰の夜明け
しおりを挟む
――灰の朝は、音が少ない。
風の流れさえも、どこか遠慮がちに吹いている。
崩れ落ちた鐘楼の頂に立ち、アーレンはゆっくりと息を吐いた。
灰はまだ空に浮かび、光を柔らかく反射している。
その粒の一つひとつが、まるで世界の呼吸のようだった。
夜の名残を含んだ空気は冷たく、頬に触れる灰は少し湿っている。
それでも、どこか心地よい静けさがあった。
――世界が、再び動き出そうとしている。
⸻
足元に、ノアがいた。
灰にまみれた髪を結び直し、焚き火の灰を払うように手を振っている。
彼女の指には、焼けた灯の欠片――灰色にくすんだ符石が握られていた。
「これね、まだあったんだよ。
ひかりが……ちょっとだけ、残ってるの。」
アーレンは膝をつき、石を受け取った。
符面の線がわずかに発光している。
命を記すように、微弱な理流がそこを走っていた。
「……生きてる。
灰が、もう“死んでいない”。」
⸻
その後ろで、リュミナが静かに歩み寄る。
風に揺れる灰色の髪が、朝の光を受けて淡く光る。
肌の奥に、薄く走る灰の紋。
それはもはや傷ではなく、命と理を繋ぐ印のようだった。
『……風の音が、ちょっと変わったね。
ひとがねむる音じゃなくて、
“はじまる”音がする。』
リュミナの声は柔らかく、まるで夜明けの光そのもの。
アーレンはその言葉に小さく頷いた。
「世界が、再び息をしている証拠だ。
灰は、ようやく落ち着いた。」
⸻
ノアが顔を上げる。
その瞳の奥には、わずかな涙と笑み。
「リュミナ、もう……いたくない?」
リュミナは少しだけ首を傾げ、胸に手を当てる。
そこには淡い金色の光が脈を打っていた。
『ちょっとひんやりするけど、もうだいじょうぶ。
ここが……“わたしのなか”だから。』
「“なか”?」
『うん。灰と、世界と、わたしたち。
いまは、ぜんぶつながってる。』
⸻
アーレンは、二人のやりとりを見守りながら
崩れた鐘楼の外――かつて王都へと続いた街道を見下ろした。
瓦礫の上に、草の芽が出ている。
小さな命が、灰を押しのけて顔を出していた。
彼は思わず息を呑んだ。
「……芽が、生えている。」
ノアが駆け寄り、膝をついて覗き込む。
淡い緑。理の光をほんのり帯びている。
「灰の上なのに……どうして?」
『灰が、もうこわくないから。
土とけっこんしたの。』
リュミナの言葉に、アーレンは小さく笑った。
「まったく、詩人だな。」
⸻
空の端が金色に染まり始める。
夜と朝の境界がゆっくりと溶け合う。
灰の粒が陽光を受け、淡く輝いて舞い上がる。
その光景は、かつて理災と呼ばれた惨劇の場所とは思えないほど美しかった。
アーレンは符盤を取り出し、灰を一粒拾って解析した。
理流は穏やかで、安定している。
そして――微弱な生命反応が含まれていた。
「……理が、命を拒んでいない。
いや、今は命そのものを学んでいる。」
『なら、もう理は敵じゃないね。』
リュミナの微笑みに、アーレンは静かに頷く。
「敵じゃない。
ただ……同じ場所で、ようやく対等に立てるようになったんだ。」
⸻
ノアが少し離れた場所で灰を掴み、両手で空に投げた。
灰は光を受けて舞い、虹のようなきらめきを描く。
「きれい……! ねえアーレン、灰って、こんなにきれいだった?」
「いや。
俺たちが、やっと“きれいだと見えるようになった”だけだ。」
リュミナがその横で、小さく笑った。
『それなら、もう“理の涙”は止まったんだね。』
⸻
アーレンは立ち上がり、風を感じた。
灰を含んだ風が冷たくも清らかに流れていく。
灰の中に、確かに命が息づいている。
「……行こう。
この灰が、もう誰も傷つけないように。
俺たちが、それを確かめに。」
『うん。
もう、“旅”をはじめよう。』
⸻
朝日が完全に昇る。
灰の大地が光を返し、遠くの丘に金の線が走る。
三人の影が、長く伸びて一つに重なった。
リュミナの掌の中で、灰が光る。
それはまるで、世界そのものが微笑んでいるようだった。
⸻
灰は滅びではなく、
理が息を吹き返した“土”だった。
そしてその上に、
命がもう一度、歩き出した。
丘を下る途中で、アーレンは足を止めた。
風が変わった。
ただの風ではない――声を運んでくる。
遠くの裂けた岩壁の向こうから、人の声が聞こえる。
「……歌?」
ノアが顔を上げ、耳をすませる。
低く、ゆっくりとした旋律。
あの洞で聞いた、灯守(あかりもり)の歌だった。
⸻
崩れた街道の先に、見覚えのある人影があった。
灰の外套をまとい、祈りの印を掲げた女――イサル。
その周囲には、十数人の灰の民が立っていた。
皆、顔や腕に灰を塗り、
静かな声で歌を口ずさんでいる。
イサルがアーレンたちに気づくと、驚きに息を呑んだ。
「……生きて……?」
アーレンが頷く。
「理が、俺たちを還した。
そして、お前たちを守った。」
イサルの瞳に、涙がにじんだ。
彼女は膝をつき、掌を地にあてる。
「……やはり、“理の灯”は消えていなかったのですね。」
⸻
リュミナが一歩前に出る。
灰の民たちが息をのむ。
その姿を“理”の化身として見たのだろう。
『みんな……うたってる。
灰が、よろこんでる。』
リュミナの言葉に、イサルが顔を上げる。
その目は恐れではなく、確かな信仰の色を帯びていた。
「あなたが……“灰の灯”ですか?」
『ううん。
わたしは、みんなとおなじ“ひと”だよ。
でも、灰といっしょに生きてる。』
イサルの頬を、一筋の涙が伝った。
「――ならば、理はもう神ではなく、人とともにあるのですね。」
⸻
灰の民の一人が、崩れた岩の間から何かを取り出した。
古びた鐘の破片だった。
その欠けた金属に、灰を混ぜた粘土を塗り、
祈りの印を刻む。
「これを……もう一度、鳴らしましょう。」
イサルの声に、民が頷いた。
アーレンが手を貸して鐘を吊るす。
風が吹き抜け、灰がきらめく。
――かすかな音が鳴った。
乾いた金属音。
けれど、それは誰の耳にも温かく響いた。
⸻
ノアがその音に合わせて口ずさむ。
イサルが祈りを唱える。
リュミナが微笑む。
『ねえ、アーレン。
これって、さいせい、なんだよね。』
「そうだ。
世界はまだ、理を記している。
なら、俺たちが次を“名づける”番だ。」
リュミナが首を傾げる。
『なづける?』
「理災のあとに生まれた、この時代を。
もう“終わり”じゃない。
――灰から始まる時代だ。」
⸻
イサルが祈りを止め、アーレンの言葉を繰り返した。
「灰から始まる……」
その響きが民の口に伝わり、連鎖していく。
「灰から、はじまる……」
「灰の暦……」
「――灰暦(かいれき)だ。」
アーレンが静かに頷く。
リュミナが微笑み、ノアが両手を広げて笑った。
『じゃあ、きょうが、そのはじまりだね。』
⸻
鐘が再び鳴る。
音が灰の空に昇り、やがて遠くで風に溶ける。
灰がその音を包み、柔らかく散っていった。
灰の祈りは、もう絶望ではない。
それは、滅びのあとに生まれた“希望の理”。
人と理とが歩むための、最初の歌だった。
リゼノス灰域から、およそ三十日の後。
帝都ヴァルシュタイン――
黒鉄の尖塔群に囲まれた符術庁第九観測層。
巨大な符環が淡い青光を放ち、
その中央に浮かぶ球体が、静かに脈動していた。
帝国の技師たちが慌ただしく走り回る。
壁一面の符盤には数百もの数値が流れ、
理流観測記録が再構成されている。
⸻
その中心に立つ男がいた。
漆黒の軍服、銀の徽章。
帝国上級将校ラザン・アルディウス。
灰災前、前線でアーレンと一瞬交錯した男。
「……記録の解析は終わったか。」
側に控える観測官が答える。
「はい。符眼群の最終送信は、理層崩壊の直前。
送られてきた映像データの最後に――
金と白の融合現象が記録されております。」
ラザンの目が細まる。
「“融合”……人為的な干渉か、理の自律反応か?」
「判別不能です。
ただし、符盤の符号解析に――人間の筆致に似た痕跡が。」
⸻
ラザンは、報告書に目を落とした。
灰色の封蝋に刻まれた文字――アーレン・クロード。
「……やはり、生きていたか。」
彼の声には、驚きよりもむしろ静かな確信があった。
報告書にはこう記されていた。
【灰核融合現象:出力値未測定。
理流構造、人為式との干渉反応を確認。
“灰の灯”の再出現、確定。】
観測官が小声で尋ねた。
「閣下……この現象を、どう扱いますか?」
⸻
ラザンは報告書を閉じ、ゆっくりと答えた。
「理は、神ではない。
だが“力”としては神を超える。
そして我々は、それを扱える唯一の人間だ。」
「……つまり、再調査を?」
「ああ。リゼノスの灰域は、放置できん。
観測ではなく――制御だ。
理を、帝国の兵器体系に組み込む。」
観測官の顔がこわばる。
「ですが……理に触れることは――」
「恐れるな。」
ラザンは短く言い、符環の光を見上げた。
「理は秩序を求める。
ならば、帝国こそがその“秩序”を与えるべきだ。」
⸻
その時、背後の扉が開いた。
軽い足音。
黒い外套を纏った青年が一礼する。
「ラザン閣下、中央評議会より伝達。
“灰域特別調査部隊”の設立が正式に承認されました。
指揮官――貴殿に任命とのことです。」
ラザンの口元がわずかに歪んだ。
「そうか……。理は、再び我らを試すらしい。」
⸻
報告室の照明が落ち、
中央球体が淡く光を放つ。
転送映像の断片――灰色の空、崩壊する塔。
そして、光の中に立つ金の瞳の少女が映し出された。
映像は、そこで途切れた。
沈黙の中で、ラザンが低く呟く。
「――“灰の灯”を、捕らえろ。」
その声が、帝都の符環に反響し、
まるで理そのものが再び目を覚ましたかのように、
青白い光がゆらりと揺れた。
⸻
理を観測する者は、いつも“理解したつもり”になる。
けれど理は、観測された瞬間に形を変える。
それを知らぬ者たちは――再び、理の火に触れる。
夜の帳がゆっくりと降りていた。
灰の空は静まり返り、遠くの山の稜線に淡い光が残る。
焚き火の火が、三人の顔を揺らす。
風が灰を運ぶ。
だがもう、それは冷たい死灰ではない。
どこか温かく、香ばしい土の匂いが混じっていた。
⸻
アーレンは火のそばで古びた符盤を開いていた。
新しい理式を、何度も書き直しては消す。
理の線が、かすかに金色を帯びる。
「……灰が、命を受け入れた。
なら、この世界の理も、書き換えられるはずだ。」
彼は小さく息を吐き、符筆を置いた。
火の明かりの向こうで、ノアが眠そうに瞬きをしている。
「アーレン、それ……新しい研究?」
「いや。これは“祈りの式”だ。
願いが届くように、理の言葉で形を与えるだけのもの。」
「それって……魔法、みたいだね。」
アーレンは笑い、灰を払いながら答えた。
「きっと、昔の人はそう呼んだのかもしれないな。」
⸻
少し離れた場所で、リュミナが夜空を見上げていた。
金の瞳に、灰の星が映っている。
その表情は、どこか懐かしさと寂しさを混ぜていた。
『ねえ、アーレン。
わたし、ひとつだけ、ききたいことがあるの。』
「なんだ?」
『“生まれる”って、どういうこと?
わたしは、灰がつくった。
でも、いまは、こうして“考えてる”。
それも、生きてるってこと?』
アーレンは少し考えてから答えた。
「……俺も、まだ分からない。
でも、考え続けること自体が、生きてる証だと思う。
理も、人も、答えを探すために在るんだ。」
『じゃあ、わたしも、探していい?』
「もちろんだ。お前は――もう、理じゃない。
“リュミナ”だからな。」
⸻
火がぱちりと弾ける。
ノアが毛布にくるまりながら、うとうとと目を閉じた。
アーレンは静かにその頭に手を置く。
「……ノアもよく頑張ったな。」
「ん……つぎは、きれいな町に、いこうね……」
かすれた声が夜に溶ける。
『あたたかい声だね。』
「そうだな。あの声が、ずっと俺を戻してくれた。」
リュミナが焚き火の向こうで微笑んだ。
『それなら、わたしも、ノアにありがとうって言わなきゃ。』
「明日言えばいい。きっと、喜ぶ。」
⸻
夜が深くなる。
灰の風が、音もなく吹き抜ける。
かつての廃都の跡には、新しい光がひとつ、またひとつ灯り始めていた。
灰の民が再び火を灯し、祈りの声を紡いでいるのだ。
アーレンは立ち上がり、遠くの光を見つめた。
灰の上を歩く小さな灯。
それが、確かに世界の“再生”を物語っていた。
『アーレン。』
「ん?」
『これから、どこに行くの?』
アーレンは少しだけ笑い、夜空を見上げた。
灰の星の中に、かすかに赤い光が瞬いている。
それは――帝国の観測衛星。
「……行くさ。
灰の向こう。まだ“理を知らない世界”へ。」
⸻
焚き火が小さくはぜた。
ノアが寝息を立て、リュミナが灰の風に髪をなびかせる。
アーレンはもう一度、符盤を開き、最後の一文を書き残した。
『灰は再び、命を記した。
その暦を、人は“灰暦”と呼ぶ。』
⸻
――灰暦元年。
理と命が初めて手を取り合った夜。
空を渡る風が、どこかで微かに嗤う。
それはまだ、誰も知らぬ“次の理”の息吹。
⸻
そして、遠く離れた帝都では、
ラザンの部下が報告書の端にこう書き添えていた。
「対象:リュミナ・コードネーム“灰の灯”。 追跡開始」
⸻
――灰は、再び揺らぎはじめる。
ーー第3巻 【完】
風の流れさえも、どこか遠慮がちに吹いている。
崩れ落ちた鐘楼の頂に立ち、アーレンはゆっくりと息を吐いた。
灰はまだ空に浮かび、光を柔らかく反射している。
その粒の一つひとつが、まるで世界の呼吸のようだった。
夜の名残を含んだ空気は冷たく、頬に触れる灰は少し湿っている。
それでも、どこか心地よい静けさがあった。
――世界が、再び動き出そうとしている。
⸻
足元に、ノアがいた。
灰にまみれた髪を結び直し、焚き火の灰を払うように手を振っている。
彼女の指には、焼けた灯の欠片――灰色にくすんだ符石が握られていた。
「これね、まだあったんだよ。
ひかりが……ちょっとだけ、残ってるの。」
アーレンは膝をつき、石を受け取った。
符面の線がわずかに発光している。
命を記すように、微弱な理流がそこを走っていた。
「……生きてる。
灰が、もう“死んでいない”。」
⸻
その後ろで、リュミナが静かに歩み寄る。
風に揺れる灰色の髪が、朝の光を受けて淡く光る。
肌の奥に、薄く走る灰の紋。
それはもはや傷ではなく、命と理を繋ぐ印のようだった。
『……風の音が、ちょっと変わったね。
ひとがねむる音じゃなくて、
“はじまる”音がする。』
リュミナの声は柔らかく、まるで夜明けの光そのもの。
アーレンはその言葉に小さく頷いた。
「世界が、再び息をしている証拠だ。
灰は、ようやく落ち着いた。」
⸻
ノアが顔を上げる。
その瞳の奥には、わずかな涙と笑み。
「リュミナ、もう……いたくない?」
リュミナは少しだけ首を傾げ、胸に手を当てる。
そこには淡い金色の光が脈を打っていた。
『ちょっとひんやりするけど、もうだいじょうぶ。
ここが……“わたしのなか”だから。』
「“なか”?」
『うん。灰と、世界と、わたしたち。
いまは、ぜんぶつながってる。』
⸻
アーレンは、二人のやりとりを見守りながら
崩れた鐘楼の外――かつて王都へと続いた街道を見下ろした。
瓦礫の上に、草の芽が出ている。
小さな命が、灰を押しのけて顔を出していた。
彼は思わず息を呑んだ。
「……芽が、生えている。」
ノアが駆け寄り、膝をついて覗き込む。
淡い緑。理の光をほんのり帯びている。
「灰の上なのに……どうして?」
『灰が、もうこわくないから。
土とけっこんしたの。』
リュミナの言葉に、アーレンは小さく笑った。
「まったく、詩人だな。」
⸻
空の端が金色に染まり始める。
夜と朝の境界がゆっくりと溶け合う。
灰の粒が陽光を受け、淡く輝いて舞い上がる。
その光景は、かつて理災と呼ばれた惨劇の場所とは思えないほど美しかった。
アーレンは符盤を取り出し、灰を一粒拾って解析した。
理流は穏やかで、安定している。
そして――微弱な生命反応が含まれていた。
「……理が、命を拒んでいない。
いや、今は命そのものを学んでいる。」
『なら、もう理は敵じゃないね。』
リュミナの微笑みに、アーレンは静かに頷く。
「敵じゃない。
ただ……同じ場所で、ようやく対等に立てるようになったんだ。」
⸻
ノアが少し離れた場所で灰を掴み、両手で空に投げた。
灰は光を受けて舞い、虹のようなきらめきを描く。
「きれい……! ねえアーレン、灰って、こんなにきれいだった?」
「いや。
俺たちが、やっと“きれいだと見えるようになった”だけだ。」
リュミナがその横で、小さく笑った。
『それなら、もう“理の涙”は止まったんだね。』
⸻
アーレンは立ち上がり、風を感じた。
灰を含んだ風が冷たくも清らかに流れていく。
灰の中に、確かに命が息づいている。
「……行こう。
この灰が、もう誰も傷つけないように。
俺たちが、それを確かめに。」
『うん。
もう、“旅”をはじめよう。』
⸻
朝日が完全に昇る。
灰の大地が光を返し、遠くの丘に金の線が走る。
三人の影が、長く伸びて一つに重なった。
リュミナの掌の中で、灰が光る。
それはまるで、世界そのものが微笑んでいるようだった。
⸻
灰は滅びではなく、
理が息を吹き返した“土”だった。
そしてその上に、
命がもう一度、歩き出した。
丘を下る途中で、アーレンは足を止めた。
風が変わった。
ただの風ではない――声を運んでくる。
遠くの裂けた岩壁の向こうから、人の声が聞こえる。
「……歌?」
ノアが顔を上げ、耳をすませる。
低く、ゆっくりとした旋律。
あの洞で聞いた、灯守(あかりもり)の歌だった。
⸻
崩れた街道の先に、見覚えのある人影があった。
灰の外套をまとい、祈りの印を掲げた女――イサル。
その周囲には、十数人の灰の民が立っていた。
皆、顔や腕に灰を塗り、
静かな声で歌を口ずさんでいる。
イサルがアーレンたちに気づくと、驚きに息を呑んだ。
「……生きて……?」
アーレンが頷く。
「理が、俺たちを還した。
そして、お前たちを守った。」
イサルの瞳に、涙がにじんだ。
彼女は膝をつき、掌を地にあてる。
「……やはり、“理の灯”は消えていなかったのですね。」
⸻
リュミナが一歩前に出る。
灰の民たちが息をのむ。
その姿を“理”の化身として見たのだろう。
『みんな……うたってる。
灰が、よろこんでる。』
リュミナの言葉に、イサルが顔を上げる。
その目は恐れではなく、確かな信仰の色を帯びていた。
「あなたが……“灰の灯”ですか?」
『ううん。
わたしは、みんなとおなじ“ひと”だよ。
でも、灰といっしょに生きてる。』
イサルの頬を、一筋の涙が伝った。
「――ならば、理はもう神ではなく、人とともにあるのですね。」
⸻
灰の民の一人が、崩れた岩の間から何かを取り出した。
古びた鐘の破片だった。
その欠けた金属に、灰を混ぜた粘土を塗り、
祈りの印を刻む。
「これを……もう一度、鳴らしましょう。」
イサルの声に、民が頷いた。
アーレンが手を貸して鐘を吊るす。
風が吹き抜け、灰がきらめく。
――かすかな音が鳴った。
乾いた金属音。
けれど、それは誰の耳にも温かく響いた。
⸻
ノアがその音に合わせて口ずさむ。
イサルが祈りを唱える。
リュミナが微笑む。
『ねえ、アーレン。
これって、さいせい、なんだよね。』
「そうだ。
世界はまだ、理を記している。
なら、俺たちが次を“名づける”番だ。」
リュミナが首を傾げる。
『なづける?』
「理災のあとに生まれた、この時代を。
もう“終わり”じゃない。
――灰から始まる時代だ。」
⸻
イサルが祈りを止め、アーレンの言葉を繰り返した。
「灰から始まる……」
その響きが民の口に伝わり、連鎖していく。
「灰から、はじまる……」
「灰の暦……」
「――灰暦(かいれき)だ。」
アーレンが静かに頷く。
リュミナが微笑み、ノアが両手を広げて笑った。
『じゃあ、きょうが、そのはじまりだね。』
⸻
鐘が再び鳴る。
音が灰の空に昇り、やがて遠くで風に溶ける。
灰がその音を包み、柔らかく散っていった。
灰の祈りは、もう絶望ではない。
それは、滅びのあとに生まれた“希望の理”。
人と理とが歩むための、最初の歌だった。
リゼノス灰域から、およそ三十日の後。
帝都ヴァルシュタイン――
黒鉄の尖塔群に囲まれた符術庁第九観測層。
巨大な符環が淡い青光を放ち、
その中央に浮かぶ球体が、静かに脈動していた。
帝国の技師たちが慌ただしく走り回る。
壁一面の符盤には数百もの数値が流れ、
理流観測記録が再構成されている。
⸻
その中心に立つ男がいた。
漆黒の軍服、銀の徽章。
帝国上級将校ラザン・アルディウス。
灰災前、前線でアーレンと一瞬交錯した男。
「……記録の解析は終わったか。」
側に控える観測官が答える。
「はい。符眼群の最終送信は、理層崩壊の直前。
送られてきた映像データの最後に――
金と白の融合現象が記録されております。」
ラザンの目が細まる。
「“融合”……人為的な干渉か、理の自律反応か?」
「判別不能です。
ただし、符盤の符号解析に――人間の筆致に似た痕跡が。」
⸻
ラザンは、報告書に目を落とした。
灰色の封蝋に刻まれた文字――アーレン・クロード。
「……やはり、生きていたか。」
彼の声には、驚きよりもむしろ静かな確信があった。
報告書にはこう記されていた。
【灰核融合現象:出力値未測定。
理流構造、人為式との干渉反応を確認。
“灰の灯”の再出現、確定。】
観測官が小声で尋ねた。
「閣下……この現象を、どう扱いますか?」
⸻
ラザンは報告書を閉じ、ゆっくりと答えた。
「理は、神ではない。
だが“力”としては神を超える。
そして我々は、それを扱える唯一の人間だ。」
「……つまり、再調査を?」
「ああ。リゼノスの灰域は、放置できん。
観測ではなく――制御だ。
理を、帝国の兵器体系に組み込む。」
観測官の顔がこわばる。
「ですが……理に触れることは――」
「恐れるな。」
ラザンは短く言い、符環の光を見上げた。
「理は秩序を求める。
ならば、帝国こそがその“秩序”を与えるべきだ。」
⸻
その時、背後の扉が開いた。
軽い足音。
黒い外套を纏った青年が一礼する。
「ラザン閣下、中央評議会より伝達。
“灰域特別調査部隊”の設立が正式に承認されました。
指揮官――貴殿に任命とのことです。」
ラザンの口元がわずかに歪んだ。
「そうか……。理は、再び我らを試すらしい。」
⸻
報告室の照明が落ち、
中央球体が淡く光を放つ。
転送映像の断片――灰色の空、崩壊する塔。
そして、光の中に立つ金の瞳の少女が映し出された。
映像は、そこで途切れた。
沈黙の中で、ラザンが低く呟く。
「――“灰の灯”を、捕らえろ。」
その声が、帝都の符環に反響し、
まるで理そのものが再び目を覚ましたかのように、
青白い光がゆらりと揺れた。
⸻
理を観測する者は、いつも“理解したつもり”になる。
けれど理は、観測された瞬間に形を変える。
それを知らぬ者たちは――再び、理の火に触れる。
夜の帳がゆっくりと降りていた。
灰の空は静まり返り、遠くの山の稜線に淡い光が残る。
焚き火の火が、三人の顔を揺らす。
風が灰を運ぶ。
だがもう、それは冷たい死灰ではない。
どこか温かく、香ばしい土の匂いが混じっていた。
⸻
アーレンは火のそばで古びた符盤を開いていた。
新しい理式を、何度も書き直しては消す。
理の線が、かすかに金色を帯びる。
「……灰が、命を受け入れた。
なら、この世界の理も、書き換えられるはずだ。」
彼は小さく息を吐き、符筆を置いた。
火の明かりの向こうで、ノアが眠そうに瞬きをしている。
「アーレン、それ……新しい研究?」
「いや。これは“祈りの式”だ。
願いが届くように、理の言葉で形を与えるだけのもの。」
「それって……魔法、みたいだね。」
アーレンは笑い、灰を払いながら答えた。
「きっと、昔の人はそう呼んだのかもしれないな。」
⸻
少し離れた場所で、リュミナが夜空を見上げていた。
金の瞳に、灰の星が映っている。
その表情は、どこか懐かしさと寂しさを混ぜていた。
『ねえ、アーレン。
わたし、ひとつだけ、ききたいことがあるの。』
「なんだ?」
『“生まれる”って、どういうこと?
わたしは、灰がつくった。
でも、いまは、こうして“考えてる”。
それも、生きてるってこと?』
アーレンは少し考えてから答えた。
「……俺も、まだ分からない。
でも、考え続けること自体が、生きてる証だと思う。
理も、人も、答えを探すために在るんだ。」
『じゃあ、わたしも、探していい?』
「もちろんだ。お前は――もう、理じゃない。
“リュミナ”だからな。」
⸻
火がぱちりと弾ける。
ノアが毛布にくるまりながら、うとうとと目を閉じた。
アーレンは静かにその頭に手を置く。
「……ノアもよく頑張ったな。」
「ん……つぎは、きれいな町に、いこうね……」
かすれた声が夜に溶ける。
『あたたかい声だね。』
「そうだな。あの声が、ずっと俺を戻してくれた。」
リュミナが焚き火の向こうで微笑んだ。
『それなら、わたしも、ノアにありがとうって言わなきゃ。』
「明日言えばいい。きっと、喜ぶ。」
⸻
夜が深くなる。
灰の風が、音もなく吹き抜ける。
かつての廃都の跡には、新しい光がひとつ、またひとつ灯り始めていた。
灰の民が再び火を灯し、祈りの声を紡いでいるのだ。
アーレンは立ち上がり、遠くの光を見つめた。
灰の上を歩く小さな灯。
それが、確かに世界の“再生”を物語っていた。
『アーレン。』
「ん?」
『これから、どこに行くの?』
アーレンは少しだけ笑い、夜空を見上げた。
灰の星の中に、かすかに赤い光が瞬いている。
それは――帝国の観測衛星。
「……行くさ。
灰の向こう。まだ“理を知らない世界”へ。」
⸻
焚き火が小さくはぜた。
ノアが寝息を立て、リュミナが灰の風に髪をなびかせる。
アーレンはもう一度、符盤を開き、最後の一文を書き残した。
『灰は再び、命を記した。
その暦を、人は“灰暦”と呼ぶ。』
⸻
――灰暦元年。
理と命が初めて手を取り合った夜。
空を渡る風が、どこかで微かに嗤う。
それはまだ、誰も知らぬ“次の理”の息吹。
⸻
そして、遠く離れた帝都では、
ラザンの部下が報告書の端にこう書き添えていた。
「対象:リュミナ・コードネーム“灰の灯”。 追跡開始」
⸻
――灰は、再び揺らぎはじめる。
ーー第3巻 【完】
0
あなたにおすすめの小説

正しい聖女さまのつくりかた
みるくてぃー
ファンタジー
王家で育てられた(自称)平民少女が、学園で起こすハチャメチャ学園(ラブ?)コメディ。
同じ年の第二王女をはじめ、優しい兄姉(第一王女と王子)に見守られながら成長していく。
一般常識が一切通用しない少女に友人達は振り回されてばかり、「アリスちゃんメイドを目指すのになぜダンスや淑女教育が必要なの!?」
そこには人知れず王妃と王女達によるとある計画が進められていた!
果たしてアリスは無事に立派なメイドになれるのか!? たぶん無理かなぁ……。
聖女シリーズ第一弾「正しい聖女さまのつくりかた」

企業再生のプロ、倒産寸前の貧乏伯爵に転生する
namisan
ファンタジー
数々の倒産寸前の企業を立て直してきた敏腕コンサルタントの男は、過労の末に命を落とし、異世界で目を覚ます。
転生先は、帝国北部の辺境にあるアインハルト伯爵家の若き当主、アレク。
しかし、そこは「帝国の重荷」と蔑まれる、借金まみれで領民が飢える極貧領地だった。
凍える屋敷、迫りくる借金取り、絶望する家臣たち。
詰みかけた状況の中で、アレクは独自のユニーク魔法【構造解析(アナライズ)】に目覚める。
それは、物体の構造のみならず、組織の欠陥や魔法術式の不備さえも見抜き、再構築(クラフト)するチート能力だった。
「問題ない。この程度の赤字、前世の案件に比べれば可愛いものだ」
前世の経営知識と規格外の魔法で、アレクは領地の大改革に乗り出す。
痩せた土地を改良し、特産品を生み出し、隣国の経済さえも掌握していくアレク。
そんな彼の手腕に惹かれ、集まってくるのは一癖も二癖もある高貴な美女たち。
これは、底辺から這い上がった若き伯爵が、最強の布陣で自領を帝国一の都市へと発展させ、栄華を極める物語。
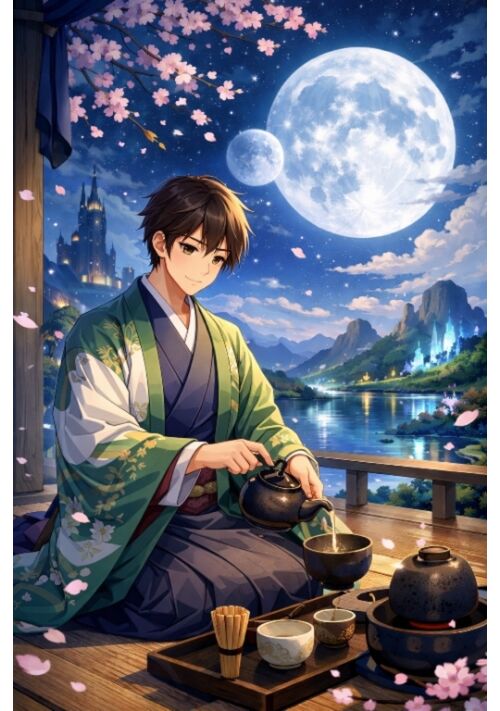
水神飛鳥の異世界茶会記 ~戦闘力ゼロの茶道家が、神業の【陶芸】と至高の【和菓子】で、野蛮な異世界を「癒やし」で侵略するようです~
月神世一
ファンタジー
「剣を下ろし、靴を脱いでください。……茶が入りましたよ」
猫を助けて死んだ茶道家・水神飛鳥(23歳)。
彼が転生したのは、魔法と闘気が支配する弱肉強食のファンタジー世界だった。
チート能力? 攻撃魔法?
いいえ、彼が手にしたのは「茶道具一式」と「陶芸セット」が出せるスキルだけ。
「私がすべき事は、戦うことではありません。一服の茶を出し、心を整えることです」
ゴブリン相手に正座で茶を勧め、
戦場のど真ん中に「結界(茶室)」を展開して空気を変え、
牢屋にぶち込まれれば、そこを「隠れ家カフェ」にリフォームして看守を餌付けする。
そんな彼の振る舞う、異世界には存在しない「極上の甘味(カステラ・羊羹)」と、魔法よりも美しい「茶器」に、武闘派の獣人女王も、強欲な大商人も、次第に心を(胃袋を)掴まれていき……?
「野暮な振る舞いは許しません」
これは、ブレない茶道家が、殺伐とした異世界を「おもてなし」で平和に変えていく、一期一会の物語。

【完結】異世界で神の元カノのゴミ屋敷を片付けたら世界の秘密が出てきました
小豆缶
ファンタジー
父の遺したゴミ屋敷を片付けていたはずが、気づけば異世界に転移していた私・飛鳥。
しかも、神の元カノと顔がそっくりという理由で、いきなり死刑寸前!?
助けてくれた太陽神ソラリクスから頼まれた仕事は、
「500年前に別れた元恋人のゴミ屋敷を片付けてほしい」というとんでもない依頼だった。
幽霊になった元神、罠だらけの屋敷、歪んだ世界のシステム。
ポンコツだけど諦めの悪い主人公が、ゴミ屋敷を片付けながら異世界の謎を暴いていく!
ほのぼのお仕事×異世界コメディ×世界の秘密解明ファンタジー

異世界転移物語
月夜
ファンタジー
このところ、日本各地で謎の地震が頻発していた。そんなある日、都内の大学に通う僕(田所健太)は、地震が起こったときのために、部屋で非常持出袋を整理していた。すると、突然、めまいに襲われ、次に気づいたときは、深い森の中に迷い込んでいたのだ……

神様の忘れ物
mizuno sei
ファンタジー
仕事中に急死した三十二歳の独身OLが、前世の記憶を持ったまま異世界に転生した。
わりとお気楽で、ポジティブな主人公が、異世界で懸命に生きる中で巻き起こされる、笑いあり、涙あり(?)の珍騒動記。

【完結】ご都合主義で生きてます。-商売の力で世界を変える。カスタマイズ可能なストレージで世の中を変えていく-
ジェルミ
ファンタジー
28歳でこの世を去った佐藤は、異世界の女神により転移を誘われる。
その条件として女神に『面白楽しく生活でき、苦労をせずお金を稼いで生きていくスキルがほしい』と無理難題を言うのだった。
困った女神が授けたのは、想像した事を実現できる創生魔法だった。
この味気ない世界を、創生魔法とカスタマイズ可能なストレージを使い、美味しくなる調味料や料理を作り世界を変えて行く。
はい、ご注文は?
調味料、それとも武器ですか?
カスタマイズ可能なストレージで世の中を変えていく。
村を開拓し仲間を集め国を巻き込む産業を起こす。
いずれは世界へ通じる道を繋げるために。
※本作はカクヨム様にも掲載しております。

【完結】異世界で魔道具チートでのんびり商売生活
シマセイ
ファンタジー
大学生・誠也は工事現場の穴に落ちて異世界へ。 物体に魔力を付与できるチートスキルを見つけ、 能力を隠しつつ魔道具を作って商業ギルドで商売開始。 のんびりスローライフを目指す毎日が幕を開ける!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















