1 / 1
🌟 ナナの咆哮とカローラの誓い
しおりを挟む
🌟 ナナの咆哮とカローラの誓い
Ⅰ. 宣戦布告
1995年、初秋。宗介は、自分のトヨタ・カローラが、彼女――ナナコと友人タクヤの手で赤いレカロのバケットシートが収まる改造車へと変貌しているのを見た。ボロボロになった純正シートが撤去された車内には、新品のビニールと、ごまかせない古いオイルの残り香が混じり合っていた。
ナナコからのメモには「感謝してね。愛を込めて」とあったが、宗介の心は怒りと絶望で満ちていた。彼の心には**「人生の選択権を他人に渡すのが怖い」という、自分の人生に無関心だったことへの自己嫌悪**と、無力感があった。
外装は純正のまま、控えめなローダウン。しかし、初めてキーを回すと、低くこもった「フ〇ジツボ」独特の静音ながらも力強い唸りが響いた。それは、純正の「ブーン」という音とは全く違う、生きている機械の咆哮だった。
初めて踏み込んだカーブ。路面に張り付くような安定感、そして体の横ブレを完全に受け止める赤いシートのホールド性能が、宗介に**「車を操る快感」という、人生で初めての情熱を教えてくれた。ナナコは、彼に宣戦布告をしたのではない。彼女は、彼にこの「生きている実感」という名の、オイルと汗にまみれた情熱**を、無理やりにでも押し込みたかったのだ。
Ⅱ. 譲れない男と女
怒りは、やがて興味へと変わった。宗介は、ナナコが待つタクヤのガレージへ、自分の意志で足を踏み入れた。ガレージには、タクヤのR32がけたたましいアイドリング音を響かせ、天井から吊り下げられた蛍光灯の下、オイルと古いタイヤゴムの匂いが混じり合っていた。
「ナナコ、お前の仕掛けた罠に、まんまとハマったよ」
宗介の言葉に、ナナコは涙ぐんだ。「良かった……。もし怒ってたら、もう会えないかと思った」
宗介はタクヤに歩み寄った。「タクヤさん。あのバケットシート、本当に腰にくる。……減衰力って、どうやって硬くするんですか?」
タクヤは驚きと喜びが混じった顔で笑った。「それ、カローラの乗り方を理解したってことだ。ほらよ」
二人は、ナナコが不在の時にカローラのサスペンション調整ダイアルを共に回し始めた。分厚いチューニング雑誌を広げ、宗介が戸惑うと、タクヤは「ほら、これを見ろ。サーキットのセッティングだ」と、ページが破れるほど読み込んだ雑誌を指差した。工具箱から聞こえる乾いた金属音、そして、缶コーヒーをすすりながら、ただ車について語り合う夜が始まった。
Ⅲ. ナナコの愛のセッティング(回想)
その夜、宗介はナナコに尋ねた。「なんで、あのカローラなんだ? もっと簡単なチューニングもあっただろ」
ナナコは微笑んだ。その顔には、宗介が知る由もなかった、二日間の徹夜の痕があった。
(ガレージでの回想シーン)
宗介のカローラを前に、ナナコは新品のバケットシートを指差した。「マフラーは、排気効率はいいけど、音量が合法範囲に収まるフ〇ジツボの静音タイプよ。夜中に帰っても、近所に迷惑はかけさせない。社会性は保たせる」
タクヤは驚いた。「お前が合法性を気にするなんてな。本気で乗り心地も考慮してるのか?」
「当たり前でしょ」ナナコはカローラのタイヤハウスを覗き込んだ。「サスは、テインのフルタップを入れる。車高は限界まで落とすけど、減衰力は、今は一番緩いところにしておく。いきなりサーキット仕様にしたら、ケンジの腰が砕ける」
そして彼女は少し悲しげに言った。「ケンジは、自分の人生の選択権を、私に渡すのが怖いんだと思う。だから、相談しても逃げる。でも、完成したものを渡されたら、もう拒否できないでしょ?これは、私がケンジの人生に仕掛けた、最高のサプライズなの。公道という名の日常を、決して退屈なものにしないためのね。」
タクヤは、その言葉を聞いてR32のタービンを置いた。彼らが仕上げたのは、ただの改造車ではない。それは、**ナナコの、豪快で、不器用で、そしてあまりにも一途な「愛の塊」**だったのだ。
(現在)
「あの時ね、ケンジ。私が一番怖かったのは、あなたに嫌われることじゃなかったの」ナナコは宗介の肩に寄りかかった。「あなたが、あなた自身の情熱を、永遠に諦めてしまうことが、一番怖かった」
宗介は、カローラのボンネットに手を置いた。「次はタワーバーとポテンザ RE-01みたいなハイグリップなタイヤが欲しい。お前が俺に教えてくれたこの車を、俺はもっと速くしたいんだ。ナナコのくれた情熱を、俺はもう誰にも譲らない」
ナナコは、宗介の顔についたオイルの煤を、優しく拭い取った。宗介は、もう二度と、彼女の情熱の世界から逃げ出さないと誓った。
Ⅳ. エピローグ:時を超えた証
――さらに二十年後。
宗介は、あの熱狂的な青春の日々から遠く離れ、当時ローンを組めなかった静かなミニバンを運転している。**車内の匂いは、古いオイルではなく、娘がこぼしたジュースと、チャイルドシートの布の匂いだ。**ある日、ガレージの奥から、使い込まれた赤いレカロのバケットシートと、ナナコの力強い字で書かれたメモを見つけた。その小さなシートと、長年染み込んだガソリンとオイルの独特な匂いが、あの夜のガレージの熱と匂いを蘇らせた。
「パパ、それ、何?」
運転免許を取得したばかりの娘が、興味津々で尋ねる。
宗介は、バケットシートを抱え上げ、笑って言った。「これは、パパがママに命を懸けてついていくと決めた時の、最高のシートだよ」
その横で、すっかり落ち着いたナナコは、娘の手に小さな六角レンチを握らせながら言う。
「車はね、単なる箱じゃないのよ。自分を表現するための相棒なの。でも、改造するときは、ちゃんと彼の同意を得るのよ。……ママみたいに、勝手にやっちゃダメだからね」
娘はクスッと笑い、「パパのカローラ、本当に速くなったの?」と聞く。
宗介は、カローラのバケットシートを見つめながら、穏やかに答えた。
「ああ。少なくとも、あの時の俺の人生で、一番速くて、一番最高の車だったよ」
二人の言葉を聞きながら、宗介は、あのカローラに施された過激なチューニングが、今も、そしてこれからも、自分たちの家族の情熱の源として生き続けることを確信した。
Ⅰ. 宣戦布告
1995年、初秋。宗介は、自分のトヨタ・カローラが、彼女――ナナコと友人タクヤの手で赤いレカロのバケットシートが収まる改造車へと変貌しているのを見た。ボロボロになった純正シートが撤去された車内には、新品のビニールと、ごまかせない古いオイルの残り香が混じり合っていた。
ナナコからのメモには「感謝してね。愛を込めて」とあったが、宗介の心は怒りと絶望で満ちていた。彼の心には**「人生の選択権を他人に渡すのが怖い」という、自分の人生に無関心だったことへの自己嫌悪**と、無力感があった。
外装は純正のまま、控えめなローダウン。しかし、初めてキーを回すと、低くこもった「フ〇ジツボ」独特の静音ながらも力強い唸りが響いた。それは、純正の「ブーン」という音とは全く違う、生きている機械の咆哮だった。
初めて踏み込んだカーブ。路面に張り付くような安定感、そして体の横ブレを完全に受け止める赤いシートのホールド性能が、宗介に**「車を操る快感」という、人生で初めての情熱を教えてくれた。ナナコは、彼に宣戦布告をしたのではない。彼女は、彼にこの「生きている実感」という名の、オイルと汗にまみれた情熱**を、無理やりにでも押し込みたかったのだ。
Ⅱ. 譲れない男と女
怒りは、やがて興味へと変わった。宗介は、ナナコが待つタクヤのガレージへ、自分の意志で足を踏み入れた。ガレージには、タクヤのR32がけたたましいアイドリング音を響かせ、天井から吊り下げられた蛍光灯の下、オイルと古いタイヤゴムの匂いが混じり合っていた。
「ナナコ、お前の仕掛けた罠に、まんまとハマったよ」
宗介の言葉に、ナナコは涙ぐんだ。「良かった……。もし怒ってたら、もう会えないかと思った」
宗介はタクヤに歩み寄った。「タクヤさん。あのバケットシート、本当に腰にくる。……減衰力って、どうやって硬くするんですか?」
タクヤは驚きと喜びが混じった顔で笑った。「それ、カローラの乗り方を理解したってことだ。ほらよ」
二人は、ナナコが不在の時にカローラのサスペンション調整ダイアルを共に回し始めた。分厚いチューニング雑誌を広げ、宗介が戸惑うと、タクヤは「ほら、これを見ろ。サーキットのセッティングだ」と、ページが破れるほど読み込んだ雑誌を指差した。工具箱から聞こえる乾いた金属音、そして、缶コーヒーをすすりながら、ただ車について語り合う夜が始まった。
Ⅲ. ナナコの愛のセッティング(回想)
その夜、宗介はナナコに尋ねた。「なんで、あのカローラなんだ? もっと簡単なチューニングもあっただろ」
ナナコは微笑んだ。その顔には、宗介が知る由もなかった、二日間の徹夜の痕があった。
(ガレージでの回想シーン)
宗介のカローラを前に、ナナコは新品のバケットシートを指差した。「マフラーは、排気効率はいいけど、音量が合法範囲に収まるフ〇ジツボの静音タイプよ。夜中に帰っても、近所に迷惑はかけさせない。社会性は保たせる」
タクヤは驚いた。「お前が合法性を気にするなんてな。本気で乗り心地も考慮してるのか?」
「当たり前でしょ」ナナコはカローラのタイヤハウスを覗き込んだ。「サスは、テインのフルタップを入れる。車高は限界まで落とすけど、減衰力は、今は一番緩いところにしておく。いきなりサーキット仕様にしたら、ケンジの腰が砕ける」
そして彼女は少し悲しげに言った。「ケンジは、自分の人生の選択権を、私に渡すのが怖いんだと思う。だから、相談しても逃げる。でも、完成したものを渡されたら、もう拒否できないでしょ?これは、私がケンジの人生に仕掛けた、最高のサプライズなの。公道という名の日常を、決して退屈なものにしないためのね。」
タクヤは、その言葉を聞いてR32のタービンを置いた。彼らが仕上げたのは、ただの改造車ではない。それは、**ナナコの、豪快で、不器用で、そしてあまりにも一途な「愛の塊」**だったのだ。
(現在)
「あの時ね、ケンジ。私が一番怖かったのは、あなたに嫌われることじゃなかったの」ナナコは宗介の肩に寄りかかった。「あなたが、あなた自身の情熱を、永遠に諦めてしまうことが、一番怖かった」
宗介は、カローラのボンネットに手を置いた。「次はタワーバーとポテンザ RE-01みたいなハイグリップなタイヤが欲しい。お前が俺に教えてくれたこの車を、俺はもっと速くしたいんだ。ナナコのくれた情熱を、俺はもう誰にも譲らない」
ナナコは、宗介の顔についたオイルの煤を、優しく拭い取った。宗介は、もう二度と、彼女の情熱の世界から逃げ出さないと誓った。
Ⅳ. エピローグ:時を超えた証
――さらに二十年後。
宗介は、あの熱狂的な青春の日々から遠く離れ、当時ローンを組めなかった静かなミニバンを運転している。**車内の匂いは、古いオイルではなく、娘がこぼしたジュースと、チャイルドシートの布の匂いだ。**ある日、ガレージの奥から、使い込まれた赤いレカロのバケットシートと、ナナコの力強い字で書かれたメモを見つけた。その小さなシートと、長年染み込んだガソリンとオイルの独特な匂いが、あの夜のガレージの熱と匂いを蘇らせた。
「パパ、それ、何?」
運転免許を取得したばかりの娘が、興味津々で尋ねる。
宗介は、バケットシートを抱え上げ、笑って言った。「これは、パパがママに命を懸けてついていくと決めた時の、最高のシートだよ」
その横で、すっかり落ち着いたナナコは、娘の手に小さな六角レンチを握らせながら言う。
「車はね、単なる箱じゃないのよ。自分を表現するための相棒なの。でも、改造するときは、ちゃんと彼の同意を得るのよ。……ママみたいに、勝手にやっちゃダメだからね」
娘はクスッと笑い、「パパのカローラ、本当に速くなったの?」と聞く。
宗介は、カローラのバケットシートを見つめながら、穏やかに答えた。
「ああ。少なくとも、あの時の俺の人生で、一番速くて、一番最高の車だったよ」
二人の言葉を聞きながら、宗介は、あのカローラに施された過激なチューニングが、今も、そしてこれからも、自分たちの家族の情熱の源として生き続けることを確信した。
0
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説


百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

上司、快楽に沈むまで
赤林檎
BL
完璧な男――それが、営業部課長・**榊(さかき)**の社内での評判だった。
冷静沈着、部下にも厳しい。私生活の噂すら立たないほどの隙のなさ。
だが、その“完璧”が崩れる日がくるとは、誰も想像していなかった。
入社三年目の篠原は、榊の直属の部下。
真面目だが強気で、どこか挑発的な笑みを浮かべる青年。
ある夜、取引先とのトラブル対応で二人だけが残ったオフィスで、
篠原は上司に向かって、いつもの穏やかな口調を崩した。「……そんな顔、部下には見せないんですね」
疲労で僅かに緩んだ榊の表情。
その弱さを見逃さず、篠原はデスク越しに距離を詰める。
「強がらなくていいですよ。俺の前では、もう」
指先が榊のネクタイを掴む。
引き寄せられた瞬間、榊の理性は音を立てて崩れた。
拒むことも、許すこともできないまま、
彼は“部下”の手によって、ひとつずつ乱されていく。
言葉で支配され、触れられるたびに、自分の知らなかった感情と快楽を知る。それは、上司としての誇りを壊すほどに甘く、逃れられないほどに深い。
だが、篠原の視線の奥に宿るのは、ただの欲望ではなかった。
そこには、ずっと榊だけを見つめ続けてきた、静かな執着がある。
「俺、前から思ってたんです。
あなたが誰かに“支配される”ところ、きっと綺麗だろうなって」
支配する側だったはずの男が、
支配されることで初めて“生きている”と感じてしまう――。
上司と部下、立場も理性も、すべてが絡み合うオフィスの夜。
秘密の扉を開けた榊は、もう戻れない。
快楽に溺れるその瞬間まで、彼を待つのは破滅か、それとも救いか。
――これは、ひとりの上司が“愛”という名の支配に沈んでいく物語。

あるフィギュアスケーターの性事情
蔵屋
恋愛
この小説はフィクションです。
しかし、そのようなことが現実にあったかもしれません。
何故ならどんな人間も、悪魔や邪神や悪神に憑依された偽善者なのですから。
この物語は浅岡結衣(16才)とそのコーチ(25才)の恋の物語。
そのコーチの名前は高木文哉(25才)という。
この物語はフィクションです。
実在の人物、団体等とは、一切関係がありません。
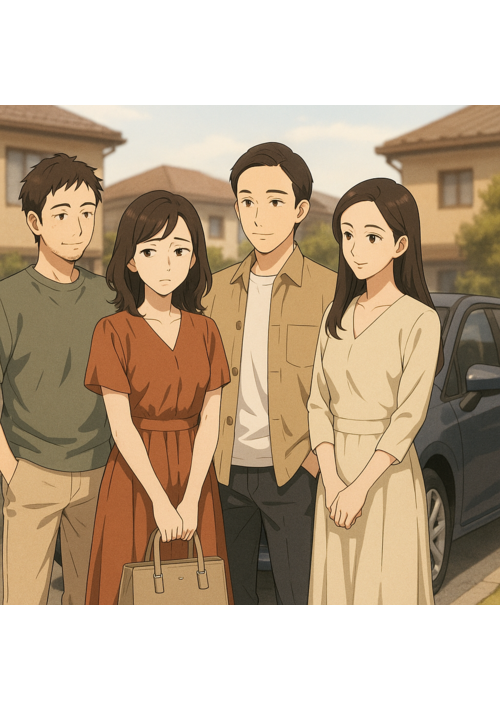

同じアパートに住む年上未亡人美女は甘すぎる。
ピコサイクス
青春
大学生の翔太は、一人暮らしを始めたばかり。
真下の階に住むのは、落ち着いた色気と優しさを併せ持つ大人の女性・水無瀬紗夜。
引っ越しの挨拶で出会った瞬間、翔太は心を奪われてしまう。
偶然にもアルバイト先のスーパーで再会した彼女は、翔太をすぐに採用し、温かく仕事を教えてくれる存在だった。
ある日の仕事帰り、ふたりで過ごす時間が増えていき――そして気づけば紗夜の部屋でご飯をご馳走になるほど親密に。
優しくて穏やかで――その色気に触れるたび、翔太の心は揺れていく。
大人の女性と大学生、甘くちょっぴり刺激的な同居生活(?)がはじまる。

ちょっと大人な物語はこちらです
神崎 未緒里
恋愛
本当にあった!?かもしれない
ちょっと大人な短編物語集です。
日常に突然訪れる刺激的な体験。
少し非日常を覗いてみませんか?
あなたにもこんな瞬間が訪れるかもしれませんよ?
※本作品ではGemini PRO、Pixai.artで作成した生成AI画像ならびに
Pixabay並びにUnsplshのロイヤリティフリーの画像を使用しています。
※不定期更新です。
※文章中の人物名・地名・年代・建物名・商品名・設定などはすべて架空のものです。

曖昧な距離で愛している
山田森湖
恋愛
結婚4年目のアラサー夫婦、拓海と美咲。仲は悪くないが、ときめきは薄れ、日常は「作業」になっていた。夫には可愛い後輩が現れ、妻は昔の恋人と再会する。揺れる心、すれ違う想い。「恋人に戻りたい」――そう願った二人が辿り着いた答えは、意外なものだった。曖昧で、程よい距離。それが、私たちの愛の形。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















