13 / 46
第三章
錆びたワイン(1)
しおりを挟む
明るい照明と華やかな色彩のディスプレイで飾られたデパートの化粧品売り場。
ルネは、かねてから気になっていた男性用のコロンを探しだすと、試しに自分の手首に吹きかけてみた。
「やっぱり好きな香りだけど…うーん、どうしようかな」
シャネルのエゴイスト。ローランが愛用しているコロンだ。
(ローランだったら、まさにこの香りをまとうために生まれてきたっていうくらいにしっくりくるけど、僕だと負けちゃうんだよね)
ルネががっかりしながらボトルをもとの場所に戻すと、カウンターから出てきた綺麗な店員が、愛想よく声をかけてきた。
「良い香りでしょう? 発売されてもう30年以上になりますが、ずっと人気のあるコロンですのよ。あなたがお使いになりますの? それとも贈り物をお探しで?」
「い、いえ…僕の職場の人がこのコロンを使っていて、すごく似合っていたものだから、気になっていたんです。でも、僕みたいな若い男の子向けの香りじゃないですね、残念ながら…これが似合う大人の男になるには、十年くらいかかるかな」
「確かにちょっと、まとう人を選ぶかもしれませんわねぇ。よほど素敵な方なんでしょうね、あなたの職場のその人は…」
「はいっ」
恥ずかしげもなく笑顔で即答してしまったルネに、一瞬店員は怯んだようだ。しかし、そこはプロらしく、すぐに営業向けの顔に戻って、まだ迷っている彼に他にも幾つかコロンを勧めた。
「あなたのような若い方が日常お使いになるのでしたら…柑橘系の爽やかな香りのこちらのコロンなどいかかでしょう?」
「あ、本当にいい匂い…グレープフルーツにベルガモット…ちょっぴりムスクの香りやペッパーみたいなスパイシーさもある」
「あら、とても嗅覚が鋭い方ですわね。もしかして香りに関わるお仕事をなさっていますの…?」
「いいえ、普通のオフィス勤務ですよ。あ、こちらのコロンもいいですね…」
実際彼女の見立てのコロンの方が、ルネがつけても無理がない、使いやすそうなものだったが、悩んだ挙句、彼は結局ローラン愛用のエゴイストを購入した。
(ああ、お給料前にまた余計な出費をしちゃったな。まさかローランのいる職場で、彼と同じコロンをまとうわけにもいかない。下手したら、家で1人でいる時にこっそりつけてみるだけになりそうなのに…)
ルネは手首に残る、先程試したコロンをそっと嗅いで、体温で温まった香りの微妙に変化にうっとりした。
(それも、いいかな…たとえば夜、ベッドで眠る時に軽くつけてみたら、ローランが傍にいてくれるみたいで安心して眠れそう…それとも、興奮して眠れないかのどっちかだな)
そんな想像をしてついにやけそうになったルネは、慌てて頬を引き締めると、怪訝そうな顔をする店員から商品の入った小さな紙袋を受け取り、足取りも軽くデパートを後にした。
ルネがルレ・ロスコーで働き始めて、ひと月近くが飛ぶように過ぎさった。
まだ秘書の学校に通いながらではあるが、物覚えのよいルネは、日常業務は難なくこなせるようになり、この様子なら1人でも大丈夫だろうと、ミラは予定を早めて来週末から産休に入ることになった。
気分転換にと密かに通い始めた道場では、気の合う友人や仲間ができ、おかげで精神的にも安定している。
当初はどうなることかと思われたが、絶対馴染めないと敬遠していた大都会パリでの生活に、ルネは少しずつ慣れてきていた。
もっとも全く不満がない訳でもない。
いくら他に気を紛らわせられる趣味を見つけ、愚痴や悩みを話せる友人ができたところで、ルネの一番の関心は、相も変わらず本心の読めないローランだった。
彼との関係は、表向きはあくまでただの上司と部下であり、普段ローランはルネに特別な感情を抱いている気ぶりも見せない。ルネもオフィスでは自分の感情に封印し、ローランと話す時も控え目で抑制のきいた態度に徹していた。
しかし、恋心というものは、隠そうとしてもなかなか隠しきれないもの。ルネの目は無意識のうちにローランの動きを追ってしまうし、他の人と話している彼の声に、つい耳をそばだててしまう。仕事がうまくいって褒められたりするとたちまち舞い上がって、ミラに、恋する乙女みたいな顔になっていると注意されることもしばしばだ。
職場では欲求不満を抱えたまま。かと言って、仕事を離れたプライベートでも、ローランとの恋に何ら進展があった訳ではない。
パリで暮らし始めた当初、心身ともに壊れそうになっていたルネを訪ねてきた夜以来、ローランが再び彼のアパルトメンに来ることはなかった。
今度一緒に食事に行こうとか乗馬に連れて行ってやるとか誘われた記憶はあったけれど、別にちゃんと約束を交わした訳ではなかったから、ルネはローランを責めることはできなかったが、やはりちょっぴり寂しかった。
「全く、じれったいわねぇ。そんなに彼のことが好きなら、自分から誘ってみたらいいじゃないの!」
仕事が終わった後、いつものカフェで、女友達のキアラ相手に、ルネは互いの恋の悩みを含むたわいのないおしゃべりに花を咲かせている。
キアラとは、秘書の学校の近くで見つけた道場で知り合った。会ったその日に意気投合し、今では、何でも打ち明け合える一番の友達だ。
「考えたことがない訳でもないけど…オフィスでのローランは、そんなに気安く近づける雰囲気じゃないし…それに、僕の方にも抵抗があるのかな。上司との恋愛関係にはまりこんだりすると仕事がやりにくくなるって…」
「もう、また、そんな言い訳して逃げるんだからっ」
女子部では、柔道でも空手でも一二を争うくらいに強いキアラは勝ち気な性格で、恋に関しても積極的だ。ルネの恋ばなは面白いと興味津々聞いてくれるが、苛々することもあるようで、時々こんなふうに叱られる。
「結局、ルネ、肝心のあなたがいつまでも恋に対して臆病なことが一番の問題なのよ」
「だって、ローランには他に最愛の人がいるだよ。なかなか積極的に迫ったりはできないよ」
ルネは困ったように唇を尖らせた。
「その人に僕が似ているから気に入ったって、即行手を出したような人でなしなんだよ。そんな変人に惚れちゃう僕も馬鹿なんだけど、これ以上都合のいい存在になんてなりたくないよ。あなたが好きなんです、身代りでも何でもいいから付き合って下さいなんてうっかり漏らしたりしたら、本当に、あの人の想い人のスペア品として扱われるよ。そんなことまで許してしまったら、この恋、僕の完敗じゃないか」
「うわ、それって最悪…でもさ、どうせなら、彼の心を自分に振り向かせてみせる、ガブリエルから奪ってやるって気持ちにならないの?」
「ええっ、奪う?!」
ルネは思わず、カフェの他の客達が振り返るくらい、すっ頓狂な声をあげていた。
「何をびっくりしてるのよ。好きなら、たとえ相手に今付き合っている人がいようが構わず押せ押せで迫って、自分の恋人にしちゃうのよ、当然じゃない」
「もう、キアラってば、無責任な煽りかたして…」
苦笑いしながら、ルネはコーヒーを一口飲み、ふと考え込んだ。
(そう言えば、ローランがガブリエルをどんなふうに思っているのか、結局僕は恐くて聞けないでいる。たまに、あの人が話の中でガブリエルに触れる時には、とても深い愛情のこもった口ぶりになるから、ああ、やっぱり好きなんだなぁとは感じるけれど…一度問い詰めて、はっきりさせておいた方がいいんだろうか)
いまだ顔を見たこともないガブリエルのことを考えると、ルネの胸は嫉妬の小さな火でちりちりと焼かれた。
(でも、ローランの本当の気持ちを聞いて、それで僕には何の望みもないと思い知ってしまったら…僕はもうあの人の傍にい続けることはさすがにできなくなるだろうな。ローランの傍を離れるしかなくなる…それは嫌だ…)
結局、玉砕覚悟でローランの本心を確かめる勇気も、キアラのように積極的に迫って彼の心を自分のものにしようとするだけの自信も、ルネには持てなかった。
(確かにキアラの言う通りだ。ローランの傍で毎日働くことができて、チャンスならいくらでもあるはずなのに、いざとなると怯んでしまう。こんな調子だと、いつまで待っても恋が叶うことなんかあるものか。ああ、軽く自己嫌悪に陥りそうだな)
ルネが悲しそうに溜息をつくのを、可愛そうなものを見るかのような目つきで眺めていたキアラが、ふいに、こんなことを言った。
「いっそ、他の相手を探してみたらどう?」
「え?」
「だってさ、大本命のローランとの恋は早くも行き詰っているんでしょう? それなら、そっちは取りあえず置いといて、他の出会いを求めてみるのよ」
「他の…出会い…?」
「初めて会った時、あなた、言ってたじゃない。自分の住んでいた田舎では、同性愛者どころか、下手すれば家畜や野生動物の生息数の方が人口より多いくらいなんだ。そんな所にいつまでいても素敵な恋人は得られそうにないけど、人口密度の遥かに高いパリでなら、理想の男性が見つかる確率も高いはずだと思ったって…真面目な顔して面白いこと考える子ねぇって、私、感心したのよ」
「…酔った勢いで話したことを、いつまでも覚えてないでよ。恥ずかしいなぁ」
「あはは…でもさ、真面目な話、このまま片思いを続けるよりは、もっと他に目を向けてみた方が、あなたの場合、いいような気がするな。どうせあなたのことだから、ローラン一筋で、他の男を意識して見てみたこともないんでしょう? せっかくパリにまで出てきたんじゃない、もっと視野を広げてみたら?」
「で、でも…僕はローランが好きなのに、他の人となんて―」
「別に恋人同士って訳じゃないでしょ、あなたとローランって? 義理立てすることはないんじゃない?」
キアラに痛い所を突かれて、ルネはぐっと言葉に詰まった。
「そうよ、その気になってちゃんと探せば、他に好きな人のいるローランより、もっと優しくてあなたを大切にしてくれる、素敵な人が見つかるかもよ?」
キアラの言うことの方がたぶん正論なんだろうが――。
「ローランより素敵な人なんて、そう簡単に見つからないよ。確かにパリの男の人は垢抜けてるなって思うけど、先にあの人を知っちゃったら、その辺りの普通の男なんか、皆マルシェに並んでいる野菜にしか見えなくなってくる…」
「あなたも結構ひどいこい言うわねぇ! 面食いなのは分かったけど、ルネ、あなたの理想の男って、一体どんな人なわけ?」
理想? ルネは首を捻って、ちょっと考え込んだ。
「そうだね、強い人、かな…この人には何をやっても敵わないって、僕が思えるくらい、強い人が好き」
「あら、いきなりハードル高いわね。うちの道場でも既に向かうところ敵なしのあなたより強い男となると、それこそ、プロの格闘家レベルじゃない。あ、トマなんかどう? 残念ながら腕っ節はちょっと劣るけれど、あなたにぶん投げられて完敗して以来、あなたに随分惚れ込んでしまったようよ」
柔道教室に見学に行った初日に手合わせをして簡単に一本勝ちして以来、ルネを『師匠』と呼んで慕ってくる大男のトマを思いだし、彼は唇をすぼめた。
「トマはいい子だと思うけど、僕はゴリ・マッチョはタイプじゃないなぁ…いや、そういうことじゃなくね、僕が求めるのは腕っ節の強さ以上の何かなんだよ。存在そのものに僕を圧倒する力があって、有無を言わさず、ぐいぐい引っ張っていかれそうな人なんだ」
「ローランがそういうタイプなんだ?」
「うん。もちろん、本気で喧嘩したら、僕が勝つと思うんだけれど…あの人から発散されるオーラはとても強くて、傍にいるだけで、逆らう気持ちを根こそぎなくしてしまうんだ」
「…惚れた男だから、そう思うのかもしれないけどねぇ。ローランの前では、柔道やってる時の気迫の片鱗も見せず、しおらしげにしているあなたが目に浮かぶわ。ところで、ルネ、そもそもローランはあなたが格闘技をやってることを知っているの?」
ルネは、またしてもキアラに痛い所を突かれて、ぎくりとした。
「知らない…よ…僕も、あの人には黙っているつもりだし…」
「黙っているって、どうして?」
「だって、ほら、僕の腕があんまりたち過ぎることを知られたら、どん引きされそうだから…自分の強さを自覚している男って、より強い男をライバル視はするけれど、恋人として好きにはなってくれないもの」
「あら…ローランに嫌われるのが怖くて、本当の自分を隠しているってわけ? まあ、気持ちは分からないでもないけど…女の子の場合は特に、強くなるほど彼氏には打ち明けにくいって、よく聞く話よ。でも、あなたは―」
勘のいいキアラは、ルネの口ぶりに何か引っかかりを覚えたようだが、これ以上追求される前に、ルネはこの話を打ち切ろうとした。
「ともかく僕は、やっぱりローラン以外の誰かと付き合おうという気持ちにはなれないから…」
「しょうがないわねぇ。せっかく、あなたにお勧めの店を見つけてきてあげたのに…」
「店?」
思ったより頑固なルネを説得することは諦めたのか、キアラはやれやれというように肩をすくめ、バッグの中から一枚のカードを取り出した。
「ゲイの知り合いに、あなたのことを相談してみたのよ。それで、やっぱりローランだけって初めから思いこまずに、色んな人に会ってみた方がいいんじゃないかって話になって…それで、ここのワイン・バーなんだけれど、最近パリのおしゃれなゲイの社交場になってるんだって。雑誌でも何度か紹介されたことがあるみたいよ。別に同性愛者ばかりって訳でもないし、雰囲気もよくって入りやすいから、あなた向けじゃないかなと思ったのよ」
「あ…」
「まあ、どうしてもその気になれないなら仕方ないけどね。一応そのカードは渡しておくわ」
ルネが目の前に置かれたカードを凝視しながら考え込んでいるうちに、キアラは腕時計をちらっと確認した。
「私、そろそろ行くわね、ルネ…これから彼と一緒に映画を見に行くことになっているの」
ルネははっと我に返って、テーブルから立ち上がるキアラに向かって、慌てて声をかけた。
「キアラ、あの…ありがとう、僕を心配して色々考えてくれてたんだね」
「ルネってば、何、そんなすまなそうな顔してるのよ。当然じゃない、私達、友達でしょ?」
キアラは屈託のない笑顔で答えると、バッグを肩に引っかけ、颯爽とした足取りでカフェを出て行った。
(都会の人は冷たくて取っつきにくいなんて、とんだ偏見だったんだな。キアラみたいに、親身になって僕のことを考えてくれる人もいる)
ほっこりと胸が温まるような気分になりながら、ルネはキアラからもらった店のカードを手に取った。
さっそくのスマホで検索してみる。
(あ、ほんとに、若者向けのおしゃれなワイン・バーみたい…気軽に入れそうな雰囲気だけれど、ワイン・リストは充実してるか…ふうん、ここなら普通にちょっと立ち寄ってみたいかも…)
ローランに奢ってもらったシャトー・ラトゥールで開眼して以来、ルネはワインにも興味を持って、少しずつ嗜むようになっていた。
ネットでラトゥールを買えないかと調べてみた時は、その値段のあり得なさに腰を抜かしそうになったものだが、たかが飲み物にここまでの価値が認められる、ワインの世界には好奇心をかきたてられた。もともと勉強熱心で、関心を覚えたことはとことんまで追求したがる傾向のあるルネだ。これも秘書の仕事の役に立つだろうと、ワイン関係の書物に手を出して、時間がある時は読みふけっている。
(でも、本で得た知識だけじゃ物足りないって思ってたところなんだよね。こういう店では、どんなワインを出すのだろう…グラスで色々試してみたい気がするな)
せっかくキアラが探してくれた店なのだし、一度くらい行ってみてもいいかもしれない。
(そうだ…いっそ、思いきってローランを誘ってみようかな…?)
自分からローランに対して積極的に出ることを躊躇っていたが、このバーを口実に、行動に出てみようか。
(この間ご馳走になったお礼に、僕に奢らせて下さい…いや、駄目だ、ラトゥールに見合うワインなんか奢ったら、僕が破産しちゃう。正直に、友達に教えてもらったワイン・バーなんですけれど、1人だと入りにくいので、よかったら付き合ってくれませんかってお願いすればいいんだ。他に約束がなければ、きっと断られたりはしないよね…?)
友達の心遣いに背中を押される形で、ルネはやっと気持ちを固めることができた。
(善は急げというし、僕の気持ちがまたしぼんでしまう前に、明日にでもローランに声をかけてみよう)
そんなことを想像しながら、ルネは妙にうきうきと弾んだ気分になっていた。
結局、大好きなローランが傍にいるのに、自分の感情に封印をし続けている今の状況を変えるきっかけを求めていたのは、他ならぬルネ自身だったようだ。
ルネは、かねてから気になっていた男性用のコロンを探しだすと、試しに自分の手首に吹きかけてみた。
「やっぱり好きな香りだけど…うーん、どうしようかな」
シャネルのエゴイスト。ローランが愛用しているコロンだ。
(ローランだったら、まさにこの香りをまとうために生まれてきたっていうくらいにしっくりくるけど、僕だと負けちゃうんだよね)
ルネががっかりしながらボトルをもとの場所に戻すと、カウンターから出てきた綺麗な店員が、愛想よく声をかけてきた。
「良い香りでしょう? 発売されてもう30年以上になりますが、ずっと人気のあるコロンですのよ。あなたがお使いになりますの? それとも贈り物をお探しで?」
「い、いえ…僕の職場の人がこのコロンを使っていて、すごく似合っていたものだから、気になっていたんです。でも、僕みたいな若い男の子向けの香りじゃないですね、残念ながら…これが似合う大人の男になるには、十年くらいかかるかな」
「確かにちょっと、まとう人を選ぶかもしれませんわねぇ。よほど素敵な方なんでしょうね、あなたの職場のその人は…」
「はいっ」
恥ずかしげもなく笑顔で即答してしまったルネに、一瞬店員は怯んだようだ。しかし、そこはプロらしく、すぐに営業向けの顔に戻って、まだ迷っている彼に他にも幾つかコロンを勧めた。
「あなたのような若い方が日常お使いになるのでしたら…柑橘系の爽やかな香りのこちらのコロンなどいかかでしょう?」
「あ、本当にいい匂い…グレープフルーツにベルガモット…ちょっぴりムスクの香りやペッパーみたいなスパイシーさもある」
「あら、とても嗅覚が鋭い方ですわね。もしかして香りに関わるお仕事をなさっていますの…?」
「いいえ、普通のオフィス勤務ですよ。あ、こちらのコロンもいいですね…」
実際彼女の見立てのコロンの方が、ルネがつけても無理がない、使いやすそうなものだったが、悩んだ挙句、彼は結局ローラン愛用のエゴイストを購入した。
(ああ、お給料前にまた余計な出費をしちゃったな。まさかローランのいる職場で、彼と同じコロンをまとうわけにもいかない。下手したら、家で1人でいる時にこっそりつけてみるだけになりそうなのに…)
ルネは手首に残る、先程試したコロンをそっと嗅いで、体温で温まった香りの微妙に変化にうっとりした。
(それも、いいかな…たとえば夜、ベッドで眠る時に軽くつけてみたら、ローランが傍にいてくれるみたいで安心して眠れそう…それとも、興奮して眠れないかのどっちかだな)
そんな想像をしてついにやけそうになったルネは、慌てて頬を引き締めると、怪訝そうな顔をする店員から商品の入った小さな紙袋を受け取り、足取りも軽くデパートを後にした。
ルネがルレ・ロスコーで働き始めて、ひと月近くが飛ぶように過ぎさった。
まだ秘書の学校に通いながらではあるが、物覚えのよいルネは、日常業務は難なくこなせるようになり、この様子なら1人でも大丈夫だろうと、ミラは予定を早めて来週末から産休に入ることになった。
気分転換にと密かに通い始めた道場では、気の合う友人や仲間ができ、おかげで精神的にも安定している。
当初はどうなることかと思われたが、絶対馴染めないと敬遠していた大都会パリでの生活に、ルネは少しずつ慣れてきていた。
もっとも全く不満がない訳でもない。
いくら他に気を紛らわせられる趣味を見つけ、愚痴や悩みを話せる友人ができたところで、ルネの一番の関心は、相も変わらず本心の読めないローランだった。
彼との関係は、表向きはあくまでただの上司と部下であり、普段ローランはルネに特別な感情を抱いている気ぶりも見せない。ルネもオフィスでは自分の感情に封印し、ローランと話す時も控え目で抑制のきいた態度に徹していた。
しかし、恋心というものは、隠そうとしてもなかなか隠しきれないもの。ルネの目は無意識のうちにローランの動きを追ってしまうし、他の人と話している彼の声に、つい耳をそばだててしまう。仕事がうまくいって褒められたりするとたちまち舞い上がって、ミラに、恋する乙女みたいな顔になっていると注意されることもしばしばだ。
職場では欲求不満を抱えたまま。かと言って、仕事を離れたプライベートでも、ローランとの恋に何ら進展があった訳ではない。
パリで暮らし始めた当初、心身ともに壊れそうになっていたルネを訪ねてきた夜以来、ローランが再び彼のアパルトメンに来ることはなかった。
今度一緒に食事に行こうとか乗馬に連れて行ってやるとか誘われた記憶はあったけれど、別にちゃんと約束を交わした訳ではなかったから、ルネはローランを責めることはできなかったが、やはりちょっぴり寂しかった。
「全く、じれったいわねぇ。そんなに彼のことが好きなら、自分から誘ってみたらいいじゃないの!」
仕事が終わった後、いつものカフェで、女友達のキアラ相手に、ルネは互いの恋の悩みを含むたわいのないおしゃべりに花を咲かせている。
キアラとは、秘書の学校の近くで見つけた道場で知り合った。会ったその日に意気投合し、今では、何でも打ち明け合える一番の友達だ。
「考えたことがない訳でもないけど…オフィスでのローランは、そんなに気安く近づける雰囲気じゃないし…それに、僕の方にも抵抗があるのかな。上司との恋愛関係にはまりこんだりすると仕事がやりにくくなるって…」
「もう、また、そんな言い訳して逃げるんだからっ」
女子部では、柔道でも空手でも一二を争うくらいに強いキアラは勝ち気な性格で、恋に関しても積極的だ。ルネの恋ばなは面白いと興味津々聞いてくれるが、苛々することもあるようで、時々こんなふうに叱られる。
「結局、ルネ、肝心のあなたがいつまでも恋に対して臆病なことが一番の問題なのよ」
「だって、ローランには他に最愛の人がいるだよ。なかなか積極的に迫ったりはできないよ」
ルネは困ったように唇を尖らせた。
「その人に僕が似ているから気に入ったって、即行手を出したような人でなしなんだよ。そんな変人に惚れちゃう僕も馬鹿なんだけど、これ以上都合のいい存在になんてなりたくないよ。あなたが好きなんです、身代りでも何でもいいから付き合って下さいなんてうっかり漏らしたりしたら、本当に、あの人の想い人のスペア品として扱われるよ。そんなことまで許してしまったら、この恋、僕の完敗じゃないか」
「うわ、それって最悪…でもさ、どうせなら、彼の心を自分に振り向かせてみせる、ガブリエルから奪ってやるって気持ちにならないの?」
「ええっ、奪う?!」
ルネは思わず、カフェの他の客達が振り返るくらい、すっ頓狂な声をあげていた。
「何をびっくりしてるのよ。好きなら、たとえ相手に今付き合っている人がいようが構わず押せ押せで迫って、自分の恋人にしちゃうのよ、当然じゃない」
「もう、キアラってば、無責任な煽りかたして…」
苦笑いしながら、ルネはコーヒーを一口飲み、ふと考え込んだ。
(そう言えば、ローランがガブリエルをどんなふうに思っているのか、結局僕は恐くて聞けないでいる。たまに、あの人が話の中でガブリエルに触れる時には、とても深い愛情のこもった口ぶりになるから、ああ、やっぱり好きなんだなぁとは感じるけれど…一度問い詰めて、はっきりさせておいた方がいいんだろうか)
いまだ顔を見たこともないガブリエルのことを考えると、ルネの胸は嫉妬の小さな火でちりちりと焼かれた。
(でも、ローランの本当の気持ちを聞いて、それで僕には何の望みもないと思い知ってしまったら…僕はもうあの人の傍にい続けることはさすがにできなくなるだろうな。ローランの傍を離れるしかなくなる…それは嫌だ…)
結局、玉砕覚悟でローランの本心を確かめる勇気も、キアラのように積極的に迫って彼の心を自分のものにしようとするだけの自信も、ルネには持てなかった。
(確かにキアラの言う通りだ。ローランの傍で毎日働くことができて、チャンスならいくらでもあるはずなのに、いざとなると怯んでしまう。こんな調子だと、いつまで待っても恋が叶うことなんかあるものか。ああ、軽く自己嫌悪に陥りそうだな)
ルネが悲しそうに溜息をつくのを、可愛そうなものを見るかのような目つきで眺めていたキアラが、ふいに、こんなことを言った。
「いっそ、他の相手を探してみたらどう?」
「え?」
「だってさ、大本命のローランとの恋は早くも行き詰っているんでしょう? それなら、そっちは取りあえず置いといて、他の出会いを求めてみるのよ」
「他の…出会い…?」
「初めて会った時、あなた、言ってたじゃない。自分の住んでいた田舎では、同性愛者どころか、下手すれば家畜や野生動物の生息数の方が人口より多いくらいなんだ。そんな所にいつまでいても素敵な恋人は得られそうにないけど、人口密度の遥かに高いパリでなら、理想の男性が見つかる確率も高いはずだと思ったって…真面目な顔して面白いこと考える子ねぇって、私、感心したのよ」
「…酔った勢いで話したことを、いつまでも覚えてないでよ。恥ずかしいなぁ」
「あはは…でもさ、真面目な話、このまま片思いを続けるよりは、もっと他に目を向けてみた方が、あなたの場合、いいような気がするな。どうせあなたのことだから、ローラン一筋で、他の男を意識して見てみたこともないんでしょう? せっかくパリにまで出てきたんじゃない、もっと視野を広げてみたら?」
「で、でも…僕はローランが好きなのに、他の人となんて―」
「別に恋人同士って訳じゃないでしょ、あなたとローランって? 義理立てすることはないんじゃない?」
キアラに痛い所を突かれて、ルネはぐっと言葉に詰まった。
「そうよ、その気になってちゃんと探せば、他に好きな人のいるローランより、もっと優しくてあなたを大切にしてくれる、素敵な人が見つかるかもよ?」
キアラの言うことの方がたぶん正論なんだろうが――。
「ローランより素敵な人なんて、そう簡単に見つからないよ。確かにパリの男の人は垢抜けてるなって思うけど、先にあの人を知っちゃったら、その辺りの普通の男なんか、皆マルシェに並んでいる野菜にしか見えなくなってくる…」
「あなたも結構ひどいこい言うわねぇ! 面食いなのは分かったけど、ルネ、あなたの理想の男って、一体どんな人なわけ?」
理想? ルネは首を捻って、ちょっと考え込んだ。
「そうだね、強い人、かな…この人には何をやっても敵わないって、僕が思えるくらい、強い人が好き」
「あら、いきなりハードル高いわね。うちの道場でも既に向かうところ敵なしのあなたより強い男となると、それこそ、プロの格闘家レベルじゃない。あ、トマなんかどう? 残念ながら腕っ節はちょっと劣るけれど、あなたにぶん投げられて完敗して以来、あなたに随分惚れ込んでしまったようよ」
柔道教室に見学に行った初日に手合わせをして簡単に一本勝ちして以来、ルネを『師匠』と呼んで慕ってくる大男のトマを思いだし、彼は唇をすぼめた。
「トマはいい子だと思うけど、僕はゴリ・マッチョはタイプじゃないなぁ…いや、そういうことじゃなくね、僕が求めるのは腕っ節の強さ以上の何かなんだよ。存在そのものに僕を圧倒する力があって、有無を言わさず、ぐいぐい引っ張っていかれそうな人なんだ」
「ローランがそういうタイプなんだ?」
「うん。もちろん、本気で喧嘩したら、僕が勝つと思うんだけれど…あの人から発散されるオーラはとても強くて、傍にいるだけで、逆らう気持ちを根こそぎなくしてしまうんだ」
「…惚れた男だから、そう思うのかもしれないけどねぇ。ローランの前では、柔道やってる時の気迫の片鱗も見せず、しおらしげにしているあなたが目に浮かぶわ。ところで、ルネ、そもそもローランはあなたが格闘技をやってることを知っているの?」
ルネは、またしてもキアラに痛い所を突かれて、ぎくりとした。
「知らない…よ…僕も、あの人には黙っているつもりだし…」
「黙っているって、どうして?」
「だって、ほら、僕の腕があんまりたち過ぎることを知られたら、どん引きされそうだから…自分の強さを自覚している男って、より強い男をライバル視はするけれど、恋人として好きにはなってくれないもの」
「あら…ローランに嫌われるのが怖くて、本当の自分を隠しているってわけ? まあ、気持ちは分からないでもないけど…女の子の場合は特に、強くなるほど彼氏には打ち明けにくいって、よく聞く話よ。でも、あなたは―」
勘のいいキアラは、ルネの口ぶりに何か引っかかりを覚えたようだが、これ以上追求される前に、ルネはこの話を打ち切ろうとした。
「ともかく僕は、やっぱりローラン以外の誰かと付き合おうという気持ちにはなれないから…」
「しょうがないわねぇ。せっかく、あなたにお勧めの店を見つけてきてあげたのに…」
「店?」
思ったより頑固なルネを説得することは諦めたのか、キアラはやれやれというように肩をすくめ、バッグの中から一枚のカードを取り出した。
「ゲイの知り合いに、あなたのことを相談してみたのよ。それで、やっぱりローランだけって初めから思いこまずに、色んな人に会ってみた方がいいんじゃないかって話になって…それで、ここのワイン・バーなんだけれど、最近パリのおしゃれなゲイの社交場になってるんだって。雑誌でも何度か紹介されたことがあるみたいよ。別に同性愛者ばかりって訳でもないし、雰囲気もよくって入りやすいから、あなた向けじゃないかなと思ったのよ」
「あ…」
「まあ、どうしてもその気になれないなら仕方ないけどね。一応そのカードは渡しておくわ」
ルネが目の前に置かれたカードを凝視しながら考え込んでいるうちに、キアラは腕時計をちらっと確認した。
「私、そろそろ行くわね、ルネ…これから彼と一緒に映画を見に行くことになっているの」
ルネははっと我に返って、テーブルから立ち上がるキアラに向かって、慌てて声をかけた。
「キアラ、あの…ありがとう、僕を心配して色々考えてくれてたんだね」
「ルネってば、何、そんなすまなそうな顔してるのよ。当然じゃない、私達、友達でしょ?」
キアラは屈託のない笑顔で答えると、バッグを肩に引っかけ、颯爽とした足取りでカフェを出て行った。
(都会の人は冷たくて取っつきにくいなんて、とんだ偏見だったんだな。キアラみたいに、親身になって僕のことを考えてくれる人もいる)
ほっこりと胸が温まるような気分になりながら、ルネはキアラからもらった店のカードを手に取った。
さっそくのスマホで検索してみる。
(あ、ほんとに、若者向けのおしゃれなワイン・バーみたい…気軽に入れそうな雰囲気だけれど、ワイン・リストは充実してるか…ふうん、ここなら普通にちょっと立ち寄ってみたいかも…)
ローランに奢ってもらったシャトー・ラトゥールで開眼して以来、ルネはワインにも興味を持って、少しずつ嗜むようになっていた。
ネットでラトゥールを買えないかと調べてみた時は、その値段のあり得なさに腰を抜かしそうになったものだが、たかが飲み物にここまでの価値が認められる、ワインの世界には好奇心をかきたてられた。もともと勉強熱心で、関心を覚えたことはとことんまで追求したがる傾向のあるルネだ。これも秘書の仕事の役に立つだろうと、ワイン関係の書物に手を出して、時間がある時は読みふけっている。
(でも、本で得た知識だけじゃ物足りないって思ってたところなんだよね。こういう店では、どんなワインを出すのだろう…グラスで色々試してみたい気がするな)
せっかくキアラが探してくれた店なのだし、一度くらい行ってみてもいいかもしれない。
(そうだ…いっそ、思いきってローランを誘ってみようかな…?)
自分からローランに対して積極的に出ることを躊躇っていたが、このバーを口実に、行動に出てみようか。
(この間ご馳走になったお礼に、僕に奢らせて下さい…いや、駄目だ、ラトゥールに見合うワインなんか奢ったら、僕が破産しちゃう。正直に、友達に教えてもらったワイン・バーなんですけれど、1人だと入りにくいので、よかったら付き合ってくれませんかってお願いすればいいんだ。他に約束がなければ、きっと断られたりはしないよね…?)
友達の心遣いに背中を押される形で、ルネはやっと気持ちを固めることができた。
(善は急げというし、僕の気持ちがまたしぼんでしまう前に、明日にでもローランに声をかけてみよう)
そんなことを想像しながら、ルネは妙にうきうきと弾んだ気分になっていた。
結局、大好きなローランが傍にいるのに、自分の感情に封印をし続けている今の状況を変えるきっかけを求めていたのは、他ならぬルネ自身だったようだ。
0
あなたにおすすめの小説
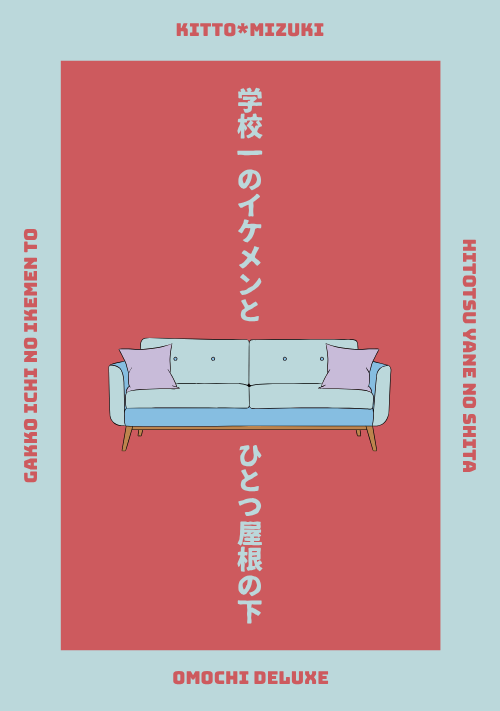
学校一のイケメンとひとつ屋根の下
おもちDX
BL
高校二年生の瑞は、母親の再婚で連れ子の同級生と家族になるらしい。顔合わせの時、そこにいたのはボソボソと喋る陰気な男の子。しかしよくよく名前を聞いてみれば、学校一のイケメンと名高い逢坂だった!
学校との激しいギャップに驚きつつも距離を縮めようとする瑞だが、逢坂からの印象は最悪なようで……?
キラキライケメンなのに家ではジメジメ!?なギャップ男子 × 地味グループ所属の能天気な男の子
立場の全く違う二人が家族となり、やがて特別な感情が芽生えるラブストーリー。
全年齢

【完結】俺とあの人の青い春
月城雪華
BL
高校一年の夏、龍冴(りょうが)は二つ上の先輩である椰一(やいち)と付き合った。
けれど、告白してくれたにしては制限があまりに多過ぎると思っていた。
ぼんやりとした不信感を抱いていたある日、見知らぬ相手と椰一がキスをしている場面を目撃してしまう。
けれど友人らと話しているうちに、心のどこかで『椰一はずっと前から裏切っていた』と理解していた。
それでも悲しさで熱い雫が溢れてきて、ひと気のない物陰に座り込んで泣いていると、ふと目の前に影が差す。
「大丈夫か?」
涙に濡れた瞳で見上げると、月曜日の朝──その数日前にも件の二人を見掛け、書籍を落としたのだがわざわざ教室まで届けてくれたのだ──にも会った、一学年上の大和(やまと)という男だった。

【完結】男の後輩に告白されたオレと、様子のおかしくなった幼なじみの話
須宮りんこ
BL
【あらすじ】
高校三年生の椿叶太には女子からモテまくりの幼なじみ・五十嵐青がいる。
二人は顔を合わせば絡む仲ではあるものの、叶太にとって青は生意気な幼なじみでしかない。
そんなある日、叶太は北村という一つ下の後輩・北村から告白される。
青いわく友達目線で見ても北村はいい奴らしい。しかも青とは違い、素直で礼儀正しい北村に叶太は好感を持つ。北村の希望もあって、まずは普通の先輩後輩として付き合いをはじめることに。
けれど叶太が北村に告白されたことを知った青の様子が、その日からおかしくなって――?
※本編完結済み。後日談連載中。

完結|好きから一番遠いはずだった
七角@書籍化進行中!
BL
大学生の石田陽は、石ころみたいな自分に自信がない。酒の力を借りて恋愛のきっかけをつかもうと意気込む。
しかしサークル歴代最高イケメン・星川叶斗が邪魔してくる。恋愛なんて簡単そうなこの後輩、ずるいし、好きじゃない。
なのにあれこれ世話を焼かれる。いや利用されてるだけだ。恋愛相手として最も遠い後輩に、勘違いしない。
…はずだった。


はじまりの朝
さくら乃
BL
子どもの頃は仲が良かった幼なじみ。
ある出来事をきっかけに離れてしまう。
中学は別の学校へ、そして、高校で再会するが、あの頃の彼とはいろいろ違いすぎて……。
これから始まる恋物語の、それは、“はじまりの朝”。
✳『番外編〜はじまりの裏側で』
『はじまりの朝』はナナ目線。しかし、その裏側では他キャラもいろいろ思っているはず。そんな彼ら目線のエピソード。


ユキ・シオン
那月
BL
人間の姿をした、人間ではないもの。
成長過程で動物から人間に変わってしまう”擬人化種”の白猫青年と、16歳年上のオッサンとのお話。
出会ったのは猫カフェ。白猫従業員としての青年と客としてやってきたオッサン。
次に再会したのは青年が人間として通う大学。オッサンは保健室の先生だった。
青年が金のためにヤバいことをしていて、あるトラブルが起こる。
そこへ見計らったかのようにオッサンが飛び込んで救出したのをきっかけに2人の距離は縮まり……
※表紙絵は自作。本編は進むにつれてどんどん動物園と化します(笑)
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















